PrejectRCL ZET REQUIEM:NOVELIZED 04-悪食ノ果テ 小説本文パート
PROJECT RCL ZET REQUIEM:NOVELIZED
第4章:悪食ノ果テ
●文:Hi-GO!
●執筆補佐:ゾンリー/らいおね
●挿絵:Hi-GO!/補欠/ててん/トナミカンジ/のばでぃ/メカクリア
▼冊子版の通販▼
※冊子版限定で『キャラクターデザイン資料』や『用語解説』
『ゲストイラスト』等のコンテンツが付属します。
※第1章~3章は以下になります。先にお読み頂く事を推奨いたします。
◆2024/08/08……あとがきコーナーにラセニアの過去の姿を追加
キャラクター紹介
▼シエル
▼ブロッサム・シエル
▼オメガ・シエル
▼アルエット
▼パッシィ
▼ペロケ
▼イロンデル
▼ジョーヌ
▼ロゼ
▼グレイシア
▼ウェクト
▼リバース・ナイツ
▼ラセニア
▼ゼットルーパー
▼ゼットール
▼ネージュ
▼ラファール
▼ダイン
▼グレイシス
!ご注意!
こちらは
【PROJECT RCL ZET REQUIEM:NOVELIZED 04-悪食ノ果テ】
の小説本文パートのみの記事になります。
『キャラクターデザイン資料』や『用語解説』『ゲストイラスト』等は冊子版のみのコンテンツとなりますのでご了承お願いいたします。
※note限定のコンテンツとして『あとがきコーナー』が付属します。
※誤字、誤表記、ご編集やご感想などお気づきの点が御座いましたら是非下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
https://note.com/p_rcl_zr/n/n90f420986bb9
【人物相関図】
FILE:Ⅰ
シエルがSEブロックに辿り着くと、ネージュから通信が入った。
外は相変わらずジャミングが張り巡らされているため、要塞に到達している飛空艇以外は直接通信が難しい。だが今回はグレイシスが搭乗している船の端末から中継することで回線に接続している。
「シエル、聞こえる? マザーエルフの調査班の安否が確認されたわ。残念ながら彼らはリバースの連中によって全滅……ヤツら、銃が効かないから本当に厄介ね……」
「そんな……私の指示でみんなが……」
自分が調査を命じたばかりに仲間が犠牲になってしまった。それは何度経験しても慣れるものではなく、シエルは通信中であることを忘れてしばらく沈黙していた。
「シエル、司令官がそんな弱気になってたらダメよ。みんなあなたを信じてついてきたのだから胸を張って。マザーの居場所にも心当たりがあるんでしょ?」
「ええ……恐らくこのヴァルハラの動力炉に組み込まれているはずよ……あの主砲の力はそうとしか思えない……」
過剰な威力に加えて地形の再構築現象。ただの兵器には不可能な性能だ。事象に干渉するほどの大きな力といえばマザーエルフの存在以外、現状の技術力ではありえない。
「えー……そんなことになってるの……? うーん……なら、取り返さないとね。調査班のみんなのためにも……!」
ネージュからの檄。すると、そこにコール音が割って入る。
「ん? 何か別の通信が入ったわ。一度切るわね」
シエルが通信を切り替えると、ウェクトの声が響いた。
「ごきげんよう、シエル嬢。あれから調子はいかがかね……?」
「ウェクト! よく口がきけるわね……! アルエットはどこなの?」
「まあ、そう急くな。あの子は塔の天辺で大人しくしておるわい」
「……無事なら今はそれでいいわ。後で絶対取り戻すまでだから」
アルエットの居場所と安否が確認出来て、シエルは内心安堵した。これで、よりミッションに専念できる。
「ほう、大きく出たものだ。塔の天辺まで来るということはロゼ様と相見えるということじゃぞ……?」
「ええ。彼が立ち塞がるなら私は悩まない」
「ほぉ……ゼットルーパーすら満足に斬れん割には随分と覚悟が決まったようじゃの。ならば止めはしまい、見守るだけじゃ。あのお方の足元にひれ伏す姿を、な……」
ウェクトが言い終わると一方的に通信は切られた。
「ッ……まだ斬れないことは見抜かれていたけれど、システマ・オメガのことは伝わっていないようね。考えようによっては当面の切り札になるわ……」
局面において情報は武器になる。システマ・オメガの存在が露見していない現在、シエルの意思にはムラがあると思われても仕方ない。それを逆手に取って『斬れない』と思わせておくことは、事を進めるにあたって有利に働く。
彼女はそのままSEブロックの奥へと歩を進めた。
◆SCENE2
同時刻。ゼニム敗北を受け、ヴァルハラ内の監視カメラを通して決闘を中継していたリバース・ナイツの騎士達はさっそく通信回線を開き、会話に花を咲かせていた。ちなみにラセニアは今まさに守護ブロックをシエルが進行中で臨戦態勢のため、不参加だ。
「なんだぁ? ゼニムのやつ一番乗りでやられちまったのかよ?!」
「……ロゼ様を目の敵にしてるような奴には当然の報い……」
開口一番、ヒガンは驚きをそのまま口にする。モネアはゼニムの複雑な精神構造を理解してか、小さな声で呟いた。
「ん? モネア、今何か言ったか?」
「い、いえ、なにも……そ、それよりヒガンどうするの……?」
自分で言い出したものの、本心を悟られるのが苦手な彼女はあわてて話題を逸らす。そこへグリオサがすかさず応答した。
「そうですね。モネアさんの言うとおりです。現在SEブロックにはラセニアが待機していますが、まさかゼニムが真っ先に倒されるとは想定外でした……Z-FACTOR係数も高レベルですし……」
「確かに。グリオサ殿の言う通り、彼は団に加入して日は浅いが武器を用いた率直な戦闘力では、我ら守護騎士の中でも随一のはず……それに、オーバードライブまでもが破られるとは……」
幸いグリオサとベラーガが話に乗ってきたのでモネアは安堵した。
「とりあえずアレだな。当たって砕けろ、だ」
「ヒガン! 仮にも仲間が倒されたのです! 少しは団長らしく真面目に対応してください!!」
「あー、あー。うるせぇなぁ……もう『ゲーム』は始まっちまってるし、自分達から仕掛けた手前、ルールを変えるわけにもいかんでしょうが。せっかくロゼ様も許可をくれたってのによぉ……」
逆上するヒガンは声を荒げた。流石にモネアとグリオサもあまりの投げやりな回答に引き気味だが、彼なりの筋があるらしい。
「ふむ……あながちヒガン殿の言うことも的外れではない。現に直接ぶつかる以外、こちらに切れるカードはない……」
意外にもベラーガがヒガンをフォローした。既に手遅れであるからこそ、対峙にあたっての覚悟が大切というのも本当のことである。
「おぉ、ベラーガ師匠わかってるぅ~。OK? グリオっさん!」
「で、ですがせめて各自の制御室は戦いに有利にすべきでは……」
「そんなこと、とっくにみんなやってるだろ? なぁ?」
「あ、あれ、ひょっとして私だけですか? なら急がないと……!」
この各メンバーに全てを投げっぱなしにするという放任方針のため、しばしばこういった事態が発生するものの、各々の能力の高さもあって今までは問題にならずに済んできた側面がある。
「そんなことよりモネアちゃん、随分ゼニムに嫌われてたねぇ」
先ほどのゼニムの激昂を見たヒガンは、また率直に思ったことを口に出していた。
「な、なにもない……一方的な逆怨み…」
「そ? ならいいんだけどさぁ……あんまり内輪でギスギスしたのはよくないと思ってね。一応団長なりの気遣いってヤツ」
「こういう時だけ団長ヅラしなくていいですから……」
回答に詰まるモネアを不憫に思ったのか、諫めるグリオサ。
「む、あの小娘の足が止まったようだ。何かあったのやもしれぬ」
「お、ちょっと様子見てみますかねぇ~」
ベラーガとヒガンのやり取りを最後に通信は一旦中断された。
◆SCENE3
「アタシの食卓にようこそ☆」
シエルは今、巨大な皿を模したような円卓のフィールドで『甲盾騎のラセニア』と対峙している。騎士の中でも最大であろう巨体の迫力に負けじと歯を食いしばっているが、思い返すとここまでの道中は散々だった。
シールドブーメランを組み込んだメカニロイドが多数配備されており、都度行く手を阻んでくれたお陰だ。いわゆるシールドアタッカータイプの派生型ではあるが、正面から攻撃が通りにくく、更にセイバーを組み込んだガビョールタイプまで配備され、進行には骨が折れた。
ガビョールタイプは基本的に攻撃で一時停止できるものの、その特殊な装甲により完全に破壊することができないため再起動するタイミングを読み間違えると厄介な手合いだ。
そもそも通路自体も侵入者を飲み込み、捕縛するようなトラップが至る所に配置されており、上記の迎撃用メカニロイドとの組み合わせが最悪に近い形で効果を発揮していた。
それでも直近で手に入れたトリプルロッドのお陰でいくつかのトラップを攻撃しながら移動と回避を兼ねることができたため、このSEブロックを守護している騎士の部屋までなんとか辿り着くことができた次第だ。
そして眼前のラセニアはというと、シエルを見るなり『美しいから自らの体に取り込みたい』と言い出す始末。精神的に疲れていたところにトドメを刺された気分である。
「さぁさぁ、デリシャスメルなコスプレ剣士ちゃん! 早くアタシのボディと一つになりましょう……☆」
頭部から生やした弁髪を揺らしながら踊るさまに早くもうんざりしてきた。どうやらこのラセニアという騎士は相手を取り込んで自らの一部とする能力を持っているようだが、お陰でうかつに接近することもできない。
「アタシはヒガンのように枯れてる人は好みじゃないノ……アナタからは迸るリビドーを感じるわ☆」
しかし、巨体は徐々に距離を詰めて迫りつつある。この制御室の壁面には先程の捕縛トラップが張り巡らされているため、逃げ回ったところで結局は捕まる可能性が高い。せめて何か気を逸らすなどして隙を作れれば初撃を叩き込むくらいはできるのだが……。
「そもそも相手はシールド持ち……ガードされるのがわかりきってはいるけども……」
呟きながら加速してその場を駆ける。とりあえず距離を保ってどこかで反撃に出るしか道は無いのだ。
思考を巡らせているとシエルの眼前にビームの塊が迫った。
まさかの出来事に面食らいそうになるも、更に加速し、ギリギリの低高度で攻撃を避ける。
「にげてもムダなのよン☆」
すれ違いざまに振り返ると、このビームの塊の正体が回転したシールドということに気付く。
「こちらの考えることはお見通しってことね。先にブーメランを投げて退路を塞ぐなんて……」
ならば、と覚悟を決めてシエルは加速した先で姿勢を低くしたまま大きく開脚し、地に手をつきながら獣のように構える。
「システマ・オメガ、スタンバイ……!」
頭部からバイザーが降り、顔を覆うと眼光が輝く。
こんな時だからこそ頭によぎる。紅き英雄を英雄たらしめていたのは、その思考から決断までのタイムラグが一切無いことなのではないかと。『相手を斬る』という前提があればそこに判断を揺るがす余地は無く、最大速度・最大効率で相手に斬りかかるだけだ。それが敵わないからこそ今回の戦いは苦戦を常に強いられていることに、改めてシエルは気付かされた。
「ここから先は手加減無しよ……!」
覚悟を決めてもう一度加速。ラセニアは再びブーメランを投擲していたが、構わずに低高度で敵目掛けて真っ直ぐに突き進んだ。完全に無防備になった今がチャンスとセイバーを構え、突きの姿勢を取る。回避と反撃のタイミングは共に完璧だった。
「このまま……貫く!」
――はずだった。しかし、目の前に現れたのはラセニアの腹部から現れた巨大な口と形容するしかない形をしたもので、視界に入ると同時に敵の弁髪が触手のように伸びてシエルの四肢に絡み付く。
大きく開いた『それ』に飲み込まれた瞬間、景色は暗転していた。
「ごちそうさまでした! う~ん、デリシャスイート~☆」
籠った声が空間に響く。何が起こったのか理解が追い付いていなかった。直後、全身から力が抜け激しい痛みが襲う。エネルギーを抜き取られてボディが分解され始めているのだとシエルは悟った。
既に何もかもが手遅れだった。通信をしようにもこの空間は外部と遮断されていて難しく、おまけにエネルギーも既に抜き取られているので尚更困難であった。
目を開けても閉じても真っ暗なまま徐々に意識も刈り取られていく。
生体ボディとのリンクが切れ始めていることでエラーや警告のアラートが鳴り響き、あらゆる面で『詰んだ』事を認めたと同時にシエルの意識は掻き消された。
◆SCENE4
完全なる闇。わずかな光さえ許さない場所。
人の営みも、レプリロイドの進化も、やがては消滅するであろう太陽や宇宙のことを思えば、いずれ無に帰し意味など無くなるのだろうと思わされる。
だとすれば、なぜ我々は存在し、その意味は何処にあるのか?
そもそも『意味』とは人が作り出したものだ。その観念に踊らされているに過ぎない。システムとして自然に備わっているわけではなく、事象を読み解くために暫定的にタグ付けされたようなものに過ぎない。
『意味』に囚われること自体がまさに無意味なのだ。
であれば、ありのままを受け入れるしかない。故に世界にも人にも機械にも意味はなく、ただそこに『在る』だけなのだ。そしていずれは無くなってしまう。終わりが待っている。そこまでをいかに過ごすかが肝要だ。
できれば、その道のりはなるべく有意義でありたいものだ――――
突如ガーディアンベースにカプセルで保管されているシエルの生体ボディと繋がれた機器が輝くと共に、シエルの額のクリスタルも光り始めた。高速で何かを演算している様子が窺える。その処理に接続された先はこの世界の裏側、即ちあらゆるデータが流れ着く『サイバー空間』を指し示している。そこで何かが起こっているのだ。
額のクリスタルの輝きが収まると、やがて彼女の視界は回復する。
◆SCENE5
シエルの目の前は闇に包まれたはずだった。確かに一度意識は途切れたはずだが、気づくと目の前にはラセニアが立ち塞がっている。
それはまさしくシエルがシステマ・オメガを発動した瞬間の状態であった。先ほどの記憶が甦り、加速をためらう。
(これはどういうことかしら……? 時間が巻き戻っている……いえ、ありえないわ……)
足を止めて思考する。確かに一度突撃した結果、相手に飲み込まれたはずだった。その記憶は鮮明に残っている。当たり前だが時間が巻き戻るような要素はこの場には微塵もない。そもそもそんな夢のような装置はこの時代には存在しないし、あったとしても社会そのものが発展していた過去の時代の方がよほど可能性が高い。
(まさか、システマ・オメガの演算を高速化するためにサイバー空間と接続した影響かしら……起こりうる可能性のビジョンがたまたま一瞬で流れ込んできたというの……?)
(仮にこの現象を『サイバー・ビジョン』としましょう。恐らくシステマ・オメガの発動がキーとなって、サイバー空間で演算された予測される未来が提示されているということなら要検証ね……)
こんな状況でも遺憾なく発揮される科学者としての性分にあきれつつも、まずは投げられたブーメランを跳んでかわす。シエルはかすかに笑みを浮かべながらシステマ・オメガを強制終了し、体勢を立て直した。
「ひとまず、様子見ね……!」
再度投擲されることは予想ができる。
ならば確実に回避しつつ敵の懐に飛び込む方法を思案しなければならない。こんな時だが『彼』がよく用いていた『三角飛び』――いわゆる壁面を脚部で蹴ると同時に上方へ連続して移動する『壁蹴り』について思いを馳せる。
あれは機体性能だけで再現可能なものではなく、当人……つまり機体の技量が問われる。ソフトウェア制御の方が重要なのだ。
大半の戦闘用レプリロイドは機動系の装備に関してそこまで基本性能の差異はない。その中で飛び抜けた能力を持つ個体は、実はソフトウェアの方が優秀というケースも多い。
問題は、シエルが未だに『壁蹴り』を習得できていない点にある。モデルBに欠陥があるわけではない。かつて人間だったシエルの精神がまだレプリロイドのボディに追い付かず、最適化されていないのだ。あくまで人間の範疇でイメージを巡らす癖は抜けきっていないため、それが足枷となって本来の性能を発揮できていない。
「マダ逃げようっていうノ?!」
敵と距離を取りながら思考を巡らす間にもブーメランの投擲は行われた。再度ギリギリまで引き付けて跳躍してかわしつつも相手の次の挙動に目を光らせる。このままイタチごっこが続くとも思えない。しかし、こちらはビジョンで敵の切り札を先に見ている。これがこちらのアドバンテージだ。
「やはりまた来たわね……! たとえ壁を駆けて上がれなくても避けてみせるわ!」
今確認できる敵の脅威はシールドブーメランによる防御と攻撃、そして弁髪による拘束と、腹部に隠された巨大な口だ。致命傷になるものが揃っているだけに迂闊な行動はできない。何かしら無効化する必要がある。
「小賢しいことォ! アタシをからかってるのかしラ?」
こちらの武器はセイバーと先ほどゼニムから手に入れたトリプルロッドだ。特にロッドは伸縮し、移動にも用いることができる。使い方次第で反撃の兆しになるだろう。
しかし、跳躍してからの接近は弁髪による拘束を許すことになる。ここは低高度での地上加速と、トリプルロッドによる中距離の攻撃で、弁髪を破壊し無効化するべきだ。
「いいえ、今度はこちらから行くわ……!」
今度こそ意を決し、再度投擲されたブーメランを緊急加速で掻い潜る。敵の4つの弁髪が動く挙動を確認すると、バックステップで距離を空け、高速の突きで全て破壊した。
「なんですッてェ~?」
「その邪魔な髪をカットさせてもらったわ!」
次はブーメランの対策だ。相手のもとへ戻る性質をなんとか利用できないだろうか?
今度は前進し敵へ攻撃する姿勢を見せる。
「頂きヨッ☆」
すると、例の隠れた巨大な口が腹部から開いた。シエルはここぞとばかりにトリプルロッドの刃を『空中』に叩きつけると、大きく跳躍する。そこには投擲された後、旋回して戻ってきたシールドブーメランがあった。
「奥の手が、かわされたッ?」
「――――ごめんなさい。それは一度『見て』いるのよ」
すると、ロッドの踏み台として利用されたブーメランがシエルの跳躍直後にラセニアのもとに戻ってくる。確実に軌道が読める武器だからこそ、タイミングを計るのは容易かった。しかし、ラセニアは前傾姿勢で開口したままだ。これでは武器をキャッチできない。
「ぎぃやぁぁアぁァァッ!!」
そのままブーメランはラセニアの腹部に突き刺さる。
「今よ!」
その隙を見計らってシエルはまた加速し、セイバーで敵の脚部を斬り裂いた。切断とまではいかなかったが確実に駆動系へのダメージは与えられたはずだ。
「これでもう移動もままならないわね……」
たちまちバックステップで距離を取る。
「アナタッ! よくもこのアタシの足をッ……!」
「もう終わりにしましょう。勝負は見えたわ。大人しく武器を渡してくれればここから立ち去るから……」
セイバーを突き付けながらシエルはラセニアに訴える。
「ふざけないでッ! アタシをバカにするの? こんなことでロゼ様の守護騎士が務まるわけないでショ!」
プライドを傷つけられ、激昂したかのように見えたラセニアだが急に冷静さを取り戻した。
「……いえ、アナタを侮ったアタシのミスね。ただのコスプレ剣士ではないこともわかったわ。でもね。この程度で引き下がるわけにはいかないの。全力で抵抗するわヨ」
何か策があるのだろうか? 激しく抵抗するなら武器だけを奪って逃走するのもやむなしだ。
「それに狩りは捕まえるのが難しいほどその味は絶品なのヨ☆ さぁ、アナタたち、出てきなさい!」
ラセニアが叫び終わると同時に突如四方より出でたゼットルーパー4体に目の前を囲まれる。これは想定しつつも相手が騎士を名乗るためにどこか意識の外に漏れていた展開だ。
「ッ……1対1を約束した訳ではなかったわね……」
「いえ、アタシは決闘は守るわ、騎士道精神に反するもの☆」
意外にも彼は彼なりに騎士道精神を持ち合わせていたようだ。だが、彼が両手を合わせる仕草をすると、辺りを囲んでいたゼットルーパーの1体がラセニアの巨大な腕に捕らえられ、たちまち腹部の口によって捕食された。
「うん、デリシャスパイシーといったトコロかしラ☆」
「どういう……こと……」
シエルの困惑をよそに、堰を切ったようにゼットルーパー達は逃げ出した。何も聞かされずこの場に呼び出されていたのであろう。
「ちょっとアナタ達! ロゼ様への信仰が足りないんじゃないの?! 今ここでアタシが勝つことがロゼ様をお護りする事になるのヨ?」
確かに理屈は通っているが、それが仲間を犠牲にする事を許す理由にはならないはずだ。そもそもシエルも先ほどまで腹部の巨大な口は奥の手として相手を噛み砕くための装備だと思っていた。
しかし、今目の前で捕食されたゼットルーパーは何処に消えたのか? その証明のようにラセニアの腹部口内や脚部の傷は塞がり、突き刺さっていたであろうシールドブーメランの柄を抜き取った。
「さァ、大人しく食べられなさい☆ かつてレプリイーターと呼ばれたこの甲盾騎《こうじゅんき》ラセニア・ザ・シールダーに!」
次の瞬間、再生した弁髪がゼットルーパー達を襲い、残りの3体がまとめて空中に吊るされる。1体、また1体と捕食され、最後の1体が飲み込まれた時、ラセニアの傷は完治し、更にエネルギーに満ちていた。
「まだまだ足りないワ☆ もっと出てきなさいッ!」
しかし反応はない。いくら信奉者といえど、黙って己の肉体を差し出す訳にはいかないようだ。
「イブーも沢山エネルギーを欲しがっていたけど、あなたほどではなかったわ……!」
ふと、レジスタンス時代にエネルギーが枯渇していた頃、人一倍エネルギーを欲しがっていたイブーの事を思い出した。あちらは単に巨体を動かす上での燃費の問題だったが、ラセニアのそれは際限がない。まるで底無しの胃袋を持っているかのようだ。
「お黙りッ! やっぱりアナタでお腹を満たすしかないようねッ」
「お断りよ! 大体あなたは見境がなさすぎるわッ!」
迫りくるラセニアにトリプルロッドの突きと反動で距離を取る。
「いいえッアタシは美食家よッ! 美しいと思ったモノしか口にしたくないの。そういう意味ではロゼ様は最高の逸品ね☆」
ひたすら距離を詰めてくるラセニア。触手のように弁髪が唸り、腹部の口は隠すのをやめたように開きっぱなしだ。
「あなた……自分の主すら食べる気でいるの……?」
思わずシエルは寒気を感じた。厳密には機械なので人間の頃に感じていた感覚の再現なのだろうが、とにかく不愉快だった。
「当たり前でショッ! それにロゼ様は許可してくれたワ☆」
迫る弁髪を紙一重でかわしつつも切断しながらシエルは後退した。目が慣れてきてはいるが相手の得体が知れなさすぎる。
「何を……こんなことに自分の体を差し出すわけが……」
「いいえッ! 部下になる代わりに、いつでも食べれる隙があれば襲ってこいと仰ったわ。ケド、それから全く隙を見せないから困っちゃうのヨ。まったく流石だわァ~☆」
ロゼの性格ならいかにも言い出しそうなことではあるが、部下を御するとはいえそこまでやるのかとシエルはあきれつつも妙な感心を覚えた。器の大きさとはこういう部分にも現れるのだろう。
「アナタこそ『アノ人』のボディに美しさを感じたことはないノッ? そんなのあり得ないでショ? さぁ何処に惹かれるか答えてみなさいッ!」
「な、何を……」
言い淀んだシエルは『彼』の姿が浮かぶのを止められなかった。
「麗しき『金の髪』! 艶やかな『紅い装甲』! 漆黒の『ボディ』! 額の『翠玉』! そして厳かな『御顔』! さァさァどうなノ?! 何とも思わないノ? そんなコトないでショ!」
思った以上に『彼』の外見的魅力を列挙され、シエルはやや混乱していた。事実ラセニアの言っていることは正しいと思うし、数あるレプリロイドの中でも研ぎ澄まされたように洗練された身体はレプリロイドの科学者としても息を飲む美しさなのは言うまでもない。
そして、隠された研究所の遺構で封印された彼を見つけた時の昂りを忘れることはこの先もないだろう。
「その様子だと……アナタ! 頭の中で『アノ人』の事を考えているわね! わかるワ! 仕方ないものね!」
うっかり敵のペースに乗せられたシエルは冷静さを取り戻そうとした。いくらなんでも敵前でこれはないだろうと思いつつも、相手はそれを戦いの中でも忘れず振る舞っているのを見るとある種の強さを感じることもできた。奇妙な話ではあるのだが。
「あなたは……『彼』の体を取り込んでどうするつもりなの?」
「……一つになるためヨ」
「それ、で……?」
「それだけヨ。一つになったらアタシがどれくらいの力を手に入れるのか見てみたい。『彼』がアタシをどれくらい満たしてくれるのかを知りたいのヨ……」
「……」
「アタシの捕食は『彼』のラーニングスキルと酷似しているワ。でも『彼』は見るだけであらゆる事を覚えていくのに対してアタシは相手を食べる必要がある……『アノ人』を取り込んだらアタシも同じになれるのかなっテ……」
「それは……どうかしらね……」
「アナタ、科学者なんでショ……」
「分野外だわ、検証しない限りはなんとも……」
「コレ以上食べずに済むならきっとアタシは元のアタシに戻れるハズだわ……傷つかずに済むのヨ……」
「あなたは……無理をしていたのね……変わってしまった自分を悔いて……」
「アナタは『彼』のどこが食べたいノ……?」
「何を……」
「確かに見た目は『彼』の魅力かもしれない……でも表面的なものに過ぎないわ……」
「アタシは……『全部』!!」
途端にラセニアの腹部の口が大きく開き、触手のように弁髪は乱れ襲い掛かってきた。シエルは加速して回避しようと思ったものの今までと敵のスピードが違う。なんとシールドブーメランを光背のごとく背負い、宙に浮かんで突進しているのだ。
そして、進む度にローブが弾け飛び、電子の花びらが舞い散る。これは強化形態《オーバードライブ》とみていいだろう。
「これは……間に合わない……ッ!」
加速方向をあえて敵に向けて同時にジャンプし、トリプルロッドを真下に突き付ける。攻撃は腕でガードされたが、その反動を利用して更に飛翔する。
「ホントにこざかしいわネッ!」
どうやら浮遊はできてもネオ・アルカディアのゴーレムに近く、地上から一定の距離を飛ぶホバークラフト系の性能のようだ。それが確認できただけでも攻撃を回避した意味はあった。
「ならばもう一撃……!」
トリプルロッドを再び真下に構え、突き刺し、飛翔する。弁髪も再生しているのでギリギリのタイミングではあるが、これで距離を大きく取ることができた。
「アナタッ! ヒガンのようにリビドーが枯れているっていうノ?! アタシはそういう無気力なヒトとはソリが合わないのヨッ!」
着地を狙うが敵も高速接近してくる。身体はまだ空中で目の前には壁がある。こんな時、『彼』ならどうするか。
「今だ! システマ・オメガ、スタンバイ……!」
同時に壁に張り付き、更に反対側の空間へ跳躍する。
敵は加速を押さえきれず、壁に激突した。
「なんですっテ……!?」
「シールドブーメランを加速のために使ったのが裏目に出たわね。警戒しなくていいから回避が楽になったわ」
反対側の壁へ再び張り付く。シエル単体では処理し切れなかった『壁蹴り』だが、システマ・オメガのアシストで再現可能になったのだ。これで空間戦闘が可能となった。
一方、当のラセニアは壁に衝突した上に未だめり込んだまま。しかもシールドに守られているはずの背中は機能が解除されたためかガラ空きだ。
「巨体がアダになったわね……」
壁から跳躍し、ラセニアに迫る。しかし、本体を守るように弁髪が空中のシエルに襲い掛かる。
「そう来ると思ったわ……!」
空中でトリプルロッドを正面に構えると高速回転させた。迫る弁髪はすべて細切れとなり、ラセニアを守るものは無くなった。
「これでどうかしらッ……!」
着地と共にトリプルロッドによる突きを3発繰り出し、更にセイバーへ切り替えての3連撃へ繋いだ計6連撃が決まる。
「こんなッ……アリ得ないッ……!」
ラセニアの背中は無残に斬り刻まれ、巨体は地面に倒れた。
「イッ……いけない……ッ」
ラセニアの巨体が小刻みに揺れると、腹部の口が更に大きく開いた。 瞬間、緑の光が液体のように漏れだし吹き飛んでいく。
「ヴォォォ……ウェェェェ……ッ」
よく見ると吐き出されているのはレプリロイドのパーツだった。エネルギーを帯びて光っており、対照的に、ラセニアはみるみる内に痩せ細っていく。
「な、何が……」
取り込んだパーツも、エネルギーも全て吐き出し終わった後には見るも無残な姿で倒れたままのラセニアがそこにいた。どうやら背面を攻撃されたことで、パーツやエネルギーを取り込む機関にダメージが入り、制御を失って逆流してしまったようだ。
「なるほど……シールドを背中に展開していたのは単に移動速度を上げるためだけでは無かったのね……」
シエルもレプリロイドの設計の知識があるとはいえ、非常に珍しいタイプのものだけにこの特性までは見抜けなかった。
〈システマ・オメガ・タイムアウト〉
念のため解除していなかったシステマ・オメガの稼動時間が限界を迎えて自動終了する。円卓の上の皿に倒れたラセニアの脱け殻は無残に食卓に並べられた料理の残骸のようでもあった。
「これで……終わりかしら……」
吹き飛んだシールドブーメランの柄を拾うと、再びゼニムの時のように記憶《メモリー》が流れ込んでくる。
◆SCENE6
彼は、元々防御に重きを置き、盾によって仲間を守護する役割を担っていたレプリロイドで、イレギュラーハンターの一員だった。
更には物質を取り込んで自らの能力を向上させるシステムを備えた点が従来の機体と一線を画していた。ただし、取り込める物質は定量が定められており、過度な摂取はボディやシステムへの弊害が発生する恐れがあったため、彼は律儀にそれを守り続けていた。
一方で、自らと同様にラーニング機能を備えた『紅き英雄』に親近感を抱いており、際限無く能力を取り込む高い領域のラーニングスキルを備えた彼に憧憬の念を抱くと共に、その域に達する見込みのない己自身の性能に劣等感を感じていた。
ある壮絶な任務で唯一の生存者となった際、彼は生還の為に壊れた仲間達の残骸を捕食せざるを得ない状況に陥ったが、その効果は通常の物質を取り込むより大幅な戦闘力の増加が認められた。
それ以降、『レプリイーター』と呼ばれるようになった彼は、研究対象となり、任務で大破したレプリロイドの残骸を与えられ続けるも、その効果は早々に頭打ちとなってしまう。
それが契機となり、力への渇望から稼動中のレプリロイドを取り込みたいという欲求が肥大化していったが、あくまで残骸のみを取り込むに留め、辛うじて理性で抑え続けていた。
しかし妖精戦争時代……運悪くイレギュラー化すると同時に、ついに仲間であった稼動中のレプリロイドをひたすら取り込み続けてしまう。それは、彼にとって革命的な出来事であった。『それ』を貪るだけでボディは肥大化し、戦闘力も飛躍的に増していく。
飢えは満たされること無く続き、体を維持するため貴重なエネルギー資源であったエネルゲン水晶の強奪も行うようになっていき、結果的にそれは体に更なる力が漲る実感を伴った。いつの間にか彼の体は『捕食』に最適化したものに変化しており、腹部に大きな口と獲物を捕らえる触手としての『弁髪』をその身に宿していた。
たちまち厄災のごとき存在として知れ渡る所となったが、そこへ立ちはだかったのはあの『紅き英雄』であった。彼は身体が震えた。
かつて憧れた存在から認知されたのだ。こんな名誉があるのなら『イレギュラー』となるのも悪くはない、と。
……ウイルスに蝕まれた身体であったが、自我は残っていた。
彼を討伐すべく動員された多数のハンターとイレギュラーが入り乱れる戦いの中、『紅き英雄』との雌雄は中々決することがなかった。そして幾度かの邂逅を重ねると、次第に彼は『英雄』をその身に宿すことが目的となっていった。
そう、かの英雄はその見た目からして彼の美意識を満たしていたのだ。いつしか彼は戦場において美食を貫くようになっていた。食した量は数知れず、その中から最上の逸品を見分けるに至っていた。その中でも至上にして唯一無二と直感したのが『紅き英雄』―――
あの小さな体躯に一体どれだけのテクノロジーが詰め込まれているのだろうか。ノーリミットの判断力、そしてその反応に追随する関節機構……更には爆発的な速度から繰り出される攻撃と、ラーニングによる状況適応力。加えて放熱を担っているのか、金色にたなびく長髪は見る者を魅了する。その全てを理解したいと願った。
そしてある日、1対1の好条件に持ち込んだ決闘が行われるも、彼は終ぞ『紅き英雄』をその身に取り込むことは叶わず、その輝く剣により盾は砕かれ、身体の芯から一刀両断された。
事切れながらも彼は思った。紅き英雄をその身に宿したらどれほどの力を得られるのだろうと。その真価はどこにあるのだろうと。
その後、秘密裏に収容されたボディとAIはウェクトの手で修復され、ゼロ・リバースの一員としてその欲望は再び世に放たれた。
「当たり前だけど、皆きっかけがあってここにいるのよね……」
ラセニアの記憶が一通り流れ込むと、武器を握り締めながらシエルは制御パネルに向かい、ロックを解除し次のSブロックへ向かうのだった。もうすぐ仲間と合流できるはずだろう。
【第4章:悪食ノ果テ 完】
最後までご覧いただき誠にありがとうございます…!
※誤字、誤表記、ご編集やご感想などお気づきの点が御座いましたら是非下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
(頂いたご感想やご意見は今後の制作の励みにいたします…!)
X(旧Twitter)へのご感想は下記からどうぞ!
(ハッシュタグ #RCL_ZR_Re にてお待ちしております )
https://twitter.com/intent/tweet?text=%20%23RCL_ZR_Re%20
▼第5章はこちら
note限定 あとがきコーナー
本作を企画し、執筆させて頂きました。Hi-GO!です。
記事をご購入頂いて最後まで読んで頂き、まことにありがとうございます。
ここからはnote限定のあとがきコーナーになります。
冊子版には編集後記というものがあるのですが、そちらは内容そのものより、書籍の編纂まわりの事情を書きましたのでこちらではもう少し内容に沿ったものを書きたいと思います。
◆2024/08/08……あとがきコーナーにラセニアの過去の姿を追加
余裕を持って年始から作業していたのですが、なぜか締め切りギリギリであたふたしておりました。なぜこうなったのかは私にもわかりません……!
さて、4章についてのお話ですが、今回のボス、ロゼ直属の守護騎士『リバースナイツ』の『甲盾騎ラセニア・ザ・シールダー』について、語っていきます。
彼については八審官でいうケルベリアンのような巨体ポジションの位置付けでデザイナーの補欠さんの方でデザインがスタートいたしました。そもそもゼロは巨体ではないですが、逸話でそういう話があったらこういう大男になった可能性などのイメージで構築しています。よく見るとゼロ(X)のヘルメットのシルエットをかなり意識して取り入れています。
元々はラフレシアモチーフでしたが、途中で食虫植物であるサラセニアモチーフへと変更しました。(EXではレフシアという名前になっています)花言葉は『憩い』『風変り』など、ゼロっぽさもややかすっている感じですね。
実は、シールドブーメランについてはお皿に見立てていたものの、『捕食』要素は結構後付けだったので、結果論としてうまい収まりを見た感じですね。元々武器の割り振りをしていく中でシールドが似合うのが彼だったというのもあります。
オーバードライブは完全に後付けなので、中々難儀しました。装甲を脱ぐというルールは踏襲して、ゼロ(ロクゼロ)のルックにかなり近づけています。(太ましいですが)頭部の展開もナナメから見るとかなりゼロ(X)のヘルメット的な意匠を更に誇張しています。
※改めてみても、腹部に口腔部を配置した補欠さんのアイデアのお陰で全体から見たアクセントになっているので、素晴らしい仕事だと思います。
変身前の形態について、前回のゼニムでは触れませんでしたが、冊子で収録できなかった部分があるので、デザイナーの補欠さんの希望により、こちらで補完したいと思います。
※ゼニムの過去の姿についても3章のあとがきを更新しておきましたので参照頂ければ幸いです。
ラセニアについてですが、過去の姿は補欠さんのアイデアもあって、肥える前の姿となりました。これは本編で描いた過去のテキストからの逆算で、どうせなら変身後とのイメージのギャップを持たせようとなりました。(厳密にはこの姿で肥えていくことになるのですが……)
旧大戦(イレギュラー戦争~妖精戦争)時は、主にタンク役のイレギュラーハンターとしてイメージしています。戦闘時は仲間だけでなく被災者などの盾にもなっていたであろうと私は妄想しています。また、マスクをつけたり、胴体だけスキンが見えているのは変身後に合わせつつ、マスクは節制のイメージなどを想定しています。弁髪も一本だけですが踏襲してますね。
ちなみに、キャラクターの性格付けなどは上記のラフを元に構築しています。特に美食家キャラやオネエ言葉などはここからの着想で、このアイデアは直感的に分かりやすくて私もお気に入りです。平和な世界であればこういった姿が拝めたのかもしれません。(言葉遣いはテキストのみでもキャラクター判別ができるようにと考えた結果です。)
ボス部屋の方は、それ自体がお皿のような形状をしていると彼『らしさ』が補強されると思い、彼の部屋の中央は食卓に見立ててお皿があります。
ゲームの場合、ここから引力が発生したり、移動速度が落ちたりなど、
色々ギミックが追加されそうです。今回はゼットルーパーの転送装置を兼ねたイメージで使っていたりします(文字数的にそこまで書ききれませんでした)
さらには、彼を撃破するとお皿が割れるような演出とかありそうですね。(床に格納された制御パネルがそうしないと出現できないので)
今回も全体的にデザイン談議になりましたがお許しください。文字で記すべき情報なども多分にありますね。次回は前半の山場となりそうですので、制作にお時間を頂く可能性がございます。
それではまた本編第5章のあとがきでお会いしましょう!
Hi-GO!
いいなと思ったら応援しよう!
 ご支援頂ける方、よろしくお願いいたします…!
ご支援頂ける方、よろしくお願いいたします…!
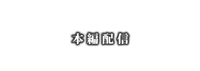

コメント