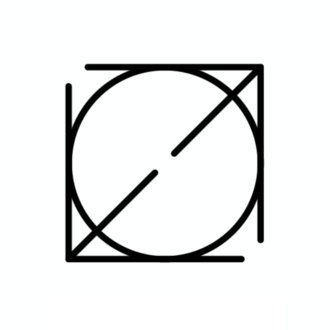ビジネスモデル3.0図鑑 #全文公開チャレンジ
『ビジネスモデル3.0図鑑』(刊行:KADOKAWA)を、2026年1月26日に発売します。国内外で13万部発行を超えた『ビジネスモデル2.0図鑑』の続編です。
本書は、ビジネスモデルの「動的な変化」をどう表現できるかに挑戦した一冊です。前作以降、大きく変化した社会や産業の環境を踏まえ、「共創性」と「適応性」を新たな軸として設定しました。さまざまな主体とどのように共創し、どのように時代に適応してきたのか。その視点から、国内外の注目企業50事例を収録しています。
そして今回、発売前に書籍の全文を公開します。
前作『ビジネスモデル2.0図鑑』でも全文公開を行いましたが、10万文字を超え、100枚以上の図解を含むビジネス書を、発売前に全文・無期限・無料で公開するのは、かなり珍しい試みだと思います。
内容をご覧いただき、共感いただけた方は、ぜひ書籍も手に取っていただけたら嬉しいです。
なお、本記事内の書籍購入リンクは、バリューブックスに設定しています。
バリューブックスは本書に掲載している50事例のひとつであり、大手プラットフォームに依存しすぎない循環型の出版流通をつくる挑戦を続けている企業です。その取り組みを応援したいという意図から、このリンク先を選んでいます。
なぜ全文公開という形を取ったのか。その理由や背景については、プレスリリースで詳しく説明しています。ご関心のある方は、あわせてご覧ください。
なお、本記事は書籍の内容をそのまま掲載しているため、「●●ページ参照」といった表現が一部残っています。オンライン記事としては分かりづらい部分もありますが、あらかじめご了承ください。
また、本記事の内容について、無断での転載、複製、改変等はご遠慮ください。シェアいただく場合は、本記事へのリンクという形でお願いします。
それでは『ビジネスモデル3.0図鑑』、スタートです!
ビジネスモデル3.0図鑑 目次(note簡易版)
● はじめに
● 序章「ビジネスモデル3.0」とはなにか?
・「ビジネス」はどこへ向かおうとしているのか?
・変わりつつある「企業が担うべき役割」
・変化を迫られてきた「ビジネスモデル」
・「ビジネスモデル1.0」から「ビジネスモデル2.0」へ
・「ビジネスモデル3.0」とは何か?
・「共創性」「適応性」という新視点
・「パーパスモデル」で明らかになったもの
・自らの構造を柔軟に変えていく力
・新しい「経済性の測り方」
・現行の会計構造にある限界
・新しい「会計」の考え方
・インパクト会計
・付加価値分配計算書
・複雑なものを、複雑なままに扱う
・「整いすぎた真実」になっていないか?
・図解には「重力」がある
・新たな関係をつくり出すためのたたき台
・変化を読み解くための紙面構成
・ビジネスモデルの背景にある「ストーリー」をつかむ
・「1.0」から「2.0」、そして「3.0」へ
・ビジネスは “ 動的な構造” として存在していく
・本書が目指すもの
・何のために、誰と、どう未来をつくるか?
● 図解の説明書
● ページの見方
● 第1章 「みつける」 新たな顧客・需要を見出す
Langaku, Arc & Beyond, esse-sense, イノカ, コミュニティナース, URASHIMA VILLAGE, BIOTA
・「みつける」チェックリスト
● 第2章 「ひろげる」 新たな市場・地域への進出
タイミー, ヘラルボニー, おてつたび, wash+, イークラウド, ADDress, RENATUS ROBOTICS, 五常・アンド・カンパニー, HADO, 逆プロポ, EFポリマー, NEWLOCAL,Oishii Farm, The Elephant People, アラビンド眼科病院, Fairphone
・「ひろげる」チェックリスト
● 第3章 「ふかめる」 新たな商品・価値を追求する
丸井グループ, マザーハウス, 星野リゾート, 久遠チョコレート, CRISP SALAD WORKS, find, 全国こども食堂支援センター・むすびえ, 神山まるごと高専, 配車頭, CLOUDY, ジーバーFOOD, SEKAI HOTEL, 宇宙水道局, シーベジタブル, Be My Eyes, Alife Holdings, KOTO
・「ふかめる」チェックリスト
● 第4章 「ふみだす」 新たな領域・状況への挑戦
よーじや, バリューブックス, 中川政七商店, ボーダレスジャパン, NOT A HOTEL, コングラント, Kuradashi, Ecosia, トニーズ・チョコロンリー, Too Good To Go
・「ふみだす」チェックリスト
● 本書の内容理解をさらに広げるために
● 自分で「ビジネスモデル3.0」を図解してみよう
● おわりに
はじめに
本書は、ビジネスモデルの「動的な変化」をどう表すことができるかに挑戦したものだ。
この本を手に取ったあなたは、おそらくビジネスや社会の仕組みに関心がある人だろう。でも、その中で「自分はビジネスが得意だ」と胸を張って言える人はどのくらいいるだろうか?
そもそも「ビジネスが得意」というのは、どういう状態を指すのだろう。収益を上げていることだろうか。年収が高いことだろうか。それとも、自分の働きが数字としてわかりやすく表れていることだろうか。
僕は長いあいだ、ビジネスの世界にうまく馴染めていない気がしていた。数字や計画を軸に語られるビジネスの言葉が、自分の見ている現実と重ならなかったからだ。まわりには、成果を数値で証明できる人も多くて、彼らは「ビジネスが得意」な人に見えた。でも、僕はどうしても、それと同じ尺度では考えられなかった。お金や成果を通してではなく、関係のつくり方や仕組みの流れを見てしまうのだ。
そんな中で、僕にとっての突破口になったのが「図解」だった。数字や言葉で説明できないことを、関係性として整理してみる。すると、バラバラだったもののあいだに、つながりが見えてくる。
たとえば、「誰のために」「何を」「どのように」「誰と」「どうやって」「お金が動くのか」。それを線でつなぐと、頭の中に散らばっていた断片が一つの構造として立ち上がる。
図解を描くことは、正解を見つける作業ではなく、むしろ「問いを整理する作業」に近い。図を描いていると、自分が何を理解していないのかが見えてくる。「理解」とは、知らないことをなくすことではなく、知らないことをきちんと見えるようにすることなのだと気付いていく。
社会の「仕組み」は常に動き続ける
こうして図解を描き続けるうちに、 「ビジネスが苦手」という僕の感覚は少しずつ変わっていった。ビジネスを数字や競争で語るのではなく、仕組みや構造としてる。そうとらえた瞬間に、苦手意識がすっと軽くなったのだ。
前作『ビジネスモデル2.0図鑑』をつくったとき、社会性・経済性・創造性という3つの視点をもとに事例を整理した。そして多くの人に読まれ、たくさんの反響をいただいた。でも、つくりながら感じていたのは、「静止画だけでは伝わらない変化がある」ということだった。どんなにうまく仕組みを描いても、そこにあるのは“ある瞬間の写真”でしかない。社会の仕組みは常に動いていて、そこに関わる人の意思や状況によって形を変え続けている。
では、動いているビジネスモデルをどう描けばいいのか。僕は今回、ビジネスモデルを「静的なもの」から「動的なもの」として描くことにした。
くわしくは序章で述べるが、本作では「1つの事例を2 枚の図で表す構成」にしている。1枚目は「BEFORE」で、変化の前の状態。もう1枚は「AFTER」で、変化した後の構造。2枚のあいだにある“差分”を読み解くことで、何が課題だったのか、なぜその仕組みに変わったのかが見えてくる。「変化」とは偶然起きる出来事ではなく、構造を組み替えることで生まれる結果なのだ。
この方法をとることで、ビジネスモデルを「静的なもの」から「動的なもの」としてとらえ直せるようになり、事業の進化や組織の成長を、「出来事」としてではなく「構造」として描けるようになった。これが、本書における最大の挑戦だった。
そして本書では、取り上げるビジネスモデルの事例数を、前作の「100」から「50」とあえて減らし、逆に、1 事例あたりの展開ページ数を「2」から「4」と倍にして、変化の背景や構造をより深く掘り下げている。つまり、前作が「事例を数多く並べ、〈仕組みの構造〉を俯瞰する図鑑」だったとすれば、本作は「事例をより厳選し、〈仕組みの変化〉を観察する図鑑」といえるだろう。
ビジネスモデルの事例数を半分にしたことで、一つひとつの事例に含まれる情報の密度を上げて量を増やすよりも、掘り下げを深める。変化のプロセスを描くには、その“深さ”が必要と考えたわけだが、これは、一つの仕組みをより立体的にとらえ、その中にある“動き”を見えるようにするための再設計だった。量から質へ、静から動へ。ビジネスの仕組みをより深くとらえるために、事例を解説するページ展開の構造そのものを変えたのだ。
本書では、創業100年以上の老舗企業から、最先端のスタートアップ、海外の社会的企業やテクノロジー企業まで、厳選した50の事例を取り上げている。そこには大企業の経営戦略もあれば、地域で小さくはじまった取り組みもある。しかし、一見まったく異なるように見えても、それぞれの事例には共通する“構造の知恵”がある。
たとえば、ある企業は、利益の使い方を変えることで社会との関係を更新し、別のある企業は、社員や顧客を巻き込みながら新しい価値をつくっている。あるいは、資産の持ち方やお金の流れを変えることで新しい仕組みを生み出している。重要なのは、規模の大小や業種の違いではなく、「どんな構造の工夫によって変化が起きたのか」という点だ。
「ビジネス」とは何なのか?
本書を通じて描きたかったのは、「成功事例の紹介」ではなく、「仕組みの進化の記録」だ。「ビジネス」とは、社会を動かす最小の仕組みであり、人やお金や情報がどう関係し合うかで結果が変わる。そこには正解がなく、常に変化がある。その変化の構造を見抜くことができれば、ビジネスはもっと面白く、もっと自分事になる。
「図解」という手法は、そのための“観察装置”だ。理解するためではなく、見えるようにするためのもの。頭の中で複雑に絡み合っている関係をいったん外に取り出し、みんなで眺めてみる。すると、同じものを見ていても、人によって違うところに注目していることがわかる。それを議論しながら、少しずつ共通の理解をつくっていく。この過程そのものが、ビジネスの本質に近いと僕は感じている。
ビジネスとは、社会の中での関係性を設計する行為だ。そこに正しい形はない。時代や環境、人の価値観によって最適な関係や構造は変わっていく。大切なのは、その変化をどうとらえ、どう設計し直すか。自分たちで、社会に対してよりよい変化をつくり出すこと。自分たちの手で仕組みを描き換えていくこと。その積み重ねが、社会を前に進める力になる。
この本が目指すのは、読者それぞれが自分の現場で「構造を描く力」を持つことだ。どんな仕事にも必ず仕組みがある。仕組みを見えるようにすると、課題が構造として浮かび上がり、解決の糸口が見えてくる。
ビジネスの変化は「価値」と「領域」の2軸でとらえる
本書では、ビジネスモデルの変化を「価値」と「領域」という2つの軸でとらえている。これは、経営戦略論で知られるアンゾフのマトリクスを拡張したものだ。アンゾフは「商品」と「市場」という2つの軸を使い、企業の成長方向を「市場浸透」「市場開拓」「製品開発」「多角化」の4つに整理した。しかし本書では、対象を単なる商品や市場に限定せず、「社会の中でどんな価値をつくるか」「その価値をどの領域に広げるか」という観点で一段さらに抽象化した構造をとらえている。
「価値」とは、提供するモノやサービスに限らない。人との関係、制度、仕組み、文化といった、社会の中で機能するあらゆる意味付けを含む。そして「領域」とは、地理的な市場や業界の境界だけでなく、人々の生活圏、コミュニティ、行政、教育、環境など、価値が届けられる“社会的な場”全体を指す。
この2つをかけ合わせることで、ビジネスの変化を単なる成長の方向ではなく、構造がどう再設計されたかの型として整理できる。つまり、「どんな価値を」「どんな領域で」扱うかを変えることで、ビジネスはどのように社会と関わり直すのか。その関係性の変化を読み解くための地図が、下の「価値×領域」マトリクスだ。
こうして整理すると、ビジネスの変化をとらえる4つの「動き方の型」が見えてくる。価値と領域のかけ合わせによって、企業や組織がどの方向に構造を動かしているのかがわかる。本書では、その代表的な4つの型を1章ずつ取り上げている。どの型も、単なる戦略や事業計画の違いではなく、社会との関わり方の違いである。ここでまず、それぞれの型の中に、変化の構造がどのように現れるのかを見ていきたい。
第1章 「みつける」 新たな顧客・需要を見出す
既存の価値を扱いながら、まだ見えていなかった顧客や文脈を発見する「変化」。ここでは、同じ価値が違う意味で受け取られる瞬間を描き、新しいニーズをつくるのではなく、すでに存在していたものの見過ごされていた関係を発掘する。市場が飽和した時代に、どのようにして新しい問いや視点を見出すのか。これは、変化の出発点にあたる。たとえば、若者が担い手のいなかった職種に魅力を感じはじめるとか、新しい流通経路が地域の価値を再発見させるとか、そうした「再発見の構造」が、この章で扱う「変化」だ。
第2章 「ひろげる」 新たな市場・地域への進出
既存の価値を新しい領域に広げていく「変化」。市場や地域、業界の枠を越え、関係を再構築する。ここでは、単なる規模の拡大ではなく、文脈の拡張としての広げ方を扱う。別の業界や地域に参入することで、新しい関係性や連携の形が生まれる。「ひろげる」とは、価値の境界を開くことでもある。異なる領域に踏み込みながら、自らの価値を翻訳し直す。
第3章 「ふかめる」 新たな商品・価値を追求する
既存の領域の中で、提供する価値を磨き直す「変化」。商品やサービスを変えるだけでなく、体験や意味の層を深めていく。表面的な商品開発や改良ではなく、価値の源泉そのものを問い直す。ブランドが自らの存在理由を再定義したり、顧客との関係の深度を変えたりする動きがこれにあたる。
第4章 「ふみだす」 新たな領域・状況への挑戦
新しい価値を新しい領域で試みる「変化」。未知の分野への進出や新しい社会課題への挑戦、既存制度の外に新しい仕組みを立ち上げる動きなどがここに含まれる。変化の中で最も不確実な領域であり、同時に、新しい発見や協働も生まれやすい。既存の延長線を越え、社会との関係のあり方そのものを描き換える「変化」だ。
「変化の型」を見つけ、自分の現場に置き換える
以上、本書で取り上げる「4つの型」は、個々の企業の戦略や施策を超え、ビジネスの変化そのものを読み解くためのレンズともいえる。どの型も単独で完結するわけではなく、互いに重なり合い、行き来しながら変化が進んでいく。4つの型は序列を持つものではなく、それぞれの事業や状況に応じて異なる役割を果たすのだ。
重要なのは、どの型をとるかを偶然に任せるのではなく、自社の状況を踏まえて意識的に選ぶこと。変化の型を理解し、自らの構造をどの方向に動かすのかを判断できることが、変化を設計する第一歩になる。本書では、それぞれの型を個別に紹介しながらも、全体として、ビジネスがどのように社会の変化をつくり出しているかを見通せる構成にしている。
本書の読み方としては、最初から順に読んでもいいし、自分の関心に近い章から入ってもかまわない。どの事例にも共通しているのは、変化の背景に「構造の工夫」があるということ。どんな企業も、どんな個人も、「変化の型」を持っている。その型を見つけ、自分の現場に置き換えて考えることが、この本を読む一番の醍醐味だと思う。
最後にあらためてお伝えしたいのは、ビジネスに苦手意識を持つ人にこそ、この本を開いてほしいということだ。ビジネスは一部の人だけの専門領域ではない。誰もが社会の中で関係をつくり、何かを動かしている。その構造を理解し、意識的に変えられるようになると、働くことも、そして生きることも、少しだけ違って見えてくるはずだ。
ビジネスは、世界を構成する仕組みの一つだ。そして、その仕組みは、誰かが描き、誰かが動かしているもの。だからこそ、仕組みを描く力を持つことは、社会をよりよくする力につながっていく。本書がその第一歩を踏み出すための道具の一つになってくれれば本当にうれしく思う。
近藤哲朗
序章 「ビジネスモデル3.0」とは何か?
「ビジネス」はどこへ向かおうとしているのか?
変わりつつある「企業が担うべき役割」
「変化が激しい時代」という言葉は、もはや聞き慣れたものになった。気候変動やパンデミック、生成AI、国際情勢の不安定化。これまで想定外とされていた出来事が、いまや日常の延長線上で起きている。社会は変化を織り込みながら動く仕組みになりつつある。だがその一方で、制度や企業の多くはいまだ過去の前提を引きずり、現実のスピードとのあいだにずれを抱えている。
社会の構造が変わるとき、ビジネスの意味も変わる。「ビジネスモデル」とは、単にお金を稼ぐ仕組みではなく、社会の中「誰が」「何を」「どのように」価値として受け取り合うかを定める関係の設計図だ。つまり、ビジネスモデルを問うことは、社会における関係のあり方を問うことにほかならない。これまでは、経済活動と、社会の営みがあたかも別の領域であるかのようにとらえられてきた。企業は市場の中で成果を追求し、社会はその外側でそれを受け取る存在と見なされていた。しかしいま、環境問題や人口構成の変化、デジタル化などを通じて、両者の境界は急速に溶けはじめている。
たとえば、SNS上の個人的な発信が企業のブランド価値を大きく左右し、企業の意思決定が環境や人権の問題と直結するようになった。個人の消費行動や働き方が社会的なメッセージを帯び、同時に企業の評価にも影響を与えている。もはや、企業と社会は対立する存在ではなく、一つの構造の中で相互に作用し合う関係になっている。だからこそ、企業が担うべき役割は「市場で利益を生み出すこと」から「社会の仕組みを更新すること」へと変わりつつある。
こうした構造転換の中で、あらためて「ビジネスモデル」という概念を見直す必要がある。従来のビジネスモデルは、効率や差別化を重視する静的な設計だった。だが現代では、ビジネスモデルそのものが社会との関係の中で常に変化し続ける。一つの事業構造を固定的に描くだけでは、現実をとらえきれない。いま必要なのは、「どのように変化をつくり出し」「どのように構造を再設計しているのか」を読み解く視点だ。
企業の目的もまた、変化している。かつては成長や拡大が目的だったが、いまは社会の中で持続的に機能し続けることが問われている。収益を生み出すだけでなく、社会課題の解決や文化の形成にどのように貢献できるかが、企業の存在意義を規定する。ビジネスの本質は、経済活動を通じて社会の仕組みをよりよく設計し直すことにある。だからこそ、ビジネスモデルを「利益の構造」としてではなく、「関係の構造」としてとらえ直す必要があるのだ。
変化を迫られてきた「ビジネスモデル」
「ビジネスモデル1.0」から「ビジネスモデル2.0」へ
「ビジネスモデル」という言葉が注目を集めはじめたのは、1990年代後半から2000年代初頭にかけてのことで、当時の関心は「どうすれば効率的に収益を上げられるか」という一点に集中していた。コストを下げ、スケールを拡大し、競争優位を確立すること。市場の成長を前提に、資本をどう循環させるかを設計すること。それが、いわば「ビジネスモデル1.0」の基本構造だった。
当時は、企業が経済合理性を追求すること自体が社会貢献につながると信じられていた。価値の起点は企業の側にあり、社会はそれを受け取る側として位置付けられていた。企業は製品やサービスを一方向に供給し、顧客はそれを消費する存在。社会は「市場」という名の前提条件のもとに整理され、企業活動と切り離された構造の中で語られていた。
しかし、利益を最大化するこの構造は、同時に多くのゆがみを生んだ。環境破壊や格差拡大、過剰消費。経済の成長を支えたそうした仕組みが、持続可能性を脅かす仕組みに転じていったのである。
そして2000年代後半になると、企業は「何のために存在するのか」という根源的な問いに直面する。社会の中でどのような意味を持つのか、どう貢献できるのか。そのような問いから、2018年に刊行した『ビジネスモデル2.0図鑑』で提唱したのが、 「ビジネスモデル2.0」という概念だった。
「ビジネスモデル2.0」は、経済性に加え、社会性と創造性を満たしたビジネスモデルを志向する概念だ。これは、いわば社会性と経済性の両立を目指す構造である。企業が利益を生み出すだけでなく、社会的価値の創出をも事業の目的に組み込みはじめた時代に、この考え方は広がっていった。企業の存在意義は「誰のために、どのような価値を生み出すのか」という問いのもとで見直され、経営そのものが社会との関係性の中で語られるようになった。
この流れで企業の活動が社会課題の解決とつながり、持続可能な経営を目指す動きが広まった。しかし、社会性と経済性はときに対立し、どちらかを優先すれば、もう一方が損なわれる構造的な緊張を抱えていた。その社会性と経済性の二項対立を超えるカギとして、ビジネスモデルには「創造性」が必要だった。
ここでの創造性をとらえるため、本書の前作となる『ビジネスモデル2.0図鑑』では「逆説の構造」という考え方を提示した。「ふつうはこうするけど、これはその逆で、こうしたんだよね」といった、ある「起点」に対してあたりまえとされる「定説」と、その逆にあたる「逆説」を考えるということだ。この考え方は、定説と逆説という2つの構造を対比しつつも、価値の転換がどのように起きたのかをとらえることができる。たとえば、「支援される側が支援する側にまわる」「競争していた企業と共創する」など、従来の関係が反転する瞬間に、新しいビジネスの可能性が生まれる。創造性とは、矛盾の中に潜む構造を見抜き、それを再設計する力である。
この創造性こそ「ビジネスモデル2.0」の核心だった。社会性と経済性という異なる価値を、対立させずに新たな関係として再構成する力。それは、複雑な社会の中で矛盾を受け入れながら、よりよい仕組みを探し続ける態度でもあった。
ところが、これら「社会性」「経済性」「創造性」という3つの軸ですべてかと思っていた中、より混沌を極めた現代にあらためて考えてみると、この3つでは言い得ない、ある2つの軸が浮かび上がってきた。
「ビジネスモデル3.0」とは何か?
「共創性」「適応性」という新視点
「ビジネスモデル3.0」とは、現代のビジネスモデルのあり方をとらえ直した概念だ。これは、「共創性」と「適応性」の2つのキーワードが軸になっている。
共創性:企業が自ら価値をつくり出し、人々に一方的に届けていた時代から、社員・顧客・地域・社会といった多様な主体と共に価値を育て合う時代へ
適応性:変化を予測して計画を立て、正解を用意する時代から、変化そのものを受け入れ、自らの仕組みを変えながら前に進む時代へ
これら2つの要素が、「ビジネスモデル2.0」で定義していた「社会性」「経済性」「創造性」という3つに新たに加わる形となる。
「共創性」は、ビジネスを「関係の設計」としてとらえる姿勢である。これまでの「社会性」が、多様なステークホルダーに配慮しながら「八方よし」の関係を築くことを重んじてきたとすれば、 「共創性」はさらに一歩進み、ステークホルダーと共に価値を生み出すことに焦点を当てる。
つまり、単に意見を集約するのではなく、異なる立場や目的を持つ人々が、ぶつかり合いながらも新しい仕組みや価値をつくっていく行為だ。
もちろん、誰とでも共創できるわけではない。自ら主体的に動く「自律的なステークホルダー」と、外側から支える「他律的なステークホルダー」を見極めながら、関係の重なりをどう設計するかがカギになる。これが、「ビジネスモデル3.0」における「関係の設計」の中核だ。
一方、「適応性」は「時間の設計」に関わる視点である。
「創造性」が、既存の構造を反転させて新しい価値を生み出す力だとすれば、「適応性」は、その変化を時間の中でどう続けていくかという力だ。
「逆説の構造」の考え方では、ある時代の逆説は、やがて定説へと変わっていく。つまり、逆説とは未来の定説を先取りする構造でもある。
「ビジネスモデル3.0」では、この動的な変化の流れを一過性のものとしてではなく、意図的に設計できるものとしてとらえる。「適応性」とは、予測不能な環境の中で自らの構造を更新し続ける力であり、変化を「受け入れる力」ではなく、「つくり出す力」である。
「共創性」と「適応性」は、それぞれが空間(関係)と時間(変化)の次元を担う。どちらも完成を目指すものではない。異なる主体の関係をどう設計し、変化の流れの中でどう再構築していくか。その連続的な再設計の過程こそが、「ビジネスモデル3.0」の本質だ。
「パーパスモデル」で明らかになったもの
「共創性」という考え方を深めるうえで重要なきっかけになったのが、僕自身が吉備友理恵氏との共著で執筆した『パーパスモデル』(学芸出版社)である。この本は「よりよい社会を実現するための行動原理=パーパス」を中心に、多様なステークホルダーが関わる共創プロジェクトの設計図を描いたものだ。企業、行政、市民、研究者など、立場の異なる主体が共通の目的を共有し、受発注を超えた価値の循環を生み出すことを目指している。
「パーパス」という言葉はよく、「ビジョン」や「ミッション」と並べて語られるが、決定的に異なる点がある。それは、目指すべき社会が起点にあるかどうかだ。ビジョンやミッションは、一般に自社を起点に「私たちは何者になりたいか」を描く方向性として語られる。一方でパーパスは、社会を起点に「社会がどうあるべきか」から考え、その共通の目的が多様な人を結びつける。だからこそ、優れたパーパスには自然と共創性が宿るのだ。
「パーパスモデル」の制作を通じて見えてきたのは、共創とは理念ではなく、設計行為だということ。誰とどのような関係を結ぶのか。どの関係を中心に据え、どの関係を緩やかに接続するのか。これらを意識的に描くことこそが「関係の設計」であり、共創性の実践そのものである。
パーパスモデルの特徴の一つは、ステークホルダーを2層に分けて整理している点にある。上半分には、顧客や企業など共創に関与する「他律的なステークホルダー」。下半分には、主体的に共創に関与する「自律的なステークホルダー」がいる。
これらすべての関係を同じ水準で共創するのではなく、それぞれの主体がどのように関わるかを意識的に設計することが重要で、この区分は排除のためではなく、関係を構築するための設計上の判断である。
パーパスモデルで明確になったのは、共創性とは共に価値をつくる能動的な構造を指すということ。社会性が「誰も取りこぼさない」という配慮の思想だとすれば、共創性は「八方よし」を土台に、八方とどう関わるかを問い直す姿勢だ。
自らの構造を柔軟に変えていく力
同様に、「適応性」という考え方を深めるうえで、もう一つの契機となったのが、2023年刊の『政策図解』(日経BP)だった。これは50の政策を共通の型で可視化した、いわば本書の政策版ともいえる一冊だ。その制作を通じて痛感したのは、どれほど個々の仕組みを工夫しても、制度の前提そのものが変わる瞬間には、すべてのロジックが組み替えを迫られるということだった。法律や税制、教育や福祉といった制度は固定的に見えて、実際には時間の流れの中で絶えず再設計され続けている。
制度が変わるとは、社会全体のルールが変わるということだ。たとえば、ビジネスの前提となる法律が変われば企業や市民の行動も連動して変化する。つまり、制度の設計は社会の前提そのものを動かす行為だと気付いたのだ。この気付きが、変わりゆく前提の中で「時間をどう設計するか」という視点、すなわち「ビジネスモデル3.0」における適応性=時間の設計の発想へとつながった。適応性とは、固定的な未来を予測して備えることではない。むしろ、制度や環境の変化によって前提が変わることを見据えつつ、自らの構造を柔軟に更新していく力である。そこでは変化をリスクとして避けるのではなく、社会の変化を取り込みながら、自らの仕組みを再定義する姿勢が求められる。だからこそ、変化に反応するだけでなく、時間の流れそのものを設計する主体であることが、これからの組織や個人に問われている。
新しい「経済性の測り方」
現行の会計構造にある限界
「共創性」と「適応性」という2つの軸が加わった「ビジネスモデル3.0」をもってしても、なお課題として残るのが「経済性そのものをどう測るか」である。僕たちは日々、企業や社会の活動を「どれだけ利益を上げたか」「どれだけ企業価値があるか」といった数値で判断している。これらの数字を定める基準となっているのが「会計」であり、つまり会計とは、社会の価値を測る“物差し”でもある。
しかし現在の会計制度は、依然として経済的な成果を中心に設計されていて、社会や環境への影響、信頼やブランドといった「経済の外側にある価値」は十分にとらえられていない。そうした見えない価値をどのように測るか、その限界を明らかにしたのが、僕が2021年に刊行した『会計の地図』(ダイヤモンド社)だった。本作では、会計の構造を「地図」として可視化し、資本・負債・資産・収益・費用といった要素を1枚のマップに整理した。その中で見えてきたのは、経済合理性の中ではとらえきれない価値の流れだった。
たとえば、企業が長年にわたって積み上げてきたブランド力や信頼、ノウハウなどは「自己創設のれん」と呼ばれ、財務諸表には記録されない。だが、こうした“のれん”のような無形の資産こそ重要なのだ。企業の価値を示す指標の一つである「PBR(株価純資産倍率)」は、その“のれん”を間接的に可視化する概念でもある。PBRは、企業の時価総額が純資産をどれだけ上まわっているかを示すものであり、言い換えれば“のれんを生み出す力”の大きさを表している。つまり、ブランドや信用、人的資本といった無形の価値がどれほど社会から評価されているかを測る一つの目安として機能しているのだ。
とはいえ、「PBR」や「のれん」がすべての無形的な価値をとらえきれているわけではない。会計の制度上、社会的インパクトや環境への影響、組織文化のような多くの要素は、いまだ間接的で測定の枠外に置かれている。こうした現行の会計構造には、経済合理性の中ではとらえきれない限界がある。会計という社会の物差しそのものを更新しなければ、社会の構造転換は起こりにくい。
新しい「会計」の考え方
インパクト会計
現行の会計構造を更新しようとする動きの一つに「インパクト会計」がある。これは、より包括的で持続可能な資本主義にしていくために、企業活動の成果を金銭的な価値だけでなく社会的な価値まで含もうとする試みで、利益とインパクトを統合しようというかなりチャレンジングなものだ。何か社会にとってよくない「負」のインパクトを与えた企業は最終的な利益が減らされ、社会に正のインパクトを生んだ企業は利益が加算されるという、いわば利益の拡張である。この考え方はまだ研究段階だが、日本でもいくつかの企業は実際に取り入れはじめている。
付加価値分配計算書
また、早稲田大学のスズキトモ教授による『「新しい資本主義」のアカウンティング』(中央経済社)では、企業が生産する価値の配分構造そのものを見直す会計の枠組みが提案されている。資本主義のもとで株主に偏ってきた付加価値の配分を、従業員や経営者、再投資、研究開発などへと広げ、より公正な分配を実現しようとするものだ。
ここでの焦点は、特定のステークホルダーに利益が集中する構造的課題を正し、企業が生み出す価値を社会全体で分かち合う方向へ転換する点にある。つまり、企業の成果を「誰が、どう受け取るのか」という視点で問い直す会計だ。
「ビジネスモデル3.0」は、こうした会計の再設計とも深くつながっている。どれほど「社会性」や「共創性」、「適応性」が進化しても、成果の配分が一部に偏れば、構造の転換は実現しにくい。変えるべきは価値そのものではなく、価値を測り、分ける仕組みである。事業の本質的な変化は、会計の物差しが変わるときに初めて社会と結び直される。本書で紹介する事例も、仕組みの再設計と共に、価値をどう測り、どう分配するかという問いに向き合う試みなのだ。
複雑なものを、複雑なままに扱う
「整いすぎた真実」になっていないか?
「ビジネスモデル3.0」の背景にあるもう一つの前提は、「複雑なものを、複雑なままに扱う」という姿勢だ。僕たちはこれまで、社会やビジネスの構造を理解するために、関係を線で結び、流れを矢印で示し、因果を整理してきた。図解は、複雑な現実を一度外に取り出して見えるようにするための装置である。だが同時に、それは「見えないものを切り捨てる行為」でもある。構造を描くということは、どこかで現実を単純化するということでもあるからだ。
社会課題や制度、組織の意思決定のような複雑な現象は、単純な因果関係では説明できない。多様な立場や時間軸が重なり合い、矛盾や葛藤が存在する。そこには、意図せず生まれる副作用や、誰かにとっての利益がほかの誰かの損失になるような構造もある。
それらを1枚の図に落とし込むとき、どうしても「整いすぎた真実」になってしまう危うさがある。図解には、理解を助ける力と同時に、世界を過剰に単純化してしまう暴力性がある。
そのことを痛感したのが、僕が富山県の黒部地域で取り組んでいる「移動課題マップ」の作成だった。このマップは、地域の移動に関する課題を因果関係で整理し、行政、企業、地域住民など異なる立場の人々の課題がどのようにつながり合っているのかを可視化したものだ。
たとえば、「高齢化」や「送迎のたいへんさ」、「免許返納」など、個別の課題として見えていたものが、交通手段の不足や行政の支援体制、地域内の助け合いといった要素と複雑に絡み合い、一つの構造を形成していることが見えてくる。しかし同時に、このマップもまた、現実の一部しか切り取れていない。描かれていない関係や声が、常にその外側に広がっている。
一方で、複雑な情報をそのまま提示しても、必ずしも届くとは限らない。だからこそ、図解を描くときには「何のために」「誰に」「何を」伝えるのかという目的が重要になる。本書では、必要な複雑さをできる限り残しつつも、共有の土台となる要素に焦点を当てて整理している。
図解は、現実をすべて写し取るものではない。多くの情報や視点の中から、共通理解に必要な要素をすくい上げ、対話のきっかけをつくる行為だ。「ビジネスモデル3.0」の図解で示されるのは、全体の一部にすぎない。だからこそ、何が描かれているのかと同じくらい、何が描かれていないのかにも目を向けてほしい。図解は理解の終点ではなく、考えを深めていくための入口なのだ。
図解には「重力」がある
新たな関係をつくり出すためのたたき台
図解には「重力」がある。空中戦になりがちな、抽象度が高くて概念的な議論を地に落として対話しやすくする力だ。
複雑な現実をそのまま言葉で語ろうとすると、立場によって見えているものが異なり、話がすれ違ってしまいがちだ。だが、図を描くことで同じ対象をいったん外に取り出し、みんなで“眺めること”ができるようになる。
図を描くという行為は、そんな、見えていなかった関係を仮に置いてみる試みだ。そこには常に暫定性がある。描かれた構造はあくまでその時点での仮説にすぎず、議論や実践を通じて更新されていく。
つまり、図解とは完成を目指すものではなく、対話しながら共創するためのツールだ。共通の理解をいったん可視化し、それをたたき台に新しい関係をつくる行為。それが「図解」という実践の本質なのだ。
だからこそ、「ビジネスモデル3.0」における図解は「動的なもの」を目指した。関係の変化や時間の流れを描き込み、変化そのものの構造を見えるようにする。これが、「ビジネスモデル3.0」での図解のあり方だ。本書では、その考え方を編集構成に落とし込み、「時間の中で、構造がどう変化したのか」を追えるようにしている。
変化を読み解くための紙面構成
ビジネスモデルの背景にある「ストーリー」をつかむ
本書は、1つの事例を4ページで紹介するという構成になっている。
まず1ページ目には、ビジネスモデルの図解を掲載している。これは、「創業時」や「初期段階」など、変化の前提となる基本構造を描いたものだ。どんな仕組みで価値を生み出していたのか、その出発点をここでつかんでほしい。
2ページ目には、概要解説を掲載。写真が入るものもあり、その事業の背景や文脈を補足するページだ。
3ページ目からが、本書の最も特徴的な部分だ。ここでは「変化のポイント」として「課題」「対応/構想」「結果」の3つを描いている。事業者がどんな課題に直面し、どのように構造を組み替えて対応(構想)し、その結果として何が変わったのか。変化を単なる出来事ではなく、構造の再設計として読み解くための視点だ。
そして最後の4 ページ目には、再び図解を掲載している。これは、1ページ目で示した基本構造が、その後どのように変化したのかを描いた「AFTER」の図だ。「BEFORE」と「AFTER」のあいだにある “差分” を見比べることで、変化の仕組みが、どこで、どのように動いたのかが浮かび上がってくる。この構成は、「起承転結」のように構造の変化そのものを物語として読むための設計である。ここでの「変化」とは偶然の出来事ではなく、必ずそこには再設計の意思と構造の工夫がある。本書における「4ページ構成」は、その意思と構造の痕跡をたどるための地図のようなものなのだ。
「1.0」から「2.0」、そして「3.0」へ
ビジネスは “動的な構造” として存在していく
1.0での「効率と拡大」から、2.0での「共感と責任」へ。そして3.0では「共創と変化」を育てるビジネスへ。この流れは単なる“進化” ではなく、むしろ、“ビジネスとは何か”という問いをその時代の価値観ごとに繰り返し更新してきた歴史だといえるだろう。
「ビジネスモデル2.0」が目指したのは、社会性と経済性を両立させるための構造の発見だった。一方で、「ビジネスモデル3.0」が目指すのは、構造そのものを社会と共に更新し続けることである。
社会や制度、価値観の前提が変わり続ける中で、ビジネスはもはや固定的な仕組みではなく、関係や時間の流れの中で進化し続ける“動的な構造”として存在していく。つまり「3.0」とは、社会と共に変化するビジネスモデルのあり方を描く試みである。それは、利益や効率を超えた次元で、社会の未来を共に設計していくための枠組みでもあるのだ。
本書が目指すもの
何のために、誰と、どう未来をつくるか?
本書で紹介する事例の多くは、誰か一人の天才によるものというよりも、社会や現場、生活者との協働から生まれたものだ。そこには、課題と制約と関係性があり、その中で育まれた小さな仕組みや知恵がたくさんある。
この本では、そうした実践の中に宿る「仕組みの知恵」を、できる限り構造として可視化し、未来につながる共有財産にしていきたいと思っている。そして、読者一人ひとりの中に、「こういうビジネスもできるかもしれない」という小さな可能性の種を宿すことが、この本のもう一つの役割だと信じている。
「どうやって稼ぐか」を超え、「何のために、誰と、どう未来をつくるか」を問う時代へ。本書『ビジネスモデル3.0図鑑』は、その変化の中にある事例と構造を拾い集めた、いわば“未来の試作品集”なのである。
第1章 「みつける」 新たな顧客・需要を見出す
価値や領域を大きく変えず、見過ごされていたニーズや文脈を掘り起こす動き。新たな意味や関係性を探索し、「これまでアプローチできていなかった顧客や使われ方を再発見している」事例を取り上げる。
Langaku
BEFORE:2022年時点
楽しくマンガを読むだけで、無理なく英語多読学習が可能に!
英語の習得では、個々の能力に適した方法を見つけることが重要だが、そんな中、 「多読学習」というアプローチが注目を集めている。この学習法は文字通り、英文を大量に読むことが特徴で、10か月の英語留学にも匹敵するといわれている。一方で、自身の語学力や趣味嗜好にマッチする多読教材を探すことは容易でなく、約25%の多読経験者が「読みたいコンテンツを探せない」ことを理由に多読学習を中断しているという。
この問題に対処するため、デジタル技術を活用した新しい方法が登場している。それが、マンガを使った英語学習を提供するスマートフォンアプリ「Langaku」だ。このアプリは、Langakuを運営するMantra株式会社に出資も行う集英社の全面協力を得ており、大人気のマンガが揃っていることも魅力。集英社から同社に貸し出される作品は北米向けに翻訳出版されたもので、名作とされる数々のマンガを、英語で大量に楽しんで読む「多読学習」ができるようになっている。
Langakuは、マンガの特性を活かした英語多読を続けやすくすることを目指して設計されている。英語に慣れていない人にとって、いきなりすべての情報が英語化されると負荷が高い。そこでLangakuでは、ワンタップで日本語と英語を切り替える機能や、学習レベルに応じて英語のコマ数を調整できる機能、読み上げ機能など、学習を助ける工夫が施されている。
これらの機能を支えているのが、Langakuを運営するMantra株式会社が翻訳エンジンの研究開発で培ってきた周辺技術だ。翻訳エンジン自体はLangakuで直接用いられていないが、そのエンジンを通じて培った技術で、学習者が英語でマンガを読みやすくなるような機能を実現できている。
同サービスは無料でも利用可能だが、月額980円からのメンバーシップに加入することで、マンガがたくさん読めたり、AI学習機能が使い放題になるなどの特典がある。
【 課題 】
英語学習とエンタメ目的、どちらにフォーカスするかで揺れていた
サービス開始時から、「すでに英語学習をはじめている人」と「マンガを読むついでに英語学習をはじめたい人」という2種類のユーザー層のどちらにフォーカスするかで揺れていた。しかし、ビジネスメディアで「英語多読アプリ」として紹介された反響を受け、前者の「すでに英語学習をはじめている人」のほうがLangakuに高いモチベーションを持ってくれていることに気付いた。
【 対応 】
英語学習者にフォーカスした開発・マーケティングに注力
これを機に、英語をまじめに学習したい人に向けてフォーカスし、AI解説機能をリリースするなど英語学習教材としての価値を高めていった。また、英語教育会社とコラボレーションするなど、英語学習市場でのマーケティングにも注力しはじめた。
【 結果 】
教育市場や海外展開を視野に
マンガを活用した英語多読の有効性が浸透してきたこともあり、高校の英語学習に導入されることも決定している。また、将来的に海外の外国語学習市場に対してもマーケットの拡大を見込んでいる。
AFTER:2025年時点
Arc & Beyond
BEFORE: 2024年時点
ソニーが30億円を預けてはじめたユニークな試み
かつてソニーの米国子会社でIoTブロック「MESH ™」の普及に挑んでいた石川洋人氏は、米国の現場である課題に直面した。日本では教育現場で受け入れられた製品が、米国ではほとんど売れず、むしろ「学ぶことから離れてしまう若者=「Disconnected Youth」が増えている状況を目の当たりにしたのだ。テクノロジーの力で学びを届けたいという思いとは裏腹に、収益だけを基準にすると本当に必要な人に価値が届かない。この経験は、石川氏に「社会課題に事業として持続的に向き合う仕組みが必要だ」という確信を与えた。
そして、日本に戻り法人設立を模索する中、ソニーグループのトップマネジメントから「ほとんど儲からないけれど、社会にとって価値がある。ソニーの未来をつくってほしい」との言葉を受けたことが大きな後押しとなった。こうして2024年4月、ソニーグループ発の非営利型一般社団法人「Arc&Beyond」が設立された。
Arc&Beyondが挑むのは「経済合理性の外側」にある社会課題。社会的意義は大きいのに、収益が見込めないため形にならなかった活動は数多い。そこで同法人は「Arc&Beyond基金」を設立し、寄付や預かり金を投資会社を通じて運用。その運用益を社会課題解決事業にまわすことで、収益性に縛られない取り組みを可能にした。ソニーグループ自身も30億円を預け入れ、基盤を力強く支えている。
この仕組みを支えるのが2種類の共創パートナー。基金に資金を提供する「ファンドパートナー」と、各プロジェクトに知識やノウハウを提供する「ソリューションパートナー」だ。両者が連携することで、資金面と実行面の両方を備えた事業が生まれる。場合によってはファンドパートナーがソリューションパートナーを兼ねて事業に関わることもある。
すでに教育や福祉、スポーツ、社会起業など幅広い領域で活動がはじまっている。具体例の一つが、ソニーマーケティングと連携した少年院でのプログラミング教育だ。IoTブロック「MESH ™」を使い、在院者が身近な課題をプログラムで解決する体験を設計。センサーを活用して「自分で考え、形にする」プロセスを学ぶ中で、成功体験や自己効力感を育んでいる。単なる教育機会の提供にとどまらず、その後の社会参画へとつなげていく構想も進んでいる。
Arc&Beyondの理念は「ネガティブをゼロにする」だけではなく、「ネガティブをポジティブに変える」ことにある。事業開発や運営費不足で立ち消えた取り組みを、テクノロジーやデザインを活用して持続可能な形に変換していく。誰もが胸を張って生きられる社会をつくるため、経済合理性の外側に挑戦する。その姿は、既存の営利・非営利の枠組みを越えた、新しい共創の形を提示しているのだ。
【 課題 】
共助の仕組みは必要だが仲間が集まらない
社会には、大企業が持つ資金や技術、人材などの豊富なリソースがある。しかし、それらは十分に社会的価値の創出に活かされてこなかった。Arc&Beyondはそのギャップを埋めるべく、基金と枠組みを整えて設立されたが、寄せられる声の多くは「資金を支援して」「事業を引き取って」という声が中心で、資金や人材を持ち寄って一緒に事業をつくる仲間はそう現れなかった。基金をどうまわし、誰と協働できるのかという「共助の仕組み」自体が立ち上げ期最大の課題となった。
【 対応 】
少年院を起点に実装&仕組み化
最初の一歩として、少年院でのプログラミング教育を開始。ソニーマーケティングと連携し、「MESH ™」を使う実践型カリキュラムを設計。在院者がセンサーとプログラミングで身近な不便を解決する体験を重ね、自己効力感を育む。運用益や行政などからの資金のみに頼るのではなく、仕組みとしてまわる形で実装した。単発の委託にとどめず、企業や専門家が参加しやすい協働の場を開き、次のプロジェクトに接続する導線をつくった。
【 結果 】
実装が信頼を生み、次の協働へ
この実装によって、教育現場での効果測定や教材資産が蓄積され、協働先の裾野も拡大傾向にある。立ち上げ後の運営は継続可能な形が実現でき、次は福祉・スポーツなどへの展開や就労・社会参画への接続を見据えている。少年院での事例が社内外の呼び水となり、資金だけでなく人材・知見を持ち寄る共創への関心が高まっている。
AFTER: 2025年時点
esse-sense
BEFORE: 2024年時点
研究者と社会を結びつける新しい形を提案
日本には約34万人もの大学所属研究者が存在する。日々の研究は本来、社会課題の解決や新たな価値の創出につながる潜在力を持つが、現実には、その成果は産業や政策の意思決定に反映されにくく、研究知は社会から切り離されたまま蓄積されている。大学内の評価制度は論文数や学術雑誌の影響度などに偏り、企業は短期的収益を重視して、研究者と社会のあいだに構造的な断絶が生じている。知が循環せず、社会も研究者も互いに孤立したままという状況が続いてきたのである。
この断絶をつなぎ直そうとするのが、2021年にNPO法人ミラツクを母体に設立された株式会社エッセンスである。この会社は、研究知を社会に開くためのメディア「esse-sense」を運営し、研究者自身の言葉で研究の背景や問いの根源を語る場をつくっている。取り上げる領域は、宇宙、AI、気候変動、哲学、建築、音楽など多岐にわたり、分野を超えた知の横断と偶然の出合いを意図的に設計している。論文では伝わらない研究者の人間性や探究の過程を可視化することで、知の担い手を社会と接続する試みである。
創業初期のエッセンスは、研究者にとって信頼できる存在となることを最優先に据えていた。研究者の利益に資する活動に徹し、金銭的な収益よりも、社会関係資本の蓄積を重視した。経済的資本ではなく、信頼そのものを資本と見なす設計思想が、創業期から一貫して根底にある。
この思想は会社の制度構造にも具体的に反映されている。エッセンスは「組合型の株式会社」という独自の形態を採用していて、株式会社でありながら、資本による支配が起きないように設計されている。出資比率にかかわらず、議決権は原則1人1票。資金の多寡ではなく、理念への共感を基準に投資家を迎える仕組みだ。短期的リターンを求める資本は排除され、活動目的や社会的意義を理解したうえで中長期的に関わる支援者だけが参加できる構造となっている。また、研究者の価値を毀損する事業を行わないことを、会社の根幹をなす定款に明記している。
この仕組みにより、資本と意思決定のあいだに生じがちな不均衡をなくし、「誰かの所有物ではなく、理念を共有する人々の公共財としての株式会社」を実現している。資本の民主化を、株式会社という制度の内部から実装しようとする点に、エッセンスの制度的挑戦がある。
さらに、研究者と市民を直接結ぶ試みとして、2023年には月額制で研究活動を支援できる「パトロン」制度を導入。支援者は講義や研究室見学を通じて研究の現場に触れ、研究者は社会の共感を得ながら継続的に活動資金を確保できる。メディアを介して生まれた関係性が、少額ながら経済的支援へと転化する仕組みであり、研究と社会を結ぶ最初の経済回路だった。
エッセンスの創業期は、研究知の社会的孤立を「関係と制度の再設計」によって解こうとした実験の段階だった。情報の発信を超え、研究と社会のあいだに “信頼のインフラ” を築くことこそが、次の段階で知を構造的に流通させるための基盤となっていった。
【 課題 】
専門用語に寄った検索構造が研究知を社会から遠ざけた
研究者の知を発信する仕組みは整いつつあったが、読者が能動的に研究者を見つける仕組みには課題があった。仮に特定のテーマで専門家を探そうにも、既存の検索手段は専門用語に依存していて、実務で使う用語の範囲で探すには困難だった。また、探して得られる情報も業績や所属が断片的で、どんな専門家なのかわかりにくい。そうした構造的な課題で、1人の研究者を見つけるのに60時間以上かかるとの見方もあった。
【 対応 】
専門用語の壁を越え、誰もが研究者を探せる仕組みに
投資家70名からの出資と銀行融資などにより約2億円の資金を確保し、メディア開発や運営などこれまでの活動を継続的に行いながらも、新たに企業や行政が自ら研究者を探せるサービス「ANSWER」を開発。23.5万人の大学所属研究者データを統合したこのサービスにより、専門用語がわからなくても研究者を探しやすく、かつ研究者の専門性が理解しやすくなった。また、生成AIの技術的進化もうまく取り入れることで、キーワードを入力する際には、一般的な用語をもとに研究者を探索しやすい専門用語を教えてくれる機能なども付けた。
【 結果 】
社会が自ら研究知を探索できる新たな市場が生まれた
数十時間を要した研究者探索が短時間で完了できるようになり、企業や行政が研究知に直接アクセス。R&D(研究開発)や投資戦略の立案に活用しやすくなり、探索コスト削減にとどまらず、研究知探索そのものが新しい市場として立ち上がる手応えを得た。エッセンスの取り組みは、知を構造化して流通させる段階に進化し、今後は、研究者が自らの活動を持続可能にするための収益循環を生み出す段階へ向かっている。
AFTER: 2025年時点
イノカ
BEFORE: 2021年時点
ラボで再現したサンゴ礁を活かし、展示や教育プログラムを通じて自然との接点をつくる事業
サンゴを愛する探究心が生んだ、海の環境を再現する技術
サンゴ礁は「海の熱帯雨林」と呼ばれるほど多様な生態系を育み、その資産価値は約80兆円にのぼるといわれ、観光や漁業、沿岸防災、医薬品開発など人類の暮らしに幅広く貢献している存在だ。しかし、この貴重な生態系は地球温暖化の影響で今世紀半ばには70~90%が死滅すると予測されている。サンゴの生態は繊細で、自然界では環境変化が激しく、科学的な検証や保全は長らく困難とされてきた。
世界有数の海洋資源国である日本は、国土の約12倍におよぶ広大な領海を持つ。その海には世界で確認されている約800種のサンゴのうち425種が生息し、突出した多様性を誇る。豊かな漁場を形成すると共に、将来的に新産業を生む可能性のある海洋資源の宝庫でもあり、ブルーエコノミーを支える基盤となっている。だが、この自然資本が失われれば、生物多様性の損失にとどまらず、漁業や観光、研究開発といった産業基盤そのものが揺らぎかねない。豊かな海をどう守り、次世代に引き継ぐかは、日本にとって喫緊の課題だ。
この課題に挑むため、2019年に設立されたのが株式会社イノカである。エンジニアの高倉葉太氏と、自宅に巨大なサンゴ水槽を構築していたアクアリストの増田直記氏が出会い、「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる。」というビジョンを掲げて創業した。彼らが開発した「環境移送技術®」は、AIやIoTを活用して水温・光・潮流を精緻に制御し、水槽内に特定の海洋生態系を再現する独自技術である。この技術によって、従来は沖縄など現地で年に一度しか観察できなかったサンゴの産卵を、東京のオフィスで再現することにも成功した。
「イノカ」の最初の事業は、この技術を活かした海洋教育プログラムだった。ショッピングモールや科学館にサンゴ水槽を設置し、子どもたちが海の生き物を観察しながら環境問題を学ぶ機会を提供した。三井不動産と連携して実施した「よこはまサンゴ礁ラボ2021」では、小学生が自ら観察や対話を通じて海の不思議を探求し、地球環境を自分事として考える体験が生まれた。これらの活動は単なるCSRにとどまらず、施設の集客イベントやスポンサー予算として事業収益をもたらし、創業期の重要な成長ドライバーとなった。
こうしてイノカは、環境移送技術®を研究者向けの実証にとどめず、都市に自然を再現し、人々が直接体験できる仕組みとして社会に広めていった。自然は遠くの海で守るものではなく、都市で触れ、学び、考えることができるものへ。その転換により教育や体験を通じた新しい自然との関わりが生まれ、次のフェーズに進むための基盤が築かれていった。
【 課題 】
生物多様性の重要性が市場で理解されず事業化が困難
創業初期のイノカにとって最大の課題は、生物多様性の価値が市場で十分に理解されず、事業化が難しかったこと。企業に相談しても「まだ考える余地がない」と断られることが多く、研究案件に発展しなかった。資金は教育イベントで確保していたが、研究設備の維持や人材確保には限界があり、ラボ技術を事業として確立する道筋を描くのに大きな困難を抱えていた。
【 対応 】
「TNFD」を追い風に企業との共同研究を本格化
イノカは独自の「環境移送技術®」を活用し、海の生態系を東京のラボに再現して、2022年には世界初となる、時期をコントロールしたサンゴの人工産卵実験に成功。その後、製品や素材が自然に与える影響を科学的に検証するサービスを展開した。さらに、自然関連リスクの開示を求める国際的な枠組みであるTNFDの動きが追い風となり、企業との共同研究が本格化した。こうした取り組みを通じて自然資本分野における信頼できる研究パートナーとしての立場を確立していった。
【 結果 】
研究案件が収益全体の柱となり、国際的なルール形成に参画
現在では研究案件が売上の中心を占め、企業の研究開発部門や新規事業部門からの委託が拡大。全体の約7割を研究案件が占めるまでに成長し、ネイチャーポジティブ関連の新規事業創出パートナーとして企業からの相談が寄せられている。環境省や国際標準化機構(ISO)関連の委員会にも参画。日本発の海洋生物多様性分野におけるルール形成を目指し、海外進出にも力を入れている。今後はマレーシアに設立したInnoqua Asia社を皮切りにグローバル市場でのプレゼンス拡大を目指す。
AFTER: 2025年時点
コミュニティナース
BEFORE: 2017年時点
積極的“おせっかい”で住民に寄り添い、街に助け合いの仕組みをつくる
日本の地域社会では、高齢化・核家族化・過疎化が同時に進み、医療や介護の制度だけでは支えきれない現実が生まれている。独居高齢者の増加によって「見守り」や「相談」の担い手が不足し、家族や近隣とのつながりが薄れる中で小さな不調が放置され、重症化してから医療に頼らざるを得ないケースも多い。
こうした状況を受けて、国は医療・介護・生活支援を一体で支える「地域包括ケアシステム」の整備を進めてきたが、専門職が対応できる範囲には限界があり、制度の外に取りこぼされる人が増えている。病院中心の臨床看護が“病気になってから治療と共に支える”役割であるのに対し、地域看護には“病気になる前から暮らしを支える”という未整備の領域が残されていた。そうしたすき間を埋める新しい実践の必要性が、各地で高まっていた。
そのような背景のもとで、「暮らしのそばにいる人が、ちょっと気付いて声をかけ合う」という小さな関係を社会の力に変えようと生まれたのが「コミュニティナース」だ。医療機関の枠を越えて地域社会に関わり、住民一人ひとりの健康と幸福を支える新しい形の存在として、日常の中から支え合いの文化を再構築してきた。専門職に限らず、誰もがその役割を担えるようにすることで、地域全体が緩やかに支え合う仕組みを生み出している。
発祥の地・島根県雲南市では、郵便局の一角を拠点に人々が集まり、世代を超えて交流するさまざまな活動が行われている。そこでは健康相談にとどまらず、声がけをきっかけに住民が手芸のワークショップを開くなど、住民の声・つぶやきから生まれた活動によって自然な支え合いや得意を活かす活動が生まれている。こうした営みは、医療や福祉の制度とは異なる形で、地域の信頼関係を支える土台となっている。行政や専門職が提供するサービスでは届かない、日常の安心感や人のつながりを補完している点に、この仕組みの本質がある。
実践の形は地域によって異なるが、共通しているのは“おせっかい”を通じて住民同士の支え合いを引き出す工夫だ。移動販売車に同行して買い物客に声をかけたり、喫茶店やガソリンスタンドで相談に乗ったりと、暮らしの身近な場所に溶け込むように信頼を築く。こうした小さなやり取りの積み重ねが、地域全体に「困っている人を見たときは声をかけていい」という雰囲気を広げていく。コミュニティナースは地域全員のことを知るという目標を掲げ、5人程度のチームで数千人とつながることを想定している。こうした営みが、各地で孤立予防や健康維持に効果をもたらしている。
この活動を支える仕組みは、学びを通じて実践者を育てる講座、自治体や地域団体との協働、そして地域の中に小さな経済を循環させる工夫など、多様な要素から成り立っている。医療や福祉の制度に依存せず、地域の人々が自分たちの暮らしを支える力を取り戻す。その流れが全国に広がり、孤立や健康格差といった課題に対して、持続的かつ自律的な解を提示している。
【 課題 】
自治体との連携を超える長期的価値の創出を模索していた
コミュニティナースの活動は当初、自治体からの委託を中心に展開していた。しかし、行政を中心にすると「行政がやるもの」として、活動が閉じてしまう可能性があった。民間も巻き込みながらみんなで取り組む活動であるというような形に、さらに広げていきたいと考えていた。
【 対応 】
公益経営企業との連携や社名変更で信頼を構築
医療・福祉の枠を越え、長期で地域の未来に関わる企業との連携を強化。民間の経営視点を取り込み、行政依存に偏らない地域投資を目指した。2023年にはミッションに「“生きる”を、進化させる。」を掲げ、社名を「株式会社CNC」に改めてビジネス人材の採用を進めた。そうして広がるパートナーと成果を共有するため、地域の住民との出会いの数や、住民から引き出したニーズの実現件数などを定量的な目標として可視化し、信頼を構築しやすい状況をつくっていった。
【 結果 】
関係づくりの価値が言語化、共創の基盤が広がる
公益経営企業との連携が広がり、企業は単なるCSRやSDGsの一環ではなく、地域の共助の取り組みを自らの使命と連動して関わる取り組みが増えてきた。リブランディング後、プロジェクトマネージャー職の採用が進み、実装スピードとクオリティが向上。全国47都道府県に1500人以上のコミュニティナースが生まれ、地域の「おせっかい」が社会的にも経済的にも持続的な循環となり、全国に広まっている。
AFTER: 2025年時点
URASHIMA VILLAGE
BEFORE: 2021年時点
地域の企業が自ら出資して運営までを担う宿泊モデル
香川県三豊市は父母ヶ浜がSNSで話題となり、年間50万人以上が訪れる観光地となった。しかし、当時の市内には宿泊施設が少なく、多くの観光客が日帰りで帰る状況が続いていた。宿泊施設の必要性は地域で共有されていたが、大規模ホテルを外部資本で建設することには抵抗があった。地域外の資本が入れば利益や意思決定が外へ流出し、地元の主体性が損なわれかねないと懸念されたのだ。そこで、地域の未来を自らの手でつくるべく、地元事業者が中心となり、共同で出資して宿泊施設を立ち上げる構想が生まれた。
こうして2021年、地元企業を中心とした11社が出資し、瀬戸内ビレッジ株式会社を設立。2000坪の土地に、一棟貸し宿泊施設「URASHIMA VILLAGE」が開業した。建物は県産材や伝統技法“焼杉”を活用し、地元の工務店・建設会社が施工、家具も地元の大工が手づくりした。外にはサウナやビーチを備え、食事には地元スーパーが提供する海の幸を用い、送迎や体験ツアーは地元交通事業者が担う。リネンクリーニングすら木材加工会社が新規事業として引き受け、清掃以外のほぼすべての業務を地元企業が担当する仕組みを築いた。これにより、宿の売上は地域内で循環し、雇用や新事業の創出にもつながった。
このモデルの特徴は、資本・運営・意思決定のすべてを地域の主体が担っている点にある。一般的な宿泊事業では、資本提供者、運営者、地元住民が分離され、外部資本と外部運営会社による分業が主流だ。それに対しURASHIMA VILLAGEは、地域の人々が「オーナー」であり「経営者」であり「実行者」でもある三位一体の構造を実現した。宿は単なる観光インフラではなく、地域の経済・文化・誇りを体現する拠点となり、住民にとっても“自分たちの宿”という帰属意識を醸成している。
開業はコロナ禍と重なるも、一棟貸しという形態が家族やグループ旅行の需要と合致し、高い稼働率を維持。2023年夏には稼働率7割を超え、4年目からは出資者への配当も開始された。この成功を受け、三豊市では観光以外にも、交通、教育、不動産などの分野で地元企業による共同出資の動きが広がった。たとえば2022年には、地元タクシー会社3社を中心とする関連企業13社が出資し、地域交通を担う「暮らしの交通株式会社」が設立されている。
URASHIMA VILLAGEは、よそ者に頼らず地域が自ら資本を出して運営を担い、利益を循環させる宿泊モデルを確立した。その影響は三豊地域にとどまらず、全国の地域活性化において地域主体で宿をはじめるという選択肢を具体化した先駆的事例となっている。
【 課題 】
資産が重く、次の一手が打ちづらい構造に
施設を自社で所有していたことで資金が建物に固定化し、新規の設備投資や改修、次の事業への挑戦に使える余力が限られていた。運営自体は好調であっても、新たな資金調達の選択肢が狭まり、財務的に柔軟な動きが取りにくい状態となっていた。また、所有を維持する前提では、外部資金を地域に呼び込む仕組みもつくりにくいという構造的な課題があった。
【 対応 】
運営主体は維持したまま、所有権をファンドに移す
こうした課題を乗り越えるために、施設の所有権を地域のローカルファンド(三豊地域活性化ファンド)に売却し、運営権のみを持つ方式へ移行した。URASHIMA VILLAGEの運営は引き続き地域企業が担い、資産を軽くすることで資金の柔軟性を確保。地域が主体となって資本を公開し、宿泊者や地域外の応援者が株主として参画できる、いわば「ローカルIPO(株式公開)」とも呼べる仕組みを導入して、外部資金が地域に流入する新たな構造まで生み出した。
【 結果 】
地域主導による観光事業として次なる挑戦へ
施設の所有を手放すことで財務の自由度が高まり、新たな設備投資や事業開発への再投資が可能になった。運営の主導権は引き続き地域企業が担い、収益は地元に循環。地域外の共感者も資本参加を通じて関われるようになり、資本と関係が結びつく、開かれた観光モデルに進化している。
AFTER: 2025年時点
BIOTA
BEFORE: 2022年時点
微生物多様性の研究を社会に示す試み
現代の都市では、衛生管理の徹底や除菌の習慣が広がる一方で、環境中の微生物の多様性が著しく低下している。無害な微生物まで減少することで、病原菌など特定の微生物のみが繁殖しやすくなり、感染症の拡大や薬剤耐性菌が生まれる要因となっている。また、空調設備の普及や密閉構造の建物が増え、土壌や植物などからさまざまな微生物が室内に取り込まれにくく、自然由来の微生物と触れる機会が減少した。人が多様な微生物に接する機会が減ることで、免疫機能の発達や健康維持にも影響がおよぶと考えられている。
「BIOTA」はこの課題を「環境中の微生物多様性の欠如」ととらえ、都市や生活空間の生態的バランスを取り戻すことを目的に活動をはじめた。除菌で微生物を排除するのではなく、有用な微生物を意図的に導入して多様性を高めるという「加菌™」の考え方を提唱し、複数の微生物が共存することで病原菌の増殖を抑え、安定した生態系を維持するという研究成果を社会に発信している。この発想は、環境中の微生物の多様性が高いと拮きっ抗こう作用が生じ、特定の微生物だけが増殖することを防ぐ傾向にあるという医学・学術的知見に基づいている。
BIOTAの活動基盤は、マイクロバイオーム解析技術と独自のデータベースにある。空間中の目には見えない微生物をDNAレベルで網羅的に解析し、その種類や機能を明らかにすることで、「微生物多様性スコア」や「健康度」を定量的に把握する。蓄積した膨大なデータをもとに空間の状態を評価・比較し、研究機関と共同で都市や建築物のマイクロバイオーム解析を進めた。創業初期は大学や研究機関を中心に、共同研究や受託調査を通じて科学的データを社会実装へと結びつけ、微生物多様性という新たな研究領域を都市の文脈に接続していた。こうした研究活動は、科学の知を、閉じた専門領域にとどめず、社会の中で共有しながら価値を再構築する試みでもあった。
その延長として、文化・教育機関との連携が進み、研究成果を社会に伝えるための展示や教育活動がはじまった。科学館や美術館での展示監修や教育プログラムを通じて微生物の存在を視覚的・体験的に伝え、人々が自然と関わる感覚を取り戻す場をつくった。2022年には、日本科学未来館で都市生活における微生物との共生をテーマに展示監修を担当し、居住空間を再現した体験展示や微生物の営みを可視化するアート作品を通じて、研究成果を文化的・教育的な形で社会に提示した。展示では来場者の反応から、微生物を「見えない他者」としてとらえ直す視点が生まれ、研究者と生活者のあいだに新たな対話が生まれた。
この時期のBIOTAは、研究と文化醸成の2軸を行き来しつつ、微生物多様性の価値を科学と社会のあいだで翻訳する役割を果たしていた。研究成果を体験に変換する営みが、のちに空間そのものを設計し、環境と人の関係を再構築する活動へと発展する礎いしずえとなった。
【 課題 】
社会実装に結びつくための仕組みが欠けていた
BIOTAは創業初期、研究開発事業と文化醸成事業の2軸を通じて都市空間の微生物多様性を可視化し、社会に伝えてきた。研究では解析技術や評価指標が整備され、文化活動では展示や教育を通じて共感を広めていたが、これらはまだ実際の空間の変化へと直結していなかった。研究成果を生活や都市の設計にどう反映させるかという課題が残され、科学的知見を社会の構造に定着させる仕組みが求められていた。
【 対応 】
研究と文化の知見をもとに空間検証の求めに応えた
こうした状況の中、企業や建築関係者などから「研究で示された考え方を実際の空間で検証してほしい」との相談が寄せられた。BIOTAはこれを契機に「空間創造事業」を立ち上げた。微生物多様性を高めるための緑地・建築設計、素材開発の手法を体系化し、調査から設計・施工・維持管理までを一貫して行う体制を整備。大手デベロッパーや建設会社との取引も増え、将来的には公共交通機関などのインフラにも関わることで、長い時間軸で進める事業へと進化を遂げつつある。
【 結果 】
研究・文化・空間の3事業が循環
空間創造事業の始動で、研究・文化・空間の3事業が有機的に連動し、企業や行政との連携も進展。その延長として、2024年にはソウワ・ディライト社と世界初の「自然資本業務提携」を締結、企業と共に自然資本を増やす関係性を構築しようとしている。TNFDなど環境関連の規制強化も追い風となり、微生物多様性の評価が今後のスタンダードになり得る未来がすぐそこまで来ている。
AFTER: 2025年時点
「みつける」チェックリスト
※noteを読んでいる方へ
ここまでで第1章が終わりです。これで全体の約24%の進捗です。ここまで読んでおもしろいって思ったら(もしくはスクロールして読むのつかれた・・と思ったら)、以下のリンクからお買い求めいただけます。第2章以降もおもしろいので、もう少し内容を見たい方はそのままお進みください。
第2章 「ひろがる」 新たな市場・地域への進出
本質的な価値を保ちながら、異なる市場や地域、業界へと拡張する動き。単なる規模拡大ではなく、「環境の違いに合わせて関係や仕組みを再構成し、新しい接点をつくり出している」事例を扱う。
タイミー
BEFORE: 2020年時点
「働きたい」と「働いてほしい」を1時間単位で結ぶ新しい雇用の形
日本では慢性的な人手不足が続き、特に飲食業では急な欠勤や繁忙期の波に人員計画が追いつかず、求人広告や派遣に依存する固定的な採用が常態化していた。履歴書や面接、シフト調整といった事前手続きは重く、学生や主婦、高齢者など短時間だけ働きたい人々とのマッチングは進まなかった。求職者側の「今日すぐ働きたい」「すぐお金が欲しい」というニーズにも、従来型のサービスでは応えにくかった。
この非効率に対して「タイミー(Timee)」は、「働きたい時間」と「人手が欲しい時間」をその場で結びつける即時マッチングを設計。アプリから最短1時間単位で仕事を選び、履歴書や面接を省いて現場に入れる体験を提供した。創業の動機は、当事者としての切実な不便さに根差すもので、現場が求める即戦力の確保と、求職者の可処分時間の活用を同時に解くことを目指したのである。
制度面では、創業当初から厚生労働省と対話を重ね、この働き方を雇用型のギグワークである「スポットワーク」として位置付けた。最低賃金や労災保険などの適用関係を明確にし、経済産業省のグレーゾーン解消制度を活用して給与の代行払いスキームの適法性を確認。制度の枠外に出るのではなく、制度の内側に新しい就労単位を定義する構造を確立したのである。
データ面では、勤務開始終了時刻、職種、頻度、評価といった実績情報を継続的に蓄積し、履歴書では測りにくい「働きぶりの信頼度」を可視化した。これにより、企業は短時間でも安心して任せられる人材を識別でき、個人は実績によって働く機会へのアクセスを広げられる。こうして、データを媒介に信頼が循環する仕組みが確立し、労働市場に新しい評価軸を生み出した。
資金の流れについては、働いた日の報酬を即日で受け取れるようにタイミーが立替を行い、企業からの回収は後日にずれ込む構造を採用した。創業期は資金繰りの難度が高く、信用や与信管理の仕組みを磨きながら運営を安定させる必要があったが、すぐに報酬が受け取れるという即時性の価値を損なわないことを優先した。これは、働き手の体験品質を担保するために、金融面のリスクを正面から引き受ける設計である。その分、多額の資金調達を行い、安定的なキャッシュフローをつくり出している。
創業から間もない時期にもかかわらず、タイミーは企業側の人手確保と働き手側の即時就労を両立させる仕組みとして急速に浸透した。雇用契約・報酬決済・評価データの三層構造を備え、労働市場に新たな接続点を生み出したことで、短時間就労を社会的に成立させる基盤を築いたのである。
【 課題 】
飲食業への依存と、 社会に広がる人手不足への対応の遅れ
創業当初、求人の約7〜~8割が飲食業に集中していた。飲食店の急な欠員対応という明確なニーズに支えられ急成長したが、コロナ禍による外食規制や来店減少を機に、単一業界への依存リスクが顕在化。同時に、物流・介護・ホテルなど社会を支える他分野でも人手不足が深刻化し、雇用のあり方そのものに柔軟性が求められるようになっていた。タイミーはこうした構造的課題に対し、特定業界の効率化から社会全体の人手不足解消へと視座を拡張する必要性に直面した。
【 対応 】
マッチング構造を維持しつつ、業界 ・ 地域の両面に拡張
求職者と企業を即時に結ぶ基本構造を変えず、飲食中心の利用から、物流・ホテル・介護などさまざまな業界へと展開した。各業界の特性に合わせて専任営業チームを配置し、需要の高い分野で短期就労者を即時確保できる体制を構築。さらに、2023年以降は全国の自治体と連携協定を結び、地域の課題(震災復興・ひとり親支援など)とスポットワークを結びつける仕組みを整えた。これにより、タイミーの存在が社会的基盤としてより広く機能するようになった。
【 結果 】
「 業界を超えて機能する雇用インフラ」 に進化
タイミーは短時間就労を起点に社会全体の人手不足を支える労働インフラへと進化。企業側は業界や契約形態を問わず必要時に人材を確保でき、働き手は年齢や属性に縛られずに働く機会を得た。この「1時間単位での雇用接続」が制度的にも定着し、短時間就労を社会が受け入れる新たな雇用モデルを確立。さらに、M&Aや新規事業などで、求人にとどまらず長期雇用や教育支援など働く機会を広げる領域にも展開を続けている。
AFTER: 2025年時点
ヘラルボニー
BEFORE: 2020年時点
一人ひとりの異彩が社会を彩る、新しい循環の仕掛け
日本各地の福祉現場では、ものづくりに携わる障害のある人たちが、絵画や雑貨、日用品などを制作・販売してきた。しかし、その多くは 「訓練の一環」として位置付けられ、販売価格は極めて低く抑えられていた。障害のある人が生み出す表現が、福祉の枠を出ないまま扱われ、社会的にも経済的にも評価されにくい構造が続いていたのである。個性や創造性が確かに存在していても、それが生活を支える収益に変わり得ないというギャップが長く放置されていた。
この閉塞を打ち破るように登場したのが、2018年に岩手で創業した「ヘラルボニー(HERALBONY)」である。創業者で双子の松田崇弥氏文登と氏の兄弟は、重度の知的障害を伴う自閉症の兄・翔太氏が幼い頃に自由帳へ書いた言葉「ヘラルボニー」を社名に掲げ、「異彩を、放て。」というミッションを定めた。2人は障害を「支援の対象」ではなく、障害があるからこそ描ける才能=異彩として捉え直し、アートを通じて世の中の障害へのイメージ変容を目指した。
ヘラルボニーの仕組みの中心にあるのは、障害のある人が描くアートを知的財産として社会に流通させる発想である。福祉施設に在籍する作家とライセンス契約を結び、作品を高解像度でスキャンしてデータとして保管する。デジタル化された作品は、ヘラルボニーがライセンスを管理し、自社ブランドの商品や企業とのコラボレーションに起用される。作品が使用された際には、ライセンス利用料として作家や福祉施設へ報酬が支払われる。
アートデータは企業との共創プロジェクトに起用される。具体例としては、ネクタイやハンカチなどのアパレル、パッケージやノベルティ、オフィス内装・壁面グラフィック、駅や施設の掲出、広告ビジュアルなど。企業はデザイン素材としてではなく、契約に基づくライセンスとして活用し、販売や掲出の規模に応じた使用料が発生する。作家側には実使用に応じたロイヤリティが入り、作品が使われるほど収益が積み上がる構造になる。
このモデルの要は関係性の置き換えである。従来の「福祉がつくったものを善意で買う」という関係から、企業は自社の事業価値向上のためにライセンスを取得し、作家は表現で対価を得る職能として参加する。
アートを福祉の枠から解き放ち、文化と経済を往還する仕組みに再定義する。ヘラルボニーが実現したのは、障害のある人の表現を「支援」する対象とするのではなく「異彩」として見る、新しい価値の転換だった。
【 課題 】
海外市場への進出における新たな壁
障害のある作家と対等なビジネスパートナーとしてライセンス契約を結び、BtoBライセンスと自社ブランドの両輪で事業展開するモデルが国内で定着しはじめた。一方、国内市場では「共感の高い層」には強く届くものの、海外に向け大きく広げていくには海外市場での接点獲得と認知の拡張が必要との新たな課題が生まれた。
【 対応 】
ブランドロゴの刷新や国際的アワード創設
2024年のLVMHアワード受賞を機にパリに子会社を設立し、海外進出。海外展開を見据えブランドロゴも英字にリニューアルするなど、グローバル市場におけるブランド基盤の整備も進めた。さらに、世界中の作家や施設から作品が寄せられる「HERALBONY Art Prize」を創設し、作家・企業・生活者が持続的に関わる循環を生み出している。
【 結果 】
グローバルに広がる異彩のブランド化
ヘラルボニーは社会的意義と経済的基盤を両立するライフスタイルブランド・アートエージェンシーへ。契約作家数は増加し、アート使用料の分配も拡大。企業コラボレーションは国内外へと広がり、2025年にはカンヌライオンズでグラス部門ゴールド賞を受賞するなどグローバルに広がるブランドとして拡張を続けている。
AFTER: 2025年時点
おてつたび
BEFORE: 2018年時点
どんな地域にも働き手がすぐに集まる仕組み
日本の地方には、著名な観光名所がなく全国的な知名度は低いものの、自然や文化、産業など固有の魅力を備えた地域が数多く存在する。しかし、そうした地域に人が訪れる機会は限られ、交流人口の拡大や地域の認知度向上につながりにくいという課題がある。人口減少や都市部への一極集中が進む中で、地域が持つ魅力を発信し、人を呼び込む仕組みをどう構築するかは長年の社会課題となっていた。
同時に、農業や宿泊業をはじめとする地域の事業者は、後継者・人手不足に悩まされている。特に収穫期や観光シーズンなど特定の時期、人手不足は深刻だ。繁忙期に合わせて人材を確保することは難しく、正規雇用で常に人を雇い続けるのも現実的でない。短期的かつ柔軟に労働力を確保できる仕組みが求められてきたが、従来のアルバイト募集や派遣では必ずしも地域事業者のニーズには十分に対応できていなかった。
2018年創業の「おてつたび」は、こうした地域と事業者双方の課題を背景に、「お手伝い」と「旅」を組み合わせた新しい形のマッチングプラットフォームである。地域の短期的・季節的な人手不足に悩む事業者と、報酬を得ながら旅を楽しみたい旅行者を結びつける仕組みを提供している。最短1泊2日から2か月まで幅広い募集期間に対応できるため、事業者にとっては観光シーズンに宿泊施設のスタッフが不足する場合や、農家が収穫期に人手を求める場合など、特定のタイミングで労働力を補える点は大きな強みだ。また、旅行者にとっても旅行日程に応じて選択ができるため大きな魅力となっている。
ただし、創業当初は事業の立ち上げに大きな困難が伴った。「そんなサービスで人が来る?」「お手伝い感覚で仕事をされても困る」といった懐疑的な声もあり、受け入れ先の事業者を一つずつ地道に説得してまわる日々が続いた。当初は旅館など5件の事業者からはじまり、代表自ら現地に足を運んで制度を説明し、少しずつ信頼を築いていった。
おてつたびの魅力は「旅をしながら報酬を得る」という新しい旅行スタイルを実現している点。通常、旅行には交通費や宿泊費などがかかるが、おてつたびでは交通費こそ原則自己負担だが宿泊費は不要で、費用を抑えつつ旅が続けられる。また、単なる観光ではなく、地域の人々と共に働き交流することで、その土地の文化や生活を深く理解できる。通常の観光旅行では得られない「地域とのつながり」を築いたり、訪れた地域に特別な思い入れを抱くことで、将来的に長期的な関係人口へと発展する可能性を持っているのだ。
このように、報酬を得ながら特別な体験を得るという旅行者の価値と、必要な時期に労働力を確保できる事業者にとっての価値のかけ算によって、地域活性化や継続的な関係人口の創出につながる仕組みとして、おてつたびは注目されている。
【 課題 】
移動 ・ 宿泊 ・ IT活用の壁が参加と受け入れを難しく
おてつたびを使って地域で働く人が増えてきたが、地方では移動手段が限られ、交通費の負担の大きさや、宿泊場所の確保も難しいなど物理的なハードルが多かった。また、受け入れ側の農家や宿泊業者の中にはITツールの使い方に不安を感じている人も多く、新しいサービスを活用しにくい状況があった。これらが結果的に、地域全体の受け入れ体制を狭めていた。
【 対応 】
自治体や民間企業と連携し、参加と受け入れを支える
移動や宿泊、ITの活用に関する地域側の課題に対し、おてつたびは自治体や企業と連携しながら一つひとつ壁を越えてきた。交通費や手数料の一部を補助する自治体も現れ、高齢の事業者に対しては導入支援を行うなど、地域がサービスを使いやすくする体制が整えられた。民間企業とも連携し、移動手段や体験機会の提供も進められることで、参加者と受け入れ先の接点が生まれやすくなっていったのである。
【 結果 】
一度きりでは終わらずに、地域との関係が育った
おてつたびで地域と関わった人の約6割が、その後も何らかの形で関係を続けている。訪れた土地を再び訪問したり、特産品を継続的に購入したり、中には移住する人も出てきている。旅や仕事をきっかけにしたつながりが、地域の応援者を増やす形で広がっており、短期の人手支援にとどまらず、地域と人の新しい関係性を育てる仕組みとして定着しはじめている。
AFTER:2025年時点
wash+
BEFORE:2022年時点
「洗剤のいらない洗濯」を実現!
洗濯は日常的行為でありながら、肌への刺激や洗剤残留による不安、そして水質汚染や時間的負担といった課題が潜む。特に肌が敏感な人たちにとっては、洗剤の成分が不明なコインランドリーの利用は不安を伴い、環境面でも排水による負荷が懸念されていた。こうした課題は、生活の質や持続可能性に直結するにもかかわらず長らく見過ごされてきた。
株式会社wash-plusは、この状況を変えようと2013年に設立。代表の高梨健太郎氏は、肌の弱い娘のために安心して使える洗濯環境がないという現実に直面し、洗剤を使わず水だけで洗う技術の開発に着手した。コインランドリー機器メーカーの山本製作所と共同で、洗濯専用アルカリイオン電解水「wash+ Water」と、その洗浄力を最大限に引き出す専用制御基盤や排水設計を組み合わせ、合成洗剤なしで汚れを落とす技術を確立。これにより、肌への刺激を抑えつつ、排水の環境負荷も軽減することが可能になった。
さらにwash-plusは、洗濯体験そのものを再設計した。IoTを活用した「スマートランドリー」では、スマホアプリから空き状況を確認して事前に予約し、キャッシュレスで決済して、終了時には通知を受け取ることができる。従来は店舗に足を運ばなければわからなかった機器の稼働状況や、終了までの待機時間といった不便が解消され、利用者にとって格段に使いやすい体験が提供されるようになった。また、多言語表示やQRコード操作などの設計も取り入れ、旅行者や留学生などさまざまな利用者に対応している。
IoTの導入は運営者側にも大きなメリットをもたらした。稼働率や売上がリアルタイムに可視化され、遠隔から複数店舗を管理できるようになった。従来のように人員を割いて現場で点検する必要性が減り、清掃や補充もデータに基づいて効率的に計画できる。夜間や無人時間帯でも安定的に稼働できるため、オーナーにとっては人件費を抑えつつ収益性を確保できる仕組みとなった。さらに、機器メーカーと共同開発した制御基盤は後から更新可能で、導入後に機能を追加・改善できる。これにより設備の寿命を延ばし、投資リスクを軽減する仕組みを整えている。
このように「wash+」は、「洗剤レス」と「IoT」という2つの要素を重ねることで、単なる便利さや環境配慮を超えた価値を生み出している。利用者には肌と生活に安心を、オーナーには効率的な経営を、社会には環境負荷の低減を提供する新しいランドリーモデルだ。日常の洗濯という身近な行為を入口に、健康・時間・環境の3つの課題に同時に応える構造を提示したことこそが、この事業の革新性なのである。
【 課題 】
ブランド力と市場展開の広がりに欠けていた
洗剤を使わない独自技術は注目を集めたが、コインランドリー市場では便利さや価格や立地、営業時間といった条件で選ばれる傾向が強く、環境配慮だけでは利用拡大に限界も。事業を広げるには最終的に最大の市場である家庭用を視野に入れることが不可欠で、そのためには認知度の向上とブランドの信頼を高めることが大きな課題だった。また、社員増加に伴う組織運営や人材マネジメントの整備も課題として浮かび上がっていた。
【 対応 】
星野リゾートとの共創が切り拓いた突破口
wash-plusは宿泊客の快適さや環境配慮が重視されるホテル市場に着目し、2022年に星野リゾートと連携。西表島ホテルでは自然環境そのものが観光資源で、排水による負荷を減らしたいというニーズが導入の背景にあった。これに応える形で、無香料かつ洗剤レスの「wash+Comfort」を開発し、IoTによる多言語対応・決済やデザイン性も備えた宿泊体験の一部として提供した。社員が働きやすい環境を整備するため、組織基盤の強化にも取り組んだ。
【 結果 】
ホテル導入を足がかりに信頼の拡大へ
知名度の高いホテルへの導入は洗剤レスのランドリーの信頼性を裏付ける事例となり、ブランド認知や事業性を大きく押し上げた。その後、ほかの宿泊施設や自治体との協働にも広がり、災害時に給水・排水を抑えた洗濯環境を提供する実証実験にもつながっている。こうして健康と環境を守るだけでなく、防災や公共性の領域へと展開しつつ、年間休日130日や有給休暇取得率88%を達成、組織としても持続的な成長を遂げている。
AFTER: 2025年時点
イークラウド
BEFORE: 2020年時点
成長資金が届きにくい創業期の企業に新しい資金の流れをつくる
日本には約2200兆円もの個人資産が存在するといわれる。しかし、その多くは銀行預金や現金として眠ったままで、成長を志す企業や社会課題の解決を目指す挑戦には十分に循環していない。一方で、創業間もないスタートアップ企業は、事業の成長初期に必要な資金を集めることが非常に難しい。銀行融資は返済実績や担保を求められることが多く、大口投資家からの出資も一定の信頼や実績が前提となる。そのため、将来性のある企業であっても資金調達の第一歩でつまずき、事業化のチャンスを逃してしまう例は少なくない。
この資金の滞りと成長の断絶をつなぐ仕組みとして、イークラウド株式会社は株式投資型クラウドファンディングのプラットフォーム「イークラウド」を運営している。2018年に創業、2020年にサービスを開始して以来、個人が企業に少額から投資可能となり、未来の挑戦を経済的にも社会的にも支援できる新しい資金の流れを広げてきた。
「株式投資型クラウドファンディング」とは、スタートアップ企業が非上場株式を発行し、インターネットを通じて個人投資家から少額の出資を募る仕組みだ。企業は年間1億円未満の範囲で調達可能で、個人投資家は1社あたり年間50万円以下の範囲で投資できる。これにより、投資家は比較的少額で複数の企業に分散投資でき、企業は社会からの共感を得られた場合にのみ資金を獲得できる構造ができる。
案件はすべて、イークラウドによる厳格な審査を通過した企業に限られる。専門家が事業内容や経営体制、将来性を確認し、複数回の面談や現地訪問を経て判断。募集期間終了時に目標額に達した場合のみ出資が成立する。IPOやM&Aによって株式を売却できれば、投資額の数倍から数百倍におよぶリターンを得られる可能性もある。一方で、目標額に届かなかった場合は不成立となり、出資金は全額返金される。
出資後も企業は活動状況を定期的に開示し、投資家は応援する企業の成長を継続して見守ることが可能。経済的利益だけでなく、社会の変化に参加している実感が得られる点が、多くの利用者に支持される理由だ。
イークラウドは、国内の同種サービス5社の中では後発ながら高い案件成立率を誇る。2023年7月には、多拠点居住サービスを展開するADDress(86ページ参照)の案件で9990万円の申込額を達成、国内株式投資型クラウドファンディングの最高額を更新した。こうした成果を支える理念が「持続的三方よし」で、スタートアップ、投資家、イークラウドの三者すべてに中長期的な利益をもたらす関係を目指している。
同社は「挑戦者と応援者をつなぐインフラ」を掲げ、日本に眠る個人資産を社会の新しい挑戦へと循環させる役割を担う。仮にその1%がこの仕組みにまわるだけでも、22兆円の巨大な資金が動き出す。これは、現在の未上場企業向け投資市場の約20倍に相当し、日本の産業と社会に大きな循環をもたらす可能性を秘めている。イークラウドは、すべての人が理想の未来を描き、挑戦できる社会の実現を目指している。
【 課題 】
創業間もない会社に限定されてしまう
これまでイークラウド上では、企業が1年間に集められる資金は基本的に1億円未満まで、個人の投資額も50万円が上限だった。そのため、投資対象が創業間もない段階の企業に限定されること、資金調達額が小規模であること、個人投資家が増加することが課題だった。
【 対応 】
新たに第二種金融商品取引業・投資運用業に登録
そこでイークラウドは、新たに第二種金融商品取引業・投資運用業へ登録し、「イークラウドNEXT」をサービス開始。これまでの上限を超えて資金調達ができるようになった。また、会社ごとにファンドをつくり、ファンドを介して出資することで、個人投資家をファンドにまとめる仕組みも導入した。
【 結果 】
さらなる成長を目指す企業まで資金調達できる仕組みへ
より大きな金額が取り扱えるようになったことで、創業間もない会社(シード・アーリー)だけでなく、事業が拡大し、さらなる成長を目指す成長段階の会社(ミドル・レイター)へと顧客の幅が大きく広がった。これによって資金の流れは大きく広がり、応援する人と企業の挑戦を結ぶ新しい循環が生まれていくはずだ。
AFTER: 2025年時点
ADDress
BEFORE: 2018年時点
使われない空き家を滞在拠点に変え、収益と地域の交流を生み出す
2018年当時、日本では人口減少と高齢化が進み、全国で別荘などを除く約348万戸の空き家が社会問題化していた。空き家は老朽化や災害リスクを抱え、地域の衰退につながる懸念が強まっていた。一方、若年層を中心に「地方と関わりたい」との声が高まり、観光などの一過性の関係を超えて地域課題の解決に関与する「関係人口」や、2拠点・多拠点居住への関心が高まっていた。
また、同年「働き方改革関連法」が成立し、長時間労働の是正や柔軟な働き方の推進が制度的に進められ、ライフスタイルの多様化を後押しした。さらに都市部では、人間関係の希薄化に伴い孤独や孤立が課題として注目され、コミュニティを重視した暮らし方への関心が高まっていた。
こうした社会的背景のもとで登場したのが、2018年設立の株式会社アドレスが、2019年にサービスを開始したサブスクリプション型多拠点生活サービス「ADDress」である。利用者となる会員は、月額料金を支払うことで全国の古民家やシェアハウス、リノベーション済みの住宅を拠点として利用できる仕組みだ。創業時は、月額4万4000円で全国の拠点に住み放題の定額制プランが提供されており、利用者は自由に移動しながら暮らす新しいライフスタイルを実現できる。
このADDressの特徴は、宿泊施設を提供するだけでなく、利用者同士や地域との交流を促進する仕組みにある。各拠点にはWi-Fiやデスクが整備され、リモートワークやワーケーションに適した環境が整うと共に、共同スペースで自然な交流が生まれる。また、各拠点には「家や守もり」と呼ばれる管理者が配置され、単なる管理にとどまらず、地域と利用者をつなぐ役割を果たしている。家守には、物件所有者自身が務める「オーナー家守」、物件に住み込みながら管理を担う「住込み家守」、近隣に住みながら関与する「通いの家守」があり、それぞれが地域情報の提供やイベントの企画を行い、地域に根差した体験を利用者に提供する。
収益の流れは、会員が支払う月額料金から、オーナーへの賃料と家守への委託料を差し引き、残りがADDressの収益となる仕組みだ。リノベーションにかかる初期費用は物件オーナーが負担するものの、1部屋あたりの投資額は比較的少額で済むため短期間で回収できる。さらに、リノベーションはプロのクリエイターが建物の歴史や地域の文化に配慮しながら計画を立てて進めるため、オーナーは安心して参画できる仕組みとなっている。
ADDressは、人口減少や空き家の増加など地域の課題に対し、住まいの流動化と関係人口の創出を通じて、新たなライフスタイルの可能性を提示するという理念のもとで誕生した組織だ。単なる宿泊サービスにとどまらず、空き家の再活用や地域コミュニティの再生、利用者の暮らし方の多様化を同時に促進する仕組みとして注目を集めている。
【 課題 】
コロナ禍での利用者減少と地域受容の壁
創業期は自宅を持たず全国を移動する「アドレスホッパー」層が主なターゲット。月額4万4000円の定額制で全国住み放題を提供し、自由な暮らしを支援していたが、コロナ禍で移動が制限されて短期滞在型の多拠点居住が困難となり、利用者数も減少、拠点維持コストが重く経営は破綻寸前に。さらに地域側には「点々とする若者の滞在」への抵抗もあり信頼構築が進まず、事業の持続性に大きな課題を抱えていた。
【 対応 】
柔軟な料金体系により地域に根付く事業へ
2023年、料金体系をチケット制(月額9800円~)へと改定し、利用頻度に応じた柔軟な選択肢を提供。ライト層や地域志向の会員を取り込み、繰り返し滞在する関係人口が増えるよう働きかけた。さらに、自治体と地域の課題を解決する取り組みを開始し、空き家調査や泊まれる場所を増やすことを行った。加えて、事業に愛着を持った人が株主として参加できる「コミュニティラウンド」を実施。共感する人々が「応援」から「共につくる仲間」へと移行する仕組みを築いた。
【 結果 】
地域と人がつながる“やさしい世界”へ
料金改定で利用者数は増化、短期から中長期滞在へ移行する利用者も増えて地域住民との接点が深まり、家守制度を通じた地域主体の運営が定着。さらに会員は広報や改善提案、イベント参加などを担い、地域に根付く事業に変化したことから自治体との信頼関係も強化され、地域課題の解決の依頼も増えた。こうした広がりの中、代表が語る「都会で疲れた人が安心でき、多様な人が思いやれる“やさしい世界”」が形になりつつある。
AFTER: 2025年時点
RENATUS ROBOTICS
BEFORE: 2024年時点
バラバラだった作業工程ごとの自動化を1つに集約
コロナ禍以降、EC市場の急成長などにより、物流業界では速くて正確な配送が強く求められたが、従来の倉庫管理は多くの人手が必要で、その労働力不足が深刻な課題だった。こうした状況に対応するため、物流業界ではロボットを導入した自動化が進められているが、複数工程間の連携効率が悪く、工程間をつなぐコンベア設備も必要となって設備費用も莫大だった。
「RENATUS」は、そうした大規模物流倉庫のバラバラな工程を、自社開発の独自のアルゴリズムで動くロボットなど設備一式の自動倉庫システムを提供するサービスだ。そして、このシステムとロボットを開発した「RENATUS ROBOTICS」は、国内最大級スタートアップイベントのピッチイベント「IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO」で優勝するなど、注目を集めている。
日本国内では2022年から、物流倉庫を持つ大企業向けの設備一式を建設・販売する買い切り型で展開していて、導入企業は商品の保管、ピッキング、集約といった、これまでの倉庫内作業の大半を自動化することができる。
従来は多数の倉庫内ロボットを同時に制御しようとすると、ロボット同士の衝突が多発して効率が落ちる問題があったが、RENATUSのロボットは独自のアルゴリズムで互いに衝突を避けるように動くため、最大2000台のロボットを同時制御できるようになって効率性を大きく高めた。さらに、従来の商品保管棚はロボットが地上を走るために高さの制約や工程間をつなぐコンベアが必要だったが、最大20mの高さに対応する保管棚とロボットを垂直移動させる高速リフトを組み合わせることで、倉庫内の空間をムダなく活用できる設計にしている。
たとえばEC業界向け倉庫では、棚に無数に並べられた何万種類もの商品を探すピッキング作業に倉庫内を駆けめぐる何十人もの作業員がいるの があたりまえだったが、RENATUSを導入をすると人手作業が大幅に減り、作業員 は20名から1名に削減が可能になるという。加えて、設備も工程間をつなぐコンベアなどが不要なシンプルな構成となったことで、設備投資の回収に必要な期間は一般的 に10年ほどかかるところ、ケースによっては約2.5年に短縮可能という試算にも驚く。
RENATUSは創業時から2025年までに、倉庫内作業の50%以上の自動化を可能にしたが、物流の「完全無人化」の実現に向けさらなるシステムや設備の開発、パートナー企業との共創を加速させる計画だという。
【 課題 】
米国に進出する際に生まれた壁。顧客層も大手に限られていた
会社設立当初から目指していた米国進出は、米国内の実績がないことや、販売するにあたり実際の設備を見たいという要望に応えられないことが障壁となっていた。また、買い切り型ビジネスモデルは顧客の所有する既存倉庫への導入が前提となり、投資回収の期間が短いとはいえ初期投資が大きくなることもあって、顧客はある程度規模の大きな企業に限られていた。
【 対応 】
自社倉庫を米国内に設立し、保管発送代行を開始
こうした課題を解決すべく、米国にRENATUSの自動化技術をフル導入した自社倉庫の設立を2025年5月に決定。この倉庫は米国内でRENATUSを買い切り型で導入を検討している企業向けのショールームとしての役割だけでなく、商品の保管から発送までを請け負う代行サービスの拠点としての役割もある。利用料金は配送数量に応じ従量課金にすることで、倉庫を持たない小規模なEC企業も利用可能になるという。
【 結果 】
将来の物流の完全無人化に向けた実証実験も加速
これにより、物流倉庫がない小規模ユーザーにサービスを提供する形で米国に進出できた。また、米国内で設備を実際に見せることが可能になったことで、日本で主流の買い切り型ビジネスモデルの米国展開も視野に。さらに、最新技術の実証実験を行う自社拠点を持つことでノウハウが蓄積しやすくなり、自社開発の装置や他社とのコラボレーションによる物流の完全無人化に向けた取り組みを加速させる構想だ。
AFTER: 2026年予定
五常・アンド・カンパニー
BEFORE: 2017年時点
“援助”から“事業”へ。金融の流れを変える日本発の挑戦
途上国では多くの人が銀行口座を持てず、必要なときにお金を借りられない状況がある。特に農村に暮らす人や女性は、生活や小さな商売を続けるための資金を手に入れたり貯蓄を行う方法が限られ、安定した暮らしを築くことが難しい。こうした金融サービスから取り残された状態は貧しさの原因の一つとされ、長く社会課題として語られてきた。少額の融資を受けられたことで商売を続けられたり、子どもを学校に通わせられるようになったという例も多く、金融へのアクセスを広げることが、人々の生活や地域経済を支える大きな力になると考えられてきた。
この課題に向き合うために日本で生まれたのが「五常・アンド・カンパニー」である。誰もが自分の未来を決めることができる世界を目指し、途上国の低所得者層に少額の融資や貯蓄の機会を届けるマイクロファイナンス事業を展開している。単にお金を貸すだけでなく、金融サービスを使えなかった人々が、自らの意思で選択し、生活をよりよくできるようにすることを目的としている。
歴史的に金融包摂の取り組みは、寄付や公的資金に頼る形で行われてきたが、事業としての継続性に課題があった。五常・アンド・カンパニーをはじめとするマイクロファイナンス機関はそこに民間の資本を導入し、社会的意義と経済的持続性を両立させる仕組みを設計した。
同社は日本や海外の個人、企業、金融機関などから資金を集め、そのお金をもとに海外の中小規模の金融機関に出資し、その経営を支援する。現地の金融機関は、金融サービスを受けにくい農村部に暮らす人や、小さな商売を営む女性などに少額の融資や貯蓄の機会を提供し、返済に含まれる利息や手数料を次の融資や事業拡大の原資にまわす。この循環が生まれることで、金融が届いていなかった層にも新たな資金の流れが生まれ、地域の低所得者層の所得向上や自立につながる。
このモデルは一見シンプルだが、構造的に見ると複数の革新がある。第一に、与信リスクを(グループ連帯責任や少額融資といった仕組みで)分散しながらも社会的インパクトを拡大できる点。第二に、収益を生む仕組みを社会課題の解決に直結させている点。そして第三に、現地パートナーの自立を前提にしている点だ。五常・アンド・カンパニーは各国の文化や制度の違いを尊重しながら現地経営陣と共に運営方針を決め、トップダウンではなく協働によって事業を広げてきた。
また、設立当初からグローバルな視野を持ち、アジアを中心に複数の国で事業を展開してきたことも特徴的だ。多国籍メンバーによるフラットでオープンな組織文化を重視し、現地の生活や慣習を理解したうえで、国ごとの制度や市場に合わせて柔軟に事業モデルを適応させてきた。これにより、各国で異なる課題や環境の中でも、共通する理念のもとに持続的な金融の仕組みを根付かせている。
五常・アンド・カンパニーは民間資本を活かし、社会課題の解決と事業の持続性を両立する仕組みを構築。金融包摂を軸に誰もが自分の未来を選べる社会の実現を目指し、途上国での地域密着型マイクロファイナンスを水平統合しグローバル展開する新しい金融の形を提示している。
【 課題 】
コロナ禍で進んだインド集中と市場変化への対応力が課題に
コロナ禍で海外への移動が制限され、新しい買収候補の開拓が難しくなったため、すでに実績のあるインドの金融機関への投資にフォーカスすることを決めたが、インドのマイクロファイナンス市場は成長が著しい一方で、規制や金利など外部環境の変化が大きく、事業の比重が高まるにつれそれらの影響を受けやすい構造が課題として浮かび上がっていた。
【 対応 】
複数の国に事業を広げ、どの地域でも続けられる仕組みへ
同社はインドへの依存を抑え、中央アジアなど新たな地域への展開を進めた。複数の国や通貨で事業を展開することで、地域ごとの環境変化に左右されにくい体制を構築しつつある。また、ガバナンス・リスク管理・コンプライアンスの仕組みを整え、各国の経営データを統合。経営の透明性とリスク管理を強化することで、外的ショックにも対応できる経営基盤をつくった。
【 結果 】
地域分散による安定化と顧客基盤の拡大
こうした取り組みにより、五常グループおよび主要投資先の顧客基盤は世界14か国に広まり、顧客数は340万人(2025年3月末時点)を突破。タジキスタンやジョージアなど 新しい地域の成長が全体を下支えし、どこかの国の経済が揺らいでも全体として安定して事業を続けられる仕組みができた。顧客の約7割は農村部に暮らす女性で、金融を通じて生活を支える仕組みが地域ごとに根付いている。国を越えて経験やノウハウを共有する体制も整い、各地で自立的な事業成長が進んでいる。
AFTER: 2025年時点
HADO
BEFORE: 2021年時点
子どもの頃に夢見た“あの技”を実現させるテクノスポーツ
子どもたちの遊び方は、都市化や少子化、学習環境の変化、そしてデジタル機器の普及によって大きく変化した。安全に遊べる屋外空間が減り、集団での外遊びは難しくなって、学習や習い事で自由に体を動かす時間も減少した。家庭ではゲーム機やスマートフォンが普及し、遊びは室内や画面の中へと移った。結果、体力低下や肥満といった健康課題が表面化し、仲間と協力したり創造的に関わったりする機会も乏しくなっている。従来のスポーツもまた、体力や筋力の差が勝敗を左右する構造で、誰もが公平に参加できるとは限らなかった。
そうした状況の中、2014年創業のmeleapは、「自らの手からエネルギーを放つ体験を現実にしたい」というシンプルな発想から、AR技術を活用した新しいスポーツ体験をつくり出した。それがテクノスポーツ 「HADO」である。プレイヤーはヘッドセットとアームセンサーを装着し、仮想のエナジーボールやシールドを駆使して戦う。最大の特徴は、エナジーボールの大きさ・スピード・シールドの耐久力といった能力を数値で調整できる点にあり、体力や筋力に依存しない公平な競技体験を可能にした。従来のスポーツが身体的条件に大きく左右されるのに対し、HADOはテクノロジーを通じて「誰でも参入できる競技」という新しい選択肢を生み出したのである。
2016年にサービスを本格開始して以降、HADOは急速に拡大した。直営店舗やフランチャイズ、販売代理店を通じて各国で導入が進み、日本や中国を含む世界39か国に展開。レジャーコンテンツとして商業施設やテーマパーク、自治体イベントなどに組み込まれ、誰もが一度は体験できる機会を提供した。さらに、企業イベントやチームビルディング研修でも採用され、新鮮なアクティビティとして注目された。2016年からは世界大会「HADO WORLD CUP」も開催、国際的な認知度を高めている。大会は年々規模を拡大し、プレイヤーが戦略を練りながら技を繰り出す姿は、観戦スポーツとしての魅力も備えるようになった。
事業モデルは直営店、フランチャイズ、販売代理店、出張イベントなどの導入形態を組み合わせる仕組みが特徴。直営店は都市部の集客拠点として運営され、フランチャイズは地方や海外での普及を担う。販売代理店は学校や商業施設への導入を支援し、イベント型の提供は自治体や企業との協働を広げる。ライセンス収益を軸にしたこの仕組みで設備投資や運営負担を分散させ、世界規模で拡張することが可能になった。
HADOはこうして、テクノロジーにより身体条件を超えた競技体験を提供すると同時に、柔軟なビジネスモデルで多様なパートナーと連携しつつ広がってきた。世界中で同じルールと体験が共有されることで、国境を越えた競技を生み出しているのだ。
【 課題 】
レジャー利用客のリピート率向上
HADOはレジャー利用や体験イベントのみでは一過性に終わってしまっていて、このレジャー利用客のリピート率を上げることが目下の課題だった。さらに、新しいスポーツを根付かせるにはレジャー利用客の人数を増やすだけでは不十分で、既存のスポーツが教育や地域、産業と結びつくように、たとえばHADOにも学校で指導する先生や部活動、公式大会の仕組み、観客やスポンサーといったさまざまな担い手が必要だった。
【 対応 】
教育現場への本格参入
そこでHADOは、教育現場への導入を本格化した。体育の授業に常設し、部活動として継続的に練習できるようにすることで、子どもたちが繰り返し競技に触れられる環境を整備。指導者向けの研修や教材も用意し、先生が教えられる体制を築いた。同時に、企業や自治体と連携して大会やリーグを広げ、保護者や地域住民が観戦できる場を増やした。スポンサーやメディアも関わることで、プレイする人・教える人・支える人・見る人が循環的につながる仕組みを育てていった。
【 結果 】
HADO活用中の学校数が世界累計2000校突破
その結果、HADOを導入する学校は世界で2000校を超え、授業やクラブ活動で、探究学習やICTなどの教材として継続的にプレイする子どもが増えた。地域大会や国際大会の開催により観戦の機会も広がり、スポンサーや企業が関わる余地も大きくなった。スポーツが得意でない子どもでも能力を調整して参加できる点が評価され、教育、地域、産業を巻き込む新しいスポーツが少しずつ形になりはじめている。
AFTER: 2025年時点
逆プロポ
BEFORE: 2021年時点
企業の募集に自治体が手を挙げる「逆」な仕組み
企業が自治体と社会課題に取り組むとき最初に立ちはだかるのが「プロポーザル」の構造だ。プロポーザルとは、自治体があらかじめ課題や仕様を定め、それに対して企業が提案書を提出する制度のことだ。しかしこの形式では、企業が持つ独自のアイデアや技術、社会への問いかけが活かされにくく、柔軟な発想や新しいアプローチを試そうとしても、形式の制約や評価基準が壁になる。
こうした壁を乗り越えるために生まれたのが「逆プロポ」だ。企業が自ら主体となって取り組みたい社会課題を提示し、共感した自治体が提案する。対等な関係で対話を重ねながら共通の問いを深め、具体的な実証へとつなげる新しい官民共創の仕組みである。制度や予算の枠組みに縛られず、フラットに「こういう課題に挑戦したい」と発信できることで、自治体の側も柔軟に応えることができる。
プロセスは4段階。①企業が逆プロポへの参加を検討し、②「誰のどんな不便を解消し、どんな体験を届けたいか」といった問いを事務局と共に言語化する。③その問いに共感した自治体が提案を行い、④選定された自治体と実証に取り組む。特に②の設計は、企業の想いや提供価値を言葉に落とし込み、自治体との接点を見出す重要な工程だ。共通言語を持ちプロジェクトをはじめられることが成功の可能性を高めている。
実際に生まれたプロジェクトは多岐にわたる。蓄光技術とエンタメを活用して子どもの登下校の安全を守ったり、物流の知見から防災備蓄品の管理や分配を効率化したり、消防や介護施設の協力を得て夜間の救急搬送を減らしたりと、技術や仕組みだけでなく、地域や人々とのつながりを生む設計が重視されている。こうした取り組みは短期間で実証から検証まで進み、他自治体へと展開されるケースも増えている。
背景には自治体と企業とのあいだの「進め方」と「判断軸」の違いがある。自治体は公共性や公平性を重視しつつ、年度予算や議会承認などの制約の中で動く。一方、企業はスピード感や先行投資、事業性を前提に判断する。このギャップを従来の官民連携では十分埋めきれなかった。逆プロポはそうした前提の違いを認識してあらかじめ双方の立場を可視化し、合意形成を支援する伴走体制が整っている点でも特徴的だ。また、逆プロポは単体のマッチングサービスにとどまらず、周辺サービスも拡充してきた。2022年には自治体側の課題を整理し、共創可能なテーマに翻訳する「逆プロポ・コンシェルジュ」が誕生。2023年には自治体の現場から集めた生の声を整理した社会課題データベース「逆プロポVoice」や、官民共創に挑むスタートアップを支援する「ソーシャルXアクセラレーション」も開始している。
いずれも共通しているのは、「場のデザイン」「意思決定のデザイン」「お金のデザイン」の3つをていねいに組み込んでいる点。自治体にとっては、限られた予算の中で柔軟に挑戦できる機会となり、企業にとっては、仕様書に縛られず、スピード感を持って現場とつながるチャンスになる。共創のハードルを下げながら、実践の可能性をひらくこの仕組みは、今後ますます注目されていくだろう。
【 課題 】
スタートアップが入りにくい構造
初期のモデルは主に大企業が活用するケースが多く、企業が手数料を支払い、自治体との共創機会を得る仕組みとなっていた。しかし初期のモデルでは、社会課題の解決に強い意欲を持つスタートアップにとって、手数料や実証実験費用が大きな負担となり、参入のハードルが高かった。自治体側としても共創に必要な予算の確保や契約プロセスの柔軟化が難しく、企業との連携を進めづらいという課題があった。
【 対応 】
資金調達と支援の仕組みを再設計
こうした課題に対応すべく、地方自治体(東京都、群馬県など)や銀行と連携した官民共創のプログラムを開始し、スタートアップも参加しやすい構造へと進化させた。実証実験にかかる費用は一部ふるさと納税型クラウドファンディングなどの仕組みで賛同企業から集めることも可能に。これにより、実証に必要な費用をさまざまな側面から調達する仕組みが整備されてきた。また、有望なスタートアップへの投資を通じて社会課題解決型ビジネスを支援する取り組みもはじめている。
【 結果 】
さまざまな共創の実現と官民連携の深化
この対応により、企業が費用を一方的に負担する構造から脱し、自治体・支援企業・市民と共に資金を調達・分担できる仕組みが整った。ふるさと納税や外部資金の活用によって、スタートアップが初期費用の壁を越えて実証に参加できるようになり、参入のハードルが大きく下がった。こうした仕組みが広がることで自治体側も動きやすくなり、逆プロポは少しずつ社会に浸透、信頼ある取り組みに育ってきている。
AFTER: 2025年時点
EFポリマー
BEFORE: 2020年時点
水不足に悩む農家のための、廃棄された果物から生まれた「土に還るポリマー」
世界では、いまも多くの農家が深刻な水不足に直面している。特にインドや中東、アフリカなどの乾燥地帯では雨が数か月も降らないことがあり、畑に十分な水を与えられないまま作物が枯れてしまう。井戸水をくみ上げても地下水位は年々下がり、灌漑設備を持たない小規模農家にとっては打つ手が限られている。地球温暖化で干ばつの頻度は増し、農業の持続性が危機にさらされている。水不足は収穫量の減少だけでなく、農家の生活や地域社会全体の存続にも直結する深刻な課題だ。
こうした現場に新しい解決策を示そうとしているのが、インド発のスタートアップ、EF Polymer株式会社だ。「ポリマー」は水を吸収して保持する素材で、紙おむつや保冷剤など身近な製品にも広く使われている。しかし、従来のポリマーは石油由来のため分解性が低く、廃棄後の焼却時に多くのエネルギーを要するなど環境負荷を与えてきた。
EF Polymerが開発する「EFポリマー」は、この課題を根本から解決するものだ。土に混ぜれば自重の約50倍の水を吸収し、半年ほどかけて水を吸ったり放出したりしながら畑を潤す。水だけでなく肥料分も抱え込むため、雨で肥料が流れ出すのを防ぎ、結果として肥料の使用量も減る。実際、インドでの実証実験では、農家の節水は最大40%、肥料削減は20%、収穫は約20%向上したという。
現在はインドや日本、米国、フランスを中心に、多くの農家に届けられている。原料にはオレンジやバナナの皮といった従来捨てられてきたものを使う。化学薬品を使わず製造され、使用後は約1年で土に分解される。まさに、自然に還るポリマーである。さらに、独自の製法や現地ネットワークを活かしたサプライチェーンにより、石油由来品と比較して価格競争力の高さにも強みを持つ。
創業者ナラヤン・ガルジャール氏は、インド西部の小さな農村に生まれた。幼い頃から、干ばつで畑にひびが入り作物が枯れていく光景を見て育ち、水不足に苦しむ両親や村人を助けたいという思いが原点となった。高校時代に構想を練り、大学在学中に仲間とEF Polymerを立ち上げ、2019年には沖縄科学技術大学院大学(OIST)のアクセラレータープログラムに採択されて来日。現在は沖縄に拠点を移し、研究開発を進めている。
この技術は国際的にも注目されている。EF Polymerは「2022 APACクリーンテック25」に選出され、LVMH主催のWorld Living Soils Forumで総合優勝した。廃棄果物を活用し、自然に還るポリマーで水不足に立ち向かう取り組みは、農家の暮らしを支えるだけでなく、持続可能な農業の未来を描くものとして評価が高まっている。
【 課題 】
インド1拠点への依存と事業拡大に向けた壁
EFポリマーはインドで製造してきたが、原料調達や単一拠点への依存によるリスクを抱えていた。気候変動や市場環境の変化でバナナやオレンジの皮などの原料供給が不安定になる可能性があり、事業の継続性に懸念があった。また製品の特性上、農家が正しく使用して効果を実感できるよう教育も不可欠だが、その方法や仕組みが整っていないことも課題だった。さらに、農業だけでなく他産業にも展開できる可能性のある素材であるにもかかわらず、応用技術の確立が進んでいなかった。
【 構想 】
地産地消型の仕組みで多拠点・多分野に展開
研究開発の重点取り組みとして、ポリマー原材料の多様化とインド以外を含む工場多拠点化を進行。各地域で出る農作物の皮などを原料に「現地で調達、現地でつくる」地産地消型の仕組みを確立しようとしている。さらに、応用開発の発展で農業以外にも範囲を広げ、国内外の企業と組んで保冷剤や化粧品、オムツやナプキンなど生活用品の共同開発を進め、石油由来ポリマーの代替として社会全体の環境負荷削減への貢献も目指す。
【 結果 】
環境負荷低減と地域経済の活性化を同時に実現
インド、日本、米国、フランスを中心に販売拡大。EFポリマーの利用が広がることで、環境負荷軽減や干ばつなどの課題解決と、持続可能な農業につながれば、またそこから生まれる農作物の皮などが原材料になるが、そうした地産地消・地域循環型モデルを目指している。また、化粧品、日用品を展開する世界的企業からの相談で、共同開発への協議を進行。EFポリマーは農業課題の解決を出発点に、環境負荷低減と地域経済活性化を同時に実現する持続可能なビジネスモデルに挑戦している。
AFTER: 2028年時点
NEWLOCAL
BEFORE: 2025年時点
地域の「新しい地元民」として、共に未来を描く
2040年までに、日本の自治体の実に半数近くが消滅の危機に直面するという予測がある。地域を牽引するリーダーの不足や人材・資金・知恵の欠如、そして、一度きりで終わりがちな街づくりの再現性の低さは、多くの地域に共通する課題だ。2022年に創業した「NEWLOCAL」は、「地域からハッピーシナリオを共に」というミッションを掲げ、このような人口減少社会における、持続可能なモデルを実現することを目指してきた。
NEWLOCALは、地域内外の共創を通じて、人・金・知恵の循環を生み出す仕組みを整備している。特徴は、地元のキーパーソンと共に合弁会社を立ち上げ、地域に深く入り込んで事業を実装する点。行政や大手デベロッパーが中心となる従来型の街づくりと異なり、住民主体で会社を立ち上げ、文化や資源を理解したうえで、宿泊や飲食、交流施設などを展開。雇用や観光需要も創出し、地域経済の循環をつくり出している。
さらに、本体である株式会社NEWLOCALが資金調達や経営管理を担い、各拠点で得た知見を横展開することで、再現性のあるモデルへと磨き上げている。資金面では、地銀融資や助成金に加え、個人投資家やVC・事業会社などから数億円規模を調達。人材面では、地域人材と外部人材を半々で採用し、拠点間でのローテーションを仕組み化する。知見の面では、立ち上げや運営のノウハウを体系化し、次の拠点へと活用している。こうして、「一度きりの事例」を「横展開できる仕組み」へと変えているのである。
現在、長野県の野沢温泉村や御代田町、秋田県男鹿市、京都府丹後地域、石川県小松市、香川県丸亀市などで事業を展開。野沢温泉では冬季営業のみのロッヂ運営を引き受けて通年のアクティビティを整備したり、音楽やワインを楽しむバー「Music Bar GURUGURU」を開業し、地域に新たな交流を生んだ。さらに2026年1月には、新たなブティックホテル「mont」が開業し、通年観光の基盤づくりが進んでいる。男鹿市ではクラフトサケブランド「稲とアガベ」と連携し、宿泊施設や蒸溜所・飲食・小売を組み合わせた交流施設を準備。京都丹後では土産物店を事業承継したり、古民家を改修して文化を体験できる宿泊拠点への転換を計画している。
創業以来3年でNEWLOCALは累計10億円を調達し、50名以上を採用。2025年時点で6拠点の事業が始動しており、数億円規模の収益を上げている拠点もある。人口減少下でも成長できるモデルが形成されることで、地域の未来に持続可能な選択肢を提示する存在となっている。
【 課題 】
10拠点×10億円モデル実現に立ちはだかる壁
日本で人口減少が進む中、地域では人材や資金の流れが細り、事業の持続が難しくなっている。NEWLOCALも各地で数億円規模の事業を育ててきたが、10拠点10億円規模に引き上げるには、人・金・知恵を全国規模で循環させる仕組みが必要。地域ごとの取り組みを単発で終わらせず、成果を束ねて再現可能なモデルにできるかが次の課題だ。
【 構想 】
人・金・知恵を循環させて10拠点10億円へ
NEWLOCALは各地域会社をネットワーク化し、人・金・知恵が循環する仕組みを整える。出資比率や会社形態、関わり方も地域ごとにより多様なスキームを想定していく。地域の事業者が中心となる場合もあれば、大企業や外部の投資家が一部を担う場合もある。また、事業承継やM&Aなどの形態もあり得る。立ち上げや運営のノウハウを共有・体系化することで事業展開を加速し、地域横断的なプラットフォーム事業も構想する。
【 結果 】
全国への展開を視野に入れ、街づくりを産業に
10拠点10億円のモデルが実現すれば、その成果をもとに全国100拠点へと広がる道筋が見えてくる。地域会社は自立しながらつながり合い、金融機関や投資家が継続的に参画し資金の循環を支え、知見やノウハウも拠点間で共有されていく。こうして点在していた挑戦が束ねられ、街づくりは産業として持続可能なスケールを持つエコシステムへと進化する。さらに、将来的には日本で確立したモデルを海外にも展開し、グローバルに街づくりを推進する構想も視野に入れている。
AFTER: 2026年以降
Oishii Farm
BEFORE: 2025年時点
世界で初めていちごの安定量産ができるようになった植物工場
現代の農業は、気候変動や資源制約の影響を受け、安定的な生産が年々難しくなっている。農業人口は年々減少し、労働力不足や土地の制約も深刻化していく。こうした背景から、天候や人手に依存せず、都市部でも農作物を安定的に供給できる新しい仕組みとして注目されているのが植物工場である。
しかし、これまで植物工場の主力はレタスやハーブなどの葉物野菜に限られてきた。いちごなどの果菜類は受粉が欠かせないが、閉じた環境では花粉を媒介するハチがうまく飛ぶことができず、植物工場内での安定的な量産は不可能とされてきたからである。この壁を破ったのが、2017年にニューヨーク近郊で日本人が創業した「Oishii Farm」だった。
Oishii Farmは、植物工場をビジネスとして成り立たせるには、技術的難易度が高いとしても、味に差が出やすくブランドをつくりやすい作物からはじめるべきと考え、いちごの生産に挑んだ。日本の高品質ないちごを、それが手に入らないニューヨーク近郊で育てて販売することで、高い付加価値を提供することを目指した。研究を重ね、温度や湿度、光のスペクトルなどを制御し、ハチが「ここは屋外だ」と感じるほど自然な空間をつくり出すことで、屋内でも受粉を実現したのである。
さらにAIやセンサーを組み合わせ、細かく制御することで、通常の農法では60〜70%程度とされる受粉成功率を95%まで高め、高品質ないちごを生産性高く、365日安定的に量産できるようにした。
こうして生まれた「Omakase Berry」は、ニューヨークのミシュラン星付きレストランで提供され、「まるでスイーツのようないちご」と評されるなど、セレブやシェフのあいだで瞬く間に話題となった。当初は1パック50ドルという高価格にもかかわらず需要は集中した。コスト削減により1パック10ドルとなった2025年現在、Whole Foodsをはじめとする高級スーパー数百店舗以上に並ぶまでに成長した。高品質ないちごを、それが手に入らないニューヨークという場で販売することによるブランド戦略が成功の原動力となった一方で、その裏側では徹底した技術革新により、果物が植物工場で安定的に生産できるという新たな常識をつくり上げたのである。
2024年、Oishii Farmはニュージャージー州でメガファームと呼ばれる大規模施設を稼働開始。収穫ロボットの導入など、農作業の完全自動化に向けた基盤づくりを進めており、従来型農場の20倍にあたる生産性を目指している。こうした歩みは、植物工場を「葉物のための仕組み」から「サステナブルな次世代農業の基盤」へと押し広げる決定的な一歩となった。Oishii Farmの挑戦は、農作物のブランドづくりと技術革新を両輪にしながら、次の時代の食料供給の可能性を切り拓いている。
【 課題 】
地域性に依存する農業と、植物工場の世界展開に向けた課題
農業は天候や土壌に左右される地域性の強い営みで、国や地域を越え同じ品質で生産する仕組みをつくるのは難しかった。Oishii Farmはいちごやトマトを育てる植物工場の実現に成功したが、設備は自社開発および既存のものを組み合わせていた。今後、工場を世界に同時に建設するには標準化が必要となった。
【 構想 】
共創型イノベーションによる植物工場の展開戦略
2025年、日本でオープンイノベーションセンターの立ち上げを開始。日本には植物工場に必要な二大要素である施設園芸と工業の両領域において世界最高峰の技術力があり、研究開発として最適な地と判断したからだ。独自に積み上げてきた植物工場の「答え」を各領域の専門企業に開示し、量産化の仕組みを共創。種苗や栽培技術、照明や空調、ロボットなどそれぞれに対して植物工場に特化した設備や仕組みの開発を行い、パッケージとして整備。地域ごとの条件に左右されず、短期間で展開可能な仕組みの構築を目指す。
【 結果 】
世界に広がる植物工場でサステナブルな農業へ
各分野でのオープンイノベーションを通じ、世界展開の基盤を構築。また、いちごやトマトだけでなく他品目にも広がり、植物工場は「サステナブルな農業」を実現する次世代インフラとして浸透していく。その過程でOishii Farmは、各領域のトップ企業と連携しつつ、自動車産業に次ぐ新たな日本発グローバル産業の創出も目指す。
AFTER: 2030年時点
The Elephant People
BEFORE: 2016年時点
実物大の象が問いかける、人と自然の共存の形
南インド・ニルギリ地域では、外来植物ランタナの繁殖が課題となっていた。トゲが多く成長の早いこの植物は、一度広がると森を覆い尽くし、在来植物の再生を妨げる。そのため森林の多様性が失われ、土地の環境は大きく変わってしまうのだ。こうした変化は野生動物にも影響をおよぼし、とりわけ象にとっては深刻である。食べ物や通り道が減ったことで人里に現れるようになり、畑を荒らすなど人間の生活と衝突を起こす。農作物の損失や人身事故が起きるたびに、ランタナも象も地域の人々から「厄介な存在」と見なされてきた。
「The Elephant People」は、これら2つの課題を切り離して考えるのではなく、むしろ結びつける発想をとった。外来種ランタナを伐採し、乾燥させた茎を素材に実物大の象の彫刻をつくる。害として扱われてきた植物を資源に変え、脅威とされた動物を象徴として表す。この組み合わせ自体が、課題を価値に転換する仕組みとなっているのだ。
制作は地域の人々が担い、特に女性の参加が大きな役割を果たしている。伐採、素材加工、骨組み、編み込みなど複数の工程を分担しながら 1体ずつ仕上げていく。参加者には地域水準を上まわる報酬が支払われ、暮らしを支えるのと同時に、誇りを持って取り組める仕事となる。制作の過程は単なる作業にとどまらず、技能の習得や協働を通じて地域の結びつきを強める機会にもなっている。さらに、ランタナの伐採そのものが森林の回復を促すため、雇用と環境保全が自然に結びついた仕組みとして働いているのだ。
完成した象は公共の空間で展示される。自然素材でつくられた実物大の象は強い存在感を放ち、人と自然の関係を考える契機となる。そして、展示が終わった象はチャリティオークションなどを通じて流通し、その収益は再び制作や森林保全に充てられる。これによって制作費や参加者の賃金をまかなうと共に、活動を継続させる資金の循環がつくられているのだ。
購入は芸術的な価値だけでなく、活動の背景や意義への共感と結びついている。作品を手にすることは、所有にとどまらず、活動を支える行為としての意味も持っていた。こうした共感を伴う流通の仕組みが、活動の継続に欠かせない役割を果たしている。
The Elephant Peopleの取り組みは、害とされた植物と脅威とされた動物を結び直し、地域の雇用と環境保全を同時に実現する循環を生み出している。伐採から制作、展示、販売、再投資までが一体となった流れは、課題を課題のままにせず新しい価値へと組み替える構造を示す。この仕組みは、環境と社会の双方に働きかける持続可能なモデルとして機能しているのだ。
【 課題 】
暮らしと森の「課題」が見過ごされていた
南インドの山間部では、先住民族の人々が森で採集や狩猟を行いながら暮らしてきた。しかし、自然保護政策で森林が国立公園に指定されると、伐採や居住が禁じられ、彼らの伝統的な生業は維持できなくなった。また、外来植物ランタナの繁茂により森林の多様性が失われ、野生動物の行動域も変化。象による農作物被害などが発生しても、それらが構造的課題として認識されることはなかった。
【 対応 】
家具から象への発展とコミュニティの変化
当初は家具を制作していたが、その後、より象徴性を持つ実物大の象の彫刻へと発展。また、その製作には地域の人々が関わり、現地の働く場となった。そうした人たちにスキルがつくことで単なる労働者ではなくなり、自信がついてマイクロアントレプレナーになる人も出てきた。
【 結果 】
社会の注目が政策を動かす起点に
象の彫刻はロンドンやニューヨークをはじめ国内外で展示され、社会的な注目を集めた。インド大統領の視察や報道などの象徴的な出来事を経て、2021年にはインド政府が初の外来植物レポートを発表。さらに、タミルナドゥ州など複数の州では、ランタナの除去と活用を組み合わせた政策的な取り組みがいくつも進んでいる。活動の広がりに伴い、組織名もThe Real Elephant CollectiveからRealelecoへと変更した。
AFTER: 2025年時点
アラビンド眼科病院
BEFORE: 2017年時点
「不必要な失明を根絶」するため医療の定説を覆したビジネスモデル
インドでは、2010年時点で年間400万人もの国民が、失明の主な原因である白内障を患っており、当時の全世界の失明患者数の4分の1を占めていた。その多くは適切な治療を受ければ失明を避けられたが、貧困が原因で治療を受けられない状況だった。
課題を感じたDr.Govindappa Venkataswamy(通称ドクターV)は、1976年にインド南部のマドゥライに「アラビンド眼科病院(Aravind Eye Hospital)」を設立。「不必要な失明を根絶する」というビジョンを掲げ、貧しい人たちが無償で治療を受けられる、独自の「Aravind Eye Care System」と呼ばれるビジネスモデルを構築した。
医療費は、全額負担・一部負担・無料と段階を設け、患者は所得審査を受けることなく自分で支払形態を選ぶことができる。ほかの患者の負担額から無償分の医療費をまかないながら黒字経営を実現しているのだ。
こうした持続性を支えているのが、独自の高効率な手術体制だ。アラビンド眼科病院では、1つの手術室に複数の患者が入り、医師が1人の手術を行うあいだにスタッフが次の患者の準備を進める。医師以外のスタッフが役割を分担することで医師は手術に専念でき、回転率が飛躍的に高まる。
一見すると衛生面の懸念を抱かれそうだが、実際には清潔区域を厳格に分け、器具は患者ごとに完全滅菌される。その結果、感染率は欧米の大病院と同等レベルに抑えられ、安全性と効率性を両立した体制が実現している。こうした高回転を支える仕組みとして、独自のトレーニングプログラムがある。医師だけでなく看護師や技師も多能工として訓練され、世界各地の医療機関にもノウハウが共有されている。
もう一つの柱が、医療コストを根本から下げたサプライチェーンの内製化だ。1992年に設立された自社工場Aurolabでは、人工レンズや手術器具、縫合糸などを製造。製造原価と流通コストを徹底的に下げることで、欧米価格の10分の1以下、1枚あたり10ドル未満で高品質な眼内レンズを供給している。
このレンズはアラビンド眼科病院内で使われるだけでなく、インド国内外の医療機関やNGOにも販売され、白内障手術の普及とコスト削減に大きく貢献。年間数百万枚が出荷され、その収益が再び医療現場に還元される循環をつくっている。医療の効率化、コスト削減、そして公平なアクセス。これら3つを有機的に結びつけたアラビンド眼科病院のビジネスモデルは、単なる病院経営を超え、医療を社会インフラとして機能させる仕組みへと進化している。 “To eliminate needless blindness.”(不必要な失明を根絶する)という理念のもと、アラビンド眼科病院は経済性と社会性を両立させた医療の仕組みを築き、そのモデルは世界各地の医療現場にも波及している。
【 課題 】
患者数に対し専門医が不足、対応が追いつかない
アラビンド眼科病院は、農村や小都市にも医療を届けるため、独自の一次診療拠点「ビジョンセンター」を各地に設立。地域の検査技師が初期検査を行い、専門医が遠隔で診断を行う仕組みを整えていた。この体制により、医療が届かない地域でも治療を受けられるようになったが、拠点の拡大と共に専門医が確認すべき検査件数が急増。すべての画像や結果を医師がチェックする仕組みが限界に近付いていた。
【 対応 】
AIスクリーニングツールを導入、眼科医不足を克服
2018年、Google社・Verily社と提携し、AIを活用した画像診断ツールを導入。検査技師が撮影した眼底画像をAIがすぐに解析し、病気のサインの有無を見つけられる仕組みをつくった。リスクの高い患者だけを専門医が確認するように変えることで、医師は診療や手術に集中できるようになり、現場での検査数も大きく増やすことができた。
【 結果 】
さらなるAI活用と国外への技術支援
その後もスマートフォンを活用した眼底撮影システムやオフラインで活用できるGoogleAI対応の眼底カメラを導入し、通信インフラが不十分な地域でも検査できる環境を整えていった。現在では年間600万件以上の外来受診があり、70万件を超える手術が行われている。さらに、アラビンド眼科病院は海外にも協力の輪を広げ、バングラデシュ政府によるビジョンセンターの整備を技術面で支援。2023年までに135拠点の設立が進み、医療提供の範囲を海外へ広げている。
AFTER: 2025年時点
Fairphone
BEFORE: 2018年時点
採掘から修理・リサイクルまで、より公正なスマホを目指す
スマートフォン産業は、常に新製品を投入して短期間で買い替えを促す構造を持ってきた。その結果、寿命を迎える前に廃棄される端末が増え、世界中で大量の電子ゴミが生まれていた。また、製造の背景には採掘現場での児童労働や環境破壊、鉱物取引が武力紛争の資金源となる紛争鉱物問題など、人権や環境をめぐる深刻な課題が横たわっていた。こうした現実を前に、オランダのFairphone社が2013年に創業。単にスマートフォンを販売するのではなく、製品を通じて業界の仕組みそのものを変えようとする社会企業として歩みをはじめた。
「Fairphone」は、一般的なメーカーが性能や価格で競争するのに対し、製品を通じてサプライチェーンを公開し、公正な取引を経た電子機器を広げるためのムーブメントとして持続可能な仕組みを広げることを目的としている。スマホは収益源であると同時に、社会変革の実験台でもある。消費者がどんな価値にお金を払うのかを選べる市場をつくることが狙いだ。
特徴的なのは、長く使える設計。Fairphone 2以降は、壊れやすいディスプレイを工具なしで交換でき、カメラやスピーカーなどもドライバー1本で修理可能となった。さらに2017年には、カメラモジュールを後からアップグレードできる仕組みを導入し、「使い込むほどよくなるスマホ」という新しい発想を提示した。修理しながら5年間使い続けることでCO₂排出量をおよそ3割削減できるという。
素材調達や製造工程の透明性も強みだ。Fairphoneは、錫・タンタル・タングステン・金といった紛争鉱物の追跡を可能にし、2016年には家電メーカーとして初めてフェアトレード認証の金を調達した。リサイクル由来の素材も積極的に採用している。さらに2018年には、公式サポートが終了していたFairphone 2に対しても、約50万ユーロを投じて独自にAndroid 7へのアップデートを行った。これは「売り切ったら終わり」ではなく、収益を製品の延命や社会的な価値づくりに使う姿勢を示すものだった。
こうした取り組みで、Fairphoneは不透明なサプライチェーンの可視化、短命な製品サイクルへの対抗、労働者福祉の改善が現実に可能なことを示してきた。公正な報酬と持続可能な生産を両立させる仕組みを築き、大手メーカーに対し、持続可能なビジネスは不可能ではないという具体的証拠の提示となっている。
Fairphoneは大手に比べればその規模は小さいが、着実に販売実績を積み上げ、公正なスマホが一定の需要を持ち得ることを示している。消費者には製品の裏側にある仕組みを選ぶ購買行動を促し、業界には、公正で持続可能な仕組みを整えても事業が成り立つ可能性を示してきたのである。
【 課題 】
販路拡大が進まず、労働者の賃金改善も停滞
直販や一部代理店に限られるFairphoneの販売は市場規模が小さく、理念を広く浸透させるには限界があった。販売が伸びなければ収益基盤も不安定で、事業の持続性が危うくなる。さらに、サプライチェーンの労働者賃金は生活を支える水準に届かず状況が改善しにくく、販路の制約と生活賃金の問題が同時に重くのしかかっていた。
【 対応 】
通信事業者との提携と追加報酬制度の導入
2019年11月、FairphoneはVodafoneと戦略的提携を結び、欧州5か国で販売網を拡大。直販依存から脱し、より多くの消費者に公正なスマホを届ける基盤をつくった。その後はドイツテレコムやフランスのOrangeなど他事業者でも取り扱いが進み、販路はさらに広がっていった。加えて、スマホ1台あたり1~2ドル上乗せし、工場労働者の生活賃金との差を補う追加報酬の制度を導入。この仕組みは組立工場だけでなく、部品を供給する工場の労働者にも対象を広げた。
【 結果 】
販売規模拡大と労働者意識の改善
販売台数は2013年の約2万5000台から累計で伸び続け、2023年には年間10万台規模を維持するまでに。倫理的なスマホという比較的ニッチな市場でこの規模を安定的に実現したことは大きな前進といえる。2019年以降の生活賃金のボーナスは累計100万ドル超が支給され、労働者のあいだで自分の賃金を公正と感じる割合は27%から49%へと高まった。まだ課題は残るものの、制度を仕組みとして定着させ、部品供給側にも対象を広げる取り組みを進めたことは意義ある一歩となった。
AFTER: 2025年時点
「ひろげる」チェックリスト
※noteを読んでいる方へ
ここまでで第2章が終わりです。すごい、よくここまで読みましたね。これで全体の約49%の進捗です。ここまで読んでおもしろいって思ったら(もしくはスクロールして読むのつかれた・・と思ったら)、以下のリンクからお買い求めいただけます。のこり半分まできているので、まだ体力が残っている方は続きをどうぞ!
第3章 「ふかめる」 新たな商品・価値を追求する
領域はぶらさないままに、提供する価値そのものを深化させる動き。商品やサービスの改良にとどまらず、体験や意味の層を深め、「ブランドや事業のあり方を再定義している」事例を紹介する。
丸井グループ
BEFORE: 2020年時点
信用を共につくる考え方を、小売と金融の一体化で具現化
「丸井グループ」の原点は、1931年に創業した家具の月賦販売にある。現金を持たない人でも分割払いで生活必需品の購入を可能にし、「収入が少なくても信用があれば暮らしをよくできる」という仕組みを整えた。戦後の混乱期には復興を支える生活インフラとしての役割を果たし、高度経済成長期には若年層や新婚家庭をターゲットにファッションや日用品などを取り揃え、誰もが安心して買い物ができる環境を整えた。こうした創業期からの姿勢は、単なる販売手法を超え、人々と共に信用を育てるという事業の根幹へと発展していったのである。
月賦販売は単なる分割払いではなく、顧客と企業のあいだで信用を築く仕組みだった。商品を購入し、期日どおりに支払うことで顧客は信用され、次の取引へとつながっていく。信用を一方的に与えるのではなく、利用を通じて共に積み上げていく。この考え方は、後のクレジットカード事業に受け継がれ、丸井グループの事業構造を支える礎となった。
しかし、バブル崩壊後の1990年代、消費の低迷と共に丸井の業績が悪化する中、「モノを介さずお金を貸すだけ」の消費者金融事業へと傾き、その後2007年以降には経営危機に直面。このときの反省を経て、丸井は金融を単なる「貸付の仕組み」ではなく「顧客との関係を育む仕組み」として再構築する決断を下した。
VISAライセンスを取得し、他店舗でも利用できる汎用カード「エポスカード」を2006年に発行。これにより、丸井のカードは「丸井の中だけで使えるカード」から「世界中どこでも使えるカード」へと進化した。店舗は商品の販売拠点にとどまらず、カード発行や会員サポートを担う顧客接点としての機能を強化。培われた顧客接点を金融のインフラへと拡張したこの転換は、同社の事業構造を根本から変え、小売と金融が往復するハイブリッドな事業モデルの原型がつくられた。
エポスカードは、入会当初は利用限度額を低く設定し、利用と返済の実績に応じて段階的に引き上げる仕組みを採用している。年齢や職業などの固定的な基準ではなく、利用履歴そのものを信用として扱う設計は、創業期の月賦販売の思想を現代的に継承するものである。初めてカードを使う人や、これまで金融にアクセスしづらかった層も含め、誰もが自らの行動を通じて信用を築ける仕組みを整えている点が特徴で、丸井はこの仕組みを通じ、金融を貸し借りの関係ではなく、「共に信用を育てる関係」へと再定義した。
丸井グループが一貫して大切にしてきたのは、顧客と共に信用を積み上げ、その信用を新しい価値へと変えていく姿勢。月賦販売からクレジットカードへ、店舗から信用基盤へ。丸井の歩みは、時代ごとに形を変えながら、信用という見えない価値を社会の中に制度として可視化してきた過程だった。金融と小売の融合を通じ、すべての人が自らの信用を築ける環境を整えてきたことこそが、丸井グループの変わらぬ強みなのである。
【 課題 】
従来の経済合理性の枠内では独自の価値を発揮しづらい
アパレルや化粧品などの領域ではグローバル企業の参入が進み、リアルとオンラインの融合も加速した。結果、競争はコストやパフォーマンスなどの効率指標に収れんし、カード事業もポイント還元率の比較に偏っていった。こうした構造の中では、丸井が長年培ってきた「人の想いを起点に価値を生む」強みを十分に発揮しにくい。経済合理性の延長線では届かない価値をどう設計するかが次の課題となった。
【 対応 】
好き」を応援するを軸に共創型の循環を設計
丸井グループは、クレジットカードを「割引で得を与える仕組み」だけでなく、顧客の関心や想いが社会とつながる仕組みへと再設計した。アニメやアーティスト、ペットなど多様なテーマと連携したカードを展開し、利用額の一部や貯めたポイントを寄付や支援に充てられる仕組みも導入した。さらに、店舗では世界観と連動した体験イベントやポップアップを開催し、好きなものを応援する行為そのものが社会的な価値循環に参加する行為となる環境を整えた。
【 結果 】
経済価値から感情価値への転換
特に「好き」を応援するカードは一般カードに比べて利用の継続率が高く、新しい顧客層の獲得にもつながった。利用行動が支援に直結することで、経済活動が個人と社会の双方に価値を生む循環が成立し、丸井グループの強みである“関係を育てる”モデルが現代的に拡張された。たとえば、ペット保険や動物病院など周辺事業との共創も進み、小売でも金融でもない新しい経済領域が形を取りはじめている。
AFTER: 2025年時点
マザーハウス
BEFORE: 2017年時点
途上国の素材・職人技術を最大限に活かしたものづくり
多くの新興国や開発途上国では、製造環境や流通体制が十分に整っていないため、製品の品質にバラつきが生じやすく、高品質なものを安定的に届けるのが難しいケースが少なくない。その結果、消費者が製品そのものの魅力で購入するのではなく「支援のために」買う形になりやすく、販売の拡大に限界があった。また、価格も低く抑えられることが多いため、経済性を保ちにくいという課題もあった。
この課題に向き合うのが、2006年にバングラデシュで創業した「マザーハウス(MOTHERHOUSE)」だ。マザーハウスは途上国の天然素材や伝統技術を活かし、現地の職人と共に上質な製品を生み出すファッションブランドである。「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げ、ものづくりを通じて現地の雇用創出や職人の技術と誇りを高めることを目指している。
創業者の山口絵理子氏は大学で開発学を学び、「現場を知りたい」との想いから、当時のアジア最貧国バングラデシュを訪れた。そして、そこでコーヒー袋として使われる天然素材ジュート(黄麻)と出合う。環境にやさしく強度が高い素材に可能性を感じた山口氏は、ジュートで高品質のバッグをつくりたいと考えるようになる。苦労しながら約半年かけて工場を探し、自分でデザインして職人と共に手を動かし、160個のバッグを完成させたことがブランドのはじまりだった。
現在もマザーハウスでは、デザイナーが素材の選定・デザイン・製造まで深く関わり、職人と対話しながら商品を生み出している。この過程が職人の技術や可能性を最大限に活かしたものづくりを可能にし、途上国でも高品質な製品を生み出し続けている。
素材の開発力も大きな強みだ。2007年の商品リニューアル時にはジュート素材でしかできない表現に向き合い、山口氏自身も職人と共に試行錯誤を繰り返した。その結果、デザインをフォーマルラインからカジュアルラインに切り替え、売上は旧作の10倍に伸びた。
また、「モノを届けるのがゴール」という精神を持ち、ものづくりだけでなく顧客に届けるまでを一貫して担う点もマザーハウスの特徴だ。創業初期はウェブサイトと卸先での販売が中心だったが、顧客と直接対面する機会が少ないことに課題を感じ、2007年、東京の下町・入谷にマザーハウス初の直営店をオープン。店舗空間にもこだわり、内装も自分たちで担当した。ブランドの社会性に共感する顧客が訪れ、売上は好調だった。
こうした複数の特徴・強みによって、途上国でも高品質な製品を生み出し、社会性と経済性を両立した途上国発のブランドを実現している。
【 課題 】
社会性だけで、ものは売れない
東京・入谷の1号店では、マザーハウスをよく知り、社会性に共感するファンがわざわざ店舗を訪れて商品を購入してくれるため、売上は好調だった。しかし、2008年に初めて百貨店に出店したところ、うまく商品が売れずフロアで下から2番目の売上に。競争にさらされたことで、社会性はあっても商品力が負けていてはものは売れないことに気付いた。
【 対応 】
工場・情報・サプライチェーン、すべてのモデルを変化させる
2008年12月に初の自社工場を設立。素材選び・製造・販売まで自社で手がける「製造小売業(SPA)」という事業形態を実現した。その結果、顧客ニーズや販売結果を瞬時にフィードバックできる状態になり、品質が向上。また、工場訪問ツアーや国内イベントで職人が最終消費者と直接触れ合う機会をつくることで、より顧客を意識したものづくりができるようになった。
【 結果 】
ものを買った後で社会性を知る人が増える
品質・デザイン改善を進めた結果、百貨店での売上は上から2番目にまで上昇。商品価格も向上した。いまでは6割の購入者が途上国でつくられていることを知らずに購入し、後からブランドストーリーを知ってファンになるケースもある。現在は6つの生産国と3つの販売国に拡大。今後は米国への進出強化を予定している。また、アパレル・ジュエリー・チョコレートなどファッション以外のブランドの自立にも力を入れていく。
AFTER: 2025年時点
星野リゾート
BEFORE: 2024年時点
運営に特化した経営で、温泉旅館からホテル運営会社へ
「星野リゾート」は1914年に軽井沢で温泉旅館として創業。4代目の星野佳路氏が1991年に代表に就任して以降、家業から企業経営へと転換し、観光業の構造を再設計する取り組みを重ねてきた。バブル崩壊で観光業が低迷し、多くの旅館が資産と負債を抱える中で、同社は早くから「資産を持たずに運営に特化する」という方向を明確に打ち出した。これは、将来のホテル市場の変化を見据え、スピード感ある施設展開によって規模の経済を確保するための判断でもあった。
この「運営特化」という選択は、当然ながら複数のトレードオフを伴う。星野リゾートの特徴はこうしたトレードオフを伴う選択を組織・人材・ブランド・運営のすべての構造に貫いている点にある。たとえば、 「運営特化」は「所有することで得られる利益をとらない」というトレードオフの上に成り立ち、「サービスチーム」は「分業型チーム」と対になる構造だ。また、「日本旅館メソッド」を活かす一方で、西洋ホテル型のマニュアル運営をあえて採用しない。さらに、上下関係よりも自律的な判断を重んじるフラットな組織文化づくりを進めていた。これらの要素は個別に真似できるものの、相互に結びついて全体として機能していて、部分的に模倣しても再現が難しい。
また、「どこで勝ち、どこで差別化し、どこを業界水準にとどめるか」を明確にする「ファイブウェイ・ポジショニング戦略」という戦略論があった。星野リゾートはこの考え方を自社の経営に応用し、商品・サービス・経験価値・買いやすさ・価格の5つの軸のうち「経験価値」を最も高水準に引き上げ、「買いやすさ」で差別化し、ほか3つは業界水準レベルでよいという戦略をとった。すべてを完璧にしようとするのではなく、経験価値で圧倒することに焦点を定めたのである。
販売の仕組みでは、「買いやすさ」で差別化するために宿泊予約サイトへの依存を減らす方針をとっていた。自社ホームページを通じた直接予約を拡大し、外部予約サイトでの販売手数料を抑えながら顧客との関係を維持する体制を構築。宿泊と食事、体験を一体で予約できる導線を整え、滞在全体をブランド体験として設計していた。
資産構造の面では、不動産投資信託(REIT)を活用し、所有と運営を分離する仕組みを構築。投資家が資金を出し、ホテルやリゾート施設を保有・運用して収益を分配する。不動産を所有するREIT法人に対し、星野リゾートが運営契約を結び施設を運営する仕組みだ。資産運用は同社の100%子会社が担い、外部資本と内部経営を結ぶ役割を果たしていた。さらに、日本政策投資銀行と共同設立のファンドが新規の「開発」や再生プロジェクトを支え、外部資金の循環を生む。こうして自己資金に依存せず、新しい施設を開発する体制が整えられていったのである。
この資本分離の仕組みで星野リゾートは運営拠点を拡大し、ブランド体系を整備。「星のや」「界」「リゾナーレ」などを確立し、それぞれが地域の文化や自然を活かした滞在を提供していた。各ブランドは共通の運営思想のもと、立地や顧客層に応じた多様な価値をつくり出していた。このような星野リゾートのブランド、運営、人材、資本が相互に連動するこの構造が、他社が模倣できない競争優位の源泉となっていたのだ。
【 課題 】
提供したい体験価値と既存管理基盤で実現できる価値のギャップ
従来の予約シ ステムでは、実現したい旅の価値を予約導線の中で十分に表現できなかった。たとえば、旅の計画段階で人数や部屋タイプ、宿泊プラン、日程に変更が出た際には予約の取り直しを要し、顧客・現場共に大きな負担だった。また、食事やアクティビティの予約が旅程の流れと分断されるなど、宿泊前後の体験まで一体的に案内するのが難しく、提供したい滞在価値をオンラインで再現するうえで構造的限界があった。
【 対応 】
旅の予約体験を再設計する独自システムの開発
こうした制約を根本から解決すべく、星野リゾートは16年かけて新たな予約システム「FleBOL(フレボル)」の開発を進めてきた。FleBOLは「Flexible Booking On Line」の略称で、2025年10月には第1弾として予約後でもオンライン上で人数・部屋タイプ・宿泊プラン・日程を変更できる機能を導入。予約変更に伴う問い合わせが全体の約4割を占めていた実態に対応し、チェックイン当日の午前9時まで変更できるようにした。
【 結果 】
宿泊を起点に、旅全体を編成できるプラットフォームへ
FleBOL導入で予約変更の負担が軽減され、顧客は旅の計画をより自由に調整できるようになった。さらに、将来的には客室・食事・アクティビティ・交通などを一体で編成できる旅全体のショッピングカートを実現する構想も。従来の予約導線では分断されていた体験情報を統合することで、宿泊業のデジタル基盤そのものを再定義し、滞在価値を最大化するプラットフォームへの進化が期待されている。
AFTER: 2025年以降
久遠チョコレート
BEFORE: 2021年時点
福祉的就労支援の課題にチョコレートで変革を起こす
日本の障害者雇用の現場には、長年の深刻な課題がある。就労継続支援B型事業所(雇用契約に基づく就労が難しい人が対象)に通う、障害のある人の平均工賃は、月1万5000円前後にとどまっている。利用者が自分のペースで働ける利点はあるものの、最低賃金が適用されないため、生活の自立にはほど遠い水準だ。働く意欲があっても十分な収入を得られない現実をどう変えていくかが大きな社会的課題となっていた。
その状況を変えようと動き出したのが、一般社団法人ラ・バルカグループだった。当初はパン工房を立ち上げ、障害のある人が働きながら収入を得られる場づくりを試みた。しかし、パンづくりは工程ごとの作業内容が複雑で、仕上がりにバラつきが出やすい。高温のオーブンを扱うためやけどの危険もあり、分担の難しさや安全性の問題から理想の環境を実現するのは容易ではなかった。
そこで着目したのがチョコレートである。チョコレートは高単価で労働生産性が高く、正しい素材を正しく使えば美味しい製品がつくれる。また、チョコレートは40~50°C程度までの温度で加工でき、パンのように高温を扱うリスクがない。失敗しても再び溶かしてやり直せる柔軟さがあり、作業を細かく分担しやすい。型に流し込む、トッピングを載せる、包装するといった多様な工程があり、それぞれが自分に合った役割を担うことができる。こうした特性が「つくる過程で誰も排除しない」働き方のデザインに適していた。「久遠チョコレート」は、この素材の可能性を最大限に活かし、障害のある人とない人が共に働ける仕組みを積み上げてきたのである。
現在では全国60以上の拠点を展開、約830人が製造や販売に携わり、その半数以上を障害のある人たちが占める。商品は百貨店や商業施設でも販売され、福祉の文脈を超えて一般の市場に受け入れられている。さらに、久遠チョコレートでは売上の多くを働き手に還元し、従来の福祉的就労では得られなかった水準の収入を実現。重度の障害がある人でも月5万円以上、中度や軽度の場合はフルタイムで月17万円に達している。これは障害者雇用における賃金の全国平均と比べても圧倒的に高く、「障害者雇用は低賃金があたりまえ」という固定観念を覆している。
2021年には重度障害者が働く「パウダーラボ」を開設。粉砕や袋詰めなどの工程を細かく分担することで、より多くの人が安全に作業できる仕組みを整えた。久遠チョコレートは、制度のすき間に置き去りにされてきた人々に経済的な自立の道をひらき、「誰も排除しない」考え方を具体的な事業として体現している。障害のある人の働き方に新しい選択肢を提示し、日本社会における「共に働く」ことの意味を改めて問い直している。
【 課題 】
働きたい人が増え続ける中、仕組みと商品力に限界が
久遠チョコレートで働きたいとの問い合わせは年間1000件以上、その6~7割は親子の就労希望だ。全国に拠点を広げてきたが、現状の仕組みではすべて受け入るのは難しい。従業員の9割は菓子づくり未経験で商品開発力にも限界があり、フランチャイズの多くを福祉事業者が担う構造はブランドの一貫性や成長力に課題を残していた。さらに、チョコレートはバレンタイン需要に依存、年間の安定的売上確保も課題だった。
【 対応 】
シェフとの協働とオーナーの多様化で課題に挑む
こうした課題に対し、フランチャイズのオーナー層を広げ、障害者支援団体に加えて医療法人や若者支援団体、子育て中の親など多様な主体を迎え入れてきた。福祉事業所に偏りがちな構造を見直し、安定した運営を行う人材を増やすことでブランド基盤を強化している。また、国内外のシェフと協働し、サブブランドや新商品の開発を推進。プリンやバターサンドなど通年商品を導入して需要を平準化し、カカオの直接取引や独自ブレンドで原料高騰にも対応、独自性の確立を進めている。
【 結果 】
より多くの人が働ける場と、選ばれるブランドへ
全国に多様な背景を持つ拠点が広がり、より多くの人が働けるようになってきた。シェフとの協働による新商品の開発で品質が高まり、プリンやバターサンドといった通年商品が定着したことで、季節変動の大きかった需要もより安定に向かう。現在は「ていねいな資本主義」をキーワードに、どんな状況の人でも胸を張って働ける環境づくりと、社会から選ばれるブランド・商品づくりの両立に挑み続けている。
AFTER: 2025年時点
CRISP SALAD WORKS
BEFORE: 2018年時点
注文からオペレーションまで、全方位でデータドリブン
成功する飲食店に必要なのは、よい商品・よい人材・よい業態の3要素だといわれる。株式会社CRISP創業者の宮野浩史氏は、日本は海外と比較してよい要素が多いにもかかわらず、経営に苦しむ飲食店が多いと感じていた。
その背景にあるのは、テクノロジー活用の遅れ。多くの飲食店ではいまだにデジタル化やデータ活用が進んでおらず、勘や経験に頼った属人的な経営が主流だ。その結果、業界全体として生産性が上がらず、収益率も低いままとなっている。
宮野氏は2014年に株式会社CRISPを創業し、「日本の外食を、ひっくり返せ。」をパーパスに掲げ、栄養バランスに優れたカスタムサラダを提供する飲食チェーン「CRISP SALAD WORKS(クリスプサラダワークス)」を展開。トッピングやドレッシングを自由に選べる楽しさに加え、たっぷりの野菜、チキンや豆などの具材、手づくりの味わいといった特徴が支持され、味・栄養・満腹感・見た目のすべてを満たす食体験として多くのリピーターを生んでいる。この背景には、「テクノロジー活用」と「データドリブン経営」による、効率的かつ高品質な店舗運営がある。
注文と会計のプロセスは、独自のモバイルオーダーアプリ「クリスプアプリ」とセルフレジによってデジタル化されていて、来店客はレジに並ぶことなくスムーズに注文・決済が可能だ。アプリを使えば事前注文もでき、受け取り時間に合わせて来店するだけで商品がスムーズに手に入るため、昼休みが限られるオフィスワーカーにとっては大きな利便性となっている。
一方、スタッフ側にとっても、注文や会計業務が簡略化されることで、接客や調理といった「人にしかできない仕事」に集中できる環境が整えられている。このようなデジタル体験を通じてクリスプは膨大な顧客データを蓄積しており、注文内容、来店時間帯、トッピングの傾向、購入頻度などの詳細な情報は、社内システム 「クリスプメトリックス」で一元管理されている。これにより、店舗ごとの需要予測や食材の仕入れ、メニューの人気分析などにデータを活用している。
さらに、売上や注文数、LTV(顧客生涯価値)、顧客満足度などの指標はリアルタイムでモニタリングされ、現場の改善や経営判断に直結。自社の成長をデータで支えるモデルを示すことで、デジタル化によって効率的かつ持続可能な成長が可能であることを証明している。
【 課題 】
チェーンの拡大と共に失われた、体験価値の一貫性と差別性
店舗数と従業員数が増え、組織が急成長したクリスプは、チェーンの拡大によって現場の柔軟性が失われ、接客の画一化や運営の硬直化が進行した。顧客体験のバラつきや満足度の再現性低下によって、「選ばれる理由」が見えづらくなり、ブランドの独自性や競争力も揺らいで、コモディティ化のリスクが経営上の明確な課題として表面化していた。
【 対応 】
従業員体験への本格投資と、外食産業変革への布石
顧客体験の裏にある従業員体験の向上に本格投資。シフト希望や業務インセンティブを柔軟に設計できるアプリを自社のエンジニアで開発・導入し、接客品質の再現性を高めた。人手が足りない時間帯には時給を一時的に引き上げたり、顧客からの年間20万件の評価をもとに従業員を評価し、インセンティブとして給与に加えて渡している。さらに、都心オフィスワーカーの主要ニーズである定食業態のM&Aを行い、LTVや売上などKPIも外部公開することで業界全体の進化を後押しした。
【 結果 】
三者の利益が循環する仕組みと展開強化
従業員の働きやすさと満足度が接客品質の向上につながり、顧客の来店頻度や購買単価が上昇。結果として企業利益も向上し、その利益が従業員へと還元されるという、三者の利益が循環する仕組みが確立された。この構造は「クリスプメソッド」として定着し、2025年末には47店舗、600人のスタッフ、年間33億円の売上高を見込む。2040年に向けて売上高3000億円を目標に掲げ、クリスプメソッドの強化、M&A戦略の推進、AIへの投資を行い、日本の外食産業の変革を進めていく。
AFTER: 2025年時点
find
BEFORE: 2021年時点
落とし物の探し方を根本からひっくり返す仕組み
年間8000万件ーこれは日本で届け出られている落とし物の数だ。駅や空港、商業施設で毎日のように発生し、現場はその対応に追われてきた。電話が鳴り、紙の台帳と写真での管理、警察への届け出......。どれも時間がかかり、しかも収益に直結しない。人手不足の中では「対応に追われる」こと自体が大きな負担になっていた。「find」は、こうした状況を根本から変えるクラウドサービスである。京王電鉄などの協力を得て現場に入り込み、実際にスタッフとして働きながら課題を洗い出して、AIとクラウドを組み合わせた仕組みをつくり上げた。
従来、落とし物の登録は、人がその特徴を文章で記録するのが一般的だった。しかし、色や形の言いまわし一つで探す人と記録する人の認識が食い違う。
「赤い財布」と記録されていても、持ち主が「ワインレッド」と申告すれば検索に引っかからない、といったことが日常的に起きていたのだ。findでは、拾得物をスマホで撮影するだけでAIが色や形を自動判定し、関連する色も含めて分類する。これで「赤」と「ワインレッド」が別物扱いされることはなくなり、検索の精度が大きく向上。結果として、落とし物の返却率は3~4倍に跳ね上がっている。
問い合わせ対応も大きく変わった。従来は電話が中心で、スタッフが何十件、何百件と応対していたが、findではAIチャットと専用オペレーターが24時間受付する。利用者はLINEやWebから時間や場所を問わず問い合わせでき、現場スタッフは本来の業務に集中できるようになった。落とし主にとっても「探す負担」が大幅に減ったことになる。さらに、落とし物管理には保管期限や警察への届け出など、遺失物法に基づく法的要件がある。findはこれらをシステムに組み込み、施設が適切に管理できるよう設計されているため、公共性の高い施設でも安心して導入できる。
findでは取り扱う落とし物の数に応じて料金が決まる。中央値は月額80万~100万円ほどだが、実際には10万~2000万円超まで幅がある。一見安価ではないが、導入施設では、落とし物登録や問い合わせ対応などの業務コストが平均80%削減され、返却率の大幅向上も実現するため費用対効果は高い。こうした成果は口コミで広まり、鉄道や商業施設にとどまらず、空港や大規模イベント会場などにも利用が拡大している。しかも、支払いはほとんど年額一括で行われるため、会社経営のうえで重要なキャッシュが先に来る仕組みになっている。
導入施設はすべての落とし物情報を単一のデータベースで管理するため、導入が広まるほど落とし主は施設ごとに問い合わせる必要がなくなる。利便性は施設側と落とし主側の双方で向上し、ネットワーク効果によって導入の価値がさらに高まる構造だ。
findは単なる返却効率化にとどまらず、落とし物を起点に現場のオペレーション改善や安全対策の高度化まで実現できるのが特徴。技術と現場感覚を融合させ、身近でありながら社会全体に影響する課題を解きほぐしていくこの仕組みは、今後ますます存在感を増していくだろう。
【 課題 】
落とし物保管スペース不足が各施設や警察で顕在化
findが落とし物管理システムを導入するにあたり各施設を見てまわると、多くの施設で落とし物を保管するスペースが慢性的に不足していることがわかった。この課題は、落とし物を一時預かる警察においても顕在化していた。落とし物を情報として管理するだけでなく、モノそのものを預かり、分類し、返却・発送するまでの現場オペレーションの負担をどう支援するかが、findにとって重要なテーマとなっていた。
【 構想 】
現場でバラバラにやっていた返却作業を一元化
そこでfindは、各施設で個別に行われていた落とし物の保管・返却業務を、一括で回収・管理・発送まで代行する仕組みを構想・実装しはじめている。自社で倉庫機能を整備し、施設から落とし物をまとめて引き取り、保管・問い合わせ対応・発送業務までをfindが担うことで、現場の物理的な負担を大幅に軽減。情報だけでなく“モノ”の流通までを包含する新たな支援体制を構築しつつある。
【 結果 】
落とし物業務そのものを委ねる“丸ごと代行インフラ”
この構想が実現すれば、導入施設は落とし物の発生から返却までのすべての業務をfindに任せることが可能となり、現場の負担は大幅に軽減される。現在では、警察のサイトにもfindのサービスが掲載され、単なる情報検索システムを超え、落とし物の保管・管理・返却までを一気通貫で担う新たな社会インフラとして、findはさらなる進化を遂げはじめている。
AFTER: 2025年時点
全国こども食堂支援センター・むすびえ
BEFORE: 2018年時点
こども食堂の持続的な運営基盤を支える“縁の下の力持ち”
近年、日本では子どもの貧困や孤食、家庭や学校以外で安心して過ごせる居場所の不足といった課題が指摘されてきたが、単身世帯が約4割になるなど、家族形態の変化や地域のつながりが弱まる中、子どもを含む誰もが気軽に立ち寄れる場へのニーズは年々高まっている。こうした社会の中で、人々のさまざまな思いと行動から生まれ、全国に広まってきたのが「こども食堂」である。
「こども食堂」という名称のイメージから、貧困家庭の子どもに限定された支援拠点と思われがちだが、実際は子どもに限らず大人や高齢者含め誰でも参加できる“地域の居場所”として機能していることが多い。みんなで食事をいただく場であり、安心して過ごせるサードプレイスであり、地域の人と人をつなぐ交流拠点でもある。だからこそ都市部から離島、中山間地域まで、全国各地で活動が根付いてきたのだ。
現在、全国のこども食堂の数は1万2000以上。その数は増加し続けていて、公立の中学校数を超え、地域に欠かせない存在として定着しつつあるが、その広がりを支えてきたのが、2018年設立のNPO法人、「全国こども食堂支援センター・むすびえ」だ。むすびえはこども食堂の現場を直接運営するのではなく、地域ごとに立ち上がるネットワーク団体や行政、企業、支援者をつなぎ、資金や物資、情報がこども食堂に届くよう橋渡しする「支援の支援」を担う。
この成長の背後には、むすびえの一貫した「見えにくい活動を社会に可視化する」姿勢がある。現場の声を集め、調査や提言を通じ制度や世論形成に働きかけることで、中間支援の仕組みそのものの価値を広げてきた。むすびえは、支援の「もの/お金、情報、気持ち」がこども食堂に確実かつスムーズに届く社会の土壌づくりに取り組んでいる。そのために、全国から寄せられる寄付金や物資を必要なところに配分・仲介するだけでなく、制度設計や広報、協働の仕組みづくりを支えてきた。実際、むすびえ運営費の8〜9割は企業や個人からの共感ベースの寄付によって成り立ち、この“共感の循環”が組織の中核を支えている。
中間支援の役割は必ずしも目に見えやすいものではない。むすびえ自らこども食堂を運営するのではないため、その存在は背後にまわりやすい。しかし実際には、表に出にくい役割だからこそ地域の団体をつなぎ、寄付や物資を仲介し、制度や企業協働を支える基盤として機能している。さらにむすびえは、政策提言や調査研究、メディアを通じた社会への幅広い発信を通じて、こども食堂を「一部の支援」ではなく「社会のあたりまえ」のインフラとして根付かせようとしている。その結果、行政・企業・市民が協働する持続可能な支援モデルが各地で生まれつつあり、「共助の文化」を育む動きも広まっている。
こども食堂の広まりは単なる福祉活動にとどまらず、日本社会における新しい公共の形を示していて、その背後には現場を支えるむすびえのような中間支援の存在がある。目立つことはなくても確かに機能する仕組みとして、むすびえはこれからも地域と社会を結び続け、誰も取りこぼさない社会を実現するため、活動を続けていく。
【 課題 】
コロナ禍による活動制限と支援ニーズが同時に拡大
コロナ禍で対面での活動が難しくなり、こども食堂は「三密」になりやすく活動に制約が生じた。会食形式ではなく、食材や弁当配布、徹底した衛生管理のための費用増も重なり、運営者の負担は急増。一方で、家庭の孤立や経済的困窮が深刻化し、安心して誰かとつながる場=「居場所」としてのこども食堂の重要性はむしろ増していた。食堂の継続と拡充を両立させる新たな支援のあり方が求められていた。
【 対応 】
従来の物資中心の支援から資金の助成を開始
2020年4月、コロナ禍で困難を深める現場を支えるため「こども食堂基金」を創設。寄付を原資にしたこども食堂や地域ネットワーク団体への資金助成を開始した。従来の物資支援に加え、柔軟な資金提供で各地の支援活動を後押しし、あわせて申請や報告を支える支援スキームも整備。地域ネットワーク団体との連携体制も強化した。
【 結果 】
制度と地域とをつなぐ共助インフラに進化
むすびえの役割は、物資提供が軸の「支援の支援」から、資金分配・制度接続を含む支援基盤の構築へ拡張。寄付を通じた年間助成額は総額約7億円にのぼり、多くの現場の活動継続と質的向上に寄与してきた。こども家庭庁の設立を機に自治体との協働も進み、子どもの居場所づくりの指針策定や政策形成支援にも参画。地域の実情と制度をつなぐ担い手として共助のインフラの一翼を担う存在に。
AFTER: 2025年時点
神山まるごと高専
BEFORE: 2023年時点
19年ぶりに新設された高専は画期的試みだらけ!
近年、日本の地方創生や人材育成の文脈において、地域資源を活かした新しい教育モデルへの期待が高まっている。特に少子化や都市部への人口流出により、地方で学びの場を確保し、地域から世界へと羽ばたく人材を育てることは喫緊の課題である。こうした背景のもと、徳島県神山町に2023年4月に開校した私立高等専門学校「神山まるごと高専」が注目を集めている。高等専門学校(高専)は、実践的技術者の養成を目的とした5年制の高等教育機関で、新設は19年ぶりとなる。
神山まるごと高専が目指すのは「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成。言い換えるなら、単に知識や技能の習得だけでなく、それらを活用して新たな価値を社会に実装する能力を重視しているのだ。
同校の開校・運営は、さまざまな形の支援によって支えられている。クラウドファンディングによる資金調達、専門知識を無償提供するプロボノ参画、物品やサービスの寄付、授業提供など、個人や企業がさまざまな関わり方でパートナーとなっている。
特に注目すべきは、学費無償化を可能にするために設立された奨学金基金。この基金に拠出する企業は「スカラーシップパートナー」と呼ばれ、その仕組みは日本初の試みとして高い関心を集めている。運営法人である神山学園は、日本を代表する大企業11社から合計100億円超の拠出・寄付を受け、「神山まるごと奨学金基金」を立ち上げた。
この基金は単なる資金の積み立てではなく、投資会社に運用を委託し、その運用益を学校に寄付する仕組みを採用している。これにより、元本を減らすことなく、運用益のみで在学生全員の学費をまかなう持続可能な仕組みとなっている。学生は一度学費を納入するものの、給付型奨学金として同額が支給されるため、実質的な負担はゼロだ。
さらに、学生は全寮制の寮で学び、寮費についても世帯収入に応じて減額される制度が整備されている。これにより、経済的な背景に左右されず、全国から意欲ある学生が集まる環境が実現している。このような学費・生活費支援の仕組みは、地方創生と教育機会の平等化の両面で先進的なモデルといえよう。
神山まるごと高専にとって、奨学金基金など企業とのパートナーシップは単なる資金支援にとどまらず、教育の質と継続性を担保する基盤だ。資金の持続的な運用と社会的支援ネットワークの構築で、経済状況に左右されない学びの場が実現しつつある。同校は地域発の教育機関として、今後も全国や世界のモデルケースとなり得る可能性を秘めている。
【 課題 】
学生の好奇心は広がる一方で、学校のリソースは限定的
入学後、学生たちは授業外でも幅広い分野に挑戦するようになった。一般的な高校であれば教員が顧問として課外活動を支えるが、神山まるごと高専では、学生の好奇心・関心が多岐にわたり、校内スタッフだけではすべてに対応することには限界があった。
【 対応 】
企業や地域と連携した学びの機会拡大
奨学金基金に参画するスカラーシップパートナー(11社)が、学生の関心に応じた実践機会を提供。ほかにも新製品開発やデザインプロジェクトへの参画、物品の提供などさまざまな支援を行うパートナー企業もある。さらに地域住民も加わり、農業体験や商店をテーマにした授業など学校外での学びの場が拡張した。
【 結果 】
学校と外部のパートナーが継続的に関与する体制へ
学校の教育活動を学校スタッフのみが担うのではなく、学生たちの興味、関心に応じた人をつなげることで社会全体が未来世代の教育に関わることができる。そのハブに「神山まるごと高専」がなりつつあり、学生の学びの成果は地域や支援者にも還元されつつある。
AFTER: 2025年時点
配車頭
BEFORE: 2021年時点
産業廃棄物業界の事業効率を大きく改善
日本ではいま、多くの産業で人手不足が深刻化しているが、産業廃棄物業界は特に厳しい状況にある。廃棄物の収集運搬は社会に欠かせない仕事である一方、業界のイメージや労働環境の厳しさから新たな担い手が集まりにくい。その結果、限られた人員で膨大かつ複雑な業務をまわさなければならない現場が増えている。特に負担が大きいのが、毎日の回収ルートや担当者を決める「配車計画」の業務だ。
配車計画は単純なルート作成ではない。ドライバーごとの、免許や経験、車両の種類とコンテナの組み合わせ、排出場の位置や訪問順序、処分場の稼働状況など、多くの条件を同時に考慮しなければならない。従来は配車担当が電話や紙の資料を使い、経験と勘に頼って計画を組み立てていた。しかし、この業務は属人化しやすく、長時間を要し、担当者の精神的負荷も大きかった。
この課題を解決するためにファンファーレ株式会社が開発したのが、産廃業界に特化したAI配車計画システム「配車頭」。この配車頭は独自のアルゴリズムで条件を一括処理し、効率的かつ実用的な配車計画を数分で自動作成する。作成された計画はスマートフォンを通じてドライバーに即座に共有でき、現場との情報連携もスムーズになる。
導入事例の中には、従来7時間以上もかかった業務がわずか数分に短縮され、配車効率が向上したことで受注数や売上が増加したケースもある。また、経験の浅い社員でも高品質な計画を作成できるようになり、ベテラン不足という構造的課題にも対応できるようになった。限られた人員で、より多くの案件を処理できるため、業務全体の生産性向上にも直結している。
配車頭の特徴は、単なる効率化ツールにとどまらない点にある。配車という最初の工程をデジタル化することで、その後の収集、運搬、処分などプロセス全体の最適化やデータ活用が可能に。さらに、導入後のサポートにも力を入れ、現場が確実に使いこなせる環境を整備している。この姿勢が現場の信頼を生み、全国各地の事業者に採用が広がっている。
また、AIが業務を肩代わりすることで担当者の負担が軽減され、長時間労働や精神的ストレスの軽減につながるなど、社会的意義も大きい。ある企業では、配車業務から解放された社員がドライバーとして現場に復帰し、人材活用の幅が広がった例もあったが、こうした変化は労働環境の改善と人材不足解消の両面に効果をもたらす。
配車頭は、産廃業界が抱えていた長年の課題に正面から向き合い、現場のあり方そのものを変えつつある。効率化と働きやすさを両立させるその仕組みは、これからのこの業界に新しい標準をもたらしていくはずだ。
【 課題 】
既存システムとの連携が課題に
産廃処理事業者にとって、「配車頭」によって配車の利便性は劇的に向上したものの、既存の基幹システムとの連携が課題となっていた。それぞれのシステムで、同じ情報の二重入力が発生していたからだ。
【 対応 】
産廃業界に特化した新たな基幹システムを開発
その構造を変えるため、既存の基幹システムとの連携開発を進めるのと同時に、自社でも産廃業界に特化した基幹システム「稼ぎ頭」を開発。これにより、配車頭とシームレスに連携できる環境を整備し、導入時の障壁を大幅に低減した。配車計画から受発注・請求までを一貫して管理できるようになり、業務全体のDX推進を加速させた。
【 結果 】
産廃業務の可視化がを業界DXの起点に
経験や勘に頼っていた配車や販売管理まわりの業務が整理され、対応履歴や処理内容がデータとして蓄積されるようになった。業務の属人化やバラつきが減り、見えづらかった日常オペレーションの全体像が可視化されはじめている。こうした動きが、業界全体のDXに向けた現場発の変化として注目されつつある。
AFTER: 2025年時点
CLOUDY
BEFORE: 2020年時点
寄付ではなく売上で学校を支える仕組みをつくった
アフリカ諸国では、教育環境の改善を目的に多くの学校が建設されてきたが、「建てた後の運営」を支える仕組みが欠けていた。特に、学校運営費の大半を占める教員給与を誰が負担するのかが常に課題となっていて、外部からの寄付に頼るだけでは持続的な教育提供が難しい状況が続いていた。
また、教育を受けても地域内での雇用機会が少なく、最難関大学を卒業しても就職率が3割程度にとどまるなど、学びが生活や成長に結びつかない現実があった。こうした背景から、教育と雇用を結びつけ、地域が自ら資金を循環させる仕組みが求められていた。
この課題に正面から向き合うため、2010年にNPO法人CLOUDYが設立され、アフリカでの学校建設を開始した。初期段階では、国内外からの寄付を主な財源として学校を建設・運営していたが、寄付に依存する構造では安定的な運営が難しいという課題に直面した。
これを解決すべく、2015年に営利法人として株式会社DOYAが設立され、アパレルブランド「CLOUDY」が立ち上がった。ここで設定された「売上の10%をNPOにまわす」というルールは、社会貢献の一部としてではなく、事業の仕組みの中に社会的な還元を組み込むものだった。これは、経営上のリスクを引き受けつつも、教育の持続性を第一に据えるという意思の表れだった。
この仕組みにより、アパレル事業で得た収益が学校運営の財源となり、教育を持続的に提供できる構造が生まれた。NPO法 人CLOUDYはガーナを中心に学校建設を進め、事業収益の一部が校舎建設や学習環境の整備、教材の供給に充てられる仕組みを確立。外部からの一時的な援助に頼らず、地域内で教育を継続できる仕組みが機能している。
学校は設計段階から、公立化を前提に当該国の政府が教員給与などの主要な運営費を担う体制を導入。加えて、校内に教員住宅や畑を併設し、教員の定着と給食の自給を支える仕組みを整えている。農業プロジェクトには専門機関が技術協力し、教育・行政・産業が連携して運営を支える構造となった。寄付に依存しない持続的な教育モデルとして、地域に定着しているのだ。
【 課題 】
学校での学びが卒業後の仕事につながりにくい
現地で学校を建て、学びの場をつくっても、学んだ先に安定した就労や成長の道筋が見えにくかった。教育で得た力が地域内で活かされず、生活基盤や夢の両面で「断絶」が生じていたのだ。この断絶を解消し、学び・就労・スキル発揮・次世代育成が循環する仕組みを設計する必要があると考えた。
【 対応 】
「学び」の先に、働く場と表現の機会を広げた
CLOUDYは、学んだ人が自分の力を活かして働ける場所や、表現できる機会を現地の人々と共につくってきた。ガーナでは、理髪を学ぶための専門学校が公立専門学校として正式に登録され、地域で職業を身につけられる環境が整った。また、デザインや写真の専門コースを設け、学びが商品の企画やデザインに活かされるようにした。さらに、現地の素材や技術を活かした商品開発を企業と共に進め、卒業生がものづくりや発信の場に関われるようにした。
【 結果 】
学びが仕事になり、仕事が次の学びを生む
この取り組みで、教育の成果が “働く力”や“創る力”として地域に還元される循環が生まれた。現地では、学んだ若者がデザイナーや職人として実際の生産に関わり、新しい価値を生み出している。こうした動きは、コロナ禍を経て「社会的意義のある購買」へと意識を向ける人々の流れにも支えられている。さらに、新ブランド「THE UNIVERSITY.」を立ち上げ、「架空の大学」がコンセプトのこのブランドは、売上の3%を学校建設に循環させる仕組みを構築。将来的にはガーナに大学を設立し、学びと仕事の循環を広げていくことを目指している。
AFTER: 2025年時点
ジーバー FOOD
BEFORE: 2022年時点
“高齢者が支えられる側”という前提をくつがえす、地域の主役再生モデル
超高齢社会の進展と共に、「高齢者の孤立」「地域のつながりの希薄化」「飲食業界の人手不足」といった複合的な社会課題が全国各地で深刻化している。そうした中で、仙台発のユニークな取り組みとして注目を集めているのが、2022年に誕生した「ジーバー FOOD」だ。これは「シニア×食×地域活性」を軸とした新たなフードビジネスで、弁当づくりや食堂運営、飲食店の仕込み業務などを通じて、シニアの就労機会を創出すると同時に、地域の食課題と飲食業界の人手不足の解消にも貢献している。
展開するのは4つのサービス。第一弾は、地元企業や仙台駅で販売される手づくり弁当。続いて、企業向け社員食堂の運営、地域住民が集う「街仲食堂」での温かな食事提供、そして、飲食店の仕込みを担う「本当においしい応援隊」が加わり、地域にシニアの活躍の場が次々と広がっている。
この取り組みを支えるのは「組合」の仕組みだ。各地域の拠点は組合として運営され、実際に働くシニア自身が現場の主役となる。本部である株式会社ジーバーは、運営ノウハウや経理、マーケティング支援を提供し、売上の10~25%をサポート費として受け取る。店舗の賃料もこの費用に含まれるため、実質的には低コストで運営可能。共感と社会性に支えられたこのモデルには、地域の大家さんや企業の理解・協力も不可欠な要素となっている。
特徴的なのは、報酬が時給制ではなく利益分配型である点だ。雇用ではなく「組合員」として関わることで、体力や時間に制約のあるシニアでも、自分のペースや得意分野に合わせて無理なく働くことができる。業務は役割分担と助け合いを前提としており、自然なコミュニティの中で、働くことそのものが生きがいや心の活力につながっている。
事業は急拡大中で、現在200人以上のシニアが参加し、宮城県内に複数拠点を展開。テレビでの特集やSDGsジャパンスカラシップ岩佐賞の受賞など社会的評価も集まっており、現在16都道府県で導入検討が進行中だ。今後は全国1889市区町村への展開を視野に入れ、「街仲食堂」が日本全国の街角に点在する未来を描いている。
高齢者を「支えられる側」ではなく「支える側」として再定義したこのビジネスモデルは、超高齢社会における新しい可能性を提示している。シニアの知恵と経験、そして手づくりのぬくもりを活かし、食と会話を通じて地域の心と体を支える。これは単なる成功モデルではなく、心にじんわりと沁みる社会変革の兆しなのだ。
また、地域との結びつきも強く、農家の余剰野菜を活用したレシピや、保育園・学童と連携した多世代交流など、食を起点とした“つながり”が随所に生まれている。ジーバー FOODは、高齢化を課題ではなく資源ととらえ、地域を再構築する挑戦そのものでもある。
【 課題 】
稼ぎたい人と生きがいを求める人が混在し、現場が混乱
ジーバーFOODが開催した「おしごと説明会」には多くの募集があったが、報酬を得たい人と生きがいを求める人の両方が集まり、働く目的の違いから現場での軋轢が発生。これまでの調理経験や味覚の違いによるこだわりから対立が起き、人間関係がギクシャクする事態も。さらに「美味しさ」に対する基準が人によって異なり、サービスの品質にもバラつきが見られた。
【 対応 】
働く目的を「生きがい重視」とし、採用・調理ルールを再設計
シニア同士の対立や価値観のずれを避けるため、働く目的を「生きがい重視」と明示し、採用段階から動機のすり合わせを徹底した。説明会では報酬よりも人とのつながりを重視する姿勢を確認し、金銭目的の応募者は自然にふるい落とされる設計に。あわせて、調理現場では味付けや工程を標準化し、こだわりの衝突を回避。安定した関係性と品質を両立できる体制を整えた。
【 結果 】
安定した現場運営が品質向上と事業拡張を後押し
「生きがい重視」の価値観に合う人が集まり、現場の人間関係が安定。業務ルールの標準化で味の品質やオペレーションも向上した。現場の余白や心の余裕が生まれたことで、「ジーバーFARM」のように農業に展開したり、地域に事業を生みつつ世代を超えたコミュニティ育成と人々のつながりを育む新たな挑戦への足がかりも生まれている。
AFTER: 2025年時点
SEKAI HOTEL
BEFORE: 2017年時点
地方の空き家と空きテナントがホテルとなり、街の日常に
都市部への人口集中が続く一方で、多くの地方では過疎化が進み、住めなくなった家屋や使われなくなった商店が増え続けている。放置された建物は老朽化が進み、景観や防災面でリスクとなるだけでなく、地域全体の活気を失わせる要因にもなる。空き家問題は、いまや全国的な社会課題だが、従来は大規模な観光施設や公共整備による解決策が中心で、日常的な地域資源を活かす仕組みに乏しかった。
この問題に「旅」という視点から挑んだのが、2017年にはじまった「SEKAI HOTEL」である。コンセプトは「街全体を一つのホテルに見立てる」こと。空き家や空きテナントをリノベーションして客室とし、飲食は地元の食堂、入浴は昔ながらの銭湯といった具合に、既存の街の営みをホテルの機能に置き換える。観光地化された非日常ではなく、地域 の「日常」そのものを旅の価値として提示した。
宿泊者は、観光ガイドには載らない場所を訪ね、地元の人とやり取りする中で、単なる観光客ではなく「町の一員」として受け入れられる感覚を覚える。商店街の食堂での夕食や銭湯での入浴は、地域住民にとって日常の一部だが、宿泊者にとってはかけがえのない体験となる。旅先での特別さと、そこで暮らす人々のあたりまえの時間が交差する瞬間こそが、SEKAI HOTELがつくり出す独自の魅力だ。
さらに、宿泊料金の一部を地域に還元する仕組みも導入した。宿泊客1人あたり200円を積み立て、地域の子ども向けイベントや祭りの運営費への寄付などに充てることで、宿泊そのものが「地域の未来に投資する行為」となる。この仕組みは、旅行者が単なる消費者として滞在するのではなく、地域の担い手と一緒に未来をつくる立場になれることを示した点で、ほかに類を見ないユニークさを持つ。
SEKAI HOTELの取り組みは、空き家の利活用という不動産的課題を超えて、地域の人々と宿泊者の交流を自然に促し、新しい経済循環を生み出している。外部からの人の流れが途絶えがちな地域に、観光という、言葉では語りきれない「関係人口」を増やす効果を持ち、街全体に新たな活力をもたらしている。
同社が目指しているのは、「旅先で出合う地域の日常を味わえる」ことを、特別な体験ではなくあたりまえにする社会だ。観光地ではない場所の魅力を再発見し、そこに暮らす人と訪れる人の関係を再構築する。こうした試みを積み重ねることで、空き家問題に対する持続可能な解決策となるだけでなく、地域社会そのものを元気にする新しい街づくりの形を提示している。
【 課題 】
宿泊体験の価値が伝わらず、資金や地域協力の壁も
創業時から「街全体をホテルに見立てる」という発想はあったが、宿泊客には、「安いから泊まる」「とりあえず泊まれる」といった一般的なホテル利用と同じ動機で選ばれることも多く、本来の魅力である「地域の日常を味わう体験」が十分に伝わっていなかった。加えて、古い建物のリノベーションは銀行融資を受けにくく、資金調達のハードルも高い。地域の人々を巻き込みながら仕組みを根付かせるまでには課題が多かった。
【 対応 】
地域店舗の関与を深めることで、宿泊体験そのものが進化
当初は宿泊客を飲食店や銭湯に案内する程度だったが、やがて飲食店が宿泊客専用のコースメニューを用意するなど、宿泊体験に直接関与する仕組みへと発展。また「太鼓判カード」を通じ、店主自身が地域の魅力を紹介することで、観光ガイドでは得られない交流体験を生み出した。資金面では、不動産投資家や地主の与信を活用して銀行融資を受ける独自スキームを築き、空き家再生のハードルを下げた。
【 結果 】
街全体で日常を共有する宿泊体験が確立した
従来のホテルのように施設内で完結するのではなく、地域住民の日常に入り込む体験が宿泊の核となり、旅行者は「街の一員」として受け入れられる感覚を得られるようになった。宿泊料金の一部を地域イベントに還元する仕組みもあいまって、旅行者が消費者であるだけでなく「地域の未来を共につくる担い手」となる構造が定着した。結果としてSEKAI HOTELは空き家問題の解決を超え、地域に新たな経済循環と関係人口を生み出す持続可能なモデルを築きはじめている。
AFTER: 2025年時点
宇宙水道局
BEFORE: 2023年時点
見えない漏水を衛星データとAIで「見える化」する
日本の水道管は老朽化が進み、全国の自治体が運営する水道局では漏水や断水、水質の低下といった問題が深刻化している。漏水が増えると水が大量に失われ、水道事業の収入も減る。断水が起これば住民の生活に直結し、水質が悪化すれば健康への不安も広がる。
水道管点検は、作業員が水道管沿いを歩き、音や振動を頼りに漏水を探す方法が主流だ。これまでは人間の経験をもとに調査をしていたため、時間も費用もかかり、すべての水道管を調べるのは現実的ではなかった。こうした課題を解決するために、株式会社天地人は、衛星データとAIを活用した漏水リスク診断システム「宇宙水道局」を開発。水道管の老朽化リスクを効率よく見つけられるようにし、水道インフラが次世代に受け継がれることを目指している。
天地人は2019年に設立された。JAXAで人工衛星開発に携わっていた百束泰俊氏と、地上データを使ったビジネスを進めていた櫻庭康人氏が出会い、宇宙のデータを社会課題の解決に活かすことを目指して会社を立ち上げた。創業当初は、衛星データや地理情報、独自のアルゴリズムを組み合わせたWebサービス「天地人コンパス」を開発。農業や土地評価などに活用され、たとえば衛星の気象データと農家が持つ水田情報を組み合わせ、米の栽培に適した土地を選定するといった成果を上げてきた。
初期の天地人は200を超える顧客ニーズのヒアリングを行い、農業、防災、気候変動など幅広い分野で可能性を探った。その中で、ある水道局から「地下の漏水を見つけてほしい」と依頼があったことを転機に社会インフラに注力し、2023年に正式サービスとして提供開始。水道局が持つ水道管の位置や材質、敷設年度、過去の漏水記録に加え、地形や地質のデータ、衛星から得られる地表面温度や地盤の動きなどをまとめ てAIで分析し、漏水リスクを地図上にわかりやすく表示できるようになった。
解析結果は100m四方の区画ごとに5段階で色分けされ、水道局はリスクの高い場所を見つけることができる。実証実験では豊田市上下水道局と協力し、診断で高リスクとされた249区域を調査。そのうち77か所で漏水を確認した。従来の方法に比べ、点検費用は最大65%、調査期間は最大85%短縮できることが示され、この成果は第7回インフラメンテナンス大賞で厚生労働大臣賞を受賞するなど高く評価されている。
宇宙水道局は、老朽化が進む水道管のリスクを効率的かつ正確に見える化し、住民の安心・安全な暮らしを支える新しい仕組みとして注目されている。これは、宇宙と地上のデータを組み合わせ、社会インフラを守る方法を示す先進的な取り組みである。
【 課題 】
漏水発生後に直すのでは事故を防げない
埼玉県八潮市で、老朽化した下水管が破損して道路陥没や交通障害が発生したことなどもあり、これまでのように「漏水してから修繕する」事後対応型のやり方では大きな事故を未然に防ぐことはできないという認識が広まった。しかも、限られた予算の中ですべての配管を更新するのは難しく、水道局は「どこを優先して直すか」という判断を迫られていた。
【 対応 】
“損傷確率”と“影響度”の分析から、優先して直す所を可視化
水道管の状態を評価する新たな仕組みとして、水道管の損傷確率に加え、破損した場合に病院や避難所などの重要な施設へ与える影響度も分析対象に加えた。危険度と社会的影響の両面から評価することで、修繕すべき場所とその優先度を提言できるようにしたのだ。さらに、企業や研究機関との協力を進め、解析の精度を高めている。
【 結果 】
宇宙のデータが切り拓く新しい官民共創の形
累計の契約自治体数が50を超え、従来の「事後対応型」から事故を防ぐ「予防型」への変化がはじまっている。そして、国や民間企業とも連携し、漏水リスクの診断や修繕、更新などの優先順位付けを支える仕組みへと発展している。さらに、自社衛星の打ち上げも計画されており、将来的にはガス管や電力、通信のケーブルなどインフラ全般への拡張も見据えている。
AFTER: 2025年時点
シーベジタブル
BEFORE: 2016年時点
失われていく海藻を救い、海藻の食文化を未来へとつないでいく
近年、日本の海では温暖化による海水温の上昇や海流の変化、さらに沿岸開発などが重なり、かつて豊かに広がっていた海藻の生息地が急速に失われている。海藻が減ると収穫量が落ちるだけでなく、そこをすみかとする魚や貝も減り、海の生態系全体が弱ってしまう。
その影響は食卓にもおよんでいる。四国地方で盛んに生産されていたすじ青のりは現在では不作が続き、生産量が激減。かつて地域を支えてきた産業が衰退の危機に立たされていた。
この課題に挑んだのが、海藻の研究を続けてきた蜂谷潤氏である。蜂谷氏は「地下海水」を利用した世界初の陸上栽培技術を開発。地下からくみ上げる海水は清らかで不純物が少なく、年間を通して温度が安定しているため海藻栽培にとても適している。やがて、この技術に目をとめた食品メーカーからすじ青のり生産の依頼があり、事業化の知見を持つ友廣裕一氏と共に、2016年に「シーベジタブル」を設立した。
シーベジタブルは、日本でも珍しい、海藻の研究から栽培、加工、商品開発、販売までを一貫して担うベンチャー企業である。独自の技術を基盤に、料理人や企業との共創を通じて、海藻を「伝統的な食材」から「新しい食材」へと変えてきた。
現在は高知、三重、愛媛、熊本などに拠点を展開、巨大な円形水槽に地下海水を満たし、太陽光を利用して海藻を育てている。海の環境に左右されず通年で安定生産できることが大きな特徴で、事業化初期には食品メーカーと5年間の長期契約を結び、その前払金を設備投資にまわしてリスクを抑えつつ安定した体制を築いた点もユニークだ。
育てた海藻は原料供給にとどまらず、商品化を通じて新しい価値を生み出している。東京に設置した「SEAVEGE-Kitchen Lab」では、社内の料理人が新しいレシピを次々と開発。和食や洋食だけでなく、パンやスイーツにも活用され、ミシュラン3つ星レストランで提供されたり、大手コンビニの商品に採用されたり、国際的な展示会でも発表されている。海藻はいまや、身近で魅力的な食材へと姿を変えつつあるのだ。
だが、同社が目指しているのは単なる食ビジネスの拡大ではない。地域で失われつつある海藻に着目し、陸上栽培によってすじ青のりの安定供給を実現することで、食の可能性と地域産業の再生を両立させようとしているのだ。海藻を持続可能な形で社会に活かしながら、人と海と地域をつなぎ直す。シーベジタブルはその先駆けとして、食の未来に向けた挑戦を続けている。
【 課題 】
海藻の陸上栽培だけでは届かない海の課題
地下海水を活用した陸上栽培により、海藻の安定供給が実現できた。しかし、磯焼けの進行で藻場が失われ、海の生態系は深刻なダメージを受けていた。さらに漁業者の高齢化や担い手不足が進み、地域の水産業は縮小傾向に。陸上栽培だけでは、海の環境を回復させるのも地域に新たな雇用を生み出すのも難しく、より広い社会的課題に応えるには限界があった。
【 対応 】
海を豊かにするために海面栽培を開始
こうした課題に応えるため、シーベジタブルは海藻の生産を海面にも広げることを決断。海の環境改善と地域の雇用創出を両立するには、海そのものを舞台にした取り組みが不可欠だった。漁業権を持つ各地の漁師と連携し、栽培面積を拡大しながら“養殖藻場”の醸成に取り組んできた。藻場は“海のゆりかご”とも呼ばれ、魚や貝などの命を育む場。海藻を育てることは、海の生態系の回復だけでなく、漁師の新たな仕事づくりにもつながっている。
【 結果 】
海の豊かさをさらに支える、持続可能な社会モデルへ
海面栽培によって水質浄化や生物多様性の回復が進み、漁業者には新たな収入源が生まれている。さらに、企業参加型の共創プログラムを立ち上げ、代替タンパク質やバイオマテリアルなど食品以外の用途でも協業を推進。加えて、創業時より海藻の新しい食べ方を提案し、食文化の広がりにも力を注いできた。シーベジタブルは単なる海藻の生産にとどまらず、持続可能な食文化と環境再生を同時に進める新しい社会モデルへと進化を続けている。
AFTER: 2025年時点
Be My Eyes
BEFORE: 2018年時点
「困り事」を持つ視覚障害者とボランティアをつなぐプラットフォーム
世界では、視力に何らかの制約を抱える人が約22億人いるとされ、日常生活や情報取得に困難を抱える人は決して少なくない。社会の制度や昨今のIT機器の機能・アプリなどによる支援はあるものの、情報は断片的で即時性や柔軟性に欠け、どうしても「人との対話」に頼らざるを得ない現状がある。しかし、その人的サポートは常に十分ではなく、必要なときに必要な支援が届かないという限界が存在している。
「Be My Eyes」は、視覚に障害のある人と、世界中の目が見えるボランティアをつなぐスマートフォンアプリとして2015年に登場した。アプリを通じて、視覚障害者がスマホのビデオ通話を使いながら「いま目の前で起きていること」をボランティアに伝え、その場で支援を受けられるという仕組みだ。
たとえば、郵便物の差出人や中身の確認、服の色合わせ、期限切れの食品チェックなど、日常生活のちょっとした「困り事」を助けてもらうことができる。特徴的なのは、これが世界中どこでも無料で使えるという点で、アプリを開いて「助けてほしい」とボタンを押すだけで、すぐにどこかのボランティアが応答してくれるという、非常にシンプルかつ温かみのあるサービスになっている。
サービスの中核は、視覚障害者が「見たいこと」をスマホのカメラで映し、その映像をもとに、ボランティアが状況を音声で説明するというライブ通話機能にある。ボランティアはあらかじめ登録しておき、誰かからのサポート依頼が届くとアプリを通じて呼び出される。そして、それに応答すればビデオ通話がはじまり、あとは映像を見ながら必要な情報を伝えるだけとなり、手軽に誰かの役に立てる仕組みとしても注目されている。支援は無償だが、双方の満足度が高く、テクノロジーを介したマイクロボランティアの成功例としても知られている。
興味深いのは、このサービスが、視覚障害者からはお金を取らずにビジネスとして成立しているという点だ。Be My Eyesは、企業向けの有償サービスを展開しており、MicrosoftやGoogleを含む企業との提携を通じて事業を成立させている。その提携によって、企業側はBe MyEyesのアプリ内にカスタマーサポート窓口を設け、視覚に障害のある顧客からのサービスに関する問い合わせにビデオ通話で対応することができる。また、視覚に障害のある従業員向けのサポートとして、Be My Eyesのソフトウェアを利用することも可能。そして、これらのサービスを利用することで、企業側は視覚障害に対するアクセシビリティ対応の質を高めることができるとして、より一層注目されている。
【 課題 】
利用のシチュエーションは多数だが、即時性に限界も
「困り事」の解決を人とのビデオ通話に頼っていたのは、これまでの画像認識の精度では、目の前にあるものだけしか教えてくれず、読み上げソフトは、ウェブページやアプリを一語一語読み上げることしかできず、必要な情報を短時間で効率的に得るには「人との対話」が不可欠だったためだ。しかし、多数のボランティアが登録していても、必ず即座に応答があるとは限らない。対話型の支援は、どうしても即時性に限界があった。
【 対応 】
人の力にAIの即時性を重ね、サービスをアップデート
Be My Eyesは、ChatGPTのAIを搭載した「Be My AI」を導入し、ユーザーが撮影した画像を即時解析し音声で状況を説明できる新しい支援手段を提供した。さらに、2025年には外部AI企業との連携でオンラインショッピング機能を実装し、検索から注文までを音声で完結可能に。こうして、人力支援に加えてAIの力を組み合わせることで即時性が高まり、支援の範囲はこれまで届かなかった生活領域へと拡大している。
【 結果 】
必要なとき必要な情報・モノを提供する
人間との対話による支援には、どうしても言語の壁・時間の壁などがあった。これまでボランティア人口を増やしていくことでしかできなかった支援体制を、いつでも稼働できて対話可能なAIを用いることで飛躍的に拡充した。これまでのシステムのように、サービスを支える数多くのボランティアによる支援と、対話可能なAIによる補助の共存で、時間・場所を問わず、「困り事」に応じた柔軟なサポート体制が可能になりつつある。
AFTER: 2025年時点
Alife Holdings
BEFORE: 2021年時点
家賃に体験を組み込み、暮らしをデザインする賃貸モデル
台湾ではここ数年、不動産価格の高騰が続き、家を買うのが難しい若い世代が増えている。台北市では住宅価格が平均年収の十数倍に達し、家賃も上昇の一途をたどっている。多くの人が月収の大部分を住居費に充てざるを得ない状況の中で、「どうせ高い家賃を払うなら、暮らしの質にも価値を求めたい」という考え方が広まり、住まいを単なる部屋ではなく、生活の質を左右するサービスや体験の場としてとらえる意識が強まっていった。しかし、従来の不動産業は「部屋を貸すだけ」の仕組みにとどまり、こうした新しい価値観には十分に応えられていなかった。
この状況に対して、「Alife Holdings」は住まいそのものを体験の基盤として設計し直す発想から生まれた。都市計画やブランドデザインなどを手がけてきた企画会社Plan bのチームが、そのノウハウを活かして2020年に立ち上げたのが、Alife Holdings Co., Ltd.(理想生活控股)である。従来の不動産が空間だけを提供していたのに対し、Alife Holdingsは空間と体験をセットで設計し、暮らし方そのものを提案することを目的とした。
最初の拠点となったAlife FL(士林区)やAlife WCH(台北駅近く)では、老朽化したビルをリノベーションし、家具付き住居に共有キッチン、テラス、シアタールーム、ワークスペースなどを併設。入居者同士が自然に交流できるような空間づくりが行われた。建物の1階にはカフェやドリンクスタンド、カレー店などを誘致し、入居者にはドリンク提供やサブスクリプション型の優待特典を用意。日常の中に小さな楽しみを織り込みながら、生活空間と商業空間を緩やかにつなげている。
さらに、フリーマーケットや音楽イベント、季節のパーティーなどの企画を運営側が主導し、暮らしに文化的な体験を組み込んだ。これらは単なる入居サービスではなく、日常をデザインする仕組みとして機能している。「部屋を貸す」から、「暮らしを編集する」へ。Alife Holdingsは賃貸住宅の枠を越えた新しいモデルとして注目を集めている。
料金体系にも独自の工夫がある。契約上は、家賃としてではなく、住居利用と企画サービスを一体化したパッケージ料金として設定。入居者は家具付きの部屋の利用に加え、カフェ特典やイベント参加、清掃サポートなど複数のサービスを得られる。この体験込みの家賃という考え方が、Alife Holdingsを他の賃貸と明確に差別化した。家賃をサービスと結びつける発想がまだ一般的ではなかった中、Alife Holdingsは都市生活者にとっての新しい暮らし方の象徴となっている。
【 課題 】
体験の一貫性を保つ仕組みが不足
Alife Holdingsは、外部ブランドやサービスを組み合わせながら暮らしの体験を設計するモデルとして展開してきたが、物件やテナントごとに内容が変化しやすく、体験の一貫性や継続性をどう保つかという課題を内包していた。暮らし全体をデザインするという理念を、個別の空間運営の中でどのように実装し続けるかが問われていた。
【 対応 】
資本出資によるブランドと共創体制を構築
Alife Holdingsは、外部との関係をより長期的で共創的なものにするため、テナント関係にとどまらず主要ブランドへの資本出資を進め、サービス設計に共同で関与できる体制を整えた。SUZAKU(カレー店)やPlanté(飲料ブランド)など価値観を共有するブランドと連携しながら、暮らしを構成する要素を安定的に運営する仕組みにした。さらに、入居者限定だった仕組みを外部の会員にも開き、収益の入口を増やした。
【 結果 】
住まいとサービスを統合するエコシステムへ
Alife Holdingsは不動産運営にとどまらず、飲食や文化活動を担う生活ブランドや店舗への出資を通じて、空間と体験を一体で設計する仕組みを築いている。入居者だけでなく外部の会員も参加することで、人や体験が街と住まいのあいだを行き来し、暮らしの価値が循環する構造が生まれつつある。住まいを単なる居住空間ではなく、文化や経済をつなぐ生活基盤として再定義し、理念として掲げてきた「暮らし全体をデザインする」という構想が、現実の仕組みとして形になりはじめている。
AFTER: 2025年時点
KOTO
BEFORE: 2000年時点
事業収益と寄付で運営する全寮制ホスピタリティ職業訓練プログラム
ベトナムの急速な経済発展の陰で、家庭環境や経済的な事情により学校に通えず、路上で生活せざるを得ない若者が少なくなかった1990年代末。都市化と格差拡大の中、親を亡くしたり家庭の支えを失った若者たちは、生計を立てるために物売りや雑用などの不安定な仕事に就かざるを得なかった。社会保障や教育制度の仕組みが届きにくく、基礎教育や職業訓練を受ける機会も限られ、安定した仕事に就くことや未来を描くことが難しい状況にあった。
そうした境遇にいた若者たちに、学ぶ機会と自立への力を届けたいとの思いから、オーストラリア育ちのベトナム系社会起業家ジミー・ファム氏は1999年、ハノイに小さなサンドイッチ店を開く。路上の若者に、実践を通じたトレーニングと支援を行い、自らの手で未来を切り拓くきっかけをつくったことが「KOTO」の原点だった。KOTOという名前には「Know One, Teach One (一人に出会ったら、一つ何かを教える) 」という理念が込められ、学びの連鎖を通じ、困難な状況にある若者たちが次の誰かを支える存在に成長していくことを目指している。
この取り組みはやがて、ホスピタリティ業界に特化した、全寮制2年間の職業訓練プログラムへと発展。ホテルやレストランといった現場で必要なスキルのトレーニングを中核に据えつつ、英語やIT、金融リテラシーに加え、ライフスキルやメンタルヘルス、コミュニケーション力の育成といった内容にも力を入れたものとなっている。
KOTOでは、年間150人前後の若者が無償で教育・住居・食事を得ることができ、卒業時には国際的に認定された資格を取得。卒業後の就職率はほぼ100%に達し、多くがホテルやレストランで安定した収入とキャリアの機会を得ている。
プログラムの費用は、飲食業を中心とする社会的企業(レストランやケータリングサービス)の運営による事業収益と、企業・個人・財団からの寄付や助成金の組み合わせでカバーされている。特に、訓練生の実践の場でもある直営レストランはKOTOの理念を社会に発信する役割も担っており、そこを訪れる客は「Dine with Purpose(社会貢献になる食体験)」を通じて、KOTOのプログラムに参加する若者たちの人生の支援者となっているのだ。
KOTOの成長を支えてきたのは「共創関係」にあるステークホルダーたちの存在だ。もともと資金提供していた寄付者が単発支援から長期的パートナーへと支援を発展させたパターンや、資金だけでなく専門分野の知見や他の支援者の紹介をつなげたパターン、さらにはプログラムの卒業生たちがKOTO Alumni Community(KAC)のメンバーとして、現学生のメンターや卒業生の雇用主、あるいはKOTOへの寄付者として関わり続けている。こうしてKOTOは、支援・教育・雇用・消費が循環する“共創型エコシステム”を築き上げてきたのである。
【 課題 】
強い需要に応えられない成長の“天井”があった
プログラムの年間の受け入れ数は最大でも約150名にとどまり、ホスピタリティ業界からの人材ニーズに対して十分に応えられない状況が続いていた。プログラムの採用枠に対する応募者数も非常に多く、「学びたいのに入れない若者」と「採用したいのに人材が足りない企業」が共に存在するという構造的な課題に直面していた。
【 対応 】
外部との協働による共創型スケーリングへの転換
こうした課題に対し、KOTOは「自分たちだけでやる」という発想を手放し、外部の協力者と共に成長を描く方向へ舵を切る。その過程で、ベトナムを代表する大企業との出会いが生まれ、不動産提供を通じてKOTO Dream School構想が動き出した。また、KOTOは業界パートナーと共に、寄付に依存せず企業が育成費用の一部を担う共同投資モデルを構築。〈企業とのパートナーシップ・社会的企業としての収益・従来型の寄付〉という3つの柱で持続的にバランスをとる仕組みへ進化させた。
【 結果 】
Dream School を軸に描く “次の拡張”
2025年秋に正式開設された「KOTO Dream School」は、年間約300名受け入れ可能な施設で、教育・生活支援の質を保ちつつ、育成規模を一気に拡大できるようになる。さらに、従来の直営レストランに加え、キャンパス自体を収益拠点(例:クッキングクラスや企業研修)として活用する構想も進行中。今後は、寄付・自社事業・業界パートナーによる育成投資という3つの収益源のバランスをとりながら、持続的で拡張性のある支援の仕組みを目指す。
AFTER: 2025年時点
「ふかめる」チェックリスト
※noteを読んでいる方へ
ここまでで第3章が終わりです。ここまでスクロールして読んできたあなたは、ぜったいに忍耐強さがあります。誇ってほしい。これで全体の約76%の進捗です。ここまで読んでおもしろいって思ったら(もしくはスクロールして読むのつかれた・・と思ったら)、以下のリンクからお買い求めいただけます。いよいよここから最後の章です!
第4章 「ふみだす」 新たな領域・状況への挑戦
新しい価値を、新しい領域で創出する動き。これまでの延長線上にない挑戦として、ときには社会課題や制度の枠を越え、「非線形的に新たな仕組みを立ち上げている」事例を取り上げる。
よーじや
BEFORE: 2019年時点
京都の美意識を日常に届ける、時代を超えて愛される商品
京都は古くから舞台芸能や映画などの文化が盛んな土地で、化粧や装いに関わる職人技も集まっていたが、舞台化粧を扱う店や化粧道具の職人たちが華やかな装いを陰で支えている環境の中、金箔づくりに使われていた和紙が持つ、肌の余分な脂をやさしく吸い取る性質が知られるようになる。そして1920年代、映画関係者から「撮影中のテカりをどうにかしたい」という相談を受けたことをきっかけに、特殊和紙を活用した「あぶらとり紙」が誕生した。現場の課題と職人の技術が結びついたこの商品は舞台裏の実用品として重宝され、やがて日常の身だしなみ道具としても広まっていった。
「よーじや」の創業は1904年。舞台化粧などを扱う「國枝商店」としてはじまり、京都の街でも顔なじみの店として親しまれていた。創業当初の主力商品の一つである楊枝(現代の歯ブラシ)にちなんで、地元の人々から「ようじやさん」と呼ばれていたことが、現在の屋号の由来である。芸能の盛んな土地柄に支えられ、舞台関係者や一般客のあいだで信頼を積み重ねながら、化粧品や日用雑貨を扱う店として地元に定着。戦中・戦後の混乱期も文化と共に歩み、世代を超えて愛される“街の日用品店”として親しまれてきたのである。
転機が訪れたのは1990年代。テレビドラマであぶらとり紙が紹介され、「かわいい」「使える」「京都らしい」と評判を呼び、全国的な人気商品へと成長した。携帯性のよさと和のデザイン性が人々に共感され、観光客が旅の思い出と共に持ち帰る定番土産として広まっていったのだ。よーじやは、祇園や清水などの観光地に直営店を展開し、季節ごとにデザインを変える限定品や、京都の自然や文化をモチーフにしたパッケージを開発。旅行者が「京都らしさ」を感じながら手に取る体験そのものが、ブランドの魅力となっていった。
2003年には「よーじやカフェ」をオープンし、ロゴ入りのラテアートやスイーツを通じてブランドを体験できる空間を創出。観光地の喫茶文化に新しい要素を加え、店舗そのものが“写真に撮りたくなる場所”として注目を集めた。そして2010年代にはインバウンドの波が押し寄せ、よーじやも外国人旅行者に向けた多言語対応を整え、京都ブランドの象徴として知られるようになった。
こうしてよーじやは、舞台の現場で生まれた実用品から、観光客が“京都らしさ”を手に取る体験を提供するブランドへと進化した。あぶらとり紙という小さな商品に、職人の技と文化、そして時代の観光経済が交差し、地元に根差しながら京都の魅力を外向きに伝えていく。その構造こそが、長く続くよーじやの原動力となっているのだ。
【 課題 】
観光地の売上が8割を占め、地域との関係性が希薄に
京都では観光客集中による混雑やマナー問題など、いわゆるオーバーツーリズムが顕在化していた。観光の恩恵を受ける一方で市民生活への影響も大きく、観光業全体への印象が悪化。よーじやも観光地の売上が8割を占め、“観光客向けブランド”という認識が強まっていった。地元では日常的に手に取られる機会が減り、地域との関係性が希薄化。さらにコロナ禍で観光客が激減、売上が約97%減少したことで、観光依存の脆さが明確に浮かび上がった。
【 対応 】
代表交代を機に、脱・観光依存へ
2019年に5代目・國枝昂氏が代表に就任し、創業家の伝統を受け継ぎながらも新たな方向性として「脱・観光依存」を掲げ、販路を全国の百貨店やECへと拡大。スキンケアやボディケアなど日常使いできる商品の開発にも注力し、開発スピードを大幅に上げた。さらに、2025年3月には「おみやげの店」から「おなじみの店」へというコンセプトのもとリブランディング。広く認知されたロゴも60年ぶりに刷新する決断をした。
【 結果 】
“京都発ライフスタイルブランド”へ
観光客中心の構造から脱却し「みんなが喜ぶ京都にする」という新たなコーポレートスローガンのもと、暮らしに寄り添う事業へ。また、地域のスポーツチームの支援やイベント協賛などを通じて観光に支えられる企業から地域を支える企業へと役割を転換。こうした取り組みで老舗としての信頼を守りつつ、観光と地元の二項対立ではなく観光客も地元民も両方大切にしながらの持続的なブランドづくりを進めている。
AFTER: 2025年時点
バリューブックス
BEFORE: 2018年時点
値段がつかない古本に価値を与え、新たな循環を生み出す
従来の古本業界は、利用者が店頭に本を持ち込み、業者が立地や目利きで競う対面取引が中心だった。そして2000年代以降になると「送料無料で送れる宅配買取」が普及し、重たい本を自宅から簡単に手放せる利便性が評価され、業界全体の標準モデルとして定着した。一方で、買取できない本までが大量に集まり、物流費や在庫リスクが増大して経営を圧迫するという構造的課題を抱えた。
こうした流れに一石を投じたのが「バリューブックス」である。本の買取と販売を行うオンライン書店として2007年に創業。当初は同業他社と同じく、送料を全額負担していたが、2018年に送料有料化に踏み切り、利用者とコストを分かち合う仕組みに再設計した。買取1箱につき500円を送料として差し引く代わりに、買取金額を従来の1.5倍とする方式を導入したことで、利用者にも納得感のある形で物流コストの適正化を実現した。
送料有料化に伴い、事前にWEB上で本の買取額を調べられる「おためし査定」をオープン。買い取れた本にはすべて個別の明細を付ける取り組みもスタートした。その結果、より高い価格での買取が実現。平均買取額はリニューアル前と比べて約1600円アップした(2018年12月時点)。バリューブックスには1日あたり約数万冊の本が届き、査定を経て中古販売可能な本がオンライン書店に出品され、次の読み手へとつながる。また、中古販売不可となった本の一部は病院や学校などの施設へ寄贈されたケースもあった。
さらに、提携した出版社の古本が売れた際に売上の3割を出版社に還元する「バリューブックスエコシステム」や、古本買取の仕組みを活用して本の寄付を集め、NPOや大学の活動資金として循環させる「チャリボン」など、価値の流れを社会へ拡張する仕組みを整えている。
こうした一連の取り組みにより、バリューブックスは「売れない本」を単なる廃棄物ではなく、次の価値や循環につなぐ資源として扱うビジネスモデルとして昇華させた。物流・中古販売・寄付の各段階を通じて、本を介した価値の循環を社会全体に広げているのである。
【 課題 】
外部プラットフォーム依存による利益構造の制約
創業当初からAmazonなどの大手ECを主要販路としてきたが、手数料負担が重く、最終利益が圧迫される構造を抱えていた。また、外部プラットフォームでの販売において、販売や在庫に関するデータは把握できるものの、顧客情報を自社の情報として活用することはできず、在庫計画や販売戦略に活かしきれない点も課題だった。さらに、本を買い取るための広告費が大きいという構造的課題もあった。
【 構想 】
新たな出版流通プラットフォームの構築
脱プラットフォーム依存を掲げ、出版社や著者と直接つながる新たな流通モデルの整備を進めている。埼玉県に開設を計画している「埼玉倉庫」は、自動化設備で本に最適化された高性能な倉庫で、将来的には出版社や著者も共同利用できる仕組みを備える予定だ。これにより、出版流通の分断をつなぎ直し、本が滞りなく読者へ届く体制を整えようとしている。
【 結果 】
販売と流通を自社で設計し、本をめぐる循環を拡張
自社ECの拡充と物流基盤の整備によって、外部プラットフォームへの過度な依存を減らし、手数料や広告費などの構造的な課題を変革していくことが期待されている。出版社との共同販売や著者が自ら読者に本を届ける取り組みなど、販売チャネルの多様化も進みつつある。結果として、本を再生・還流させる社会的な循環構造が自社の手で形成されはじめている。
AFTER: 2026年以降
中川政七商店
BEFORE: 2006年時点
ものづくりの背景を消費者に伝えられる直営店の展開で売上拡大!
日本では古来より、地域の素材と職人技による工芸品が生活に根付いていたが、1980年代からは安くて大量につくれる工業製品や海外品が増えたこと、また、ライフスタイルの変化により、手間と時間がかかる工芸品の需要は急速に減少した。1980年代に約5400億円あった工芸品の産地出荷額は、2000年には約870億円まで縮小。手仕事による少量生産ゆえに価格競争が難しく、各地で工芸品メーカーの衰退が進んでいたのだ。
株式会社中川政七商店は、1716年創業の日本の老舗企業で、奈良で高級麻織物の卸問屋として創業した。2000年代からは麻織物にとどまらず、工芸を軸とする生活雑貨の製造小売業を展開し、職人技と手仕事の美しさを守りながら、現代の暮らしに合った製品を開発している。 「中川政七商店」ブランドを通じて全国に60店舗以上の直営店を展開、工芸業界が縮小を続ける中にあっても堅実な成長を遂げ、産業全体の再生を牽引する存在となっている。
こうした成長の背景には、工芸品を現代の消費者に届けるための構造転換がある。中川政七商店は、製造から販売までを自社で一貫して担う独自のSPA(製造小売)モデルを確立。従来のように百貨店などに卸すだけでなく、自社で企画・製造した商品を自ら運営する直営店で販売することで、ブランドの世界観をそのまま届ける仕組みを築いた。
この一貫した構造を土台に、工芸が持つ素材や技術を現代の暮らしにどう活かすかを考え抜く商品企画が進められている。伝統的な技法の美しさや背景を踏まえつつ、使い心地や手入れのしやすさ、インテリアとのなじみ方など、生活者の視点から細部を設計し直すことで、工芸の価値を日用品として受け取りやすい形へと翻訳していったのである。こうした価値編集の積み重ねが、自社ブランドの世界観と品揃えの広がりにつながっていった。
企画から製造、販売までの流れを自社が握ることで、直営店は単なる販売の場ではなく、工芸と生活者をつなぐ接点として機能するようになった。店頭では、工芸品の背景にある素材や技術、つくり手の工夫を伝えながら商品を提案できるため、生活者は「もの」と同時に「物語」も受け取ることができる。こうした場づくりにより、工芸の魅力を体感しながら選べる環境が整っていった。
中川政七商店は、工芸の価値をどのように再編集し、どう届けるかという問いを事業の中心に据え、製造小売の仕組みを磨き続けていた。工芸を現代の文脈に合わせてとらえ直し、生活者の側から見て使い続けたくなる形へとつくり替える営みを重ねることで、のちにさらなる変化へと踏み出していくための基盤が整えられていった。
【 課題 】
「ものづくりが続けられない」業界共通の危機に直面
中川政七商店は、自社の事業運営は順調に成長していたが、商品の製造委託先である工芸メーカーの廃業が続き、将来的に供給網が縮小する危機に直面。産地全体のものづくり基盤が弱まる兆しが見えはじめていた。産地の技術やつくり手が減少すれば、将来的に自社の企画や製造にも影響がおよぶ可能性が高まるため、工芸の価値を支える基盤そのものにどう向き合うかが問われていた。
【 対応 】
ビジョン策定と工芸メーカーの経営・流通を支援
2007年にビジョンを「日本の工芸を元気にする!」と定義。さらに、これまで培ってきた自社の経営再生ノウハウは他のメーカーにも通ずるのではないかと考え、そのノウハウを体系化し、2009年から他社支援をはじめた。自社のSPAで培った商品開発・ブランディング・生産管理・販路などのノウハウを開放し、他の工芸メーカーへのコンサルティングや教育講座、合同展示会を開始。自社の成長に閉じず、産業全体を共に育てる体制を整えた。
【 結果 】
産地の一番星」をつくると共に、工芸の出口を拡張
経営・流通支援を通じ、赤字500万円の工芸メーカーが10年で年商3億円に成長するなど、産地の事業再生が進んでいる。決算書の読み方からブランド開発、製造計画、展示会出展まで一貫して伴走し、産地の個性が生活者に届く機会が拡大。さらに中川政七商店自身は、工芸の出口を拡張すべく、海外でのポップアップ展開や工芸建材事業など新たな市場創出にも取り組み、工芸の価値をさまざまな形で社会へ届けている。
AFTER: 2025年時点
ボーダレス・ジャパン
BEFORE: 2023年時点
社会課題に挑む人が生まれ続ける“社会の仕組み”をつくる
従来、多くの社会課題は「ビジネスにならない」として見過ごされてきた。貧困や環境問題、教育といった分野は解決の必要性が明らかでありながら、収益性が乏しいために民間企業が積極的に取り組むことは難しかった。
「ボーダレス・ジャパン」は、「儲からない」と切り捨てられてきた課題に、あえてソーシャルビジネスで挑み続けている。現在は世界13か国 で50以上の事業を展開し、2024年度には売上100億円を超える見込みで、この分野では異例のスケールを実現している。
その一例が「AMOMA」だ。ミャンマーの農家はタバコ栽培による健康被害や借金に苦しんでいた。AMOMAは彼らがタバコ畑を無農薬ハーブ畑に転換することを支援し、適正価格で買い取ることで安定収入を保証した。このハーブは、日本の授乳期の母親が抱える母乳不足の悩みを解決する「ミルクアップブレンド」として商品化され、産婦人科でのサンプル配布を通じて多くの母親に届けられている。こうしてAMOMAは、生産者と消費者、双方の社会課題を結びつけて解決している。
こうした事業はAMOMAにとどまらない。失業率の高い地域で雇用を生み出す事業、開発途上国での環境保全や再生可能エネルギー事業、難民や障害者の自立支援事業、教育格差を埋めるための学習支援事業など、多様な課題に対応する事業が世界各地で立ち上がっている。ビジネスモデルはそれぞれ異なるが、いずれも「解決すべき社会課題」を起点に設計されている点で共通している。
ボーダレス・ジャパンが生み出してきた事業群を支えるのは、資金やノウハウを循環させる独自の仕組みだ。それは大きく3つの機能に整理できる。第一に、「生み出す仕組み」。黒字化した事業は利益の一部(当期純利益の10%)を共通の資金に拠出し、それが新たな起業家への創業資金となる。こうして「恩送り」の連鎖が広がり、次々と新しい事業が生まれていく。第二に、「育てる仕組み」。立ち上げ期の事業は、マーケティングや広報、人事・財務などをスタジオの専門チームから支援される。事業が軌道に乗れば一部利益を拠出し、経理や労務といったバックオフィス業務も専門家に任せられる。起業家は社会課題の解決という本来の使命に集中でき、事業の安定化が加速する。第三に、「広げる仕組み」。国内外で活動する起業家同士が知見やネットワークを共有し、互いに事業を広げ合う。単独では届かない規模や地域にも集合体として挑むことができる。
こうした循環型の仕組みによって、ボーダレス・ジャパンは「社会貢献か、ビジネスか」という二者択一を超え、社会性と経済性を両立するソーシャルビジネスを持続的に生み出し続けている。今後も、まだ誰も手をつけていない領域や新しい地域に挑み、社会課題解決の可能性を広げていくはずだ。
【 課題 】
ソーシャルビジネスでは届きにくい領域がある
ボーダレス・ジャパンはビジネスで社会課題の解決に挑んできた。しかし、ビジネスだけでは届かない領域や時間がかかる課題があることも実感した。教育格差や貧困問題などの背後には、制度や価値観など複雑な構造が連鎖していて根本的な解決が難しかった。また、多くの大手企業や財団がCSRなど社会課題解決に向けたニーズを抱えながらも、どこにどれだけ寄付をすべきかなどに悩む現状もあった。
【 対応 】
非営利領域に踏み込みNPO設立
社会にとって最も意味のあるお金の使い方を設計し実行するため、NPO法人ボーダレスファウンデーションを設立し、非営利の領域に踏み込んだ。これにより、ビジネスで培ったスピードと実行力を非営利領域に持ち込み、これまでインパクトを出しにくかった領域まで対応できるような土台をつくった。
【 結果 】
営利と非営利の両輪によって社会の課題を希望に変える
NPOと株式会社、その両輪によってボーダレス・グループが目指すのは「社会を変えたいという想い」を仕組みに変えること。ビジネスだけでは解決が難しかった構造的な社会課題に対し、NPOが根本的な解決策を設計・実行して、社会貢献のための資金が最も意味のある形で活用される社会の実現を目指している。
AFTER: 2025年時点
NOT A HOTEL
BEFORE: 2025年時点
別荘体験を開放する、不動産とホスピタリティを融合した事業
日本のリゾート会員権市場は約4000億円規模にのぼり、別荘や宿泊施設への潜在需要は大きい。しかし、現実には一部の富裕層に限られ、別荘を1棟丸ごと所有していても利用日数は年間わずかにとどまるケースが多く、豊かな地域資源が十分に活用されていなかった。一方で、暮らしや働き方の多様化により、都市と地方を行き来するなど新しいライフスタイルへの関心が高まっていた。長期滞在やセカンドハウスを求める声は強まるものの、既存の別荘や宿泊施設では利用機会が限られ、持続的に使う仕組みも整っていなかった。こうした状況を背景に「世界中にあなたの家を」というビジョンを掲げて生まれたのが「NOT A HOTEL」である。
同社は世界的建築家やクリエイターが手がける、絶景が舞台のハイエンドな別荘を完成前にCGパースでオンライン販売。最小単位年間10日分から、自分のライフスタイルに合わせ必要な分だけ購入できるシェア購入のモデルを構築。セカンダリーマーケットプレイスの運用も開始し、物件の引き渡しから3年経つと売却がいつでも可能に。オーナーにとっては安心して資産を流動化できる環境を、購入希望者にとっては新たな取得機会を提供している。従来の不動産販売では困難だった柔軟性を備え、リゾート会員権市場の代替・進化系としても位置付けられる。
同社の第1号プロジェクト・宮崎県青島の拠点「NOT A HOTEL AOSHIMA」と栃木県那須の「NOT A HOTEL NASU」では完成前にCGパースのみで販売し、販売開始約2か月で40億円の売上。銀行融資に頼らず前受金で着工資金を確保する手法は不動産開発の常識を覆した。さらに、オーナーは自身が所有する物件以外の全国拠点も相互で利用でき、ネットワークとして多拠点生活を楽しめる仕組みが広がっている。
価値を支えるのは、土地選定から建築設計、販売、ホテル運営や食体験までを一貫して社内で担う体制。建築デザインには世界的建築家であ るBjarke Ingels Groupや藤本壮介氏らを起用し、唯一無二の圧倒的な空間を創出。個人には負担の大きい建物の維持や保全、管理を同社のグループ会社が担い、オーナーは別荘のメンテナンスから解放される。2020年の創業から5年で9拠点の開業を実現し、2025年9月末時点では累計契約高559億円・オーナー数1023名を達成。さらに同社はWeb3領域にも踏み込み、未使用日の宿泊権をNFT化して販売。NFTユーザーは不動産購入を伴わず体験にアクセスできる。独自トークン「NOT A HOTEL COIN(NAC)」も発行し、保有者はNACを預ければ実質無料で宿泊できる新しい仕組みを取り入れている。
NOT A HOTELは、所有・運用・デザインに加えNFTやトークンといった仕組みも組み合わせつつ、不動産業界の枠を越えた事業へ進化している。それは新しいライフスタイルを提示する事業であり、進化の行方に注目が集まっている。
【 課題 】
拠点滞在の体験に依存し、提供価値が限定的
NOT A HOTELは全国に拠点を展開、建物やサービスを通じて新しい暮らしを提案してきたが、その提供価値は個々の拠点での滞在にとどまり、拠点同士をつなぎ周囲の地域資源を含むより大きな体験につなげる仕組みにまでは至っていなかった。成長機会をさらに活かすには、不動産を超えた体験価値をどこまで生み出せるか、従来の枠組みを越える挑戦が求められた。
【 対応 】
滞在価値をより拡張するため、移動や所有の仕組みも整備
同社はこれまで、世界的な建築家やクリエイターが手がける唯一無二の建築を使いたい分だけ所有できるサービスを全国に展開し、「住まい」をアップデートしてきたが、その仕組みを「モビリティ」に広げ、ヘリコプター、クルーザーなどの多彩なモビリティをライフスタイルに合わせてシェア購入できる仕組みを整えた。これにより、滞在・移動・食を一体で楽しめる環境が整った。
【 結果 】
地域資源を活かすことで日本の価値を上げる
その土地ならではのユニークな体験を融合し、モビリティまで拡張したことで、滞在に加えて移動そのものが特別な体験となった。クルーザーやプライベートジェットを利用した旅は、オーナーに新しい暮らしの選択肢をもたらし、地域にとっても新しい層の人の流れを生み出して、魅力を再発見する契機となっている。こうして単なる不動産開発やホテル運営を超え、日本全体の価値を高めるという覚悟を持った挑戦が続けられている。
AFTER: 2025年以降
コングラント
BEFORE: 2017年時点
人手や資金に限りがある非営利団体の強い味方
多くの非営利団体にとって、オンラインで寄付を募ることは長らく高いハードルだった。クレジットカード決済の導入には、審査や契約、システム構築が必要で、特に小規模な団体や任意団体にとっては大きな負担となっていた。その結果、活動資金を得る機会を逃す事例も少なくなかった。
この課題を解決するために生まれたのが、オンライン寄付DXシステム「コングラント」である。寄付募集、決済、支援者情報管理、領収書発行を一体化して提供し、団体の寄付活動全体にかかる時間と労力を大幅に削減している。2025年3月時点で3000以上の団体が導入し、累計寄付流通額は100億円、寄付件数は123万件を超える。運営するコングラント株式会社は、社会課題をビジネスで解決するITサービス事業を展開していたリタワークス株式会社から独立して設立された。
最大の特徴は、寄付募集から決済、支援者情報の管理、領収書発行までをワンストップで提供する点にある。決済手段はクレジットカード、Apple Pay、Google Pay、PayPay、Amazon Pay、銀行振込、郵便振替など多様で、支援者のニーズに応じた幅広い選択肢が揃っている。団体に代わって決済代行会社との契約や審査を担うことで、即日でのオンライン寄付受付を可能にし、寄付募集のハードルを大きく引き下げた。
利用の流れはシンプルだ。団体はコングラント上で寄付募集ページを作成・公開し、支援者はこのページを通じて寄付を行う。決済完了後には自動的に領収書が発行され、集まった寄付金は月末締めで集計されて、翌月20日までに決済手数料や事務手数料を差し引いた金額が団体の指定口座に振り込まれる。
ITに強い人材の確保が難しい団体でも運用できるよう、機能は直感的かつ使いやすく設計されている。寄付募集ページの作成、支援者情報の管理、領収書作成など必要な業務を容易に行えることが、人手や資金に限りがある団体にとって大きな利点となった。これにより、支援者との関係構築や継続的な支援の促進につながっている。
このビジネスモデルは月額利用料と決済手数料によって成立している。サービスは無料から利用できるが、機能拡張を求める団体向けに月額4000円のライトプランや8800円のスタンダードプランが用意されている。有料プランでは決済手数料が3.4%に抑えられ、公開できる募集ページ数が増加し、年間を通じた寄付活動の幅が広がる。
コングラントは単なるサービスの提供にとどまらず、団体の寄付活動を支援する伴走者としての役割も重視している。新たに月額寄付者を募る団体向けには「マンスリー寄付挑戦プログラム」を実施し、セミナーや目標設定支援を行う。こうした取り組みにより、小規模団体が寄付活動をはじめやすい環境を整えているのだ。
【 課題 】
寄付が “特別な行為”のまま広がらない社会
決済まわりの仕組みは整ってきたものの、非営利団体にとって資金を集めるのは、そもそもの寄付が少ない日本ではそう簡単ではない。継続的な寄付や新しい寄付者との出会いをどう生むかという課題は残る。さらに、寄付後の税優遇制度は手続きが複雑・煩雑で、制度や文化の面でも寄付を日常の行動にしにくい状況が続いている。
【 対応 】
仕組みと制度の両面において寄付のハードルを下げる
寄付そのものを、もっと多くの人にとって身近なものにするため、ワンタップ寄付アプリ「GOJO」をリリース。同アプリ上のマイページ機能やポイント制度で個人の寄付体験を身近で気軽なものにし、それと同時に、税控除申請プロセスに関する制度の改善のための政策提言など、寄付市場全体の成長を意識した施策に取り組んだ。
【 結果 】
社会に寄付が根付く土台が少しずつ動きはじめた
寄付アプリ「GOJO」の企業向け機能では、事業会社の従業員の社会貢献の見える化、非財務情報開示ニーズにも対応可能になったことで対法人のサービス展開が進んでいる。また、寄付控除手続きのオンライン化に向けた政策提言も実を結びつつあり、寄付文化の醸成に向け、ハードルとなっていた制度の改善に向けても手応えを得ている。
AFTER: 2025年時点
Kuradashi
BEFORE:2023年時点
「三方よし」で実現する、フードロス削減の社会インフラ
日本国内では年間約450万トン以上の食料が廃棄されていて、これは国民全員が毎日茶碗1杯分のご飯を捨てている計算に相当する。半分は家庭内で発生しているが、残り半分は、品質に問題がなくてもパッケージの汚れや季節限定商品の期間終了に伴い破棄される、事業会社に起因するものである。会社での廃棄というとコンビニ弁当などを想起するが、実際はそれ以上にメーカーや卸での廃棄が多い。この問題は個人の意識だけで解決できるものではなく、流通慣行や商習慣、需給調整の困難さといった構造的な背景に起因している。
「Kuradashi」は、こうしたフードロスの構造的課題に対し、ビジネスの力で持続可能な解決策を提示している。賞味期限が迫った商品やパッケージにキズがある商品、季節商品や販促期間を過ぎた商品など、品質に問題はないが通常の流通ルートでは販売が難しい商品をメーカーや卸売業者から買い取り、自社のECサイトでお得な価格にて販売する。
このビジネスモデルの特徴は、単なる在庫処分ではなく、消費者が「おトクな買い物」を通じて「社会貢献」に参加できる点にある。商品購入時、ユーザーは売上の一部を用いて、自身が選んだ社会貢献団体(環境保護、災害支援、飢餓対策などの団体)を支援できる仕組みとなっていて、楽しい消費行動が社会的意義を持つ体験へと転換される。
メーカーにとっても、Kuradashiは単なるディスカウントチャネルではなく、「フードロス削減に取り組む社会貢献企業」としてのブランディング機会を提供する存在となっている。これにより、かつては消極的だったメーカー側の参加意欲も高まり、多数の企業がKuradashiのプラットフォームに参画。加えて、会員登録ユーザーは50万人、累計支援金額も1億円以上に到達するなど、社会的インパクトと経済的成果の両立を実現している。
Kuradashiの成長を支えるもう一つの軸は、同社の企業理念にある。創業者が阪神淡路大震災や中国駐在時の経験を経て立ち上げた同社は、「ソーシャルグッドカンパニーでありつづける」ことをミッションとし、「日本で最もフードロスを削減する会社」というビジョンを掲げている。この理念は単なる収益追求にとどまらず、社会課題と経済合理性を同時に追求するという高次の企業行動に直結している。
このようにKuradashiのビジネスモデルは、消費者・企業・社会が同時に恩恵を受ける「三方よし」の構造を実現している。従来見捨てられていた価値を再流通させ、消費者の行動変容を促しつつ企業の社会的価値の向上にも寄与する。単なるECビジネスを超え、社会課題に対するアクションを「日常的な消費行動」に組み込む仕組みとして機能している点において、Kuradashiは持続可能な社会の実現に向けた新しいモデルケースとなっている。株式会社クラダシは、新たな領域へ挑み、社会課題を解決するビジネスモデルの構築を進めている。
【 課題 】
拡大していく需要に対して流通・在庫管理が限界に
Kuradashiの事業は、消費者の共感と企業の社会的評価の高まりを背景に急成長を遂げた。一方で、取引先の拡大と取り扱い商品の多様化により、商品ごとの賞味期限やロット管理、保管・出荷タイミングの調整といった物流機能の複雑性が増大。特に、メーカー側が自社で在庫管理・物流最適化までを担うには限界があり、商品価値の再流通を阻むボトルネックとなっていた。
【 対応 】
物流ノウハウを活かし支援の幅を拡大
そこで、急成長するEC運営で培った物流ノウハウを体系化し、自社活用にとどまらず、メーカー向けの物流支援サービスとして事業を開始。全国150拠点超の倉庫ネットワークを活用し、賞味期限・在庫状況の可視化、発送代行、販促支援などを包括的に提供することでメーカーの業務負荷を軽減しつつ、価値ある商品をロス前に再流通できる体制を整備した。
【 結果 】
物流課題の解決を通じてフードロス削減へ
これにより、単なるソーシャルECを超え、メーカーのサプライチェーン最適化を支援する流通パートナーとしての新たなポジションを確立。余剰在庫の解消の場から、在庫を最適に循環させる仕組みへと進化した。いまや同社の事業は、フードロスという課題への対応にとどまらず、そもそもフードロスが起きない仕組みづくりへと進化しつつあり、社会インフラ的存在へと歩みを進めている。
AFTER: 2025年時点
Ecosia
BEFORE: 2017年時点
「検索」という日常行動を森林再生の仕組みに変えた
気候変動の影響が各地で顕在化し、森林破壊や干ばつ、生態系の崩壊が連鎖している。経済成長を優先してきた社会は、自然資源の搾取に依存する構造の転換を迫られている。異常気象や食料危機が現実の脅威となり、暮らしや企業活動にも波及する中で、日常の行動を環境再生へ結びつける仕組みが求められている。
「Ecosia」は2009年にドイツのベルリンで設立された検索エンジンだ。検索で得られる広告収益を森林再生にまわす仕組みで、日常のオンライン行動を再生の循環に組み替えることを目的としている。創業当初は広告収益の大半 をWWFドイツの森林保護プロジェクトなど既存の環境団体に寄付し、熱帯雨林の保全を支援していた。その後、寄付での支援から、現地パートナーとの協働で苗木育成から植樹後のモニタリングまでを行う仕組みへ発展していった。
EcosiaはMicrosoft Bingの検索技術と広告ネットワークを基盤とし、ユーザーの検索行動により広告収益が生まれる。得られた利益の大部分を森林保全や再生プロジェクトに充てる方針を掲げ、事業運営に必要な費用を差し引いたうえで再投資を行う。資金の使途は月次の財務レポートで公開され、収益から現場までの流れが可視化されている。2014年には、環境や社会への配慮、説明責任などの基準を満たしたB Corp 認証企業となり、社会的使命を追求する姿勢を外部からも評価されている。
植樹活動は、Ecosiaが各地域の専門団体と連携して進められる。現地のパートナーは気候や土壌に合わせて樹種を選び、植えた後の管理も長期的に続けている。Ecosiaはその活動を契約やデータ報告によって支え、成果を衛星画像などで確認。これにより、単発の寄付に終わらず、植えた木が根付くまで見届ける仕組みが確立された。プロジェクトはマダガスカル、ブルキナファソ、ブラジルなどに広がり、木々はCO₂を吸収するだけでなく、土壌や水の回復、農業の安定化にも貢献。森林の再生が地域の暮らしを支える循環を生み出しており、検索で得た収益が地球規模の再生ネットワークとして機能している。
さらにEcosiaは、再生可能エネルギーによる自立運営を進めている。自社で太陽光発電所を建設し、検索サービスに必要な電力をすべて再生可能エネルギーでまかなうと共に、余剰分を電力網に供給。石炭などの化石燃料に依存する電力を実質的に代替することで、CO₂排出を相殺し、事業全体で気候への影響を減らしている。こうしてEcosiaは、森林再生での炭素吸収と合わせ、排出される温室効果ガスの総量より吸収・除去される量のほうが多い「カーボンネガティブ」状態を実現している。
検索が生む経済価値が森林回復と再エネ拡大に循環し、環境負荷を減らしつつ新しい価値を生む構造を形づくる。Ecosiaは、テクノロジーの仕組みを社会や自然の再生とつなぐ新しい経済のあり方を提示している。
【 課題 】
非営利企業の仕組みはを人の意思に依存
Ecosiaは検索を通じて木を植える活動を広めてきたが、その理念は最終的に経営者や出資者の判断に依存していた。仮に将来、創業者が交代したり、経営環境が変化した場合、営利目的の企業へと転換する可能性を完全に排除することはできなかった。理念や独立性を人の意思だけで守るには限界があり、環境のための事業を長期的に続けるためには、理念そのものを構造で守る仕組みが必要だった。
【 対応 】
利益を社会のために使う仕組みを制度化
Ecosiaは理念を経営者の意思に頼らず守り続けるため、ゴールデンシェア(黄金株)と呼ばれる特別な株を、自社から独立した非営利財団であるPurpose Foundationに譲渡した。この株には、会社を売却したり使命や目的に関わる定款の変更を拒否する権限があり、財団が理念の維持を制度的に担保している。さらに、創業者が持つ残りの株式にも配当や売却を禁止する制約を設け、利益を個人が引き出すことを不可能にし、理念を体現する仕組みをつくった。
【 結果 】
理念を守る構造が持続的な環境貢献を支える
Ecosiaが採用したその所有構造は「スチュワードシップ・オーナーシップ」と呼ばれ、会社の利益を社会のために使うことを制度として守る考え方だ。これにより、短期的利益に左右されず、長期的視点で環境再生や気候変動対策に取り組める体制が整った。世界で2000万人以上に利用され、得られた収益をもとに累計2億本を超える木が植えられて、理念を基盤にした社会的・環境的な循環が拡大中だ。
AFTER: 2025年時点
トニーズ・チョコロンリー
BEFORE: 2018年時点
「5つの調達原則」を掲げ、農業支援をも行う持続可能なカカオ生産
チョコレートの原料カカオの主な生産地である西アフリカ、特にガーナやコートジボワールでは、世界のチョコレート原料の約70%がこの地域でつくられているのに、農家の多くは1日1~2ドルしか収入がなく、彼らの多くが極度の貧困に苦しんでいた。また、その地域で暮らす子どもたちは学校に通えず、人権上問題のある形で働かされるケースが後を絶たない状況も続いていた。
「トニーズ・チョコロンリー」は、「チョコレート業界から労働搾取をなくす」という壮大なミッションを掲げるオランダ発のチョコレートブランドだ。見た目はカラフルでポップな板チョコだが、その裏側では、児童労働や強制労働を根本からなくすための独自の原則があり、それがカカオの調達から製造、販売の過程に組み込まれている。値段はふつうのチョコレートより高いが、「美味しくて、社会を変えるチョコレート」としてオランダ国内売上1位を記録し、Tony’s Factory B.V.(以下、Tony’s)を本社として、他国にも製造販売拠点を持ち、世界的にインパクトを与えている。
「労働搾取のないチョコレートを実現すること」を目標とするTony’sの取り組みのカギとなるのが、Tony’sが掲げる「5つの調達原則」だ。その原則とは、カカオ豆の完全なトレーサビリティ(追跡可能性)を確保すること、生活可能な収入を得られる高価格で買い取ること、農家が協同組合を通じて組織力をつけること、少なくとも5年にわたって継続的に買い取る長期契約、そして農業技術支援による品質と生産性の向上である。
この「5つの調達原則」が特にユニークなのは、現地に農家の協同組合をつくり、その協同組合と長期のパートナーシップ契約を結んで「強い農家」を育てるという視点だ。Tony’sは、農家が生活するのに十分な金額でカカオ豆を取引するだけでなく、協同組合を通じて、農家が農業の専門的な知識や技術を身につけるための支援も行っている。そうすることで、カカオ豆の品質と生産量が上がり、農家はより多くの収入を得られ、チョコレートの美味しさにもつながっているのだ。
Tony’sは、2018年時点でオランダにおける市場シェアがネスレを抜き、国民的チョコレートブランドとなった。そして最も注目すべきは、その売上の一部が確実に農家の生活向上に役立っている点だ。Tony’sの利益率は一般的な大手チョコレート企業と比べ低めの水準だが、これは売上からカカオの代金に充てられてる比率が高いためで、提携する農家に支払われるカカオの取引額は、政府の定める最低価格よりも40%も高い。トニーズ・チョコロンリーの取り組みは、食べる人とつくる人、そのあいだに横たわる大きな「不平等」をどう埋めるかという問いに、実践的かつ創造的な答えを出しているのだ。
【 課題 】
業界全体の労働搾取の構造
Tony’sで販売するチョコレートについては労働搾取を減らせて、販売数量も着実に伸ばすことができたが、世界全体のチョコレート業界で見れば規模は小さく、従来どおりのカカオ取引を続けている生産地では労働搾取が続いていた。チョコレート業界には永年慣れ親しまれているブランドが世界各地にあり、大手スーパーに並ぶ商品もそうしたロングセラー中心で消費者の選択肢を変えることの難しさもあった。
【 対応 】
労働搾取のないカカオ調達の仕組みを他社にも派生
自社のチョコレート生産だけではカカオ農家全体の労働搾取をなくせない状況を変えるため、2019年、カカオ取引業者向けに「Tony’s Open Chain」というオープンプラットフォームを立ち上げた。このプラットフォームでは、カカオ製品を取り扱う他企業にも「5つの調達原則」を公開し、調達ルールの原則を実行することを条件に、Tony’sが契約する農家の協同組合からカカオを仕入れることができる。
【 結果 】
チョコレート業界全体で労働搾取を減らす
プラットフォーム立ち上げ後、オランダの大手スーパー、世界的なアイスクリームメーカー、イギリスの栄養食品スタートアップなどが参加しており、2025年時点で20もの企業が調達原則に沿ったカカオ取引を行っている。実際、参加企業と取引する協同組合の児童労働の発生率は2025年時点で3.9%と、業界平均の46.7%を大幅に下回る。こうした取り組みでTony’sは業界全体にインパクトを広げようとしている。
AFTER: 2025年時点
Too Good To Go
BEFORE: 2016年時点
売れ残り食品を「売りたい店」と「欲しい人」とをアプリでマッチング!
世界では「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品=食品廃棄」が大きな社会問題となっている。世界で生産される食料の約4割が廃棄されているといわれ、その過程で生産や輸送に使われた水や土地、エネルギーも同時に失われてしまう。その結果、温室効果ガスの排出増加や気候変動の加速にもつながっている。こうした課題に立ち向かい、「誰もが食品廃棄削減に参加できる」ことを理念に据えているのが「Too Good To Go」である。
2015年、デンマーク・コペンハーゲンで若手起業家グループによって設立。創業のきっかけは、ビュッフェ形式レストランで大量に廃棄される食材を目にしたこと。翌2016年には、飲食店やスーパーの売れ残り食品を消費者に割安で提供するアプリがローンチした。その年の後半、食品廃棄問題に関心を寄せる新たな仲間が加わり、ノルウェー、英国、フランスでToo Good To Goが設立された。2016年10月には、フィットネスコミュニティEndomondoの共同創業者であるデンマーク人起業家メッテ・リュッケが投資家として参画し、2017年春にCEOに就任した。
アプリの使い方はシンプル。ユーザーは位置情報をもとに近隣店舗の売れ残り商品が詰められた「サプライズバッグ」を検索し、決済後に指定された時間に店舗へ取りに行く。ユーザーは定価の25%以下で食品を手に入れられ、袋の中身は受け取るまで不明だが、それが福袋のようなワクワク感を生み、SNS上で中身をシェアする文化も広まった。
ユーザーにとってアプリの利用は無料であり、収益は加盟店が支払う利用料からなる。形態は国ごとに異なり、主に「売上連動の取引手数料」と「年会費」が仕組みとして存在。米国では、1バッグ販売ごとに約1.79ドルがToo Good To Goに入り、年会費約90ドルも設定されるが、一定の売上に到達するまでは発生しない。
このビジネスモデルは、環境・ユーザー・加盟店の三者すべてに利益をもたらす。環境面では食品廃棄削減が温室効果ガス排出抑制につながり、ユーザーは手頃な価格で食品を得ることができる。加盟店は廃棄を減らし、新しい顧客との接点をつくり、環境配慮型のブランドイメージを形成できるうえ、本来廃棄予定だった商品から売上を得られるという実利もある。
サービス開始以降、Too Good To Goは欧州・北米・アジア太平洋地域の20か国で事業展開し、その利用規模と展開力の大きさが特徴となっている。また、アプリ運営に加えて食品廃棄削減に関する政策提言や教育活動にも取り組み、家庭向けには「Look-Smell-Taste」キャンペーンを展開。賞味期限を過ぎても見た目や匂い、味で判断する習慣を広め、「賞味期限切れ=廃棄」の固定観念を問い直している。こうした活動は行政やメディアからの信頼につながり、利用者や協業相手の獲得にもつながっている。Too Good To Goは余剰食品を価値に変換する仕組みを社会に根付かせ、食品廃棄の課題に持続的に取り組むモデルとして存在感を強めつつある。
【 課題 】
食品廃棄の一部にしかアプローチできない
当初のサプライズバッグ方式は、レストランやベーカリー、コンビニエンスストアなど、消費者に近い店舗で発生する食品廃棄の削減には効果を発揮した。しかし、小売が自社在庫の期限管理に対応するニーズや、製造段階で生じる大量の余剰食品、人口密度の低い地域での課題に十分応えられる仕組みではなかった。
【 対応 】
小売の在庫管理とメーカーの余剰削減を支援する
小売や食品メーカーを含むサプライチェーン全体で食品廃棄をさらに削減できるよう、Too Good To Goはサービスを拡大した。小売向けには在庫回転や賞味期限の管理をより効果的に行い、割引販売を食品廃棄防止につなげられる「Too Good To Go Platform」を提供。一方、メーカーの余剰食品を消費者に直接届ける「Too Good To Go Parcels」も欧州で開始した。
【 結果 】
廃棄削減を多面的に支える存在へ
メーカーやブランドから余剰食品を直接消費者に届ける仕組みを取り入れ、同サービスだけで2900万食分の食品廃棄削減を実現。同サービスとサプライズバッグ方式分を合わせると5億食分の食品廃棄の削減、年間でCO₂換算135万トン以上の排出回避、4050億リットルの水資源、1400平方キロメートルの土地利用を節約したことに相当する。さらに大手小売との提携も進み、欧州・北米・アジア太平洋の20か国で18万店超が参加、ユーザー数は1.2億人を超えるグローバルなプラットフォームへと成長している。
AFTER: 2025年時点
「ふみだす」チェックリスト
※noteを読んでいる方へ
ここまでで第4章が終わりです。最初からここまで読んだ人いる?もうスクロールしすぎて指が痙攣し、丸一日は動かないのではないかと推察します。これで全体の約91%の進捗です。ほぼ終わりです。本当におつかれさまでした。もうここまできたら、最後まで読み切っちゃってください!
本書の内容理解をさらに広げるために
ここまで50のビジネスモデルを通じ、さまざまな組織がどのように価値を生み出し、構造を組み替えてきたのかをたどってきたが、「共創性」と「適応性」という視点から事業の変化を見ていくと、その背景にある奥深い判断や仕組みの差異が立ち上がり、「ビジネスモデル3.0」の輪郭が少しずつに見えてくる。
そこでこの巻末では、ここまで展開してきた内容を受け、さらに理解を広げるためのページをいくつか用意した。本編第1~4章での事例解説とは性質が異なり、読後の視座を緩やかに補うための構成である。
まず、次のページから「Community Drive Project」を取り上げる。これは、僕が実際に携わっている現在進行形の取り組みであり、完成したビジネスモデルではないが、あえて「不完全」ともいえる現在進行系の取り組みを紹介することで、本書で示した「共創性」や「適応性」の考え方をどのように実践に移していくのか、「51個目」の事例として何かの参考にしていただければ幸いだ。
そして248ページからは、読者が実際に自分でビジネスモデルを図解することができる「ビズグラムツールキット3.0」を紹介する。このツールキットは本書の視点を実践に移す際の手がかりとなり、252ページ以降の「おわりに」や「参考文献」のページは、本書全体を読み終えたあとに自分の理解を整理し、背景を補う補足にもなる。巻末の各ページには用途の違いはあるが、本編の内容をより立体的にとらえるための補助線として配置している。
Community Drive Project
BEFORE:2024年時点
移動が伴う生活上の課題を、“疎”な社会でどう支え合うか?
人口減少と高齢化が進む中で、人と人、人とサービスの距離が広まり、暮らしが“疎”になりつつある。かつて徒歩圏にあった交通の結節点が遠のき、日常の移動に時間と労力がかかるようになっている。たとえば、学校の統廃合で通学距離が延び、徒歩や自転車では通いづらい子どもが増えている。放課後には習い事の送迎が家庭の大きな負担となり、家族の生活リズムにも影響が出ている。公共交通の維持が難しくなる一方で、免許を返納した高齢者は買い物や通院など日常の移動が課題となることがある。
こうした移動の不自由さは、世代を超えて暮らしのつながりを弱める可能性が問題視されている。こうした課題に対し富山県黒部市で立ち上がったのが「Community Drive Project」だ。行政・企業・住民が立場を越えて対話し、「地域の移動はみんなでつくる」ことを目指す取り組みである。プロジェクトでは、地域の動きを加速させる人材を「コミュニティ・ドライバー」と呼び、日常の移動や助け合いを自分事として考え、周囲を巻き込みながら小さな実装を生み出していく人を発掘・育成している。住民の主体性と合意形成を起点に、仕組みそのものを再設計していく点が特徴だ。
このプロジェクトの起点となったのは、黒部市社会福祉協議会から派生して2022年に設立された「SMARTふくしラボ」である。プロジェクトマネージャーの小柴徳明氏は、20年以上にわたって社会福祉協議会に勤務し、介護や生活支援の現場で多くの住民と向き合ってきた。その経験から、地域によって介護サービスを受けられる人と受けられない人が生まれるという構造的な課題に直面した。たとえ同じ介護保険料を負担していても、中山間地域では事業者の移動距離が長く採算が合いにくく、送迎ができないことがある。小柴氏は、こうした移動の課題に対し、福祉の分野だけでなく地域全体でどう解決していくかを模索していた。
この課題意識に、建築・都市デザインの知見を持つ日建設計と、社会構造を図で可視化してきた図解総研が合流。この3社を中心に2024年度、国土交通省のモデル事業として採択を受け、黒部市をモデルケースに実証に取り組んだ。住民の課題感や移動実態をていねいに集め、見える化して共有。各地で行われる交通や移動サービスの実証実験は、補助金期間が終わると継続されないケースもあり、利用者が定着しないまま終了してしまう課題も指摘されている。こうした現場の実情を踏まえ、3社は技術やサービスからではなく、住民の主体性と合意形成を出発点に据え、対話・調査・可視化を同時並行で進めた。
この連携は、社会環境デザインを推進する日建設計の共創プラットフォーム「PYNT」での議論を経て発展してきた。黒部市での成果をもとに、2025年度以降、他地域への展開を進めている。
【 課題 】
共創の芽をどう事業化し、地域に根付かせるか
黒部市での実証により、住民・行政・企業の対話を基軸とした共創のプロセスが機能しはじめたが、その取り組みを一地域にとどめず、他の地域にも展開できる仕組みにしていく必要があった。地域単位で自律的に運営できる基盤が弱く、共創で得られた主体性をどのように事業化し、地域に根付かせるかが課題となった。さらに、2年目からは国土交通省の事業要件として多地域での実証が求められ、黒部で生まれた共創のモデルを異なる地域の文脈に適応させる方法が問われた。
【 構想 】
地域ごとに共創会社を生み出す全国的なモデルの形成へ
黒部市で行った「対話・調査・可視化」のプロセスを他の地域でも実装可能にすべく、活動で得た知見を体系化し続けている。そして一般社団法人コミュニティドライブを設立、全国の地域での共創を支える中間支援的枠組みの構築を目指している。今後は、各地域で共創プロセスを実践する中で育まれるコミュニティ・ドライバーが、将来的に地域の事業主体として自律的に活動できるよう、支援と伴走の仕組みを整えていく構想だ。
【 結果 】
公的基金だけに依存しない持続的な運営体制へ
Community Drive Projectは、黒部での実証を起点に、共創の知見を全国へ展開するための体制づくりに踏み出した段階にある。各地域のさまざまな特性に応じて、自治体や企業、コミュニティ・ドライバーと連携しながら地域ごとに共創会社を生み出すための仕組みづくりがはじまりつつある。これにより、行政・企業・住民が協働して地域の移動を再設計するための全国的な共創モデルを形づくろうとしている。
AFTER:2026年以降
自分で「ビジネスモデル3.0」を図解してみよう
ここまで本書では、ビジネスモデルの変化の事例を数多く紹介してきたが、次のステップとして、自分自身が関わる事業や関心のある事業を実際に図解してみてほしい。
本書はすべての事例に、共通のルールを持つ「ビズグラム」という手法で記述している。このビズグラムを使うことで、ビジネスモデルの構造をとらえながら可視化することができる。
本書の前作となる『ビジネスモデル2.0図鑑』でも巻末にツールキットを掲載したが、それはあくまで一時点のビジネスモデルを記述するためのものだった。しかし、本書で展開した「ビジネスモデル3.0」では「動的な変化」に着目している。
その変化を記述するために考えたのが、序章でも取り上げた「変化前と変化後を対応させる4ページ構成」だ。そして、これを本書読者が自分で描けるようにするため、実際に書籍をつくる際に使っていたファイルを改良する形で「ビズグラムツールキット3.0」を作成してみた。
「ビズグラムツールキット3.0」には、主体に使うアイコンや矢印などのパーツが揃っていて、それが4ページ構成のフォーマットの中に埋め込めるようになっている。
つまり、自ら全4ページの構成を穴埋めしていくことで、本書と同様にビジネスモデルの変化を追うことができるということだ。また、穴埋めしにくい箇所があれば、まだ見えていないものがあるということにも気付ける。
「ビズグラムツールキット3.0」は、ビジネスモデルを「描く」ための基本セットではない。すでにあるビズグラムという形式を前提に、変化を記述し、比較し、検証するためのツールである。
変化前と変化後を並べて描く。どこに課題があったのかを言語化する。どの構造を組み替えたのかを図で示す。その結果、価値やお金の流れがどう変わったのかを確認する。
これらは、完成した図をきれいに見せるための手順ではない。変化しているつもりの構造を、本当に変わっているのか、という視点で分解するための作業だ。
実際に図解すると感じる難しさ
おそらく、図解や文章を読むよりも自分で記述するほうがはるかに難しいことに気付くはずだ。一見すると簡単そうだが、実際にやってみると案外難しい。何が難しいのか?
たとえば、情報が限られていることで情報の取捨選択を次々と迫られることだ。ビズグラムの図解は9マスという限られた情報量にすることで、必然的に情報を削らなければならないフォーマットにしている。その制約があることで、情報の優先順位をつける必要がある。
事業の優先度を判断して取捨選択しなければならない。何がその事業にとって大事な情報なのか。その事業の業界特性や競争環境など外部環境が大きく影響するときもあれば、組織の置かれている状況や経営資源など内部環境が大きく影響することもある。
期間限定で行われる広告キャンペーンや、ある施策の資金をクラウドファンディングで集めた、といった要素はビジネスモデルには含めにくい。なぜならそれは、一時的な措置であり、継続性のある仕組みではないからだ。こうした、どの情報がよりビジネスモデルに関連する情報なのかを見出す必要もある。
また、そもそもその事業の話を誰に伝えるのか、その相手に何をしてほしいのか次第でも情報の優先度は変わってくる。そうした多くの変数を同時に考えながら、適切な判断をしていかなければならない。
そんなわけで、なかなか一筋縄ではいかないのだが、それでも図解して可視化することで多くの人に伝わりやすくなり、巻き込みやすくなり、自分の頭の整理にもなる。
「ビズグラムツールキット3.0」の活用法
「ビズグラムツールキット3.0」は、事業を説明したいときだけにとどまらず、関係者との合意形成や戦略を検討する際にも使えるだろう。
代表的な活用場面
•自社事業の構造や進化のポイントを整理し、課題と強みを把握する場面
•新規事業案を検討し、変化の方向性を明確にする場面
•他社や行政と未来の構想を描き、共創の設計図を共有する場面
•投資家や顧客など異なる立場の関係者に対し、構造の変化を説明する場面
•チーム内で判断基準を統一し、意思決定を迅速化する場面
「ビズグラムツールキット3.0」の目的は、構造を単に整理することではなく、構造の背後にある因果関係と変化の必然性を共有することだ。
右に掲載したQRコードからアクセスして手順を踏むことで「ビズグラムツールキット3.0 」を利用できる。本書を読むだけで終わらせず、自ら変化を起こすため、このツールキットをぜひ使ってほしい。
※ 実際の書籍ではここにQRコードが掲載されています。ビズグラムツールキット3.0を利用されたい方はぜひ書籍を購入ください。
おわりに
2023年5月、僕の初著書『ビジネスモデル2.0図鑑』の発行部数が10万部を突破した頃、KADOKAWAの担当編集者・色川さんから「『ビジネスモデル2.0図鑑』の次世代版をつくるのはどうか」という内容のメールがあった。だから、そこから本書の刊行までに足かけ3年弱かかったことになる。
ふり返ってみると、出版企画の大枠が定まったのは2024年9月のこと。そこから出版が決まったのが2025年2月で、同年3月には、SNSで正式に『ビジネスモデル3.0図鑑』を出すことを告知。しかし、実はそこから自分にとって暗黒の3か月があった。
企画の進行が全然思うように進まない。本当にこの構成で伝わるか?読者にとって本当にわかりやすいのか?そんな問いがずっと頭の中をめぐり、何度も何度も構成を見直し、同じ場所で足踏みし続けているような感覚にも陥った。
そこで、そんなもやもやした気持ちを正直に外部に開示し、相談に乗ってくれる方をSNSで募集。幸いにも、10年以上会っていなかった友人から、初対面の方、前作『ビジネスモデル2.0図鑑』を一緒につくった仲間まで、実に15名超の方々に相談することができた。
相談を進めていく中で、大きな発見があった。それは、僕自身の、「わかりやすい本にしたい」という思いと、「より難しいことに挑戦したい」という思いの二つが、自分の心の中で静かに衝突していたということだった。
前作から重ねてきた僕の経験が、知らず知らずのうちに難しい方向へと舵を切らせていたのかもしれない。しかし、本当に届けたい相手は、かつての自分と同じように「ビジネスに苦手意識を持つ人たち」だった。この矛盾に気付けていなかったことが、企画を前に進められなかった理由だったのだ。
相談を通じてその構造がはっきりと見え、心のどこかにあった霧が晴れるような瞬間があった。そこから企画は一気に動き出した。
2025年7月、SNSで募集をかけて「ビジネスモデル3.0図鑑編集室」を立ち上げ、15名弱のメンバーが集まってくれた。制作においても「共創性」を大事にしようという意図で、心理的安全性の土台になるような「共創ポリシー」や、報酬の分配方法を定めた「報酬ガイドライン」、編集時のクオリティを保つための「編集ガイドライン」などを定めていき、メンバー全員が一体となって制作する体制を整えた。
生成AIの進化も追い風になった。すべての会議や企業への取材はAIに参加・要約してもらうことで、参加していないメンバーへの情報共有や取材後の執筆もスムーズになった。また、調査・執筆・内容のレビューなど、ありとあらゆる箇所で生成AIを活用した。
さらに、編集会議の様子をすべて取り込み要約する形で、7~10分程度の対話型音声コンテンツをメンバーが主体的に制作し、おそらく世界初の書籍制作の舞台裏を生成AIで即時的に公開していく形式でSpotifyのポッドキャスト番組として公開した。
もとはといえば、書籍自体をどのようにいまの時代に合わせて広報していくか、という問いがあった。しかし、著者である僕が指示したわけではなく、メンバーが自主的に発案し、新たなコンテンツが生まれていった。新たな技術を取り入れ、その進化に呼応するようにコンテンツも変化させていく。こんなリアルタイムな創作が起こりはじめたことも印象的だった。それは、「適応性」を大事にするスタンスが自然と形になったものだと感じている。
そんな実験的な形式で本書をつくるにあたり、まず「ビジネスモデル3.0図鑑編集室」に集まってくれたメンバーに感謝したい。今回、編集室を立ち上げてからの数か月間、一気に執筆や実験を進めることができたのは、メンバーのみんながいてくれたからだ。それぞれに本業や用事がありながらも、主体的に行動し、ほかのメンバーと連携しながら進めてくれた。その存在が何より心強かった。
また、本書に掲載された企業のみなさまにも感謝したい。ご多忙の中で取材の時間を捻出いただき、通常明かされないような背景や課題感、裏側の意思決定まで、快く開示してくださった。また、原稿を何度も確認のうえ、細やかな修正提案をいただいた。通常は該当する原稿だけを共有するところ、すべての原稿が入った元データも共有することで、「ほかの事例がこうだから、うちもこうしたい」とリクエストいただけたり、「序章を読んで共感した」という声をいただけたり、掲載企業の方々とのポジティブな共創も生まれていた。
掲載企業の方を快く紹介してくださった方々にも感謝したい。呼びかけをしたらすぐに連絡してつないでいただき、スムーズに連絡を取り合うことが可能になった。
編集室立ち上げ前に相談に乗ってくれた方々にも感謝したい。本当に悩んでいたため、ふわふわした状態の僕の話にも親身になって付き合ってくれ、たくさんのフィードバックをいただいた結果、自分の中の矛盾をメタ認知することができた。
前作の「次世代版」をつくるという素敵な機会をくださった編集担当の色川さんにも感謝したい。いつも粘り強く、難しいコミュニケーションを軽やかに進めてくださった。
図解総研に入社していきなりこの書籍執筆の全体進行を担ってくれた今村真帆にも感謝したい。入社してくれなかったら本の完成はまだだいぶ先だったのではないかと思う。また、僕が書籍執筆にかまけているあいだ、ほかの業務を安定感を持って進めてくれた沖山誠、竹村栞里、中森源、鵜飼七緒子にも感謝したい。
2018年の『ビジネスモデル2.0図鑑』の刊行後、僕の活動の幅は大きく広がった。 「ビジネス図解研究所」として続けていた取り組みに、社会課題や制度、構造を図解してほしいという依頼が加わり、扱うテーマが一気に広がっていった。
そうしたニーズに応えるため、2020年にビジュアルシンクタンク「図解総研」を設立し、1社目の会社の経営は共同創業者に任せることにした。結果として、いまは図解一本で仕事をしている。
「図解」といっても、ビジネスモデルや会計を通じた経営・事業開発支援や、社会課題・構造の可視化、企業研修、専門的な領域の知見の構造化・可視化など、多岐にわたる仕事に日々向き合っている。
社会の課題が多様化・複雑化し、分断が進む中、ますます人々をつなぐ共通言語が求められる。そのため、図解やその考え方は有効な手段となる。生成AIの進化によって、表層的な意味での図解はどんどん自動化されるが、そもそも何を図解すべきか、どんな切り口で物事を構造化すべきか、どのように分断を乗り越えていくか、どうしたいのかといった思想や意思は、すべて人間から生まれるものだ。そこにこそ、根源的な価値があるのだと僕は思う。
近藤哲朗
〈参考文献〉
『コミュニティナース―まちを元気にする“おせっかい”焼きの看護師』
矢田明子著(木楽舎)2019 年2 月刊
『地域が動く経営戦略 公益経営のすすめ』
土屋有/藏本龍介/矢田明子著、野村高文著・編集(ウェアハウス)2025 年8 月刊
『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』
松田文登/松田崇弥著(新潮社)2022 年10 月刊
『裸でも生きる ~25 歳女性起業家の号泣戦記~』
山口絵理子著(講談社)2007 年9 月刊
『Third Way 第3の道のつくり方』
山口絵理子著(ディスカヴァー・トゥエンティワン)2019 年8 月刊
『競争優位を実現するファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略』
フレッド・クロフォード/ライアン・マシューズ著、星野佳路監修、長澤あかね/仲田由美子翻訳(イースト・プレス)2013 年10 月刊
『温めれば、何度だってやり直せる チョコレートが変える「働く」と「稼ぐ」の未来』
夏目浩次著(講談社)2024 年2 月刊
『むすびえのこども食堂白書 地域インフラとしての定着をめざして』
全国こども食堂支援センター・むすびえ著、湯浅誠編集(本の種出版)2020 年12 月刊
『日本の工芸を元気にする!』
中川政七著(東洋経済新報社)2017 年2 月刊
『9割の社会問題はビジネスで解決できる』
田口一成著(PHP 研究所)2021 年5 月刊
『「新しい資本主義」のアカウンティング「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』
スズキトモ著(中央経済社)2022 年7 月刊
『ビジネスモデル2.0図鑑』
近藤哲朗著(KADOKAWA)2018 年9 月刊
『「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図』
近藤哲朗/沖山誠著、岩谷誠治監修(ダイヤモンド社)2021 年3 月刊
『パーパスモデル 人を巻き込む共創のつくりかた』
吉備友理恵/近藤哲朗著(学芸出版社)2022 年8 月刊
『政策図解』
近藤哲朗/沖山誠著、鈴木寛監修(日経BP)2023 年12 月刊
〈ビジネスモデル3.0図鑑編集室〉
菊池 明日美
山内 信明
日下 裕輔
松川 倫子
藤川 瞭
泉 宏隆
田所 憲
松長 卓志
八島 綾乃
島影 真奈美
水野 圭輔
陳 柏翰
宮下 巧大
〈全体進行〉
今村 真帆
〈図解協力〉
鵜飼 七緒子
〈進行協力〉
竹村 栞里
〈連携協力〉
特定非営利活動法人ARUN Seed
〈図解開発〉
株式会社図解総研
〈紹介協力〉
秋間 早苗
大畑 慎治
笠間 健太郎
上村 遥子
吉備 友理恵
功能 聡子
瀬賀 未久
陳 柏翰
寺松 千尋
早 剛史
宮下 巧大
山崎 大祐
〈序章協力〉
スズキ トモ
五十嵐 剛志
〈壁打ち協力〉
宇井 吉美
小田 裕和
川上 恭輔
喜納 彬光
木綿 秀行
髙野 雄一
鶴田 七瀬
中島 亮太郎
中林 真太郎
松川 倫子
松本 梧楼
水口 怜斉
水澤 貴
茂木 香菜絵
森谷 朋基
山手 俊明
〈取材・監修協力〉
Langaku
山中 武
乗峰 愛美
Arc & Beyond
石川 洋人
萩原 丈博
esse-sense
西村 勇哉
イノカ
竹内 四季
コミュニティナース
北垣 佑一
藤田 奈津子
URASHIMA VILLAGE
古田 秘馬
BIOTA
伊藤 光平
安藤 帆菜美
タイミー
小川 嶺
加藤 彩花
荒川 真志歩
ヘラルボニー
曽根 秀晶
小野 静香
安藤 奈穂
おてつたび
永岡 里菜
園田 稚彩
早川 健星
wash+
高梨 健太郎
イークラウド
波多江 直彦
古川 園子
ADDress
佐別当 隆志
RENATUS ROBOTICS
竹内 耀大
堂本 拓磨
五常・アンド・カンパニー
堅田 航平
田中 はる奈
HADO
福田 浩士
逆プロポ
伊藤 大貴
志賀 久美子
EFポリマー
中尾 享二
下地 邦拓
NEWLOCAL
石田 遼
Oishii Farm
古賀 大貴
石原 優月
The Elephant People
Subhash Gautam
功能 聡子
丸井グループ
相田 昭一
矢野 夏樹
総務部広報室
マザーハウス
山崎 大祐
吉浪 優香
竹内 純子
久遠チョコレート
夏目 浩次
CRISP SALAD WORKS
宮野 浩史
唐橋 佑
find
和田 龍
清水 健史
全国こども食堂支援センター・むすびえ
三島 理恵
神山まるごと高専
藤川 瞭
配車頭
近藤 ゆきと
永瀬 裕史
CLOUDY
銅冶 勇人
大竹 奈佳
ジーバーFOOD
永野 健太
市川 千尋
SEKAI HOTEL
矢野 浩一
宇宙水道局
樋口 宣人
砂流 恵介
工藤 恵子
Alife Holdings
Justin Yu
KOTO
Jimmy Pham
Linh Bui
Linh Nguyen
よーじや
國枝 昂
出野 沙優美
バリューブックス
鳥居 希
竹村 奈々
中村 和義
中川政七商店
荻野 祐
佐藤 菜摘
ボーダレス・ジャパン
峯 美紀子
清水 愛
コングラント
佐藤 正隆
内藤 千賀
Kuradashi
徳山 耕平
齋藤 花伽
Too Good To Go
Daniel Convertini
Community Drive Project
小柴 徳明
羽鳥 達也
畑野 了
吉備 友理恵
沖山 誠
以上、本書掲載順
〈制作STAFF〉
校正 コトノハ
図版・本文DTP エヴリ・シンク
ブックデザイン 吉岡秀典+セプテンバーカウボーイ
著者
近藤 哲朗
図解総研代表取締役。東京理科大学工学部建築学科を卒業、千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学専攻修士課程を修了後、面白法人カヤックに入社。ディレクターとしてWebサイトやアプリの制作に携わる。2014年、株式会社そろそろを創業、NPO支援を行う傍ら、グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻(MBA)にも通学(後に中退)。2018年刊の初著書『ビジネスモデル2.0図鑑』(KADOKAWA)が10万部突破のベストセラーとなり、「ビジネスモデル図解」で2019年度GOOD DESIGN AWARDを受賞。そして2020年、「共通言語の発明」をコンセプトとするビジュアルシンクタンク「図解総研」を設立し、大手企業・研究機関・行政と共に、ビジネスモデル、会計、共創、環境問題、政策など複雑な仕組みや社会の構造などの可視化に取り組む。共著に『会計の地図』(ダイヤモンド社)、『政策図解』(日経BP)、『パーパスモデル』(学芸出版社)などがある。
note
ここまでで全文公開はおしまいです。
10万文字以上をスクロールして、ここまで辿り着いたあなた。本当にお疲れさまでした。そして、ありがとうございます。親指と人差し指が無事であることを心から祈っています。
せっかくここまで読んでくださったなら、振り返りとして実際の書籍もぜひ手に取ってみてください。
そして「読む」だけで終わらせず、自分が関わっている事業や身の回りの仕組みを、実際に図解してみてもらえたら、とても嬉しいです。
ビジネスモデル3.0を図解できる「ビズグラムツールキット3.0」は、1月26日の書籍発売と同時に公開予定です。発売後、ぜひ図解までチャレンジしてみてください。
ちなみに、通常版のビズグラムツールキットはすでに販売中です。
今すぐ図解してみたい方はこちらからどうぞ。
もしかしたらお気づきの方もいるかもしれませんが、今作『ビジネスモデル3.0図鑑』と前作『ビジネスモデル2.0図鑑』は全く同じ判型で、並べてシリーズ感があるようにデザインいただいたので、もし前作をお持ちの方がいたら、2冊並べて置いていただきたいです。
今回で、全文無料公開は3回目になります。
1回目は『ビジネスモデル2.0図鑑』、2回目は『会計の地図』でした。
この2冊を合わせると、発行部数はおよそ20万部になりますが、全文公開がその後押しになった面は確実にあったと思っています。
毎年、数万点の新刊が出る中で、一冊の本の存在を知ってもらうこと自体がとても難しい。それなら、読まれないくらいなら全部開いてしまおう。そんな考えで続けてきたのが全文公開です。
とはいえ、何度やってもやっぱり緊張します。本当に受け入れてもらえるのか。全部オープンにしてしまって大丈夫なのか。正直、公開ボタンを押す前は毎回ちょっと胃が痛くなります。
それでも、知をオープンにすることで、ビジネスモデルという考え方が一部の人の専有物ではなく、誰もが「仕組み」を考えられるものになるなら、そのほうがいいと思っています。
かつて自分自身も、ビジネスモデルという概念に出会って、世の中にはこんな仕組みを考える人たちがいるんだと知り、「自分もやってみたい」と思えた一人でした。本書を読まれた方もぜひ、ビジネスモデル3.0な仕組みを、一緒につくっていきましょう。
ここまで読んでくださった方に、最後にひとつだけお知らせです。『ビジネスモデル3.0図鑑』著者の近藤哲朗が代表を務める会社、図解総研について紹介します。
図解総研は、情報や課題の構造を見極め、それを「図解」として可視化し、設計や実行を支援することを軸に活動しているチームです。
図解を、思考を揃え、議論を前に進め、意思決定を支える技術として捉え、書籍、研修、ワークショップ、プロジェクト伴走など、さまざまな形で社会に提供しています。
事業としては、大きく3つに分かれています。
ひとつは、企業や組織と一緒に課題を整理し、図解を通じて思考や戦略を形にしていく受託事業。研修やワークショップ、プロジェクト伴走などがこれにあたります。
もうひとつは、書籍やツールキット、図解データなどを自ら企画し、世の中に届けていく自社事業です。『ビジネスモデル2.0図鑑』『会計の地図』、そして本書『ビジネスモデル3.0図鑑』も、その延長線上にあります。
そして三つ目が、補助金や助成金なども活用しながら、他者と一緒に社会的なテーマに取り組む共創事業です。正解のない問いに向き合い、構造を整理しながら、新しい仕組みをつくる実験的な取り組みを行っています。
図解総研についてもう少し全体像を知りたい方は、こちらの記事がいちばんわかりやすいと思います。
また、図解総研では、会計、共創、政策といったテーマでの研修や、図解を使ったワークショップも行っています。「ビジネスモデル3.0」の研修も受け付けています。『ビジネスモデル3.0図鑑』を読んで、自分たちの事業や活動を一度整理してみたい、変化の構造を言語化してみたい、そんなふうに感じた方がいれば、HPから気軽にお問い合わせください。
いいなと思ったら応援しよう!
 最後までお読みいただきありがとうございます。サポートは「図解総研」の活動費として使わせていただきます!
最後までお読みいただきありがとうございます。サポートは「図解総研」の活動費として使わせていただきます!