捜査が「わたし」をつくりかえる:Disco Elysiumにおけるプレイスタイルとナラティブ
文・murashit
気がつくと、見知らぬ安ホテルの床にパンツ一丁で転がっている。最悪の宿酔い。昨日の記憶どころか、自分が誰なのかさえ思い出せない。鏡を見る。これが自分だって? ほんとうに?
『Disco Elysium - The Final Cut』(ZA/UM, 2020)の幕開けです。
なんだか理不尽な気が……いや、ぼやいたって仕方ありません。あなたは記憶喪失の刑事として、荒廃した街で起きた殺人事件の捜査に着手せねばならない。そして同時に、膨大なテキストとダイスロールによるスキルチェックを通じ、「自分が何者であったのか、そしてこれから何者となるのか」の(再)確立を迫られもする。『Disco Elysium』(以下、DE)はそんなロールプレイングゲーム/アドベンチャーゲームです。
本稿ではこれを、ビデオゲームのプレイスタイルすなわちいかに捜査を遂行するかが、ナラティブひいてはアイデンティティに独特なかたちで結びつく作品として分析していきたい。
……していきたいのですが、正直申し上げて、DEはどうにもめんどうくさい作品です。幸いなことに記憶喪失の心配の(たぶん)ないわたしたちは、しっかり準備を整えておくべきです。というわけで、「プレイスタイルがナラティブに結びつく」とはどういうことか、まずはDEとはまた別のかたちでこれを実現した作品を通して、もうすこしはっきりさせるところからはじめましょう。
(この記事は、『Signalis』『Disco Elysium - The Final Cut』の物語についてのネタバレを含みます。)
プレイスタイルの解釈者 ── Signalis
『Signalis』(rose-engine, 2022)は、「バイオハザード」シリーズや「サイレントヒル」シリーズ(特に初期作品)の精神を色濃く受け継いだ、見下ろし型のサバイバルホラーゲームです。プレイヤーは「エルスター」というアンドロイドとして、限られたインベントリに限られたリソースをやりくりしながら、異形のクリーチャーたちが徘徊する謎の地下施設を探索し、失踪したパートナーの行方を追います。サバイバルホラーとしてのメカニクスはソリッドで、謎解きもなかなかちょうどいい。ストーリーやその設定は難解ですが──正直わたしもよくわかっていません──グリッチを強調した演出と謎解きのヒントを兼ねた環境ストーリーテリングはかなりキマってる。あと百合。いいゲームです。
ここで問題。サバイバルホラーの目的といえば?
もちろん「生き延びて、先へ進むこと」ですね。サバイバルなので。
とはいえ、目的は同じでもやりかたはさまざまです。弾薬に糸目をつけずにかたっぱしから敵をやっつけていくこともできるし、敵の目をかいくぐり弾薬を節約することもできる。そうです、これがプレイスタイルです。繰り返される行為の傾向、ある種の習慣といってよいでしょうか。
実は『Signalis』のシステムは、こうしたプレイスタイル──敵を何体倒したか、どれだけダメージを受けたか、どれだけ回復アイテムを使ったか、どれだけ長く探索したかなどなど──を、プレイヤーに知らせることなく静かに観察し、集計しています。そして、2周目以降限定の隠しエンディングを除く3種類のエンディング──約束、記憶、離別──のうちどれが選ばれるかが、この集計結果のみによって決定される。
ここでのシステムの役割は、解釈者とでも呼ぶべきものです。
安全を重んじる慎重さ、そして探索もみっちり。なるほど、ではこのエルスターは、目の前の世界にとらわれ「離別」を望むようになったのではありませんか? 迅速かつ効率的な行動……もしかして、情熱に欠けているのかも。そんなとき、大切だったはずのなにかは「記憶」の彼方にとどまったままかもしれません。あるいは、傷つくことを恐れない姿勢。そのある種の無謀さは、「約束」の履行にこだわる意思の現れなのでしょう。
実際のところ『サイレントヒル2』(Team Silent, 2001)のエンディング分岐にも一部で似たような条件が課されている──そのいみでも後継であるといえる──のですが、それでも特定の手紙を読んでいるかどうかといったナラティブ面での条件が含まれていました。こうした条件を排し純粋にメカニクス的な「習慣」のみで結末を決定する『Signalis』のやりかたは、比較的めずらしいものといってよいのではないでしょうか。
プレイスタイルって、結局なんなのよ
「プレイスタイルがナラティブに結びつく」という表現の輪郭がなんとなく見えてきましたね? そういうことにします。そういうことにしたうえで──じゃあ、ここでいう「プレイスタイル」って、結局なんなのよ。
ありそうな答えとしてたとえば、効率性の観点からみた「戦略」でしょうか。『エルデンリング』(フロム・ソフトウェア, 2022)でどの武器が最強か、みたいな。ティアリストを作るのは楽しいものです。あるいは、TRPGにおけるプレイヤー類型を思い出す人もいるかもしれません。戦闘大好きリアルマン、なりきりに凝るリアルロールプレイヤー、ウケ狙いのルーニー、最強厨のマンチキン。
ただ、『Signalis』の例に対しては、どうにもうまく当てはまらないと感じられてしまいもします。なんらかの優劣をつけようとするものではないし、もとから持ち合わせている性格を診断したいわけでもない。
ここで白状しますが、実は先の『Signalis』の例はわたしのオリジナルではありません。『Game Studies』誌に掲載されたJohan Kalmanlehtoの論文「Playstyles in Signalis」(2025b)で展開される議論を紹介したものです。Kalmanlehtoは本論文、およびその理論的な背景を掘り下げた「Style Makes the Player?」(2025a)において、「プレイスタイル」という便利なようで(だからこそ)曖昧な言葉を、もうすこしかっちりと定義しようと試みています。ここでの「プレイスタイル」は、単なる効率的な戦略や、プレイヤーの生来の性格が直接的に反映されたものではありません。
ではなにかといえば、「ゴール指向のゲームプレイ課題を達成するための、美的に価値のあるやりかた」とされます。プレイヤー自身の感性に訴えかけるような主観的な経験をもたらす、ゲームとしての目的達成のために繰り返される行為のありかたこそが「プレイスタイル」だよ、と。『Signalis』でいえば、生き延びて先へ進むというゴールに向けた「敵を殲滅するプレイが気持ちいい」「戦闘を避けたステルスプレイにわくわくする」といったプレイヤー自身の美的な判断や楽しさがプレイスタイルを形成するということです。
この定義を核とするKalmanlehtoの主張のうち、特に次の2つの視点は重要です。
第一に、プレイスタイルを「ゲーム的な課題をいかに遂行するか」という実践の過程に現れるものと限定し、そのきっかけとなる「なぜそうするのか」という動機のレイヤーを、分析のために概念的に分離していること。
ここでいう「動機」とは、たとえば「これが最適だから」「こういうキャラクターを演じたいから」「道徳的に正しい選択をしたいから」といった思いや、プレイヤーの性格といったものを指します。これらは当然に入り混じってしまうものではありますが、それらをあえて切り離し、あくまで課題遂行のやりかたそのものに関する現象であると捉えるわけです。『Signalis』はプレイヤーの動機のいかんにかかわらず、まさにこのプロセスの集積のみを解釈の対象としたのでした。
第二に、プレイスタイルが能動性と受動性というふたつの側面をもつと指摘していること。「かくありたい」という理想に近づこうとする能動的な実践であると同時に、過去の経験などによって無意識的に形成された受動的な習慣でもある。プレイスタイルがこの両面の摩擦や相克として現れることをKalmanlehtoは強調しています。
ここでいう「かくありたい」という理想が先ほど分離した「動機」とは異なるレイヤーにあることに注意してください。これは「こういう性格のキャラを演じたい」というナラティブ上の動機ではなく、「(たとえ非効率でも)こういうやりかたで攻略するのだ」という、あくまで実践の過程そのものに向けられた美的な理想を指します。『Signalis』の例でいえば、「エルスターは慎重な性格だから」という動機ではなく、「戦闘を避けたステルスプレイにわくわくする」という感覚を目指し、それを実現しようと振る舞うことです。
これらのあるからこそ、わたしはKalmanlehtoの定義を採用させてもらったんですね。というわけで以降では、これら「動機/実践の分離」と「理想/習慣の二重性」という視点からDEについて検討していきましょう。
ロールプレイをロールプレイする ── Disco Elysium
あらためて、DEとはどのようなビデオゲーム作品なのか。
冒頭でも述べたとおり、プレイヤーが担う役割は、殺人事件の捜査を任された記憶喪失の刑事。相棒のキムとともにマルティネーズという街を探索し、聞き込み、張り込み、証拠を探し、しばしばひどい脱線を繰り返しながら、事件の謎を解き明かすことが目的となります。そんな本作には、通常のRPGにあるような「戦闘」はありません。会話、そして行動の成否を決定するスキルチェックによって本作は進行していく。
スキルチェックがあるということは、スキルビルドもあるということです。本作には、「知性」「精神」「肉体」「運動能力」という4つのアビリティのもとに、合計24種類のスキルが存在します。といって、これらは単なる能力値ではありません。[論理]や[共感]、果ては[内陸帝国]といったそれぞれのスキルはみな、まるで独立した人格のように、ことあるごとに主人公の脳内で語りかけてくる。喚きたてると言ってもいい。
さらに、「思考キャビネット」と呼ばれるシステムも搭載されています。ほかに類を見ないシステムであるため少々説明が難しいのですが──捜査の途中で得たふとした思いつきや特定の行為について時間をかけて思い巡らせ「内面化」させることで、主人公の能力や性格をさらに発展(あるいは変容)させられるといったもの。きみは[黙示録刑事]にもなれるし[体積くそ圧縮機]にもなれる。
こうした[内陸帝国]や[体積くそ圧縮機]の様子は、演出にとどまるものではありません。プレイヤーが能動的に行うアクティブなチェックだけでなく、システムが裏で自動的にダイスを振るパッシブなチェックにも影響しているからです。[知覚]が高ければ見逃したはずの証拠が勝手に目に入り、[南の高速道路]を内面化していれば知性に関するチェックがいつのまにかアンロックされるようになる。「なにができるか」だけでなく、「世界がどう見えるか」という認識そのものを決定づけているのです。そうなれば、そこでわれらが刑事が取りうる捜査のアプローチ──なにを手掛かりとして拾いあげ、だれの言葉を真実として受け取るか──もまた、必然的に変容せざるをえません。
どうでしょう、いかにもプレイスタイルがナラティブに結びついてきそうじゃありませんか? ですからここで、先の「動機/実践の分離」に立ち返る必要があります。
くどいようですが繰り返させてください。Kalmanlehtoは、プレイスタイルをあくまで「ゴール指向のゲームプレイ課題を達成するための、美的に価値のあるやりかた」、すなわち目的をいかに遂行するかの実践の過程に現れるものとして定義しました。そして一般的なゲームにおける道徳的選択やロールプレイといった要素を、プレイスタイルとは異なる「動機」として意図的に分離しています。『Signalis』におけるプレイスタイルは、たしかにこの定義に当てはまっていました。生き延びて先へ進むという課題に対し、敵を殲滅する/回避するというやりかたの習慣が、結末というナラティブとして事後的に解釈されるのですから。
一方のDEはといえば──この2つの領域をリアルタイムに、不可分なものとして絡み合わせているのではないか。
そもそも、DEにおける「殺人事件の捜査」という目的指向の課題は、『Signalis』における敵の回避のような物理的な課題ではありません。「情報を引き出す」「嘘を見抜く」「相手を説得する」といった、社会的・心理的な障害を突破する実践こそが中心です。そしてDEは、こうした社会的な課題を遂行するための具体的なやりかた(プレイスタイル)として、どのスキルを伸ばし、どのように行動するか(ロールプレイ)という選択を要求します。
そのうえで「ドアを開ける」という課題があったとき──ドアを物理的に蹴破るのか?([肉体装置])鍵の構造を推察するのか?([論理])ドアの向こうの人物と共感し、開けてくれるよう説得するのか?([共感]) といった可能性がありうる。このとき目の前のドアは、[肉体装置]が高いわれらが刑事には「いかにも蹴破りやすそうな物理的対象」として、[共感]が高いわれらが刑事には「対話可能な他者」として認識されています。これが積み重なるとどうなるか。プレイヤーのロールプレイ上の選択(自分は何者か)が、捜査という課題に対して「世界をどのように知覚し、注意を向けるか」という認知的な習慣を、かたちづくってしまうにちがいありません。
記憶を失い、いわば白紙の状態からはじまるからこそ、捜査という課題を遂行する過程は同時に、「わたしはどのような人間なのか」という自分だけの刑事像を──あるいは、人間のクズを──かたちづくっていくプロセスにもなる。したがってこう言ってもよいでしょう。本作はロールプレイをロールプレイするゲームであると。
この世界で踊るために
では、このようにプレイスタイルとロールプレイが接続された本作において、「理想/習慣の二重性」はどのように機能しているのでしょうか。
まずは24のスキルについて。
ゲームの開始時、あるいはレベルアップ時に、プレイヤーはこれらのいずれかにポイントを割り振ります。あるいは特定のアイテム(ネクタイとか)を装備することでさらに伸ばすこともできる。これはわたしたちが「こんな刑事でありたい」と手探りで選択する理想の表明であると同時に、いかに社会的課題を解決するかというプレイスタイルのための能動的な試みです。知的で冷静な刑事でありたいって? だったら[論理]や[平静]にステ振りしよう。ヤク中? オッケー! [電気化学]だね。
こうしたスキルビルドは、たしかにそのようなプレイスタイルを実現させてくれはします。でも、残念ながらそれだけじゃない。高められた人格たちは、プレイヤーの忠実な道具にとどまってはくれないのです。[論理]は単純作業を嫌い気力を挫いてくる。[内陸帝国]はネクタイが喋っているとヤバげに主張し、[権威]はときに差別的な思考を差し挟む。
ここでは、プレイヤーが能動的に選択した理想が、やがてプレイヤーの意図とは無関係に──ときには邪魔になるほど過剰に──作動しています。受動的な習慣あるいは無反省な自発性への転化を露わにしているといえるでしょうか。あくまであなたに主導権があるはずなのに──捜査だってどうにもままならない。まあ、あなた自身にも覚えがありますよね? それって大事なことじゃありませんでした?
思考キャビネットはどうか。
捜査の途中で得たふとした思いつきがどうにも気になる。なぜだかはよくわかりません、いつの間にかそんな行動をとっていたらしい。俺は[浮浪刑事]なんだって、思っちゃったんだから仕方ない。べつに、なりたいなんて理想がはじめからあったわけじゃないけれど……。
そんな受動性から、とはいえこれとひとつに決めて、思いをめぐらせはじめる。そして一定の時間を経てその思考が内面化されてみれば、それはもはや単なる思いつきではない、意識的に形成された「理想」のスタイルとなってしまう。もちろん、それが最初の思いつきからは予想もつかない形でズレてしまってるなんてことも珍しくありません。
でも、スタイルの形成ってのはそういうものです。身についたものは身についたもの。あなたが[浮浪刑事]であると自覚したならば、ゴミ箱あさりに精を出すのもいいじゃありませんか。換金可能な空き缶を見つけるのが得意なんですから、やらんともったいないね。街が宝の山にしか見えなくなっちゃったんだもんね。
スキルが勝手に喚きたてる。思考をあえて凝り固ませる。これはわれらが主人公だけの話じゃありません。プレイヤーキャラクターの脳内を借りて世界を認識するしかないわたしたちにとって、その偏りやノイズはわたしたち自身の認知を条件づけるフレームとして機能してしまう。わたしたちの認知は思ったとおりに偏らせられ、かつ思ってもみなかったとおりに偏らせられる。望んでいるかもしれないし、望んでいないかもしれない。けれど特定のプレイスタイルを生きることを強いられている。そのことに気づいてしまうかもしれない、あるいはいつの間にかそれが自分らしい捜査だと思い込んでしまうかもしれない。
多くのRPGは「ロールプレイ」をストレスなく実現させようと心を砕いて作られています。でもDEはそうじゃない。「かくありたい」自分を演じようとするまさにその行為が、予期せぬ「なってしまった自分」へといかに変容するか。それが捜査という実践的な行為との摩擦、あるいはそれと接続されたアイデンティティとの摩擦をいかに生み出すか。そしてそれによって自己をどのようにつくりかえていくか。そんな過程をメカニクスを通して表現しているのではないか。
ここではスキルや思考キャビネットといった、主人公あるいはプレイヤーのうちにある摩擦を扱いましたが、さらには外部から事実を突きつけるダイスロールという偶然や、あるいは誰もが愛さずにはいられない──だからこそどうしても気になってしまう──他者としての相棒・キムのまなざしだって加わってくる。
考えてみればこれは、アクションゲームなどにおける失敗の体験とも通じているのかもしれません。そこでわたしたちは「うまく操作できない」という物理的なままならなさに直面します。理想を求めて何度も失敗し、練習を繰り返し、自己の習慣に気づく過程を通して、やがて乗りこなすすべを身体に刻み込む──かもしれない。あるいはもちろん、別のアプローチを試したっていい。そんな失敗との格闘は、なんらかの課題を遂行することを目的としたビデオゲーム作品におしなべて備わるものです。
本作はこの構造を、アイデンティティとナラティブの領域へと拡張している。
アクションゲームの「練習」が肉体的な操作の反復による身体化(あるいはそのできなさの自覚)であったならば、DEの「練習」とは、「なってしまった自分」をどうにか引き受け、別のスキルで補いながら捜査を進め、ときには相棒に対してだって開き直る、そんなふうに「わたし」をつくりかえつづける、終わらないプロセスです。だからこそそこには、どうにも歯がゆい、けれどだからこそ美的に経験されうるプレイスタイルの美学が、まちがいなく息づいている。
世界はめちゃくちゃで、どうしたって型通りに演じ切ることはできない。そんな自己を踊りはじめるための物語なんです。ディスコ・エリジウムってのはね。
補注:プレイスタイルの美学をめぐって
本文では、Kalmanlehtoによるプレイスタイルの定義を「ゴール指向のゲームプレイ課題を達成するための、美的に価値のあるやりかた」と紹介しました。本題から外れることもあり短くまとめてしまいましたが、そもそも「やりかた」を美的に経験することや、そもそも「美的」とはなにかについて疑問を持つ方もいらっしゃることでしょう。というわけでここでは──専門家ではないわたしが、という重大な限定がつきますが──それを補うためのいくつかのポインタを示してみることにします。
まず、「やりかた」ないし(一連の)行為を美的に経験することについて。芸術作品や自然といった対象(オブジェクト)を美的に感じることはあっても、なんらかのプロセスを経験するときに「美」という語が登場することに違和感を覚えるかもしれません。実際、美学という分野のなかでは比較的新しめの議論ではあるらしい。日常の美学などなどにも関連するところではあるし、さすがに素人がまとめるにはしんどすぎる論点ではあるものの、とくにゲームに関連してはNguyen『Games: Agency as Art』(2020)あたりがひとつの流れを作ったものとは言えそうです。Kalmanlehtoもこの流れのなかに位置するものですね。日本語でアクセスしやすい紹介記事としてはたとえば上野による次の記事を参照してください:1/2。また、多少別の文脈にはなりますが、松永『ビデオゲームの美学』(2018)の第7章(特に7.6節)あたりにも似た議論があります。
もちろんこうしたことを考える前に、「そもそも美的経験ってなによ」「美的ってなによ」という疑問が立ちはだかるかもしれません。とりあえずのところ、日常的ないみで「これは美しい」と表現するような概念とは(重なりつつも)異なっています。なんならカントとかまでさかのぼる話題でさっきよりさらにしんどいのですが、とりあえずステッカー『分析美学入門』(2013)の第3章・第4章あたりを読んでみるのはどうでしょうか。ちょっとハードルが高そうなら、ロペス、ナナイ&リグル『なぜ美を気にかけるのか』(2023)や、先述の日常美学への入門書である青田『「ふつうの暮らし」を美学する』(2024)あたりがおすすめかも。
ところで、先ほどNguyenの紹介として参照した記事の著者である上野自身も、プレイスタイルの美学について論じています。「個人的なものとしてのゲームのプレイ」(2024)および「プレイスタイルの対立」(2025)ですね。Nguyenを引いていることはもちろん、前掲の『なぜ美』の共著者でもあるリグルのスタイル論の影響が強い点も同じで、プレイスタイルをある種の美的なやりかたであると定義するのも同じなのですが、ちょっとアプローチが違うっぽい。Kalmanlehtoがプレイスタイルを理想と習慣の摩擦による自己形成というきわめて内面的なプロセスとして捉えようとするのに対し、上野は(たしかに個人的なものであるとしつつも)それが他者やコミュニティとの対立や、スポーツ哲学的な卓越性といった社会的・規範的な文脈でどう機能するかにより強くフォーカスしているように思えます。DEを検討するにあたっての扱いやすさもあり今回はKalmanlehtoを引きましたが、あわせて読んでみるとよいかもしれません。芋砂がなんで嫌われるのかとか気になったことがある人には特におすすめ。というかそもそも、先の記事を含めた連載全体でかなりそのへんの話が多いので、そちらの別記事も見てみようぜ。
また、ここまで紹介したプレイスタイルに関する考察は基本的に身体的な動作やその習慣を重視する傾向にあります。とはいえもちろん(それこそ松永がダネージ『パズル本能』(2007)を引きつつ述べるように)思考における美的な感覚も同様に考えられるところでもある。ただそのうえで、本稿で扱ったようなナラティブな側面との関連については──物語という対象に美的な価値がともなうこと自体は明らかでありそれほどおもしろくないというのもありますが、やはり実践的な行為の文脈から外れるといういみでややこしくなってしまいがちかもしれません。
あとは……前掲の上野も引いていますが、麻雀で自分のプレイスタイルにこだわるあまり、その非効率さを突きつけられたプレイヤーがゲームそのものに失望するさまについて考えた山田「プレイスタイルの裏切り」(2012)はかなり共感度が高いのでおすすめ。プレイスタイルの話ではないものの、Nguyenを引きつつ具体的なビデオゲーム作品について論じたものとして(ワークショップの資料ではありますが)村山「ビデオゲームの表現力:『OMORI』におけるトラウマと行為者性の表現に注目して」も好きなのでぜひどうぞ。
みなさんもおもしろそうな本やゲームがあったら教えてね。
文献情報
青田麻未 (2024). 「ふつうの暮らし」を美学する. 光文社.
ダネージ, M. (2007). パズル本能:ヒトはなぜ難問に魅かれるのか? (冨永星, 訳). 白揚社. (原著2002年刊)
Kalmanlehto, J. (2025a). Style Makes the Player? The Relation between Playstyle, Aesthetics and Subjectivity. ACM Games, 3(2), Article 13. https://doi.org/10.1145/3721120
Kalmanlehto, J. (2025b). Playstyles in Signalis: Style as an Aesthetic Habit. Game Studies, 25(2). https://gamestudies.org/2502/articles/kalmanlehto
ロペス, D. M., ナナイ, B., & リグル, N. (2023). なぜ美を気にかけるのか (森功次, 訳). 勁草書房. (原著2022年刊)
松永伸司 (2018). ビデオゲームの美学. 慶應義塾大学出版会.
Nguyen, C. T. (2020). Games: Agency as Art. Oxford University Press.
ステッカー, R. (2013). 分析美学入門 (森功次, 訳). 勁草書房. (原著2010年刊)
上野悠 (2024). 個人的なものとしてのゲームのプレイ:卓越的プレイ、プレイスタイル、自己実現としての遊び. Replaying Japan, 6, 85-95. https://doi.org/10.34382/0002001105
上野悠 (2025). プレイスタイルの対立. Replaying Japan, 7, 61-71. https://doi.org/10.34382/0002002375
山田貴裕 (2012). プレイスタイルの裏切り:ゲームとプレイの哲学. 京都大学文学部哲学研究室紀要, 15, 13-24. http://hdl.handle.net/2433/173161
執筆者について
murashit
インターネットが好きで、ブログを書いたり、ときどき小説を書いたりしています。
https://murashit.net/
お知らせ
「遊星歯車機関」は、実験的な試みのあるゲームをガイド/批評する同人誌企画です。メカニクスやUI、シナリオ分岐、乱数、報酬設計など、ゲーム特有の仕組みによって広がる物語の可能性に着目します。いずれ本稿群を『遊星 物語るゲームたち(仮)』として編み直し、一冊にまとめる予定です。寄稿をご希望の方はご相談ください。詳細は続報にて。

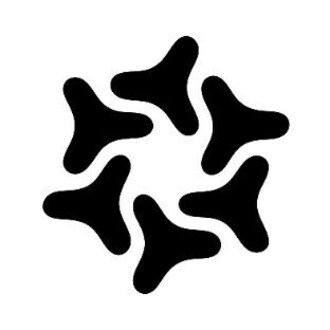
コメント