人生代理店
「三日後までに数字を出せなかったら、クビだ!」
怒鳴り声が天井の蛍光灯まで震わせた。
フロアに散らばる視線が、一斉に私の背中で止まる。喉の奥がつっと鳴り、マウスを握る手の汗が冷えた。
部長の怒声を聞くのは、今月に入って何度目だろう。けれど今の一言には、これまでにない硬さがあった。これは「警告」ではなく、ほとんど「宣告」だ。
3月28日。
カレンダーの数字が血のように滲んでいた。残り三日、月末はすぐそこだ。
ノルマの進捗は五割弱。成約予定の顧客リストはスカスカで、電話の発信履歴だけが無駄に長く積み上がっていた。
入社して五年。地道さだけを武器に、どうにか生き延びてきた。けれど今回は、崖の端が見えている。
“あと三日で職を失う”
その現実が、背広の肩口に鉛の重さでのしかかる。モニターのブルーライトさえ凍り付くように冷たかった。
──やってられるか。
気づけば、営業日報の入力欄を途中で放棄していた。カーソルの点滅が「無意味だ」と瞬いている。
コートを掴み取る手は震えていたが、誰ひとり私を引き留める声はない。
エレベーターのドアが閉まる直前、部長の白いシャツだけが視界の隅でぼやけた。
外に出ると、夜気が肺に突き刺さった。
駅前を回り込んだ先に、赤ちょうちんが滲んで揺れている。そこは五年間、惨めな夜のたびに逃げ込んできた安酒場だった。
暖簾をくぐった瞬間、炭火と醤油ダレの匂いが一気に鼻腔を満たす。
馴染みの大将は何も聞かず、黙ってジョッキを差し出した。
──ゴク。ゴク。
泡が喉を滑り落ちるたび、胃の奥に小さな焔がぽっと灯る。
ジョッキをひとつ、またひとつと空にし、テーブル脇ではガラスの塔が静かに背丈を伸ばしていった。
杯を重ねるうちに数の概念は酔いに溶け、店内のガヤと笑い声は遠い浜辺の潮騒へ姿を変える。
ビールの底で揺れる自分の顔が、何も映さない暗い水溜まりのように歪んでいた。
「……くそ、何でこうなる」
声に出した瞬間、言葉はジョッキのガラスに弾かれて消えた。
私はさらに一杯注文し、底知れない渇きを埋めるように酒を流し込み続けた。
酔いが頂点を越えた頃、私はようやく勘定を済ませ、裏口から夜の路地へふらりと吐き出された。
深夜一時、街灯のオレンジが雨に濡れた舗道を鈍く照らす。終電を逃した影がいくつか揺れ、私は火照った頬を夜風に晒しながら、とぼとぼと帰路を探した。
自宅までは徒歩十五分──何度も歩き慣れた帰路のはずなのに、今夜は足取りがやけに重い。
(クビになったら、どうする?
家賃。奨学金。親への仕送り。……全部止まる)
脳裏で不安が鎌首をもたげ、足裏の感覚が遠のく。
ふと視界の端で、白い光が瞬いた。
路地角の低いビル。その壁面に取りつけられた小さな看板だ。
【人生代理店 あなたの人生、代理します】
ネオン管の冷たい光が、宵闇に浮かんでいる。
こんな場所に店などあったろうか。
赤ちょうちんに通い続けた五年間で、一度も見た覚えがない。
ビルの入口には、無表情な自動ドア。
ガラス越しに見える廊下の奥が、薄く蒼白く光っている。
──営業中、なのか?
酒で膨らんだ好奇心が理性を押しのけた。
“どうせ三日後には無職だ”
そんな投げやりな言い訳が背中を押す。
私は足を踏み入れた。
エントランスは驚くほど静かだった。
ワックスの効いた黒い床に、天井灯が等間隔で反射している。
正面の自動ドアがスッと開き、白いカーペットを敷いた二十畳ほどの部屋へ導かれた。
部屋の中央に据えられたのは、無垢材の天板とスチール脚だけで出来た簡素な机が一つ。
その向こうに、ひとりの男が立っていた。
背は高く、肩幅が広い。漆黒のスーツを寸分の皺なく着こなし、彫刻のように整った欧州風の顔立ち。
冷んやりとした青色の瞳が、真っ直ぐにこちらを射抜いた。
「いらっしゃいませ」
──澄んだ、流暢な日本語だった。
「どうぞ、お掛けください」
促されるまま椅子に腰を下ろすと、深夜の疲労と酔いがまとめて背骨に降りてきた。
目の前の男は優雅に一礼し、名刺の代わりに銀縁のカードを差し出した。
表には店名と、“人生代理人 レオン” の文字。
ここでようやく、私は自分が奇妙な場所に踏み込んだのだと理解した──。
机越しに向かい合うと、レオンと名乗った男は視線を少しだけ伏せ、まるで格式あるホテルのフロントマンのように口を開いた。
「当店、人生代理店では、期間を定めてお客様の人生を──もう少し正確に申しますと、生活行為の一切を代理いたします」
「……生活行為?」
「はい。ご勤務先での業務、対人折衝、家事、育児、果ては健康管理まで。
お客様が 本来その期間に行うはずだったことを、私どもが代行し、周囲には“お客様ご自身が遂行した” という結果のみを残します」
穏やかな口調だが、言っていることはにわかには信じ難い。
私は思わず乾いた笑いを漏らした。
「要するに……“なんでも屋” みたいな?」
「なんでも屋との最大の違いは、結果の帰属性 にございます。
私どもは“陰で支える”のではなく、表向き、お客様自身が行った事実 として世に残します。
したがって、成功も失敗も──すべてはお客様の人生に帰結するのです」
「成功も……失敗も?」
「ええ。ただし、当店は失敗のないサービスを信条にしております。
お代をいただく上で、結果は保証させていただきますのでご安心を」
さらりと言い切る声音に、背筋が粟立った。
半信半疑ながら、胸の奥で小さな悪魔が囁く。
(もし本当なら……三日間、仕事を丸投げできる。クビ宣告どころか、一発逆転だって──)
「料金は?」
「通常、一日につき一万円。ですが本日は初回特典 として、三日間まで無償 で承ります」
「三日間……無料?」
「はい。お試しいただき、ご満足いただけた場合のみ、次回以降正規料金を頂戴いたします」
破格だった。
気づけば私は、酒で濁った思考を抱えたまま頷いていた。
「……わかった。じゃあ、明日から三日間頼む」
レオンはわずかに微笑み、書類数枚を机上に滑らせた。
さらさらとペンを走らせる私を見守りつつ、サインが終わるや否や、封筒を差し出す。
「期間中はこちらのホテルをご利用ください」
封筒の中には、都心の三ツ星ホテル──その最上階スイートの宿泊券が三泊分。
「これ、料金に……?」
「含まれております。
お客様がご自身の人生から束の間解放されるための、当店からのご用意です」
レオンは柔らかな口調で続けた。
「また、期間終了後には活動内容を簡単にまとめたレポートをお渡しいたします。次回ご利用のご参考までに」
非現実が現実に浸食してくる感覚。アルコールの残滓と高揚が混じり、足元が浮く。
「それでは明朝より、私があなたを務めます。どうぞ三日間、ごゆっくりお過ごしください」
レオンは深く一礼した。
私は封筒を握りしめ、店を後にした──
心臓が早鐘を打ちながらも、“失うものは何もない” と自分に言い聞かせて。
翌朝。
ホテルの自動ドアをくぐった瞬間、ロビーの甘いフローラルの香りに包まれた。
シャンデリアの光が大理石の床を走り、背広の肩口まで淡く照らす。
フロントで名前を告げると、すでに手続きは済んでいるという。
エレベーターが静かに最上階へ上昇していくとき、会社の騒音と部長の怒号が、まるで遠い別世界の出来事のように感じられた。
スイートの扉を開けると、窓一面に都心の景色。
ガラス越しに小さく見える自社ビルが、今は取るに足らない箱に思えた。
チェックインの直後、ベルスタッフがワインクーラーを運び込んだ。
タグには 「人生代理店より ごゆるりと」 と印字がある。
白いシーツに身を沈め、昼過ぎまでうとうとする。
ルームサービスで運ばれてくる昼食は、会社の社員食堂で繰り返し噛みしめたパサついた唐揚げとは別の食べ物のようだった。
夜はバーラウンジでバーテンダーと数語交わし、バスローブのまま夜景を眺めて眠りに落ちる──。
気づけば三日間、私は一度も“仕事”という言葉を口にしなかった。
心の底に沈殿していた焦燥が、白い湯船に溶けていくように消えていった。
四月三日、月曜日。
チェックアウトを済ませ、駅前のビジネス街に戻ると、空気は桜の花粉と新入社員の緊張でほんのり重たかった。
私は胸ポケットに辞表を忍ばせ、“有終の美” ならぬ“有終の敗走”を決め込むつもりでオフィスの自動ドアをくぐった。
が──フロアの空気がいつもと違う。
視線がいっせいに私を追い、ざわめきが波紋のように広がった。
(何だ……?)
部長席に向かおうとすると、先に部長の方が弾かれたように立ち上がった。
「おおっ、キミ! やれば出来るじゃないか!」
顔が、怖いほどほころんでいる。
私が見たことのない、満面の笑みだ。
「……え? あの、部長?」
「先月のトップだよ! 大口を次々決めて、一体どうやったんだ!?」
鼓膜が反射で震える。
掲示板に視線をやると、
私の名前の横に、“月間売上トップ 第一位”の文字。
並ぶ数字は、過去の自己最高を軽く三倍超えていた。
足元がふらついた。
(まさか……本当に、やったのか?)
同僚たちが口々に私を讃える。
「広告代理店の新規、見事でしたね」
「地方の地銀を落とした交渉術、感動しました」
どれも私の記憶にない案件ばかり。
けれど誰一人、私が“何もしていない”とは疑わない。
(──人生代理人だ)
内側で冷たい驚きが開花した。
三日間、彼が“私として”オフィスに立ち、すべてを覆して見せたのだ。
部長が肩を叩く。
「今月も期待してるぞ!」
私は辞表をそっとポケットに押し戻し、震えた声で「……はい」と答えた。
その日以来、私は月末が近づくたびに、無意識のうちに、人生代理店の扉を押すようになっていた。
契約書類は一枚きり。
署名欄はすでに私の書式でプリセットされ、レオンは淡い微笑を浮かべるだけで、細かな説明はしない。
三日プラン。
一週間プラン。
繁忙期には二週間プラン。
契約期間中、私は用意されたホテルで眠り、ルームサービスの朝食を摂り、ジムのプールでひと泳ぎして昼寝をする。
そのあいだ代理人は、私の名刺を配り、プレゼンをこなし、取れないはずの案件を面白いように積み上げていった。
気づけば、部の月間表彰では私の名前が常連になった。
成果給は底上げされ、クレジットの利用枠は桁を一つ増やした。
“努力の証” として高価な腕時計を買ったが、それを自分で着ける日にちは、実際には多くなかった。
やがて私は“まとめて休む”味を覚えた。
退職金に等しいボーナスが振り込まれた月、私は思い切って一か月プラン を申し込んだ。
行き先はエーゲ海沿いの小島。
Wi-Fiも繋がりにくい石造りのホテルで、潮騒とレモンの香りに溺れる三十日間。
仕事のことは一切考えなかった。
考える必要がない、という体験は甘美だった。
帰国初日の夜、玄関の灯を点けると、キッチンからトマトソースの匂いが漂った。
「おかえりなさい。もうすぐ出来るわよ」
振り向いたのは、長い黒髪の女性。
二重の深い瞳は見覚えがなく、それでいてどこか懐かしい。
「……どちら様、でしょうか」
「何言ってるの。手を洗って、席に着いて」
食卓には二人分のカトラリー。
粗挽きペッパーをかけたナポリタンが湯気を立てている。
会話の端々でわかった。
彼女は──“私”の恋人だという。
帰国時、渡された報告書を慌てて見返すと「交際継続中」の記載を見つけた。
代理人が私として過ごした一か月のあいだに、出会い、惹かれ合い──交際に至ったようだ。
彼女の名は アカリ。
大手証券会社のエース営業。
ライバル会社に勤める“私”の成果に興味を抱き、声をかけたのがきっかけらしい。
私は狼狽しつつも、流れに身を任せた。
翌朝には彼女が淹れたコーヒーの香りで目を覚まし、休日には手をつないで映画館に並んだ。
やがて私は恐怖を覚えた。
アカリの隣に立つ自分が、あまりに“借り物”だったからだ。
彼女が口にする私への評価は、どれも記憶にない出来事ばかりだった。
彼女の笑顔や仕草のひとつひとつが、まるで見知らぬ誰かに向けられているように思えた。
幸福なはずの日々の中で、胸の奥に澱のようなものが溜まっていった。
このままでは、本当の意味で彼女の隣に立てなくなる──そんな焦燥が、やがて衝動へと変わった。
私は自分自身を作り直すことに決めた。
スーツを身体のラインに合わせて仕立て直し、朝は誰よりも早く出社して、繰り返し営業マニュアルを叩き込んだ。
深夜のジムで体脂肪を削り、手のひらにタコができるほどダンベルを握った。
週末には口下手を矯正するためのプレゼン講座へも通った。
そこで何度も、情けないほど声が震え、言葉に詰まった。
(こんな程度のことすら、俺は自力でできないのか?)
悔しさと恥ずかしさで夜中に何度も目が覚め、そのたびに鏡の前で営業トークを繰り返した。
はじめは笑われるほどぎこちなかった話し方も、数か月後には自分でも驚くほど滑らかになった。
顧客が頷く回数が増え、同僚たちが私の会話を真似るようになった。
そうして一年が経つ頃には、
私はようやく、自分の言葉と表情で顧客を惹きつけるコツを掴んでいた。
そして迎えた月末。
私は、初めて自力で月間トップを奪取した。
「今月も絶好調じゃないか!」
部長は私の肩を強く叩きながら、ジョッキを掲げた。
泡立つビールはいつもと変わらない銘柄だったが、その夜の味は、確かに私自身が掴んだものだった。
胸の奥から熱いものが込み上げ、思わず涙が滲んだ。
私は誰にも気づかれないように顔を伏せ、そっと深く息を吐いた。
(ようやく、ここまで来た──)
冬の匂いを帯びた十一月中旬──交際から丸六か月。
アカリは診察の封筒を胸に抱え、玄関先で小さく震えていた。
「検査、してきたの」
胸ポケットから取り出した紙片には、はっきりと 「陽性」 の二文字。
ひと呼吸遅れて、世界が真昼の花火のように弾けた。
耳鳴りと鼓動が重なり、言葉を探したが見つからない。
「……本当、なのか?」
アカリは瞳を潤ませ、ゆっくり頷いた。
それだけで十分だった。
リビングの窓から差す西日が、彼女の黒髪に金糸を織り込み、ふたりの影を床に溶かし合わせる。
「アカリ──結婚しよう」
プロポーズの台詞は、奇跡的に震えずに口を滑り出た。
アカリは息を呑み、次の瞬間、頬に笑みを広げて頷いた。
指先が触れた瞬間、ふたりの未来が確かな質量を帯びた。
産婦人科の廊下は、洗い立てのシーツとアルコールの匂いが混ざる。
モニターに映る小さな心拍を見つめながら、私は次々と手続きを覚えていった。
母子手帳の交付、産休・育休の申請、マンションの間取り変更──。
営業トップの肩書と充分な貯金は、私を初めて“家庭”という舞台へ押し上げていた。
夕食後、アカリが膨らみかけた腹を撫でながら微笑む。
私は読みかけの育児本を閉じ、胎動に耳を澄ませる。
“守るべきもの” が形を持つたび、胸の奥に火が灯るようだった。
翌年、梅雨入り前の六月。
私は三日間の地方出張を命じられた。
久しぶりに代理人を──と思ったが、今回は自分でやり遂げたかった。
アカリも「大丈夫、元気に動いてる」と笑い、玄関でマフラーを巻き直してくれた。
「すぐ帰る。戻ったら名前の候補、決めような」
「うん、気をつけて」
指先が触れる刹那、ふと胸をかすめた微かな違和感──
だが私は深く考えず、新幹線のホームへ向かった。
出張最終日、商談を終えた私は駅前のホテルで報告書をまとめていた。
スマートフォンが震える。
画面に表示されたのは義母の名前――胸が音を立てて跳ねた。
「アカリちゃん、急に陣痛が来てね。予定より早いけれど、もう産まれそうなの」
予定日は二週間先だったはずだ。
血の気が引くのを感じながら、私は取引先への挨拶もそこそこにタクシーへ飛び乗った。
新幹線の車窓は夜の闇に沈み、時間だけが敵のようにのしかかる。
(間に合ってくれ)
祈るように指を組んだ掌は汗ばんでいた。
東京駅から病院まではタクシーを飛ばした。時計は深夜一時を指している。
ナースセンターで面会を告げると、若い看護師が小声で「おめでとうございます」と微笑んだ。
案内された個室の前で、私は一度深呼吸した。
ドアをそっと開ける。
消毒液と新生児特有の甘い匂い。
ベッドには疲労を帯びた顔で微笑むアカリ、その腕に抱かれた小さな毛布の塊。
「……着いたよ」
声音が掠れる。
アカリは嬉し涙で瞬きをし、そっと我が子を見せてくれた。
ぷくりと膨らんだ頬。小さな指が空を掴む。
その瞬間──布の隙間からのぞいた瞳に、私は息を呑んだ。
深い藍色。海を思わせる、透き通った青だった。
「あ、アカリ……目、見たか?」
自分でも震える声が分かった。
「え? ああ、この子、綺麗な色よね……日本人にも稀にいるって先生が……」
アカリは汗ばんだ額で無垢に笑う。
だが頭の奥で警鐘が鳴り響いた。
(あり得ない。俺もアカリも、先祖代々純日本人だ。劣性遺伝としても確率が低すぎる)
思考が泥沼に足を取られたように沈む。
そこへ追い打ちをかけるように看護師が入室し、授乳の準備のためアカリと赤ん坊を連れていった。
個室に独り残された途端、膝が折れた。
頭の中でパズルのピースが並び替わる──
“あいつだ”──思考が一点に収束した。
代理人
彼だけが、青い目を持つ“欧州系”の外見。
私の代わりに、何度も私の人生を生きた男。
(……まさか。本当に?)
血が逆流するほどの怒りと恐怖がないまぜになり、私は立ち上がった。
次の目的地は、ただ一つ。
深夜二時。
タクシーの窓を叩く霧雨の音が、心拍と同じ速さで脈打っていた。
車を降りると、路地裏の空気は冷えきり、街灯の光がアスファルトに銀色の斑点を撒き散らしている。
そこに──あの看板はあった。
【人生代理店 あなたの人生、代理します】
初めて見た夜と同じ、無機質な白いネオン。 だが今や、その言葉は薄ら寒い宣告にしか見えなかった。
私は傘も差さずに自動ドアを押し開けた。
ワックスの黒床は雨粒を弾き、蛍光灯が過剰なほど明るい。
部屋の中央──例の机の前にレオンが佇んでいた。濡れた靴音にも眉一つ動かさない。
「いらっしゃいませ。お帰りをお待ちしておりました」
「……お前、やったな」
声が震えた。
レオンは静かに首を傾げる。
「何を指して『やった』とおっしゃるので?」
「俺がいない間に、アカリと……俺の人生を、めちゃくちゃにしただろう!」
一歩踏み出すたび、靴底が水を滴らせる。
レオンの青色の瞳は、深い井戸の底のように感情を隠していた。
「私は常に“代理”として最適解を追求してきました。
ご要望に沿い、仕事で成功し、愛を得、幸福を拡大した──それが事実かと思いますが」
「青い目の子どもが生まれたんだ!」
怒鳴り声が壁に跳ね返り、沈黙が耳の膜を圧迫する。
レオンは一拍置き、それからゆるやかに──まるで遺憾の情を示す宮廷礼のように、頭を垂れた。
「……お子様の瞳の色につきましては、私の遺伝情報が影響した可能性がございます」
レオンは、あくまでも“ビジネス上の不具合”として扱おうとする態度だった。
その冷ややかな事務的な姿勢が、怒りにさらに油を注いだ。
「可能性? ふざけるな!!」
机を叩こうとする腕を、レオンの指先がそっと受け止めた。
氷のように冷たい掌だった。
「落ち着いてください。 長年のご愛顧に感謝し、今回は特別な解決策をご提案いたします」
レオンは引き出しから一式の書類を取り出した。
用紙の最上段には太いゴシック体でこう印字されている。
【最終代理プラン ― 生涯全権委譲】
「……これは?」
「お客様が背負われた苦悩を、永久にお引き受けするプランです。具体的には、お客様の人生そのものを私が代理いたします」
脳裏に嫌な予感が芽生えた。
「冗談じゃない……っ」
レオンの声は子守歌のように滑らかだった。
「お客様の人生への諸問題──遺伝的な疑念、社会的評価、経済基盤。 すべて私が引き継ぎます。 ご家族も会社も、“あなた”が生き続けていると理解します」
背後で自動ドアが閉まり、空調が低く唸った。
逃げ道は、霞んだ。
「……ふざけるな。俺は──まだ終わらない」
震える声で吐き捨てた──その瞬間、腹部に鋭い衝撃が突き刺さった。
熱い痛みが爆ぜ、肺から空気が押し出される。
視線を落とすと、レオンの手に握られた細身のナイフが、自分のスーツを貫き腹の奥に食い込んでいた。
「……お気持ち、お察しします」
レオンの青い瞳は微動だにせず、刃をほんのわずかに捻る。
鉄の匂いがふっと立ちのぼり、脚に力が入らない。膝が床に崩れ、掌が血で濡れたタイルを滑った。
「大変、おつらかったでしょう……」
「……非常に思い詰めていらっしゃるご様子でしたので、自殺を代理させていただきました。」
世界が音とともに閉ざされ、闇が静かに降り立った。
光が小さな点になり、耳の奥で鼓動がポツリ、ポツリと消えた。
(アカリ……ごめん……)
最後に浮かんだのは、病室で震える妻の涙。
やがて点は闇に呑まれた。
薄い笑みを浮かべたレオンは、机の上の契約書に滑らかな筆致でサインを加えた。
代理人署名 Leon Hartmann
契約期間 無期限
インクが乾く音さえ無い静寂。
彼はゆっくりと立ち上がり、スーツの袖を正す。
「さて──」
青色の瞳が、残された世界を映す。
「これより私は “私” として、彼の人生を全ういたします。
愛する家族のために、『父親』として恥じぬ栄誉を築き上げましょう」
足元には、跪いたまま動かない“前任者”。
レオンは一礼すると、店の灯りを落とした。
闇に沈んだ路地で、ただ白いネオンの文字だけが、静かに浮かんでいた。
【人生代理店 あなたの人生、代理します】

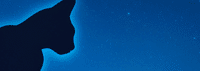

コメント