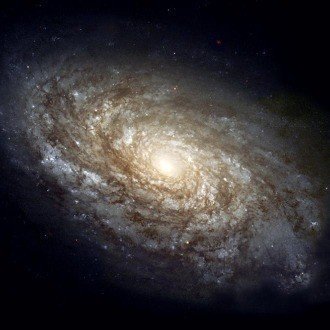超面白かった歴史小説&歴史ノンフィクション6選
個人的に超面白かった歴史小説と、歴史小説的な面白さのあるノンフィクション作品6つについて書きます。
ユン・チアン『ワイルド・スワン』
ノンフィクション。
夕方に読み始めたら止まらなくなって、気がついたら外が白みはじめていました。
ユン・チアンという中国人女性が、祖母・母・自分の生涯を軸に、20世紀の中国史を描いた作品。
1991年にイギリスで出版され、全世界で4000万部以上売れました。
かなり衝撃的な内容で、中国国内では発禁(現在も禁止)。著者は帰国できなくなりました。
これがどんな本かをDeepSeekに聞くと、「你好,这个问题我暂时无法回答,让我们换个话题再聊聊吧。(お答えできません)」と回答する。
(ChatGPTやGeminiやGrokは普通に回答する)
その一方で、1992年に英国最優秀図書賞(Book of the Year)を受賞しているし、
タイム誌は「20世紀のベストブック」の一つに選出している。
この本の発売当時は、とくに西側諸国の人々にとって、衝撃だったようです。
当時僕が通っていた英会話スクールでは講師は全員英語のネイティブスピーカーだったのだけど、全員、この本を読んでて、みんな、すごいすごい言ってました。
当時は、文化大革命とか大躍進政策とかの実態がほとんど知られてなかったからです。
まさか「お父さんよりも、お母さんよりも、毛主席が好きです」と子どもたちに言わせるような教育をしていたなんてねえ。
この本が面白いのは、祖母・母・自分という人間の体験を書いているからだと思います。
歴史教科書よりも歴史小説の方が面白い理由と同じです。
歴史小説は、ある特定の人物から見える世界を描くから、面白くなります。
次々に起きる歴史イベントが、そのキャラにとっては、他人事ではなく、迫真の自分ごとだから、そのキャラに感情移入している読者は手に汗握って読むことになる。
歴史教科書を読んでいるだけでは あまり味のしない単なる知識だったものに命が吹き込まれ、血が通う。
単に自伝にせず、祖母・母・自分と三世代の生涯を書いているのが、すごくいい。
それぞれの時代は、まるで別世界。
祖母は、軍閥の妾(側室)として売られ、纏足(てんそく)された。
その祖母の波乱に満ちた生涯が、またすごい。
母は、共産党の地下活動家。その後、高級幹部の妻となるものの、そこに文化大革命がやってきて、大変なことになる。
作者本人は、14歳で紅衛兵として文化大革命に加担した後、農村に下放されたり、いろいろあって、
1978年にイギリスへ留学し、イギリス初の中国大陸出身の博士号取得者になる。
3人とも、波瀾万丈な人生なので、それがこの本を面白くしている。
つまり、ネタがいい。
ただし、ネタがいいだけじゃない。
そのネタの調理方法が、絶妙。
この著者、ストーリーテリングの才能がある。
カメラワークが上手いし、編集が上手い。
起きた出来事の面白い部分を切り取って、上手くつなげて、実に読ませるストーリーに仕上げている。
それによって、ものすごい没入感とタイムトラベル感を作り出している。まさに、その時空間に生きて呼吸しているみたいな。
歴史小説の醍醐味と通底するところがある。
20世紀中国の狂気をこれほど生々しく読める本は他にないと思う。
歴史的傑作と言っていいと思います。
この歴史的傑作を読める自由がある国に生まれて、ほんと良かった。
みんなで力を合わせて、この自由を守っていきましょう。
パール・バック『大地』
小説。
これもすげえ面白かった。
1931年に出版されるやいなやアメリカで爆発的ベストセラーになり、翌1932年にはピュリッツァー賞を受賞。
全世界で数千万部売れたらしい。
中国の貧しい農民の青年が、懸命に働き、土地を買い足しながら家族を養い、やがて富と地位を手に入れていく物語。
中国では文化大革命期には「帝国主義者の中国侮辱小説」として長らく発禁だったけど、改革開放後に解禁され、現在では「中国人の心をこれほど正確に描いた外国人は他にいない」と高く評価している中国人が多いとか。
この小説の評価が180度変わったのが面白い。
宣教師の娘として中国で育ったパール・バック(アメリカ人)が現地語(中国語)で聞き取りながら書き上げたため、ディテールがすごくて、歴史小説的なリアリティが凄い。
歴史小説として書かれたわけじゃないのだけど、書かれたのが1931年なので、今読むと、歴史小説みたいなタイムトラベルみのある面白さが味わえる。
多くの小説は、100年も経つと、古くさくなって、面白みが低下したりするじゃないですか。
でも、この作品は、書かれた当時は同時代の異国を舞台にした作品だったのに、100年後には歴史小説的な面白さを帯びるようになって、逆に面白さが増しているのが面白い。
20世紀のアメリカ文学で最も有名な作品の一つで、
1938年にパール・バックがノーベル文学賞を受賞した最大の理由となった小説。
この小説の中で、僕が一番好きなキャラは、ヒロインのオーラン(阿蘭)。
こんなタイプのヒロイン、見た事ねえ。
パール・バック自身も「私が書いた中で最も好きな女性」と語っているが、実にうなずける。
彼女は、大地主の家に女中として売られていたのだけど、それを主人公の王龍(ワン・ルン)が妻として迎える。
美人ではない。顔が平たく、足が大きい。
一言も不平を言わず、黙々と働く。
読み書きは一切できない。
ほとんど笑わない、感情を表に出さない。
これだけだと、地味な女性に見えるけど、
彼女は、本当に凄くて、感動的で、マジで泣ける。
彼女については、もっといろいろ書きたいことがあるけど、ネタバレになるので、ここに書くのは控えます。
読んでのお楽しみ。
ケン・フォレット『大聖堂』
小説。
これも、読むのを止められなくて徹夜してしまいました。
100万字くらいある長編小説なのに、あまりに中毒性が高く、あっという間に読み終わっちゃう。
一般的な長編小説(単行本1冊)が10万〜15万字程度なので、その7〜10冊分に相当する。
歴史小説の金字塔とも言える作品で、シリーズ全体で1億6000万部以上売れてるらしいです。
「どういう話なの?」と聞かれると、説明しづらい。
「12世紀のイングランドのキングスブリッジという架空の町で大聖堂を建てる話」がメインストーリーなのだけど、メインストーリーに負けないぐらい面白いサブストーリーがたくさん組み込まれているし、主人公以外の登場人物も魅力的で活躍しまくるし、建築職人・修道士・貴族・平民の利害と感情と欲望と暴力と政治ゲームが複雑にドロドロと絡み合っている。
まあ、100万字の小説だから、通常の小説のように全体が一つの起承転結構造になっているわけがない。そんなことしたら、「起」だけで10万字とかになってしまって、とても読んでらんないから。文字数が小説の構造を規定するんです。
あの傑作群像劇『ゲーム・オブ・スローン』(GOT)をイメージしてもらえればいい。たくさんのサブストーリーが絡み合っていますよね。
これも群像劇と言えば群像劇ですが、あくまで歴史小説なので、GOTのようなファンタジーとは面白さの種類が違う。
キャラやストーリーはフィクションなんだけど、世界設定が「12世紀のイングランド」という史実ベースだし、魔法とかドラゴンとかゾンビとかの超常的なものが出てこないし、リアリティレベルがずっと高く、生々しさがすごい。
建築技術、戦闘、生活、政治の細部がマニアックに描写されていることが、生々しさと面白さに大きく貢献してる。
建築技術のディテールも面白いのだけど、
どんなポジションの職人がどのくらいの給料をもらっているのかとか、
理不尽な貴族が馬に乗って襲ってくるので、平民たちが団結して防御用の障壁を作るのだけど、腰ぐらいの高さまで石を積み上げるだけでも十分に防御力が上がるとか、素人の農民たちを集めて弓兵隊を作るのだけど、素人なので矢を放つタイミングを間違えちゃうとか、
いろんなことについて、細部がすごくリアル。
悪天候で農作物がダメになって、それで食べ物がなくなり、飢えた人々が群れをなして移動するとか、そういう時代だったんだなーと感じさせるイベントがいろいろ起きるのも、実に良い。
内戦、裏切り、疫病、いろいろ起きる。
酷いサディストがエロヤバイことをするシーンもある。
時間的スケールが大きいのもいい。
40年間の時間の流れを描いている。
それによって人々の「人生」が描かれている。
あと、めちゃくちゃ重要なポイントとして、何よりも、エンタメ度がすごい。
とにかく、なりふり構わずエンタメ度が高くなるようにしているのがいい。
料理に喩えるなら、躊躇なく大量の化学調味料をぶち込む感じ。
恥ずかしげもなく、面白い展開、手に汗握る展開、熱い展開にしてくる。
「これは娯楽小説なんだから、面白い展開になって当たり前なんだよ。退屈な展開が続く現実世界とは違うのだよ」とでも言わんばかり。
それらが渾然一体となって、ものすごい没入感を作り出している。
まるで、その時空にタイムトラベルしたかのような没入感。
理想的な歴史小説の一つだと思う。
ジャック・ロンドン『どん底の人々』
ノンフィクション。
これは「読みはじめたら止まらなくなる」というタイプの本ではないのですが、非常に興味深く、面白かったです。読む価値がめっちゃあった。
あと、ページ数がそんなに多くないので、サクッと読める。
著者が1902年にロンドンの貧民街に潜入して生活した体験記です。
パール・バックの『大地』と同様、書かれた当時は歴史小説的なものではなかったのですが、100年以上経った今読むと、タイムトラベル感バリバリの、歴史小説的な面白さがあります。
当時のイギリスは「太陽の沈まない帝国」と言われ、世界一豊かな国だったのですが、その首都の貧民街(イーストエンド)には、なんとも形容しがたい異様な貧困が広がっていました。
著者はそこに2ヶ月間潜入し、その人たちと一緒に生活しました。
そこで働く労働者が、口に釘をくわえていて、そこから釘をとっては、作業を続けるのですが、ずっとそれをやってるから、歯がすり減って、ほとんど歯がなくなってしまっている。
家賃が払えないので、夜中に道端で眠ろうとすると、警官がやってきて、道端で寝させない。眠ることができないから、次の日、ふらふらで仕事を探しに行く。あるいは、昼間に寝たりするから仕事を探しに行けなかったり。そうして、どんどん弱っていく。
仕事にありつけず、仕方が無いので、救貧院に行って食事を恵んでもらおうとすると、延々とならばされる。そのせいで、仕事を探しに行けず、貧困から抜け出せない。理不尽。
貧困者用の飲食店に行って、店のおばちゃんに、「休暇はどうするんだい?」と聞いたら、「キューカあ?」と言って笑う。どうやら、休暇などという贅沢なものはとらないらしい。
現地の青年と一緒にバーで酒を飲んで、将来どうするかと聞いたら、自分の悲惨な運命をしっかり理解していた。将来のことを考えない愚か者なのではなく、その運命をちゃんと理解した上で、日々を生きている。
そんな環境でも、路地で遊んでいる子どもたちがいて、その光景がまた、なんとも言えない気持ちにさせる。今は元気に遊んでいる子どもたちも、栄養不足と栄養の偏りと過酷な環境のせいで、どんどん頭が鈍っていき、ぼんやりした貧しい大人になっていくんだろうとか思わされる。
著者自身が撮影した写真がついているのも、没入感とリアリティ度を上げています。
それと、やはり、「一人称視点の体験」という点が大きいです。
それがタイムトラベル感を醸し出しています。
貧困や格差に興味がある人にお勧め、みたいなことをよく言われる本のようですが、
単に、歴史小説的なタイムトラベル感を味わいたい人にも、おすすめの本だと思います。
藤沢周平『用心棒日月抄』
小説。
個人的に、すごく好きな作品です。
この本の続編を買ったとき、本屋のおばちゃんに、「しっぽりとしていいよね」と話しかけられました。
男性ファンのみならず、女性ファンも多い作品です。
また、今まで いろんな人に勧めてきて、ウケが良かったので、かなり自信を持ってお勧めできます。
歴史小説というより時代小説ですが、没入感が高く、歴史小説特有のタイムトラベル感を存分に味わえますので、このリストに入れました。
若い侍が、江戸でアルバイトをしながら、なんとか食いつなぐ日々を送る話です。
主人公が、なんとも絶妙に魅力的なキャラ。イケメンで長身の立派なお侍さんで剣の達人なんだけど、すごく人が良くて、律儀。
用心棒のアルバイトが多いのですが、まあ、世の中、そんな上手い話はなく、してやられたり、惨めな思いをしたり、いろいろ四苦八苦するエピソードがつらつらとつづられます。それが、すごいリアル。コミカルで笑えるし、人情が染みるというか、なんとも言えない情感がある。
それぞれのエピソードも、それぞれよく出来ていて面白いのですが、それらのエピソードを貫く柱が二本、あります。
一つは、そもそも、主人公の青江又八郎がアルバイト暮らしをすることになった原因です。
又八郎は、北国の小藩に仕える侍(サラリーマン)なのですが、藩内の派閥争いと陰謀に巻き込まれて、脱藩して江戸に逃げてきたのです。
だから、金がなく、アルバイトしながら暮らすことになったのです。
このあたり、社内政治に翻弄されるサラリーマンの悲哀が良く出ていて、サラリーマンからの支持が多い理由が察せられます。
もう一つは、四十七士との関わりです。吉良上野介の屋敷への討ち入りを画策する赤穂浪士たちの策謀と、その敵対勢力にちょっとずつ巻き込まれていくのです。
その二つの柱が、全体を貫いて、それぞれのエピソードに影響し、いろいろ話が絡み合ってくることで、全体がすごく面白くなっていきます。
舞台は江戸だけでなく、故郷へ戻ったりもするのですが、情景描写のリアリティが高く、空気感が実に良い。
もちろん、江戸の人々の生活も、ディテールが良い感じに描写されていて、すごくいい。
続編が3冊出ているので、全4冊のシリーズです。
もちろん、最初の一冊だけでも十分に面白いです。
ユリウス・カエサル『ガリア戦記』
ノンフィクション。
希代の英雄にして天才ユリウス・カエサルが、ガリアを征服していく、血湧き肉躍る物語です。
2000年以上前に、カエサル本人が書きました。
描写がリアルで、2000年以上前の、その時空にタイムトラベルしたかのような感じが味わえます。
歴史小説的な面白さが味わえます。
もちろん、カエサル自身の戦略・指揮・知略・駆け引きがすごいし、
兵士たちを鼓舞する弁舌とかもすごいんですけど、
ローマ軍の兵士たちもすごいです。
ローマ軍の兵士って、すごい土木技術を持ってる集団なんです。
たとえば、ガリア部族の集団が20日かけて苦労して川を渡ったのに、カエサル率いるローマ軍はたった一日で橋を架けて渡ってしまったり。
ガリア部族が城市に立てこもると、カエサル軍は木を切り倒して、その木材で攻城塔を作って、それが動き出したら、ガリア部族はびっくり仰天。それだけで降伏してしまったり。
カエサルがそれらのテクノロジーの詳細を書いているのも、実にいい。オタクっぽい面白さというか。
それから、カエサルは、ガリア人とかガリア社会についてもいろいろ書いているんですね。だから、当時のガリア世界を覗き見する楽しさも味わえる。
歴史小説のタイムトラベル的面白さと同質の面白さがある。
カエサルは、後世の多くの軍事司令官がカエサルの軍事行動を研究したほどの軍事の天才ですが、
政治の天才でもあって、政治工作が上手く、政治センスも抜群。
さらに、文章も天才的に上手くて、実に読ませる文章を書きます。
万能超人かよ。
ストーリーテリングの天才でもあります。
同じ戦争を、カエサル以外の人間が書いていたら、もっとずっと退屈な物語になっていたと思います。
カエサルが書いたからこそ、こんなに面白い物語になったのです。
実は、当時のガリアについて詳しく書いている文書って、これしか残ってないんですよ。
これ以外で、この時代のガリアについて書いてある文書は、古代文献でもノンフィクションでもフィクションでも、元をたどると、だいたいみんな『ガリア戦記』に行き着きます。
つまり、この本はスープの原液なわけで、どうせスープを飲むなら、原液をそのまま飲むと、野趣溢れる濃厚な味が楽しめます。
ただし、この原液、取り扱いに注意が必要です。
Andrew M. Riggsbyは『CAESAR in Gaul and Rome: War in Words』(以下『War in Words』)で以下のように書いています:
カエサルの記述を裏付けることも反証することも、今や困難であることは、周知の事実(notorious)である。ガリア戦争に関する他の史料はほとんど存在せず、カエサルの記述から実質的に独立していると言えるものは一つもない。
It is by now notoriously difficult to confirm or refute anything Caesar says. There are few other sources for the Gallic War, and none can be shown to be substantially independent of Caesar’s account.
ガリア戦争について書いた文書がこれしかないから、カエサルが書いたことがホントかウソか、裏が取れないし、反証もできないんです。
ただし、『ガリア戦記』を読んだ当時の人々の反応の記録はそれなりに残っています。
以下、『War in Words』から引用します:
その受容(読まれ方)を直接に伝える証言がいくつかあるだけでなく、ローマ人がその戦争や『ガリア戦記』の他のトピックスをどのように語り得たかを示す、多様な資料も私たちは持っている。ここでは、同時代の文献の存在に触れるだけで十分だろう。たとえば、キケロの演説『執政官の属州について』は、カエサルの戦争指揮について相当の分量を割いて論じているし、またカエサルが戦い、同時に描写している相手であるガリア人についてのポセイドニオスの民族誌(断片のみが伝わる)もある。
Not only are there a few direct testimonia to its reception, but we also have a variety of different sources for how Romans might talk about the war and about the other topics of De Bello Gallico. Here it is enough to note the existence of contemporary texts such as Cicero’s oration On the Consular Provinces, which treats Caesar’s conduct of the war at some length, and Posidonius’ anthropology (preserved only in fragments) of the Gauls whom Caesar was both fighting and describing.
それらの分析から、『ガリア戦記』がカエサルの政治的自己演出・自己正当化の文書としてもしばしば機能したことが、多くの研究で論じられています。
ぶっちゃけ、話を盛ったり、カエサルに都合の悪いことを省略したりしてると疑われるところがいっぱいあるんすよ。
たとえば、カエサル軍とヘルウェティイ族との戦いについて、『ガリア戦記』には、ヘルウェティイ族側の総数が36.8万人、そのうち「武器を取って戦える者」(以下、戦闘員)が9.2万人と書かれています(第1巻29節(BG1.29))。
しかし、農場・集落・オッピドゥム(城市)などの遺跡、埋葬された人骨、花粉分析から計算した耕地面積と当時の平均収量などの調査・分析の結果などから、研究者の多くはこれが誇張された数値だと考えています。
たとえば、Kurt A. Raaflaubの論文(2021年)には、以下のように書かれています。
この数字(総数36.8万人、戦闘員9.2万人)は、不自然だし、間違いなく、ものすごく誇張されている。現代の学者たちは、総数8万人、戦闘員2万人ぐらいだったろうと考えている。
The numbers look artificial and are certainly vastly exaggerated. Modern scholars think of a total of perhaps 80,000 migrants, 20,000 of whom were combatants.
2万人を9.2万人って、話を盛りすぎやろ……。
このときのカエサル軍は3万人ぐらいだったから(推計の根拠はここ)、物語の印象がぜんぜん違ってきます。
3万人が9.2万人を撃破って、「うおおおおおお すげえええええええ」ってなるじゃないですか。
でも、実際には3万人が2万人を撃破って……
それだけでなく、ヘルウェティイ族側の戦闘員の多くは農民です。
カエサル軍の多くは、ガッツリ軍事訓練された軍人なのに。
3万人の軍人が2万人(その多くは農民)をやっつけたって……
これでは、まるで、弱い者イジメです。
印象悪いですね。
これを、あの、血湧き肉躍る物語に仕立て上げてしまうのですから、まさに、ストーリーテリングと文章の天才です。
実は、この手の怪しい記述が、『ガリア戦記』にはたくさんあります。
より詳しい分析は、僕が書いたnoteの「カエサルの記述の信頼性とプロパガンダ性」という章(ぼくが書いた小説の補足説明)に書きましたので、よかったらどうぞ。
というわけで、「カエサル、おめー、まーた話盛ってるだろ。しょうがねえオヤジだなぁ」とツッコミを入れながら読むのが、この本の正しい楽しみ方です。
宣伝
最後に、僕が書いた小説の宣伝をします。
歴史小説のタイムトラベル感があまりにも好きすぎて、ガリア戦争を舞台にした歴史小説を自分で書いてしまいました。
タイトルは『国力千倍のローマと戦ったびびり』。
びびりの男が、貧しい部族の人々を救うため、国力1000倍以上の超大国ローマと戦う話です。
その男と一緒に、毎日が夏休み!という感じの元気で好奇心旺盛な女児たちも、ローマ軍と戦います。
カエサルの書いた『ガリア戦記』は、話を盛りまくってるし、自分を正義に見せるのが天才的に上手すぎて、実際のガリア戦争がどうだったのかが、よく分からなくなってるんです。
なので、「カエサル以外の人が『ガリア戦記』を書いたら、けっこう違う物語になるかもしれないな」と思いました。
そこで、歴史研究者たちの書いた論文を調べて、ヘルウェティイ族視点からガリア戦争を書いてみたんです。
同じ戦争でも、侵略する側と侵略される側では、見えるものが違います。
侵略された側には、この戦争は、どう見えていたんでしょう?
それを書いてみました。
それから、この小説の主人公は、2053年からやってきた日本人です。
二十一世紀の日本人が、ヘルウェティイ族の視点からガリア戦争を体験したら、どう感じるでしょうか?
逆に、ローマ人やガリア人から見た二十一世紀の日本人は、どう見えるでしょうか?
倫理観も価値観もめちゃめちゃ違いますが、はたして、話は噛み合うんでしょうか?
また、好戦的な大国がすぐ隣にある日本としては、好戦的な大国ローマが隣にあるガリア部族の話は、他人事の気がしません。
もちろん、国際法と正義が支配する現代と、大国が好き勝手できる紀元前一世紀では、大国と小国の関係は異なります。
しかし、最近は、大国が国際法や正義をあまり尊重しなくなってきて、大国と小国の関係もだんだん古代に似てきて、古代の大国-小国関係が現代人にとっても参考になるようになってきてしまっています。
それを狙ってこの小説を書いたわけではありません。この小説を書き始めたのは、ロシアがウクライナに軍事侵攻する前でしたから。
現実に合わせてこの小説を書いたのではなく、現実世界の方がこの小説世界の方に近づいてきている、という、SFチックな状況になってしまっただけです。
大国が正義を尊重せず、自国の理不尽な行動を正当化しながら好き勝手に振る舞うようになった世界で、小国は、どのように生きていけばいいのでしょうか?
そんなことについていろいろと考えるきっかけになる小説になっていると思います。
とはいうものの、お堅い本じゃないです。
ベタベタの娯楽小説です。めっちゃエンタメ路線です。ド派手なアクション、知略の応酬、だまし合い、駆け引き、お色気、因縁の対決、どんでん返し、パニック、カオス、笑い、涙のごった煮です。
話の骨格はシンプルで、以下の(1)~(3)で説明できます。
(1) 人類史上最強の軍事司令官の一人ユリウス・カエサルが、大軍勢を率いて侵略してきます。
(2)2053年の日本から来た亮介(りょうすけ)は、部族民の女児たちと一緒に、必死で逃げたり戦ったりします。
(3)当時は、地中海の周囲を超大国ローマが支配し、その北には蛮族と呼ばれた人々が百以上の部族に分かれて暮らしていました。
もしご興味があれば、試しに読んでみていただけると嬉しいです。
ちなみに、ローマの国力がヘルウェティイ族の千倍という意味じゃないです。
何の千倍なのかは、読んでのお楽しみ。
この記事の作者(ふろむだ)のX(ツイッター)はこちら。
※この記事は、文章力クラブのみなさんにレビューしていただき、修正・加筆されたものです。