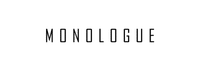Vol.012|なお、一人の人間であれ
『MONOLOGUE』は、エッセイのようでいてコラムのようでもある、そんな型に囚われない備忘録を兼ねたフリースタイル文筆を、毎回3本まとめてお届けするマガジンです。毎週月曜午前8時に定期更新。何かと思想強めですので、用法容量を守ってお読みください。
騙された、なんてことはない
自分が騙されたとわかった時、典型的に見られる反応として「騙してきたそいつを非難する」がある。善良な一市民である私を騙すなんて、世の中には極悪非道な人間がいるものだと、まるでそう言わんばかりにそいつを責め立てることで、少しでも溜飲を下げようとする。
その清々しいまでの他責っぷりは、自分の棚上げを通り越して、さながら自分を神棚へと祀っているかのよう。今後とも「自分の神棚祀り」という概念を積極的に提唱していきたい所存である。
とはいえ、憤る気持ちはよくわかる。よくわかるし、もちろん騙してきたそいつに一定の非があることは明白である。その行為が詐欺罪にあたるならば、当然ながら法的にも罰せられることになる。
しかしながら、これは正しいリアクションではない。リアクションに正しい正しくないがあんのかと、そういう違和感を瞬時に抱く言語性IQ高めの偏屈屋たちに向けて厳密に定義しておくと、人間的な成長を促さないという意味において、これは正しいリアクションではない。
では、正しいリアクションとはどんなものか。一言でいえば「自分が騙している自分とは、はたしてどんな自分だろうか」である。騙してきたそいつを非難している暇があったら、このように自分に問うべきなのだ。
一見すると悪意ある他者に騙されたかのように見えるその事象は、自分が自分を騙しているがゆえに起こりえた事象なのであって、騙してきたそいつを非難するなんてのは、はっきりいってお門違いであるということだ。騙された当事者なのに、である。いや、より正確には騙された当事者だからこそ、である。
多くの人はこの誤った当事者意識に囚われてしまい、正しいリアクションをとることができない。そうすると、いつまでたっても人間的に成長せず、その後もいろんな文脈で自分を騙し続けて、半ば必然的に困窮の一途をたどることになる。
先述したように、騙してきたそいつに非があることは明白である。そのことを否定して自己責任論に矮小化するつもりは毛頭ない。だがしかし、そいつを非難したり罰したりするなんてのは、あくまで外野にまかせておけばいいことなのであって、自分がとるべきリアクションではないのだ。少なくとも人間的な成長を望むならば。
たとえば投資詐欺の一種であるポンジスキームに騙されたとしよう。そもそもなぜ騙されたのだろうか。投資リテラシーがなかったからだろうか。たしかに一定の投資リテラシーがあれば、ポンジスキーム案件で謳われるような高利回りが到底実現不可能であることは、瞬時に見抜けたことだろう。知識武装の重要性にもはや議論の余地はない。
けれども、実はそれは本質ではない。本質は「何者でもない自分から目を背けたこと」だ。己の卑小さを直視せずに、自分はそういうおいしい話が突然降って湧いてくるにふさわしい人間なのだと、盛大に誤解をしていたからこそ、あっさりと騙されたのである。たとえ投資リテラシーに乏しかったとしても、卑小な自分を直視できていたならば、警戒してそこから調べることも十分可能だったはずなのだ。
そして、自分から目を背けるということは、すなわち自分で自分を騙しているということに他ならない。
これはわかりやすい一例で、実際にどういう形で自分で自分を騙しているかは人それぞれだが、いずれにしろ自分で自分を騙しているその構造は変わらない。構造とは見えざる神の手であり、見えざる神の手に取りこぼしはありえない。そう、これはあくまで構造論なのであって、自己責任論とは似て非なるものなのだ。
松下幸之助の言葉に「雨が降っても自分のせい」があるが、これは正しいリアクションをとる上で、非常に重要なマインドセットである。これぐらい理不尽なまでのマインドセットがなければ、人はすぐに易きに流れて他責に走ってしまうのだから。
時の風雪を耐え抜く
敬愛するラッパーZORNの楽曲に『Roots』がある。
ヒップホップ界隈ではお馴染みのティンバーランド「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ」(通称:イエローブーツ)の五十周年を祝うセレブレート・ソングとして制作された楽曲だ。ティンバーランドのツリーロゴから着想を得て、自身の成長と木々の成長とを重ね合わせるリリックとなっている。
何かしらの活動をしていて、なかなか芽が出ずにくすぶっている人は、ぜひこの機会に聴いてみてほしい。心の奥深くまでぶっ刺さって、再び歩き出す勇気をもらえること請け合いである。
自分はこの曲にはじめて触れた時、誇張抜きで思わず目頭が熱くなった。ああ、だから自分はZORNという存在にどうしようもなく惹かれるんだなと、あらためてそう確信した瞬間だった。長年にわたって見えない根っこを育て続け、ついには嵐が来てもびくともしない巨木となったZORN。本当に随一のラッパーだと思う。
そんな才気溢れるZORNですら、ここまで葛藤しながらやってんのに、自分みたいな凡夫が弱音を吐いてどうすんだと。十年やって駄目なら二十年、二十年やって駄目なら三十年やる覚悟がなくてどうすんだと。
ここ最近、あらためて強く感じていることがあって。それは「やはり長期的には残る人が残る」ということ。
これまでいろんな界隈に触れてきたけれど、時の風雪を耐え抜いてこれたのは、本当に一握りの人たちだった。そもそも芽がでずにやめてしまう人が大半で、早咲きで芽がでた人も見えない根っこが育っていないがために、数年も経つといつのまにか萎れてしまい、その姿を消してしまった。芽が出ないのに水をやり続けることも、出た芽を大事に守りながら育てることも、どちらも本当に難しい。
そう考えると、古典というものはやはり真っ先に押さえておくべきである。現代人は何かとコスパだのタイパだのにこだわるが、そのくせ古典にはまるで興味をもとうとしない。時の風雪を耐え抜いてきた事実ほど、それが本物であることを示す信頼の置ける保証はないというのに。時の審判という絶大な力をもつレビュワーを頼らずに、コスパもタイパもへったくれもないだろうよと。時の審判を頼らずして、インフルエンサーとやらを頼る機序がまったく自分には理解できない。
たとえば哲学でいえば、古代ギリシャの哲学者であるプラトンやアリストテレスの哲学なんかは、今から約2400年も前に打ち立てられたものであるにもかかわらず、今もなお読み継がれている。いや2400年て。スケール感おかしいやろ。バケモンかよ。
ホワイトヘッドの有名な言葉に「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈にすぎない」があるけれど、そう言わしめるほどの本物の哲学であったからこそ、約2400年もの時の風雪を耐え抜いてこれたわけだ。
他ならぬ自分もまた、プラトンやアリストテレスの哲学には多大なる影響を受けている。その一方で現代の哲学者にあまり興味が湧かないのは、哲学の本懐であるところの「善く生きる」というテーマから、どうにも逸れているようにしか思えないからだ。なんだか小難しい見かけだけは立派な哲学体系を、延々とこねくり回して悦に浸っているようにしか見えない。
哲学ってそういうことなんか。哲学ってもっとわれわれの生に根ざしたものちゃうんかと。そんな拭いきれない違和感があるからこそ、自分はいつだって古代ギリシャ哲学に立ち返るのである。
なお、一人の人間であれ
学問に傾倒するあまり地に足がついておらず、現実社会へと接続できていない人があまりにも多すぎる。特に哲学はその傾向が強いように思う。
象牙の塔にひきこもって、延々と内輪での議論や批評に興じてみたり、自らの興味関心のみに突き動かされた研究に没頭している。おそらくは彼ら自身も薄々気づいてはいるものの、プライドやエゴが邪魔して見て見ぬふりをしているのだろうが、それでは現実は何も動かない。
人生の一時期にそういう期間があるのは別にかまわない。自分も若かりし頃はそういう時期があった。今はもうなんとも思っていないどころか、むしろ誇りにすら思っているが、教育らしい教育を受けてこなかったコンプレックスの反動で、社会を拒んで精神の密室へと立てこもり、ひたすら真理探究へと邁進してしまった時期があった。
自分にとっては、それもまた必要な時期だったのだろう。あの時期があったからこそ、今の自分がいるのは間違いない。
けれども、いつまでもそれではいけない。われわれがこの現実社会に生きている以上、現実社会と接続されないままに過ごせば過ごすほど、それだけ手痛い代償を払わされることになる。現に思い返してみると、やはりこの時期は辛く苦しかった。いかんせん現実が一ミリも動かないものだから、当然ながら自分自身の豊かさも増すことはなく、身を焦がすような閉塞感と焦燥感が絶えず襲いかかる中で、自意識だけが肥大化していった。
こうした状況を喝破しているのが、英国で古今最大の哲学者と目されるデイヴィッド・ヒュームである。彼の警句を引こう。
科学に対する君の情熱の身を委ねよ、と自然は言う。しかし諸君の科学をして人間的であり、かつ行為や社会に直接関連をもちうるごときものたしめよ。難解な思想や深淵な研究を私は禁止し、そしてそれらが持ち込む思弁的な憂鬱によって、それらが諸君を巻き込む終わることのない不確実さによって、さらにまた諸君の自称発見が世間に伝えられた場合に出会わざるをえないであろう冷たい応対によって、私はそのような思想や探究を厳しく処罰するという結果になるであろう。哲学者たれ、しかし諸君の一切の哲学のただなかにおいても、なお、一人の人間であれ。
原注でも述べられていることだが、ここでヒュームが言っている科学とは Science の訳で、今日で言われる科学とは意味が違うことに留意してほしい。ここで言うところの科学とは、もっと広い意味で使われていて、ニュアンスとしては学問に近い。
圧巻は最後の一文「哲学者たれ、しかし諸君の一切の哲学のただなかにおいても、なお、一人の人間であれ」だ。真理を探究しながらも、現実の生との調和の大切さを説く、ヒューム独特の言い回しが色濃く反映された箴言。そう、まさにそう。これが若かりし頃の自分にはできなかった。それゆえ思弁的な憂鬱さと世間の冷たい応対によって、罰せられることとなった。そうして傷だらけになった今となっては、このヒュームの箴言が五臓六腑に染み渡っている。
ヒュームのいう哲学者は、現代にはほとんど見られない。現代において哲学者と評されている人、哲学者を自称している人のそのほとんどは、哲学研究者であっても哲学者ではない。「哲学者たれ」のずっと手前に留まっている人たちだ。そんな有様だから、もちろん人間であろうはずもない。