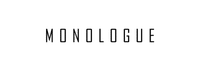Vol.017|うつ病投薬デブは甘えなのか
『MONOLOGUE』は、エッセイのようでいてコラムのようでもある、そんな型に囚われない備忘録を兼ねたフリースタイル文筆を、毎回3本まとめてお届けするマガジンです。毎週月曜午前8時に定期更新。何かと思想強めですので、用法容量を守ってお読みください。
うつ病投薬デブは甘えなのか
とある舌鋒鋭い女性配信者が「デブは甘え」と発言したことに対して、一部のリスナーが「うつ病の薬で太っている人もいるんです」とコメントしたところ、その女性配信者は「たしかにそれはしかたないんやけど」と答えていた。
ちらっと切り抜き動画を見ただけなので、細かい前後の文脈はさておくとして、この一連のくだり、どう思うだろうか。要素分解すると「デブは甘えである」「うつ病の薬で太るケースもある」「その場合は甘えではない」の三つの主張があるわけだけど、どこかに違和感を覚えないだろうか。それともごく自然なやりとりに映るだろうか。
順番に検討していこう。まず「デブは甘え」について。これは三つの主張の中では、もっともラディカルな主張であり、それゆえもっとも異が唱えられそうな主張である。現に今回のケースもそう。デブ当事者からしてみれば、おまえは甘えていると火の玉ストレートにそう言われているわけだから、そりゃあ脊髄反射で反論したくもなるだろう。
個人的には、たしかに過度な一般化の傾向は見られるものの、おおむね首肯できる、といったところだろうか。基本的にデブは甘えだと自分もそう思っている。「肥満と喫煙は怠惰の証」なんてのは、いにしえの時代から説かれていることであり、鼻を突き刺すクリシェ臭はともかく、別にこれといって違和感は覚えない。
では、次に「うつ病の薬で太るケースがある」はどうか。たしかに一部の抗うつ薬には、そういう副作用があることが報告されている。であれば薬によるケミカルな反応を、当人の意思力の問題に矮小化するのは、あまりにも酷というものだ。そのような芸当が可能ならば、この社会からあらゆる依存治療のための施設や団体は、とっくに消え失せている。人間の意思というものは、われわれが思っている以上に脆いものである。というわけで、この主張にも別に違和感は覚えない。
ここまでくればもう答えは述べたようなものだ。そう、最後に残った「その場合は甘えでない」こそが、自分が違和感を覚える主張である。
うつ病を治療する過程で薬を飲んでいたら太った。はたしてこれはしかたのないことなのか。先述したように、たしかにケミカルな反応はしかたがない。けれども、ちょっと待ってほしい。薬によるケミカルな反応はしかたがないにしても、そもそもなぜ薬を飲むに至ったのだろうか。もっとわかりやすく言い換えるならば、何があなたをうつ病の発症へと至らせたのか。
ブラックな職場のパワハラ上司が原因なのかもしれない。あるいはDV彼氏のモラハラが原因なのかもしれない。人によってその原因はさまざまだろう。けれども、それらはあくまで至近要因であって究極要因ではない。究極要因は「自分で自分を裏切ったこと」だ。
うつ病の発症へと至るその何段階も前から、あなたの魂はたしかに悲鳴をあげていた。その悲鳴を無視して、社会や周囲の声に耳を傾け続けてしまったからこそ、うつ病という形で表出したにすぎないのである。(このあたりの話は『成功曲線の実感』もあわせて参考されたい)
われわれが心に刻んでおかなければならないのは、至近要因は外部に求めることができるものの、究極要因はいついかなるときも自己に求められる、ということだ。
アウトサイド・インから
『7つの習慣』という本がある。スティーブン.R.コヴィーが著した言わずと知れた自己啓発・成功哲学ジャンルにおける古典であり、読んだことがある人は少なくないかと思う。読んだことはないものの、一度は耳にしたことがある人を含めるならば、本読みのあいだでは相当広く知れ渡っている本である。もはや全員知ってると言い切ってしまっても差し支えないほどだ。
しかしながら、その真価はあまり知られていないように思う。ジャンルがジャンルでめちゃくちゃ売れているだけに、真価を見抜く目をもたない人ばかりが手に取り、真価を見抜く目をもった人は嫌厭するという、ターゲット層のミスマッチが起こった結果、その真価があまり知れ渡っていないように見受けられる。
自己啓発や成功哲学、あるいはこれらに限らずビジネス書のたぐいが嫌いな人も、食わず嫌いしてないでこの本だけは読むことを強くお薦めしたい。この手のジャンルにしては珍しく、この本は精読する価値がある。同ジャンルの他の本を手に取る暇があるのならば、この本を再読すべきである。それぐらいよき本だ。本質を鋭く抉りとりながらも、平易な筆致で読みやすく、体験談をまじえて、実に読ませる内容に仕上がっている。
参考までに付記しておくと、自分もこの手のジャンルの本は基本的に嫌いで、ろくに物事を抽象化して体系立てることができないくせに、大上段にかまえて所詮はn=1にすぎない体験談を、まるで普遍の真理かのように語るその厚顔無恥さを見ると、はっきりいって反吐がでる。もうおまえ黙ってたほうがいいよ。あまり馬鹿だと殺されると思うから。と、ヨツバ火口の往年の名台詞を吐き捨てたくもなる。
しかも、こういうゴミみたいな本ほどよく売れるのだから、まったくもって始末におえない。自分から見れば「いやそれ本っていうか産廃じゃね」としか思えないのだけど、そういう本ほどなぜかよく売れる。そんでもってなまじ部数がでるもんだから、ますます無知蒙昧な書き手は調子づき、同じく無知蒙昧な読み手もこれは価値ある本だと錯覚する。
ああ、つくづく社会ってやつはくだらない。一生そうやって数字に踊らされて、本当に大事なことは何もわからないまま死んでいけばいい。まあ逆説的にいえば、こういう無知蒙昧人(むちもうまいんちゅ)が大半であるからして、ちょっと真贋を見抜く目を養うだけで、すぐに突き抜けられるわけだけども。
若干ヒートアップしてしまったので、ここらで話を戻そう。そんな『7つの習慣』の冒頭には、インサイド・アウトという考え方が登場する。多くの人はアウトサイド・インのパラダイムで生きているが、それではいつまでたっても問題は解決せず、幸福からは遠ざかるばかりである。そうではなくインサイド・アウトこそが、幸福へと向かうあるべきパラダイムなのだと。
アウトサイド・インとはその名のとおり外から内へ、つまり問題の原因を外部に求めようとする思考のことだ。圧倒的大多数の人々は、このアウトサイド・インで生きている。社会の縮図ともいえるSNSを見渡してみると、誰も彼もが外部にばかり目を向けて、やれあいつが悪いだのこいつが悪いだのと、延々と外部に向けて呪詛を垂れ流すばかりで、まるで自己を見つめようとしていないことに気付く。
それゆえ彼彼女らの人生は、いつまでたっても好転しない。アウトサイド・インで生きているかぎり、たとえ目先の問題が解消したとしても、根っこのパラダイムが歪んでいるので、また同じような問題に見舞われ続ける。対症療法としてのアウトサイド・イン、根治療法としてのインサイド・アウト、そう言い換えることができるだろう。
これもまた多くの人が勘違いしていることだが、医学、特に西洋医学というのは、結果であっても原因ではない。
どういうことかというと、たとえば胃に炎症が起きていれば、胃の痛みや胃もたれといった症状が引き起こされる。この時、そうした症状に見舞われる原因は「胃に炎症が起きている」ことなわけだが、これはあくまで至近要因であって究極要因ではない。ではなぜ胃に炎症が起きたのかと、まだまだその要因を掘っていけるからだ。わかりやすいのはストレスがそうだろう。
では、なぜ胃が炎症を起こすほどのストレスを受けたのか。そういう環境に身を置いたからである。ところが、同じ環境に身を置いたとしても、人によってストレスを受けたり受けなかったりする、し、同じ人でも成長するとストレスを受けなくなったりもする。さらにそもそもその環境に身を置くと決めたのは、他ならぬ自分自身である。
ということは、そうやってどんどん掘り進めていった際の原因は、とどのつまり自己のパラダイムにあるということだ。究極要因が自己にあるとはそういうことである。
このように西洋医学もまたアウトサイド・インのパラダイムに支配されている。それゆえ投薬による対処療法に留まってしまい、いつまでたっても根治しないのだ。「うつ病ですね。お薬だしておきます」じゃあないのである。人生上の問題も医学上の問題も、アウトサイド・インという同じ歪んだパラダイムによって引き起こされている。
以前、興味深い事例を目撃したことがある。数十年もの長きにわたって、ずっと薬を飲み続けてきたものの、一向に寛解へと至らなかったうつ病患者が、仏教との出合いをきっかけにすぱっと薬をやめ、ついには社会復帰をはたしたのだ。この事例は非常に示唆に富むもので、人間がいかにパラダイムに支配されているかを雄弁に物語っているように思う。
インサイド・アウトへ
大事なことなので、もう一度言っておこう。
アウトサイド・インではなく、インサイド・アウトこそが、幸福へと向かうあるべきパラダイムである。アウトサイド・インからインサイド・アウトへ。このパラダイムシフトは、劇的に人生を変革させる力がある。それぐらい強力かつ不可欠なものなので、『7つの習慣』でもそれぞれの習慣に入る前に触れられているわけだ。
とはいえ、アウトサイドの影響を一切無視せよと、そう言いたいわけじゃない。世の中にはまるでアウトサイドが及ぼす影響を、夢幻かのように語る人が一定数いるが、これはこれで正しいパラダイムではない。
「現実をありのままに受け入れる」こともまた非常に大切なパラダイムであり、アウトサイドの影響を一切無視して生きるなんて、この肉体に囚われたわれわれ人間には、どだい無理な話である。
たとえばいわゆる毒親のもとで生まれ育ち、その影響で社会人になってもくすぶっている人を考えてみよう。たしかにこの人がくすぶっている要因として、毒親の影響はあるのだろう。それはそれでたしかな現実としてまず認めて受け入れる必要がある。
すべての親は子を愛すはずだと理想に溺れることなく、また本当は親は自分を愛してくれていたのだと願望にその目を曇らされることもなく、まずは起きている現実を受け止める。これが「現実をありのままに受け入れる」ということだ。
が、しかしここで多くの人は、地続きでアウトサイド・インへと陥ってしまう。それだから今も私はこんなに苦しんでいて、今後も救われる見込みがないのだと。こうしてアウトサイド・インという狭い檻の中で、生涯をみじめに過ごすことになる。
違う、違うのだ。そうではない。今、あなたが苦しんでいて、未来に絶望しているのは、あなたがアウトサイド・インのパラダイムで生きているからだ。インサイド・アウト、すなわち究極要因はいつだって自己にあることに気づけずに、ずっと同じパラダイムの中を生きているから、変わらず苦しみ続けているのである。
アウトサイドの影響を現実として受け入れつつも、究極要因はいついかなる時もインサイドたる自己に求める。これこそが真理にかなった態度である。
たとえこれまでずっとアウトサイド・インに支配されていたとしても、われわれにはそれを断ち切る自由が与えられている。
哲学者のハンナ・アーレントは「何かを始めるその瞬間にこそ自由がある」と喝破している。なんら因果的な必然性がないにもかかわらず、われわれは突如として何かを始めることができる。その何かを始める瞬間にこそ自由は宿るのだと、アーレントはそう言う。今回は深入りしないが、決断し続ける人間の、行動し続ける人間の人生が、どんどん開けていくのはこのアーレントによる自由論と密接に関わっている。
そして、因果的な必然性がないにもかかわらず、何かを始めることができるということは、換言すれば悪習慣を断ち切ることができるということだ。これまで悪習慣に囚われていたからといって、これからも悪習慣に囚われねばならないなんて道理はない。これまでアウトサイド・インで生きてきたからといって、これからもアウトサイド・インで生きねばならないなんて道理はないのだ。
今この瞬間からインサイド・アウトで生きるのだと、そう決断すればよいのである。