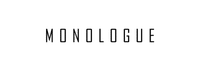Vol.018|もうこんなに書きたい
『MONOLOGUE』は、エッセイのようでいてコラムのようでもある、そんな型に囚われない備忘録を兼ねたフリースタイル文筆を、毎回3本まとめてお届けするマガジンです。毎週月曜午前8時に定期更新。何かと思想強めですので、用法容量を守ってお読みください。
もうこんなに書きたい
毎回、冒頭で触れているように、本マガジン『MONOLOGUE』は毎週月曜午前8時の定期更新を掲げている。Vol.5以降が対象なので、今でようやく3ヶ月が経過したところだ。たかが3ヶ月、されど3ヶ月。その間、一度だけ午前8時更新がどうしても間に合わず、大幅に遅れて午後8時更新になったことはあったものの、なんとか月曜更新だけは守り抜いてきた。
週に一回せいぜい5000字程度、楽勝に思われるかもしれない。だが実際はというと、月曜の早朝に書き上げるなんてことはざらで、常に締め切りに追われている。
自ら設定したにすぎない締め切りなのだから、破ろうと思えば簡単に破れるのだけど、それをやってしまうと自分は絶対に書かなくなる。これは予感というよりも、確信めいた何かだ。自分のような凡夫には、締め切りが必要なのである。悲しきかな、われわれのような凡夫は締め切りのような強制力が働かないと、すぐに言い訳を並べ立てて自己から逃走してしまう。
わかっている。誰よりも自分自身がよくわかっている。毎日こつこつ書き進めていけば、本業や生活との両立が決して難しくないことぐらいは。
ところが、これは本当に不思議でしょうがないのだけど、月曜朝に無事更新を終え、ようやく胸を撫で下ろしたかと思うと、もう次の瞬間には日曜の夜になっているのである。
その間、ずっと「書かなければ」と頭では考えているのに、思考が無限に引き伸ばされて行動に移すことができない。すなわち無量空処の領域展開。領域内の必中効果によって避けることができないので、もはやそういうものだと諦めている。決して自分の先送り癖のせいではない。決して。
そんなこんなで、いっそのこと締め切りごと虚式「茈」で吹き飛ばしてくれよと願いつつも、今もこうして書き続けている。文筆とは不思議なものだ。もう沢山だ……!!!もうこりごりだ……!!!幾度もそう思ったハズなのに、もうこんなに書きたい。
結局、自分は書くことが好きなのだ。言語によって自らの思考に輪郭を与えていくその過程が、他の何よりも楽しい。ぼんやりとした思考や閃きという素材を、言語という道具で削り取って形作っていく。ある種、彫刻のような楽しさがある。
当初、思い描いていた構成とはまったく異なったものになることも少なくない。その不確実性もまた自分を虜にして離さない要因の一つである。だからこそ、なんだかんだとこれまで続けてこれた。一時、離れることは何度もあったが、気付けばまたこうして書いている。
ちょうど一ヶ月ほど前だろうか。キングジムのDM250ポメラを買った。出先には必ずこいつを持ち歩いていて、本マガジン『MONOLOGUE』も含めて、今はすべての文筆をこれ一台でこなしている。
手に取る前は「文筆しかできんくせに高すぎわろた」と思ったが、これは愚かな勘違いであった。スマホ一台タブレット一台あればなんでもできるこの時代に、あえての文筆機能のみなのだ。究極なまでに無駄をそぎ落とし、文筆に特化したこの製品はまさに引き算の美学の結晶ともいうべきものであり、われわれを文筆ひいては自己との深い対話へと誘ってくれる。
アテンション・エコノミーなんて言われるように、ビッグテックを筆頭に注目を資源として奪い合い、ろくに集中できなくさせられている現代において、この価値は計り知れないものがある。
日常的に文筆をやる人は、ぜひ手にとってもらえればと思う。汚れやすいのがたまに瑕だが、そこにさえ目をつぶれば本当によい製品である。
宗教性なくして人生なし
前回『アウトサイドインから』にて、スティーブン.R.コヴィー著『7つの習慣』を褒めそやした。ジャンルがジャンルでめちゃくちゃ売れているだけに、何かと誤解されがちな本だけど、同ジャンルでは頭一つ、いや二つも三つも抜きん出た読みやすい上に骨太な本なので、食わず嫌いしてないで一読することをお薦めした次第である。
ただ、相当よい本であるのは間違いないものの、やはり片手落ちになっている感は拭いきれない。自己や人生、あるいは成功を語ろうと思うならば、普遍の原理原則という観点に立つならば、絶対に欠かしてはならない要素がごっそりと抜け落ちてしまっている。現代に出版されるほぼすべての本にはこれが欠落しているが、この本とてそれは例外ではないのだ。
では、何が欠けているというのか。ずばり言おう。「宗教性」である。神や霊といった宗教性を欠かしたままに、どれだけ自己や人生を語ろうとも、すぐに限界にぶち当たってしまう。それもわりと早い段階で。なぜなら『死を前にしてはすべてが茶番』だから。この壁は宗教性を欠いては絶対に乗り越えられない。
多くの現代人は誤解している。神や霊なんてものは、前時代的な負の遺物であり、われわれ現代人は科学の力によって、ようやくそうした宗教性の呪縛から解き放たれたのだと、大なり小なりそう思い込んでいる。
馬鹿馬鹿しい。そういう致命的な誤解をし、さらにはそのことに無自覚であるからこそ、あなたがたはいつまでたっても自分の人生を生きられない、生命を躍動させることができないのだ。
真に科学的思考を突き詰めた者ならば、その限界もよくわかっている。どこまでが科学で扱える領域で、どこからが信仰の領域となるのか、その境界線がはっきりと見えている。哲学者のカール・ポパーは、この境界線のことを反証可能性と呼んだことで知られるが、中途半端に科学をかじった人間ほど、反証可能性を考慮せずに神や霊を否定する。越権行為もいいところだ。
世界的に高名な物理学者が、突然スピリチュアルなことを言い出して、世間をざわつかせたりするが、あれは別に不思議な話でもなんでもない。彼らは科学の限界を悟り、名誉もプライドもかなぐり捨てて、その境界線を勇気をもって踏み越えたのだ。ゆえに「あの人も終わったな」なんてのは、的外れな見解でしかない。終わっているのはその勇気を賞賛できないおまえのほうだろうよと。
人間賛歌は勇気の賛歌、人間のすばらしさは勇気のすばらしさ。さぞご立派な大学を危なげなく単位を取得して卒業したのだろうが、完全なるジョジョの履修不足である。もう一度ツェペリ男爵からやり直してきたまえ。
人は宗教的動物である
古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、主著の一つである『政治学』において、次のように述べている。
「人間は本性においてポリス的な(社会・共同体的な)動物である」
また、アリストテレスはこうも言っている。「孤独を愛する者は野獣か、しからずんば神なり」と。つまり、人は自然と社会・共同体を作って生きる動物なのだから、そうした社会・共同体を拒否して孤独に生きようとする者は、もはや人ではなく野獣か、それとも完全たる神であるか、そのどちらかであるというわけだ。
いわゆる無敵の人を思い浮かべてみると、まさにそのとおりだなと思う。共同体の一員として生きることを拒否し、幼稚な精神のまま孤独に大人になってしまった結果、手がつけられない野獣と化してしまったのが、彼ら無敵の人である。
アリストテレス哲学に照らせば、そういう生き方は人間の本性から外れた歪な生き方である。人間の本性から外れた生き方をしていては、当然ながら人間らしさが育まれることもない。
とはいえ、群れていればそれでよいのかというと、そういうわけでもない。孤独に陥ってはならないが、孤高ではあらねばならない。孤独と孤高は似て非なるものだ。そして似て非なるものは、似ているけれど非なるものである。
孤独と孤高の違いは、英語でいえばLonelinessとSolitudeの違いで、その違いは「自己に共にあれているかどうか」にある。孤独は自己を疎外し、孤高は自己を精錬させる。真に共同体の一員となるためには、孤高を通して自己を確立せねばならない。自己を確立していない者は、たやすく共同体の価値観へと飲み込まれてしまうからだ。こうして人は全体主義へと陥る。そして全体主義がいかに危険であるかは、これまでの歴史が示す通りである。
さて、ここでアリストテレスの言葉を借りて、自分も一つ主張しておきたいことがある。すなわち「人は本性において宗教的な動物である」と。
神や霊を求めるのは、人間の本性である。これが人間の本性であることを認めずに、無理矢理そこに蓋をするような真似をするから、誰も彼もが不幸そうな面をして生きているのだ。少なくない人たちが精神を病んでいるのだ。自己の深いところから湧き上がる宗教性を認めることは、なんら恥ずべきことではない。それは人間としての本性なのだから。
ニーチェが神の死を宣言してから、約150年といったところか。本当に神は死んだのだろうか。いいや、神は死んでなどいない。たしかに近代におけるキリスト教的世界観は崩壊し、科学的思考が支配的となった現代においては、もはや神の存在など誰も信じちゃいない。まともに神の存在を論じようものなら、下手をすれば狂人扱いである。
だが、しかし誰がなんと言おうと、神はあいかわらずわれわれと共にある。これまでも、これからもずっと。なぜなら神とはこの世界そのものだからだ。ゆえに神はすべてに宿り、すべてを内包する。その意味で神即自然を洞察した哲学者のスピノザは、まさに慧眼であった。
自分は人生のテーゼとして「Servus Dei」を掲げている。これはラテン語で「神の僕」を意味する。忠実なる神の僕として、人生をかけて神の存在証明に取り組みたいと思っている。
それは言葉によって為されるようなものではなく、「あんな生き方ができるならば、この世界に神はいるのかもしれない」と、そう思ってもらえるような生き方をすることで、はじめて為されるものだと考えている。語りえぬものについては、沈黙せねばならない。