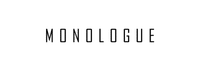Vol.011|人間関係の定期リセットは当たり前
『MONOLOGUE』は、エッセイのようでいてコラムのようでもある、そんな型に囚われない備忘録を兼ねたフリースタイル文筆を、毎回3本まとめてお届けするマガジンです。毎週月曜午前8時に定期更新。何かと思想強めですので、用法容量を守ってお読みください。
人間関係の定期リセットは当たり前
世の中を見渡していると、勘違いされてんな~と思うことが数えきれないほどある。それはもう掃いて捨てるほどに。「人間関係のリセット」もその一つだ。「人間関係のリセット」と聞いて、おそらく多くの人はネガティヴなイメージを抱くんじゃないだろうか。
しかしながら、人間関係というものは、自己をまっとうすべくちゃんと生きていれば、定期的にリセットされて当たり前のものである。それゆえ中高時代の友人とずっと仲良くやってますみたいな話は、別に美談でもなんでもない。それだけ成長していないことの証でもあるのだから。むしろ、本来は恥ずべきことである。
たまたま同じ地域に生まれ育っただけの同年代の人間が、同じ速度で自己をまっとうすべく生きて成長しているなどとは、とてもじゃないが考えづらい。そういうケースもなくはないものの、もはや無視してもなんら差し支えないほどのレアケースであり、まず間違いなく両者ともに停滞していると考えてよい。
それは「自己をまっとうすることこそが人生における至上命題である」の前提に立つならば、互いに足を引っ張っているだけの歪な関係である。自己から目を背けた者同士が慰め合う、ある種の憐れむべき共依存関係でしかない。
ある日突然、それまで築いてきた人間関係をリセットする人種がいる。人間関係リセット症候群とも呼ばれ、一種の病気扱いされている現状があるわけだが、自分に言わせればあれは別におかしなことでもなんでもない。
たしかにやり方自体は褒められたものではないかもしれない。不誠実といえばそうなのだろう。目の前の現実から逃避している面は否定できない。なるほどそれは弱さでもある。けれども、その根底には何があるのかというと、「自己をまっとうしたい」という魂の慟哭である。
だからこそ、その内なる叫びに真摯に耳を傾け、やり方は稚拙であったかもしれないが、まがりなりにも勇気を奮い立たせ、実際の行動に移したという点を鑑みると、そういう人は伸びしろがあるなと感じる。逆に何の疑いもなく、ずっと同じような関係をだらだらと続けている人には、まったく伸びしろを感じない。
これは地理的にもそう。自己をまっとうすべくちゃんと生きていれば、そのステージに見合った場所へと自然に移動するものだ。ただし、ここでいうステージとはいわゆるライフステージのことではない。あくまで自己の確立という意味でのステージである。それゆえ生まれてこのかたずっと地元で過ごしてますみたいな人は、もうその時点でだいぶ見込みが薄い。
本人は居心地の良さを感じているのかもしれないが、実際はぬるま湯に浸かっているだけであり、自己の確立という観点から見れば、その地元はある種ゲットーでしかない。自己の確立こそが人間性を育むのであり、その人間性を育む機会が剥奪されているのだから。早いとこ抜け出せよ、ぬるま湯ゲットー。
ところで、なにかと可燃性の高いことで知られる元AV女優の三上悠亜さんは、AV業界に入る前にそれまでの人間関係をリセットしたという。そのことを告げた番組内では、やはりというかなんというか、共演者の女性からは「そういう人っているよね~」と、わりと否定的なニュアンスで捉えられていた。
番組のすべてを視聴したわけではなく、あくまで切り抜きをちらっと見ただけではあるものの、この共演者の女性に対して、自分は率直に「こいつなんもわかってねえな」と思った。彼女は自己をまっとうすべく、覚悟をもって差別と偏見に満ち満ちたAV業界へと足を踏み入れた。そのためにはそれまでの人間関係を断ち切る必要があったのである。
おそらく彼女は「自己をまっとすることこそが人生における至上命題である」を肌感覚で理解している。炎上中の対応なんかを見ていると、それがよく伝わってくる。誰が何と言おうが、私は私をまっとうするだけなのだと。そういうスタンスで生きているであろうことが、発言や振る舞いの端々からありありと見て取れる。
自分は彼女のファンでもなんでもないので、擁護しようなんて気はさらさらないが、客観的に事実を指摘するならば、自己をまっとうせんとしている彼女に対して、SNS上でがたがた文句を並べ立てている人間というのは、男女問わず総じてろくに自己の確立ができていない、有り体にいってしまえばカスである。
自己の確立ができていないからこそ、そうやってよく知りもしない他人にがたがたと文句を言うのだ。他人の一挙手一投足が気になってしかたがないのは、それだけ自己と共にあれていない証である。彼女とそういう有象無象のカスたちとでは、生きるステージが何段階も違う。そりゃあろくに会話も通じないわけだ。周囲が勝手に騒ぎ立てるばかりで、肝心の本人が蚊帳の外へと追いやられるはずである。
IQが20違えば会話は通じないとは、よく言われる俗説だが、本質的な問題はそこではない。問題の本質は「どのステージで生きているか」である。生きるステージさえ一致していれば、たとえIQに差があったとしても、世界そして自己と向き合う態度は共通しているので、ちゃんと会話は通じるものだ。
なぜ全身ハイブランド固めマンは痛いのか
三上悠亜さんは、自身が理想とする女性像を体現するファッションブランド『MISTREASS』をプロデュースしていることでも知られており、こうした事象からもまた彼女が「自己と共にあること」を志向していることが読み取れる。
全身ハイブランド固めマンが、痛々しくて見てられないのはなぜか。自己こそが最大のブランドであり、どれだけ名の知れたハイブランドでその身を固めようとも、決して自己の代替品とはなりえないことを、まるで理解していないからである。それゆえ必然的に耐えがたいペラさがデバフされてしまう。
にもかかわらず、いつまでたってもそのことに当の本人だけは気づかないという地獄。あれか、そのたっけえバッグはパンドラの箱か何かなんか。これみよがしにアピっているそのでっけえロゴは、箱に刻まれた紋章か何かなんか。どう見てもあらゆる災いが詰まってるやないか。
中世の哲学者トマス・アクィナスは、主著『神学大全』において、人間は神へと向かうべき存在であるにもかかわらず、しばしば神に代わるものに執着し、それに溺れてしまうと述べている。
神の代替品として挙げられているのは、富・権力・快楽・名誉であるが、これは現代を生きるわれわれにも通ずるものがある。通ずるものがあるというか、そっくりそのまま適用できるといっていい。現代社会を見渡してみると、誰も彼もがこの四つのいずれかに溺れ、自己から目を背け続けていることに気付く。
そして、自己から目を背けるということは、すなわち神へと背くことに他ならない。なぜなら、自己〈ミクロコスモス〉と神〈マクロコスモス〉、二つのコスモスは互いに照応しているからだ。このあたりの話はややこしくなるので、今回は詳しい話は割愛するが、ともかくそういう構造になっている。
これは以前にも書いたことであり、今後も折に触れて主張していきたいことの一つなのだけど、知性とは学歴でも職歴でも、ましてやIQでもない。知性とは「自己と共にあること」だ。その自己と真摯に向き合う態度こそが知性なのである。その意味で、全身ハイブランド固めマンに知性はまるでないといえる。ドラミング中のゴリラとかのほうがまだ賢い。
別にブランド品を一切買うなと言ってるわけじゃない。買うにしても自己というブランドをより洗練させる目的で買うべきだと、そう言いたいまでだ。ブランド品に限らず、すべての消費行動は自己というブランドの確立へと接続されるべきである。
Creepy Nuts屈指のボースティング曲である『耳無し芳一Style』には、こんなバースがある。
奇抜な髪型と
ド派手なお召し物
でも黒シャツ一枚の
俺にしか目がいかない
いや、最高かよ。これこそがまさに自己のブランド化である。黒シャツ一枚でなんら着飾らずとも、ラップを通して自己と向き合い続けることによって、磨き抜かれた自己というブランドが、人々の目を惹きつけて離さない。R指定がいかにバケモンであるか、全身ハイブランド固めマンには、生涯をかけても理解できないことだろう。
凡庸一確フレーズ
これは当該方面に対して喧嘩を売るタイプの尖った持論なのだけど、これからますます加速していくAI時代においては、当たり障りのない綺麗事にまみれた優等生言説で溢れかえるであろうことは想像に難くないので、ここは果敢に攻めていきたい。尖ってこそ人間、歪んでこそ人間、揉めてこそ人間なのだから。
自分の中には、それを言った瞬間に凡庸な人間であることが確定し、もはや人間存在としてのセンスに見切りをつける、そういういわば凡庸一確フレーズというものがいくつか存在する。凡庸図柄が三連で1リール目にズドンするわけだ。これが7絵柄で「がーっはっはっは」からの「じゃっきーん」であれば大歓迎なのだが、いかんせん凡庸さのリーチ目なので笑えない。
最近はあまり見かけることはなくなったが、一世を風靡した凡庸一確フレーズの一例をあげると、たとえば「死ぬこと以外かすり傷」とかがそう。
断言してもいい。こういうフレーズを用いる人間というのは、ろくに死と向き合ったことがない凡庸きわまりない人間のくせに、大上段から構えて人生論を語りたがる自分に酔っただけのワナビー野郎である。いいからぎりぎり死なないレベルの傷を負って黙っとけと。
「人生なんて所詮は死ぬまでの暇つぶし」も、わりとよく見られる凡庸一確フレーズである。こちらは流行り廃りに関係なく、いつの時代も一定の支持を集めている。一生そのまま暇をつぶしてろと、自分からすればそう一蹴したくなるフレーズだが、なぜか根強い支持がある。
こうした凡庸一確フレーズを用いる人間の特徴は、歴史・宗教・哲学といったリベラルアーツ系科目に、まったくといっていいほど触れてきていない点にある。それもそうで、一度でもこれらと真摯に向き合ったことがある人間ならば、絶対に凡庸一確フレーズになびいたりなどしない。それがいかにぺらっぺらの言説であるかが、一目でわかるからだ。ぺらっぺらの言説に惹かれるのは、相応にぺらっぺらの人間だけである。
自分が嫌悪感を抱くのは、対象とろくに向き合ったことがないくせに、まるでその対象の全容を掴んだかのような口ぶりで、対象を語らんとするその見るに堪えない傲慢さである。傲慢な人間だけは本当に度し難い。世界と真摯に対話しようともせず、またその世界に生きる自己とも真摯に対話しようとしないからこそ、能天気にそんな傲慢な態度がとれるのだ。
リベラルアーツ系科目を学ぶ意義とは、とどのつまりこの対話の技法を修得するためにある。