イタリア人の僕が、マンマに内緒で「ナポリタン」を崇拝する理由。考案者はマジで天才だ
イタリア人にとって「パスタ」とは、ただの炭水化物ではない。
宗教であり、歴史であり、アイデンティティそのものだ。麺はアルデンテでなければならない。ソースは素材の味を最大限に活かさなければならない。そして何より、「ケチャップをパスタにかける」なんて行為は、イタリア刑法で裁かれるべき重罪だと教わって育った。
もし僕が実家に帰って、マンマやノンナ(おばあちゃん)の前で「今日はケチャップでパスタを作るよ」なんて言おうものなら、家を追い出されるどころか、一族の恥としてピエモンテの山奥に幽閉されるかもしれない。それくらい、イタリア人にとってケチャップパスタはタブー中のタブーなのだ。
しかし。
今日、僕はここで、ある重大な告白をしなければならない。
僕は、日本の「ナポリタン」を愛している。
いや、愛しているどころではない。崇拝していると言ってもいい。
そして、この「ナポリタン」という、イタリアには存在しないイタリア風料理を考え出した日本人シェフは、間違いなく歴史に名を残すべき天才だ。この料理が生まれた瞬間に立ち会えるなら、僕はタイムマシンを使ってでも過去に戻り、そのシェフの手を強く握りしめて「Grazie!」と叫びたい。
なぜ、イタリア人の僕がここまでナポリタンに魅了されたんだろう?ナポリタンについて深く知れば、この謎が分かるかもしれない。そう思って少し調べてみたら、イタリア料理の常識を覆す、日本人の凄まじい「アレンジ力」と「味覚の天才性」が隠されていたのだ!
「アルデンテ」を捨てた勇気
まず、ナポリタンの最大の特徴であり、イタリア人が最初につまづくポイント。それは「麺」だ。ナポリタンの麺は茹で置きが基本。アルデンテ?そんな言葉はナポリタンの辞書にはない。一度茹でてからあえて時間を置いて、ふにゃふにゃになった太麺。これをさらにフライパンで炒める。
来日したばかりの頃、初めて喫茶店でナポリタンを食べた時の衝撃は忘れられない。
「なんだ、このうどんのような食感は……!」
口に入れた瞬間、脳内のイタリア人としての警報が鳴り響いた。コシがない。小麦の香りが、油とケチャップの匂いで完全に書き換えられている。
でも、2口目を食べたとき、その警報は止んだ。「……あれ?これ、めちゃくちゃうまいんじゃないか?」
気づいてしまったのだ。
この「茹で置きされた太麺」こそが、濃厚なケチャップソースを受け止めるための最高なキャンバスであることに!もしこれがアルデンテの細麺だったらどうなるだろう?きっと、ソースが絡まず酸味が立ちすぎて、口の中で喧嘩をしてしまう。麺が水分を吸ってもちもちとした食感になることで、初めてあの強烈な味付けと対等に渡り合えるのだ。
イタリア料理の根幹である「アルデンテ」を捨てる。その常識外れな決断をした考案者は、パスタという食材を「イタリアのもの」としてではなく、純粋な「食材」としてフラットに捉えていた証拠だ。この柔軟性。これこそが天才の所業である。
「炒める」という魔法
イタリアのパスタは、基本的には「和える」料理だ。ソースと茹で汁を乳化させ、麺に絡める。だが、ナポリタンは違う。「炒める」のだ。焼きそばのように、鉄板やフライパンでガンガンに炒める。
ここにも天才的な発想がある。ケチャップというのは、そのまま舐めると酸っぱくて甘い調味料だ。でも、高温で炒めることで酸味が飛び、代わりに香ばしさと深い甘み、つまり「コク」が生まれる。具材の玉ねぎやピーマン、そしてあの赤いウインナー。これらを麺と一緒に油で炒め合わせることで、すべての旨味が一体化する。
特にピーマン!あの苦味!イタリアのパスタでピーマン(あるいはパプリカ)を使うときは、じっくりローストして甘みを引き出すことが多い。一方、ナポリタンのピーマンは、シャキシャキとした食感と青臭い苦味を残している。この「苦味」が、甘ったるいケチャップ味の中で唯一のアクセントになり、飽きさせない役割を果たしている。これを計算して入れたのだとしたら、考案者は味のオーケストラを指揮するマエストロだ。
さらに、熱々の鉄板に乗って出てくるスタイルの場合、底の方で少し焦げた麺ができる。この「おこげ」のカリッとした食感と香ばしさ。これはもう、パスタ料理ではない。「焼きパスタ」という新しいジャンルだ。イタリア人が思いつかないのも無理はない。僕たちはパスタを焼こうなんて、2000年間一度も考えなかったのだから。
日本人の口に合い、外国人も虜にする「洋食」の完成形
ナポリタンは、イタリア料理の真似事なんかではない。日本人の主食である「米」に合うおかずの論理で構成された、完璧な「日本の洋食」だ。
味が濃い。旨味が強い。だから、ナポリタンをおかずに白米が食べられるという日本人の意見も、今なら理解できる(実際にやるかどうかは別として)。そして不思議なことに、この味はイタリア人の僕にとっても、どこか懐かしい。トマトソースのパスタとは違う、お母さんが冷蔵庫の余り物で作ってくれたような、温かくて飾らない味。
実は、僕の周りの在日イタリア人たちも、声を大にしては言わないが、ナポリタンが好きだという人は多い。「あれはパスタじゃない。ナポリタンという別の食べ物だ」と言い訳をしながら、粉チーズとタバスコをたっぷりかけて、ホクホクの笑顔で食べている。そう、タバスコ。あれもイタリアにはない。
しかし、ナポリタンには不可欠だ。甘みの中にピリッとした刺激を加えることで、味が完成する。この「味変」まで含めてデザインされているとしたら、恐ろしいほどの完成度だ。
過去に戻って伝えたいこと
ナポリタンの発祥には諸説あるけど、横浜のホテルニューグランド、2代目総料理長の入江茂忠シェフが、進駐軍が食べていたケチャップパスタを見て、もっとちゃんとした料理にしようとトマトピューレを使って改良したのが始まり…とか、あるいは横浜のセンターグリルがケチャップを使って大衆化させた…とか、歴史を紐解くだけでも面白い。
だけど、誰が元祖であれ、「茹で置き麺×ケチャップ×炒める」という形を完成させた人は、間違いなく天才だ。戦後の日本で手に入る食材で、いかに美味しく、いかに腹持ちよく、いかに人々に活力を与えるかを考え抜いた結果生まれた奇跡。
もし僕が過去に戻れるなら、その厨房に忍び込んで、中華鍋を振るシェフの背中に向かってこう言いたい。
「マエストロ、あなたが今作っているその赤い料理は、2025年の未来でも愛されています。日本人はもちろん、遠い国から来たイタリア人の僕でさえ、この味に救われているんです。イタリアの常識を壊してくれてありがとう。あなたはパスタの歴史を変えたんです!」
そして、出来立てのナポリタンを一口食べさせてもらって、「Buono! これ考えた人、マジで天才!」と叫ぶだろう。
週末、僕はまたいつもの喫茶店に行くつもりだ。おしゃれなカフェの洗練されたパスタもいいけれど、今の僕が求めているのは、銀色の皿に乗った、口の周りが赤くなるあのナポリタンなのだ。
粉チーズを雪のようにかけ、タバスコを数滴。フォークで巻き取るたびに感じる、もちもちとした重量感。一口食べれば、そこには日伊の文化の壁を越えた、「美味しい」というシンプルで力強い真実がある。
イタリア人の僕が言うのだから間違いない。ナポリタンは、世界に誇れる日本の傑作だ。
いいなと思ったら応援しよう!
 みなさんからいただいたサポートを、次の出版に向けてより役に立つエッセイを書くために活かしたいと思います。読んでいただくだけで大きな力になるので、いつも感謝しています。
みなさんからいただいたサポートを、次の出版に向けてより役に立つエッセイを書くために活かしたいと思います。読んでいただくだけで大きな力になるので、いつも感謝しています。

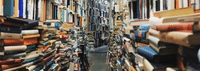

こちらの動画にもあるように、イタリアも最近は伝統から一歩進んだパスタ料理があるようですよ! https://youtu.be/ycrgr0_vzkE?si=mL20ZDVT0PBVXmce
スパゲッティが大好き 温泉卵・オリーブオイル・ガーリック とあと何かを入れると 最高のスパゲッティの完成です😊🫶
赤いウィンナーも入れて欲しい。
書いてくださってありがとう。 あなたの表現力に感服します。