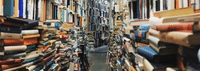「数学は役に立つか?」より大事なこと
下記の文章は、私が今年の某月某日に熊本県立熊本高校で1年生向けの講演をしたときの講演原稿に少し手を加えたものです。講演には特にタイトルはありませんでしたので、上のタイトルは後で私が付けました。講演の依頼及び原稿の掲載に同意して頂いた熊本高校の諸先生に感謝致します。
皆さん、こんにちは。今日は「世界の中の日本」という視点から今後の学問のあるべき姿や、そんな中で「頭を使う」とはどういうことかについてお話しするようにご依頼を受けています。これらについて、まずは私自身の経験から始めようと思います。
私は今から30年前、1995年の6月から1ヶ月半ほど、初めて数学の研究のための旅行でヨーロッパを数カ国旅しました。当時私は京大の博士課程の学生で、特にグラントやフェローシップもなかったので、自費で旅行しました。自費だったところが、実はよかったと思っています。いろいろ吸収しようと本気で頑張らざるを得ないですからね。
その旅行でできた多くの人脈はいまでも続いています。研究者を続けていると、時間が経てば経つほど、「誰と知り合い、誰と話し続けているか」が自分の研究の多くの側面を支えていることに気づきます。
旅行から得られたものとして、さらに大きかったのは、旅行中にドイツの大学で、自分の修士論文の内容を何回か講演させてもらえたことです。それがきっかけになって、後にその大学から研究員として来ないかというオファーをもらいました。これによって、旅行が終わってほんの数カ月後、1995年の10月から私は急遽ドイツに留学することになったわけです。自分の人生の方向が、ひとつの旅と、そこでの対話によって突然開けた。いま思い返しても、かなり大事な出来事だったと思います。
ここで、私がヨーロッパで強く感じたことをお話ししましょう。欧米の研究者たちは、会話によって学問を進めている面がとても大きいです。もちろん彼らも一人で机に向かいます。ただ、何か新しいことを考えるときや、考えが詰まったときには、すぐに誰かと議論します。研究室や廊下やカフェで短い会話が何度も生まれ、その中からアイデアが育っていく、という感じです。
それに対して日本人は、やはり個人で机に向かい、紙と鉛筆でじっと考える時間をとても大切にします。これは良い悪いの問題ではなく、文化的な趣向の違いだとは思います。ただ、ドイツで研究生活を始めてみて、私はそこにある種の「頭の使い方」の違いがあることを強く感じました。欧米流の学び方は、専門分野の知識を深めるだけでなく、それを他分野や社会と統合し、対話を通じて新しい価値を生み出していくように進んでいきます。つまり「頭を使う」というのは、ただ自分の専門を掘り下げることだけではないんだ、というわけです。
日本人にとって、こういう頭の切り替えは簡単ではありません。私自身、最初はうまくできませんでした(今でもうまくできているかどうか怪しいです)。議論のスピード、言葉のぶつけ方、意見の違いを恐れず前に進む姿勢、そういうものに慣れるまでには、ずいぶん時間がかかりました。でもこれは訓練で何とかできるものだと思います。結果として、個人的に深く掘り下げる思考法と、対話によって物事を総合していく力の両方が体得できれば、研究者としても、人間としても、単純に得だと思います。
海外経験を積むことのよさはほかにもあると思いますが、私の場合、発想や異なる意見・やり方・価値観を得るチャンスになったと思います。海外に行く価値は、語学が上達することだけではありません。違う学問の作法、違う社会の空気、そして違う「頭の使い方」を体に刻むことにもあります。
さて、もう一つ、日本人の学問観と欧米人の学問観の違いについて、私が常々感じていることをお話しします。
まず大前提として、数理科学や自然科学というのは、人間が有用な知識を少しずつ蓄えながら、歴史上弛みなく連続的に発展してきたわけではありません。その歴史には、普通の政治史や社会史と同じように、繁栄と滅亡の繰り返しがありました。
西洋科学は、実は11世紀以前にはほとんど存在しませんでした。その頃のヨーロッパは生活・文化の水準が低く、イスラム帝国の文化や科学に大きく遅れをとっていました。いわば当時のヨーロッパはあらゆる面で「後進地域」だったわけです。
12世紀になってようやく、ヨーロッパで学問の復興が始まります。ちょうど日本の明治維新のような、知の近代化運動が起きたのです。アラビア世界の科学や哲学、数学を大量に輸入し、遅れを取り戻すために、多くの人たちが懸命に努力しました。
そしてそこから、微分積分学の発見や万有引力の発見など、西洋が本当の意味で「自分たちの科学」を作り上げるのが17世紀です。つまり、輸入した科学を土台にして独自のやり方を完成させ、自分たちの科学として再構築するまでに、大まかに見ても5世紀くらいかかっているわけです。
その長い時間の中で、ヨーロッパの人々は科学が産業への影響などを通じて現実に世界を変え、自分たちの生活を変えていくことを何度も体験したのだと思います。科学は机上の空論ではなく、社会や経済や技術を通じて歴史そのものを動かす力だという実感を、彼らは積み重ねてきました。周辺地域から多様な数理科学を受け取ったヨーロッパ地域では、知や技術がさまざまな階級の人たちに浸透しました。大航海時代を支えた航海術は、まさに当時の最先端数理科学の結晶でした。知の胎動は宗教改革の遠因ともなり、その後の歴史を決定づけました。もちろん、産業革命では直接的に目にみえる変化の力を、科学は実証的に示してきました。ですから欧米では、科学や数学が「世界を変える武器」であり「未来を作るエンジンだ」という感覚が、文化の至るところに根づいていると思うのです。
では対する日本はどうでしょうか。日本は19世紀後半、明治維新のときに大きな決断をしました。和算など、江戸時代まで日本人が培ってきた数理科学や自然科学のやり方を一旦捨て、西洋の数理科学を輸入することを選びました。江戸時代にも日本には高度な数理科学が存在していました。しかしそれは、いわゆる「無用の用」として、直接社会を変える技術というより、個人の精神を鍛え、能力を高めるための高貴な文化的素養として位置づけられていた面が大きかったと思います。
明治維新以後に入ってきた西洋の数理科学を、日本人は持ち前の吸収力で急速に学びました。これは素晴らしいことです。ただし忘れてはいけないのは、それが「すでに完成されたレディメイドの科学」だったという点です。その点は初発の西洋科学も同様でした。彼らは5世紀かけてゆっくりそれを吸収しましたが、日本人は科学を輸入し、理解し、急速に自分のものにする力に長けていました。その点で確かに日本人はすごかったと思います。しかし数学のような理論科学が歴史の中で「実際に社会を変える力を持つ」という実体験を、自分たち自身の手で積み上げてきたのではなかったわけです。
明治維新以降、日本の科学技術は高度に進みました。現時点でも、日本の数学や自然科学が世界で占める位置は高いと思います。けれども、その割に日本では理論的科学が「世界を変える力を持っている」という意識が、欧米に比べるとやや薄いように感じます。
例を挙げましょう。江戸時代の和算の世界では円周率を、(そろばんによる)計算で小数点以下40桁も(加速)計算できるほどの高度な数理科学と計算技術がありました。これは当時の世界の水準を上回るものです。しかしそれを、社会や世界の仕組みを変える原動力だとは考えなかったわけです。数学を「精神の鍛錬」として見る姿勢は尊いのですが、その一方で「数学が世界を動かす」という感覚は育ちにくかったのかもしれません。
この状況は、実は現在でも続いていると思います。いま世界では、機械学習、データサイエンス、人工知能の研究がとても盛んです。私も、自分が所長を務める数理科学の研究所(ZEN数学センター)で数学とAIと証明支援系の技術について研究しています。
しかし、この手の研究ではどうしてもGoogleやMetaなど、海外の巨大IT企業に敵わないところがあります。なぜでしょうか。技術力や資金力、データ量など、いくつも理由はあります。ただ私は、その根っこには「数理科学が世界を変える」という感覚をどれだけ本気で信じ、その未来に投資できたか、そこに大きな差があったのではないかと思っています。
ITの草創期に、どのくらいの人が「ITがこれほど世界を変える」と予測できたでしょうか。おそらく予測できた人は少なかったはずです。しかし、その少なかった人たちは、それで「世界が変わる」と信じて突き進んでいきました。そしてそのような、当時は何なのかよくわからなかったアイデアに投資し支援する社会的な仕組みや雰囲気があったか否かが、結局は決定的な違いを生んだのではないでしょうか。科学や数学の未来は予測しにくいところがある。だからこそ「これが世界を変えるかもしれない」と賭けられるかどうかが重要になるのです。
皆さんも「数学は役に立つのか?」という問いは何度も聞いたことがあると思います。でも、本当に重要なのはむしろ「数学は世界を変えるのか?」という問いです。役に立つかどうかは、現時点での用途の話にすぎません。しかし世界を変えるかどうかは未来の話です。
要するに、この30年くらいで日本人は「数理科学はただの理屈ではない。それは世界を変えるのだ」ということを痛いほど学ぶことになったのではないかと、私は思うのです。インターネット、スマートフォン、AI、データ社会。これらは全部、数学と理論科学が実際に世界を変えた結果として現れているわけです。
では、日本はもうダメなのか?というと、私はそうではないと思います。まだ遅くはないと思っています。日本人の研究者の能力は非常に高く、そのアイデアは素晴らしいです。ただ、それらが「もしかしたら世界を変えるかもしれない」という社会全体の意識が、少々薄いのが問題なのです。12世紀のヨーロッパが、輸入した科学を土台に自分たちの科学を作り上げたのと同じように、日本人も明治維新で吸収した西洋の数理科学を、いまからでも本当の意味で自分のものとして再構築し、自分たちなりの方法で世界を変えていくことを目指すのは十分可能だと思います。
そのために必要なことは何でしょうか。私は、学問をする人たちが、数理科学も自然科学も人文科学も、もっと活発に交流し、個人の努力だけでなく、多くの人と会話しながら学問を進めることが、いよいよ重要になると考えています。冒頭にお話しした、個人的に深く掘り下げる思考法と、対話によって物事を総合していく力の両方を駆使していくことです。
重要なのは、学問とは一部の学者だけがするものではない。本当は社会の人たちみんなが関わる事業なのであり、みんなの知恵が混ざり合う場所なのだということです。そして、その実現のためには異なる背景をもつ人たちが活発に対話を繰り広げることが重要だと思うわけです。
そういう意識が育つ土壌が、この国でももっと豊かに育っていってほしい。私はそう願っています。そのためにも、まずは皆さんには、ぜひ積極的に外国に出て行き、いろいろな人と出会い、話し、学んでみてほしいと思うのです。また皆さんが将来、大学や研究所だけでなく、民間や官庁など、社会のどんなところで仕事をすることになったとしても、学問は世界を変える力を持っているということを常に意識してほしい。そしてそこに投資し助成することは、大きく変化する未来を迎えるための大切な「備え」なのだという意識を持ってもらえたらと思います。
海外に出ることは、単に「外を見る」ことではありません。自分の頭の使い方を広げ、自分の学問観を揺さぶり、そして自分の未来の可能性を予想もしない方向に開いていくことです。私の人生が1995年の旅で大きく変わったように、皆さんの人生も、ひとつの旅と対話で思わぬ形に変わることがあり得ます。
皆さんがこれからどんな道に進むにせよ、「自分の専門を深めること」と「それを社会や他者と統合していくこと」の二つを、ぜひ意識して歩んでほしいと思います。世界はまだまだ変わっていきますし、その変化の中心に皆さんの世代が立つ可能性は十分にあるからです。
まあ、とはいえ、未来のことはわかりません。30年前に今の世の中が見えていれば、私の人生は大きく変わっていたことでしょう。そして皆さんの多くも30年後の未来を予測することはできないでしょう。そのこと自体は難しいにしても、変わり得る未来に対するアンテナを少しだけ注意深く張り巡らせ、学問の未来に期待してほしい。そうすればいつでもワクワクする未来を迎えることができるのだと思います。