自己紹介②:COOまでの道のり ー 何が分岐点になったのか ー
このnoteは自分の体験やコーチ・トレーナーとしての伴走の経験に基づいて、COOやマネジメントについて考えることを目的としているのですが、今回はそもそもCOOを含む「経営者」とは何かということを考えてみたいと思います。
私は起業経験はなく、抜擢される形で経営者になりました。つまり、後天的に経営視点を身につけた人間です。経営者として優秀かどうかはさておき、会社の急成長に伴って急激に役割が変わり、荒波に揉まれるがごとく順応したプロセスについて、どういう分岐点・転換点があったのか振り返ってみたいと思います。
ちなみに前回の自己紹介①はこちらです
1. 急に管理職を任されることになった経緯
1社目ではwebデザイナーとしてキャリアをスタートして、ユーザサポートや営業など様々な仕事をさせていただいたのですが、マネジメントの役割になったことはありませんでした。
それが、2社目のpaperboy&co.社(現GMOペパボ社、以下ペパボ)に入社してから数ヶ月で管理職になり、2年経たないうちに取締役になりました。
これは完全に当時の会社の状況と成り行きの話ではあるのですが、それまでまともにマネジメント経験もなかった自分が、事業部長〜東京・福岡2拠点の統括責任者〜取締役〜上場プロジェクトの事業部門責任者〜上場企業取締役という変遷の中で、徐々に経営視点で物事を考えるようになるには、いくつかのシチュエーションや転換点があったのだと思います。
まず、ペパボの入社当初、組織は典型的な「鍋蓋型」でした。社長がいて、それ以外はメンバー横並びという構造です。創業した福岡に祖業のレンタルサーバーとドメインのスタッフを残し、本社機能と新規事業のブログチームだけが東京にきたという状況です。
私はといえば、当時の社長の家入さんには面接時点で、前職でやっていたwebデザイナーではなくディレクターがやりたいという話を伝えていたのですが、完全に忘れられており、普通にバナーデザインの仕事をふられるなどのトラブルもありつつ、ブログサービスのリニューアルにあたって、情報設計やHTMLコーダーとして仕事をしはじめていました。
その中でシステムトラブルが発生したのです。完全な解決には半年の時間を必要とする大トラブルだったのですが、当時のブログチームでは、フロント・バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、デザイナー、との間で意思疎通が難しく、トラブルをどの様に収束させるか、メンテナンス計画はどうするか、ユーザーへの告知はどうするのか等々、スムーズに進まない状態でした。
たまたま前職で、エンジニア中心の会社でデザイナーとして働き、サポートその他もやっていた自分は、それぞれの役割の人と話が通じる状態にあり、間にはいって翻訳や通訳、共通理解を取り持つ形で奔走していました。
おそらくそうした動きを認めてもらう形で、鍋蓋組織からミドルマネジメントを作るというときに、ブログサービスの事業部長という役割を任される流れになりました。
2. 転機:「自分がやらざるを得ない」状況の連続
トラブルが起こっているサービスのメンテナンスは深夜に行うことが多く、担当してくれるエンジニアにつきそう形で、週に2日ぐらいのペースで会社に泊まっていた時期もありました。メンテナンスが予定通りに進まない場合、ロールバックするのか、時間を延長するのか、アナウンスはどうするのか、全てその場で決める必要がありました。
当時は大規模webサービスの知見もパブリックになっているものは少なく、Flickrのエンジニアブログが公開されたと聞けばそれを読みに行ったり、前職のエンジニアや他のベンチャーにいた知人に相談することもしばしばでした。
また、事業部長と同時に東京・福岡の2拠点をあわせた統括本部長の役割も任されました。2拠点で複数サービス・事業を展開している中で、社長以外に全体を見る人が必要になったという話でしたが、これもたまたま自分が抜擢されたのだと思います。
幸か不幸か当時の社長には頼りない部分があり、予期せぬ状況が次々と発生しました。
社長不在の数日間
ある時、社長が急に数日出社しなくなったことがありました。結局3,4日で連絡はついたのですが、その後もいつかいなくなってしまうかもしれないなという感覚は持ったままだったと思います。
また来客とのMTGで、社長が急に出席できなくなったこともありました。秘書さんから「代わりに出てもらえないか」と言われた時、最初は戸惑いました。誰と、どんなアジェンダで会う約束になっていたのかもわかりません。
しかし、相手方は既に会議室で待っています。こうした急場を凌ぐ経験も、時々発生していました。
レンタルサーバーやドメインは福岡で運営していたのですが、東京本社に電話がかかってくることもありますし、受付に人がくることもありました。通常の窓口で受けたクレームがエスカレーションされて、自分に回ってくることもしばしばありました。自分より後ろはありません。
この場合も自分がその場で、会社の代表として対応を決めて、判断しなくてはいけなかったのです。
3. オーナーシップが芽生えた瞬間
外部との折衝で感じた責任の重さ
上場準備プロジェクトが始まり、事業部門管掌役員となったことで、外部に対しても責任者として説明しなければならない場面が増えました。グループ会社との調整も私のミッションとなりました。
外部の人たちと話すとき、私の発言は個人の意見ではなく、組織の公式見解として受け取られます。間違ったことを言えば、組織全体に迷惑をかけてしまう。グループ会社の人たちや証券会社の人たちに、自社のことを説明するために、より深く理解しておく必要がある。その上で、責任者として発言をし、折衝をする。この緊張感が、私の中でオーナーシップを育てたのだと思います。
「自分ごと」として捉える変化
上場プロジェクトを通じて、より、組織の成果を自分の成果として捉えるようになったと思います。社内のどんな問題も、自分に直接関係ないこととは思えなくなったのです。なぜなら、組織全体の成功が自分の責任だと感じるようになったからです。
当事者性:組織の成果を自分の成果として捉える
責任感:組織の課題を自分の課題として解決しようとする
長期視点:組織の将来を自分の将来として考える
リスク受容:組織のために必要なリスクを取る覚悟がある
4. 管理職と経営者の違いを実感した瞬間
責任の質の変化
管理職から程なくして取締役になりましたが、取締役になった瞬間に経営者になれたわけではなかったと思います。
先に述べた様ないろんなトラブルや、役割、シチュエーションで自分で判断・決断する、会社の公式見解としての責任を負う。こうした出来事が日々の判断基準を徐々に、かつ根本的に変えました。「組織全体にとって最適か」を常に考えるようになったのです。
時間軸の変化
事業部長になったばかりのときは、目の前のトラブルを収束させることが第一で、中長期のことや「事業」としてのことは考えられていませんでした。しかしその後、年間の予算・計画を立て、それを説明し、実行する役割になること、上場プロジェクトの中で会社の事業の戦略を言語化し、説明すること、これらを通じて年単位、数年単位の戦略的思考が必要になってきました。
仮に短期的には不利でも、長期的には組織のためになる判断をする。このような意思決定を繰り返すうちに、自然と長期視点が身についていきました。
アイデンティティの変化
最も大きな変化は、アイデンティティでした。
任された事業だけではなく、組織全体の成功が自分のアイデンティティになっていきました。
丸10年務めることになるのですが、辞める瞬間まで自分と会社を切り離して考えることは、うまくできなくなっていたと思います。
5. 成長に必要だった条件を振り返る
「自分がやらざるを得ない」状況
おそらく一番重要だったのは、単に「役割を与えられた」のではなく、「自分がやらざるを得ない状況」に置かれたことでした。誰かの許可を求めることができない状況で、自分の判断で動かざるを得ない経験の積み重ねが、オーナーシップを育てたのだと思います。
失敗を許容できる環境
当時は組織もまだまだ未熟でしたし、自分も多くの失敗や判断ミスをしたと思います。しかしそのまま任せ続けてもらえました。
担当していたブログが無料サービスであり、会社の業績・売上に直接影響しなかったことも、判断を任せられていた理由の1つだっただろうと思います。
そういった状況の中で、リスクを取って挑戦することができたのだと思います。毎回お伺いをたてないといけない環境だったとしたら、いろいろとその後が変わった気がします。
段階的な責任拡大
事業部長としてのトラブル解決、統括本部長としての2拠点の利害調整やコミュニケーション、事業部門管掌役員として対外的な説明責任、と非常に短期間ではありましたが、段階的な役割の拡張・変化も結果的にプラスに働きました。
6. 管理職から経営者への脱皮を阻害する要因
管理職最適化のパラドックス
おそらく自分は管理職として自分を最適化する前に経営者の役割に移行する必要に迫られたのですが、
もし、管理職経験が長かったとしたら、経営者としての自分に移行しづらかったかもしれない、と考えることがあります。
というのは「優秀な管理職」になることと「経営者への準備」をすることは、実は相反する行動を要求する部分があるからです。
管理職として評価される行動:
リスク回避
短期KPIの確実な達成
役割の忠実な履行
経営者として必要な行動:
リスクテイク
長期視点
役割を超越した判断
この矛盾を乗り越えるためには、(特に短期の)組織の評価に縛られすぎず、長期的な価値創造を重視する必要があります。
確実性を求める思考パターン
管理職は役割に忠実であろうとすると、不確実性を避け、確実な成果を求めやすくなる傾向がありますし、優秀な管理職はそこに最適化していきます。
しかし、経営者には不確実性の中で判断を下す能力が求められます。
まとめ:オーナーシップは後天的に育てることができる
私の経験から言えるのは、経営視点やオーナーシップは後天的に育てることができるということです。
ただし、それには適切な環境と経験が必要です。
重要なのは:
「自分がやらざるを得ない状況」に置かれる経験
段階的な責任拡大
外部に対して組織を代表する経験
これらをどう設計し、経験していくかということ。
もう1つのポイントは、管理職に最適化することが経営者への変化を難しくするパラドックスがある、ということです。
管理職から経営者への脱皮は決して簡単ではありませんが、適切なアプローチがあれば十分に可能だと思います。
自分個人の話でいうと生存者バイアスになってしまいますが、火中の栗を拾う経験が本当に役に立ったなと思いますね。
次回予告
次回は今回の続きとして、COOという独特なポジションについて、他のCXOとの違いや独特の役割について考えてみたいと思います。


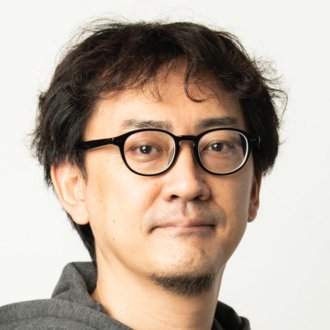
コメント