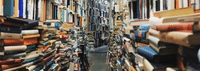『利己的な遺伝子』は「人生とは目的もなく空疎なものだ」と説く本ではない! 「あまりに深い誤解」の真相をドーキンス本人が語る
1976年、約半世紀前にリチャード・ドーキンスが発表した『利己的な遺伝子』は生物界のみならず多くの分野に影響を与えた一方、誤解も多く生みました。一般の読者からの反応としてしばしばあったのが「救いがない、無味乾燥だ、冷たい」というもの。しかしドーキンス本人によればそれはまったくの誤解で、むしろ科学が明らかにする真実こそ、私たちに鮮やかな「センス・オブ・ワンダー」(驚異の念)をもたらしてくれるのだというのです。
私の初めての著書『利己的な遺伝子』を出版してくれた外国のある編集者がいった。あの本を読んだあと、冷酷で血も涙もない論理に震撼して3日眠れなかった、と。別の複数の人間からは、毎朝気分良く目覚めることができますか、といった旨の言葉をもらった。遠い国で教師をしているという人物からも手紙が来た。この本を読んだある女生徒は、人生とは目的もなく空疎なものだと知らされて泣きだしてしまった、と。他の生徒まで虚無的な悲観論に染まってしまっては大変だと思ったこの教師は、泣きだした女生徒に、友達にはこの本のことをいわない方がいいと忠告したそうだ。このように、救いがない、無味乾燥だ、冷たい、といった非難は、しばしば科学に対して投げつけられる言葉である。科学者の方もわざとそのような表現を好む。私の大学のピーター・アトキンスは著書『エントロピーと秩序』(1984)において次のような調子で述べている。
私たちはカオスから生まれた子どもである。そして何かが変化するとき、その奥底では腐敗が起きている。根底には、ただ崩壊があるのみで、カオスがくい止めようのない波となって押し寄せてきている。カオスになることには、何も目的などはなく、あるのは、カオス状態に向かう方向だけである。宇宙の内部を奥深く冷静に見つめると、このような、なんとももの寂しい真理が見えてくるが、これこそ私たちが受け入れなければならない現実なのである。
このような発言はまさにサッカリンのもつ偽の甘味を一掃するものであり、この世界にまつわる感傷的な幻想を剥ぐため、あえて選ばれた声高な言葉なのである。しかしこの言葉は、個々の人間がもつ希望をないがしろにするものではまったくない。確かにこの宇宙には究極的な意志や目的などなにもないだろう。しかし、一方、個人の人生における希望を宇宙の究極的な運命に託している人間など、私たちのうちに一人として存在しないこともまた事実である。それが普通の感じ方というものだ。われわれの人生を左右するのは、もっと身近で、より具体的な思いや認識である。本来、生きる意味に満ちた豊かな生を科学が意味のないものにしてしまう、という非難ほど徹底的に的外れなものもあるまい。そういう考え方は私の感覚と180度対極に位置するものだし、多くの現役の科学者も私と同じ思いだろう。しかし、私に対するそのような誤解のあまりの深さに、私自身絶望しかけたこともあったほどである。
だが『虹の解体』では気を取り直し、あえて積極的な反論を試みることにした。ここで私がしたいのは、科学における好奇心(センス・オブ・ワンダー)を喚起することである。というのも、私に対する非難や批判はすべて、好奇心を見失った人々に由来しており、それを考えると心が痛むからである。私の試みは、すでに故カール・セーガンが巧みに行なったことでもあり、それゆえに彼の不在がいまはいっそう惜しまれよう。ともあれ、科学がもたらす自然への畏敬の気持ちは、人間が感得しうる至福の経験のひとつであるといってよい。それは美的な情熱の一形態であり、音楽や詩がわれわれにもたらすことのできる美と比肩しうるものである。それはまた、人生を意義あるものにする。人生が有限であることを自覚するとき、その力はなおさら効果を発揮する。
本書のタイトルは、キーツから借用した。キーツは、ニュートンこそが虹の持つ詩的なものをすべて破壊したと考えた。ニュートンは、虹を単なる分光学的な現象に還元してしまったというのである。だが、キーツはこれ以上間違うことができないほど間違っている。私の目的はこのような誤解によって間違った結論にむかっている考え方を、正しい方向に導きなおすことにある。科学こそが、偉大な詩の霊感の源となり、なるべきものである。しかし私自身にはそのことを体現できるだけの詩的才能がない。そこで、すくなからず散文表現に頼らざるを得ない。本書中のいくつかの章のタイトルもやはりキーツから借用したものだ。本文中でも、キーツの引用、あるいはキーツをほのめかした部分に気づく読者もいるだろう。むろん、キーツの感受性あふれる才能には敬意を表する。実際、人間としてはニュートンよりキーツの方がずっと好感がもてる人物だった。という次第で、本書の執筆中、キーツの影はいつも、見えざる査読者として私の肩越しに原稿を追っていたのである。
ニュートンによる〝虹の解体〟は、天体望遠鏡につながり、ひいては現在、われわれが宇宙について知り得ていることを解く鍵をもたらした。ロマンティックという形容詞で語られる詩人なら誰でも、アインシュタイン、ハッブル、あるいはホーキングが語る宇宙のありさまを聞いて心弾まずにはいられないはずである。フラウンホーファー線とスペクトル偏移について取り上げた、第3章「星の世界のバーコード」でこの点について検討してみよう。バーコード、というイメージはまた私たちをまったく別の場所へと導く。そこもまた別の意味で心弾む音の世界である(第4章「空気の中のバーコード」)。さらに、バーコードは私たちをDNA鑑定の世界へと誘う(第5章「法の世界のバーコード」)。そこでは社会における科学の非常に特異的な位置づけについて考える機会があるだろう。
それに引き続く2章(第6章「夢のような空想に ひたすら心を奪われ」、第7章「神秘の解体」)を私は特に科学的幻想に関する章と呼びたい。そこで私は、よくある迷信的な民間伝承について取り上げたい。迷信は、虹を称揚することにかけては詩ほど重んじられることは少ないが、不思議な現象に満ちあふれたものばかりだ。しかし科学的に説明されればどれもたわいのない話なのである。そんな迷信が好んで語るもののひとつに、よくできた幽霊の話があり、そこでは決まって奇妙な事件が発生し、ポルターガイストが登場したり奇跡が起こったりする。そして必ずハムレットの次の言葉が引用される。
この天と地のあいだにはな、ホレーシオ、
哲学などの思いもよらぬことがあるのだ。
科学者はこういう。いや、それはいずれ科学的に解明できる、と。しかし迷信を信ずるものはそんな言葉に耳を貸そうとはしない。彼らは嘆く。深遠な謎を科学的に説明するなどというのは興ざめもはなはだしい、と。ニュートンが、虹をないがしろにしてしまったと嘆いた叙情派の詩人と同じつもりなのだ。
雑誌《スケプティック》の発行人、マイクル・シャーマーは、ある時、テレビに出演し、有名な霊能者と対決した。そのときの様子を次のように語っている。霊能者は、よくあるインチキ演技によって、あたかも死者の霊と交信しているかのように見せかけていた。シャーマーはそのまやかしを暴いてみせた。ところが、視聴者の反応は予想外だった。化けの皮が剥がされたこの山師を非難するのではなく、逆に矛先はシャーマーに向けられた。番組では、ある女性の出演者が、みんなが信じていることに水をさすのは「不適切な行為」だといってシャーマーを攻撃した。視聴者はなんとこの女性を支持したというのだ。この女性は本当なら目の前にかぶせられていた覆いをはずしてもらって感謝していいはずなのに、逆にその覆いをより強くかぶることを選んだのである。私は、この宇宙の秩序こそ人類がもっとも知り得たいことだと思う。しかし、それはつまらないインチキ手品で説明できるような秩序ではなく、ずっと美しく素晴らしいものだと信じている。その秩序のもとでは、すべてのものが究極的には説明可能なのだと思う。たとえわれわれがその説明を見いだすまでにまだ長い距離を進まねばならないとしても、である。
超自然現象を信じる心性というのは、詩的な畏敬の念が本来内包する感覚を踏みにじるものだといえるだろう。本当の科学がもたらすべきものはこの詩的な畏敬の念である。この感覚を踏みにじるものは別のところからもやってくる。それは〝偽の詩〟とでも呼ぶべきものである。第8章「ロマンに満ちた巨大な空虚」では、偽の詩を身にまとった科学の問題について論じたい。偽の詩は言葉巧みに人々を誤った場所に導く。その好例として、私の専門領域でもある進化の分野におけるある有名な人物について検討したい。彼の想像力豊かな語り口は、彼にアメリカにおける進化論の論客として比類なき影響力をもたらしたが、それは私にいわせれば大変不幸な現象と思える。もとより本書の主眼は、よき詩を旨とする科学を唱導しようとするものである。もちろん、〝詩の言葉でかかれた科学〟という意味ではなく、〝詩的な畏敬の念を霊感源とする科学〟という意味で。
最後の4つの章はそれぞれ別の、しかし互いに連関するトピックスについて扱っている。ここでは、私よりも詩的な感性を持ちあわせた科学者にめざしてもらいたいものを示そうとしたつもりだ。遺伝子は利己的なものである。と同時に、アダム・スミス的な意味で、協調的なものでもある(第9章「利己的な協力者」をアダム・スミスの引用ではじめたのはそのためである。ただし、この引用は章の内容というよりは、驚異ということに照応している)。種における遺伝子はその種がたどってきた歴史の記述書であるといってもよい。第10章「遺伝子版死者の書」とはその謂である。一方で、脳は、常に新しいヴァーチャル・リアリティをつむぎだすことによって世界を再構築しているといえる。第11章「世界の再構成」はそのことを論じた。第12章「脳のなかの風船」ではわれわれヒトという種のもっともユニークな特徴である脳の起源とそれがもたらすもの、そして進化における役割について考察してみた。そのことを考えること自体が、詩的な驚きとなる。
(リチャード・ドーキンス『虹の解体――世界はなぜ美しいのか』福岡伸一訳、序文より抜粋)
著者プロフィール
リチャード・ドーキンス(Richard Dawkins)
イギリスの生物学者・作家。1941年ケニア・ナイロビ生まれ。英国王立協会フェロー。オックスフォード大学で学び、カリフォルニア大学バークレー校を経てオックスフォード大学講師。1976年刊行のデビュー作『利己的な遺伝子』(紀伊國屋書店)が世界的ベストセラーとなり、その名を一躍知らしめた。その他、『遺伝子は不滅である』『ドーキンスが語る飛翔全史』(以上早川書房刊)、『進化とは何か』『神のいない世界の歩き方』(以上ハヤカワ・ノンフィクション文庫)など著作多数。
書誌情報
書名:『虹の解体――世界はなぜ美しいのか』
著者:リチャード・ドーキンス
訳者:福岡伸一
出版社:早川書房
発売日:2025年11月19日
本体価格:1760円