知識を属人化させないためにやったこと 〜部内wiki改善の記録〜
こんにちは、LINEヤフーコミュニケーションズ OPSチームの下川です。
みなさんの会社・組織には「社内wiki」ありますか?
そして、うまく整理され、情報が活用されていますか?
私は弊社に在籍してわりと長く、経験と勘で社内wikiを眺め「この情報はたぶんこの辺にあるはず」と見当がつきます。
だから、目的のページに比較的すぐたどり着ける方です。
でも、どうやらみんながそうではない。
「この情報知ってますか?」と、wikiに書いてある内容を聞かれることも多々あります。
これは組織のナレッジが個人に依存してしまっているサインと言えます。
本記事では、部内wikiの整理を通して取り組んだ、ドキュメントの非属人化に向けた実践を紹介します。
01/ wikiのカオスな現状
クリエイティブ部には複数のチームがあり、階層としては
・全体向けの情報
・各チームの情報
・管理職向けの情報
と一応整理されている……はずでした。
けれど実際に覗いてみると、想像以上にカオスです。
◾️実際にどんなページがあるのか調べてみた
まずは全体を把握するため、部内wikiにどんなページがあるのか、階層構造を書き出すことにしました。その結果、こんな課題が見えてきました。
どの階層にも属さないページが最上位階層にあぶれている
=情報の置き場所がわかりづらく、探しづらいチーム内に全体向けの情報が眠っている
=チーム内に閉じてしまい、共有が広がらない古くなって誰も触っていない情報が残っている
=古い情報が放置され、せっかく見つけた情報が信頼できない
つまり、「情報はあるのに活かされていない」状態でした。
階層構造も深く深くなっており、5〜6階層目まで確認して諦めたページも多数ありました。
◾️理想は、情報が資産として共有され、活用されている状態
情報をどこに置けばよいか分かりやすく、誰でもすぐ見つけられる
全体で共有されるべきものが共有されている
内容が更新され、信頼できる
この状態を維持できる仕組みを考えていきたいと思い、取り組み始めました。
02/ 本当に整理できるのか?という不安
取り組みを始める前に、ふと立ち止まりました。
「そもそも階層で整理すること自体、限界があるんじゃないか?」と。ちょうどその頃に読んだのが、『階層整理型WiKiはスケールしない』 という記事。
「確かに…」と思いました。
階層構造は整理しやすいけれど、ページが増えるほど維持が難しくなる。
環境や人が変化していく中で問題が再発しやすい、という指摘に納得しかありません。
「一度整理しても、また同じことになるんじゃ?」
そんな不安を抱えつつも、
“情報が資産として共有され、活用される状態”を維持する仕組みづくり
を目指して、やってみることにしました。
完璧な階層構造を作ることが目的ではなく、
組織内で継続的に知識が共有される仕組みを作ることを目的と考えました。
03/ どこに手をつけるか見極める
膨大な情報を前にいきなり全体を直すのではなく、
まずwikiに集まっている情報を「性質」で3つに分類しました。
全体向け × 流動性が低い
部内全体のルール、ガイドライン、ナレッジなど特定層向け × 流動性が低い
チームや職種別の業務マニュアル、ナレッジなど流動性が高い
議事録、プロジェクトログなど、随時更新されるもの
まず全員が関わる“基盤”を整理するため、「全体向け × 流動性が低い」情報に手をつけることにしました。
04/ 実践したこと
①情報の置き場所を分かりやすくする
情報の置き場所が曖昧だと、上位階層やチーム階層にページが増え続け、
どんどん迷路のようになっていきます。
まずは“誰が何を探しに来るか”という導線を意識し、情報の置き場所を用意します。
「部のメンバーが、部内向けのルール・ガイドライン・ナレッジを探しにくる」場所として、上位階層「組織運営ポータル」を新設。
そこに各チームの階層内に眠っていた共通情報を統合・公開しました。
中身をブロックに分けて入れ子構造にすることで、組織構造や使用するツールの変化があっても柔軟に入れ替えしやすくなっているのもポイントです。
②曖昧なページ名を減らす
wikiの混乱を招く大きな要因のひとつが“曖昧なページ名”です。
「**関連」「その他」「まとめ」…数ヶ月後には誰も中身を覚えていませんし、中身を想像することも難しい、良くない命名です。
そこで、命名ルールに関しては最低限のルールを決めました。
上位階層は「初見でも内容が想像できる名前」にする
「**関連」は禁止。
【例】× 購買関連 ◯ 購買フローページ新規作成時の最低限のルールを明文化
┗親カテゴリを乱立させない
┗ページテンプレートの準備 等
このルールを整えることで、似たページの乱立を防ぎ、新しく書くときの迷いも少なくする狙いです。
③維持するための仕組み
古い情報が残っていると、部内wiki自体の信頼度の低下を招いてしまいます。そこで、情報ができるだけ古くならないような工夫 + 運用を維持するための役割を設定しました。
ページテンプレートを活用
準備したテンプレートの形式に全ページを当てはめて整理しました。形式が揃っていることで、今後の更新もグッと楽になるはずです。ページ内でのバイネーム記載の廃止
【例】お問合せは下川まで → お問合せはOPSチームメンバーまでバイネームするときはどこの誰か明確にする
【例】所属部署を併記+社内プロフィールページのリンクを設定 等部内wikiの定期パトロールをルーティーンとしてスケジュール
人の手で運用していると、どうしても漏れは出てくるもの。ここは腹を括って半期に一度のパトロールをカレンダーに登録しました。
こうして場所を用意し、最低限のルールを設定することで、整理されつつも新しい情報を追加しやすい仕組みとしてのバランスを狙いました。
逆に、細かすぎる・厳格なルール設定は運用の妨げとなることを懸念し、採用しませんでした。
まとめ
社内wikiの整理は地味な活動ですが、組織の知を支える“地盤”を固める作業です。
実際に整理を進めた結果、wikiに書かれている内容を質問されることが減り、「まず調べてみよう」という動きが生まれるようになったと感じます。
テンプレートを準備したことでページ作成の手間も減りました。
また、「情報の置き場所」ができたことで、新たに発生した情報・これまでに蓄積していたナレッジへの導線も作りやすくなりました。
階層構造の限界は確かにあると感じますが、知識を個人のものからチーム全体の資産に変えていくことは、欠かせない視点だと思います。
そして、ナレッジは“増やす”ことも大事ですが、“活かせる状態で維持すること”のほうが、ずっと難しいと改めて感じています。
完璧にとはいきませんが、少しずつでも情報を見つけやすく、使いやすい状態を保つことが大切です。
あなたのチームのwikiも、少し覗いてみませんか?
今日ひとつのページを整えるだけでも、きっと未来の誰かが助かります。
LINEヤフーコミュニケーションズ クリエイティブ部では、「WOW」で「!」なサービスづくりに一緒に挑戦してくれるデザイナーを募集しています!
まずはカジュアル面談からでも大歓迎です◎
興味のある方は、ぜひご応募ください!
◾️ LINEヤフーコミュニケーションズ クリエイティブ部 求人
LINEヤフーコミュニケーションズ クリエイティブ部のX(旧Twitter)でも情報発信を行なっています。フォローしていただけると励みになります!
よろしくお願いします!

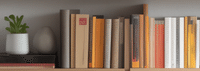
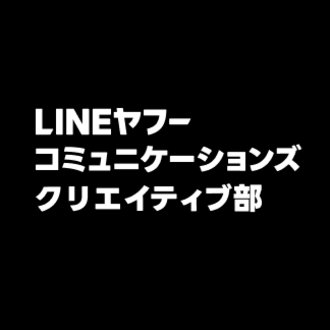
コメント