領域国民国家以後
世界はいま、米国を頂点とした単極モデルから、BRICS を核とする多極的ネットワークへと静かに重心を移しつつある。GDP 比率でも人口比でも、G7 の占有率は年々縮小し、ドルのみを軸に回っていた国際金融の歯車も人民元・ルピー・リアルなど複数の歯車を噛み合わせ始めた。だがこの変化は単なる勢力図の書き換えではない。近代が創り上げた「領域国民国家」という制度そのものを、基礎から揺さぶる地殻変動である。
国民国家は十九世紀ヨーロッパの発明品だった。均質な民族、一つの言語、明確な国境、そしてその中で絶対的に振るわれる主権。だが二一世紀のグローバル化は、この四本柱を一本ずつ腐食させた。資本はスプレッドシートの上を瞬時に移動し、サプライチェーンは国境線を鷹揚に跨ぎ、デジタル空間はパスポートを要求しない。残ったのは徴税と戸籍と防衛という「国家の皮」だけであり、その皮も監視資本主義と民間軍事企業によって穴だらけになりつつある。
多極化を促す BRICS 諸国は、国民国家を形式的に維持しながら中身を別の論理で満たそうとしている。中国は「華夷秩序」を、ロシアはネオ・ユーラシア帝国を、インドはヒンドゥー世界の宗教帝国を思い描く。つまり彼らは「主権国家」を語りつつ、内側では帝国・文明・宗教というより古いコードを再起動しているのだ。それは、巨大な多頭鷲がそれぞれの翼を広げながら互いに距離を取る姿に似ている。
この転換を神話的に読み替えれば、単一言語で天を目指したバベルの塔の崩壊であり、洪水から身を守ったノアの箱舟が海面上昇で底を抜かれる瞬間である。塔と箱舟がともに役目を終えるとき、人類は「空間で括る秩序」から「関係で織る秩序」へと向かうほかない。ネットワーク国家や DAO(分散型自治組織)は、まさにその萌芽である。国境ではなくプロトコルが共同体の骨格となり、法典ではなくコードが腐敗防止剤となる世界。
しかし秩序が名を失えば、不安も無限に噴出する。国旗は偶像、国歌は呪文、国名は神の名――そう定義するなら、私たちはいま「名を持つ神々」が退場する夜明け前に立っている。夜明けは混沌を連れてくるが、その混沌は創造の母胎でもある。中心を失った世界は、かえって多中心的な小さな臨在――家族、信仰圏、価値観コミュニティ――を無数に産み出す可能性を抱いている。
要するに、多極化は「国家の崩壊」ではなく「国家神話の脱魔術化」だ。BRICS の台頭は、近代国民国家をふたたび神話の水平線へ押し戻し、帝国とネットワークという相反する二つの道を同時に開く。この二重露光の風景のなかで、人は従来のパスポートを握りしめながら、別の次元で「魂の市民権」を獲得する方法を模索するだろう。国境線の地図が色褪せるとき、私たちは互いの声を国名ではなく物語で呼び合う。多極化の果ては、恐らくそのような「名を超えた対話空間」――中心なき神の沈黙を背景に、新たな言葉が芽吹く場である。

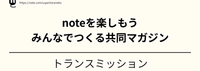

コメント