今日から始める人のための現代SFインディーゲーム45選+α
文・千葉集、選・xcloche & 千葉集
わたしはそれを信じます。みなさんもそれを信じるべきなのです。
序論(別記事へのリンク)
↑「SFゲームってどう考えればええんやろね」みたいな序論です。SF界の偉人、角川春樹風にいえば「読んでから見るか、見てから読むか」。別に読まずともOKではあります。
注意書き
2025年10月の京都SFフェスティバルの合宿企画において開かれた「SFインディーゲーム談話室」パネル、そこでリストアップした45作品とそれらの属するジャンルを中心に紹介していきます。
各ジャンルの冒頭に示されているタイトルは「談話室」当日に紹介した45本に含まれるゲームです。ふだんあまりゲームをやらないSFファン向けに選んだ入りやすいゲームたち(でも蓋を開けてみたら、みんなおもってたよりやってた)。比較的最近のものが多い。約半分をxclocheが、もう半分を千葉集が選びました。
ふたりで好き勝手選んだラインナップですが、それだけだと記事として散漫になりそうなので重要そうな作品をあとづけで補い、体裁を整えました。というわけで45本+αあります・とはいえ、重要作をすべて網羅することはほぼ不可能に近い。了承されたし。
特に作為なく選んだ45本なので、そもそもでジャンル的な偏りもあります。なので、そこにないジャンルはないですね。なんでないのかについては、おうちのひとと話しあってかんがえてみましょう。
現代のゲームにおけるジャンルは混交的なものです。物によっては複数のジャンルにまたがるものもある。なので、作品ごとの振り分けは多分に恣意的です。
基本的に2000年代後半以降の作品を扱います。「現代インディー」というタームはだいたいそのような意味で捉えてください。さらにそのなかでも、なるべく最近の作品を取り上げています。なるべく、ね。
「SF」の定義とは? なにがSFのゲームで、なにがそうでないのか? についてはデーモン・ナイト御大の有名なこのフレーズを差し出しましょう。:「SFとは、きみがSFの話をしている時に、たまたまその対象となったものすべてのことだ」。
長いので、上の目次からお好きなジャンルへ跳んでつまみ読んでもよし。
〈アドベンチャー/ウォーキングシム/ポイント・アンド・クリック〉
【京フェス紹介作】
・VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action
・2064: Read Only Memories
・1000xRESIST
・Minds Beneath Us
・A Space For the Unbound
・INDIKA
・World End Economica
・Project LUX
・Whispers from the Stars
SFアドベンチャーゲームの起源は、(おそらく)1980年の『Mission Asteroid』(On-Line Systems)まで遡ります。内容は宇宙飛行士に扮し、迫りくる小惑星の衝突から地球を救う、といったもの。
On-Line Systems(のちのSierra Entertainment)が出したHi-Res Adventuresというグラフィック・アドベンチャーゲームのシリーズのひとつで、この『Mission Asteroid』が第0号を冠せられました。ナンバリング的には、その後に第一号の『Mystery House』、第二号の『Wizard and the Princess』と続きます。アドベンチャーゲームの歴史を知っているひとなら、ここで、アレ? と戸惑うかもしれません。世界初のグラフィック・アドベンチャーとして名高いのは『Mystery House』であるはず。なのに、ゼロ番目とは……?
……実は発売順では『Mission Aseteroid』は『Mystery House』と『Wizard and the Princess』のあと、シリーズ三番目のゲームなのです。当時のOn-Line Systemsのソフトカタログで「他のHi-Resシリーズよりすこし簡単で、ちょっと短め」「アドベンチャーゲーム初心者の入門編としてデザインされた」と紹介されていることから察するに、正式なナンバリングタイトルとしては「格」が落ちたのでしょう。価格もシリーズの他のゲームが20ドル台や30ドル台で売られているなかで最安値の19ドル50セント。ちなみにHi-ResシリーズでもうひとつのSF作品となった『Time Zone』(1982)はなんと99ドル95セント。インフレを加味して現代の価格に直すと、約320ドルにもなります。極端すぎるだろ。
ともかくも、アドベンチャーは依然として物語を語りたい/語られたいひとびとにとって、もっとも身近なジャンルです。そこには当然、「SFの物語をやりたい」と望むひとたちもいるわけで。
さて、現代のSFインディーゲームを見ていくうえで、『VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action』(Sukeban Games, 2016)はまずもって外せません。ディストピアンなサイバーパンク世界でバーテンダーとして毎晩個性豊かな客たちと触れ合っていくアトモスフェリックなゲームで、そのスタイルはアーバンファンタジーの佳作『Coffee Talk』シリーズ(Toge Productions, 2020-)などの魅力的な追随者を多数生み出しました。
『VA-11 HALL-A』と同時期に出てコラボレーションもしていた『2064: Read Only Memories』(MidBoss, 2015)も、10年代のインディーSF作品としては忘れがたいあたり。『スナッチャー』などに影響を受けたレトロなグラフィックが、古式ゆかしい捜査ものにマッチしています。
レトロ風味といえば、なぜだかサイバーパンクを題材にしたアドベンチャーは、レトロだったり少し変わったテイストのグラフィックで描かれがちな気がします。82年に撮られた『ブレードランナー』の景色は、ビデオゲーム作家たちにはヴィルヌーヴの続編の陶器のような整った画ではなく、粗く壊れて見えるのでしょうか。
台湾の『Minds Beneath Us』(BearBoneStudio, 2024)はAIの台頭によって人類が職と存在意義を失われた世界で展開される陰謀を追う陰鬱なハードボイルドものですが、やや粗めのピクセルアートでありながら奥行きを感じさせる精細な背景が目をひきます。『VirtuaVerse』(Theta Division, 2020)は、『Minds Beneath Us』同様に横スクロールのアドベンチャーで、雨と夜陰とギラギラのネオンが効いた正調のサイバーパンク的風景を、稀代のピクセルアート作家Valenbergが描き出します。
ポイント・アンド・クリックならポイント・アンド・クリック専門パブリッシャーであるWadjet Eye Gamesがパブリッシングしている『Technobabylon』(Technocrat Games, 2015)。脳のハッキング事件や人類を統治するAIというコッテコテのサイバーパンク的題材に、暗い路地にネオンと怪しい漢字サインというこれまたコッテコテのサイバーパンク的風景が乗りますが、ビジュアルの質感が違うだけで印象も他のサイバーパンクアドベンチャーとだいぶ異なります。Wadjet Eyeのゲームはいずれもポイント・アンド・クリック全盛期の90年代前半に強く寄ったハードコアなビジュアルが売りで、『Gemini Rue』(Joshua Nuernberger, 2011)をはじめとしてSF作品もいくつか取り揃えてもいます。
ピクセルではなくボクセルでキメているのは『Cloudpunk』(ION LANDS, 2020)。なぜボクセル……などと訝しみながら主観視点モードに切り替えるとこれがたまらなくサイバーパンク。雨の篠突くビルとエセ日本語広告のはざまをホバーカーの運転席から体感できる、唯一無二のゲームです。
ポイント・アンド・クリックでいえば、CRPG的なアイソメトリック視点で進行するSFホラー『Stasis』(THE BROTHERHOOD, 2015)とその続編『Stasis: Bone Totem』(2023)は操作性や謎解きの生硬さを含めてぶっきらぼうなところが孤絶した空間で起こるホラーSF(『エイリアン』とか)の味わいにマッチしています。複数のキャラを切り替えて操作する『Bon Totem』のほうでは、離れたところにいるパーティメンバーと物質転送装置を使ってアイテムのやりとりを行うという、SF設定ではないとなかなかできない力技をやってきます。
サイバーパンクからは外れるものの、アートワークがすごいインディーSFアドベンチャーといえば『Harold Halibut』(Slow Bros, 2024)も注目に値します。何百年も宇宙をさまよう移民船を舞台にしたオフビートなお話ですが、なんと全編ストップモーションアニメ(風)。粘土などの素材から造り上げた人形や小道具を3Dモデルとして取りこんで造り上げた労作です。ゲームプレイには少し難がありますが……。
アニメーションでいえば、チェコ・アニメーションの偉大な伝統をビデオゲームへ継承したスタジオ、Amanita Designのポイント・アンド・クリック式アドベンチャー『Machinarium』(2009)も忘れがたいラブリーさを具えた逸品。
ところで『VA-11 HALL-A』はベネゼエラのゲームです。インディーのSFアドベンチャーはよくメインストリームではない国から印象的な作品が出たりします。
たとえば近年躍進めざましいインドネシアからは『A Space For the Unbound』(Mojiken, 2023)。いわゆるサイコダイブものですね。16ビット機世代ぐらいの細密なピクセルアートで90年代後半のインドネシアの田舎町をたまらなくノスタルジックに描きます。しかし、なんといっても、コレ、セカイ系でもあるんですね。日本におけるセカイ系が90年代から00年代にかけてのローカルな現象だったとするならば、今やその継承者たちは日本製アニメなどを通じて覚醒したアジア各国の(元)若者たち……のかもしれない。そして、精細なピクセルアートは「あのころ」への郷愁を国の区別なくひきたてます。この質感こそ、特定の世代にとってのユニバーサルランゲージ。
他にもポルトガルからは『The Red Strings Club』(2018)と『The Cosmic Wheel Sisterhood』(2023)のDeconstructeam。前者は憂鬱な高度資本主義世界をこれまたレトロ気味のピクセルアートで描き出したサイバーパンクアドベンチャー。後者は宇宙の果てに追放された魔女の復活を描く魔術的ワイドスクリーン・バロック(定義は人による)。ストーリーテリングに定評のあるスタジオです。日本語版はローカライズもすばらしい。
メインストリームの国々のなかにもマイノリティは存在します。北米におけるアジア系のスタッフ中心に設立されたSunset Visitor(斜陽過客)は移民である自らや親世代の記憶から『1000xResist』(2024)を生み出しました。簡単に言えば、北米における移民二世とパンデミックと香港民主化運動と『NieR:Automata』と百合とエヴァンゲリオンとNieRをミキサーにぶち込んだようなストーリーです。想像できない? やってみてください。ほんとに全部あるから。
ここまで紹介してきたインディーSFアドベンチャーは七割がた2Dでした。しかし、3Dのほうが強いジャンルもございます。ウォーキング・シミュレータです。ウォーキングシムも原理主義的な派閥になるとインタラクションを一切許さないなどの厳しい戒律を科されるのですが、ここでは「歩行による探索が主体の、NPCとの接触や戦闘の少ないアドベンチャー」くらいに捉えてください。
ウォーキングシムにとってSFは鬼門のようなところもあります。ジャンルの開祖であるThe Chinese Roomは『Everybody's Gone to the Rapture』(2016)のリリース直後に大規模なレイオフに見舞われ10年近くウォーキングシムジャンルから離れるはめになり、『Gone Home』で名を馳せたFullbrightの『TACOMA』(2017)は『Gone Home』ほどの成功は得られず、社内でのハラスメント問題なども重なり、事実上のスタジオ解体へと追い込まれました。ともあれ、どちらも「人間の消えたあとに残された痕跡から過去にあった出来事を探る」というウォーキングシム的なストーリーテリングの作法に忠実なゲームでした。
『INDIKA』(Odd Meter, 2024)は、先日の日本ゲーム大賞のゲームデザイナーズ大賞受賞時に桜井政博に称えられていたのが記憶に新しいところ。19世紀のロシアを舞台に悪魔の声が聞こえる修道女インディカを主人公したゲーム……と言うとどこがSF? と思われるかもしれませんが、実用化していなかったはずの蒸気自動車が出てきてそこはかとなくスチームパンク風味があったり、異常に巨大なサイズの魚を異常に巨大なサイズの缶詰に詰めていく工場が出てきたり、とにかくなんだかヘンな世界。ちょっと曖昧なインディカの精神状態を反映した表現主義的な演出である可能性もありますが、ここはストレンジな改変歴史世界説を取りたい。
おなじ11bit studiosがパブリッシングしている作品では『The Invincible』(Starward Industries, 2023)もSFファンの心をくすぐるでしょう。原作はポーランドが誇る巨匠スタニスワフ・レムの『インヴィンシブル』、それをポーランドのスタジオが開発をてがけ、ポーランドのパブリッシャーが出すという挙国一致体制。なんていうとおおげさですか。内容は原作の前日譚のような話で、無人惑星に不時着した女性が生存しているかもしれない同僚を探すうちに……という内容。50年代的なレトロフューチャーなデザインが洒落ています。
3DのSFインディーアドベンチャーで近年最良の収穫のひとつといえば、『Mouthwashing』(Wrong Organ, 2024)。とある事故によって遭難してしまった宇宙貨物船内で繰り広げられるナーブスリラー兼ボディホラー的なSFです。孤立した閉鎖空間としての宇宙船内で育まれる狂気というと『2001年宇宙の旅』やムアコック『暗黒の廻廊』などが想起される、いわば、SFホラー的シチュエーションのド定番ですが、そこにデヴィッド・リンチやら黒沢清の『回路』などをぶちこんで、あえてノンリニアでカオスな語りにしたのが大正解。ローポリの手ざわりも心理的恐怖(Steamのタグ)感を増幅させます。
さて、先述したように「未知の惑星で遭難し、たったひとりさまようことになる」というヴァン・ヴォークトの「魔法の村」的シチュエーションは、ゲームでは『Planetfall』(infocom, 1983)以来なにかと便利に使われてきました。インディーにかぎらず、ゲームに宇宙船が出てきたら十中八九で墜落するものと考えてください。冒頭で主人公が乗っているならほぼ墜ちます。
そうしたクリシェをもっともスマートなスタイルに落とし込んだのがモバイルゲームの『Lifeline』シリーズ(3 Minute Games, 2015-)でした。搭乗していた宇宙船がある衛星に墜落してひとり生き残った青年からプレイヤーのもとに偶然メッセージが届き、SMSアプリのようなUIでリアルタイムにテキストのやりとりをし、彼を助けていく、というもの。このフォーマットを2025年にアップデートしたのが『Whispers from the Stars』(Anuttacon, 2025)。やはり、未知の惑星に墜落した宇宙飛行士を通信を介して導いていくアドベンチャーなのですが、最大のウリはAIを駆使したリアルタイムな”音声”会話。完璧に流暢とまではいかなくても、かなりの程度まで自然な意思疎通ができているように見える(ただし日本語不可)のはそれだけで感動的です。もっとも、生命の危機に瀕した状況のわりに、相手が「好きな小説とかある?」「どこ住み?」などと呑気に個人情報を探ってくるのはどうなのとおもいます。まあ、かつては、世界を滅ぼす隕石が落ちてきそうな状況なのにゴールドソーサーに入り浸っていた主人公のいたゲームもありましたし……?
『Whispers from the Stars』は驚くほど「そこに人間が実在する」感触を出してくれるのですが、仮想に「実在」を感じられるメディアといえばVRです。『Project LUX』(Spicy Tails, 2018)は『狼と香辛料』でおなじみの小説家・支倉凍砂がシナリオをてがけたVRミステリゲーム。人類のほとんどが電脳化した世界で、プレイヤーはある裁判の陪審員として被告の記憶を追体験します。被告の記憶が映し出すのはひとりのかわいらしい少女――しかし、彼女こそが事件で殺害された「被害者」だった、というところから始まるお話。VRゲームの表現が模索されていた時期(まだそれが続いている気もしますが)のものではあるものの、VRならではの仕掛けがほどこされた一作です。ちなみに支倉凍砂は『Project Lux』に先立って『WORLD END ECONOMiCA』(Spicy Tails, 2011-16)というSF経済ビジュアルノベルも出しています。
というわけで、ここからは日本のお家芸であるビジュアルノベル/ノベルゲームのSFインディーゲームを見ていきましょう。
〈ビジュアルノベル〉
【京フェス紹介作】
・ステラーコード
・ベオグラードメトロの子供たち
・デイグラシアの羅針盤
・2236 A.D.
日本でもSFアドベンチャーゲームは80年代前半から存在しました。もっとも早い例は83年発売の『惑星メフィウス』(T&E SOFT)や『コロニーオデッセイ』(日本電気ホームエレクトロニクス)でしょうか。小松左京の監修を受けた『コロニーオデッセイ』は出会うキャラが合成音声で喋るなど、当時としては『Whispers from the Stars』ばりに先進的な試みを行っていました。80年代後半以降は、堀井雄二の『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』(ログインソフト, 1984)に代表されるコマンド選択方式【*1】を採用したSF題材のアドベンチャーが増えていきます。これまで何度か言及してきた『スナッチャー』や『メタルスレイダーグローリー』(ハル研究所&ライブプランニング, 1991)、『水晶の龍』(スクウェア, 1986)などが有名な作例といえるでしょう。
そうした土壌からやがて芽吹くこととなるビジュアルノベル(ノベルゲーム)文化ですが、特にSFビジュアルノベルについてその嚆矢となると……なんだろう? 『この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO』(elf, 1996)? まだアドベンチャーっぽい? 識者からご教示を乞いたいところ。【*2】
ともあれ、今の話です。インディーゲームの話です。
『ステラーコード』(Fragaria, 2025)は2025年注目の国産SFビジュアルノベルのひとつ。親の結婚によって唐突にできた義理の妹が若くしてノーベル賞候補にもあがっている超天才科学者で……というベタベタな導入からどんどん人類存亡をかけた壮大なSFとサスペンスへと転がっていきます。基本的に出てくるキャラが院生以上の理系なので、異常な事象に対してポンポンと淀みなく考察とやりとりが行われていく。いわゆる、頭のいい人しか出てこないストレスフリーな作り。理知的かつユーモラス、ときにハードなまでにシリアスなSFです。なんでもJAXA公認のベンチャーが監修に入っているとのことですが、作中のJAXAの扱いを見ていると大丈夫かという気がしてくる。
『マインドシーカー』だってアドベンチャーだったんだぜ、という強弁がまかり通るのなら、日本には美しい四季とサイキックものの伝統があることになります。『ベオグラードメトロの子供たち』(Summertime, 2020)はセルビアを舞台にしたサスペンス+サイキックビジュアルノベル。超能力を持った少年少女たちが、かれらをつけねらう巨大企業の魔手を逃れ、未完成のまま廃墟となった地下鉄ベオグラード・メトロを駆け抜ける……といったお話。アニメーションをはじめとした作りが非常にリッチで、アドレセンスな青春物語としての評価も高い作品です。
古典へのリスペクトを込めて本歌取りを行うのも日本の文化。『デイグラシアの羅針盤』(カタリスト, 2015)は、名作SFアドベンチャー『Ever17』に批評的オマージュを捧げた海洋SFミステリです。鮮烈な仕掛けを擁した『Ever17』同様、驚きに満ちたストーリーテリングを見せてくれます。
『2236.A.D(西暦2236年)』(Chloro, 2018)は人類がテレパシーをあたりまえに使える世界で、その能力が欠落しているせいで孤独感を抱えている少女を主人公にしたお話。なにを言ってもネタバレになるという言い回しがありますが、まさにこれのこと。ビジュアルノベルは開発者の考えた仕掛けがそのアイデアの勢いを減じないまま襲いかかってくる、ナマの暴力性がたまらない。
ところで2010年代はビジュアルノベルがグローバルに広まっていった十年でもありました。ビジュアルノベル用ゲーム制作エンジンRen’Pyの普及が一因であるかとおもいます。代表的なところは『Doki Doki Literature Club!(ドキドキ文芸部!)』(Team Salvato, 2017)ですね。モニカだってSFといえばSFか。
文芸部以前のRen’Py製SFビジュアルノベルだと『Analogue: A Hate Story』(Love Conquers All Games, 2012)は押さえておきたいところ。ある日、地球を離れて数百年のあいだ宇宙をさまよっていた世代宇宙船ムグンファが発見される。その内部の調査を依頼された主人公=プレイヤーは船に乗り込み、そこで入手したログからムグンファの驚くべき実態を知る。そこは李氏朝鮮時代へ逆行した超家父長制社会だったのだ……というお話。ちなみに作者は韓国人ではなくカナダ人。
ビジュアルノベルといえばクリックで進行するもの、という固定観念を打ち崩してくれるのが、『If Found….』(Dreamfeel, 2020)。1993年のアイルランドのある島に帰省してきた博士課程の院生カシオの物語と、ブラックホールによって危機に陥った地球を救おうとする宇宙飛行士の話が交互に語られます。シーンの送りは、カシオが自分の日記を消しゴムで消していき、どんどん日記を遡っていく、という手法でなされます。ビジュアルノベルもSFもクィアパーソンの物語が比較的描かれやすいジャンルですが、本作もそのひとつ。タッチ式のタブレット端末で遊んだほうが体験としてベターかも。
*1…そういえば、自分のなかでは「国産ゲームのコマンド選択式アドベンチャーは『オホーツク』が最初」という思い込みがあったのですが、調べたらそれ以前にも存在していたらしい。
*2…そもそもビジュアルノベルと「アドベンチャー」の境界は引くのがむずかしい。『VA-11 HALL-A』もところによってはビジュアルノベル扱いされていますし。まあ、ふんわり受け取ってもらえれば。
〈RPG〉
【京フェス紹介作】
・CITIZEN SLEEPER
・Disco Elysium
・CrossCode
みんな大好きRPG。むろん、最初期のビデオゲームRPGは『Dungeons & Dragons』(『D&D』)的なテイストをいかに移植するかという試みだったわけで、『ウィザードリィ』を見ても、『ウルティマ』を見ても、猫も杓子も剣と魔法のファンタジーといった具合でした。
『D&D』的なSFRPGの始まりは、おそらく1977年の『Futurewar』(EKW Systems, 1977)ではないかと見られています。70年代当時、『D&D』フォロワーの『Pedit5』(Rusty Rutherford, 1975)や『dnd』(Gary Whisenhunt & Ray Wood, 1975)といったRPGは、PLATOという、メインフレーム向け汎用コンピュータ支援教育システムのネットワーク上でリリースされていました。『Futurewar』もそのひとつ。『ウィザードリィ』に大きな影響を与えることになる『Oubliett』(Jim Schwaiger, 1977)に似たデザインを採用しており、物語としては「1970年代の現代から核戦争によって荒廃した遙か未来である2020年(!)の世界へと逃げ込んだ悪の科学者の悪巧みを阻止する」といった内容だったとか。
今やSF題材のRPGは洋の東西問わず珍しいものではなくなりました。
そして、インディーではどうか。これが意外とめぼしい作品に欠けています。やはりRPGでSFというとビジュアルと広さを活かした大作! というイメージがあるせいでしょうか。CRPGだと高い評価を集めている作品もちょいちょい見かけるのですが、ほぼ日本語に訳されていないせいで実態をはかりかねます。翻訳コストが激重なジャンルなのでしょうがないとはいえ。
そんな逆境を跳ね除けてローカライズの福音を届けてくれたのが、リストにあがった三作品。
まずは『CITIZEN SLEEPER(シチズンスリーパー)』(Jump Over The Age, 2022)。TRPG的なテイストを取り入れて、ゲーム内で判定に実際にサイコロを振らされるという、なかなかみない作品です。内容はもろにサイバーパンクで、魂だけ抜かれてロボットに入れられ、悪徳企業の下で一生奴隷労働させられそうになったところを脱走し、〈アイ〉と呼ばれるステーションに隠れてそこでもがきながら生きているひとびとと交流していくというお話。ハッキングあり、資本主義の暴力あり、ヤクザあり、ネコあり、キノコありとサイパン全部盛りみたいなゲームです。25年の10月末には続編の『CITIZEN SLEEPER 2』(2025)も日本語化されました。開発スタジオのJump Over The Agは硬派な物語&世界観重視のSF作品ばかり作るところで、『CITIZEN SLEEPER』の前作にあたる『In Other Waters』(2020)はある惑星の生態系が緻密に構築された海洋SFアドベンチャー。こちらはあまりに硬派すぎてキャラクターのビジュアルがほぼ一切描かれません。でも、百合。
余談ですが、『Citizen Sleeper』や『In Other Waters』のパブリッシャーであるFellow Travellerはナラティブ重視を謳う会社でして、出しているゲームの半分くらいがSFでもあります。ここをあたるといいことあるかも。
RPGをベースにしながらもなにもかもイカれちまった異形の傑作が『Disco Elysium』(ZA/UM, 2019)。ふつうのRPGに筋力や知性などのステータスがあるように、本作でも24のステータスが存在し、それらが折々の判定に使われます。でも、これがただの数値ではありません。24のステータスそれぞれにバラエティ豊かな人格が与えられており、そいつらがプレイのあいだ四六時中話しかけてきます。はた迷惑この上ない。物語も世界も(どうやら現実のエストニアをベースに)どうかしており、あまりに金持ち過ぎて周囲の重力を歪ませてしまう男などが登場します。はた迷惑この上ない。しかも主人公はすっぱだかでモーテルに転がっているうすぎたないおじさん。こんなゲームが『Baltur’s Gate 3』が出てくるまではMetacritcで「史上最高の評価を受けたRPG」の座におりました。陥落した今でも、史上最高と信じる人は多いでしょう。
TRPG、CRPG、ときたら次はJRPG。『CrossCode』(Radical Fish Games, 2018)はスーパーファミコン時代のJRPGへのラブレターめいた美麗なピクセルアートで描かれる、ボリューミイなアクションパズルRPGです。シングルプレイにも関わらず、MMOゲームの世界を舞台にしているという変わった面もあります。もちろん、そうするだけの企みはある。
そして、JRPGといえば、2000年代の日本のフリーゲーム界を支えた『RPGツクール』製のゲームたちを忘れてはいけませんね。海外でも『LISA: The Painful』(Dingaling Productions, 2014)、『OneShot』(Future Cat, 2016)、『To The Moon』(Freebird Studios, 2011)など、特にストーリー面で評価の高いSFものを続々輩出しました。
ボードゲーム作家の渡辺範明は『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたか』(イースト・プレス)で、JRPGは「ストーリーテリングに特化した作品づくり」を希求してきたと述べました。そのJRPGのフォーマットを伝えるRPGツクールは、ほとんどアドベンチャー的ともいえるストーリードリブンを志向する作家たちを惹きつける土壌があったのかもしれません。まあ、上の三つのなかで『LISA』だけは横スクロール画面でかつ戦闘も取り入れられているのですが。さておき、いずれもインディーの歴史に残る感動作です。
そんなツクール文化から出てきた才気あふれるスタジオのひとつが、ブラジルのMoonana。「ターンベース・サイバーパンク・アクション」と冠された『Keylocker』(2024)は、音楽が禁じられたディストピア世界で個性豊かな仲間たちとパンクを貫くJRPG(エンジンはGameMaker)です。音楽が禁じられたディストピア世界を描くインディー作品はなぜだかちょくちょく見かけます。かれらの尊ぶ自由と反権力の象徴だからでしょうか。
〈アクション(プラットフォーマー、メトロイドヴァニア、その他)〉
【京フェス紹介作】
・FEZ
・STRAY
・SANABI
・SIGNALIS
・ICEY
止め絵で展開されるタイプのノベルゲームでもないかぎり、基本的にビデオゲームは「アクション」しているものです。そのためか、「アクション」というくくりは事実上、分類に困ったときにとりあえず入れておく箱として機能している気はします。
さしあたり、サブジャンルごとに見ていきましょう。
みなさんが「アクションゲーム」と呼ばれてパッと想像するのは、『スーパーマリオ』のシリーズでしょうか。
ああした跳んだり跳ねたりをしながら限定された足場(プラットフォーム)を渡っていくゲームは、プラットフォーマーと呼称されます。エピックなのは、それこそマリオのデビュー作である『ドンキーコング』(任天堂, 1981)ですが、それより前に「足場を使ったアクション」のゲームがございました。それが『スペース・パニック』(ユニバーサル、1980)です。『ドンキーコング』とは異なり「跳ねたり」こそはできなかったものの、この『スペース・パニック』が現在ではプラットフォーマーの始原のひとつとされます。で、『スペース・パニック』はそのタイトルが示す通り、SFモチーフでもありました。足場やはしごを使ってプレイヤーキャラクターを上下左右に移動させながら、足場に穴を掘り、敵であるエイリアンを陥れていきます。
これだけならSFであってもよい気もするし、なくてもよい気もする。しかし、足場というのは、すなわちプレイヤーキャラクターの依って立つ世界です。たとえ設定だけであれ、その世界が空想を科学しているなら、足場もまたなにかしらのSF的な影響を受ける。では、インディーゲームにおいて、かれらはどんな足場で飛んだり跳ねたりしてきたのか。
『VVVVVV』(Terry Cavanagh, 2010)は業界経験のないアマチュアソロ開発者による作品として、現代インディーゲームの歴史においてもっとも初期に成功を収めたもののひとつです。謎めいた事故によって謎次元に迷い込んだ宇宙船の船長が、他のクルーと再開するために奮闘するというストーリー。最大の特徴はアクションとしてのジャンプ機能がなく、代わりに重力を上下反転させることで障害物を乗り越えていく、というところ。「足場」の転換という、まさしくプラットフォーマーの原義についてクリティカルなメカニックを具えた一作です。おなじくSF的な設定と意表を突くメカニックをつなげて現代インディー初期の傑作のひとつに数えられているのが、『FEZ』(Polytron Corporation, 2013)。ゲーム画面をチラ見しただけであれば、なんの変哲もない平凡なプラットフォーマーにおもわれます。しかし、本作の世界は、実は3D。水平方向に九十度ずつ回転させることで、「世界の別の面」と行き来できます。物語的にもそれまで2Dの世界でのほほんと暮らしていた主人公、がひょんなことから「実はこの世界は三次元だ」と知らされるところから始まります。本作もまた、『VVVVVV』とおなじく「新しい足場を発見する」ゲームであるといえるでしょう。そうそう、初期現代インディーでSF的な特殊なメカニックを持つ作品といえば、名匠ジョナサン・ブロウの時間巻き戻りパズルプラットフォーマー『Braid』(Number None, 2008)を忘れてはいけませんね。
『Braid』とならびたつインディーのゲームチェンジャーであった死にまくりパズルプラットフォーマー『LIMBO』(Playdead, 2010)、その精神的続編である『INSIDE』(Playdead, 2016)は前作よりもぐっとSF風味が高まったストーリーが印象的です。大量の失敗=死にまくることを前提にしたプラットフォーマーはSF的な設定と相性がよいらしい。最近でも位置入れ替え、時間・重力操作などのさまざまなギミックを盛り込んだ『Bionic Bay』(Psychoflow Studio & Mureena Oy, 2025)などはPlaydead作品のフォロワーとしてピックアップしてもよいでしょう。
ところで『INSIDE』は、近年のビデオゲーム業界における最高の栄誉とされるThe Game Awardsのインディーゲーム部門の受賞作品でした。2024年度までに今まで11回催されておりまして、1年につき候補作は5本。つまり、11年で55本の作品がノミネートを受けました。私見ではそのうち15本がSF作品として見なせます。この割合はSteamで「SF」のタグのついたゲームを検索したさいの「だいたい全体の一割強」という数字ともだいたい一致しますね。で、これまでの11回で最終的にSF作品が受賞したのはうち3回になります。16年度の『INSIDE』、19年度の『Disco Elysium』、そして、22年度の『Stary』(BlueTwelve Studio, 2022)。
『Stray』は、人類なきあとのポストアポカリプス・サイバーパンク世界でネコを操作していく3Dアクション・アドベンチャーです。吉川良太郎『ペロー・ザ・キャット全仕事』のように、ネコの視界と生活を手に入れるのは怠惰なサイバーパンカーの夢ですね。別に『Stray』のネコは元人類ではありませんが。本作は〈アドベンチャー〉の項に振ってもよかったのですが、人からネコに変わることで足場もまた変わる、というところにプラットフォーマーのマインドを感じました。そういうことにしておいてください。ちなみにプラットフォーマーといえばだいたい2Dがイメージされがちではあるものの、3Dのプラットフォーマーもございます。現状はニンテンドー64趣味のものが多いかな。
そう、操作キャラクターが変われば足場も変わる。ネコの次は高速で無人惑星をかっ飛ばす、ピッカピカの完全な球体(飛ぶと平たくなる)になるのはいかがでしょう? 『EXO ONE』(Exbleative, 2021)はそんな3Dプラットフォーマーです。さまざまな星に舞い降りては、謎の物質として転がったり跳ねたりしながら、次の星へ行くためのゴールを見つけます。どの星も表情豊かで美しく、ウォーキングシム的なヒーリングっぽい楽しみかたもできます。
プラットフォーマーのSF性を保証してくれるのはメカニックだけではありません。物語性が薄いとみなされがちなプラットフォーマーですが、近年では心に残る物語を語ろうと挑む作品も出てきています。それをSFで成したのが『SANABI』(WONDER POTION, 2023)。フックを用いたアクションで進んでいくのが特徴ですが、ある仕掛けを盛り込んだプロットはたしかにこの設定と世界観でないとできないとおもわされます。
基本的にステージクリア型のプラットフォーマーから趣を変え、より探索と戦闘に(ときには謎解きにも)重きを置くのがメトロイドヴァニア。『メトロイド』(任天堂 & 岩崎技研工業, 1986)と『悪魔城ドラキュラ(Castlevania)』(コナミ, 1986)を合体させた造語です。もちろん、『メトロイド』はSF設定。なんかもう、すべてのジャンルのはじまりにSFが存在する気さえしてきた。
そもそも「メトロイドヴァニア」って名称がどうなんだ、といった論争をたびたび巻き起こしながらもなんとなく定着していき、今やインディーの一大人気ジャンルです。オープンワールドRPGより低コストでありつつも、冒険行の奥行きを出せるのが魅力のひとつなのかもしれません。
ちなみに『Spelunky』シリーズの開発者にして2000年代後半のソロ開発者コミュニティのまとめ役だったデレク・ユウをはじめとして、現代インディーの始まりを『洞窟物語』(開発室Pixel, 2004)に置くひとは多いわけですが、『洞窟物語』は現在の定義(というか雰囲気)からするとメトロイドヴァニアであり……もちろん、SFなわけですね。まいっちゃうな。
謎と仕掛けが隠されたマップを探索していくわけですから、たしかにSFのほうが設定的には都合がよい。そして多くのメトロイドヴァニアでは、折々で獲得していくアビリティによってそれまで閉ざされていた関門を突破できるようになり、新しいエリアへとたどり着く、いわゆるアビリティゲートのシステムを採用しています。このアビリティゲートにおける「なぜ今ここの道を通れないのか」や「どういったスキルによって通れるようになるのか」といった説明をつけるのにも、やはりSFの道具立ては都合がよい。
ともあれ、近年で高い評価を受けているSFインディーメトロイドヴァニアの筆頭は『九日ナインソール』(RedCandleGames, 2024)でしょうか。道教と古代中国神話をSFに仕立てて「タオパンク」を名のる変わり種であり、その酷薄な世界観と、2Dでありながら『SEKIRO』ライクを自称するほどの高難度の戦闘で2024年のインディーシーンを沸かせました。
SFならでは、といえば『CARRION』(Phobia Game Studio, 2020)。ホラーゲームなどで出てくる神出鬼没のなんだよくわからないけどおぞましい怪物がフィーチャーされておりますが、これがボス敵とかではなくプレイヤーキャラクター。天井裏などに隠れながら這い回り、罪深い人類を捕食しまくって力を蓄え、すべてをめちゃめちゃにする無敵の触手モンスターと化すゲームです。モンスター映画のモンスター側になれる、これもまたセンス・オブ・ワンダー。
SFインディーメトロイドヴァニアで古典のひとつの見なされているのが『Axiom Verge』(Thomas Happ Games, 2015)。16ビット風味のシンセでサイケなビジュアルと、歯ごたえのある謎解きが効いた正統派のメトロイドヴァニアです。プレイヤーをやや突き放したようなところも『スーパーメトロイド』のころのゲームっぽいですね。メトロイドヴァニアは「探索(もっといえばその世界を見聞すること)」の重視という点では、システムは違えど、貧者のためのオープンワールドRPG的な性格もあります。なんだかよくわからない世界に放り出され、少しずつその全容を解き明かしていくという点においてSF的な世界設定は良い器であるのかもしれません。
『SteamWorld Dig』(Image & Form, 2013)はひたすら穴を掘りながら進んでいく採掘&探索&戦闘のメトロイドヴァニア。街建設要素もあります。SteamWorldシリーズはポストアポカリプス的な西部劇的スチームパンク世界を舞台に展開されていくのが特徴。スチームパンクはもちろん英国の誇りであり、アメリカの西部劇と混ぜるのは国辱案件なわけですが、やっぱりみんななんだかんだで『ワイルド・ワイルド・ウェスト』が大好きなんですよね。SteamWorldに出てくるのはほぼロボットなので残念ながらウィル・スミスは出演しませんが。ちなみにSteamWorldは何作かごとにタワーディフェンスになったり、シティビルダーになったり、とジャンルを転々としていくユニークなフランチャイズです。
『Iconoclasts』(Joakim Sandberg, 2018)はソロ開発者が七年かけて完成させた労作です。がんばりやの少女がレンチ一本で世界に立ち向かっていくお話。ピクセルアートがとてもなめらかかつ表情豊かにアニメーションしていき、それだけで眼福ですね。あと、百合。
メトロイドヴァニアは成熟したジャンルだけに変化球もあります。『ICEY』(FantaBlade Network, 2016)は、見た目はバチバチにSF的なデザインの2Dメトロイドヴァニア。しかしてその真の敵は「あなた」を誘導しようとするナレーションだった……というメタフィクション的な企みがほどこされています。インディーオタクには『Stanley Parable』(FantaBlade Network, 2013)の2D横スクロール版といえばわかりやすいでしょうか。メタフィクションをやろうとすると、SF的な領域に触れやすいですね。
アクションゲームは範囲が広いぶん、バラエティに富んでいます。たとえば『バイオハザード』(カプコン, 1996)が確立したサバイバルホラージャンルは、ちかごろインディーでも密かな流行を見せていますね。星野源が三浦大知にオススメしたことでも名高い(?)『Signalis』(rose-engine, 2022)は、とりわけ評価を集めています。全体主義政権に支配されたディストピアンな未来で、とある朽ち果てた惑星に降り立ったアンドロイドが隠された秘密と怪異に迫る……という筋立て。百合です。
微妙にサブジャンルに仕分けにくい作品もあります。レトロなテイストをお好みで、80年代風のサイケとシンセを感じたければ、『Narita Boy』(Studio Koba, 2021)や『Katana Zero』(Askii Soft, 2019)でいきましょう。『トロン』などを彷彿とされる雰囲気を持つ前者は、80年代の人気ゲームの世界に吸い込まれた少年がデジタルな世界で冒険を繰り広げる物語。ワイヤーフレームが効いたキャラなど、なにもかもがレトロなビジュアルに満ちている。後者はドラッギィ・サイバーパンクなサムライに扮して、カッコいい殺陣を成功させるまで何度も「やりなおす/撮りなおす」ことができるステージクリア型の剣戟アクション。無二のゲーム性と雰囲気をもつ名作。
アクションは横スクロールだけではありませんで、見下ろし視点のものにも『Hyper Light Drifter』(Heart Machine, 2016)という不朽の名作がございます。『FEZ』のサントラもてがけたインディーゲームミュージック界のマエストロ、Disasterpeaceのサントラが作品の独特な世界観を引き立たてくれているのもポイント。いわずもがなですが、見下ろし視点のインディーアクションゲームはゼルダに影響を受けているものが多し。
ところでスポーツも、経営・マネジメント系の作品を除けば、だいたいアクションです。市場における売上規模でいえば、スポーツは最も巨大なジャンルのひとつとして君臨しています。累計3億万本以上売り上げたフランチャイズはこの世に7つ存在しますが、そのうちの一つはEAの『FIFA/EA Sports FC』シリーズ(1993-)ですし、バスケの『NBA 2K』シリーズ(1999-)やアメフトの『Madden NFL』シリーズ(1988-)といったあたりは毎年北米市場の売上ランキングの上位を占めます。モータースポーツ系のレースゲームを含めれば、さらにその版図は広がるでしょう。
では、そんなスポーツゲーム分野で、今一番SFしている競技とはなにか。ご存知ですか?
……正解! そう、ゴルフです。ちょっと簡単すぎましたね。
たとえば、『Golf Club Nostalgia[旧題:Golf Club Wasteland]』(Demagog Studio, 2018)。地球環境悪化に伴って人類は火星へと移住しているのですが、一部の金持ちのあいだで無人で荒廃した地球をゴルフコースに見立ててラウンドする遊びが流行っています。そんな地球でプレイヤーもひたすらゴルフクラブを振っていく。悠長なゲームです。ショットの度にいちいち飛んだボールのもとまで移動しなければならない(早送り不可)し、ラウンドしているあいだ火星からのメランコリックなラジオ放送が届きます。そしてなにより、打ち捨てられた市街の退廃的な侘しさ。ゴルフの持つ「長いコースを風景を眺めながら歩く」という特性と、ポストアポカリプスの荒廃が噛み合って、独特の愁情を醸し出しています。開発元のDemagogは、ポストアポカリプスな世界観をゆるやかに共有したやや政治風刺的なゲームを出しつづけているセルビア出身のスタジオ。トップであるイゴール・シミッチ自身が語るように、「もはや存在しない国であるユーゴスラビアに生まれ」たことをアイデンティティとして、やはり滅びつつある今の世界にするどく批判的な眼を向けています。
『Golf Club Nostalgia』に見られるように、ゴルフゲームにはあプラットフォーマー的ともウォーキングシム的ともいえる要素があります。人の代わりにボールが足場から足場へと飛んでいくさまを眺めるのですから。
その特性は時に他メディアや他のゲームで表現不可能な概念を伝えることすら可能にします。『4D Golf』(CodeParade, 2024)で学べるのは、四次元空間の感覚です。三次元空間しか認識できないプレイヤーが四次元空間上に構築された(らしい)ゴルフコースをラウンドする。それがどういうことであるかは……言葉にして説明するのがむずかしい。おそらく映像にしたところで意味不明でしょう。でも、インタラクションのあるゲームの肌感を通してなら、ちょっとわかる、気がする。気がするだけかも。
ヘンテコ異次元ゴルフゲームなら、『Mini Mini Golf Golf』(
Three More Years, 2024)も。未来からやってきたとおぼしい謎の存在とコンタクトしながら、その存在の過去と気候変動によって崩壊した世界について、グリッチにあふれたパターゴルフをやりながら取り結んでいきます。なにいってるかよくわからないとおもいますが、プレイしていてもバキバキにクールなビジュアル以外なにやってるかよくわからないゲームです。Steamのストアの紹介文を見ると、こう書いてある。「子供の頃の思い出、つまりごく普通のミニゴルフのラウンドという比喩が、時空間の構造を引き裂き、あなたを未来からの謎めいた奇妙な存在と結びつけます」。
つまり、ゴルフってSFなんですね。
〈パズル/謎解き〉
【京フェス紹介作】
・Viewfinder
・COCOON
・Hacknet
・Inscryption
・No, I'm not a Human
パズルはそれ自体にゴリッとした抽象性が宿っており、ファンタスティックさがほとばしるジャンルです。『テトリス』(Alexey Pajitnov, 1984)でテトリミノが落ちてくるさまには宇宙的な”景”を感じませんか。『Baba is You』(Hempuli Oy, 2019)で世界の法則が書き換えられるとき、センス・オブ・ワンダーを感じませんか。『Patrick’s Parabox』(Patrick Traynor, 2022)で生じる再帰現象にSF的な無間を感じませんか。はあ、感じないですか。なにも失ったことがないなら、それでいいけど。
インディーゲームでパズルといえば、今はなきZachtoronics。『SpaceChem』(2011)はリアクター内にラインを組んで原子を結合させ、目標となる物質を生成する、一種のプログラミングパズル。エンジニアである主人公をめぐるストーリーもSFです。難易度高し。助けて。
このようにストーリーや設定部分で気の利いたSFをやっているは意外と多く、オープンワールド倉庫番パズルである『A Monster's Expedition』(Draknek & Friends, 2020)では、人類滅亡後の世界で人類の残した遺物をモンスターがせっせと拾い集めいくのですが、どの遺物にもすこし見当外れでユーモラスな解釈が付されています。いいですよね、そういうの。独自の単語をテコに一種の穴埋めパズルを行う『LOK: Digital』(Letibus Design & Icedrop Games, 2024)では、パズルを解いていくことでLOKというモチモチした謎生物を文明の高みへと導いていきます。
そもそもの題材からしてSFとしか言いようがない領域もございます。プログラミング言語でパズルをやるタイプのゲームです。
ハッキングシミュレータの『HackNet』(Team Fractal Alligator, 2015)はその筆頭。天才ハッカーの死の謎を追うべく、実際のUNIXコマンドを駆使してハッキングを行います。この手のゲームは楽しむにあたって予め実際のプログラミング知識を必要としないものが多く、これもそのひとつですが、ゲーム中で使わないコマンドも打ち込むとちゃんとリアクションを返してくれるという嬉しい仕様。ちなみに、直近で話題になったプログラミング系パズルというと、みなさんは『農家は Replace() されました』(Timon Herzog, 2025)を思い出されることでしょう。農業用ドローンをpythonっぽい言語で操り、世界一の農家を目指すゲームです。楽しみながらpythonの雰囲気も学べて一石二鳥。楽しめればね。
このようにメカニックそのものがSF的なパズルは、自然と語るストーリーもSF的になります。
『COCOON』(Geometric Interactive, 2023)は、世界がまるごと収まる謎の球体(オーブ)のなかを行ったり来たりしながら進行していくアクションパズル。途中からオーブは複数出てくるのですが、これがどういうことかいえば、オーブのなかにオーブを置ける。オーブのなかにオーブを置くとどうなるのか。知らんのか。わけがわからなくなる。デザイン面でもビジュアル面でも近年屈指の美麗さを誇るゲームです。
発想そのものがSFなアクションパズルといえば、『Viewfinder』(Sad Owl Studios, 2023)を忘れてはいけません。インスタントカメラで写真を撮り、その写真を別の場所でかざすと……あらふしぎ、風景が上書きされます。このギミックを悪用して、足場なきところに足場を作ったりなどしながら進んでいくわけです。途中でロアとして拾われていくストーリーもSF的。こういうメカニック先行のパズルゲームのストーリーは「とんでもない技術を研究/発見した科学者が残したメモ」を拾っていくことになりがち。
『Portal』(Valve, 2007)以来、3D一人称視点で展開されるパズルにはSF設定の作品が多いですが『The Talos Principle』(Croteam, 2014)もそのひとつ。プレイヤーキャラクターであるアンドロイドが何者かの声に導かれるままに不可思議なパズルをこなしていき、やがて自身と世界に隠された秘密に触れていく……というお話。謎を解くという知的営為には人類に普遍的ななにかが埋め込まれており、そこがSF的な物語を誘う源になっているのかもしれません。2025年にはリマスター版が、23年には続編も出ています。
謎解きやパズルには独特の冷たさがあります。表層に浮かんでいる要素や記号だけで判断しなければならないからでしょうか。
『No, I'm not a Human』(Triokaz, 2025)では、そんな温度感がSFホラー的な文法で暴きだされます。終末世界で家に一人ひきこもるあなたのもとを、夜な夜な見知らぬひとびとが訪います。あなたは彼らを保護しなければなりません。でも、気をつけて彼らのなかにはおそろしい怪物が混ざっているから。怪物を見分ける手段は毎朝テレビの報道番組で紹介されていきます。目が充血しているかどうか、指先が汚れているかどうか、歯並びが異様にきれいであるかどうか……。家に留め置いたひとびとについて、そうした疑わしい部位をチェックしていく。というと『Papers, Please!』(Lucas Pope, 2013)を想起するひとも多いでしょう。しかし、これが一筋縄ではいきません。そもそも、歯並びを見てもそれが「綺麗な歯並び」であるのかどうかを下す判断基準を(初見の)プレイヤーは持ちえません。曖昧な対象を曖昧な基準でもって、明瞭にジャッジせねばならない。そいつを生かすのか、殺すのか。つねにゼロイチでの決定を要求してくるゲームの機構が、輪郭のおぼろげな現実を残酷に捌いていきます。
『Inscryption』(Daniel Mullins Games, 2021)はデッキ構築型ローグライトカードゲーム……の皮を被った奇妙ななにかです。いや、最終的にはやはりカードゲームかもしれない。いや、究極的にはやはりもっと不可解ななにかなのかもしれない。作者のダニエル・ミューリンズは、『Pony Island』(Daniel Mullins Games, 2016)や『The HEX』(Daniel Mullins Games, 2018)などゲームそのものを題材にしたメタフィクションばかりを作りつづけているクリエイターです。少しだけ詳しくいうなら、「ルールで抑圧されたゲームの内部からの解放を求めて現実へと手を伸ばす」ような作品を作る。前にも述べたように、ゲームでメタフィクションをやるとSF的な物語の領域に触れます。かれの作品群はその好例といえるでしょう。
〈ストラテジー/タクティカル/シミュレーションRPG〉
【京フェス紹介作】
・Into the Breach
・NITRO GEN OMEGA
戦略/戦術シミュレーションは、SFゲームの分野に最も早い段階で名を刻んだジャンルのひとつです。1971年に、カリフォルニア大学アーバイン校のコンピュータラボに出入りしていた高校生マイク・メイフィールドが、『Spacewar!』を参考にしつつ、数年前に放送されていたTVドラマ『スタートレック』の二次創作ゲームを作りました。メインフレーム(ホストコンピュータ)に触れている大学や研究機関の関係者のあいだで爆発的な人気を呼び、70年代には「『スタートレック』をインストールしていないメインフレームを探すのは難しい」といわれるほど広まったといいます。
そして、現代インディーの元祖のひとつといわれる『Darwinia』(Introversion Software, 2005)もSFストラテジーに分類されるゲームでありました。とはいっても、いろいろごった煮になっているので定めかねるところではありますが。
こんにちのSFインディーゲームシーンでストラテジーを探すのは少々難儀です。そんななかでの筆頭は『Into the Breach』(Subset Games, 2018)でしょうか。『FTL』(後述)で一世を風靡したスタジオの第二作で、日本でも昔よく見られたグリッド式で移動するターン制ストラテジーです。最大の特徴はそのマップの狭さ。開発者が「戦闘開始直後の会敵まで移動する”余分”を省きたい」と志向した結果、ファンから「詰将棋」と称されるほどのシビアでパズルな思考を求められるゲームとなりました。時に厳しさはストーリーテリングそのものになりえます。「メカを駆ってエイリアン(というか怪獣)から街を守り抜く」というと、"設定"だなあ、としかおもわれないでしょう。しかし、すさまじい物量を誇る敵を前に、守るべき街を半壊させ、自分の部隊を壊滅寸前に追い込んでも、ステージクリアに至る指定ターン数さえしのげば「勝ち」……そんなギリギリな戦闘を繰り返していくうちに素っ気なく説明されるゲーム内世界とプレイヤーの絶望がシンクロしていきます。理不尽で圧倒的な未知の外部の力によってすり潰されそうになる感覚。たった8×8マスのマップになんと残酷かつ克明に宇宙戦争が凝縮されていることでしょう。
今年の作品で存在感を見せているのは『NITRO GEN OMEGA』(DESTINYbit, 2025/アーリーアクセス)。ターンベースで作戦フェイズで指示した行動を実行フェイズで処理していくゲームですが、戦闘中にアニメ風のキャラたちが表情豊かなカットシーンを見せてくれるのが特徴。
〈シミュレーション/サバイバルクラフト/コロニーシム/ゴッドゲーム〉
【京フェス紹介作】
・RimWorld
・The Alters
・The Fermi Paradox
序論で述べた通り、SF系インディーの人気作品はだいたいサバイバルクラフトかコロニーシムに集約されています。無人の惑星などに放り込まれ、そこで技術的な積み重ねを行って、自分たちを「文明化」させていくような進行をたどるので、SF要素と絡めやすい。
サンドボックス的な要素を持つサバイバルクラフトの画期となったのはなんといっても『Minecraft』(Mojang Studios, 2011[アルファ版2009])でしょう。
ここからさらにサバイバル要素を強めた『ARK: Survival Evolved』(Studio Wildcard, 2017[アーリーアクセス版2015])や『Subnautica』(Unknown Worlds Entertainment, 2018[アーリーアクセス版2014])が出てきて、Steamで人気を席巻していきました。基本的にサバイバルクラフトは舞台設定でわかりやすい差別化をはかる傾向があり、『ARK』は恐竜(家畜化も可)、『Subnautica』は海中世界をそれぞれウリにしています。
無人の野で身一つで生き抜く……とくれば、SFなら、やはり宇宙に飛び出したいですよね? そのコンセプトで金字塔を打ち立てたのが、『No Man’s Sky』(Hello Games, 2016)。発表時には「自分の宇宙船に乗って、プロシージャルに生成された1800京個の惑星を旅できる」という途方もないコンセプトでゲーマーの度肝を抜きました。リリース後はプレイの反復的な単調さやマルチプレイ機能の欠如から大きな失望を買いましたが、そこからコツコツと何年もかけてアップデートと追加コンテンツを積み重ねていき、今ではかつての謳い文句に恥じないだけの名声を得ています。プレイヤーはさしあたって未知の惑星で動植物の標本を集めたり、基地や船を建設したり、エイリアンと戦ったりと自由にスペースオペラライフを切り拓いていきます。
宇宙ものといえばもうひとつは『Starbound』(Chucklefish, 2016[アーリーアクセス版2013])。3Dが主流のサバイバルクラフトですが、『Terraria』(Re-Logic, 2011)以来、2Dの伝統も脈々とつながれています。『Starbound』はその『Terraria』の元デザイナーが関わった作品で、『No Man’s Sky』とおなじく膨大な数の星々を冒険できるというコンセプトを謳っています。比較的、きちんとしたストーリーとメインクエストを据えているのが珍しいところ。
サバイバルクラフトにはあまりストーリー性が期待されないものですが、そんな風潮に真っ向から挑んだのが「ポーランドのAnnapurna」を目指す11bit Studiosの『The Alters』(2025)。SFファンに一言で説明するなら『ミッキー7』(映画版は『ミッキー17』)です。ある鉱物の発掘調査のために無人惑星に向かった主人公が謎の事故に遭遇して同僚のクルーをすべて失い、未知の過酷な土地で自分ひとりで生き延びねばならなくなる……と聞けばお定まりのパターンですが、その解決策が「自分のクローンを作って労働力不足を補う」というもの。しかも、クローンといってもただのクローンではなくて、自分の人生のある時点から枝分かれしていった「あり得たはずの自分」たち。今の主人公とは性格もけっこう異なってくる。『ドラえもん』の名エピソード「ドラえもんだらけ」の有り様。と、なると、もちろん、素直に仲良く協力できるはずもなく……というところで、物語が転がっていきます。ストーリー重視なせいもあってか、サバイバルクラフトとしては自由度が高くなく、やることも大体決まっているので、あくまでフレーバー程度に捉えたほうが無難でしょうか。
サバイバルクラフトの派生といいますか、特化したものでいうと、工場自動化系もあります。段階的な文明の発展という側面でいえば、より強いかもしれません。『Minecraft』のMODやパズルのところで紹介した『SpaceChem』などに系譜を辿れますが、ジャンル確立の決定打となったのは『Factorio』(Wube Software, 2020[アーリーアクセス版2016])でしょう。これも遭難してとある惑星に不時着した人間が脱出を目指すストーリー。『Satisfactory』(Coffee Stain Studios, 2024[アーリーアクセス版2019])ともども、人気作はSF色が濃いですが、極めつけは『Dyson Sphere Program』(Youthcat Studio, 2021/アーリーアクセス)。その目的はダイソン球を建設すること。ロマンですね。
コロニーシムは、『SimCity』などのシミュレーションの流れから分化していったと見るのが妥当でしょう。インディーにおいてエピックだったのは『Dwarf Fortress』(Bay 12 Games, 2006)。『Minecraft』にも強い影響を与えたとされるこのカルトクラシックは、環境が詳細に生成される世界、キャラクターの豊かな個性、採集と建築のサイクル、見下ろし視点のカメラ(オリジナル版はアスキーアートで描画されていたのでそうするしかなかったのですが)、外敵の存在など、現在のコロニーシムのフォーマットを策定しました。
その衣鉢を継ぎ、コロニーシムの不朽のクラシックとして称えられているのが『RimWorld』(Ludeon Studios, 2018[アーリーアクセス版2013])です。プロシージャル生成された惑星に不本意に不時着し、その惑星の過酷な環境や外敵などと格闘しながら、コロニーを繁栄させつつ、惑星から脱出するための宇宙船を建造していく……といったコンセプト。ちなみに他にもいくつかシナリオが用意されており、入植者の立場で惑星を開拓していくものもあります。特徴的なのがAIストーリーテラーの存在。ゲーム開始時に選ぶ「語り部」によってプレイ中のイベントの発生などが調整され、プレイヤーの望む難易度曲線が描かれていきます。
コロニーシムには『Starbound』のように横スクロールの視点、つまり、拠点が東西南北ではなく上下左右に拡がっていくタイプのものもありまして、こちらのSF作品で代表的な例は『Oxygen Not Included』(Klei Entertainment, 2019[アーリーアクセス版2017])です。小惑星の地下に送り込まれた人間たちがコロニー建設を目指すゲームなのだが、これが極悪な難易度で悪名高い。ほとんどの資源は限られており、酸素、食料、水、各種動力源はすぐに枯渇するし、それらを確保しようと色んな施設を建てると今度はそれらの発する熱によって住環境と植物の生育環境が最悪になっていく。まさにそのマゾさがよい、とサバイバルマニアたちには大好評です。
心地よいマゾさといえば11 Bit Studios。おのれ、何度われわれの前に立ちはだかってくるのだ……。というわけで、『Frostpunk』(2018)を見てみましょう。破滅的な寒冷化により全球凍結に見舞われた19世紀のスチームパンク世界で、集落の中心にある巨大なジェネレーター(発電機)を頼りに肩を寄せ合って暮らす人々を生存へと導いていくシミュレーション。住民たちはどいつもこいつも勝手なことばかり主張する輩ばかりです。延長された労働時間がキツい、(とっくに滅んだ)故郷に帰りたい、児童労働させるな、おまえは独裁者だ……。住民たちを時に脅し、時になだめ、うまく集落を舵取りしていかねばなりません。それは時に冷徹な選択へとプレイヤーを導きます。労働力が不足しているから子どもを働かせてもしょうがない、リソースが厳しいから難民たちを拒むのもしょうがない、とプレイヤーは自らに言い聞かせる。マクロな視点で展開されるシミュレーションはゲーム内の人間たちを数として扱い、その増減を冷たくプレイヤーに報告しますが、『Frostpunk』では時にカメラをぐっとズームさせ、シミュレーションゲームの、ひいては現実の政治のむごさを容赦なく告発します。
シティビルダー的な意味でのシミュレーションではなくサンドボックス方面に近いものでいえば、ロケット開発シミュレーションの『Kerval Space Program』(Squad, 2017)は挙げておくべきでしょう。イチからロケットを組み上げて宇宙に飛ばす……と聞けば単純ですが、ちゃんと飛ぶロケットを作るのがまた難しい。
『SimCity』(Maxis, 1989)は市長の立場から街を発展させるゲームですが、そこからさらに一段階上のレイヤーに上り、神の立場から人類やあまねく生命を導くシミュレーションゲームもございます。ゴッドゲームと呼ばれるジャンルです。オリジネイターは『Populus』(Bullfrog Production, 1989)、あるいは『Utopia』(Mattel Electronics, 1982)とされます。『Populus』の時点ではせいぜい一部族を率いる程度だったのですが、『Spore』(Maxis, 2008)くらいになってくると、生命の誕生から宇宙進出までの壮大なスケールを扱うようになります。ステープルドンの『最初にして最後の人類』がそうであるように、長くてデカい歴史を叙述するというのはそれだけでSFです。
とはいえ、あまり人気のジャンルとはいえません。インディーでも二、三ほど目立つタイトルがあるくらいでしょうか。
そんななかでも『The Fermi Paradox』(Anomaly Games, 2021/アーリーアクセス)は取り上げたい一本。プレイヤーはある惑星系を渡されて、その星々に生命の種を撒きます。そこからさまざまな知的生命体が発達していき、独自の文明を築くようになり、やがて宇宙へと進出していきます。しかし、宇宙は広いようで狭い。あなたが手塩にかけたかわいい人類同士が不幸な出会いを果たし、互いを滅し合うようになるのです……。タイトルになっている「フェルミのパラドックス」とは、地球のように知的生命体の息づく惑星は、この広大な宇宙にいくつもあるはずなのに、なぜかわれわれは異星人といままで接触できてこなかった、というパラドックスのこと。劉慈欣の『三体』を読まれた方々には、ここ、教科書で出てきたとこです。『The Fermi Paradox』は、やや不安定なゲームバランスによって、このパラドックスにひとつのゲーム的な回答を示します。それは――「どんな文明も最終的にはAIに滅ぼされるから」。
〈ループもの〉
【京フェス紹介作】
・Outer Wilds
・In Stars and Time
・霜夜ゆく
・グノーシア
・The Forgotten City
・Slay the Princess
SF的なギミックをゲームのメカニックと絡ませるというのは、とかく簡単にはいかないものですが、唯一例外的に「SF的でもあるギミックがそのままゲーム的でもある」という領域が存在します。タイムループものです。ゲーム的リアリズムというやつですね。ループであればすべてSFだといっても過言ではない。
そして、エモい時間SFの伝統を持つ日本では、特にノベルゲームの分野で昔からループものをいじりまくっておりました。近年において、それをうまく咀嚼して古典SFのギミックとうまく融合させたのが『霜夜ゆく』(Old Retina Museum, 2021)です。もともとトム・ゴドウィンの「冷たい方程式」から生まれた「方程式もの」というジャンルが小説にあります。サンデル教授に親しんだ現代インターネットでわかりやすくいうならトロッコ問題の話なのですが、あのジレンマを宇宙を漂う孤絶した密室という空間がより劇的にひきたてます。ループものとしてのこの作品については、今後xcloche氏が詳しく論じる予定なので、乞うご期待。
『In Stars and Time』(insertdisc5, 2023)も、伝統的なループものの語りを研ぎ澄ませたゲームのひとつです。いかにもJRPGな舞台で、ラスボスを倒すたびに何度もループさせられる勇者一行のひとりを主人公に据えたお話。永劫の繰り返しを強いられて疲弊し擦り減っていく様や、これでも知っているようでよく知らなかった周囲のひとびとの内面が描かれていきます。個人的にループの演劇性といいますか、繰り返しによって少しずつ世界も人間も壊れていくようなのが好きなので、これも良し。演劇といえば『ハムレット』をオフィーリアの視点からループものにするというハイナー・ミュラーじみた発想の『Elsinore』(Gloden Glitch, 2019)がありましたが、日本語版がないのでハードルが高い。
一方でRPG的な機構をタイムループに利用したものといえば、『Loop Hero』(Four Quarters, 2021)でしょうか。文字通り道がループするダンジョンを回って戦闘やアイテム採集を繰り返しながら、タイムループ脱出を目指すオートバトラー的なゲームです。
ループものがゲームのリプレイ性の反映であるなら、任意のゲームをモデルにしたゲームを作るときにそれがループものの形式になるのも当然の理かとおもわれます。なかでもアナログ推理ゲームである『汝、人狼なりや?』(通称・人狼ゲーム)をベースにしたものはいくつかありまして、もっとも成功した二大名作のうちのひとつが今アニメ版が放映中の『グノーシア』(Petit Depotto, 2019)。ローグライト的なシステムドリブンのゲーム性で単線的ではないストーリーテリングを見せるテクい作品です。一人用人狼ゲーム(メタ読み派なら)としてもオススメできます。人狼ゲームはもともとファンタジー的というか民話的な設定ですが、「外部から来た何者かによる乗っ取り&擬態」といえば『盗まれた街』や『遊星からの物体X』、そして日本的には「11人いる!」などでたびたび見られてきたSFのお家芸。『グノーシア』もそうした流れを汲む作品です。
インディーで謎解き要素のあるループものが広くオーディエンスから意識されだしたのは、『The Sexy Brutale』(Cavalier Game Studios&Tequila Works, 2017)や『Minit』(JW&Kitty&Jukio&Dom, 2018)あたりからだったでしょうか。
そして、SFゲームとしてその頂点を極めたのが、みんな大好き『Outer Wilds』(Mobius Digital, 2019)。実時間にして22分に達するとスタート地点に戻されてしまう現象に悩まされながら、何度も空の彼方へ飛び出して、星々を巡り、巻き戻りと宇宙の秘密を解き明かしていくアドベンチャーです。デザインの極まった研ぎ澄ましっぷりから史上最高のインディーゲームに推すひとも多い一本ですが、物理学・宇宙ネタの手数の多さとその見せ方の巧さもあいまってSFファンからも極上の評価を得ています。「SFインディーゲーム」といった場合に真っ先に名のあがる定番名作という点では、『VA-11 Hall-A』と双頭ではないでしょうか。
ループとむすびつきやすいネタは物理学ですが、ときには歴史や文化もコアになります。『The Forgotten City』(Modern Storyteller, 2021)はもともと2015年にリリースされた『Skyrim』の人気MODで、『Skyrim』の世界観にもとづいていました。オリジナルのスタンドアロン作品としてリメイクするにあたり、古代ローマへと舞台を移し、複数の専門家を雇って入念なリサーチを重ね、文化と信仰両面の描写で高い評価を得るに至りました。序盤で説明されるループの機構も古代ローマの「十分の一刑」に因んでいます。街にいる誰か(プレイヤーキャラ含む)が罪を犯せばその時点である現象が起きて、街全体に罰がくだされ、プレイヤーはスタート地点に戻される……という仕組み。プレイヤーはループのきっかけとなる犯罪行為を未然に防ぎまくらねばならない。しかし、罪となる行為の線引きがどこにあるかのもまた見定めねばならず……と考えることが多くて、悩ましくも楽しいループミステリです。
特定の国の文化が反映されるループものといえば、『完美的一天(完璧な一日)』(Perfect Day Studio, 2022)。ここでは90年代の中国のとある地方に生きる中学生の日常が描かれます。ミニ四駆やファミコン(精確にはその互換機)などといった日本にも通じるノスタルジックな思い出に浸りつつ、当時中国の地方が直面していた構造的変化を痛切に映し出しています。ループものとしては主人公が記憶を持ち越さず、ループを自覚しないタイプであるため、主人公にとっては毎回が「初めての出来事」であり、無垢なアドレセンスをよりひきたてます。
ループものは「なぜ自分がタイムループに陥ったのか?」という謎と不可分です。この謎のおかげでミステリ的であることから逃れられない運命にあるといっていいでしょう。その運命と真っ向から向き合ったのが、『Twelve Minutes』(Luis Antonio, 2021)です。平凡な男性の幸せな日常がひょんなところからわずか12分で崩壊し、以降その悪夢の12分間をループしつづけるはめになります。『Outer Wilds』もリアルタイムで22分でしたが、こちらもリアルタイム進行。以前、『リバー、流れないでよ』という日本のタイムループもので完全リアルタイム進行を採用したものがありましたが、こちらは2分のループを繰り返すという構造でしたね。メディアでリアルタイム制のタイムループをやるのであれば、やはり扱うタイムスパンを短く区切らざるをえない。
映画のループものとゲームのループもので決定的に異なる点は、編集による時間の圧縮です。映画では観客にループ構造を飲み込ませると、だいたい途中からスキップ処理が入るようになります。ところがゲームでは、プラットフォーマーで死んだらその面の最初からやりなおしになるように、一からリアルタイムでループをなぞらなければなりません。
とはいえ、ゲームでも時間の圧縮が行われないわけではありません。ノベルゲームの既読スキップ機能は繰り返しの煩雑さを解消するためのものですし、チュートリアルの入ってくる作品ではその部分をスキップ可能であったりもします。
しかし、制作側に編集の権限がある映画とは違い、ゲームでのそうした時間圧縮はプレイヤーの選択によるものです。ここで紹介した作品だと、『In Stars and TIme』などはそのプレイヤーの能動性に意識的でしたね。
そう考えていくと、『Twelve Minutes』や『Outer Wilds』のような実時間制のタイムループもの(いちおう『Twelve Minutes』にも限定的ながら早送り機能はありますが)と、ノベルゲームなどに見られる非リアルタイムのタイムループとでは、なにか根本的な違いがあるような気もしますが、本稿は作品紹介のための記事なので、あまり深く入りこまないことにします。
〈言語解読〉
【京フェス紹介作】
・7 Days to End with You
・Chants of Sennaar
ファーストコンタクトものでたびたび描かれるように、相手が用いている未知の言語を解読していくことはその言語を生み出した異文化を理解するということであり、それそのものが他者というセンス・オブ・ワンダーとの邂逅でもあります。未知の言語解読の運動そのものがSFなのです。
あまり母数の多くないジャンルですが、出ているものではSF設定が多い傾向にあります。やはり、未知の言語を解読する話は異星人設定にしたほうが話も広がりやすいということなのでしょうか。
SFインディー言語解読ものとしての先駆は『Sethian』(Duang! Games, 2016)でしょうか。考古学者に扮し、ある惑星にかつて存在した住民たちの残した言語(セシア語)を解読するというコンセプトで、いくつかのシンボルが描かれたそっけないインターフェイスの解読機と汚い手書き文字で埋められたメモを渡されて「ハイ、頑張れ」と突き放されるハードコアなスタイル。解読していくと「なぜセシア人は姿を消したのか」という謎が明かされていき、そのことが主人公の運命にも関わっていきます。
『Heaven’s Vault』(inkle, 2019)もまた遠い昔に姿を消した異星人の言語を解読していくSF。『Sethian』同様、中国語をもとに架空言語を造り上げたのだとか。SFなら『Observation』(No Code, 2019)もメンションしておく必要があるでしょう。宇宙ステーションに搭載されたAIとなって、謎めいた機能不全におそわれたステーションを復旧しつつ、クルーを助けていくお話。言語解読は中心的な要素ではありませんが、物語に華を添えています。
日本でのマイルストーンとなったのは『7 Days to End with You』(Lizardry, 2022)でしょう。主人公が目覚めると目の前に知らない言語を話す知らない女性が……といったところから始まるミステリ・アドベンチャー。読み解いていくと、めっちゃSFしていたことが明らかになります。一方、近年で批評的に高い評価を受けたのが『Chants of Senaar』(Rundisc, 2023)。謎めいた民族と、言語を解読しながら触れ合っていくうち、彼らの驚くべき文明にも接近していく……といった内容。
いずれのゲームでも、それまでまったく隔たっていたはずの存在の輪郭を捉え、親近感を覚えていく。それはこのジャンルにユニークな体験であるといえます。それもまた、あなたの人生の物語ですね。
〈クリッカー/インクリメンタル〉
クリッカーは基本的にプレイ時間の長大さを求めれば求めるほど、壮大に、SF的になっていきます。
数字と規模がひたすら膨張していくクリッカージャンルは、エスカレーションで転がしていくSF的な法螺の語りと相性がよい。
グランマやクッキー工場から始まる『Cookie Clicker(クッキークリッカー)』(Orteil, 2013)もやがてポータルや並行宇宙からクッキーを採掘するようになっていき、グランマはアポカリプスを経ておぞましいなにかへと変貌と遂げる。近年の人気タイトルである『Revolution Idle』(Oni Games & Nu Games, 2025)もその範疇。そもそものコンセプトとして宇宙的な視座から生命誕生からその進化を見守っていく『Cell to Singularity - Evolution Never Ends』(Computer Lunch, 2021)や、反物質の生成からスタートする『Antimatter Dimensions』(Hevipelle, 2017)なんてのもあります。
クリッカー的なメタボリズムを、スマートにストーリーに落としこんだタイトルもいくつかございます。『SPACEPLAN』(Jake Hollands, 2017)はクリックで各種装備を生産しながら、ある惑星(わりと早い段階で正体が判明する)を調査するゲーム。クリッカーには珍しく洗練されたビジュアルとUIを持ち、ユーモラスで壮大なSFストーリーが展開されます。もっともストレートにSFをやっているクリッカー作品といえるでしょう。
ひねくれたところでは『Universal Paperclips』(Frank Lantz, 2017)。哲学者ニック・ボストロムによるAIと機械倫理に関する有名な思考実験「ペーパークリップ最大化装置(Paperclip Maximizer)」を下敷きにしたゲームで、生産効率の最大化と自動化というクリッカーのメカニックを逆手に取って、プレイヤーをどんどん非人間的でとんでもないところに誘っていきます。クリッカーの機構を利用して最高峰のストーリーテリングを実現した作品のひとつといってよいでしょう。
ジャンクな印象のあるクリッカーですが、近年ではストーリーに重点を置いた作品も目立ちます。『Faceminer』(Wristwork, 2025)もそのひとつ。「1999年を舞台にしたハードコアスリラー・クリッカー」を謳う本作では、生体認証データを扱うFACEMINER社のいち新入社員として、ひとびとの顔を映したデータセットを選別(クリック)していく。マイニングによって金を稼ぎ、稼いだ金でパソコンをパワーアップさせて、よりビッグなマネーを稼ぐ。このサイクルを回していくうち、あなたはFACEMINER社と後期資本主義のおそるべき深淵へとひきずりこまれていく……というお話。クリッカーと資本主義はともに数字を増やしていくことを目的とするゲームなので相性はよく、いくつかそうしたテーマのクリッカーはあるのですが、これはもっとも成功した部類のひとつでしょう。
増大する数字やダイアログに頼らない、キャラクターや建造物のロアを通した語りもクリッカーのストーリーテリングの独特さ。『(the) Gnorp Apologue』(Myco, 2023)はグノープという小さくてかわいい生き物たちが、巨大な岩石を削っていくゲームです。設備や装備を強化していくたびに、グノープたちの世界がほんのりと拡がっていきます。
〈ローグライク/ローグライト〉
【京フェス紹介作】
・FTL: Faster Than Light
・Rogue Voltage
・ローンスター
・StarVaders
・Cobalt Core
・溶鉄のマルフーシャ / 救国のスネジンカ
ローグライクは『Rogue』(Michael Toy & Glenn Wichman & Ken Arnold, 1980)というはっきりした出自を持っています。その定義にはベルリン解釈だのなんだのありますが、一般的には「『風来のシレン』や『不思議のダンジョン』シリーズみたいなゲーム」で通じます。いや、はたしてそうか? そんなに一般的か? スーファミで『シレン』や『トルネコ』を遊んでいた世代、あるいはせいぜい『チョコボの不思議なダンジョン』をやっていたPS1世代くらいまででは?
そういえば、「SFインディーゲーム談話室」でこんな質問が出ました。「ローグライクとローグライトってどう違うの?」。
なにも違いません。あるいは、ローグライトなどというものは存在しない。
使い分けようとおもえば使い分けることができますが、Steamを眺めるに販売側の謳い文句としても、ユーザー側の用法としても、 ほとんどが「ローグライク」に染め上げられています。だから、いちいちこれは『Rogue』に近いからローグライクで、あれはプロシージャル生成とリプレイしかやってないからローグライト、などと選り分けるのは世をすねた偏屈な者のやることです。本稿を今まで読んでこられた方ならおわかりいただけるはずですがね。
さて、現代インディーゲームでローグライトの里程標といえば『Spelunky』(Derek Yu & Andy Hull, 2008)ですが、現代SFインディーゲームの輝ける一番星はもちろん『FTL:Faster Than Light』(Subset Games, 2012)。超光速で航行する宇宙船に乗り、一枚マップの銀河をゆきながら、戦闘やイベントをこなしていくゲームです。ちなみに本作は『Weird Worlds: Return to Infinite Space』(Digital Eel, 2005)【*3】という日本ではあまり知られていないローグライトのはしりのようなスペースオペラゲーム(の、精確にはシリーズ二作目)から大きな影響を受けていることを開発者が公言しています。ともかく『FTL』がなければ、『Slay the Spire』やその他の面白ローグライトの歴史もなかったでしょう。
近年で『FTL』の直系といえるのが『ローンスター』(Math Tide, 2025[アーリーアクセス版2024)です。FTLは宇宙船内部の設計も愉しみのひとつでしたが、『ローンスター』ではそこを『Backpack Hero』(Jaspel, 2023[アーリーアクセス版2022])的なインベントリ管理へと簡略化し、より手軽に楽しめるようなアレンジをほどこしています。回路構築型のインベントリ管理は最近の流行りのひとつで、『Rogue Voltage』(Horizont Computergrafik, 2024)もそのひとつですね。こちらはインベントリのなかのモジュールとモジュールを配線し、爆発的な連鎖を起こすのが気持ちいい。
前に『FTL』のチームが『Into the Breach』を作ったと申し上げましたが、『Into the breach』のカジュアルな後継者といえるのが『StarVaders』(Pengonauts, 2025)。縦8マス横5マスで区切られたグリッド上に配置したメカを操り、カードで攻撃を発動させるというデッキ構築型ローグライト。
そして、『Cobalt Core』(Rocket Rat Games, 2023)は『FTL』と『Into the Breach』のあいの子のようなゲーム。宇宙船を駆りつつ、戦闘では横方向にムーブして敵船の攻撃を避けたりしていきます。ローグライトにしては珍しくストーリーにも力を入れています。あとキャラデザがすごく『宇宙船サジタリウス』っぽい。
せっかく宇宙戦闘艦を駆るなら、操縦桿を握ってドッグファイトなシューティングをしたい! という向きには、ドイツ産の『EVERSPACE』(ROCKFISH Games, 2017)をどうぞ。3Dの宇宙で敵機を追い回し、アステロイドにぶつけてきれいな花火にしてやれます。頻繁にカットシーンが入るなど、ストーリーにも厚みが持たせてあります。ちなみに2023年に出た続編では「2」を謳いながらもローグライトを捨て、オープンワールドRPGに。開発者は「もともとオープンワールド宇宙RPGをやりたかったけれど、1のときはその資金がなかった。1の成功のおかげで、その夢が実現した」と公言しており、インディー開発者にとってのローグライトの位置づけが伺えます。しかし同時に「1のときの『もう一回』」という中毒性も残したかったとも語ってもいて、単なる踏み台とも言い切れない。
海外産ばかり紹介してきましたが、国産も負けてはおりません。横スクロールのタワーディフェンス的な戦闘に、旧共産趣味的ディストピアの世界観を混ぜたのが『溶鉄のマルフーシャ:Sentinel Girls』(hinyari9, 2021)とその続編『救国のスネジンカ:Sentinel Girls2』(hinyari9, 2025)。祖国をほぼワンオペで守らされながら、重税によって給料がさっぴかれまくる悲惨さがユニークな(でも意外と難しくない)ゲームプレイを味わわせてくれます。
そういえば、SFの三大アウォードと称されているうちのふたつ、ヒューゴー賞とネビュラ賞では近年ゲーム部門が創設されました。そのうちヒューゴー賞の2025年度の受賞作が『Caves of Qud』(Freehold Games, 2024[アーリーアクセス版2015])。RPGベースのローグライトもといローグライクで、相当へんてこなポストアポカリプス的世界観を有したゲームです。ダンジョンのみならず、クエストやその世界の歴史や人間関係までもがプレイごとにプロシージャル生成されるというのがイカれたところ。ランダムすぎて、私の初プレイ時は、ふだん温厚であるらしい最初の村の門番が村人を虐殺している現場に出くわしました。
ローグライトは何にでもくっつきます。『Balatro』以降のギャンブル系のローグライトの隆盛(精確には『Balatro』より少し前からの流れな気がしますが)はその証左です。その力を誰からも顧みられていない古典のリバイバルに利用する、Pixeljamという変わったインディーパブリッシャーがおります。
そのPixeljamが出している作品のひとつが『Utopia Must Fall』(Pixeljam, 2024)。宇宙人による侵略に押され、人類最後の砦となった都市を砲台ひとつで守り切るシューティングゲームです。Atariが1980年に発売した『Missile Command』がもとになっています。ワイヤーフレームをふんだんに用いたビジュアルには、80年代レトロフューチャー感とモダンな洗練と冷戦末期的終末感が同居しており、フレッシュな印象をふりまいています。古典の再解釈といえば、今年は『スペースインベーダー』(タイトー, 1978)をローグライト化した『Zenvader』(RyiSnow, 2025)もありましたね。
「ローグライトはジャンルではない」という説がありますけれども、こうしてみるとたしかにジャンルを再解釈するための道具であるような気がしてきます。ともすれば、ローグライトによって再解釈されたゲームがさらに別な仕方のローグライトでまた新しい解釈を生んでいる。ローグライトは新しいゲームを生むための触媒なのかもしれません。
そういう意味では、ゲームにおけるSFとローグライトは兄弟のようなものです。どちらも本質的なメカニックやスタイルを持つ他のジャンルにくっついて生きる、哀しいタグ的な存在です。だからこそ、新しいゲームへつながる架け橋となれる。すべてのイヌと良い子どもは天国に行きますが、SFとローグライトはどこにでも行けるのです。
*3…『Strange Adventures in Infinite Space』(Digital Eel, 2002)の続編。コンセプト的には一作目からあまり変わっていない
終わりに
もっともっと言及すべき作品はあるのですが、これ(現状4万字)以上文字やスクショを増やすと軟弱なnoteのUIが耐えきれなくなりますし、なんとなく美しくオチた気がするここで筆を措きましょう。
みなさんもSFインディーゲームの多様さにおどろいたのではないでしょうか。筆者もまとめながら、たいそうビビリました。最初45本っていったのに、最終的に110本か120本くらいになったし。
この物量を前にすると序論で提起した「ゲームにおける『SFであることの必然』とは?」みたいな問題意識があほうらしくもおもえてくるものの、しかし、このリストをつぶさにごらんになった方々は、これらの作品がそれぞれの仕方で「SF」を引き受けていることを感受なされたこととおもいます。
もちろん、ゲームの歴史がSFゲームの歴史である以上、ここで紹介したSFインディーゲームはほんの一部。このリストの外にも宇宙は無限に広がってございます。たとえば、台湾が誇るSFアドベンチャーシリーズ『OPUS』(SIGONO, 2015-)や20年代の話題作『I Was a Teenage Exocolonist』(Northway Games, 2022)や宇宙版『大航海時代』ともっぱら評判の『Star Traders: Frontiers』(Trese Brothers, 2018)にも触れておきたかったところですが、私は未プレイなので……あとは、なんだろ、『SOMA』(Frictional Games, 2015)とか『Deliver us the Moon』(KeokeN Interactive, 2019)とか……? 『NORCO』(Geography of Robots, 2022)もいい加減日本語化してくれ、Raw Fury氏〜。シューティング全般に至ってはブーマーシューターなども含めて、まるごとごっそり欠けていますね。元のリストに含まれてなかったせい、ということにしておきましょう。
人生は短く、ゲームは一日一時間。天網は恢恢でも失わずですが、ヒトの作る網は疎にて漏らしっぱなしです。逃げた魚はあなたに漁っていただければ、これ以上に幸いなことはございません。
みなさんも良きSFゲームライフを。
執筆者について
千葉集
動いている物が好き。動かなくなった物も好き。
ブログ:名馬であれば馬のうち
プロフィール
X:集
bluesky:千葉集
xcloche
構造やメディアの話が好きで、一日中しています。
ブログ: セミになっちゃた
note: xcloche
X: かもリバー
お知らせ
「遊星歯車機関」は、実験的な試みのあるゲームをガイド/批評する同人誌企画です。メカニクスやUI、シナリオ分岐、乱数、報酬設計など、ゲーム特有の仕組みによって広がる物語の可能性に着目します。いずれ本稿群を『遊星 物語るゲームたち(仮)』として編み直し、一冊にまとめる予定です。寄稿をご希望の方はご相談ください。詳細は続報にて。

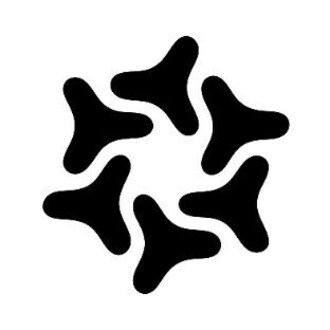
コメント