テイルズオブエターニアの「繊細さ」が好きだ
最近、『テイルズ オブ エターニア』をクリアしたのですが……なんか、すごく繊細なゲームだなと思いました。どこまでも丁寧に、繊細に、微に入り細を穿つような作りこみのゲームだった。
そしてエターニアは、いろいろ遊んできたRPGの中でも、特にクリア後の「なんていいゲームなんだ……」と、じわじわ心に染みてくるような感覚が強かった。この感覚もきっと、繊細かつ丁寧に作りこまれたからこそ、生まれたものなのだと思う。着々と積み上げたから、どこまでも心に響く。
なので、この記事でも「エターニアの繊細さ」について書いてみようと思います。だいぶシンプルな感じですが、よろしくお願いします。
奥ゆかしさと、繊細さ
このゲームの「繊細さ」がどこから来ているのかというと……自分は、「ひたすらメインキャラクターの4人を掘り下げ続けているところ」だと思うんです。リッド、ファラ、キール、メルディ。エターニアは、基本ずっとこの4人のことを掘り下げ続けていく。着実に、丁寧に。
これはどちらかというと作劇的な雰囲気の話なのですが、この4人の間で「思ってはいるんだけど、実際に言葉にしていない気持ち」や「直接会話するわけじゃないけど、お互いに通じ合っている感覚」みたいなものが、かなり描かれていると思います。そしてプレイヤーは、その空気を察していく。
たとえば、リッドとファラとキールの、幼なじみ3人組。
ずっと仲のいい3人組として描かれているけど、具体的にこの3人がお互いをどう思っていて、幼なじみとしてどういう関係なのかは、そこまでハッキリと語られるわけじゃない。断片的に見える過去や、普段の3人の会話から、うっすらその空気を読み込んでいくような感覚でした。
だけど、明らかにこの3人の間には、「口には出さないけど、幼なじみ同士で通じ合っている感覚」が存在している。わざわざ口に出さずとも、わかりあっている共通認識。しかし、それをプレイヤーに語りすぎはしない。この独特な距離感が、エターニアの根底にあると思うんです。
リッドって「こいつモテるんだろうな……」とリアルに思わせてくるタイプだと思う。リアルにモテそう pic.twitter.com/iT7W45rUEv
— ジスロマック (@yomooog) October 18, 2025
具体的なところを言うと、ファラの「おそらく彼女はリッドのことが好きで、リッドとメルディが仲良さげにしていると、うっすらモヤモヤしている」という絶妙な気持ちの揺れ動きも、ストーリー中でチラつかせはするけど、それが表層化するわけじゃないし、ケンカに発展するわけでもない。
特に、上記のシーンで描かれている「リッドのことを追いかけてきたけど、メルディと2人きりで話していることに気づいて、サッと引っこむファラ」なんか、これでもかとエターニアの繊細さを物語っていると思う。ここで「何話してるの~?」と首を突っ込みに行くのは、ファラじゃないのだ。
この「各々が心の中で抱えているけど、表層化しない感情」や「ハッキリとプレイヤーに見せない、キャラの繊細な感情」が着々と積みあがっていき、ゲーム全体に「繊細さ」や「奥ゆかしさ」といった印象を与えている。
いきなり結論になってしまうけど、自分はここが『テイルズオブエターニア』という作品の、最大の魅力だと思うんです。それぞれの内心がハッキリと説明されるわけじゃない。でも、確実に、そこには揺れ動いている気持ちが存在する。プレイヤーは、その繊細な揺れ動きを察していく。
いわゆる「セリフで説明する作劇」の逆を行っているとは思います。キャラクターが内心思っていることはうっすら感じ取れるけど、それ以上は、スキットなどの些細な演技や温度から察していくしかない。
この「キャラの気持ちを察していく」という、プレイヤーが自発的に相手のことを考えるようなターンが、エターニアはすごく楽しい。じっくりと、慮るように、相手のことを理解していく。この4人の解像度を、少しずつ鮮明にしていく。その積み重ねが、面白いゲームだと思います。
個人的には、ファラのキャラクター造形の繊細さがものすごいと思うんです。というか、エターニアを遊んでいて「繊細なゲームだなあ……」と思った瞬間のほとんどは、ファラのことが描かれている時だった気がします。
途中で出会ったレイスに無意識に惹かれていそうなところとか、それでもリッドのことを想っているところとか……ちょっと一朝一夕では出てこないキャラクターの奥行きだし、かなり多層的な人物像ですよね。
それこそ、ファラの「誰かを助けたい」という強迫観念のようなものが、過去に起こしてしまった出来事への贖罪から来ているところなんか、すごいキャラ造形だなと思います。
キャラクターへの「なぜそんなことを言うのか?」「どうしてこの行動をしているのか?」という疑問のすべてに、しっかりと裏付けがあって、それが長い旅路の中で見えてくる。この裏付けやバックボーンが丁寧に肉付けされているから、キャラの繊細さが際立っているんだろうなと思います。
そうやってキャラクターの造形を深めていったからこそ……エターニアは「人と人との距離感」が結構リアルだと思うんです。この4人で旅をしている最中、ぼんやり「気まずいな……」と思う瞬間がある。だけど、みんないい人だから争いに発展するわけじゃなくて、その気まずさだけがある。
表面的には明るく仲良くやっているけど、何かの弾みで引火したら大変なことになるんじゃないか……というのは悲観的すぎるかもしれないけど、この4人の関係は、そんな薄氷の上を渡っているような、すごく絶妙な距離感で成立していると思います。みんないい人だから、崩壊してない。
同時に、この4人の優しさや善性が、エターニアの物語を支えてもいる。リアルで繊細に描かれているけど、そこのいるのは、いい人たち。どんなに苦しいことがあっても、悲しいことがあっても、それでもみんなのことが好きだった。プレイヤー自身も、そう思えるゲームだと思います。
「全部が夢なら・・・メルディは、キール達と会わなかった」
「キールと・・・こんな風にお喋りは出来なかったよ。
夢でなくて、よかったな」
「苦しいことはあっても、メルディは、今が好きよ。
みんなと生きてるから・・・」
ここまで「リッド、ファラ、キール、メルディ」の4人を突き詰められてしまったから、ゲーム的にも自分の中で「最後まで絶対この4人でクリアするぞ」という決心があったというか、そこに意固地になっていました。
私って、RPGを遊んでる時はかなりの「性能厨」なんですよ。
そのキャラクターに思い入れがあったとしても、バトル的に最適解があるなら、普通に外せるタイプの冷血人間です。でも、エターニアは違った。「最初から最後まで、この4人で旅を終えるんだ」と決心してしまった。
たしかに、チャットはかわいい。フォッグも使いこなすと強いらしい。でも、この4人への圧倒的な思い入れが上回って、スタメンを動かす気になれなかった。むしろ、「この4人でラスボスを倒したい」と、自分の方から思っていた。そう思うと難儀なゲームですよね。
そのくらい、「メインキャラクターの4人を深堀りすること」に全身全霊をかけているんだと思います。私もこの4人が大好きだし、この4人以外は考えられない。いつの間にか、そんな気持ちになっているゲームです。
制約と限界を超えた掘り下げ
ただ、「キャラを丁寧に掘り下げているゲーム」自体は、探せば結構あると思う。そこに対して、エターニアの何がすごいかと考えると、プレステでここまでその掘り下げを行っていることだと思うんです。
このテキスト量と、膨大なボイス量と、ディスク3枚にも及ぶ壮大なストーリー……そのなかで、「4人のメインキャラクター」をひたすらに掘り下げていく。当時のハードの制約や限界を感じさせないほどに、繊細かつ丁寧に掘り下げていく。プレステでこのボイス量は本当にすごいと思う。
あと、声優も豪華すぎるし。
石田彰ですよ、石田彰。みんな演技が上手すぎて、正直声優の演技力でキャラの魅力が2~3倍は増していると思う。そのボイスの入れ方であったり、演出なんかも含めて、プレステの限界に挑戦したタイトルなんだろうなと思います。プレステ末期のゲームってこういう殺気に溢れたヤツ多いよね。
すいません
— ジスロマック (@yomooog) October 22, 2025
これって
“愛”ですよね? pic.twitter.com/6eyqMJIeIh
そのボイス周りを含めて、エターニアで「テイルズの基盤」が一度完成しているのかもな、と思いました。かなりのボイス量と会話の数で、キャラクターのことをひたすら掘り下げていく。この「まず第一にキャラを掘り下げる」感じが、後年のテイルズの基盤になっている感じがします。
もちろん『ファンタジア』や『デスティニー』も偉大なタイトルだとは思いつつ、「テイルズの強み」をよりハッキリと完成させて、シリーズの方向性を決定づけたのはエターニアなんじゃないかと思う。初期2作が道を切り拓いて、そこにエターニアが「基盤」を作り上げた。
それこそ、『シンフォニア』や『デスティニー2』は、明確に「エターニアが作った基盤」をもとに派生していったタイトルな気がします。シリーズ全体でテイルズ系譜図を作ったら、サンデーサイレンスくらいのポジションに位置しそう。とりあえず家系を辿るとエターニアが先祖にいる。
そのくらい、「キャラクターを掘り下げていくRPG」としての、ハイレベルなスタンダードを提示してみせたタイトルなんだろうなと思いました。テイルズだけじゃなくて、エターニアが切り開いた道がRPG史になんらかの影響を与えてそうな気がする。エターニアには、そういう存在感がある。
変われる強さ、変わらぬ想い
「変われる強さ、変わらぬ想い」。
これ、めちゃくちゃいいキャッチコピーだと思います。
個人的には「生まれた意味を知るRPG」に匹敵してます。
その言葉の通り、エターニアは「キャラが変わっていく過程」が、すごく丁寧に描かれている。たとえば、序盤は受動的で、旅に出ることにも消極的だったリッドが、旅の中で能動的になっていく。最後には、自ら世界を救う決心をする。キャラクターが着実に成長して、変わっていく。
ファラは、自分の罪と向き合った。
キールは、外の世界を知った。
メルディは、身近な「愛」に気づいていった。
キャラクターがしっかりと、緻密に描かれていたから、この「成長」に納得できる。繊細に描かれているから、「変化」に気づくことができる。何度も同じワードを出してしまっているかもしれないけど、この「着実な積み上げ」を、とにかく重んじているゲームなんだと思います。
個人的な感覚なのですが、エターニアっていかにも感動的なシーンより、なんでもない些細なセリフの方が心に来ることが多い気がするんです。
そういうところが繊細なゲームだなと思うんですが……たとえば、久しぶりにラシュアンに帰ってきて、ふと民家に入った時の上記のシーン。なんかこれ、すごい涙腺に来ました。
大きな変化ではなかったかもしれない。
でも、原点に立ち返ってみたとき、たしかに変わっていた。あの日見ていた家が小さくなったのではなく、キールが大きくなっていた。それは確実な一歩。人間も、世界も、少しずつ変わっていく。大きな変革から、身近な成長まで。ストーリーも、小さなイベントも、そんな変化を描き続けている。
ずっと、人間と世界の「変われる強さ」を描き続けているし、それがどのキャラクターにも一貫している。ストーリー中に退場しているレイスすら、リッドたちの姿を見て「変わった」人間のひとりとして描かれている。だけど、レイスの「世界を救いたい」という想いは変わらない。
弾いたァッッッ pic.twitter.com/vKxvHDO0O1
— ジスロマック (@yomooog) October 23, 2025
そんな「変われる強さ」を描きながら、「変わらない想い」も描いている。リッドのファラを守りたい想いは、ずっと変わらなかった。極光術は、そんな大切な人を守るためにある。
……っていう前提を踏まえた時に、いかにも最終奥義っぽい「極光術」が、ラスボス戦において「相手を倒す技」ではなく、「相手の攻撃を防ぐ技」として機能するのがめちゃくちゃアツいと思うんです。最強の必殺技が「仲間を守る技」って、もうこれだけで最高のゲームですよね。
終わらせる剣<ファイナリティ>に対して、終わらない盾<インフィニティ>をぶつける。変わることも、変わらないことも、存続しなければ生まれない。守り、続けていくことこそが最強の必殺技。必殺技にこういう文脈を織り交ぜてくるところが、エターニアらしい丁寧さだなと思います。
理解する力
物語のカギを握る力として登場した、「極光術」。
その力の根源が「理解する力」なのが、すごい納得感だと思う。
別の世界からやってきたメルディとコミュニケーションをして、インフェリアからセレスティアへと旅をした……そんなエターニアの物語自体が、「他者を理解していく旅路」だった。ずっと、「自分の知らないものを理解していく」ことを描いているゲームだったと思う。
そんなエターニアの最後に登場し、物語のカギを握る極光術の根源が、「理解する力」。もう納得しかない。他者を理解して、変わっていく人間と世界を、プレイヤーが見届けていくゲームだった。
しかも、エターニアの「キャラの気持ちをこちらが察していく」ターンが楽しかった身としては、このゲームを通して、プレイヤー自身が「他者を理解する力」を獲得していくようにできているんだ……とも思えて、勝手にすごい納得してました。だからきっと、プレイヤーも極光術を使えるはず。
もっと言えば、「フリンジ」がここと繋がってくるのにも驚きました。インフェリアとセレスティアの異なる晶霊の力を混ぜ合わせて発生する、新たな力。このシステム自体が、「自分の知らないものを理解する力」をストレートに表している。まさにエターニアを象徴したシステムだった。
私は、こういうゲーム内のシステムがストーリーと繋がってくる演出にかなり弱い。序盤からずっと触り続けていた「フリンジ」というシステムが、ストーリー的にも意味があり、シゼルを倒すための突破口になる。これこそが、ゲームでしかできない演出なんだと思います。
セレスティアとインフェリアに協定が結ばれ、2つの世界の技術が交わることで、「フリンジ砲」を生み出す。プレイヤーがゲーム内で術を生み出すためにずっと実践してきたことでもあり、同時にメルディと旅をすることで理解しあってきたリッドたちの縮図でもある。なんて美しいゲームなんだ。
「ラストフェンサー」が完成するのもアツい
「ネレイド・・・シゼルの気持ちがわからねぇか?
わからねぇようじゃ・・・オレ達には勝てねぇぜ」
「あんたの言う通り、セイファートの世界は不完全だ。
いろんなヤツがいて、勝手な正義を信じて生きてる」
「そのせいで争いも悲しみも絶えることはないし、
不安定で乱れきっている」
「だけど!だからこそ、人は変われんだ。
違う何かを知ろうとすることが人を変えるんだ」
「人が変われば、世界だって変わる・・・
グランドフォールなんて必要ねぇんだよ!」
他者を理解すること。理解して、変われること。セレスティアとインフェリアの異なる世界を通して、そんなテーマを描き続けてきたエターニアの、リッドが最後に返すアンサー。あまりにも完璧な答えだと思うんです。
インフェリアは、セレスティアを偏見で憎んでいた。
でも、相手のことを理解すれば……理解しようと歩み寄ることができれば、人も世界も変わって、手を取り合える。嫌いだった相手も、憎んでいた世界も、いずれは愛せるようになるはずだ。
RPGには、必ず「そうか、自分はこのために旅をしてきたんだ」と、最後に納得できる「答え」が必要だと思う。エターニアの解答は、あまりにも完璧だった。リッドの答えを聞いた時、そして崩れゆく世界のなかでキールとメルディが抱き合った時、この旅のすべてに納得した。
インフェリア生まれのキールと、セレスティア生まれのメルディが手を取り、愛し合っている。異なる世界の人間だとしても、最初は嫌っていたとしても、理解し合うことができれば……必ず変われる。あのふたりの愛が、エターニアで描かれてきたことを証明している。私はそう信じています。
「・・・でも、今は、メルディは、しあわせだから。
ありがと、言うよ」
「クィッキーを・・・頼むな」
「そんなこと言うな!
ずっと一緒に生きるんだ。
・・・何があっても!」
「・・・ありがと」
この旅は、「理解しあえば、人も世界も変われる」ことを証明するための旅だった。その姿を、そんな4人を、私は冒険の中で見届けてきた。そのために、どこまでも繊細に「人間」を描いたゲームなんだと思います。
理解して、変わっていく人間。
手を取りあい、愛し合う人間。
そこに納得感と説得力を持たせるためには、どこまでも人間を繊細に、奥ゆかしく描く必要がある。だから、エターニアはこんなにも丁寧に、着実な描写を積み重ねてきた。そして最後に、大花火を打ち上げた。
エターニアをクリアした時、どこまでも繊細にキャラを掘り下げていく作劇はこのためだったのか……と、妙に腑に落ちたような感覚がありました。愛を証明するための繊細さであり、そう信じさせるための繊細さだった。
そして、エターニアをクリアした「現在」の話になるのですが……オープニングの「flying」を聞いていたら、エターニアが終わってしまった事実がどんどん心に染みてきて、謎に泣けてくる身体になってしまいました。
遊んでいる最中は、身も心も捧げるほど熱中していたような感覚はなかったのですが、いざ終わってみたら、エターニアのことを思い出すと泣けてくる。繊細で奥ゆかしいから、本当にじっくりじわじわと身体の深くにまで入り込んでくる。そういう、遅効性のRPGなんだと思います。
「別れは終わりではない。とこしえに想うことこそ、共にあるということなのだ」という作中の言葉を借りるとしたら、エターニアのことをずっと想い続ければ、たとえエンディングを迎えても──いつまでも共にあれるのかもしれない。そう思わせてくれるキャラクターたちであり、物語だった。
だから、私はテイルズオブエターニアの「繊細さ」が好きだ。


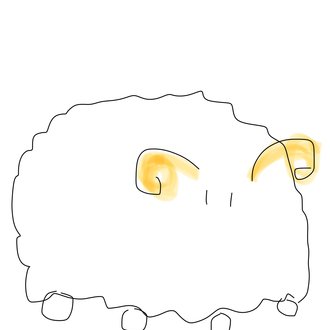
コメント