夏目漱石「こころ」下・先生と遺書三十七「先生:魔物(=K)に永久に祟られた……」
「二人は各自(めいめい)の室(へや)に引き取ったぎり顔を合わせませんでした。Kの静かな事は朝と同じでした。私も凝(じ)っと考え込んでいました。
私は当然自分の心をKに打ち明けるべきはずだと思いました。しかしそれにはもう時機が後(おく)れてしまったという気も起りました。なぜ先刻(さっき)Kの言葉を遮(さえぎ)って、こっちから逆襲しなかったのか、そこが非常な手落(てぬか)りのように見えて来ました。せめてKの後に続いて、自分は自分の思う通りをその場で話してしまったら、まだ好かったろうにとも考えました。Kの自白に一段落が付いた今となって、こっちからまた同じ事を切り出すのは、どう思案しても変でした。私はこの不自然に打ち勝つ方法を知らなかったのです。私の頭は悔恨に揺(ゆ)られてぐらぐらしました。
私はKが再び仕切(しきり)の襖(ふすま)を開けて向うから突進してきてくれれば好(い)いと思いました。私にいわせれば、先刻はまるで不意撃(ふいうち)に会ったも同じでした。私にはKに応ずる準備も何もなかったのです。私は午前に失ったものを、今度は取り戻そうという下心を持っていました。それで時々眼を上げて、襖を眺(なが)めました。しかしその襖はいつまで経(た)っても開(あ)きません。そうしてKは永久に静かなのです。
その内(うち)私の頭は段々この静かさに掻(か)き乱されるようになって来ました。Kは今襖の向うで何を考えているだろうと思うと、それが気になって堪(たま)らないのです。不断もこんな風(ふう)にお互いが仕切一枚を間に置いて黙り合っている場合は始終あったのですが、私はKが静かであればあるほど、彼の存在を忘れるのが普通の状態だったのですから、その時の私はよほど調子が狂っていたものと見なければなりません。それでいて私はこっちから進んで襖を開ける事ができなかったのです。一旦(いったん)いいそびれた私は、また向うから働き掛けられる時機を待つより外(ほか)に仕方がなかったのです。
しまいに私は凝(じっ)としておられなくなりました。無理に凝としていれば、Kの部屋へ飛び込みたくなるのです。私は仕方なしに立って縁側へ出ました。そこから茶の間へ来て、何という目的もなく、鉄瓶の湯を湯呑みに注(つ)いで一杯呑みました。それから玄関へ出ました。私はわざとKの室を回避するようにして、こんな風に自分を往来の真中に見出だしたのです。私には無論どこへ行くという的(あて)もありません。ただ凝としていられないだけでした。それで方角も何も構わずに、正月の町を、むやみに歩き廻(まわ)ったのです。私の頭はいくら歩いてもKの事でいっぱいになっていました。私もKを振(ふる)い落す気で歩き廻る訳ではなかったのです。むしろ自分から進んで彼の姿を咀嚼(そしゃく)しながらうろついていたのです。
私には第一に彼が解(かい)しがたい男のように見えました。どうしてあんな事を突然私に打ち明けたのか、またどうして打ち明けなければいられないほどに、彼の恋が募(つの)って来たのか、そうして平生の彼はどこに吹き飛ばされてしまったのか、すべて私には解しにくい問題でした。私は彼の強い事を知っていました。また彼の真面目な事を知っていました。私はこれから私の取るべき態度を決する前に、彼について聞かなければならない多くをもっていると信じました。同時にこれからさき彼を相手にするのが変に気味が悪かったのです。私は夢中に町の中を歩きながら、自分の室に凝(じっ)と坐っている彼の容貌を始終眼の前に描き出しました。しかもいくら私が歩いても彼を動かす事は到底できないのだという声がどこかで聞こえるのです。つまり私には彼が一種の魔物のように思えたからでしょう。私は永久彼に祟(たた)られたのではなかろうかという気さえしました。
私が疲れて宅(うち)へ帰った時、彼の室は依然として人気(ひとけ)のないように静かでした。
「二人は各自(めいめい)の室(へや)に引き取ったぎり顔を合わせませんでした。Kの静かな事は朝と同じでした。私も凝(じ)っと考え込んでいました。」
Kはお嬢さんへの恋という、人生初の自分の感情に戸惑っている。先生は、ライバルの出現に困惑し、以前からずっと言おうと思っていた恋の相談ができなかったことを後悔している。
先生は、「当然自分の心をKに打ち明けるべきはずだと思」うが、「それにはもう時機が後(おく)れてしまったという気」も起こる。「なぜ先刻(さっき)Kの言葉を遮(さえぎ)って、こっちから逆襲しなかったのか、そこが非常な手落(てぬか)りのように」見えて来る。「せめてKの後に続いて、自分は自分の思う通りをその場で話してしまったら、まだ好かったろうにとも考え」る。また、「Kの自白に一段落が付いた今となって、こっちからまた同じ事を切り出すのは、どう思案しても変」だと思う。「この不自然に打ち勝つ方法を知らなかったのです。私の頭は悔恨に揺(ゆ)られてぐらぐらしました。」
先生は、Kに対する恋愛相談の「時機が後(おく)れて」しまっており、「Kの自白に一段落が付いた今となって、こっちからまた同じ事を切り出すのは、どう思案しても変」・「不自然」と考える。確かに、「Kの後に続いて、自分は自分の思う通りをその場で話してしまったら、まだ好かった」だろう。しかし、これから話しても全く問題はない。「さっきは、突然のことでびっくりした。実は、俺もずっと彼女が気になってたんだ」 たったこれだけのセリフを、長年の友達に言えない先生。そうして、これから言うのは「変」だし「不自然」だからということを、言えない理由にする先生。全く「変」でも「不自然」でもない。さらに言うと、少しぐらい「変」でも「不自然」でもいいじゃないか。若者なんだもの。「変」や「不自然」を、自分が行動できない理由にするのは、「不自然」に失礼だ。(比喩的表現です)
何で言わないかなー? 何で言えないの? 今、思ったのだが、この二人には、若々しさが欠けている。思い切って何かやるとか、失敗を恐れず何かに挑戦するとか、(同じことか)、そういう青春のキラメキがない。老人みたい。かといって、老成ではない。いろんなことを二人ともぐるぐる考えているだけ。そうして結果を恐れて行動しない。
失敗が怖いんだね。でも、やらない失敗もあって、そっちの方がこの二人の場合、より重大・悲惨な結果をもたらすという物語。
次は、先生のいつもの他力本願が発動します。
「私はKが再び仕切(しきり)の襖(ふすま)を開けて向うから突進してきてくれれば好(い)いと思いました。」
他者からの働きかけがないと、この人は動けない人なのだ。自分の意志というものがない人。それは、人ではない。
さらに続きます。
「私にいわせれば、先刻はまるで不意撃(ふいうち)に会ったも同じでした。私にはKに応ずる準備も何もなかったのです。私は午前に失ったものを、今度は取り戻そうという下心を持っていました。それで時々眼を上げて、襖を眺(なが)めました。しかしその襖はいつまで経(た)っても開(あ)きません。そうしてKは永久に静かなのです。」
自分が反撃するために、もう一度Kの方から来てほしいと願う先生。しかし、反撃は、こちらから行くべきではないか。これでは、相手が来なければ、永遠に反撃できなくなってしまう。そうしてここでは実際にそうなっている。
他者の行動を「不意撃」と批判し、それに対する自分の反撃という行動のためにはもう一度Kの方から来なければならないと願う先生。先生自身、自分のこの考え方に対して少しのやましさがあったのか、「下心」と表現している。しかし、「いつまで経っても開きません」とか、「永久に静かなのです」と相手を責めるかのような表現が、これに続く。
わかりました。先生とは、そういう人なのです。青年に「先生」と呼ばれるので、これまで私も「先生」と呼んできましたが、これでは青年に範を示すことはできません。反面教師ということでしょうか?
『こころ』上・先生と私 の先生からは、思慮深さや落ち着きが感じられたが、学生時代の先生は、人任せの言い訳野郎だったのだ。
でも、ここの場面はちょっと複雑で、この場面を語っているのは自死前の先生だ。それと学生当時の先生の行動や考えが、ある意味融合して読める。他者依存がこの当時だけだったのか、現在でもその名残があるのかが微妙だ。
私は、先生の自死には、青年の肉薄が強く影響していると考える。これが無ければ、先生は、いつまでも自死をためらい続けていたかもしれない。その意味では、大人になった先生も、重大な事柄の決断・行動には、やはり他者の働きかけが作用している・必要だったと考えられる。
「その内(うち)私の頭は段々この静かさに掻(か)き乱されるようになって来ました。Kは今襖の向うで何を考えているだろうと思うと、それが気になって堪(たま)らないのです。」「それでいて私はこっちから進んで襖を開ける事ができなかったのです。一旦(いったん)いいそびれた私は、また向うから働き掛けられる時機を待つより外(ほか)に仕方がなかったのです。」
この先生の考え方については先に述べたので長くは述べないが、「いいそびれた」自分の失敗の挽回のためには、「また向うから働き掛けられる時機を待つより外(ほか)に仕方がなかった」という言い訳は、成立するのだろうか? ふつうは恥ずかしくて、こんなこと言えない。先生、恥ずかしくないの? このような弱く恥ずべき自分も含めて、青年に示そうとしているの?
「しまいに私は凝(じっ)としておられなくなりました。無理に凝としていれば、Kの部屋へ飛び込みたくなるのです。」
飛び込めばいいじゃん。なんで飛び込まないの? 「仕方なしに立って縁側へ出」たり、「そこから茶の間へ来て、何という目的もなく、鉄瓶の湯を湯呑みに注ついで一杯呑」んだり、「わざとKの室を回避するようにして、こんな風に自分を往来の真中に見出だ」す必要はない。
先生は、Kという問題を、「回避」している。
問題を回避する以上、問題は解決しない。「正月の町」は、答えを教えてくれない。「頭は」むしろ「Kの事でいっぱいになって」しまう。先生は、「私もKを振(ふる)い落す気で歩き廻る訳ではなかったのです。むしろ自分から進んで彼の姿を咀嚼(そしゃく)しながらうろついていたのです。」と強がるが、あてもなくただ衝動に任せて歩き回っている人にそのようなことを言われても、にわかには信じがたい。一時(いっとき)、Kを忘れたかったんでしょ? Kという問題を「振るい落」としたかったんでしょ? 沈思黙考するならば、自分の部屋にいればいい。それができないから、街中を歩き回る。
「むしろ自分から進んで彼の姿(Kの考えや気持ち)を咀嚼(そしゃく)し(よく考え)しながらうろついていた」という説明が、やはり厳しい。「うろつき」ながら考えるタイプなのか。
先生にはKが、もはやトラウマになっている。だから近くにいるのもつらい。
「私には第一に彼が解(かい)しがたい男のように見えました。どうしてあんな事を突然私に打ち明けたのか、またどうして打ち明けなければいられないほどに、彼の恋が募(つの)って来たのか、そうして平生の彼はどこに吹き飛ばされてしまったのか、すべて私には解しにくい問題でした。」
これまでも不可解な相手だったのだが、先生にとってKがさらに理解不能の存在になってしまったことを表す。
「どうしてあんな事を突然私に打ち明けたのか」…恋をなぜ自分に知らせたのか?
「どうして打ち明けなければいられないほどに、彼の恋が募(つの)って来たのか」…恋を告白する衝動をKに与えた理由は何なのか?
「平生の彼はどこに吹き飛ばされてしまったのか」…恋愛否定派だったKが他者に恋を告げるということは、今までの自分の考えを翻すことになるが、それでいいのか?
「私は彼の強い事を知っていました。また彼の真面目な事を知っていました。」
Kは、「強」い心をもって、「真面目」にお嬢さんへの恋愛の道を進むのではないかと先生は感じている。従って、「私はこれから私の取るべき態度を決する前に、彼について聞かなければならない多くをもっていると信じました。」となる。
Kが畏怖の対象となった先生は、「これからさき彼を相手にするのが変に気味が悪かった」。「自分の室に凝(じっ)と坐っている彼の容貌」。「いくら私が歩いても彼を動かす事は到底できない」。先生にとってKは、とうとう「魔物」となる。そして「永久彼に祟(たた)られたのではなかろうかという気さえ」する。
Kは「魔法棒」を持った「魔物」である。簡単に自分の心を弱らせる力を持つ。そうして自分には、彼に反抗するすべがない。
そんなことを考えていたら、心は休まらない。先生が「疲れて宅(うち)へ帰った時、彼(魔物)の室は依然として人気(ひとけ)のないように静か」だった。
Kはもう、人ではない。空間を「静か」に支配する存在となった。抗うことができない超自然的存在が隣に住んでいる。しかもそれが、自分の最愛の人を奪おうとしている。下手に逆らうと、[永久」に「祟られ」る。対抗手段を持たない先生は、まさに手も足も出ない状態だ。
こう感じた先生は、やがて最終手段に出ることになる。

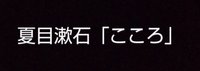

コメント