大阪・関西万博(2025)紀行
去る八月下旬、大阪・関西万博に行った。
夏パス(平日券2枚分の値段で夏季に限り何度でも入場できる)を使用し、単独で1日、5人ほどの集団で2日と、計3日間の滞在である。
本稿執筆時は10月13日の深夜。
万博が会期を終えて閉幕した日であり、良い機会ということで個人的な紀行文をネットの海に放流することにした。普通に書き終わらないので、公開されるのは14日である。
15日になった…
本稿は字数14000弱、写真約40枚で構成されている。
個人の感想、偏見、意見が多分に含まれることに留意。
Day1
筆者は経済的に余裕がある方ではないので、大阪へは最安の高速バスで乗り込んだ。
初日は一人で、下見を兼ねつつ、気分で見たいところを見ることにした。
現地入り、入場
朝、バスは予定から30分遅れで到着した。
ユニバーサルスタジオジャパンに。
より厳密には、JR桜島駅近くにあるUSJ提携ホテル前に。
別に間違いではなく、無料の渡し船に乗りたかったからである。
桜島駅前には万博西ゲート行のバスが大量に来ていたが、それらを横目に10分ほど歩き、天保山渡船場に到着、乗船した。
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000011249.html
快速で、向こう岸に着くまで3分もかからなかった。風が心地いい。
大阪市の公営航路は、海運の都合で橋が無かったり、自動車専用道しかない所などに設置され、主に通勤・通学の足として利用されているようである。
港湾開発や渡船の歴史を偲びつつ、無料で船に乗れる。楽しい。
JR桜島駅からは夢洲駅まで乗り換え3回、所要時間30分強だが、大阪メトロ大阪港駅からは直通2駅なので、電車賃的にも手間的にもありがたい。
所要時間はやや増えるが、船に乗れて海辺も散歩できるのでお得である。
閑話休題、こうして桜島→大阪港→夢洲と移動し、万博東ゲートに到着。
渡し船の周期を一本逃したこと、散歩の時間が少し長かったこともあり、
ゲート到着は11時過ぎ、実際に入場できたのは12時ごろであった。
公式サイトに「通期・夏パスの顔認証は通常入場より早くてオススメ!」(意訳)と書いてあったのだが、実際には顔認証無しレーンがほぼ待ち無し入場、顔認証レーンは1時間待ち、といった状態だった。
通期・夏パス率の想定が甘かったんだろうな、と納得はしつつ、優良誤認風味も感じつつゲートをくぐった。
オーストリア、EARTH MART
13時にEARTH MARTの予約を取っていたので、時間つぶしで目についた売店、パビリオンに入った。
まずサウジアラビア館に入った。(写真は無い。)
並んでおらず、「エアコンあるよーすぐ入れるよー」と呼びこんでいた。
吹き抜けと大きな柱で見ごたえのある建築に、伝統系と宇宙関係の展示、後にTECH WORLDで見ることになる、大量のタブレットが同期して動く謎ブースがあったのを覚えている。
次に30分ほど並びオーストリア館に入場。
どちらの写真も撮っていなかった…
見た目で入ったが、演奏以外はオーソドックスなシアター+展示スタイルだった。
作曲家以外だと、最近読んだ「夜と霧」、「それでも人生にイエスと言う」などの著者、フランクルが紹介されていたのでちょっとテンションが上がったぐらいであろうか。
(写真ではちょうど柱の陰に入ってしまったが……)
少し時間が余ったので、近場にあった国際機関館に入り、さらっと一周。
ITERがデカデカとトカマク型核融合炉の模型を展示していて、スタッフがかなり詳しく説明していた。
ロマンがあって大変良い。
予約時間になりEARTH MARTに入場。
手前は一人が一生で食べる卵の数、左奥はねぶたの技術で10年分の食料の体積を表しているそう。
コンセプトよし、導線よし、展示自体のクオリティよしと、文句をつけにくいパビリオンだった。
前半は今の食に関する消費の現状などを見て触って分かりやすく示すもの、後半はフリーズドライやIoT調理器など、技術はそこまで真新しくはないが、興味深いアイデアで未来を魅せてくれるものが多かったイメージである。
フリーズドライの使い道に、気候変動による生産量減少への備えとして保存性を上げる、というものが紹介されていたりと、やや灰色の未来像を示すパビリオンだったように思う。
EARTH MARTは当万博で数少ない、具体性、実現性、説得力を備えた未来像を描こうとしたパビリオンであるように感じ、非常に高く評価している。
(余談)万博って、何?
この後も個人の感想を書き連ねることになるが、本稿に通底する姿勢を語るため、国際博覧会(万博)条約における博覧会の定義を引用する。
第一条 定義
1. 博覧会とは、名称のいかんを問わず、公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段又は人類の活動の一若しくは二以上の部門において達成された進歩若しくはそれらの部門における将来の展望を示すものをいう。
勿論、これはお題目にすぎないという見方もできる。
歴史的に、博覧会は国威を示してナショナリズムを強化する場であったし、今も経済効果やインフラ整備への期待が誘因となっているのは確かである。
ただ、私は定義通りの展示、すなわち未来に繋がりうる、ロマンのある展示をこそ評価している。
当然これは本稿の評価軸、および個人の嗜好表明にすぎず、異論は大いに認めるところである。
また全体の感想で後述するが、この定義と現代社会・環境のミスマッチが、万博不要論・時代遅れ論の根源ではないかと考えている。
再び閑話休題。
チェコ、散策(大屋根リング)
EARTH MARTでパビリオン欲がある程度満たされたので、今度は景色を見ることに。
少し南下して海辺、屋上にも登れるチェコ館へ。
個人的には、今回の万博で一番センスが良い建物だと思う。
見た目のユニークさとシンプルさが良いバランスで、機能性も十分な良い建築。
ピルスナーウルケルを現地スタイルで飲めるそうだが、予算的制約で断念。
(というか、この3日間で会場内の飲食物を買うことはついぞなかった。)
後にスーパーで缶を購入したが、本稿執筆時点ではまだ飲んでいない。
中は現代アートだらけで、人によって好みが大きく分かれそうなパビリオンだった。好きな人は大満足だろうし、そうでなくとも種類は豊富だったので一つぐらいは好みに当たりそうである。
特に前後の脈絡なく、遺伝学の祖として有名なメンデルの直筆原稿(のレプリカと思しきもの)もポンと展示されていた。
出身が現在のチェコだとは知らなかったので、少しびっくりした。
というか、キャプションも置き場も雑だったので逆に目立っていた。
どうやら展示経緯にも謎が多いようで、それだけを調査・分析したnote記事が存在している。
他にも亜化石オークや3Dプリンタなど幅広く展示があり、並び時間の少ない割に楽しいパビリオンである。
スタッフから全パビリオン中で一番高いと聞いた気がするが、ネットでは裏付けできなかった。
チェコ館を出てそのまま大屋根リングへ向かう。
太陽の塔ほどの鮮烈さ、凄味は無くとも、ランドマーク性は十二分にあったと感じる。
万博は基本人だらけだが、パビリオンのないすみっこは案外そうでもない。
シンガポール、イタリア
リングの南側を半周して、西側に降りた。
見た目とそこそこの行列(30分待ち)に惹かれてシンガポール館へ。
切り絵風の展示は綺麗だったが、チェコ館よりも展示の系統がやや統一的で、子供向けの体験が多いパビリオンだった。
と内外装は好きだが、サッと見るぐらいで良かった枠である。
そして、本日の大本命、イタリア館へ
幸いにして、2時間半の待ち時間で入場できた。
2日目、3日目に見たときは7時間待ちだったことを考えると、非常に運が良かったと言える。
事前に万博先駆者のS氏から「折りたたみ椅子を持っていくべし」と助言を受けていたが、持って行かなかったし必要性も感じなかった。が、3時間超コースに挑む覚悟があるなら持っていくべきものに入ったのかもしれない。
ステージがあったのはこの写真の真後ろである。見飽きてしまったが
並んでいる間は、ステージの喧騒を聞きながら右手でTwitter(現X)を、左手でパビリオンの当日予約を試みていた。結果的にこの日は一件も予約を通せなかったので両手でTwitterをすべきだったが、まぁ後知恵である。
イタリア館の凄まじさに関しては、各所で徹底的に言及されており、今更付け加えることも無かろう。
近代以前の展示品が無くてもある程度評価されたと思うが、それらが評価の平均値を跳ね上げている。トリム平均ですら十分高水準なのだが…
個人的には、それらの実物は言わずもがなだが、工業製品や現代アート部分も良かった。
7時間並んでもペイできる、と考える人がいるのも大いに納得である。
イタリアパビリオンだけで保険料はいくら掛かっているのだろうか……
夜
イタリア館を出る頃には閉場時間が近づき、パビリオンの入場も締め切られ始めていた。
手近なアルジェリア館やコモンズでオーソドックスな民俗展示を見た後、再び大屋根リングに上って夜景を楽しむことにした。
ドローンショーは天候の都合で中止され、サーチライトが空に伸びる様だけを見ていた。
だからこそ暗い場所とのコントラストが映えると見るか、ただの下品な光害と見るか。
コメントが面倒臭い人みたいになっているのは、当時光過敏で偏頭痛が惹起されて、イラついていたためである。
ちなみに、大屋根リングの照明は、暖色系にされていたり、空を直に照らさない向きにするなど、光害対策がされているらしい。
そのせいでリング内のまばゆさが強調されているような気もするが……
リングを降りて夜の園内を散策しているうちに閉場時間となり、西ゲートから退場した。
1時間ほど、何もない西ゲート周辺を散歩したのち、23時発の夜行バスに乗って夢洲を離れた。
以上が人生初万博の一日である。
Day2
同行者が4人いるので、余裕を持って前泊、市内観光をした。
筆者は大阪より京都派の人間なので、大阪観光は7年ぶりで、夜の道頓堀にも初めて行った。本当に全く関係がありませんが、京都のリプトン(喫茶店)はいいぞ。
ラブホの居抜きっぽい安宿に皆で泊まり、朝一に突撃した。
フランス、未来の都市
真っ当に東ゲートから入場し、真っ先にフランス館へ。
長蛇の列だったが1時間
ルイヴィトンやディオールなど、ブランド関係の展示が豊富にあって、好きな人にはたまらないパビリオンだったのではないだろうか。
筆者はそのあたりに疎いので、はえーと思いながら鑑賞した。
プラダを着た悪魔で予防接種を済ませていたのが功を奏したのだろう。
ただ、ロダンの彫刻をはじめ、ブランド系も見て楽しめるようにはなっていたので、総じてクオリティは高かったと思う。
同行者で万博ヘビーユーザーのD氏によれば、本館にある立体配置されたLEDインスタレーションはいのち動的平衡館のそれと近しかったそうで、少しお得感があった。平衡館はついぞ予約できなかったので慰めにもなった…
フランス館をじっくり見た後は、当日予約に成功した未来の都市パビリオンに急いで向かった。
フランス館は東ゲートからすぐの場所にあるのだが、未来の都市は西ゲートよりさらに西にあるため、かなりの距離を早足で進むことに。
入口で美少女アバターの人がカメラ(画面)越しに挨拶をしていた。
VRChatでは毎日見られる光景だが、やはりあれは未来に位置付けられがちな光景なのだなぁ、と感じた。
ロマンがあって大変Good. 競争力のある値段にするのは相当大変そうだが…
「全自動」「完全無人」「汎用」もまたロマンだと思う。
入口と、それに続くウォークスルー型シアターではこれが未来…?と訝しみがちであったが、中の企業ブースでは中々面白いものが多かった。
実動レベルには無いとしても、万博という未来を示す場でコンセプトモデルの実物を用意するのは好ましい試みである。
当日予約がほぼ全滅している中、ほとんど唯一の空き枠が残り続けるステージ。
フィリピン、USA、トルクメニスタン
毎正時にあるアメリカ館の英語版ツアーに参加するため、西の果てにある未来の都市を出て、フランス館の横、つまりは東側に戻った。
計画になかった当日予約のせいだが、短時間で西と東を往復するという、非効率的な回り方になってしまった。
そして、50分にアメリカ館に到着したところ、「今回は満員」と言われたので、隣のフィリピン館で時間を潰すことに。
展示より、ご飯やマッサージの方が高評価のようだった。
特産の生地と一緒に各州の歴史や習俗を紹介する感じで、外装の派手さ、大きさの割には控えめな印象だった。
コモンズなどでさらに時間を潰し、今度こそUSA館の英語ツアーへ。
曲はTOGETHER(アーティスト:SPARK)として各配信サービスで配信中。
前回の月の石はその前年に採取されたものだが、今回のは半世紀前に採取された石である。
英語版ツアーだが、MCや曲が英語になる程度で、展示内容などは一切変わらないので並び時間が少ないというメリットだけを享受できて良かった。
このパビリオンだけエンタメ系というか、テーマパークのアトラクションのような印象を受けた。
もはや米国の宇宙開発に全盛期ほどの勢いは無いが、それでもこの展示はその進歩を想起させるに十分な材料を提供してくれたという点で、万博の本懐を果たしているのではなかろうか。
自分用のお土産は米国館で購入した。ただ、心が震えたので。
米国館を出たころ、同行者一行がトルクメニスタン館でご飯を食べると連絡が来たので、合流しにトルクメニスタン館へ。
しかし、並んでいる最中にいのちの未来館の予約が取れたので、そちらに行き、トルクメニスタン料理は食べ損ねることに。
いや、あのトルクメニスタン料理は酸っぱいトルクメニスタン料理だから…
展示を急いで見て、いのちの未来館へ。
いのちの未来、TECH WORLD
いのちの未来館では骨伝導イヤホン付きの端末を配られ、それ越しに映像やアンドロイドが動いて喋るのを聞く形式だった。
特に骨伝導イヤホンや端末を持つ必要は感じなかったが、多言語対応はこの形式の方がしやすいのかもしれない。
攻殻機動隊(SAC)などの各種SFでしばしば扱われる、多少手垢のついたテーマである感は拭えないが、映像や演技、シナリオの質は非常に高かった。
アンドロイドの実物や、リアル会場ならではの映像表現などが秀逸で、最後の一部屋以外は満足だった。
最後の一部屋について、この部屋ではドラマ要素は無く、機械による演出のみが行われる。
私には、この部屋が何を示したかったのかよく分からなかった。
ここまでの丁寧さに対して、あまりにも投げっぱなしであり、存在意義が不明である。あくまで個人の感想だが、ない方が良かった。
これまでの部屋では、あくまでも技術の進歩という前提、生命倫理という議題が提示され、考えることが可能だった。しかし、最後の部屋だけは、何もない。
過去も現在も経由しない、文脈の欠落した未来などおよそ語るに値しまい。
この館に対して辛辣な理由は、最後の部屋以外にもある。
このパビリオンで展示されるアンドロイドたちは、歩行しない。決まった場所で顔や上半身を動かすのがせいぜいであるし、案内のロボットは配膳ロボットスタイルである。
自立歩行すらままならないような体たらくでは、電脳化ですら夢のまた夢であろうし、そのような状況で意味不明生命体の話をしてもただの妄想に留まる。具体性、実現性、説得力が全て欠如しているのは、ただ残念である。
いのちの未来館を出るとすっかり日も暮れており、列形成が打ち切られる寸前だったTECH WORLDに並んだ。
半導体産業が盛んで、神農生活があり、台湾杉で有名な略称TW。
一体何湾なんだ……
入口で心拍計を渡され、どこでときめいたかを最後にお知らせしてくれるサービスがあった。
普段心拍計をつけているので、平時は精神よりも運動量の影響の方が大きいと思うのだが、歩きながら見るところと留まって見るところの間で何か補正がかかっているのだろうか…?
TECH WORLDという名前の割に自然への言及が多かったが、後半は技術信仰的な要素が強くなり、中々に味の濃いパビリオンだった。
貰えるお土産にガチャ要素があるらしく、私がもらったのは肉まんタオルだった。一回ほぐせばただのタオルなので便利である。
TWの外で同行者と合流して、ドローンショーを横目に見ながら芋洗い状態の駅に行き、宿に帰り着いた。
Day3
最終日だが、同行者の飛行機の時間のため、比較的短時間の滞在となった。
ベルギー、英国
土産屋を巡った後、見た目が気になっていたベルギー館にとりあえず入場。
国際検疫チームとバイオテロ組織がパンデミック下でドンパチする本。中々ぶっ飛んでて面白い。
映像主体でまぁまぁ普通だった。
医学とスポーツ推し。
続いて、行きたかった英国館へ。
SPARKより落ち着いてるが、植民地支配とかの不都合なことは綺麗に回避する模範的英国紳士。
複数シアターで国の名所や発明品を紹介していくスタイルだが、ストーリー構成や映像のクオリティが高く、退屈しづらい。
アメリカ館よりも映像の占める比率が高いが、子供とかはこちらの方が楽しめるかもしれない。
宇宙開発のようなキラーコンテンツなど、際立った強みこそないが、無難にレベルの高いパビリオンだった。
null^2(ウォークスルー)、中国
null^2の予約は初日から試みていたが、ついに一度も取れなかったので予約なしでも入れるウォークスルーモードに並ぶことにした。
英国館から出ると丁度開放時間だったので、比較的時間のロスなく入ることができたが、それでも炎天下+null^2からの照り返しできつい並び列だった。
30秒弱の通り抜けだったが、膨大な文字列や反射がチカチカしていて、愉快な空間だった。
面白い趣味に馬鹿みたいに金をかけて建てたクラブ、という感想である。
同行者のI氏はインスタレーションの予約を取れたので見に行っていたが、「いい感じにぐねぐねで良かった」そうである。
私も帰ってからYouTubeに上がっているアーカイブ動画を見たが、いささかイデオロギー的というか、あまり肌に合わなかった。
実物を見ればそういうショーとして十分楽しめただろうが、私は落合洋一のファンではないし、ウォークスルーで軽く楽しむぐらいがちょうど良かったのかもしれない。
null^2を出ると、駆け足で中国館に向かった。
時間も残りわずかだったので間に合うかヒヤヒヤしたが、存外早く入場できて事なきを得た。
35度越えにもかかわらずパンダの着ぐるみが長時間絶えず動き回っていて、畏敬の念を抱いた。
ガラスの反射のため写真が無いが、前半部分は博物館のようになっていて、展示品のガラスケースがタッチ操作対応の透過ディスプレイになっていた。
キャプションや3Dデータをを表示するなどちょっとしたものだが、未来感があって大変良い。
鑑真や最澄、空海などがいたし、鉄腕アトム、朱雀、パンダもいた。
石、というより土か砂状のものだったが、2020年と24年のサンプルが2つ展示されていた。
アメリカ館ほどの情熱感は無かったものの、中国館も宇宙開発をかなり推していて、中国宇宙ステーションからのメッセージブースであったり、月面、深海探査の成果などが多く展示されていた。
TikTokでおなじみのByteDance資本だからか、米国では販売されていない。
ちょうど中国館を見終わったあたりで撤収時間となり、帰途に就いた。
3日間にわたる万博観光、その紀行文はこれにて終了である。
だが記事はもう少しだけ続く。
こぼれ話
夢舞大橋
突然だが、大屋根リングの建設費をご存じだろうか。
約350億円である。
ところで、会場の北に、大きな橋があることもご存じだろうか。
総工費約635億円で架けられた、夢舞大橋である。
インフラ整備は高額になりがちなので、これぐらいならよくある話だが、
この橋は世界に唯一の浮体式旋回可動橋である。
つまり普段から浮いてて、いざとなったらぐるっと旋回して水路を開けることができる橋、ということだ。
三井住友建設鉄鋼エンジニアリング株式会社公式HPより
詳しく述べよう。
まず片方の橋の端に据え付けられた巨大杭を、陸地側の軸受けに差し込む。
次に陸地側(浮いてない部分)を浮かせて橋の固定を解く。
その後、浮きの部分(橋脚の下)の固定装置を解除して動くようにする。
あとはタグボート3隻で橋を回転させ、岸と並行の位置で再固定する。
大阪港のメイン航路は別にあるのだが、災害などで使用不能になった場合のサブ航路を用意するため、こんな機構の橋を用立てたらしい。
どうにもバブル期の港湾開発、夢洲新都心構想や五輪招致構想などの産物らしいが、なんとも壮絶な橋である。
2016年以降一回も可動機構のテストをしていないようなので、今も動くのかはよく分からないが、名前通り何とも夢のある橋ではないか。
会期中に一回ぐらい動かしてくれてもよかったのに…
…下手なパビリオンの未来像よりもよっぽどロマンがあるのでは…?
デジタル万博()
今回の万博はデジタル万博と銘打っていた。
先端デジタル技術を用いて、未来を先取りする“超スマート会場”を実現します。自動翻訳システムやAIを用いた情報案内アプリなどを提供することで利便性の向上を目指し、最先端の通信や映像装置を使った演出を行うなど、来場者の体験と万博運営をトランスフォーメーションしていきます。
しかし、今回の万博で最も酷かったものは、公式サイト・アプリ・サーバーであった。
引用した「超スマート会場」の要素自体は、確かに実装されていた。
例えば、公式の「EXPO2025 Personal Agentアプリ」は確かに計画策定AIやマップなどを備えた高機能な総合情報案内アプリとして提供された。
しかし、毎回起動に要する時間が長い、パビリオンの検索機能が表記ゆれに弱い、待ち時間などの都合で計画通りに行かないなどの問題があった。
しかし、結局来場者はアプリではなく、非公式の万博マップをより好んで使用した。要件は実装されたが、ユーザー体験は十分に顧みられなかったのである。
上述したアプリは十分な機能を備えていて、ちゃんと使えば大いに有用だったのだが、全く擁護できないのは予約システムとサーバー強度である。
万博通期勢のD氏に聞いたところによると、開幕直後で人が少なかった頃は問題なかったようだが、会期後半には完全にキャパオーバーになっていた。
並んだり歩いたりしながら、F5連打で使いづらいサイトとにらめっこするのが未来を示すデジタル万博の姿で本当に良かったのだろうか。
会場のキャパシティーが十分ならただ微妙なサイトで終われたのだろうが…
全体の運営見込みや、アップデートが不十分であったと言わざるを得ない。
ちなみに、デジタル万博の他には、
スマートモビリティ
バーチャル
アート
グリーン
フューチャーライフ
の5つが挙げられている。
次の項でバーチャルだけ少し言及するが、これらにはデジタルほどの突っ込みどころは無いと思う。
アートとグリーン要素は各パビリオンで見飽きるほど見せられるし、モビリティもそこまで推しが強くないが、雰囲気はまま感じられる。
フューチャーライフだけ、当たり判定が大きすぎるような気もするが……
バーチャル万博
本稿執筆直前に、駆け込みバーチャル万博をした。
筆者の所有しているVRHMD、PCVRは非対応だったのでDesktopモードでプレイした。駆け込みのため、一枚も写真が無いのはご容赦いただきたい。
結論から言えば、ピンキリだが成功例もある、といった感想を抱いた。
まず良かった点・納得できた点。
会場や各パビリオンの外見などは、スマホやHMD単機にも対応させることを考えると妥当なものだった。デフォルメ感があるとはいえ、デジタルツイン的な機能は十分だろう。
ライブやパレードなど、イベントのクオリティも総じて高かった。
やや微妙だった点。
UI/UXが微妙である。デスクトップ版以外は触っていないので、スマホやHMDだとマシだったのかもしれない。
初回ログインの挙動は鈍重だし、各パビリオンに入る度にDLとロードが入る。パビリオンの数を考えれば、事前DLオプションがあっても良かった。
ダッシュを最高速にするためには助走が必要で、じれったい上に急に速度が変わると酔いやすい(気がする)。
視点移動が矢印キーメインで、マウスカーソルによる視点移動はドラッグが必要でやや手間である。
まぁ、テレポート機能など最低限のユーティリティは整備されていたので、致命的ではなかった気がする。
長時間やっているとストレスが蓄積されそうだが…
一方で、明暗・特色が分かれたのは各パビリオンの内装である。
そのスタイルは大きく3タイプに分類できる。
タイプ1 ~量産動画ルーム型
まず目立ったのは、一部屋+動画プレイヤースタイルのパビリオンである。
小物などが申し訳程度に置かれていることも多いが、総じてYouTubeの視聴で事足りる。
V万博はパビリオンに入るごとにインスタンス移動、ワールド読み込みが入るため、この手のパビリオンは検索妨害的な面倒臭さを提供してくれる。
外装はメインワールド側に全てあるのだし、サーバー費用や製作の手間などを考えても、このタイプはワールド化せず、動画へのリンクのみの方がマシだったのではないか。
タイプ2 ~デジタルツイン型
現実にある展示をバーチャルで再現・模倣する、王道スタイルである。
EARTH MARTがその筆頭で、ここは間取りや展示物など全般が、リアルのパビリオンとかなり近しいと言える所まで再現されていた。
動画や体験コンテンツは流石に再現し切れていないので、完全に代替可能でこそないが、7割ぐらいは楽しめるのではないだろうか。個人の感想だが、EARTH MARTの脳内株価はずっと右肩上がりである。
EARTH MARTほど高精度に再現するのは少数派だが、目玉コンテンツだけ置いたり、簡略化してそれっぽく見せるようなスタンスを取る館は多い。
後述するタイプ3でも、バーチャル独自の手法でリアル展示を演出しているパターンが多く、やはりタイプ2が基本的で作りやすいのだろう。
タイプ3 ~バーチャル重視型
バーチャルでしかできない表現を積極的に取り入れ、独自性が強くなりがちなスタイルである。
ゲーム要素があるもの、超現実的な演出で魅せるものなどがある。
日本館やnull^2、TECH WORLDなどが代表例だろうか。タイプ2とのハイブリッドが多いが、どれぐらい現実離れするかはパビリオン次第である。
もしV万博がPCVR対応などでスペック要件が緩和されていたら、もう少し身体性を活かしたコンテンツが増えたのかもしれないが、今回はあまりその手のものは無くRPGスタイルが多かった。
V万博の感想として、可能性は感じる良いコンテンツではあったと思う。
打率は低いものの、EARTH MARTやイベントなどのクオリティを見ると、バーチャルが実用レベルに普及する未来がありうるのではないかと思えた。
既存のプラットフォームに依存しているという大きな違いはあるが、そのあたりはVketなどの方がまだ一日の長があるとも感じた。
V万博は多分NTTコノキューが主宰してるのだろうが、そのあたりの面々には今後とも頑張って競争してほしい。
本心から応援している。頼む。リアル芋洗いイベントはもう嫌です……
万博全体の感想
大阪万博開幕の直前・直後には、Twitterでこのような意見が出ていた。
上記のまとめ記事で言われているのは、「万博に未来感が無い」ということである。「未来のネタ切れ」と称したYouTuberもいたそうだ。
誘致~会期前半まで、万博に対してネガティブな論調が強かったことを考慮しても、この意見には一定の納得感がある。
野放図な進歩ができなくなったことで未来の行き詰まり感が世間を覆い、
万博はワクワクしないものとみなされるようになったのではないだろうか。また情報化社会になり、進歩や展望を共有する役割が各メディアに移譲されたこと、大きな物語が成り立たなくなったことも大きな要因だと考える。
ここで今一度万博の定義を引こう。
第一条 定義
1. 博覧会とは、名称のいかんを問わず、公衆の教育を主たる目的とする催しであって、文明の必要とするものに応ずるために人類が利用することのできる手段又は人類の活動の一若しくは二以上の部門において達成された進歩若しくはそれらの部門における将来の展望を示すものをいう。
「利用することのできる手段」は社会や環境への悪影響が懸念されているために、大きく制限を受ける。
となれば、今後の進歩が鈍化するという厭世的な見込みが優勢になり、自然と「将来の展望」は暗いものとなる。
その結果、もはや輝かしいものは過去に「達成した進歩」のみとなり、万博はノスタルジーで無聊を慰めるだけになりつつあるのではないか。
目的が「公衆の教育」の任意参加イベントで刺激や面白さが容易には見出されないなら、行く意味が感じられないとか、浪費であるとの意見が出るのは道理であろう。
ただ、個人の感想だが、この構造が問題なのかどうかを断じることは、現時点ではできないと考える。
会期後半で、入場者は劇的に増えた。
これは万博の傾向としてよくある形らしいが、今回の場合はSNSなどでの口コミが要因として挙げられている。
つまり万博に行った人は、何らかの形でそこに価値を見出したわけである。
まだ考えが纏まっているわけではないが、万博は過去ではなく、未来を対象としたダークツーリズム的な要素を帯び始めているように思える。
たとえ万博が客観的に見てこの上なく陰鬱/退屈なものだったとしても、あるいは出展者が何らかの意図を伝えたかったのだとしても、そこから何を見てどう解釈するかは各個人に委ねられているのである。
いささか楽観的なきらいはあるが、無い未来を有るものにしようとする主体は、望むと望まざるとにかかわらず、現代人であり、未来人である。
万博に不満を持ち、納得しないこと。
提示された未来像をただ消費するのではなく、批判的に継承することが新たな価値として成立しつつあるのではないだろうか。
徹底的な批判に耐え、洗練され尽くしたアイデア、あるいは絶望的な状況でも強さ故に張り続けられたアイデアこそが、より良い未来に相応しいものとなるのではないか。
いのちのかがやきは、昏さを超克した先にあるのかもしれない。

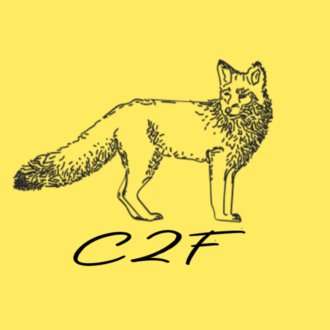
コメント