アメリカでは商品の選択肢が無い:アメリカを例に見る資本主義による寡占化の弊害に関する経済社会学的考察
1. 概要
よく日本人駐在員の話を聞くと、「アメリカでは欲しい物がなかなか手に入らないので、一時帰国の際に日本で大量に買い込み、それをスーツケースに詰めて戻る」というエピソードに出会う。アメリカといえば「物が溢れる国」「資本主義の象徴」というイメージが先行する。しかし、実際に生活してみると、「物は多いのに欲しいものがない」という逆説的な現象が現れるのだ。
もちろん、これは単なるイデオロギーの対立を語るものではなく、一消費者として資本主義の先鋭化がどのようなデメリットをもたらすかという、あまり語られてこなかった現象の一端である。日本にいると、SNSやメディアから「アメリカ=巨大市場で品揃え豊富」という表層的な情報だけを受け取りがちだが、実際に暮らしてみなければ体感できない部分が確かにある。
ニューヨークやカリフォルニアのような大都市圏では、日系・韓国系スーパーも進出しており、Whole Foods、Walmart、Targetなどの大手やローカルスーパーを使えば、一見「選択肢は十分ある」と思えるだろう。しかし、そこで流通している商品は驚くほど限られており、例えば日本で日常的に目にするような、細やかな商品バリエーションや、ちょっとした便利グッズは姿を消している。
この違いは、アメリカ人が日本に来てコンビニやドン・キホーテ、ヨドバシカメラを訪れた際に歓声を上げる光景によく表れている。アメリカにもBest Buyがあり、セブンイレブンやサークルKも存在する。だが、Best Buyには日本のヨドバシカメラほどの「商品を選ぶ楽しさ」はなく、アメリカのコンビニは“軽食と飲料を買う場”以上の役割を果たしていない。ではなぜ日本の店に彼らは驚嘆するのか。
それは単に「文化の違い」で片づけられる話ではない。むしろ、アメリカの小売市場が進んだ寡占化の結果、品目が単一化している「競争のパラドックス」に起因している。寡占が進むと、消費者にとって価格は下がる一方で、商品バリエーションは削られる。供給側からすればSKUを絞ることが効率化につながり、利益を最大化できるからだ。その結果、表面的には「物が溢れているように見える」のに、実際には同じ商品が巨大な棚を埋め尽くすだけの状態になる。
この現象は本の世界にも見られる。アメリカでは地域の本屋が次々と消え、Amazonが一強となった。その過程で「どこでも買えるベストセラー」は残ったが、地域性や多様性を支えていた小さな書店の棚からは多くのニッチな本が消えた。つまり、寡占化は「効率」を生む一方で「多様性」を犠牲にし、結果として消費者の選択肢を狭めてしまう。
アメリカでの生活に直面する「欲しい物が見つからない」という不満は、単なる個人的な違和感ではなく、資本主義が成熟しすぎた社会が抱える構造的な矛盾の一つである。卸とメーカーの関係性、流通網の効率化、そして寡占の進行がもたらす負の側面、それらを見ていくと、「物が多いのに物がない」というアメリカの paradox がより鮮明に見えてくるだろう。
なお本稿においては、アメリカの小売流通を論じる際に ウォルマートを主要な参照例として用いている。これは、ウォルマートが単に「米国最大の小売業者」であるからだけではない。むしろ、アメリカにおける多くの小売業者がウォルマートのビジネスモデルに近い仕組みを採用しており、物流効率化やサプライチェーン戦略において同社が 最も代表的な事例とされるからである。
実際、MBAなどのビジネススクールにおけるロジスティクスやサプライチェーン・マネジメントの授業では、ウォルマートは「現代的流通システムを理解するための格好のケース」として頻繁に取り上げられている。本稿においてもその学術的・実務的有効性を踏まえ、ウォルマートを中心に論じることで、アメリカ型小売流通の特徴をより明瞭に示すことを意図している。
もちろん、アメリカにはウォルマート以外にも多様な小売業者が存在し、各々に独自の戦略や特徴がある。それらについても後ほど言及するが、まずはウォルマートを基準点として論じることが最も理解を得やすいと考える。そこでアメリカでは私の好きなTrader Joe’sやWhole Foodsの言及がない!とか頭に思い浮かぶ前にいったん落ち着いてほしい。
もちろん、一部の品目や後ほど言及するニッチなスーパーなど、アメリカの小売市場に例外が存在することは否定できない。しかし、それでも アメリカの標準的な流通・小売の商流においては、日本と比較しても寡占化による品揃えの少なさが顕著である*1*2*3*4*5*6 という点は、純然たる事実である。
本稿はその結論を提示すると同時に、しばしば耳にする「そんなことはない、アメリカでもスーパーを探せば品揃えはいくらでもあるはずだ」という主張に対して、明確な反論を与えるものである。確かに一部の都市や特定のニッチスーパーでは多様な商品が揃う場合もある。しかし、それはあくまで例外にすぎず、標準的な流通・小売の商流においては寡占化が進行し、結果として選択肢が体系的に制限されているという事実を覆すものではない。
つまり、本稿は「アメリカにも多様性は存在する」という表層的な反論に流されるのではなく、むしろその例外性を認めつつも、市場全体を規定する構造的な寡占の力学こそが消費者に最も強い影響を与えていることを明らかにするものである。
この現象は、単なる印象論ではなく、アメリカにおけるメーカーと小売の寡占構造による必然的な帰結である。具体的には、カテゴリーキャプテン制度やスロッティング手数料、支配的リテーラーによるアソート戦略などの仕組みが、商品選択肢を体系的に制限していることが、ビジネス研究や産業経済学の分析を通じて繰り返し指摘されてきた。
一方で日本においては、この点が十分に特集される機会は少なく、むしろ「アメリカ的効率性」への表層的な賛美が目立ってきた。しかし現実には、その効率性の裏側に 消費者の選択肢喪失や改善停滞 という構造的リスクが潜んでいる。本稿は、まさにその事実を浮き彫りにし、日米の小売構造を比較することで、我々が気づくべきポイントを提示する試みである。
では、なぜそのような状況に至ったのか。本稿で論じてきたように、その背景には 流通形態の集中化、経済構造の規模の経済、そして小売とメーカーの寡占関係 が複雑に絡み合っている。結果として、アメリカの棚が「あたかも画一的に見える」のは単なる印象ではなく、実際にアメリカ国内でも広く認識されている 構造的なファクト なのである。
この事実を踏まえたとき、我々日本人が気づくべきことは何か。それは、普段当たり前のように享受している「多様な選択肢と競争による品質改善」という環境が、実は世界的に見ても極めて稀で恵まれた状況であるという点である。本稿を通じて、そのことを改めて理解し、選択肢があることの価値を再認識していただきたい。
2. アメリカの流通及び小売事情
まずアメリカの流通および小売事情について簡単におさらいしておきたい。米国の小売売上高(自動車ディーラー、ガソリンスタンド、レストランを除く)は、2025年の見通しで5兆4,200億~5兆4,800億ドル(約813兆円~822兆円、1ドル=150円換算、出典:JETRO)とされており、世界最大規模の市場であることは疑いない。*7
アメリカにおける流通は基本的に「メーカー → 卸(Distributor、ディストリビューター)→ 小売」という構造のもとに成り立っている。この基本枠組み自体は日本と大きく変わらない。ただし決定的な違いは、卸がどこまで力を持ち、小売に影響を与えるかというパワーバランスにある。
ディストリビューターの役割
ディストリビューターとは、メーカー(生産者)と小売(スーパーやコンビニ)をつなぐ中間業者であり、主な役割は以下の通りである。
メーカーから大量に商品を仕入れて保管する
在庫を管理し、必要に応じて小売へ配送する
小売ごとに細かい数量に仕分けして納品する
商品によっては陳列や販促も担当する(例:飲料やスナック菓子など)
例えばコカ・コーラやP&Gのようなメーカーが大量生産した商品は、まずディストリビューターの倉庫に納められる。そこからウォルマートのような小売に届く流れとしては大きく二つに分けられる。
ダイレクト・ストア・デリバリー(DSD)方式
飲料、ビール、スナックなどはメーカーや地域ディストリビューターが自社トラックで直接ウォルマート店舗に納品・陳列する。
→ 例:コカ・コーラの配送員が店舗に来て、棚に商品を並べる。倉庫型(ディストリビューションセンター経由)方式
洗剤、シャンプー、缶詰など多くの商品は、まずウォルマートの巨大な地域物流センター(DC)に集められ、そこからウォルマートの自社トラックで各店舗に配送される。
ウォルマートを例としたアメリカ流通の特徴
アメリカの小売最大手であるウォルマートは、独自の物流網を構築し、通常の小売店に比べてディストリビューターへの依存度が低い。クロスドッキング方式(倉庫に長期間保管せず、入荷後すぐに仕分けして出荷する)を徹底することでコスト削減を実現している。*8 その圧倒的規模により、メーカーに「直接DCに納品してください」と交渉できるほどの強い交渉力を持つ。
この構造の下で、アメリカでは必然的に小売(ウォルマートやコストコ)がサプライチェーンを支配する。卸の力が日本より弱いため、小売が「何が一番売れるか」を基準に品目を選択し、一品目に集中して販売する傾向が強い。結果として、低頻度で大量配送・標準化が実現し、消費者にも安価で大量の商品が届く仕組みが出来上がった。
さらに地理的要因も無視できない。アメリカは広大な国土を有し、大型ディストリビューションセンターを基点とした長距離トラック輸送に依存する。日本のような小規模店舗への多頻度配送は非効率であり、結果として配送回数を減らし、SKU(商品種類)を絞る必要が生じる。
まとめ(アメリカ型流通の要点)
大量・標準化前提:SKU回転が遅く、品揃えは限定的
店舗柔軟性が低い:種類より「安さ・量」で勝負
広大な国土ゆえ:長距離輸送中心、小規模店舗への多頻度配送は不向き
倉庫一括納品:大規模ロットで配送、店舗も大型で在庫を抱えやすい
日本型流通との対比
一方で日本は、卸主導の多頻度小口配送を基盤にしているため、多品種少量の流通が可能である。これにより、消費者には豊富なバリエーションが提供され、新商品も素早く店頭に並ぶ。とりわけコンビニは象徴的で、1日3~5回配送があり、棚は常に新鮮に保たれる。さらに共同配送(同一トラックに複数メーカー商品を積載)により、狭い店舗でも多品種を維持できる。*9
もちろん日本にもアメリカ型の流通モデルを導入する事例はある。代表例がコストコで、卸を介さずメーカーと直接取引、あるいは本国から輸入する形態をとっている。ただしこうした形態はまだ少数派であり、日本の主流は依然として卸と小売本部の緊密な連携を基盤とする。
事実、ウォルマートが日本で西友を買収した際も、複雑な日本の流通網や卸との関係性をうまく扱えず、最終的に撤退に至った。この事例は、アメリカ型「中央集権的サプライチェーン」が日本市場と相性が悪いことを示している。*5
アメリカ市場の寡占化
アメリカ小売市場は過去20年で急速に寡占化が進み、ナショナルチェーンが市場の大半を占めている。代表的企業は以下の通りである。
Walmart:フルライン+低価格戦略、最大手
(2024年売上高:5,339.6億ドル)Costco:会員制倉庫型、少品種大量販売
(2024年売上高:1,753.9億ドル)Target:中間層向け総合小売
(2024年売上高:1,058.4億ドル)
特にウォルマートは全米ほぼすべての都市に拠点を持ち、メーカーにとって最大の販売チャネルであると同時に、最も価格交渉が厳しい相手である。*10
もっとも、全米が完全に大手3社だけに支配されているわけではなく、地域密着型や民族系スーパーも生き残っている。例として、日系スーパーのミツワマーケットプレイス、韓国系H-Mart、テネシー州ナッシュビル拠点のTurnip Truck Natural Market、ノースカロライナ州拠点のHarris Teeterなどが挙げられる。こうしたプレイヤーは差別化によって市場に存在感を残しているが、それでも流通形態そのものは大手チェーン主導の「少品種・大量販売」という枠組みを大きく逸脱してはいない。
つまり、日本とアメリカの流通の最大の違いは、中間業者(卸)の役割の強弱にある。日本では卸が「多品種小ロット配送」を支え、消費者の多様なニーズに応える構造を作っている。一方、アメリカでは小売がサプライチェーンを支配し、「少品種大量販売」で効率性と低価格を追求している。
日本の卸売に対して「非効率的だ」という批判もあるが、実際には多品種少量を実現するための不可欠な存在であり、単純に否定できるものではない。ここに、両国の小売・流通文化の根本的な違いが表れている。
3. 競争のパラドックス
ここまでで主にアメリカと日本の流通形態の事実整理を行ってきたが、本題に入ろう。なぜそもそも、アメリカにおいてこれほど大手小売が寡占状態に至ったのか。寡占(オリゴポリー)や独占(モノポリー)とは何か、そしてなぜ独占状態は必ずしも消費者に恩恵を与えるものではなく、むしろ競争の観点から避けられるべき状況なのか、ここでは社会哲学的な視点を交えて考察していきたい。
日本とアメリカの競争環境の違い
日本に住んでいると、一社あるいは数社だけが市場全体を独占する状況は起きにくい。理由は二つある。第一に、地理的に狭く供給過多になりやすいため競争が自然と激化すること。第二に、独占禁止法(公正取引委員会の規制)が比較的機能しており、ある企業が市場を独占的に収益化すれば、すぐに類似の事業者が参入し競争が発生する仕組みがあることだ。結果として、価格は競争によって抑制され、品質も競争によって向上する。この「需要と供給のバランスこそが経済学の基本」である。*11
例えば、日本における外食産業は世界でも類を見ないほど競争が激しく、2023年時点で外食店舗数は約18万7千店にのぼる。特に東京だけで約15万店近くが集中しており、まさにレッドオーシャン市場といえる。*12 さらにコンビニやスーパーでの弁当・総菜販売も加わり、食品市場は過剰供給の典型例である。その結果、食品価格全体にデフレ傾向が生じており、これは競争原理が消費者に強いベネフィットを与えている事例だといえる。
このことから、国際的な比較指標としてよく用いられる「ビッグマック指数」に筆者が懐疑的なのも理解いただけるだろう。日本のビッグマックの価格は購買力を直接示すのではなく、むしろ「外食産業が過剰競争状態にあるがゆえの低価格」を反映しているに過ぎないからだ。
アメリカにおける大型小売台頭の歴史
アメリカは都市と都市の間に距離があり、生活圏が広大である。必然的に消費者は自動車で移動し、週単位でまとめ買いをする文化が生まれた。1950年代以降の郊外化(Suburbanization)により、広大で安価な土地が確保でき、巨大駐車場付きの大型店舗やショッピングモールが次々に建設された。*13
この背景のもと、Target(創立1962年)、Walmart(創立1969年)、Costco(創立1983年)といった大型小売チェーンが台頭し、規模の経済のスパイラルを確立した。すなわち、大量仕入れ → 単価削減 → 低価格販売 → 顧客拡大 → さらなる大量仕入れ、という循環である。ここにこそ、アメリカ型資本主義小売の典型がある。
なぜ「第4」「第5」のメガチェーンが生まれなかったのか
しかし、ここで疑問が生じる。なぜターゲット、ウォルマート、コストコに続く第4、第5の大型小売チェーンは現れなかったのか。
理由は明白である。ウォルマートやコストコは規模の経済を徹底的に活かし、物流・価格競争で他社を圧倒した結果、中堅チェーンが成長する余地を奪ってしまった。事実、ウォルマートは食品小売だけで米国シェアの20%以上を占め、地方スーパーや中堅チェーンを淘汰した。*14
この結果、アメリカ市場は「Big Three」の寡占構造に固定され、それ以下は ニッチ特化型としてしか生き残れなくなった。Whole Foods(オーガニック志向)、Trader Joe’s(高品質PB)、Dollar General(低所得者層向けディスカウント)といったプレイヤーはその典型だ。
競争のパラドックス
ここに現れるのが「競争のパラドックス」である。資本主義における競争は本来、価格を下げ品質を上げる方向に働く。しかし、競争の結果として一部の巨大プレイヤーが市場を寡占すると、逆に選択肢は狭まり、効率化の名のもとにSKUは削られ、「安価だが単一的な商品」が棚を埋め尽くす。つまり、消費者にとっては「選択肢があるようで実はない」状況に陥るのである。
これは経済学的に、競争が極端に進んだ結果、資本主義の内部から社会主義的な構造(寡占による供給統制)が現れる矛盾を意味する。まさに「資本主義の逆説」といえるだろう。*15
消費者にとっての影響
この寡占状態は、価格の低下という恩恵を与える一方で、商品バリエーションやサービスの質におけるマイナスを生む。これが独占禁止法が存在する理由であり、競争状態こそが最も健全で自然な市場の姿である。
例として決済サービスを考えてみよう。日本ではVisa、Mastercard、PayPayをはじめ数多くの決済手段が乱立し、「多すぎるから3つ程度に絞ってほしい」という意見すらある。しかし、本当に寡占状態が望ましいだろうか。もし選択肢が少なければ、サービス向上や価格競争は起こらず、利便性も落ちる。むしろ決済手段が多いほど競争は働き、消費者はより多くの恩恵を受ける。これこそが競争という概念の本質である。
4. アメリカのメーカーと小売の奇妙な共存関係
小売が支配し、メーカーが従属する
アメリカにおけるメーカーと小売は日本のそれとは異なり奇妙な共存関係にある。特に力関係の逆転がそうで、小売主導型サプライチェーンにより、日本や伝統的な流通においては メーカーが主導し、卸を通じて小売に商品を流すのが一般的だが、しかしアメリカ、とりわけウォルマートでは 小売が主導する。当たり前だが、ウォルマートの販売規模が圧倒的で、 「メーカーにとってウォルマートは最大の顧客」ということは、逆に言えば「ウォルマートを失うことは死活問題」であり、結果、交渉の主導権はメーカーではなくウォルマートにある。
ウォルマートはメーカーに対して、以下のような厳しい条件を突きつけることができる。
低価格での納品:
大量仕入れを前提に「もっと安く」と圧力をかける。納品方法の指定:
クロスドッキング方式(DCに納品したらすぐに仕分け・出荷)をメーカーに徹底させる。データ共有の義務:
POSデータや販売動向をリアルタイムでウォルマートに共有。棚割りの制御:
「この商品を優先的に並べる」「不要なSKUは削減せよ」と指示。
つまりウォルマートは「取引先」ではなく「サプライチェーンの司令塔」としてメーカーを従わせる存在であり、メーカー側からするとウォルマートに採用されれば、全米で一気に巨大な販売網に乗せられる反面、もし契約を打ち切られれば、一気に市場シェアを失うリスクがあるため依存率が必然と高く、価格交渉力が弱まってしまう。メーカーにとってウォルマートは「最大の顧客であり、最大のリスク」である。ウォルマートにとってメーカーは「安く効率的に商品を供給させる存在」であり、両者の関係は「対等なパートナー」ではなく、むしろ「小売が支配し、メーカーが従属する」構造に近い。しかし、これに対してメーカー側もただ従属するのではなく、メーカーはウォルマートとの交渉力を補うために、しばしばロビイングを活用し対等な交渉力を得る為に駆け引きを行っている。勿論ウォルマートもロビイング活動を通して、小売>メーカーというパワーバランスを維持するために、商流規制、独占禁止法の対象外等含め、小売り側の不利益にならないよう誘導している。
カテゴリーキャプテン
ウォルマートとメーカーは一見「対立」するように見えるが、実際には 利害が一致している部分が大きい。
ウォルマート:SKU削減 → 在庫コスト削減 → 価格競争力強化
メーカー:棚の独占 → シェア拡大 → ブランド力強化
結果として、「消費者には商品が溢れて見えるが、実際には一社独占に近い状態」が棚の上で生まれる。ウォルマートは流通効率のために品目を絞り、メーカーは市場支配のために競合を排除する。結果、両者の思惑が一致し、消費者の目の前には「見かけ上の豊富さ」と「実質的な寡占」が並存する という奇妙な共存関係が成り立つのだ。これは他社小売り大手でも同様であり、またWhole FoodsやTrader Joe'sといった中堅小売に関しても、メーカー同士を競争させるのではなく、流通効率のための品目を絞るという手段を取っている。P&G(洗剤)、コカ・コーラ(飲料)、ペプシ(スナック)などの大手メーカーは、ウォルマートのような巨大小売との取引で自社が「カテゴリーキャプテン」になることを目指し、大手メーカーが独占供給する、及びまた自社に有利になるよう、一度ウォルマートの棚を抑えることで、全国規模で他社を排除でき、事実上の独占供給が可能になる。
メーカー主導の寡占化
ロビイングを通じて「競争制限ではなく市場の効率化だ」と正当化し、規制当局からの監視を弱めることがメーカーとしてもまた有利な立場にいられる。メーカー主導の寡占化により、他社製品がウォルマートやその他小売に陣列しないよう政治家に働きかける。ロビイングによって参入障壁を固め、大手小売と組んで棚を実質的に独占する仕組みを例えばP&Gを例に見てみよう。
洗剤市場:P&G(タイド)
背景
アメリカの洗剤市場で最大手は P&G(Procter & Gamble)。主力ブランド「Tide(タイド)」は市場シェア30%以上を占める。棚の実態
ウォルマートの洗剤コーナーでは、Tideのサイズ違い・香り違い・液体・粉末・ポッドタイプが棚の大半を占める。
→ 一見「多様な選択肢」に見えるが、実際には メーカーはP&G一社。ロビイングの影響
P&Gは米議会やFTCに対して巨額のロビイングを行っており、表示規制・流通ルールで優位に立つ。
小規模メーカーが参入しづらい基準(安全試験や表示要件など)を維持し、自社ブランドが棚を独占できる状況を制度的に固定化。
消費者影響
P&G製品自体は安く手に入るが、他メーカーを探す場合はAmazonやニッチ専門店へ行かざるを得ない。
このように独占的な供給が固定化され、棚の品目が「最適化」された状況では、当たり前ながら競争が発生しにくい。その結果、商品は改善の圧力を受けず、同じ品質・同じ仕様のまま何年も停滞することはアメリカでは決して珍しくない。
実際、過去を振り返れば、日用品が消費者に対して健康被害や不便をもたらした事例は数多く存在するが、その多くは企業が自主的に改善した結果ではなく、規制当局からの是正命令や強い指導を受けて、ようやく改善に至ったケースがほとんどであった。つまり、市場原理による自然な改善ではなく、外部からの圧力でようやく変化が生じるという構造が繰り返されてきたのである。
このことは、競争が機能していない寡占市場が、どれほど消費者にとってマイナスであるかを如実に示している。しかし日本国内に暮らしていると、日常的に多様な商品が競争的に改良・投入される環境に慣れているため、こうした不便や停滞を実感するのは難しい。
だからこそ本稿では、この疑問に対して一つの答えを提示する意味合いで、アメリカにおける流通事情を整理した。すなわち、「便利さに見える寡占」がいかに消費者にとって選択肢の喪失や改善停滞という不利益をもたらしているかを明らかにするためである。
結論
アメリカにおけるメーカーと小売の関係性を象徴する仕組みの一つが、いわゆる 「カテゴリーキャプテン制度」 である。これは、ウォルマートのような巨大小売チェーンにおいて、特定のカテゴリー(洗剤、飲料、菓子など)の棚割りを事実上、大手メーカーが決定できるという仕組みである。たとえば洗剤ならP&G(タイド)、飲料ならコカ・コーラといった具合に「カテゴリーキャプテン」が任命され、棚の陳列やSKU構成にまで強い影響力を持つ。
さらに、大手メーカーは自社の優位性を守るために積極的なロビイングを行い、規制当局(FTCやDOJなど)がこの仕組みを「不当な競争制限」と認定しないよう働きかける。その結果、制度的にも政治的にも大手メーカーによる棚支配が黙認される傾向が強い。
こうして生まれるのが、「見かけ上は商品が溢れているが、実態はごく限られた選択肢しか存在しない」という消費者体験である。棚一面に数十種類の商品が並んでいるように見えても、そのほとんどは同じメーカーのブランドのサイズ違い・香り違いにすぎない。
この状況は一見「資本主義的な豊かさ」に映るが、実際には「社会主義的な画一性」に近づいているという逆説をはらんでいる。つまり、資本主義の競争が極端に進みすぎると、逆に市場が単一化し、消費者の選択肢が奪われるのである。そして、この矛盾を構造的に維持しているのが、まさにロビイングと大手小売の力学なのである。これがまさに本稿において一番言いたかったことであり、アメリカにおいて商品が一見多いけど種類は多くないというのは気のせいではなく必然性だと言える。
5. ネット小売店の台頭
その中において、Amazonをはじめとするネット小売店が台頭した理由は、既存の大手三社(Walmart、Target、Costco)が築き上げた寡占状態を正面から突き崩すことができなかった領域を貫いた点にある。Amazonは、検索機能を通じて消費者に「選択の自由」を提供し、大手三社が取り扱わない商品やニッチな商品をも消費者の手元に届けることを可能にした。この「多様性へのアクセス」がAmazonの最大の強みであり、従来型の寡占小売に欠けていた部分を補完した。
では、なぜAmazonがアメリカで生まれたのか。それは必然であったといえる。アメリカ小売市場は、数社の巨大チェーンが流通を支配し、効率性と低価格は実現したものの、消費者の選択肢は大幅に制限されていた。Amazonはこの「独占的供給網の閉塞感」を打ち破るイノベーションであり、資本主義的な競争を再び市場に持ち込む存在だったのである。*16
逆に言えば、なぜAmazonが日本で生まれなかったのかという問いに対しては、単純に「その必要がなかったから」という結論に帰着する。日本の小売市場は、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、百貨店など多様なプレイヤーが乱立し、競争が激しい。国土の狭さと高人口密度、そして多層的な流通網が組み合わさることで、全国的な寡占状態が生まれにくく、消費者はすでに日常的に多様な商品へアクセスできていた。さらに、日本の卸売業者は中小小売の存続を支え、小規模チェーンや地域スーパーを市場に残す役割を果たしてきた。これによって「多様性を維持したまま競争を促す」という構造が守られ、消費者にとっては選択肢が豊富であり続けた。つまり、アメリカにおいてはAmazonが消費者の自由を回復させたが、日本においてはすでに「実店舗の多様性」という形で消費者の自由が確保されていたのである。アメリカでは寡占小売が選択肢を奪ったが、日本では消費者がすでに多様な選択肢を享受していたため、「検索による新しい選択肢の解放」というAmazon的イノベーションの必然性が低かったのだ。
また、地理的要因も見逃せない。日本の都市は商圏が小さく、駅前や住宅地ごとに店舗が必要とされるため、アメリカのように「一店舗で半径50kmをカバー」といったモデルは成立しにくい。結果として、多店舗展開しても全国的寡占には至らない。これに加え、日本の消費者は「新商品」「地域限定」「季節限定」といったシーズナリティ重視の購買行動を取る傾向が強く、アメリカのように一年中同じ商品を陳列し続けるだけでは支持を得られない。
例えばアメリカにおけるAmazon Primeの価格は、2022年に年会費 119ドルから139ドルへ 引き上げられた。日本と比較すれば割高に映るが、アメリカの消費者にとってPrimeはもはや「便利なオプションサービス」ではなく、生活必需的インフラに近い存在となっている。言い換えれば、Primeは単なるサブスクリプションというより「実質的な税金」とも形容できる。ウォルマートやターゲットといった大型チェーンが唯一の購買先となる地域では、そこにない商品を確実に手に入れる手段としてAmazonが不可欠であり、Primeに加入しなければ日常生活そのものが不便になる。
この「なくても困らない」レベルの日本と、「なければ死活問題」レベルのアメリカという立ち位置の違いこそが、Amazonがアメリカ市場で価格を容易に引き上げられる背景である。消費者が選択肢を奪われているからこそ、Prime料金の上昇は事実上受け入れざるを得ない。それは、消費者行動にとってほとんど不可避の「固定費=生活コスト」の一部に組み込まれてしまっているからである。
日本ではしばしば悲観論として、「なぜ日本からAmazonのような企業が生まれなかったのか。それは日本が遅れているからだ」「イノベーションが育つ土壌が教育に欠けているからだ」といった国家論や教育論に帰結しがちである。しかし実際のところ、イノベーションは教育水準や国家の気質以前に、そこに切実な必要性が伴うかどうかで決まる。特に需要側、すなわち消費者の視点から見れば、日本はすでに日用品やサービスにアクセスできる環境が充足していた。コンビニ、スーパー、ドラッグストアが過剰なほど存在し、必要なものは「近所で、すぐに」手に入る。この状況で「Amazonを使えばもっと便利になりますよ」と言われても、消費者にとっては「すでに十分便利なのに、これ以上何が必要なのか」というハテナ感が生じる。
アメリカの地方都市や郊外では事情が大きく異なる。生活圏が広大で、最寄りの大型スーパーまで50 km以上、場合によっては100 km以上という状況も珍しくない。実際、USDAの「Food Access Research Atlas」では、農村地域において「住民の 33 %以上あるいは人口500人以上」が最寄りスーパーマーケットから10マイル(約16 km)以上離れている区域が“低アクセス(Low-Access)地域”と定義されている。*15 *18 そうした地域では、小売インフラが脆弱で、身近な購買先がウォルマートのような大型チェーン1社しか存在しないことも少なくない。実際Amazon自身も、2025年までに4,000を超える小都市・農村地域で即日/翌日配送ネットワークを拡大する計画を打ち出しており、地方顧客向け物流強化に40億ドルを投じる方針を公表している。*19
結論として、両者の違いは 「あったらうれしいもの(Want)」なのか、 それとも 「必要不可欠なライフライン(Need)」なのか にある。Wantにとどまる日本のAmazonと、Needを満たすアメリカのAmazon。その立ち位置の違いこそが、両国におけるAmazonの存在意義を決定的に分けている。Amazonは、アメリカ市場において寡占による商品選択の制約という構造的問題に対する「必然的な打開策」として誕生した。しかし日本には同じ問題が存在しなかった。これこそが、両国の小売市場における決定的な差異である。
6. イオンとアメリカの大型スーパーの違い
よくある反論として、「日本のイオンだって、アメリカのウォルマートのように独占しているのではないか」という声がある。しかし、筆者が日米両方に暮らして導いた結論は、日本のイオンとアメリカのウォルマート(あるいはターゲット、コストコといった大型スーパー)は根本的に異なる存在である、というものである。
まず、日本の地方都市や郊外では人口密度が低く、商圏が広いため、大型モールを1つ建設すると、その地域の購買需要をほぼ一手に引き受けることになる。結果として「その町ではイオンしか大規模な選択肢がない」という状況は確かに生まれやすい。だがこれはあくまで地域寡占であり、全国規模で見ればイオンは数あるプレイヤーの一つに過ぎない。セブン&アイ、ライフ、イトーヨーカドー、地方スーパー、さらにはコンビニ各社が競合しており、アメリカのように全土を数社で分け合う構造とは大きく異なる。
言い換えれば、アメリカは例外的な地域を除けば、基本的に「セブン&アイもライフもコンビニも存在しない市場」を想像すると理解しやすい。つまり、多様な小売フォーマットが存在せず、ほぼ数社の大型スーパーが全土で支配力を持っている状態である。対して日本は、都市ごと・商圏ごとに異なる事業者がひしめき合い、全国規模での絶対的寡占に至らない市場構造となっている。
さらに、事業形態の違いも見逃せない。イオンは総合スーパーにとどまらず、ドラッグストアや食品スーパー、金融サービス、映画館などを抱き合わせたショッピングモール複合体として展開している。一方でウォルマートやターゲットは、基本的に「小売業」そのものを中核としたビジネスモデルであり、事業の射程が異なる。イオンの「地域生活インフラ」としての存在感と、ウォルマートの「全国規模の価格破壊型小売」としての存在感は同列には論じられない。
加えて、東京・大阪・名古屋などの大都市圏ではイオンのシェアは必ずしも圧倒的ではない。ライフ、西友、東急ストア、百貨店、さらにはコンビニ各社が混在し、競争は依然として激しい。結果として、日本においては「一社が全国規模で完全独占する構図」は成立していない。
簡単に言えば、日本のイオンは人口減少や商圏規模の特殊性から生じた「地域寡占」現象であり、アメリカのウォルマートはM&Aや物流網支配を通じて競争を排除した「全国的寡占」現象である。つまり、「マクロ的要因による結果的独占」と「経済的手段を駆使した意図的寡占」という点で両者は本質的に異なるのだ。
7. 消費者への弊害
ここまで競争の重要性について熱を込めて語ってきたが、では具体的に寡占状態がもたらす弊害とは何か。第一に挙げられるのは、商品の選択肢が著しく狭まることである。
アメリカの大手小売は、自社にとって確実に売れる「定番商品」に仕入れを集中させる。その結果、日本のスーパーで見られるように「メーカーAの○○、メーカーBの○○、メーカーCの○○」といった多様な陣列は消え去り、「メーカーAの製品だけが棚一面を埋め尽くす」といった歪な光景が広がる。要するに、見た目には商品が大量にあるように見えても、実際には同一メーカーの同一商品ばかりが並んでいるという「商品の不在」が起きてしまうのだ。
消費者が別のメーカーの商品を求める場合、Amazonなどオンラインで探すか、あるいはニッチな専門店まで足を運ばなければならない。これが消費者にとっての最大の不便であり、寡占の弊害である。もちろん、大手小売の立場からすれば「価格を安く提供できる」というメリットはある。しかし同時に、棚から「面白さ」「多様性」が失われ、消費者にとっては安さと引き換えに“楽しさ”を失った買い物体験になってしまう。
興味深いのは、こうした状況がアメリカ社会主義的な様相に近づいて見える点である。小売大手3社が「売れる品目」をコントロールすることで、表面的には豊富な在庫があるように見えても、実際にはほとんど同じ商品しか選べない。言ってみれば「資本主義の極限」が「社会主義的な単一化」に転化するという逆説的現象である。薬といった人体に必要不可欠な商品に関してもこの資本主義が適用されており、必要なのに商品がない、特定の眼鏡がないといった、社会主義に見られる不思議な現象が資本主義大国アメリカにおいても再現される。
食品、薬、本、日用品、服等、人間に必要不可欠なものが寡占により独占供給になると慢性的に不足するということになるという、売れるものしか売らないという弊害が起きてしまうのがこのアメリカなのである。
だからこそ、アメリカ人が日本に来てドン・キホーテやヨドバシカメラ、コンビニを訪れた際に感激するのだろう。そこにはメーカー同士の商品が並び立ち、互いに競争し合う「多様性のショーケース」が存在する。日本では日常であるこの風景が、寡占化したアメリカ人の目には驚きをもって映る。
結局のところ、資本主義が極限まで突き進むと、逆に社会主義に似た構造を帯びてしまう。これが、寡占が消費者にもたらす本質的な矛盾であり、競争の欠如が引き起こす最大の弊害なのである。
8. まとめ
なぜ本稿でこのトピックを取り上げたのか。それは、日本社会に根強く残る「アメリカ=先進的で優れている」という漠然とした憧憬や、表層的理解に基づいたアメリカ礼賛に対して、批判的な視点を投げかける必要があると考えたからである。資本主義の極致は必ずしも消費者に恩恵をもたらすわけではなく、むしろ過剰な競争を排除し、ロビイングなどを通じて規制回避を図る「最適化された独占」の姿を示している。
近年、日本でもアメリカの長所と短所を冷静に捉える傾向が出てきたが、それでもなお「競争は非効率だから、むしろ2〜3社に統一した方が合理的だ」といった意見が一定数存在することに、私は強い違和感を覚えてきた。競争があるからこそ商品は改良され、価格は抑制され、消費者は多様な選択肢を享受できる。これを当然視しているからこそ、「選択肢を減らせ」という発想が生まれるのだ。
果たして本当に消費者は「便利そうに見える寡占」を望んでいるのだろうか。本稿はその問いに対し、アメリカの小売構造を例に「競争を失うことは消費者の利益を奪う」という逆説を示した。私たちは経営者ではなく消費者であり、選択肢が多いことこそが豊かさの象徴である。
この30年、日本では経済停滞とともに「選択肢は少ない方が良い」というミニマリズム的な発想が広がった。しかし帰国子女としてアメリカの不便さを経験した身からすれば、それは「選択肢の多さに慣れたからこそ言える贅沢な錯覚」にすぎない。実際には、多様な選択肢があることこそ人間の生活を豊かにし、消費者に最大のメリットをもたらしている。
外食市場や決済手段を見れば明らかなように、プレイヤーの多さこそが価格競争と品質向上を生み出す。逆に「選択肢を減らせ」という言説は、競争を避けたい供給側の論理にすぎない。本稿を通じて伝えたいのは、消費者にとって選択肢の多さは無駄ではなく、むしろ最大の恩恵であるということである。
一方ではアメリカでは資本主義の成熟化の帰結として、商品バリエーションの削減や品目不足といった現象が進んでいる。必要な時に必要な製品が手に入らないという経験は、まさに「競争の不在」がもたらす弊害であり、そこから得られる消費者利益は極めて限定的である。また様々な商品の競争があるが故、商品開発や商品の品質向上が見込められるのであり、アメリカのように商品がひたすら改善もなく停滞する状況が何十年も続くといったまるで社会主義的な状況に陥ってしまうのを防ぐのがこの競争なのだ。
したがって、本稿の目的は単にアメリカの小売事情を紹介することではなく、競争が働いている市場がいかに消費者にとって健全で、豊かであるかを再確認することにある。極端な意見に惑わされるのではなく、競争がもたらす価値を改めて問い直す意味において、今回のアメリカにおける流通事情の考察を提示した次第である。
9. 脚注(例示)
*1INFORMS PubsOnline, Category Captainship and Antitrust Issues in Retailing(カテゴリー・キャプテン制度が競争排除を招くリスクを論じた研究)。American Antitrust Institute, Category Captains and Antitrust Concerns(法経済的視点からの分析)。
*2 Rob Innes, Slotting Allowances and Retail Assortment Choice(スロッティング手数料が小売の品揃え選択に与える影響を示した理論研究)
*3 Assortment Choice by a Dominant Retailer(支配的リテーラーが戦略的に浅いアソートメントを選択するインセンティブを分析した研究)。ResearchGate.
*4 Assortment Reduction, Demand Shocks, and Consumer Welfare(需要ショックによる小売の品揃え削減が消費者厚生に与える影響を実証的に分析した研究)。Wiley Online Library
*5 The Impact of Walmart Supercenter Entry on Market Structure(ウォルマート・スーパーセンターの参入が既存店の収益を押し下げ、市場集中を進めることを実証的に示した研究)。Duke University Economics Department
*6 McKinsey & Company, Private Label Growth and Assortment Rebalancing(プライベートブランド拡大がナショナルブランドの棚を置き換え、実質的な品揃えの多様性を縮小させることを指摘)
*7 JETRO「米国小売市場に関する統計」2025年予測値より。
*8 Magestore Blog “What is Cross Docking?” (2024) 参照。
*9 全日本物流ネットワーク「共同配送の仕組み」解説。
*10 UniAthena “The Walmart Japan Saga: What Went Wrong” (2023) より
*11 Walmart Annual Report 2024。
*12 Mankiw, N.G. Principles of Economics (Cengage Learning, 2021).
*13 総務省統計局「サービス産業動向調査」(2023年)。
*14 Jackson, K.T. Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States (Oxford Univ. Press, 1985).
*15 Walmart Annual Report 2024, および USDA Economic Research Service “Food Retailing and Wholesaling” (2023)。
*16 Schumpeter, J.A. Capitalism, Socialism and Democracy (1942) における「創造的破壊」の議論参照。
*17 Stone, B. The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon (Little, Brown, 2013) — Amazon誕生の背景と、既存小売寡占への挑戦について。
*18 米国農務省経済研究サービス+1
*19 Amazon “Amazon’s investing $4B to expand its rural delivery network” (2025年4月30日)

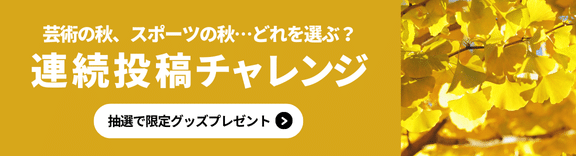
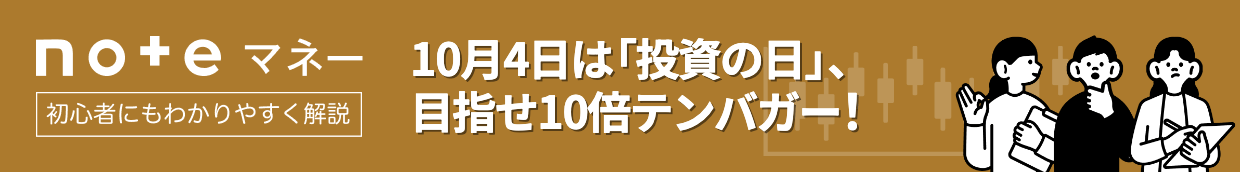


品揃えがすごい勢いで減っていて、残っているのは同じ製品の味付けやサイズのバリエーションばかり、というのは最近SNS等でよく言われているようで、実際のところ、小売り側だけでなくてメーカーのほうもかなりの勢いで減らす方向です。 Stores don’t sell your favorite product anymore. That’s…
ウォルマート1店舗のSKU数は10万以上といわれています。日本の食品スーパーは1万SKUs程度。アメリカの方が選択肢が多いですよ。
事実、ウォルマートが日本で西友を買収した際も、複雑な日本の流通網や卸との関係性をうまく扱えず、最終的に撤退に至った。 日本の流通網の複雑さは、外国企業が日本企業を買収することを防いでいるんですね。
アメリカ礼賛の否定という観点からみればこのような側面もないとはいえないが、チェーンストア理論関連の書籍を読んでいただければもう少し日米の流通業の違いの理解が進むかと思います。