米空軍は2019年「B-21に空対空戦闘能力をもたせる」と言及していたが、Air&Space Forces Magazineは29日「空軍は数十発の空対空ミサイルを搭載した全翼機を制空戦力の一翼に加える可能性を検討中」「このプラットフォームはB-21をベースとしている可能性がある」と報じた。
参考:Why Anduril, RTX are pushing new ground-launched munition variants
戦場で誰が何の役割を担うのかという古臭い概念に基づいて任務を割り当てる時代は過ぎ去っている
米空軍は2019年「B-1BやB-2Aの後継機として開発しているB-21は戦闘機が備えているのと同等の空対空戦闘能力を備えている」と述べていたが、Air&Space Forces Magazineは29日「空軍は数十発の空対空ミサイルを搭載した大型全翼機を制空戦力の一翼に加える可能性を検討している」「このプラットフォームはB-21をベースとしている可能性がある」「まだ構想は初期段階でB-21の生産能力も限られているため他の企業が開発に参入する可能性もある」と報じた。

出典:Northrop Grumman B-21
米空軍はB-21に空対空戦闘能力をもたせることに言及したものの、実質的には2024年まで説得力のある議論は行われておらず、この状況が一変したのは2024年夏に実施された軍事演習(2035年頃に米軍と中国軍が衝突するシナリオ)において米太平洋軍が空対空戦闘能力を備えたB-21の配備を要請した為で、戦略爆撃機を運用する地球規模攻撃軍団はB-21の取得数が限られているため米太平洋軍の要請に抵抗感を示したが、台湾が位置する中国沿岸部での戦いにおいて米軍の不利は明らかだ。
中国軍が沿岸部の基地を起点に大量の航空戦力を容易に動員できるのに対し、米軍が台湾周辺に航空戦力を展開させるには大規模な後方支援が必要になる上、接近阻止・領域拒否に基づく長距離攻撃能力の強化によってグアム辺りまでの地上インフラが開戦と同時に破壊される可能性があり、台湾周辺まで長距離飛行で航空戦力を展開させるには大規模な空中給油が必要で、さらにF-22やF-35といった第5世代機はステルス性能を維持するため兵器システムの運搬量が少なく、交戦空域で発揮できる射撃量で米軍は中国軍に相当劣っている。

出典:U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Lauren Cobin
さらに米軍当局者は「大量の労力とコストを投じて交戦空域に運搬した空対空ミサイルを吸収するため、中国軍は無人機に改造して第3世代機のJ-7を相当数を展開させてくる」と予測しており、最近開催された空軍の上級会議でも各指揮官は「そもそも戦闘機とは何なのか」という問が投げかけられ、ある指揮官は「F-15Eを操縦したキャリアの中で最も多かったのは爆撃任務だった」「それなら私は戦闘機ではなく爆撃機のパイロットだったのか」「戦場で誰が何の役割を担うのかという古臭い概念に基づいて任務を割り当てる時代は過ぎ去っている」と述べた。
ミッチェル航空宇宙研究所も「台湾を起点とした中国沿岸部での衝突において最も不足しているのは武器ではなく武器を運搬するプラットフォームだ」と指摘し、米空軍はF-22、F-35、F-47、CCAが前方空域に侵入して目標を検出し、後方に展開するステルスに優れた大型プラットフォームが目標を攻撃することを検討し、その脈略で「B-21もしくは派生機、B-21とは異なるプラットフォームの活用が浮上している」という意味だが、これは構想の初期段階なので「何かが確定している」という話でもない。

出典:General Atomics Aeronautical Systems
要するにF-22、F-35、F-47に随伴するCCAは有人戦闘機の追加弾薬庫として機能するものの「戦闘機と呼ばれるプラットフォームで中国沿岸部の交戦空域に運搬できる空対空ミサイルの量では足りない」「もっとも根本的な解決策が必要になる」「戦闘機と呼ばれるプラットフォームだけに空対空戦闘を割り当てるというのは時代遅れ」「プラットフォームの名称ではなく能力によって任務を割り当てるべき」となり、もうパイロットが目視距離で腕を競う空中戦など時代遅れで、目標の検出能力と武器の運搬量で制空戦力を再構成するべきだと言いたいのだろう。
因みに第5世代機と第6世代機を区別する能力の定義について様々な意見があるが、恐らく第6世代機を象徴する最も重要な能力は「第5世代機よりも優れたステルス能力」ではなく「自機や他機が収集したデータをリアルタイムで統合し分析しパイロットに供給する情報処理能力=戦場認識力の拡張による戦闘効率の向上」で、第6世代機は膨大なデータのリアルタイム統合能力で第5世代機とは比べ物にならない戦場認識力を獲得し、通信が保証されない競争が激しい環境下でも自機を起点とするローカルネットワークを構築し、見通し通信で制御するシステム単位の能力を維持できる点が第6世代機と第5世代機の決定的な違いだ。
関連記事:中国、無人化した低コストの戦闘機「J-7」を飛ばして台湾空軍の負担増を狙う
関連記事:第5世代機と第4.5世代機の生産が順調な中国、今年中にJ-7が退役
関連記事:戦闘機を撃ち落とす爆撃機?B-21は空対空戦闘が可能
関連記事:GA-ASIが開発を進めるLongShot、制空権獲得に革命をもたらす無人迎撃機
関連記事:GA-ASIがLongShotを受注、第4世代機や空対空ミサイルの交戦範囲を拡張
関連記事:米GA-ASI、複数の空対空ミサイルを運搬可能なLongShotのフェーズ2に選定
関連記事:米軍、複数の空対空ミサイルを運搬可能な空中発射型UAV「LongShot」開発を発表
関連記事:これは無人戦闘機?ノースロップ・グラマンが空中発射型UAV「LongShot」案を公表
※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force





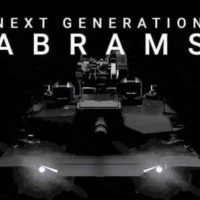













あくまで前衛後衛に分かれるだけでやる事は皆マルチロールってのがこれからの時代か
B-1BにJASSM-ERが台湾戦の切り札って言われたし、空対空でも同じ事が要求されて当然ってわけね
LRASMでしたか
いや同じ様なもんだからセーフ(オイ
レーダーで補足できる相手であれば空対空ミサイルを発射さえ出来れば後はミサイルの仕事ですし用は足りると。
しかし、お互いにレーダーに映りづらいステルス機同士であった場合って、空戦ってどうなるんでしょうか。
お互いに見つけられないから偶然の遭遇戦意外に空戦が発生することがなくなるんでしょうか。
衛星からの監視がメインになるのかも
今はaiで見分けや補正も出来るし、よっほど厚い雲で無い限り視界が途絶えることもないだろう
B-21のプラットフォームを利用した、大型のミサイルキャリア=新型戦闘機ということかな。
第3世代戦闘機を無人機に改造して、飽和攻撃してくる中国空軍を想定した、対抗策ということになりそう。
大量のミサイルとドローンに守られた、大型全翼機・・・・・
なんか、そういうのが好きな人が、開発陣に混じっていそうな気がする。
マクロスプラスでYF-21の評価試験時にいた、ミサイル搭載したターゲットドローンの母機だったウイングスロップ SB-10/10 スターウイング想像した
戦闘妖精 雪風のフィリップナイトとかも入れていいなら、時代が追いつくのに半世紀かかったか・・・・ と思ってしまう。
「FLIP」KNIGHTね。
中国のJ-36と似たようなコンセプトですね
あっちもタンデム複座でかなりの大型機のようですし
B-21をCCAの管制母機にするにしろ、B-21自体にミサイルプラットフォームとしての能力をもたせるにろ、当初の計画からブレブレなので開発現場が死にそうになるのでは
米軍が台湾有事に能力を最適化しようとするのはあんまり良いこと
ではないのではないか、という気がする。
要するに色々なシンクタンクとかが研究して分かったのは遠くから
戦うのは効率が悪いってただそれだけの事やんな。
B-1BがLRASMを抱えて海峡に突撃するより今すぐ台湾の対艦SSM
を増やした方が現実的では?安いし生存性もマシ。
後は一段後ろにいる日本フィリピンもSSM中心の態勢にすれば貢献できる。
要するにわざわざ遠くからやってくる米軍を主力にしようとするのが
そもそも間違ってて、如何に現地で戦うか、米軍を関与させないかが重要。
アメリカは外洋を制圧することに集中すべきであって、地域大国のホームグラウンドで
戦うのは協力者に任せた方が良いと思う、お互い得意なことに集中するべきでしょ。
低価格巡航ミサイルという別手段も考えてはいると思いますが、思惑が色々あるのでしょう。
さすがのアメリカ軍も距離の暴威には抗えませんからね
ただアメリカ軍としては国益が絡むので
何らかの形で関与していたいのだと思います
それに中国はもちろん、中国の脅威を感じている国に
アメリカは直接関与しませんよ、という誤ったメッセージを
与えることを何より恐れているのではないでしょうか
飛行コストは凄そうですね、ステルス機ならではの補修作業に稼働率…
B-21のように、アメリカ本土の基地から世界中に出撃するのか?
もう「A」「B」「F」見たいな区分けは意味を成さなくなってきているって事でしょうか
B-21を空中戦にって、もはや空のアーセナルシップ
大量のミサイルを持って早く戦域へ駆けつけ、大量のミサイルを敵に投げつけて、終わらなければ早く帰還してミサイル再装填して戦域へトンボ帰り、これを勝つまで繰り返し
確かにドッグファイトは過去の物…
ナイトレーベンだ!ナイトレーベンが良い!
全く同じこと考えてたw
全翼複葉機はロマンあるし旋回性能も倍や
ふふふ、やはり時代は空中巡洋艦。やっと時代が私に追いついたか。
VLS載っけて散弾ミサイルを搭載しよう(彼は疲れていた)
ネタにマジレスすいませんが常に水平方向に高速移動する固定翼機から「VL」する意味ってあるんですか…
下方向にバーティカルとかっすかね
下向きでもあんまり変わらないかな。
長物を垂直方向に配置する時点で空力的に邪魔くさいし、
下向きに射出した瞬間、射出体は亜音速の「横風」を喰らう訳です。
雲の上はいつも晴れだから、レーザとかもロマン溢れるますね。
地上に向けて撃つから話は全然違いますが、ラピュタを思い出した笑
うろ覚えですがそのまた昔、B-1でも似たような構想があったような…。そのころはAWACSから目標指示されるのでAAMをたくさん積めるミサイルキャリアー(大規模戦限定)という印象でしたが。
「高強度の電子戦下での情報統合ネットワーク構築機が第6世代」という定義はB-21でも当てはまる、ということですね。
管理人さんも過去に記事にしていましたが、当時より具体化・理解しやすい形になった印象です。
リンク
何故かB-17のガンシップが頭に浮かんだ。
あれはどっちかというと爆撃機の護衛なんだが···何故だ
・ハイエンド兵器から無人機を利用したローエンド兵器へ。
・電子戦環境下で通信が途絶えたとしても自機を中心としたローカル通信の確保。
・ローカル環境下での作戦行動のための、戦力細分化と柔軟な部隊構築。
・ローカル環境下のために情報の中央集中ではなく部隊運用。
・ローカル環境下での高度かつ高速な指揮・統制のためのAI。
・モザイク戦において、多くの機体を運用し、敵のOODAサイクルを妨害・遅延しながらも、自軍はOODAサイクルを高速で回す。
・多数の機体から得られたデータを高速・高効率で処理しOODAサイクルを高速化するためのAI。
これらは、米軍の2020年の「Center for Strategic and Budgetary Assessments」という報告書にありました。
このためには、
・低コストの無人機と自律飛行のためのAIの開発。
・多数の機体運用による情報優位と膨大な情報を処理、指揮・統制のためのAIの開発。
・膨大な情報とAIを扱うための発電能力を持ったプラットフォームの開発。
GCAPの開発方向がこれらに沿っていて安心しています。
中心機の航続距離の増加、ミサイルキャリアーを念頭に置くと、高機動性より機体の大型化するのは理解できます。そうするとFCASはどういった運用を想定しているのでしょう?
また、同じ戦術国同士の戦闘において、互いに無人機を先行させることになると思います。そこで、互いに発見し合い撃墜、互いに無人機を消耗し合う。最終的に有人機が取り残される。結果、この戦闘は、1部隊の機体数がより多い方が勝つということでしょうか。
B–21がどれほどの機動性や速度を持っているのか私は知りませんし、また、それらが第6世代戦闘機においてどれほど必要とされるのか分かりませんが、もし、合致するならば、この話は「B−21型のプラットフォームを元にした第6世代戦闘機の開発」がしっくりきます。
上記の戦闘において、ローエンド兵器(無人機)を統合、指揮・統制を行うために中心に存在するのが第6世代戦闘機の役割といえます。
その時、Bー21を単に空対空性能を付与した「マルチロール機」として「ミサイルキャリアーの有人機」としてこの部隊ネットワークに組み込み、第6世代戦闘機と同等以上のステルス性やそれ以上の大容量性を持つ超高価な機体を単なるミサイルキャリアーとして扱うより、「ローカルネットワーク構築能力」や「膨大な情報の処理能力と高度かつ高速な指揮・統制のためのAI」を付与して中心機として扱う方が、上記のローエンド戦闘方針に合致しますし、戦力の効率化・増強に寄与すると思うからです。
私は米空軍関係者ではないので部外者の素人の勝手な妄想となりますが。
第6世代機は処理する情報量的に複座が基本になるのかな?
勝敗に関しては無人機を操るソフトウェアの出来次第になりそう
最低限戦場でミサイル撃てれば及第点だけど、生還して再利用させるんなら撃たれたときの回避とかもプログラムで組まなきゃ駄目だもんな
でも人が乗らない分無理も出来るから、一気に空戦の技術が跳ね上がるかも
AI次第かな
「情報を分析・処理し、必要な情報のみをパイロットに表示する」の高度なAIが開発できたなら単座だし、AIの能力が限定的なら複座でしょう。
「膨大な情報を分析・処理」は間違いなくAIを利用するでしょうから、その延長上で情報関係は全てAIに任せたいのが理想でしょう。
そもそも米軍は、OODAループにAIを利用し、サイクルの高速化、戦術の複雑さを生み出し敵のOODAループを阻止、遅延をさせたいようなので、AIを頑張ると思います。
イメージ的にはアイアンマンのジャーヴィス位のレベルで、作戦やCCAや自機の機体、ソフトウェア制御を任せられるaiが出来ればって事か
まああそこまで人間味がある必要は無いけど、中々に未来感がある話だな
「将来の技術を楽観視できる」状況ではないので。当初は複座可能な機体設計で出し、最終的にはAIが副操縦士や兵装システム士官、さらには機長を代替する形で段階を踏んで実施していくのが現実性の高いプランではないか、と思ってますが、無人機ならレイアウトの自由度が高いのも悩ましいですね。
ガンダムのエルメスのような感じ。
ニュータイプはいないので母機に無人機を操る人員を複数人数乗せるなら合理的。
ブラウ・ブロはパイロットを複数乗せればNTでなくても操縦と攻撃が可能だったな
損失が絶対に許されない超高額大型ステルス機に空戦してこいなんて言えるのかな
相手もステルス機なのにどうやって把握するのか
露払いの無人機大量にばら撒いて安全確保するなら射し世から大量の無人機でいいよねってなるだけでは?
しかもミサイルの足は敵の方が圧倒的に勝っているというのに
迷走してるなあ
もうF-35はやめたほうがいいのか
対露であればF-35で、というか4.5世代の戦闘機でも十分な気はするが
まだまだ仕事はあるかと。
無人機を自律飛行させるとしても、最終的なミサイル発射は人間の許可制になると思われるので、有人機1機に対し無人機2、3機でしょう。
第6世代機1機と無人機2、3機では効率が悪いように思えます(コストと得られる戦力で)。それより、1機の第6世代機に対し複数の第5世代機とそれぞれに無人機が2、3機の部隊を組む方が効率的です。
第6世代機の役割は「電子戦下でのローカルネットワーク構築」「膨大な情報の処理とそれに基づいた高度かつ高速な指揮・統制」。部隊内の有人機と無人機は第6世代機の情報と指揮の下戦闘を行う。
上記の役割は第5世代機にはできないものですが、ステルス性や無人機随伴能力は第5世代機でも獲得できます。手持ちの戦力の最大化とコストを抑制には、第6世代機のネットワークに第5世代機を組み込むでしょう。
まだまだ仕事はあるかと。
無人機を自律飛行させるとしても、最終的なミサイル発射は人間の許可制になると思われるので、有人機1機に対し無人機2、3機でしょう。
第6世代機1機と無人機2、3機では効率が悪いように思えます(コストと得られる戦力で)。それより、1機の第6世代機に対し複数の第5世代機とそれぞれに無人機が2、3機の部隊を組む方が効率的です。
第6世代機の役割は「電子戦下でのローカルネットワーク構築」「膨大な情報の処理とそれに基づいた高度かつ高速な指揮・統制」。部隊内の有人機と無人機は第6世代機の情報と指揮の下戦闘を行う。
上記の役割は第5世代機にはできないものですが、ステルス性や無人機随伴能力は第5世代機でも獲得できます。手持ちの戦力の最大化とコストを抑制には、第6世代機のネットワークに第5世代機を組み込むでしょう。
遂にF-111の後継が
アメリカは開発中の新型多すぎて、どれが本命かわかりませんな。
GCAPのデザインの変化を見ていると、当然想定できた話です。
足りないのはスピードぐらいですが、レーダーステルスはもとより、機内容積の大きさや高速性の放棄による赤外線ステルス能力の確保と、大発電力に裏打ちされた対空ミサイルに対する対抗能力(ECM、EMP兵器、レーザーなど)で、生存性を確保するのも考え方の一つです。
GCAPなどの従来型の戦闘機の延長にある機体は、レーダーステルスとハイパークルーズによる時間を味方につける考え方です。どちらも一長一短があり、多分どちらが優れているではなく、作戦目的次第で選択したり組み合わせたりするのが理想なような気がします。
しかし、だんだんコンセプトや戦術上の課題が潜水艦に似て来ていますね、特にB-21規模の戦闘機(戦闘爆撃機)なんて、高度な戦力を持つ敵中で捕捉されたら、まず逃げきれない点とか。(某小説に出てくる、超小型の対ミサイル迎撃ミサイルとか出て来たら別ですが)
コンセプトや概念を考えさせたら、アメリカ人は強いな……
なによりそれを実現していくパワーと体制がある
けど敵を先に見つけて叩く、というのは古今東西変わらない法則だから、基本的な戦略・戦術の思考がしっかりしてるなぁと……
敵ステルス機に懐に入られたらどうする?
大型航空機だけで全部済ませろとは誰も言ってないという事かと
それだと戦闘行動半径がF-35とかと大差なくなってしまいます。
F-35だけで戦うよりはたくさんミサイル撃てる事を追求するならそれでも良いか
>それだと戦闘行動半径がF-35とかと大差なくなってしまいます。
どゆこと?後の文はその通りに思ってるんだけども
あ、ごめん分かった
前線で戦う事の想定か
自分は後方から火力投射する巨大なミサイルキャリアーを想定してた
やはり基本は反撃を受ける恐れの無い環境で運用されるんじゃないかなぁ
輸送ヘリが襲撃を受けたらどうする?→そもそも攻撃される所には飛ばさない、的な解
仰る通りでそれこそ少し前の記事のSlingShotキャリアとかが主任務になるんじゃないですかね。
「空対空戦闘能力」「制空戦力の一翼」であって「戦闘機と同じことができる、やる」とはいってないですし。