金子薫さん「生きようが死のうが、小説のことは放っておく」への応答
応答先の文章はこちら(https://note.com/kaoruknknote/n/n5c9d6be3447a)です。
1.言い訳、弁解
小説のことは放っておくのもいい。
開かれたままにしておけば、生き生きとした作品はひとりでに芽吹き、またひとりでに枯れていく。
正直金子さんの結論とも読める上の一説を私は「信じたかった」と思いました。それも言い訳でしょう。だからこそ金子さんは放っておくの「も」いいとお書きになったのだと思います。
今回の批評を仕上げた段階で私が明確に隙があると考えていたことがいくつかありました。
1.待川匙「光のそこで白くねむる」からの引用を怠ったこと
2. 挑発的役割として「小説のことは小説家にしかわからない」という言説を使用したこと(といっても論争しようとしたわけではなく、これきっかけに読んでくれる人がいたらいいかなと考えていた)
1に関しては複数の要因があるものの、主因となるのはやはり書いている時期の私の怠慢でしょう。いくらでも自身を今回の論旨に導いてくれた魅力的な文章はあったのに、それを引用することを怠ったわけです。限られた紙幅のなかで、はっきりと持論を書くことを優先しました。『新潮』稿はいくつかの条件から、一連の作家論と区別して私の「思い込み」からすべてを書き「思い込み」で終える。だからこそ書けることだけを書く。そう考えていたせいでもあります。これまで書いた作家論に関しては、紙幅の制限もなかったこともあり、引用の枠を多くとっています。当批評企画の第二回目として書いた桜井論に関してはおそらく引用しすぎの範疇でしょう。しかし以前から私の引用態度は厳密ではなく、もちろん「ある程度」は批評的発見に相応しい箇所を切り取る、と同時にたんに「面白い!」と思った箇所を抜き出し持論を書きつける傾向がありました。
2に関しては難しいところです。
一連の「批評」を、私は保坂に倣って「批評」ではない形で書くことが可能でしたし、当初から「批評」を名乗るメリットはとくにないとも判断していました。しかし、金子さんの今回の批判を読んで、私の書いたものが「批評」でなければこれは書かれなかった文章の真価であると思ったし、「小説のことは小説家にしかわからない」を持ち出さなければ、果たされなかった批判だったのではないでしょうか。「批評」とは抑圧であり、抑圧から跳ね返るようなコミュニケーションにその本懐がある、それが私のいまの「批評」観です。この意味で、あくまでも私の狙いとしては「持ち出してよかったな」と思ってしまうわけです。しかし、読者にとっては果たしてどうだったろうか? あるいは「批評」前後の、私の「文章」そのものにとっては? 果たしてよかったのだろうか? 正直いまは分からず、迷っています。
さらに、私が疑問を感じたのは、保坂和志の小説および小説論からの引用も少ないことであり、彼の小説観を基礎として(盲目的に踏襲するにせよ、批判的に継承するにせよ)置いているからには、ここで具体的な検討を怠れば、論考は支えを失ってしまう。また、引用の不足にも増して問題なのは、町屋が保坂の小説観を内面化し過ぎていることの弊害として、町屋の声が保坂の声と混じり、町屋自身の小説観が、保坂の背後に隠れてしまう場面が見受けられることだ。
このご指摘は私が過去の論考のなかで宣言していることではあります。たしかに私は保坂を精読的に読み直すことを怠り、かつて影響を受けた者である自認を宣言したうえで、一連の批評を書きました。とはいえ金子さんがnoteにお書きになった「内面化」という指摘は適切なのか?とは思っています。私がまだ自分の中にうまく定着していない語彙であるせいか、定義としても曖昧に感じる上、当該noteにおいて金子さんがそう断じる論拠は伝わってきません。くわえて、「内面化」に関しては対象、つまり保坂だけではない論者から受けるもの、そしてそれぞれの深さともに複数のグラデーションがあり、また「内面化」というからには書き手が十分には自認しうるものでないようにも思えることから、このご指摘は妥当なのだろうか? そうかもしれないが、よく分からないというのが本音です。
あと「内面化」はだれしもしているのではないか? たとえば金子さんは随筆にお書きになっていた印象ほどにはアントナン・アルトーを「内面化」してはいないのか? 読書においてそこを明確に剥がして読むことが他の人はできているのだろうか、むしろ私は文学においてはだれかの批評を「内面化」している方が好ましいと考えているかもしれない、しかし金子さんは町屋が保坂の小説観を「内面化」し過ぎていると否定的に断じているし、私が特にそうということなのだろうか、だが私は保坂の影響を受けたと自認する者たちの「内面化」可能性とその言説の蓄積と更新のなさを批判してもいるのだが……と素朴によく分からなくなりました。私は私に固有の小説観というものは信じておらず、しかしそれはある種の可能性、多様性の放棄にほかなりません。これは私なりに正当性のあることですが、ここでは金子さんのご批判に関して概ねその通りだと認めたいと思います。
加えて、保坂の影響下にあると書かれている他の作家については、ろくに検証の過程を経ることもなく「現状、磯﨑以外の保坂の文脈にある書き手は、磯﨑以上にこの「読み」の更新を怠っている[10]」と判定されたり、あるいは「このように影響を受けた下の世代が創作面においてはつぎつぎ作品を発表しそれぞれ大きな成果を収めている反面、批評面においてはだれも保坂を乗り越えられる兆しがない[11]」と断じられたりしているが、文学的な影響関係の規定自体に恣意性がつきまとい、説得力のある論拠も示されてはいない。
存命の小説家であり、本人の生の声を聞く機会があったとしても、作品を通してのみ、小説の声を聞くことができる。だが、町屋は肝心の小説の声を閉め出して、その代わりに共同体の内部規範を語っているかのようである。
この批評プロジェクトの目論見は、2000年から2015年までの小説を再読し、失われた批評的な文脈を再構築することで、小説の可能性を信じようとすることにあった。しかしながら、小説の死後にも残る散文の可能性を探究する営みは、いつしか町屋良平の身体という一点にまで収斂している。
町屋が自らに課した意義ある課題は、眼の前に開かれている作品に耳を澄ませることで果たされるべきものであった。硬直した枠組みのなかに絡め取るように読んでしまえば、発せられた声は失われ、思慮を欠く一般化、恣意的に設定された文脈への一方的な回収が行われるばかりだ。
こうして「小説のことは小説家にしかわからない」という命題は、体験に内在するべく深く潜り続けるうちに、知らぬ間に外へと連れ出され、かつて抵抗していたはずの対象、小説を抑圧する力と同一化を遂げてしまった。
とはいえ「抑圧」それ自体は批評そのものが「抑圧」だと考えていることを、今回の『新潮』稿、および上記に書いた通りであります。その「抑圧」が悪質であることを金子さんは指摘され、それは私は現段階で妥当かもしれないと思っています。
保坂論に関しては、金子さんのご指摘通りほんらい膨大な作家の「再読」の要請がありましたが、私は自身の読んできた経験だけで書きました。その方がよいと判断しました。そもそも上にも書いたように保坂以降の作家は実作以外に、若い人の議論の素地となるべき「読み」に導かれるべき素材が弱いのではないか。書かれてこなかったのではないか。とくに保坂の影響が指摘されてきた者が読むものとそれに纏わる言説に、更新がほとんどないのではないか。これを論考では問題視しています。ですが怠慢ととられたらその通りであり、それも「放っておくのもいい」、そう考えるほうが普通だろうと思いますので反論はありません。これが私の「言い訳」となります。
2.反論
金子さんは当該noteにおいて非常に緻密で精確な批判を投げかけてくださっていますが、全体的に仰っている論旨は、私+今回の『新潮』稿が保坂礼賛のために書かれている先入観ありきで読んでいる節をどうしても感じています。深く読み込んでいくと金子さんから町屋への批判は以下の2点に収束するかと思っています。
1.引用を怠っている
2. 今回の『新潮』稿においては、保坂を「内面化」した町屋はじしんの身体、経験にもとづく主観でしか他者の小説を語らない、それでいて一部の読みを悪質に抑圧している。
1.は「言い訳、弁解」の章で扱いました。
ここではおもに2.について反論していきます。
それでは、第1章「保坂和志」において「『弱い人』を他者の言葉で再言語化、規定することの暴力、その上でそれを引き受けること[8]」、ならびに「社会的マジョリティであることを自覚して、言語的マイノリティであることを志向する[9]」といった問題提起をしていた意義が霞んでしまう。
これは果たしてそうでしょうか? 私は上に書いたように実態としては影響を受けてきた保坂を、ほかの批評との関係性を捉え、指摘する読みによって私は自身の「内面化」の「可能性」を剝がそうと試みているのではないか。すでに書いたように「内面化」自体書き手としての私はそう指摘されたらそうかもしれないと思ってしまいますが、実際には今回の『新潮』稿がそれほど保坂が「内面化」されたものの書く文章だったか。2章はたしかに保坂の影響下にあるのは自明でしょう。しかしたとえば青木の『四十日と四十夜のメルヘン』評においては私は少なくとも「作品が発表されてからの22年の時間、なるべくこれまでの論者が書いていないことを」という出発点から書いたものです。正直まったくうまく書けたという手ごたえがあるわけではありません。しかし少なくとも保坂に書けない(書かない)ことを書く、3章にあたる『四十日ー』評においては明確にそこを目標においています。
また、当批評は保坂を批判する立場からすると擁護にうつるが、保坂を擁護する立場からすると批判にうつる、そのように心がけて書いたものです。影響関係を認めた人間として、そうとしかできないし、そういう選択を取るべきだという戦略からです。実際に双方向からの批判が寄せられています。金子さんが本批評に保坂(と保坂に影響を受けたもの)批判の文脈を(ただしこれは奥山さとさんもXで書いてくださったように、批判擁護どちらにせよ「抜本的」ではありません)どれぐらい汲んでお書きになっているのか、そこが不明瞭なのが終始気にかかりはしました。これまで保坂に強く影響を受けた自認の上で保坂を批判した文章の例は、私見ではあまりなかったように考えています。
町屋良平の批評プロジェクト「小説の死後――(にも書かれる散文のために)――」の最終回、「保坂和志、私、青木淳悟」(『新潮』2025年10月号)は、「小説のことは小説家にしかわからない」という、素朴でありながらも閉鎖的なニュアンスを帯びるテーゼが、小説家自身の思考を袋小路に追い込んでいく実演のようにすら見えた。
この言説は言わば小説家にとっての護符である。作品に固有の力を読み取ろうとしない批評による回収や、商品として流通しやすい作品を要請する市場原理から、自分の小説を守るため、時として小説家はこの護符を身につけることがある。
私も装備している。時には確信してさえいる。しかし、この護符の文言を解きほぐしてみれば、「小説を書くのは小説を書くものだけである」という、ある種のトートロジーでしかないことが明らかになる。
「小説を書くのは小説を書くものだけである」または「小説家だけが小説を書くという体験をする」という、ただそれだけの身も蓋もない事実を、町屋が語ったように「小説のことは小説家(としての身体を色濃く経験する批評家)にしかわからない[1]」といった域にまで格上げしてしまうのは、勇み足と言わざるを得ない。
「身体」という語は便利だが、実に曖昧で、適切な内実を伴わせることなく使用されることがある。小説家としての身体を色濃く経験する、という、言語化の困難な内的体験を担保に小説の自由を守るのは無理がある。また、それが発露しているかどうかを基準に、作品を評価することにも慎重さが求められるだろう。言語化が困難な時間が背景にあるとしても、その時間のなかで書かれる文体や構成まで不明瞭になるとは限らない。
いずれにせよ、曖昧なまま拠り所に置かれた「身体」は、言論においてそれほど有効に働かないことがあり、町屋の批評でもその限界が感じられた。
「この言説は言わば小説家にとっての護符である。」
一面的にはたしかにそうでしょう。この言説に含まれる抑圧に、跳ね返される多様性は存在しますし、その実態は金子さんが書かれた論旨の通りです。ここの文脈で「身体」と書いたのも不用意だったと認めます。
しかしこの言説は私の実感的にはまったく「護符」たりえません。もっというと私自身は装備も確信もしておらず、自信がない。正直曖昧です。「小説のことは小説家(としての身体を色濃く経験する批評家)にしかわからない」の(としての身体を色濃く経験する批評家)の部分は「小説のことは小説家にしかわからない」の格上げとは限らず、格下げとも見做されるはずです。4章には小説のことは小説家にもわからないというニュアンスがその前後の議論に組み込まれているはずです。小説家にはわかって「しまう」小説とわからない小説とあるという当たり前のこと。それと小島信夫がかつてそう述べたらしいように、「(自分の)小説のことは小説家(自分)にしかわからない(決定責任が自分にしかない)」という当たり前のこと。それが私の「小説のことは小説家にしかわからない」の、元々の評価でした。
無責任かつ卑劣と思われるかもしれませんが、「小説のことは小説家にしかわからない」というのが金子さんが指摘する何も言っていないようなトートロジーであることは、読者には余さず伝わるものだと私は思っていました。それは、かつてこの言葉に直面した私がそうだったからという予断にすぎないかもしれません。しかし当時もわずかながら読者からの反発および論争はありましたが、(私見では)その実りは乏しいものでした。つまり、私は卑怯なところのある人間ゆえ、この言葉が挑発として機能すると感じたのも、まさにその「中身のなさ」もっと言うと「どうでもよさ」の反復によってでした。現在の小説批評の状況において、もっと論じる価値があり意見の割れるようなことであったなら逆に、反論する人など誰も出なかったのではないかとすら考えています(実際に書いているときにそう考えていました)。中身がなにもないのにもかかわらず、伝わりやす過ぎるから採用したのです。「小説のことは小説家にしかわからない」がどうでもいい宣言であることは既に伝わっているが、だからこそ、さまざまな読者の記憶、経験を想起させなにか「言いたくなる」のにふさわしい言説だからと、『新潮』稿の主旨に合致していたこともあって利用したわけです。「小説のことは小説家にしかわからない」の論争が当時展開された主たる場の移動『文藝』→『新潮』での対談・座談会を、私の批評企画は一部に議論を呼んだ『文藝』での座談会(矢野利裕からのご批判を頂いた場)から『新潮』へと移す。そうした趣旨がおそらく、無意識下にはありました。
金子さんはこれに当初強く反発されました。その反発はnoteにお書きになった論調よりもっと激しく、辛辣なものでした。ゆえに、金子さんが本当に反駁したかったのは、今回noteにお書きになったような内容ではなく、もっと強い動機を伴うものではなかったか。そうでないと不自然に感じる、そう思えたのは事実です。これは今回金子さんがnoteにお書きになったことの正当性を毀損するものではもちろんありません。
しかし、この箇所に見られる美点こそが、その後の議論を綻ばせていく。自分の体験に沈潜し、体験の質を見極めようとする姿勢が、他者の書く小説と出会う際の障壁になっている。私は、小説家でありながら批評を引き受けた町屋の出発点に潜み、終着点において明示的に標榜される「小説のことは小説家にしかわからない」というテーゼが、個別的なテクストを遠ざけ、その批評を鈍らせているのではないかと考える。
もし読む側としてだけなら「わからない」ことがわずかにありうるとしたら、小説家(としての身体を色濃く経験する批評家)でなければわからない具体的なことが微かにあるとしたら、その可能性を新しく考える、『新潮』稿の4章はそれを目標に書きました。なぜなら1章で私は保坂受容の更新の要請を訴えていたからです。当企画一連の論考において私は読者の創造性を書き手の創造性より上位に置く議論を何度か書いてきており、また「小説家」を職業としてのそれ、小説を「書く」者に限って論じていません。くわえて小説読解においてはむしろ小説家のほうが読者より総じて視野狭窄になってしまう宿命についても論じています。この例外的な定義のニュアンスを『新潮』稿では書き落としました。やはり挑発に意識が行っていたのだと思います。『新潮』稿のみを読む読者を意識していたつもりが、それゆえか、手続きに敬意を欠いていました。
ゆえに「自分の体験に沈潜し、体験の質を見極めようとする姿勢が、他者の書く小説と出会う際の障壁になっている。」「私は、小説家でありながら批評を引き受けた町屋の出発点に潜み、終着点において明示的に標榜される「小説のことは小説家にしかわからない」というテーゼが、個別的なテクストを遠ざけ、その批評を鈍らせているのではないかと考える。」の指摘には説得力は感じませんでしたが、実際そう書かれるとそうかもしれない、だが本音を言うとやはり分からないのです。私の実感だけでいうとまったく見当外れにも感じるが、しかしテキストとしてはそう読まれるのが妥当か、などなどと。ゆえにこの期間何度も金子さんの批判に立ち返っていました。それはこれから先もそうなのでしょう。
町屋が保坂和志を敬愛していて、その作品を数多く読み、これまで小説に関する思考を練り上げてきたことは、理解できる。そしてこの批評プロジェクトの源に保坂の小説観があり、それを批判的に継承しようと試みていることも、同様に理解できる。しかし、そうした局所的な言論の場に流通している言説および文脈を前提とする以上、論述を説得的に成立させるには、より明確な手続きを踏む必要があるだろう。
青木淳悟の『四十日と四十夜のメルヘン』といい、待川匙の『光のそこで白くねむる』といい、個々の作品を取り扱うにも拘わらず、相当な量の紙幅が、町屋の受け取る印象や小説にはこうあってほしいという願いの記述に割かれている。
前半の指摘はそうかもしれないと思っています。しかし「小説にはこうあってほしいという願いの記述」が批判に値するものかは正直迷いがあります。批評とはそういうものではないかという楽観性が私の根底にあるからです。私はこの論点においては研究論文と一部分けて考えています。それに思うところがあるなら今回金子さんがされたような批判が寄せられる。基本的にはそういうものと考えています。
構造を整える行為や構築的な工夫にも内在している創造性を、エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属として低く見積り、書くという体験への内在を、書き手の正当性の拠り所に置き換えてしまう仕草こそ、この批評で語られる保坂=町屋的な小説観の最大の欠点であり、それは小説の自由を著しく制約する。
実際、私自身もはっきり「抑圧」と述べた上で『新潮』稿では明確にある種の小説の(読みの)自由を封じようとしていますが、この記述は誤読、というより読解として恣意的なものを感じています。私が書いたのは「エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属」がある曖昧さを突破して、ようするに物語(構造)ありきでしか言葉が存在できないようになっているのではないか、そうすると歴史的に読めない言葉も存在してしまうのではないかというようなことですが、「構造」の定義はもう少し厳密にせねばならず上のようには簡単に纏めきれない論点でありますし、これは読者に判断してもらうしかありません。書き手は「主題」を選べないという立場をとっている私は「エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属」と自身の問題意識をうまく接続出来る人はそうした方がよいと思っています。そして待川作(の後半)も、加えていうなら私自身も、書き手の意思か市場の要請か分からないが、結果的に(あいまいに)その選択を採っている。私はそう考えています。
基本的に「読む」側の自由への問題提起として本批評は書かれています。私の問題意識は「小説」の現場が「エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属」を必須のものとしたうえで、それにそぐわぬ者は同化させられる向きがあるのではないかというものでした。「エンタメ」「物語性」これを私は「構造」「主題」と言い換えることもあります。
以前矢野利裕さんに応答したnoteに書いたことですが、ありふれた歴史観だと思いますが「文学」と呼ばれてきた営みは「エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属」を曖昧に引き受けることが本懐であって、そうできないものも生き延びられる余地がある。むしろそうできないことの「強み」もある。しかしそういう書き手は徐々に減っており、ますます「エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属」が必須であることがなんとなしに強化され続けるのであれば話は違う、そういう主旨です。そうできないならばもっと小規模出版のほうへ行く(それはそれで良いことのほうが現在は多いかもしれませんが、私の立場でそれを肯定するのは違うでしょう)、そんな流れが生まれるのではないか、今後よりそうなっていくのではないかという「思い込み」から端を発した問題意識であるわけで、金子さんの文脈においては私はその方向性へ進む「小説の自由を著しく制約」しようとしています。簡単に言うと、もっと、とりとめもないことを書いてもいい。「必然性」のないこと、構造に寄与しない(と誰かに判断されうるかもしれない)ことも小説は受け容れるんだと、それだけでなくそういうものを含めることが時には良い、強い、面白いんだと、これからも信じてもらいたい(しかしすでに信じてもらうには難しい現状。私はそう思ってますが。私の批評における「死後(にも書かれる散文のために)」という標題にはこのニュアンスがひとつ込められています)。
とはいえ、結果的には私が抑圧したところで、読みの自由が損なわれるなどとは思いません。誰が抑圧したところで、同様に思います。しかし、誰かは書かなければいけないのではなかったか、もっと早く、私はそう考えたから自分で書き始めました。「小説の自由を著しく制約」しようとする言説で却って自由になる人がいる、それはかつての私でした。同様の若い人がいるのではないかと思って書いています。
しかし私は金子さんの読書の一部分を、ロマンシシズム+センチメンタリズムの「巻き込み」として、その発露が時に怒りを伴うことから悪質であることを批判します。すでに同種の批判はXでもいたしましたが、読み落とされたのか、反論に価しないと判断されたのか、noteにてすでに反論を終えたと思われているのか、いまは判然としないため、繰り返します。
ご批判は甘んじて受け止めますし、ご批判の内容について反論はありません。しかし私は連日の金子さんのツイートを拝読して、私が論考のなかで批判した「読みのセンチメンタリズム+ロマンシシズム」の抑圧そのものだな、と批判的にも捉えていますし、それほど新鮮な論点とも考えていません。そういう言… https://t.co/w9AsJWNSTs
— 小説の死後––(にも書かれる散文のために)–– (@shosetsunoshigo) September 12, 2025
反論の最後として、
だが、エンタメ的な「生理」を内包する身体を否定し、「物語」「意味」「メッセージ」の外を切実に信じようとする小説家として、町屋が待川の作品について語る言葉は、町屋の身体というフィルターで濾された印象の再構成であるがゆえ、テクストに存在したはずのニュアンスや差異が削ぎ落とされ、解釈の幅を失っていく方向に収束してしまう。
このように主観的な印象を漫然と語るのは、町屋の批評プロジェクトなのだから自由である。しかし、大きな目標を掲げた上で批評に身を投ずると宣言した以上、せめて小説の言葉とは向かい合うべきではないのか。言語以前の認識や他者との境界の消失を示唆しているが、こうした記述がもたらすのは、あくまで町屋の身体に立ち現れるノスタルジーである。待川のテクストの手触りは伝わらない。そして自分の読みにこれほどの自由を許すならば、他者の読みも断定的に排除することはできないはずだ。
「このように主観的な印象を漫然と語るのは、町屋の批評プロジェクトなのだから自由である。しかし、大きな目標を掲げた上で批評に身を投ずると宣言した以上、せめて小説の言葉とは向かい合うべきではないのか。」「そして自分の読みにこれほどの自由を許すならば、他者の読みも断定的に排除することはできないはずだ。」これはその通りだと認めますが、「言語以前の認識や他者との境界の消失を示唆しているが、こうした記述がもたらすのは、あくまで町屋の身体に立ち現れるノスタルジーである」は誤解に基づく拙稿の矮小化でしょう。
3.-1 批判 待川作読解について
つまり、不明確さにはそれが存在する明確な理由があり、その明確な理由が、不明確な語りをいっそう霞ませていく力をもたらしているのである。ゆえに、曖昧さにこそ価値を認め、前半の描写を小説の本領と断定し、後半を評価する(前半を平板なものと見做す)小川哲の読み方を、物語を求めるエンタメ的な枠組みに依拠している[5]、と言い切るような二項対立に基づく読みでは、あの作品の取り組み、文章と構造、語りと物語の相互干渉を取り逃がすように思われる。
待川匙『光のそこで白くねむる』に関しては私はむしろ、固有名を欠落させつつ語りと世界を曖昧化する手つき、言葉による狂気の演技を楽しみました。不明確さを丹念に追求するために、明確な方法が据えられており、そのねじれこそが同作で遂行された芸であり、私も面白く読みました。
— 金子薫 (@knkkaoru) September 9, 2025
上記が金子さんによる待川匙『光のそこで白くねむる』評、そして町屋の読解批判の一部です。
一方私は荻世いをらを論じた項でこう書きました。
『四十日―』にしても「宦官の授業」にしても、よくぞこの設定を思いつくな……と感服する部分はあるのだが、しかしまずは思いついてもそれを言語で現出させることが至難のビジョンである。だからこそよくぞこの設定を思いつくな……という言い方ができるわけなのでこれは正確ではない。この設定を言語で現出させることができた、結果的に表現することができたからこそそれが設定に成ったのだから。厳密には小説を書きつけ散文を増幅させるうちに同時に生成される〈設定〉〈ビジョン〉なのである。
ここで斎藤の提言に立ち返る。〈小説は「どう書くか」が問われるジャンルですが、「何を書くか」も大事だと思うのね。〉
まさにそうなのだ。両者は小説家としての類いまれなる力により、「どう書くか」の技術の成果によって「何を書くか」の独創性はいや増し、「何を書くか」の独創性により「どう書くか」の技術が際立ったものとして立つ。
つまり「構造」-「非構造」の対立は無化されるべきものだと、私は本質的にはそう考えています。加えて私は鹿島田真希が「エンターテインメント小説」の性格を曖昧にせずにエンタメ作品を発表したことも重要だったと評価してきました。しかしはっきり言ってこれは作品によります。批評というのは、作品の要請によって批評家の読み方がまったく覆ることをよしとすべきとの価値観が私の中にはあり、読み手の美学も哲学もマナーもルールも、すべて作品の要請の前には無力であり、作品の要請にしたがうことだけが条理だと思っています。この「構造」-「非構造」の対立の是非をよく考えるに値する作品と私が感じたのが、まさに待川匙『光のそこで白くねむる』でした。
「不明確さにはそれが存在する明確な理由があり、その明確な理由が、不明確な語りをいっそう霞ませていく力をもたらしているのである。」
このように書き手の「意図」「明確な理由」を待川作に見ることに、私は「少し」批判的です。たしかに読み手としては冷静、かつ正当な指摘です。テキストとしてもそうなっています。短いながら引用による論拠も示されております。しかし時間を置いて考えるに、私にとって同作のとくに前半は、そのように作品成立の事後的に読むとそういう風にも読める操作の分析を選択するならそれを徹底するしかなく、それも批評の一つの意義として大いにあるので誰かはやってほしいですが私自身は「そうしようと思えばそうできる作品」という両義性のそうしない方を採用したいという立場をとりました。
「光のそこで白くねむる」の前半部分は、果たして金子さんが指摘する「明確な理由」があって書かれた文章か。あるいは同作前半の全体は「明確/不明確」の対立があって書かれた文章か。このような疑問はいずれにしても断定的に言うべきことではありません。ただし「明確」とは言えない領域もあった、とは言えそうです。私としてはその対比を無化するような余地こそを見るべきだと『新潮』稿にて主張しています。だからこそより後半との捩れが露になる。そうしたあいまいな領域に読み手が踏み込み「明確な理由」とはっきり指摘することが、果たしてこの小説の本質をすくっているか。『三田文學』(2025年夏・秋合併号)に掲載されている金子さんの『光のそこで白くねむる』書評では、上のnoteでの読解とまた少しモードが違う印象を受け明確/不明確の対立をはっきり指摘すべきものとして書いているわけではないように読めましたから、金子さんの意図としてもややもすると私と同様に、そこに大きな意義は見出していないのかもしれないのですが、はっきりとは分からなかったので続けます。
金子さんの文脈を借りるならば、逆に「明確さにはそれが存在する不明確な理由があり、その不明確な理由が、明確な語りをいっそう霞ませていく力をもたらしているのである。」と読む、それが私の『光のそこで白くねむる』読解の方針でした。前半のかなりの部分を書いているところまで著者の書き方、その方針に「明確な理由」はない。それは事後的に発生したものである。そしてその事前の運動のほうに注目したほうが、実りが多い作品である。それが私の立場です。受賞時の村田沙耶香との対談において著者自身が制作過程をある程度話しているので多少の論拠はありますが、これ自体、著者を含めても、作品成立後にはっきり問えるような性質にはないことだと思いますし、作品そのものの読解において金子さんの読みを批判するほどの大きな違和感や、なにより動機が私にはありません。しかし根本的な批判を頂いた以上は、そのささいな乖離をできるだけ丁寧に記述していきます。
昨今の小説の潮流として、前半にあらゆる構造(的なもの)から逃れようとする痕跡(『新潮』稿にも書いたようにそれはそういう「意思」でしかないかもしれないもの)があってこそ導かれる「物語」「意味」「メッセージ」を後半で展開する、という前後半の分裂をふくむ小説がいくつか散見されると私は考えています。歴史的にも珍しいものではないと思いますし敢えてそう指摘するほどの発見ではありませんが、たとえば大田ステファニー歓人『みどりいせき』もまた同型の構造をとっていると私は考えています。文体に慣れて後半になると読みやすくなる、という普遍的によくある感想にふくまれる実態がこの分裂にあることも多いとみています。一年ズレですがおなじ三島由紀夫賞の候補に残り、『みどりいせき』にはその指摘はなかったかと思いますが、『光のそこで白くねむる』においては前後半の差異にまつわる指摘がいくつかありました。私見にすぎませんがこれは、『みどりいせき』には作者というより作品にその自覚がなかったのに対し、『光のそこで白くねむる』においては作品にその自覚があったこと、つまり「後半において」金子さんの言うように「明確な理由」の手つきがあったことによって分裂の痕跡が認められやすくなっている。私はそう思っています。しかし私個人としては書き手の「明確な理由」の有無そのものには評価は生じえないものだと思っています。良いでもないし悪いでもない、そう考えています。
しかし、『光のそこで白くねむる』においてはあくまで後半の「構造」が前半の「構造への抵抗(の意思)」に導かれてのものであるという捩れが肝腎であるという立場を私はとります。そこで、たとえば「文藝賞」という場の連続性を考えたときに、小川哲の選評にある「(後半の展開のために必要不可欠な)序盤と中盤の平板さ」は本質は逆なのだと、つまり「(後半の展開のために必要不可欠な)序盤と中盤の厚み」と見るべきだとの指摘は必要だとずっと思っていました。しかし考えてみれば三島賞の選評ですでにまあまあ近い指摘がある以上、私は自分の読解を不当に自分の批評のワンテーマに落とし込んでしまったな、という反省が残ります。加えて金子さんにご批判を頂いたいまなら、小川は自身の読みをただ全うしたのだと考え直しました。
とはいえ全体の問題意識としては一部近い感じもする私と金子さんはなぜこう争っているのか。それは私と金子さん、もしかしたら保坂と金子さんの、読みの「性格」的な違いによるものではないか。私は「本音」としてそう考えています。そしてそれを私は「性格」にとどまらない本質的な批判として、以下書いていこうと思っています。
3.-2 批判 悪質な抑圧 「ロマンシシズム+センチメンタリズム」の「巻き込み」について
今回の金子さんから頂いた批判は精緻で私にとっての価値が高い、ありがたいものでした。しかしこの「精緻」さと「価値」は当初のXでなされたかなり攻撃的な論調にはなかったものです。いまはもう消して頂いていますが、私はあのときの金子さんの熱量を根拠として、以下の批判を書いていきます。金子さんは私の批評を「ナンセンス」「雑」「いやらしい手つき」と評しました。私の書いたものをもっとも傷つけた批判はまた別にありましたが、しかしそれについても当該noteにて局所的に訂正と謝罪を頂いたと理解したので、正直わだかまりはありません。わだかまりがないところで、冷静に拘っていきます。
そしてそれを起点に、今回のnoteには強くは見受けられない「保坂批判」にかかわる反論を、これから書いていきたく思っています。なぜなら、金子さんに書いていただいたことは、じつは私がかねてよりこれからの「小説」の問題意識としてずっと引き摺っていたことを含んでいたからです。金子さんは保坂の言説を「放ってお」きはしない、そのようなことをいっとき、Xで宣言されました。今回頂いた批判の論旨とはかなり離れていきますし、金子さんのnoteから論争を知った読者には伝わらないでしょうが、以下、私の「思い込み」から出発する本音を書いていきます。
正直、今回の金子さんのご批判は、私に対してのものは局所的に妥当、的を射ているものだと思っています。私じしん、この原稿を単行本にするにあたり、何度も立ち返れる有益な文章を書いてくださったと思っています。
一方で、主にXのほうで強くみられた保坂批判。これは凡庸だと思っています。これまで何度も繰り返されたような批判を更新もなく持ち出されているな、と思いました。しかし上に書いたように何度も繰り返されてはいるのです。これも私の実感でしかないかもしれませんが。
私は金子さんがXで具体的に批判をしていたような保坂のベケット読解に、はっきりとは心当たりがなく(私は金子さんが主張していたほどベケットを「矮小化」する保坂の言説は、すぐには思い浮かびませんでした)、しかしアルトーなら心当たりがありました。「キース・リチャーズはすごい」(『地鳴き、小鳥みたいな』収載)のなかで、保坂はアルトーをある種のわからなさを宣言したうえで引用しています。金子さんがポストのなかで「アルトーもあんなに七転八倒せずに済んだわけです」とお書きになっていたことからこれを想起しました。
書き手に固有の体験というものが、人称を捻じ曲げるように操作したり、言い淀みや書き損じの痕跡を残したり、明瞭さよりも曖昧さを志向してみたり、その程度の罠に掛かって現前してくれるなら、アルトーもあんなに七転八倒せずに済んだわけです。危険な曲芸の舞台に立ち会うには、精緻な読みが不可欠。
— 金子薫 (@knkkaoru) September 11, 2025
一方、私は過去に、矢野利裕さんとのトークイベントのなかで、こう申し上げたことがあります。
町屋:これは言っておかなければと思った話ですが、『「国語」と出会いなおす』にも仮想敵みたいなものがありますよね。この本は本当に面白くて多くの人に読んでほしい、ベストセラーになっていい本だと思います。けれど一方で、自分は疎外感を感じる本ではありました。
それはなにかというと、帯の背に「すこやかな文学」と書かれていて、あとがきでも二回ほど「すこやか」と使ってるんですね。私は「反・すこやか」なんですよ。
すこやかであるとはどういうことなのか、それは感情のぶつかり合いで、ロジックではなんともならないものだと思いますが、でもこの本を読んで矢野さんは実は「反・反すこやか」なんじゃないかと思いました。やや無自覚に「反すこ」を批判する立場なのではないかと。
これは、保坂和志さんの話につながってきて、一般的に保坂さんはすこやかな印象を持たれている感じがするんですけど、私自身も批評を始める前はかなりそう思っている部分があって、しかしよく読んでいくと本人自身は一貫してすこやかさに欠けるところがある。保坂さんにつづく作家はけっこうすこやかに感じることがありますけど。
それで保坂さんは影響力自体はずっとゆるやかに下がっていると思うんですが、論敵にする人がいつの時期にも必ず現れるというか、なぜ目立つ存在でありつづけるのだろうとずっと思っていたんです。それであるとき、そのぶつかりは保坂さんの反すこやかな部分に対する反・反すこやかの立場からなんじゃないか、つまり、保坂さんの反すこやかの部分にすこやかな人が反発しているのじゃないか、論理のぶつかり合いじゃなくて、見かけ上そう見えているけど、じつは根っこのところでは感情のぶつかり合いではないのか、と仮説を立てたときにすごい腑に落ちた気がしたんです。
保坂和志さんを「小説の死後」で論じていて、一番思ったのは振る舞いにおいて権威的部分はやはり見受けられる。そこに関しては、しっかりその都度批判していかなきゃいけないと思いました。
けれど一方で、思った以上にもう一度保坂さんのことが好きになっちゃったんですよね。保坂和志さんを批判的に乗り越えようと思っていたけど、保坂さんの反すこな立ち位置みたいなものにすごい共感しちゃったんですね。だから矢野さんとのやり取りをしていただいた後に、むしろ保坂さんのことが好きになっちゃったんですよ。
私は、金子さんからすると丁寧さを欠くのであろうベケット、アルトー読解の保坂の「軽さ」は、それこそが保坂の「重さ」なのだという、捩れた立場をとりたいと思っています。これは主観的に、私の中にもそういう素地があるからです。ゆえに私は矢野さんからの批判を受けたことで、むしろ保坂のことが再度「好きになっちゃった」などとあられもなく発言しているのです。『新潮』稿の保坂論において金子さんに既にこれが伝わっているのなら、蛇足になってしまいますがnoteからはそれが読み取れなかったので、続けます。
つまり、ベケット、アルトーを評する文章に頻出する語彙は一般的に「重い」ものです。上のトークの文脈でいうと「反すこやか」なもの。だからこそ、一部の「すこやか」な人もその「重さ」に焦がれ、さらにその一部はその「重さ」を「重さ」として扱わない言説に厳しい。これが読書の「ロマンシシズム+センチメンタリズム」の「巻き込み」、怒りの感情を伴うことがままある、つまり悪質な抑圧だと批判したいわけです。
ようするに、保坂は保坂なりにベケット、アルトーを尊重し「軽く」引用している、金子さんは金子さんなりにベケット、アルトーを尊重し「重く」読み込んでいる。両者は分かり合えない。そう思います。しかし私自身はどちらかというとベケット、アルトーを「重く」読みたい立場であるにもかかわらず、立場としては保坂に同調するものである。保坂の読みの「軽さ」を批判すること自体は妥当なこととも思われます。しっかりと批判するのであれば、するのがよいでしょう。しかし、その内実は既視感に満ちた、感情的な議論に帰してしまうのではないか。だから金子さんの今回のnoteにもそのニュアンスが見られないのではないか。「重い」×「重い」の読みにひそむロマンシシズム+センチメンタリズムの範疇なら読み手の自由だし金子さんの言う「放っておくのもいい」。しかしその「巻き込み」において特定の作家を「軽く」読むことは怒りとともに許さない。このことを私は批判いたします。
私が本文で保坂を擁護した一因として『新潮』稿の本文に
また保坂は私のような大学などの専門領域での体系的な読書経験やその指南を経ず徒手空拳で本を読んでいくしかない人間へ向けた、いわば初学者のための王道を志向しているような側面もある。
と書きました。今回のことで読んだ『アルトー横断――不可能な身体』(月曜社)の後半に書かれていた、アルトーのゴッホ論にまつわる論考があまりに面白く(全体的に面白かったですが)、私は興奮しました。しかしこれを面白がるためには、私は保坂を経由することを必要とする可能性があったし、今回は金子さんからの批判が分からないという強い動機があって出会えた、そう思っています。
何が言いたいかというと、研究対象としてアルトーを選ぶ選択肢があった金子さんには不要に思われるかもしれないが、保坂の「軽さ」によって私はアルトーに出会えたかもしれなかった。そんな可能性も大いにありえたということです。私はアルトーに関しては他の書物に引用されていたもの以外では、今回のことでそのごく一部を読んだにすぎないので、あくまでも「可能性」です。
そんなことはどんな読書においても当たり前で、どうでもいいことかもしれない。しかし、私(の中で)はずっと繰り返されている「読書」の軋轢が、ずっと引っかかっていたのです。
金子さんのXで消して頂いた批判において書かれていた通り、じつは「雑」で「ナンセンス」で「いやらしい」読みというのを、私は好んでする立場です。そのことへの批判は当然あるべきでしょう。そして金子さんが批判をお書きになった。私はそれを一部受け容れます。
ただ今回、上述もした『アルトー横断――不可能な身体』(月曜社)に収録された金子さんの原稿を読んで、私は率直にいってかなり驚き、戸惑いました。なににか? そこに書かれた短い随筆の、とくに後半に見られる「明るさ」「軽さ」にです。金子さんがXでアルトーの名を重々しく持ち出さなければ、生まれなかった戸惑いだと思います。
彼の言葉は楔の如く心臓に打ち込まれており、先には釣り針のように返しがあり、もはや抜くのは不可能である。
前半にアルトーに対する金子さんの「内面化」を指摘した論拠となったのは上記のような文章ですが、このような宣言から続いていく小説家の紀行文的性質を含む随筆。他の執筆者と並べて読むと、浮いて感じられるほどの「軽さ」ととれるが、「雑」でもなければ「いやらしく」もない端整な文章。だからこそ金子さんの読書に対する言葉の「重さ」とここで書かれている文章の「軽さ」との乖離に戸惑ったのです。これは「重く」なりがちなアルトー読解において意図的にそう振る舞った演出的な明るさなのだろうか。私は一瞬そう考え、いや、そうではないのではないかと結論づけました。くわえて今回のnoteに補填としてお書きになった「演技する言葉と誰のものでもない身体について」に登場する言葉が「演じる」という現象の論述にもまたその「軽さ」に不満を覚えてはいますが、結局それも待川作読解と同様に批判するほどの違和感や動機があるわけではなく、言語観の違いと言うにとどめます。
つまり違うのは、「読むこと」と「書くこと」における態度です。金子さんの、読みにおいては誠実に「重く」虚心であること。一方書くことにおいてはときには「軽さ」を敢えて選択することが反転し「重く」なることすらある。私は私が好きな金子さんの小説を読んでいるときですら、「このひとは(性格、というより厳密にいえば小説的な)根の明るい人なのではないか」という「思い込み」を昔からずっと抱いていました。その明るさ(という「思い込み」)によってもたらされる小説を傑作と思うこともありました。金子さんもデビュー時の対談で「(前略)だから小説を書いたら、素朴に「光とか熱とかいいですよね」みたいなのが出てきて、驚きました。僕の小説からは性も暴力も締め出されています。」(『文藝』2014年冬季号)と発言されていたので、ご自身にもその感覚はあるのではないか、とは思っていますし、そもそも私は当時から無意識下でその発言に引っ張られていたかもしれません。それでも、こうした「思い込み」の言語化は暴力的だと思いますが、そう自覚したうえで続けますが、一部のすこやかな人にも、アルトーのようなすこやかとは程遠い「重さ」の評されがちな書き手に耽溺することがままある。それこそが「読書」です。
しかし、人には人の「重さ」がある、と申しますか、金子さんの筆致にはその明るさゆえの素晴らしさ、病、闇、懊悩、端整、狂気、面白さも含まれている。私は自己認識としてはすこやかでない人間ゆえに、これを十分には分かりえないかもしれない。同じように人には人の「軽さ」もあるのではないか。飛躍ととられるだろうことを敢えて続けますが、これは私の中で高橋源一郎と保坂和志という存在に対応します。高橋は私の理解(「思い込み?」)では、一見軽そうにも見られがちですが非常に他者の文章を「重く」読む人です。そして私が知る限り「小説のことは小説家にしかわからない」を持ち出したのは高橋のほうです。保坂は今回の『新潮』稿の註に書いたように、小島信夫の文脈を除けばそこまでその「小説のことは小説家にしかわからない」というテーゼを積極的に打ち出そうとしていないという印象です。これは私の見えていない現実、文献や歴史があるのかもしれませんが。
しかし金子さんは高橋ではなく保坂に批判の目を向けています。私としてはこれは、金子さんが「感情的に」高橋のことは理解できる、許せる(というより放っておける)。しかし引用態度の「軽さ」や金子さんからすると読みの自由の「悪質な抑圧」が見受けられる保坂のことは「感情的に」理解できない、許せないと思っている、だからあれほど反射神経的に強い言葉が出てしまったのではないか。正直そう「思い込み」ました。
構造を整える行為や構築的な工夫にも内在している創造性を、エンタメ的な磁場または物語性の引力への従属として低く見積り、書くという体験への内在を、書き手の正当性の拠り所に置き換えてしまう仕草こそ、この批評で語られる保坂=町屋的な小説観の最大の欠点であり、それは小説の自由を著しく制約する。
上は二度目の引用になります。何度か書いたように、金子さんが保坂にした批判は真新しいものではないのと同時に、保坂はそれに対する適当な応答を何度か書いています。だからこそ金子さんはnoteではあまり繰り返さなかった、というか保坂を「内面化」した町屋への批判に注力したのかもしれません。しかし現実としては、手続きの問題とはまた別に、他者の読みを「放っておか」ず悪質に抑圧するものは金子さんと、金子さんのみならずある種の読書に普遍的に偏在するものではないかと、私は常々考えていました。
あるいは批判が最初から当該noteのようであったなら、あるいはそうでなくとも、3‐1までで終わらせるのが適切であったかもしれません。結局金子さんは保坂の言説を批判的に捉えているものの、それが「局所的な言論の場に流通している言説および文脈」であるから、今回の主旨にそぐわないと判断し取り上げなかった。そういうことだったのでしょうか。しかし金子さん自身が私の「内面化」を指摘できる程度には保坂の言説をよく摑んでいる、そういう印象を持ったのも事実です。つまり金子さんのnoteも「局所的な言論の場」の内側からの批判であるということでしょうか。
これは私の『新潮』稿全体に含まれた予断と表裏一体である可能性があります。まだ金子さんの書いてくださった批判の中心を私は掴み損ねているのかもしれない。
今回いちばん私が反省したことは、私のなかに「重い」ものを「重く」読む人への不明、誤解、不誠実がありました。そこにある切実さにたいする誠意を欠いていたのです。それでも、そうした「重さ」にときに怒りに近い昂りの感情をもって人を巻き込む類の読書に批判的である。私はそういう人間です。これに近い価値観は保坂も著書の中で何度も繰り返していることでもありますから、当然、「読書」においてこの先にもたやすく相互理解がかなうようなすれ違いではないのでしょう。だからこの違和感は「放っておくのがいい」。そう結論します。よって当記事に対する金子さんからの再応答などの反応を私の方からは求めていません。

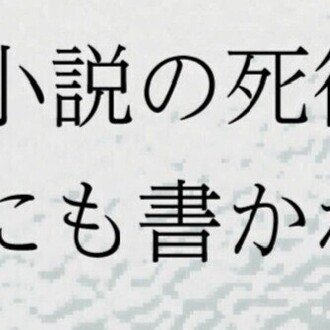
コメント