「本格ミステリー論」 島田 荘司
【したがって「本格ミステリー」の作家は、完全な二重人格者でなくてはならない】
「島田荘司がなぜその眼をアジアに向けたのか」という問題について、私たちは真剣に考えなければならないだろう。少なくとも「江戸川乱歩がなぜ戦後あれだけ社交的になったのか」という問題と同程度の重みを以て考えなければならない。
その前に島田の「本格ミステリー論」に耳を傾ける必要がある。島田は本格ミステリーに必要なものとして《「幻想味」と「論理性」》を挙げる。《「幻想味」》とは《「美しい謎」》であり、《「論理性」》とはその名の如くである。ここまでは妥当なのだが、その後の展開がなかなかに異様だ。
《「幻想味」と「論理性」、これは、先人の言葉を借りて「詩美性」と「科学性」と呼んでもかなわないだろう。まったく相反する二つのファクターの織りなす、えもいわれぬ危うさ、犯人が及ぶ限りの力で構築した犯罪計画の、あるいは構築の途上不測の事態によって発生した、そのガラス細工のようなはかない輝きと、そして続く、探偵による崩壊のスペクタクルとを、読者は楽しむのである》
《「幻想味」と「論理性」》が《「詩美性」と「科学性」》に摩り替わってしまうあたりが島田荘司である。だが、この哲学を掲げているからこそ、島田作品に現れる謎はスケールの大きさばかりではなく、謎それ自体が一個の〝詩〟を持ち得ているのだし、時として解決そのものよりも強烈な印象を残すのだ。そして、島田は巨大な謎を解明するために、極端な偶然や科学的な知識を投入することも厭わない。
しかし、日本の推理小説界はこの理論を忠実に実践させる場として適していなかった。なぜか。
例えば、戦後、江戸川乱歩は推理小説界の発展のために、多くの新人を送り出した。その中には、例えば大藪春彦のような乱歩の好みには合わないハードボイルド作家もいた。だが、乱歩はたとえ自分の嗜好に合わない作家がいたとしても、決して排疎したりはしなかった。そして、その大きさの下に戦後の推理小説ブームは花開いた。所謂〝社会派〟の隆盛や海外ミステリから影響を受けた〝都会派〟の登場は、乱歩の寛容さがなくてはあり得なかったと思う。
また、乱歩の死後、理論面から推理小説を支えたのは、その〝都会派〟たる佐野洋と都筑道夫である。前者は視点の問題を始めとして推理小説における技法の洗練を説き、後者はトリック中心の推理小説を批判し論理のアクロバットを提唱した。二人は〝名探偵論争〟でやりあったりもしたが、両者の必然性を重視するという共通した態度は後続の作家に大きな影響を与えた。
また、島田と同世代の笠井潔は、謎解きと哲学闘争を同心円状に形作らせることによってその強度を高めるという手法を自覚的に採用した。この手法は後の〝新本格ミステリー〟作家たちにも共通して見られる手法である。例えば、綾辻行人は運命論的世界観やホラー趣味を、有栖川有栖は青春小説としての味わいや時事的な問題を、麻耶雄嵩は名探偵論やキュビズムを、北村薫は文学趣味を…というように。
まとめよう。戦後の乱歩は自分が花を咲かせる代わりに、その畑を多くの作家に解放した。そして、都筑や佐野はその畑を整備を指導し、尽力した。対して、笠井は新たな花を咲かせるために他品種との交配のノウハウを提示した。無論、ここに挙げたのはあくまでも一例に過ぎない。この他にも〝社会派〟〝ハードボイルド〟〝黒の水脈〟といった様々な畑があり、様々な書き手が様々な花々が咲かせていたのである。
だが、幾多の地盤を持つ日本の推理小説界は、島田の理論を花開かせるためには、あまりにも整備がなされ過ぎていた。島田の理論は、この複雑な土壌で花を咲かせるにはあまりに原初的であり過ぎた。だからこそ、島田は未開の土壌を求めて、その眼を近隣国に向ける他なかったのだろう。そして、その成果が徐々に花開きつつあることは、『13・67』や『虚擬街頭漂流記』の登場によって遂に証明されつつある。十年後にもし、アジア推理小説史が書かれるとしたら、恐らく島田荘司の名が大著されることは確実である。ちょうど、日本推理小説史における江戸川乱歩のように。
★島田荘司(一九四八― )…一九八一年に『占星術殺人事件』でデビューして以来、常に第一線で活躍し続けてきた本格ミステリの巨匠。近年は国内のみならずアジア全体で新人作家の発掘に力を注いでいる。
初出…『本格ミステリー宣言』(講談社)一九八九年一二月
底本…『本格ミステリー宣言』(講談社文庫)一九九三年七月


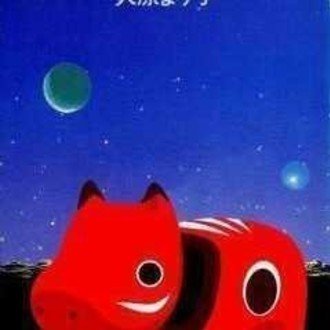
コメント