さやのかたちをたどる道|第6章 つつじ園
第6章 つつじ園
緑深い三隈山の裾野に、ひっそりとつつじ園は建っている。園に行くには、三隈山へ向かって伸びる一本道をのぼっていかなければならない。あたりには他に建物は見当たらず、 この道は園に行くためだけに作られたかのようだ。
ほとんどの人たちは町の中心部や駅に向かって通勤していくけれど、わたしは逆。町中にあるアパートを出て、山の方に向かってひたすら自転車をこぐ。だから、行きがのぼりの坂道になる。いい運動だと思うしかないけれど、仕事前に正直きつい。わたしはまだ免許を持っていないので車通勤はできないのだ。きつくても自転車をこぐしかない。
ピーチチチチ。ひばりが頭上で鳴く声が聞こえる。それすらも、わたしを応援しているような気になるから不思議だ。立ち漕ぎでようやく坂をのぼり切り、職員駐輪場に自転車を留めると、額にうっすらかいた汗を手の甲でぬぐった。
春が来て、わたしは晴れてつつじ園の新人職員になっていた。中学3年の12月、クリスマスの前の週、下川先生につつじ園に就職したいですと伝え、よろしくお願いしますと頭をさげた。先生は「よく決断したな」と涙まじりに褒めてくれた。下川先生とはあまり関りはなかったけれど、それを見てすごく心があたたかくなった。
しかし母には、今どき高校に行かないなんて恥ずかしいと言って大反対された。どうせ反対されるので就職が決まってから母に伝えたのだった。
「なんだってつつじ園なのよ」
母は頭を搔きながらいらいらした口調で言った。正社員として雇ってくれそうなところが他にはないし、先生からも頼んでもらえるからと何度も説明したはずなのに、母は同じ質問を何度もくりかえした。
「あんな人たち相手に仕事することなかやん。さやで懲りたんじゃなかったの」と母が言い放ったとき、わたしは思わず母を睨んだ。
わー、怖かあ、親に向かってなんその目、と母が言ったのに対し、わたしはもう決めたから、と言い、それ以上相手にしなかった。
なんだかんだと文句を言いながら、母はわたしがアパートを出て行くのは反対しなかった。施設から自転車で10分くらいの場所に1Kのアパートを借りたのだけれど、母はすんなり保証人になってくれた。
正直、こちらとしては母と縁を切る勢いで出ていくのに、敷金を払ったり保証人になってもらったりするのに母を頼らなければならないのは悔しいことだったけれど、未成年のわたしにできることには限界があった。
母は引っ越しに関するもろもろを手助けしてくれた上、「餞別よ」と言っていくらかのお金を手渡してくれた。引っ越しのあと、母のアパートを出るとき「まあ、健康に気をつけてがんばらんね」と言ってくれもした。
記憶にある限り母からやさしい言葉をかけられたのは初めてだったと思う。
こんなふうにして、3月の末、わたしは中学校を卒業するとほぼ同時に職を得て、自分のアパートに引っ越し、小さいながらも一国一城の主になったのだ。いきなり大人になったような気分になったものだった。
「おはようございまーす!」
わたしは声を上げてさくらホームに入った。わたしは女性棟さくらホームに配属されていた。さくらホームには障害区分が軽度で自立度の高い32人の利用者さんが生活している。
「お、お、おはよーご、ございます」
すれちがった利用者さんから挨拶を返された。利用者の中には自閉症の人も少なくなかったけれど、少しならコミュニケーションを取れる人も少なくない。
聞くと、園に入所する前はまったくしゃべれなかったけれど、園でリハビリテーションを受けたり職員や他の利用者と関わったりする中で、刺激を受けてコミュニケーションが取れるようになった利用者もいるとのことだった。わたしは事務室に急いだ。
「はい、おはようございまーす」
事務室に夜勤さんが入ってきた。わたしたちの仕事は事務室で前のシフトの職員の引継ぎを聞くことから始まる。今の時間帯は、夜勤者から日勤者への引継ぎだ。新人のわたしはまだ研修中で夜勤には入っておらず、慣れるまで日勤が続く。
わたしの指導者には川西さんという40代後半の女性職員がついてくれていた。川西さんは、ちょっと一緒に仕事しただけで、厳しいけれどやさしさもあり、仕事のできる先輩だとわかった。
引継ぎでは、昨夜までの利用者さん一人一人の様子が伝えられる。体調を崩した人、精神的に不安定になっていて安全面で注意すべき人、別棟に移った人、病院受診の結果、ご家族からの要望や苦情など、さまざまなことが一気に伝えられるので、その速さに誰の何のことを言っているのか、最初は申し送り内容をつかめずおろおろするばかりだったけれど、最近はだいたいのことを理解できるようになった。
朝の引継ぎをしている間、利用者さんたちは食堂に行って朝食を取る。食事が済むとホールに集まってレクレーションの時間になる。レクレーションと言ってもただの遊びではない。身体機能や認知機能を保ったり、利用者同士の交流を図って社会性に働きかけたりする大切な目的がある。
内容は日によって変わる。風船バレーや玉入れ、散歩、しりとりやなぞなぞゲーム、工作、絵画など、レク当番が決める。当番が進行と全体の指導をし、他のスタッフは一人ではできなかったり指示が聞き取れなかったりする利用者さんの隣に付き声をかけて一緒に活動する。
朝食を終え、ホールの奥のエレベータや階段から上がってきたころを見計らい、当番さんが声をかける。
「じゃ、レクレーションはじめまーす!」
その声を聞いた利用者さんたちがホールに集まってきた。ゆっくりと一歩一歩歩いてくる。「今日のレクは何をするのか」とか「職員の〇〇さんは今日は来ているのか」とか、そばにいる職員に話しかける利用者さんもいるけれど、自閉症の人も多いので利用者同士の雑談や交流はほとんどない。同じ空間にいてもそれぞれの利用者さんの間には微妙な距離感があり、でも同じ場所に集まり、空間を共有していて、同じ作業をそれぞれのペースややり方でする。ホールにはおっとりとした穏やかな空気が流れ、利用者さんそれぞれが自分のペースで世界を楽しむ、不思議が生まれていた。
今日は絵画の時間だ。この間お散歩でお花見に行ったので、桜の絵をテーマに絵を描くことになっていた。レク当番がすでにテーブルに人数分の画用紙と絵の具を置いて準備していた。みんなが着席すると、当番が声をかけ絵画の時間が始まった。
絵を描くのが好きな人が多いようで、みんな筆を持ち、思い思いに描いていく。画用紙からはみ出すような桜、真っ赤に燃え盛る桜、画用紙の端にひっそりと弱々しく立つ桜など、個性あふれる桜があちこちで咲き乱れる。
テーブルのそここで「水がこぼれましたー」「すみませーん」など利用者さんから声が上がるので、わたしたちは呼ばれたところに行って手伝いをする。
わたしはレクレーションのサポートをしながら、描かれた絵と、描いている利用者さんたちをじっと見ていた。上半身をかがめ、一心に画用紙を見つめて絵筆を握り、画用紙に色を乗せる一人の利用者さんに目が止まった。
そのとき、ふと、さやの面影が目に浮かび、びっくりして目をこすった。顔立ちは違うかもしれないけれど、その面影が、まなざしが、まとう雰囲気が、さやにそっくりだったのだ。
わたしはその利用者さんに歩み寄り、後ろから絵をのぞきむと、瞬間、息をのんだ。画用紙から浮きだすかのように、コンクリートの壁の上に桜が咲き誇っていた。桜は写真そっくりで、花びらの一枚一枚、めしべやおしべなどの淡く黄色い部分まで描かれていた。
「上手……」
自分の陳腐な言葉が恥ずかしくなるほど、その絵は上手だった。
「ああ、のんちゃんね。絵、うまいでしょう。昔からめちゃくちゃうまかったのよね。佐々木野乃花さんっていうの。利用者さんのことをあだ名で呼ぶのはよくないって言われてるけど、みんな昔からのんちゃんって呼んでるんよね。年は……27くらいだったかな。年齢は若いけどここの利用者さん中では長いほう。のんちゃんはつつじで一番絵が上手なのよね」
川西さんがのんちゃんを見て微笑む。のんちゃんは無表情のままわたしたちを見げたけれど、それは一瞬のことで、振り向いたのは褒められたからというよりも何か雑音が聞こえたからと言う感じでなんの関心もないように見えた。のんちゃんは言葉を発することもなく、つうっと視線を画用紙に戻してまた筆を黙々と動かし始めた。
「のんちゃんは自閉症と知的障害があるのよ。だいたいいつもこんな反応だから気にしないでね。じきに慣れるよ」
川西さんはわたしを気遣って言ってくれた。自閉症の人はコミュニケーションに問題を抱えており、話さなかったり無表情だったり視線が合わなかったりすることが多い。
ああさやもこんなふうだったなと思い出す。
川西さんによると、自閉症や障害の特性を知らない新人職員は、どんなに一生懸命利用者さんに話しかけたり手伝ったりしても反応が乏しいことにがっかりし、やる気をうしなうこともあるのだそうだ。
わたしはさやのことを思い浮かべて、「いえ慣れていますから」と言いかけてやめた。わざわざ自分からいもうとのことを言わなくてもいいかと思った。それに、「家族にそういう人がいたならいろいろわかってるよね」という目で見られるようになるのも嫌だった。
川西さんは続けて説明した。
「でも反応がないからって、彼女たちが聞いてないわけじゃないとわたしは思ってるの。気持ちはきっと伝わってるって信じてる。ただうまく表現できなかったり、人とは違う風に感じ取ったりしているだけなんじゃないかって思うのよ。だから支援が無駄だなんてわたしは思わないわ」
わたしはハッとして川西さんの顔を見つめた。意思の強い、凛としたまなざしが心に深く残った。
わたしはのんちゃんの視線の先を見つめた。のんちゃんの目と画用紙の間に電流のようなエネルギーが見えるかのように集中している。「絵を描く」そのためだけに今ここの時空が存在しているような雰囲気が張り詰めている。
うかつに寄り付けない感覚。この感じをわたしは覚えている。体験したことがある。
さや。わたしはまたこの感覚に戻ってきたとさえ思えた。その雰囲気に、わたしは久しぶりに自分を思い切り浸していた。
午前中は2時間ほどレクレーションの時間があり、その後は自由時間。利用者さんたちはそのままホールで過ごしたり自分の部屋で過ごしたりする。それからお昼ご飯の時間だ。
レクレーションの時間が終わり、片付けて自由時間になろうという時だった。「ギャー―――ッ」という叫び声がホールに響き渡った。
何事かと声の方を見ると、のんちゃんがガンガンガンと頭を上下に動かし、テーブルに打ち付けていた。
それを見た途端、わたしは体が固まってしまった。頭を板に打ち付ける、鈍い音が何度も鳴る。音が記憶を呼び覚ます。さやも昔、同じことをしていたのを鮮明に思い出していた。
止めなくちゃと思うのに体が動かない。
「あらら。始まちゃったね。今度はのんちゃん何が気に入らなかったんだろ」
川西さんがふうと息を吐いた。
「自閉症の人は何か思い通りにならなかったりしたときにパニックを起こしてこんなふうに自傷行為を起こすことがあるのよ。初めて見たからびっくりしたよね」
川西さんはわたしに言い、
「パニックの時はこちらが慌てて止めちゃダメなの。もっとエスカレートするから。まず他の利用者さんが危なくないように離れてもらって、本人も怪我しないように危険物は取り払うとか、クッションとかでガードして、落ち着くのを待つの」
と、川西さんが涼やかに説明した。そして事務所からサッとクッションを持ってきて、テーブルとのんちゃんの頭の間に差し込むと、がんがんと鳴り響いていた音が、急にポスッポスッと間の抜けた音に変わった。のんちゃんが数回頭を上下させたあと、ゆっくりと動きを止めた。
そこにすかさず川西さんが声をかけた。
「のんちゃん、どうしたの。何か嫌なことがあったの?」
テーブルをのぞく。片付け途中の絵の具セットを見ると、絵の具が一本ない。
「絵の具がなくなったのね。色は……灰色ね。すぐに探すから安心してね」
そうのんちゃんにやさしく言うと、川西さんはわたしに目配せし、「他の利用者さんの絵の具セット確認して。どっかに灰色が混じっているかもしれないから」と言った。
わたしは利用者さんの絵の具道具を見せてもらいながら灰色の絵の具を探した。結局、他の利用者の絵の具セットに紛れ込んでいた。のんちゃんは絵の具セットにすべての絵の具が揃い、すっかり何事もなく落ち着いていた。
わたしはホッと胸をなで下ろすとともに、さやのときもこんなふうに落ち着いて対応すればよかったんだなと思った。さやもよくパニックを起こし、暴れたり自傷していたけれど、わたしはどうしていいかわからず、無理に押さえて止めようとして何度も噛まれたり引っかかれたりした。
当時、今、川西さんが説明してやって見せてくれたように、パニックへの対処法を誰かが教えてくれていたら。母がこんなふうに冷静に対応できていたならば。いや、母がさやの自閉症を受け入れ、理解し、対処法を学んでいたならば。そしてわたしもそれを知っていたならば。
今さら考えてもどうしようもないことが次々に脳裏に思い浮かんだ。
「じゃ、中村さん、部屋回り行こうか」
川西さんの声がする。さっきまであんなに激しいパニックを起こしていたのんちゃんはどこ吹く風で自分の部屋へ引き上げていた。わたしは我に返り、「はいっ」と返事をして、川西さんの背中を追いかけた。
やがて一日の勤務が終わった。生活支援員の仕事はほぼ一日立ち仕事だ。足がぱんぱんで腰が痛い。まだこの仕事を始めたばかりなのに、立ち仕事って辛いなとしみじみ思った。同じく新人の梨花とおしゃべりしながら更衣室に向かい、着替えながら「足痛いねー」「疲れたね」と言い合っていたら、「まだ若いのにこれからじゃない」と川西さんに笑われた。単に体力がないだけかもしれない。明日も立ちっぱなしと思うと気持ちがどんよりしたけれど、梨花に「明日もまあがんばろっ」と言われ、わたしも、うんと笑って見せた。
「中村さん!」
ある日の勤務の最中、鋭い声で呼ばれて振り向くと、川西さんが腕組して立っていた。
「ねえこれ。危ないわよ。こんなもの出しっぱなしにしないで!」
川西さんの指さす方にハサミがあった。次のレクレーションで使うため、さっきホールで牛乳パックで工作の準備をしていたときに使った後、利用者さんに呼ばれて、ついうっかり置きっぱなしにしてしまっていた。
「こういうのを置きっぱなしにして、万が一、利用者さんが扱って怪我とか自傷とか事故につながったらどうするつもり⁉」
川西さんの声が空気を切り裂くように辺りに響く。
「すみません……」
わたしは頭を下げながら駆け寄り、サッとハサミを片付けた。「すみません」ともう一度頭を下げた。川西さんは仕事に抜かりがなく、利用者さんにも職員にも目が行き届き、指導は厳しい。いつもプロだなーと思って見ている。
この間の休憩時間、誰かが川西さんのことをアラフォーだと言っていたから、年齢は40代後半くらいだろうか。全然染めていない黒髪や肌がきれいで、ほっそりしていて姿勢がよく、30代に見えなくもない。でも母と同じくらいの年齢だと思うと、なんとなく複雑な気持ちになるのを押さえられなかった。
その時、事務室から川西さんを呼ぶ声がした。川西さんが「はーい」と返事をして事務室に行き、少しして川西さんが戻ってきた。
「孫が熱出して迎えに行かなくちゃいけなくなったの。パックはここに置いたままにしないで、事務室の横の倉庫に片付けといてね」
川西さんがため息をつきながら言った。
「孫、ですか?」
川西さんがわたしのきょとんとした視線に気が付いて言った。
「そ、わたしこう見えてもおばあちゃんなの。娘は23歳で、市民病院で看護師してるんよ。うち、二代にわたってシングルでね。保育園に行ってる孫が熱出したって連絡あったんだけど、娘はオペ室勤務でそうそう早退なんてできんのよ。こうやって、熱出したとか友達とケンカして怪我させたーとかって、なんかあったら私に電話かかってくるのよ」
と川西さんが苦笑いした。
孫? 娘? わたしはあまり聞いたことのない川西さんのプライベートを一気に知り、びっくりしていた。
「私だってこうしっょちゅう早退とか休んでたらやばいんだけどねえ」
と川西さんがため息をついた。
「でも孫なんだし、誰かがやらないとしょうがないし」と川西さんが自分に言い聞かせるようにつぶやき、
「あと、わかんないことあったら主任さんとかに聞いてね。じゃあお先に、お疲れ様」
と言い残すと、エレベーターの扉が閉まって姿が消えた。
取り残された私は、まだ呆然と突っ立っていた。川西さんがシングルだということも、もうお孫さんがいるということも初耳だった。
これから川西さんは保育園に車を走らせて、熱を出してぐずるお孫さんを家に連れて帰り、娘さんの帰宅を待って看病するのだろう。
わたしはその様子を想像し、何とも言えない気持ちになった。同じ母親でも、わたしの母とこうも違うのか。なんだかがっくりし、やるせない気持ちになった。
川西さんは施設で働き、娘さんは看護師さんと言っていた。シングルだけどお孫さんのお世話までして、娘さんを支えている。
なんでわたしの母は。なんでわたしの母はあんなに無責任で、やる気のない人だったのだろう。なんで母は、川西さんみたいにしゃきしゃきと働いたり、子どもを立派に育てて、孫の面倒を見れる人じゃなかったんだろう。
悔しい。何に対して悔しいのかわからないけれど、悔しいとしか言いようのない気持ちがわいてきた。見たことのない娘さんに、嫉妬としかいいようのない感情がわくのを感じた。
もしわたしの母が川西さんみたいだったら。そこまで考えて、ハッとしてやめた。こんなこと考えても無駄だし、疲れるだけ。わたしはハサミを握り、指に力を込めると、牛乳パックをじゃきじゃきと切り続けた。
そして就職して一カ月が経ち、昨日わたしは人生で初めての給料を手にした。社会保険料が差し引かれ、もろもろの手当てが付き、15万ちょっとがわたしの銀行口座に入っていた。まだ夜勤がないから、基本給より低いけど、わたしは初めて自分で稼いだお金を手にし、天にも昇るほどうれしかった。
今日は勤務が終わったら、同じく新人職員の岩倉梨花と、初給料祝いと称してご飯を食べに行く約束をしていた。それもあってわたしは朝からわくわくしていたのだった。
つつじ園は山裾にあり、周りにはお店どころか民家もない。仕事終わりに食べに行くには、山を下り町へ出なくてはいけなかった。高校を卒業している梨花はもう運転免許を持っていて車で通勤していたので、店まで乗せていってくれることになった。わたしたちはこの間、駅前の通りに雰囲気のいいイタリアンレストランを見つけたので、そこに予約をしているのだ。
仕事終えて着替えると、わたしは梨花の車に乗せてもらい、お店に向かった。
20席くらいのこじんまりしたイタリアンのダイニングレストランは、半分くらいお客さんが入っていた。わたしたちはおすすめコースを頼み、すぐに出された前菜をつついた。前菜は、生ハムとズッキーニ、ルッコラがあしらわれたものだった。フォークで刺して一口含むと、オリーブの香りが鼻に抜けた。飲み物はお互いジュース。
「じゃあ、乾杯といこっか」
梨花が言い、わたしたちはグラスを持ち上げて乾杯をした。
「あー、なんかいいね。こういうの。大人になったって感じ」
店内にはビールやカクテルのグラスを傾け、顔を赤くしているお客さんもいたけれど、わたしたちはまだ未成年なのでお酒は飲めない。でもこうしてちゃんと正社員として働いて、給料を手にし、そのお金で食事をしに来ている。くすぐったい気持ちだった。
「わたしたち、大人だね」
とわたしも梨花の顔を見て笑った。そこで次の料理が運ばれてきた。話したいことは山ほどあったけれど、なにしろ日勤が終わったばかりで腹ペコだ。「まずは食べよっか」とどちらともなく言い、パスタやサラダを口に運ぶ。
「でさー、川西さんてちょっと言い方きつくない?」とか「理事長先生ってなんかお多福みたいだよね」とか、「ここの雰囲気、やっぱそとの世界とちょっと違うよね、ゆっくりっていうか、最初びっくりしたけど、慣れたらなんかいいよねえ、こういうペースも」とか、利用者さんや職員の話など話題はあちこち飛んだ。
わたしたちはしゃべり続け、笑い、ジュースを飲み、どんどんお皿を空にしていった。
「でさあ、ここで一カ月ちょい働いてみて思ったんだけど」
梨花が急に神妙な顔をして言った。わたしは口の中のものを急いで咀嚼して飲み込んだ。
「うちらもいずれ結婚して子どもを産むやん、きっと」
正直、男の子とつき合った経験のないわたしに結婚とか出産とかそんな想像はできなかったけれど、とりあえず「うん」と返事した。
「もしさ、生まれた子どもが障害児だったら、どうする?」
「えっ」わたしは口ごもった。これまで考えたこともないことだった。
「わたしも障害者にちゃんと接したの、ここに来てはじめてだったんだよね。小中の頃はクラスか別の学年に障害のある子がいたけど、あんまり積極的に話したりしてなくて。なんかどう接していいかわかんなかったていうのが正直なところだったんよね。で、高校の頃、おばさんががんで亡くなってさ。ずっと独身のおばさんでね、自宅が大好きで、最期は訪問看護師さんとかヘルパーさんが来てくれて、家で亡くなったんよね。それに感動して介護の道に入ったってわけだけど」
梨花が頬杖をつき、壁にかかった額縁の絵を見ながら話す。
「ここ一カ月ちょい、毎日利用者さんたちと関わってたらさ、ふと自分の子どもに障害があったらどうしようって思ったんよね」
「どうしようってどういうこと? 育てられるかってこと?」
わたしはなんだか胸がどきどきした。
「いろいろ全部。まず、妊娠中に障害があるってわかったらどうするかだし、生まれた後に障害があるってわかったらどうするかだし……。いや、生まれたら育てるしかないけどね」
梨花が焦って訂正したけれど、わたしは「わが子に障害があるとわかっても放ったらかしというか、きょうだいに子守りを押し付けて遊び回って、育ててると言えない母親もいたよ」と言いかけてやめ、グラスを持ち上げてジュースを飲みほした。梨花には家族のことをまだ話していなかったのだ。
「ああ、まだ前があるよね。妊娠したら、出生前検査するかどうかもあるか」
梨花が話を戻した。わたしは黙ってうつむき、グラスの中の氷が溶けるのを見つめた。
「私さ、彼氏おるとよね。」
そこで、あはっという感じに梨花の表情が崩れた。
「いやー、今度の彼、めっちゃいい人で、彼はもう社会人なんだけど、わたしも社会人になったことだし、結婚できたらなーと思ったら、急になんかそういうリアルなことが思い浮かんじゃって」
梨花が頬を少し赤くして、
「ねえ、亜紀はどうする? 検査する? それでもし赤ちゃんに何か問題があるってわかったらどうする?」
と言いながら、上半身をぐいっとわたしの方に近づけた。
出生前検査のことはテレビで聞いたことがあった。赤ちゃんがお腹にいるうちに障害の有無がわかると知って驚いた記憶がある。それにも驚いたけれど、障害があるとわかったら、「産む」のか「産まない」のか自分で判断しなくてはならないことにもっと衝撃を受けた。
わたしが「産まない」と選択したら、親がわが子の生きる権利を断ってしまうこなるとわかったとき、ぐらりと目の前が回り地面が揺れたような気がした。
生まれてから赤ちゃんを殺めれば罪になるのに、お腹の中にいる間に命を摘んでしまうことは許されるのだ。
そして、出生前検査でわかる障害は染色体異常などごくわずかで、発達障害は検査ではわからないと知ったときにもなぜだかショックを受けた。
もしもの話として、検査をすれば発達障害になるかどうかもわかるならば、もし母がさやを産む前に検査を受けていたら、母はどう判断したのだろう。
さやがいなかったら母は……。
どくどくと心臓が鼓動を打つのを感じた。
そしてわたし自身が将来妊娠したら? わたしは検査を受ける? 検査を受けて障害がわかったらどうするんだろう?
わたしは体が震え、怖くなってそれ以上思考するのをやめた。
「大丈夫? 亜紀―!」
うつむいて黙っているわたしの顔を梨花がのぞき込んだ。
「いや、もしもの話だからそんなに深刻になんないでよー」
梨花があははと笑って見せた。「もうなんかごめんね、せっかく楽しくご飯食べてたのに。それよか亜紀は彼氏いんのー?」と梨花が話題を変えた。
「えー! いないよー」私が答えると、梨花が「やだもったいない! 今度彼氏に誰か友達紹介してもらうよう頼んでみるわー」と言い、わたしが「いいっていいって。まだ仕事で精いっぱいだもん」などと答え、押し問答のような会話がしばらく続けた。
22時過ぎにお開きになった。ノンアルコールのわりには相当長居をしてしまった。わたちは飲まない代わりに結構食べた。デザートまで堪能し、会計は一人4千円くらいになってしまった。
店を出ると駅ビルの向こうに満月が見えた。梨花が「あ~、食った食った! もう食べれん! はあ~お月さんキレ~ね~! あ~いい夜!」と伸びをして深呼吸したので、わたしは「やだ梨花、ノンアルで酔ったの?」と突っ込んだ。
帰りも梨花が送ってくれると言うので、駐車場に歩いて行っているとスマホが鳴った。見ると母からのLINEだった。実家を出て以来、母とは会っていないし連絡を取っていなかった。
何度かLINEのメッセージが来ていたけれど、全部既読スルーしていた。今日も返事をするつもりはさらさらなかったけれど、一応画面をタップして、メッセージを確認する。
〈仕事どう? そろそろ初給料もらったんじゃない? あんたも立派な社会人やね。〉
何よ今さら、と反射的に思った。今さら母親ぶってどうしようっていうんだろうと思った。今頃母親らしい気持ちがあったのなら、なんでわたしが家にいる頃に、さやが生きている頃にちゃんと母親業をしなかったわけ。
怒りがふつふつとわき起こる。せっかく楽しい時間を過ごしたのに最後にぶち壊しにされた気分だった。
「亜紀? どした?」
梨花に名前を呼ばれて顔を上げるとコインパーキングに着いていた。わたしは慌ててバックにスマホを突っ込み、財布を取り出して「駐車場代、わたし払うね」と梨花に駆け寄った。
第7章に続く

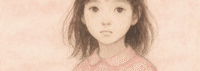
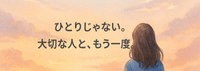


コメント
6会話がうまいですね。わたしが知っているだけでも、いくつかのコーナーにランクインされていますよ。今日は、6月ですね。今日からわたしも真面目に取り組まないと。
私の初めてのnoteにスキありがとうございます!励みになります!
これからもよろしくお願いします!
冒険者さま
またまたお褒めの言葉を頂きまして、恐れ入ります🙇♀️
ランクインしてるんですか、自分では気づかず…教えてくださってうれしいです!
いつもありがとうございます。
頑張って下さね。