「もう帰っていいよ」バキバキに心が折れたデータ分析の報告会。筆者はどうやって再び立ち上がれたか?
バキバキに心が折れた日
報告会で、クライアントから「もう帰っていいよ」と言われた経験はありますか? 私はあります!(得意気に言うことでは無いですが)
笑いながら怒る竹中直人さんのような、めっちゃ笑顔なのに発言に怒気を込めて「もう帰っていいよ」と言われました。
そう、あれは今から10年ほど前の2016年ごろ。某社で毎月行われていた施策報告会に広告代理店、製作会社、ツールベンダーが参加していました。ある月、1テーマとして「データ分析による施策の効果検証」が主催者である某社から求められ、筆者はツールベンダーの報告者として参加しました。
パワポで作ったスライドは、150枚超えだったと記憶しています。印刷した紙を配り、スライドも投影しながら説明していると、責任者クラスの偉い人から何度もツッコミを貰いました。
筆者「…というわけで、AとBを比較すると、Aが大きいと分かりました。そして次に…」
偉い人「ちょっと待って。なぜAが大きいの? 理由は?」
筆者「それは…えっと、えーと…それは…」
適切に回答できない筆者の態度に、責任者クラスの偉い人がイライラしているのが分かりました。何度も何度も「ちょっと待って砲」を喰らいながら、45分に及ぶ報告を終えようとした最後、筆者はやらかしてしまいました。
筆者「…というわけで、はい、以上です」
偉い人「えー!? ちょっと待って。結局、どうしたらいいの?」
筆者「えーと…」
(そんなこと聞かれても! それはそっちで考えてくれ。私が担うのは「分析」だけでしょ…)と思いました。それが顔に出たのか、責任者クラスの偉い人の顔が真っ赤に変化したのが分かりました。
「よーし、分かった。あなた、もう帰っていいよ」
あの瞬間のピリッとした緊張感。みんなの強張った表情。責任者クラスの偉い人の怒りが滲む声色。その後に、同行していた上長の「まあまあまあ…」と取り成す小刻みなリズム。今でも鮮明に思い出せます。
報告会が終わった後も地獄です。某社の担当者に別室へ呼び出され「こんな下らないレポート!」と1時間近く説教されました。オフィスに戻ると、今度は上長に呼び出され「先方との関係性がさぁ…」と1時間近く小言と嫌味を聞かされました。
もうええ! 辞めたらあ! そう言えたら、どんなに楽か。
大勢で面罵された恥ずかしさ。品質が低いと言われた悔しさと悲しさ。「俺が間違ってるの?」と滲んだ怒り。あの日、筆者の心はバキバキに砕けました。心の折れた音は確かに聞こえました。
挫折というより、絶望に近い経験でした。
データから知恵へ
その後、縁があって何度か転職したのですが、定性分析の最前線に立った時も、支援会社から事業会社に移った時も、定量データ分析はなるべく避けて通りました。
筆者は、心の奥底で「逃げた」と自責の念をずーっと抱えていました。データ分析から逃げたのか、報告会から逃げたのか。あまり深く考えることもなく、心に封をして生きていました。
転機を迎えたのは2020年6月です。現在はマイナビ出版の代表取締役を勤める角竹さんから「中学校の授業で習う『情報』のような、中学生からでも読めるデータリテラシーの書籍を書いて欲しい」とオファーを頂きました。
「データとは何か?」について正面から向き合わないと、絶対に完成しないという直感を抱きました。この時点で、絶望から4年経過していましたが、未だトラウマのままでした。
向き合うか。本当に向き合えるのか?
深く、広く、色々調べて発見したのがオペレーションリサーチやシステム思考で著名なラッセル・アッコフ教授の書いた論文『From Data to Wisdom』(1989)でした。
アッコフ教授は、「人間はデータから知恵へ段階的に進む能力を持っているが、機械には出来ない」と主張しました。だから論文のタイトルが From Data(データから) to Wisdom(知恵へ)なんですね。
具体的には「人間は見たもの聞いたもの触れたものを、心の中で5つの階層に分類できる(濾過できる)」と主張しました。以下の通りです。
==============================
Data(データ):記号や数字など、情報を表現ている。
例「20000、5000」Information(情報):一定の文脈で意味が分かる状況を記述している
例「Twitter上での反響はAは20万件、Bは5万件、Aの方が大きい」Knowledge(知識):構造的な文脈で意味を捉え、再現性を発見する
例「新商品AはTVCMを出稿するだけでなく、店頭の販促にも力を入れたので、多くの消費者の目に留まった。だから既存商品Bよりも新商品Aの反響が4倍大きかった」Understanding(理解):知識を再編集できて、新たな発見を得られる
例「同じGRP・同じ販促費だった過去の新商品プロモーションと比較すると、反響は少なかった。その理由として、SNSの投稿を読むと「前と何が違うの?」等、新商品であることが伝わっていない可能性が伺えた」Wisdom(知恵):実際の行動や意思決定に適用できる
例「新しいだけで商品を手に取ってくれる時期は短いなので、クリエイティブを急ぎ修正するか判断を願いたい」
この図では Understanding が Insight になっている。「Conspiracy Theory」とは陰謀論のこと
==============================
ちなみに、この5段階は「DIKWピラミッド」の原型ではありますが、アッコフ教授の論文を読む限りは、彼がピラミッドの考案者では無いようです。DIKWピラミッド=アッコフ教授が編み出したと解説するコンテンツに多く遭遇するのですが、それは誤解です。
難しいのは Information と Knowledge と Understanding の違いです。
Information(情報)は、事実、事象、過程、着想、妄想など対象物に関して知り得た事柄を指します。40,000,000,000(400億)は単なるDataですが、400億『の男』と記述すると「煉獄さん」「鬼滅の刃」といった特定の意味を持ちます。
Knowledge(知識)は、情報の背景にある構造を捉え、因果関係を把握し、1度抽象化して他の具体に転用できる状態を指します。『400億の男』を生んだコロナ禍という時代背景、ufotable作品の素晴らしさ、良い作品がSNSで広がり易い環境など「鬼滅の刃」に特定しない意味を持ちます。
『ONE PIECE FILM RED』(2022年, 203.4億円)、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』(2024年, 158.0億円)、現在進行形で『国宝』(2025年)など、2020年以降は100億円越えの超大作が連発しています。この文脈の上に『鬼滅の刃』がいると考えるのが「知識」です。
ちなみに、何でも知っている人を「知識人」と評することもありますが、上記の定義に照らすと「情報通」が妥当です。「知識人」とは、さまざまな情報を統合してスキーマを構築し、XだけでなくYにもZにも転用できる人を指します。なんでも知っているだけじゃ「知識人」は名乗れません。
Understanding(理解)は、そうした知識を再編成したり、既存の知識と組み合わせたりして、知識から新たな気付きを得えられる状態を指します。コンテンツ流通のDX化で、配信サービスを通じて世界中にアニメが行き届き、漫画アプリのおかげでマンガ市場が過去最高規模になっていることまで捉えて、400億の男を「理解」している、と言えます。そうした人を、教養人と呼びます。
いわば、違いがわかる男。上質を知る人。ダバダ~って聞こえてきますね。
「女性だって違いが分かりますよ」というのは、もう本当におっしゃる通りでございます。まずは、こちらをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=FFwph7CkCb8
https://www.youtube.com/watch?v=dhKxPB54LUc
知識と理解と知恵を求めるデータ分析
論文を読んで、筆者は全身が痺れました。比喩的な意味ではなく、本当に電流が走ったような衝撃でした。
筆者のデータ分析は、情報に留まっていました。情報を知識に出来ていませんでした。Aが大きいです。Cチャネルの反応が良いです。Eカテゴリ―が売れています。どれも、構造(奥行き)を捉えていません。
某社の責任者クラスの偉い人が求めていたのは、知識であり理解であり知恵でした。Aが大きい理由。Cチャネルの反応が良い背景。Eカテゴリ―がより売れるためには。
ギャップが激し過ぎる。そりゃ、ダメ出しされるわ。
筆者は何を間違えていたのか、どのように回答するべきなのかが、ようやく分かりました。データ分析は知識と理解と知恵を求めるべきなのです。情報に留めない。なぜ?を追う。再現性と普遍性を求める。何をすべきかを考える。それがデータ分析です。Aが多いですBが昨対を上回りましたは、データ分析ではない。
筆者が叱責(という名のパワハラ)を受けた理由が腹落ちしましt。もう、報告会から逃げない、データ分析からも逃げない。挫折と絶望から立ち上がれた瞬間でした。
長い長い長い暗闇のトンネルから抜け出せた心境でした。気持ち的には「ショーシャンクの空に」のアレに近い。
■
少しだけ余談を。
そもそも、デジタルマーケティングの現場では、テクノロジーの力で大量のデータと情報に溢れていますが、知識となると一気に減ります。GA4の数値だけで「因果関係を把握し、1度抽象化して他の具体に転用できる状態」を目指せるでしょうか? 相当な難易度です。
当時の筆者は、情報と知識の違いを分かっていなかったのです。GA4の数値や、各種ツールのダッシュボードから言えることを明らかにするのが「データ分析」だと思っていました。
そうではなく、例えばGA4からAカテゴリとBカテゴリを比べてAの方がSU数が多いと分かったなら「なぜか?」「背景に何があるのか?」と情報を知識に変える思考を身に付けなければならなかったのです。
そのためには、今あるデータに閉じてはならない。今わかるデータに限ってはならないのです。
以前に、BtoB事業時代の筆者の上司は「公式サイトならトップページから会社情報に飛ぶのが鉄則」「なぜなら『この会社大丈夫かな?』『信頼できるかな?』『信用していいかな?』と思ってサイトに訪ねているから」と教えてくれました。
実際にGA4で経路データ探索をしてみると、まさにそのような遷移が最大を占めました。「なんで分かったんですか?」と聞くと「どの会社もそうだから」と教えてくれました。何度も経験を繰り返し、具体を積み重ねて抽象化されている。これが知識であり理解だと痛感しました。
そんな知識は、社内に閉じ籠っていると気付けない。知識は社外にあると確信しました。それこそ筆者が意識的に副業に取り組む理由です。
ドラッカー教授の『経営者の条件』に、次のような一文があります。
愚鈍な機械コンピュータは定量的なデータを処理するだけである。データを非常な速さ、正確さ、精密さをもって処理する。これまで不可能だった大量のデータを提供する。しかし大体において、早く定量化できるデータというものは、組織の内部についてのデータである。コストや生産性、教育訓練の報告である。外の重要なことは、もはや手遅れという時期になるまで定量的な形では入手できない。
(略)
フォードの新車エドセルも同じ教訓を与えてくれる。エドセルの設計にあたっては、当時手に入る定量的なデータはすべて集められた。当然、生産されたエドセルはねらった市場において求められている車であることが数字によって示されていた。
しかし、もはやアメリカでは、購入する車種は所得ではなくライフスタイルによって決められるようになっていたという定性的な変化は、いかなる統計も明らかにしていなかった。その変化が数字としてわかるようになったときには、すでにエドセルは売り出され、そして失敗していた。
生成AIの時代、アッコフ教授やドラッカー教授の示唆は「レガシー」でしょうか? いえ、生成AIを使い倒している人ほど、人間の役割は「知識」であると肌身を持って理解している筈です。
いずれ、「知識」領域も生成AIが担うかもしれませんが(そしてそれはAGIじゃね?と思いますが)、それはまだ遠い先の未来だと考えます。
ソフトバンクは2025年度に人に代わって定型作業を行う「AIエージェント」の利用を始める。同社では24年度末から「AI時代の働き方」と題したテーマで議論を重ね、人の役割について「知識を生かす知恵の創出」と定義した。そのため社員同士の交流や部門間の意思疎通をより重視する。
ラッセル・アッコフ教授の知識が無ければ、ソフトバンクの言っていることは何のこっちゃ抹茶に紅茶だと思います。人の役割は「知識を生かす知恵の創出」である。おっしゃる通りです。
いいなと思ったら応援しよう!
 1本書くのに、だいたい3〜5営業日くらいかかっています。良かったら缶コーヒー1本のサポートをお願いします。
1本書くのに、だいたい3〜5営業日くらいかかっています。良かったら缶コーヒー1本のサポートをお願いします。

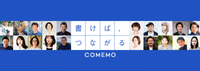



コメント