『真の特講』講座ガイド・全問題紹介|JUKEN7物理講座
JUKEN7物理講座『真の特講』の講座の案内と全問題の紹介を行います.
◆ 『真の特講』のコンセプト
『真の特講』は,難関大で合否を分ける問題を確実に得点する力と,解法に迷う初見問題を突破する思考力を養う講座です.
対象・目的
基本的な手法を一通り学び終えた難関大受験生対象.
必須の知識・スキルを確認・定着させ,上級の基礎力を築く.
入試で必要な解法を網羅し,実践的に整理・体系化して身につける.
未知の問題でもロジカルに解法を判断する思考力を養成する.
特徴
目的に特化し効率を追求した唯一無二のオリジナル精選40題.
徹底的にシンプルな問題で本質に集中できる.
教材に沿って取り組むだけで,基礎力・思考力が自然に積み上がる.
大学進学後の学習にも直結する力が育まれる.
※ 原子物理範囲は扱いません.
※ 一部有名入試問題を含みます.
※ 解説講義は1題あたり1時間程度.
※ 難関大:旧帝・科学大,早慶,慈恵,慶医などをイメージしてください.
※ 進学後も物理を学び続けたい標準大志望の方も歓迎します.
※ 基礎学力にやや不安がある場合は,基幹物理やFNDsとの併用をお勧めします.
問題一覧
【リンク】
◆ 取り組み方
取り組む時期
Aのついたセクションが夏,Bのついたセクションが秋~冬頃をひとつの目安.
余力がある方は,もちろんどんどん先に進んで構いません!
予習時
時間無制限で問題に向き合う.
ある程度時間をかけても(20分程度)歯が立たない場合には,無理に考え続けない(変な癖がつくとよくない).
テキストの【方針】を読んで,再度取り組んでみる.
【解答】を読み,解けなかった所・解答を読んでも分からなかった所を洗い出してから解説講義を受講するのがベスト!
※ 問題文をよく読んで(出来れば音読し),ノートに図を描きながら考えることを忘れずに(一部の問題の図は敢えて省略してあります.文章から状況を図示する訓練もまた大切)!
◆ 全問題紹介
力学A
物理の土台となる力学.その力学の土台となる部分を扱います.優先的に取り組んで欲しい部分です.
1. 滑車とばね
動滑車の関わる束縛条件.
ばねにつながれた糸の張力,糸がたるまない条件.
仕事の計算,系の見方.
単振動.
2. ベルトコンベア
一定速度で動くベルト上の物体が受ける摩擦.
エネルギーと仕事,系の見方.
初期位相を考慮すべき単振動.
3. クーロン力の下での運動
時間追跡不可能な運動の取り扱い.
つりあい点付近での微小振動.
可動領域.
大雑把に捉える:運動の定性的把握.
4. 天体の運動
万有引力の下での天体の運動.
円軌道の定石.
楕円軌道の定石,ケプラーの法則.
非典型設定:双曲線軌道も定石で扱える.
5. 斜面と壁に挟まれた物体
面による束縛.
時間追跡 / エネルギー収支.
仕事の計算,系の見方.
6. 円筒面を持つ台
2物体系全部入り(重心絡み除く).
強制外力で動かす:見かけの重力,外力の仕事.
2体問題:保存則と束縛条件の連立,相対円運動.
7. 三角台と小球の衝突
固定面斜衝突,力積.
三体衝突のモデル.
力学B
浮力や剛体など力学の中でも後回しにしてもよい部分を扱います.ある程度の実力がついてから取り組むべき部分でもあるので,焦らずに取り組んでください.
8. 浮力
浮力の下での単振動.
外力の仕事.
浮力の位置エネルギーの解釈.
9. 渦巻き運動
面積速度保存則と全体のエネルギー保存則の連立.
運動の定性イメージ.
10. ばね連結2物体
力積と仕事,系の見方.
ばね連結2物体の時間追跡.
11. 棒連結2物体
保存則による取り扱い.
重心系での取り扱い.
12. 円板の回転
剛体のつりあい.
剛体の運動.
熱力学A
熱力学の根幹をなす部分を扱います.基本と例外に対応する1と2は特に優先して取り組んでください.
1. ばねつきピストンで封入された気体
熱力学の基本思考と例外処理(非平衡過程).
系の見方.
2. 気体ばね
ピストンが動く際の取り扱い.
微小振動,微小ではない振動.
断熱変化.
力学的準静過程と熱力学的準静過程.
3. カルノーサイクル
定積モル比熱,比熱比,内部エネルギーの表式.
熱効率.
4. 気体分子運動論
気体分子運動論の基本.
応用:スペクトルの揺らぎの分子運動論的説明.
熱力学B
5. 気体の密度勾配
気体の圧力分布.
近似の妥当性:差を測定すると高精度.
6. 液体と接する気体の熱現象
難関大頻出設定,系の見方.
7. ひも状物体の熱力学
理想気体以外の物体の熱力学.
電磁気A
電磁気の中でも電気分野を扱います.入試では出来の悪い分野ですが,体系的に扱うことで得点源にすることができます.
1. 2つの点電荷の作る電場中での点電荷の運動
点電荷の作る電場.
時間追跡できない運動.
可動領域.
微小振動.
2. 帯電球内部での運動
拡がった電荷分布の作る電場.
電位の基準.
可動範囲.
3. 太陽電池
回路の状態の決定:まずはキルヒホッフ則.
未知の素子の取り扱い例として太陽電池を扱う.
4. コンデンサーとダイオードからなる回路
コンデンサ回路の切り替え(コッククロフト=ウォルトン回路).
回路の状態の決定:電荷保存則とキルヒホッフ則の連立.
無限回後の取り扱い.
5. はく検電器
定性的理解は定量計算に支えられる.
6. コンデンサーの充電・放電
コンデンサ充電におけるエネルギー収支(典型と非典型).
過渡現象.
ジュール熱の分配.
7. 3枚の金属板
内部構造の見えるコンデンサ.
極板間引力.
8. 誘電体の受ける力
コンデンサへの誘電体の挿入.ただし.非典型的配置
誘電体が受ける力.
電磁気B
電磁気の中の磁気分野を扱います.電磁気Aのセクションをしっかりと身につけた上で取り組んでください.
9. 電磁場中の電子の運動
与えられた電場・磁場中での荷電粒子の運動の基本と応用.
入試的扱いと微分方程式を解くこと.
10. 静磁場中の正弦波形レール上を動く導体棒
静磁場中を動く導体棒のタイプの電磁誘導.
レールの形状が非典型.
交流も登場.
11. 円形導線の近くで動く磁石
磁場が時間変化するのタイプの電磁誘導.
磁石が受ける力をどう求めるか.
12. ソレノイド内に生じる誘導電場
ソレノイド内の磁場.
誘導電場を求める手順.
13. 変圧器
相互誘導の復習.
論理的思考法.
相互誘導におけるエネルギーの理解.
波動A
波動分野でも力学的波動の部分を扱います.
1. 疎密波
振動グラフと波形グラフ.
応用的な問題だが基本に忠実に.
2. 弦の固有振動
進行波・定常波の式.
弦の固有振動,うなり.
弦を伝わる波の力学モデル.
3. 流れのある液体中の音波
流れのある液体中でのドップラー効果
波動B
波動分野でも光波の部分を扱います.
4. プリズムによる光の屈折
屈折,全反射.
光の分散による色づき(虹と同様のしくみ).
5. 球形レンズ
非典型形状のレンズの式を作る.
6. 複数の波源からの波の干渉
複数の波源からの波の合成波を定量的に扱う.
7. フレネルの輪帯板
等間隔でない多重スリットからの回折光.
光の強度とエネルギー.
8. 単スリットによる光の回折
単スリットのいろいろな見方.

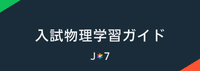

コメント