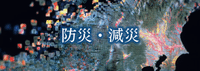「ひとりでも多く助かってほしい」 過去の記録を未来の防災に
「せっかくNHK内に映像があるのに、それをなんとか活用できないか・・・」
そんな思いを出発点に、大きな企画がスタートすることもあります。
NHKは2025年10月、放送に加えて、インターネットを通じた番組配信などが必須業務となる、歴史的転換点を迎えます。
公共メディアとして、放送とネットの両方で、「知るべき多様な情報・コンテンツ」にあまねく多くの人に触れてもらう。その先駆けとして、今回は、災害情報をより広く届けるために生まれた『災害記録マップ』と『災害情報マップ』という二つの防災コンテンツを紹介させていただきます。
放送で取材してきた信頼できる情報を、ネットではその特性をいかして、きめ細かく伝えていくためには、どのような過程が必要だったのか。どんな課題や学びが得られたのか。
前後編でお届けする特別企画。前編となる今回は『災害記録マップ』の舞台裏について、担当者本人からのレポート形式で紹介させていただきます。
大石 寛人 2011年入局・メディアイノベーションセンター所属。
広島、福井放送局でディレクターとして情報番組やドキュメンタリーなどを制作。2016年からは東京で防災に関するデジタルコンテンツを番組と連携しながら制作。「災害記録マップ」を企画し現在も運営しているほか、全国ハザードマップやシチズンラボなどにも携わる。
現所属のメディアイノベーションセンターは、テクノロジーを活用してコンテンツの質的向上とサービスの進化を実現するための開発拠点。エンジニアやディレクターなどさまざまな職種の人たちが所属。
1. 原動力は「せっかくあるのに、もったいない」
「フィルム保管庫」と書かれた扉を開けると、大量のフィルムが整然と並ぶ圧巻の光景が広がります。
NHKには、各時代・各地域の膨大な映像が残されています。媒体はフィルムやテープなどさまざまですが、記録自体はデータベース化されていて、放送で使用したい時などは簡単に検索できるようになっています。
しかし、過去の映像が実際に再使用されるようなケースは、全体の量からするとほんの一部。多くの視聴者にとっては、見ること聞くことはもちろん、存在していることすら知ることのできないままの状態となってしまっています。
「せっかく膨大な映像記録があるのに、それはちょっと、もったいないなぁ・・・」
そんな気持ちを出発点に、防災コンテンツ『災害記録マップ』は生まれました。
「あのとき」「ここで」「なにが」起きたのか。『災害記録マップ』の地図上に並ぶアイコンをクリックすると、過去の災害を取材した動画や画像、文章などを確認することができます。
せっかくNHKには過去の災害に関する映像がたくさんあるのだから、それをインターネットの特性をいかして、多くの方に教訓として活用してもらい、未来の災害に備えてもらえたら、被害を減らすことができるのでは・・・。
こうした気持ちを原動力に公共メディアとしての使命感を持って今日も更新を続けています。
2. 映像じゃないと、伝わらないものがある
現在『災害記録マップ』の制作を担当している記者の藤島とエンジニアの浅野は、この取り組みに先立って2022年に公開された『全国ハザードマップ』の立ち上げでも一緒だった“顔馴染み”の仲間です。
(そういえば当時も「自治体に存在するデータが活用できないのは、もったいない」という気持ちが出発点でした。)
↓「全国ハザードマップ」については、こちら↓
その『全国ハザードマップ』の取り組みの中で、忘れられないやりとりがありました。
当時は全国の自治体の防災担当者と頻繁にやりとりをしていたのですが、その時によく言われたのが「NHKには、映像がたくさんあっていいですよね」という声でした。
どういう意味だろうと思って詳しく尋ねてみると、
“災害の展示などをやることがあるんですが、画像は残っていても動画ってほとんどないんですよね”
とのこと。確かに市役所などで催される災害展示では、写真をパネルにし、その下に説明文を添える形式が多い気がします。
“映像じゃないと伝わらないことってあるような気がします。
臨場感とかですね。「ああ、こうなっちゃうんだ、こわいな」って。”
その言葉にうんうんと頷きながら、「そうだよな。映像って確かに、そういう身に迫るものがあるよな」と、映像の持つ大きな力を、改めて感じていました。
3. 映像だから残った「災害」の貴重な記録
その後、災害報道の新しいチャレンジの一環として立ち上げられた『災害記録マップ』。第一弾として、阪神・淡路大震災の際にニュースとして実際に放送された映像を、地図上に掲載していくという企画に取り組みました。
その掲載作業の過程で見た映像の内容は、私たちにとっても驚きと発見の連続でした。
たとえば地震発生当日の避難所の様子。
食料の配給の様子を映した映像には、パンを手渡しで配っていて、「こっちにもちょうだい」という声と「これしかないのですみません・・・」という担当者の申し訳なさそうな声が残されています。地震直後の避難所の空気感が伝わってきます。
数日後の映像には、被災された方が自分で食料を調理する様子も映っていました。
こちら、よく見ると網の代わりに使われているのは、なんと「側溝のふた」です。
使えるものは何でも使い、少しでも避難生活を便利にするための工夫が行われていた様子が分かります。
避難所生活のリアルが写し出されたこれらの映像は、「大きな災害が起きたとき、避難所では何が起こり、どんなものが足りなくなるのか。そしてどんな工夫ができるのか」など、多くのヒントをうかがい知ることができる貴重な記録でもあったのです。
4. 映像の使用判断 基準はどこに
そんな『災害記録マップ』は、取り組み開始直後に大きな壁にぶつかります。
それは「写っている方の使用許可が確認できていない過去の映像を、掲載していいのか?」という問題でした。
意外に思われるかもしれませんが、実は「こういう過去の映像は使ってOK」「こういうものは、ダメ」という明確な指針が存在しているわけではありません。映像の使用判断については、各制作現場が、ケースバイケースで判断しているのが実情です。
もちろん原則として、人が映った映像を番組で扱う場合、許可が取れたものだけを使用していますし、許可が確認できない場合は「個人が特定できるような映像は避け、他の映像を使おう」となることも珍しくありません。
しかし約30年前の映像に写っている全員を探し出し、一人ひとりに「インターネットで掲載してもよいでしょうか?」と確認して回るのは、現実的には不可能です。だからといって、許可がすでに取れている映像だけを使うとなると、数が相当限られてしまいます。
さらに、映像ごとに判断するとしても、現場やメンバーごとに映像の使用判断にバラつきが出てしまう状況は、プロジェクトとして避けなければなりません。
そこで記者の藤島と一緒にあたったのが、デジタル空間上の情報基盤の構築に向け産学官の専門家などでつくる【デジタルアーカイブ学会】の「肖像権ガイドライン」でした。
肖像権という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「みだりに自分の肖像や全身の姿を撮影されたり、撮影された写真をみだりに公開されない権利」のことです。この権利を侵害していないかどうかは、人の映った映像の使用可否に関して大きな判断材料となります。
デジタルアーカイブ学会のガイドラインでは、過去の肖像権関連の裁判の判例をもとに、「公開に適する」「条件付きであれば公開に適する」などを総合的に判断できるようになっています。
もともと映像ではなく写真に用いられることが前提のガイドラインでしたが、策定された学会の方にもご相談のうえ、こちらを『災害記録マップ』の映像の指針にも実験的に使用させていただくことにしました。
『災害記録マップ』では掲載可能性のあるすべての映像に対してチェックを実施していくため、作業者も多く必要になります。そこで誰でも簡単に作業ができるように、対象の項目をクリックすると自動で点数が計算されるオリジナルのチェックシートを準備し、業務効率化およびミスの防止に取り組むことにしました。
あわせて、「その他の配慮すべき事項はないか(差別的な発言や過激な批判、悲嘆にくれる人など)」、「著作物(本・映画など)の映り込みはないか」、「個人情報(氏名・住所・電話番号など)が映っていないか」というチェックフローを作り、一つずつ映像の精査を行なっていきました。
ただし、どれだけ対策を講じても、万一、被写体となった方や知人が「取り下げてほしい」と希望された場合はすぐに確認・対応がとれるよう、公開されたすべての映像に異なる「情報番号」を振っておくことにしました。
5. 新しい「記録」の形。多角的に災害を伝えていく未来
こうして無事2024年1月のリリースを迎えた後、新たにユーザー参加型の企画をスタートさせました。それが、「みんなでつくる災害地図」でした。
『災害記録マップ』は地図コンテンツとして、位置情報がわかる映像を地図に掲載しているのですが、実は詳細な位置情報がわからない映像のほうが圧倒的に多いのです。(過去の災害の映像には、GPSの情報などありませんから、スタッフが映り込んだお店や電柱の表示などから、一つずつ位置を特定しています・・・!)
そこで、災害当時を知る方やその土地に詳しい方などに、私たちでは位置の特定が出来なかった映像をご覧いただき、もし「この場所、知ってる!」という映像があれば、詳細な位置情報を特定することも可能になるのではないか、と考えての企画でした。
また、2024年元日の能登半島地震では、災害情報や支援情報をリアルタイムで伝える『災害情報マップ』から、ピックアップした情報を『災害記録マップ』として掲載することにも取り組みました。
この中で新しいコンテンツとして、3Dで視点を自由に動かしながら視聴ができる「360度映像」も試験的に公開中です。
地震後に崩壊した「見附島」を空中撮影した映像をもとに、立体データ化。少し操作が難しいですが、ユーザーが見たい角度・見たい縮尺で詳細を見ることができるため、さまざまなニーズに応えられるコンテンツとして可能性を感じています。
今後も「多角的に災害の実相を伝える」ことを目指し、映像を軸にしながら、いろいろな表現方法や企画を模索していきたいと思っています。
6. 取り組みの輪を広げ、災害に向き合う機会を提供したい
『災害記録マップ』がプロジェクトとして迎えた大きな転換点の1つは、阪神・淡路大震災のマップを公開したあと、盛岡放送局から「同じような地図を、東日本大震災でもつくりたいと考えていた」と連絡をもらったことでした。
私たちも掲載を考えていた災害なので、さっそく連絡をくれた盛岡放送局の荒井と打ち合わせを実施。すると東日本大震災のマップについては、盛岡放送局チームが映像の選定からチェック、動画のアップロードまでを独立して担当してくれることになったのです。
自分たちが情熱をもって取り組み続けてきたプロジェクトが、別のチームの力を得てさらに広がっていくという流れは実に理想的で、とてもうれしい出来事でした。
東日本大震災のマップは、地域の夕方のニュースで紹介されるなど放送と連動。被災地の陸前高田市で開催した盛岡放送局のイベント展示でも使われ、多くの方にマップを見てもらう機会を得ることができました。
展示会の現場にいた荒井によると、震災発生当時、被災地では停電や避難の影響で「何が起こっていたのか」をテレビで見られなかったという方も多く、展示では長時間マップを見ていた方も多かったとか。
中には、映像を見ながら涙ぐむ方もいらっしゃったそうです。
実際に被災された方も、その災害を全く知らない方も、『災害には人それぞれの向き合い方がある』と改めて思いました。
7.終わりに
『災害記録マップ』は、公開して終わりではなく、使ってもらうためのコンテンツです。「つくり手の自分たちのメッセージを提示するのではなく、自分たち放送局の人間には思いつかない使い方をしてもらいたい」と、いつもチームで話をしています。
経験した災害を振り返る。
知らない災害を学ぶ。
これから起こる災害に備える。
使い方や目的は人によって異なるからこそ、さまざまなニーズに応え、参考にしてもらえるようなサービスを目指さなければなりません。
そのために、まずは掲載する映像・情報を充実させ、全国の主要な災害の映像を見られるようにするべく、チーム一丸となってまさに今、頑張っているところです。
並行して、研究・教育・自治体などで活用してもらえる形を模索していて、ユーザビリティ(使いやすさ)も向上させていきたいと考えています。
災害の発生自体は避けられないからこそ、蓄積した過去の災害の知見を未来に残していけたら。そんな思いで、今日もコツコツと過去の映像と向き合っています。
後編となる『災害情報マップ』は今月末に公開予定です。そちらも是非ご覧ください。