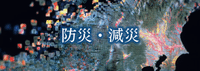デジタルマップを用いた災害報道「災害情報マップ」開発のオモテとウラ
公共メディアとして、放送とネットの両方で、「知るべき多様な情報・コンテンツ」にあまねく多くの人に触れてもらう。その先駆けとして生まれた『災害記録マップ』『災害情報マップ』という二つの防災コンテンツ。
放送のために取材してきた信頼できる情報を、ネットの特性をいかして、きめ細かく伝えていくためには、どのような過程があり、どんな課題や学びが得られたのか。
前後編でお届けする特別企画、後編となる今回は『災害情報マップ』の舞台裏について、役割の異なる2人の担当からレポート形式で紹介させていただきます。
システム担当 ナガモリ
2017年入局・メディアイノベーションセンター所属。
放送技術として入局し、現所属ではニュースに関連するコンテンツやシステムの開発・運用を担当。『災害情報マップ』では全体のシステム設計・開発を担当しているエンジニア。
能登半島地震から5日、「災害情報マップ」の公開
震度7を観測した2024年1月1日の能登半島地震の発生から5日後。NHKでは、避難所や仮設トイレなどの支援情報をデジタルマップにプロットした防災コンテンツ「災害情報マップ」を公開しました。マップ上のアイコンをクリックすると、映像や画像とあわせて詳細情報がテキストとして表示される仕組みです。
公開期間 2024年1月6日~2月28日
開設避難所 約8100か所 (石川、富山、新潟の3県)
給水所 約5600か所 (石川、富山の2県)
支援情報 約230か所 (石川県のみ)
被害情報 約90か所 (石川、富山の2県)
通行可能道路 国交省「道路復旧見える化マップ」公開データより
「災害情報マップ」の開発でまず最優先に考えたのは、ライフラインに関する情報を迅速に公開できるようにすること。被災した皆さんにいち早く必要な情報を伝えたいという思いからでした。そのうえで、より必要性の高い情報を素早く提供するためのアップデートを重ねるべく、私が所属するメディアイノベーションセンターという部署にいるエンジニアたちがチームで取り組むことに。
スピードと質の両方が求められるなか、数々のサイトを手がけてきたフロントエンジニア(「見た目」や「画面の動き」を作るエンジニア)や動画配信設備の開発経験のあるバックエンドエンジニア(「裏側の仕組み」や「データ処理」を作るエンジニア)など、多種多様なメンバーで構成されるエンジニアチームによって、開発は加速していきました。
フロントエンジニアたちが連携し、掲載コンテンツをアップデート
「災害情報マップ」は、当初は豪雨災害での利用を想定して開発が進められてきたコンテンツでしたが、能登半島地震の発生を受け地震災害利用に適した形になるよう改修が進められていきます。まずはフロントエンジニアの対応により、1月12日には地図上で通行可能な道路を可視化した機能が実装されました。
そこから、日々刻々と変わっていく状況とともに多くの改修要望が寄せられる中で、▼災害の様子を伝える「災害の情報」▼避難所や給水所などライフラインに関する情報を伝える「支援の情報」を切り分けて伝えること。あわせて▼発災当時の災害情報は残したままにするという改修の方針を決定します。
これらの複雑な内容を短期間で実装するには、開発を分業して取り組む必要がありました。本件ではフロントエンジニアのリーダーを中心として4名ほどのフロントエンジニアが関わり並行して開発を進める体制が迅速に組まれ、「マップ部分」の開発、「情報ウィンドウ」の開発など、機能ごとに実装を進めていきます。デザイナーとも近い距離で連携することで短期集中での開発を実現させることができました。
そして1月26日、見やすさ・使いやすさ・わかりやすさの全てを改善した「災害情報マップ」のアップデート版がリリースされます。
後日フロントエンジニアの開発担当が「自分たちが手を動かして開発しながら各所と連携することができ、チーム力を感じることができた」と振り返ったように、スピード感と柔軟な対応力が発揮された開発でした。
バックエンドエンジニアたちによって正確性と速度が向上
フロント面のアップデートが進む一方、バックエンドのエンジニアたちはデータの取り扱いに悩まされていました。「避難所がどこに開設されているか」「給水所がどこにあるか」など、取り扱うデータは種類も数も膨大でした。
これらのデータ作成から正確性のチェックに至るまで、当初は災害情報マップチームで全てを対応していました。しかし、避難所や給水所の情報などは日々更新されるものであり収集にもチェックにも手間がかかるため、公開までに時間を要してしまいます。
改善を望む声が多く上がってきたこともあり、バックエンドのエンジニアたちでデータフローの改善に取り組むことに。
まずは独自でデータ作成することをやめ、データの大元を放送で利用しているものへと切り替え、それをシステムで自動化する仕組みを開発することを決定します。放送で利用しているデータを使うことで、新しくデータを作成する必要がなくなる点はもちろん、放送用途などの既存データフローのチェックを通るため正確性が担保されます。
また、放送用のデータを放送とは異なるデジタルマップで用いることになるため、データを自動でマッピングできる形式に変換する仕組みの開発を4人ほどのバックエンドエンジニアが関わり協力して取り組みました。
「マッピングするために、場所の緯度経度はどのように付与するか」「すべてシステムで処理するのではなく、データの重要な部分はやはり人の目でチェックした方が良いのではないか」など、要件定義の議論を重ねながら丁寧にシステム仕様に落とし込んでいき、避難所の情報が自動掲載できるようになったのが1月31日。給水所の自動掲載ができるようになったのは2月19日のことでした。
このデータフローの自動化で短時間で正確な情報の公開が可能となり、データの確認を担当していた方からは1日のチェック時間がおおよそ10分の1程度になったとの効果を聞きました。
こうして完成した「多くのデータの正確性を保証し素早く提供する」を目指して組み上げたシステムは今も動いています。
開発時にチームとして考えていたのは、データを起点に未来に向けて長く活用できるシステムにすること。放送のためには様々なデータが集まりますが、それを利活用していく上ではデータ基盤の構築こそがポイントになります。データの重要性を改めて実感するとともに、その高度化に向け取り組んでいくべき課題を実感できた開発となりました。
以上が能登半島地震の発生直後から約2か月間に渡る「災害情報マップ」のオモテとウラ、それぞれで連携・開発していたエンジニアたちの対応が一区切りを迎えるまでのお話でした。
このときに提供した災害情報マップのデータのうち、発生から1週間あまりの間に確認された被害や状況についてはこちらのサイトから見ることが出来ます。
ではここからは、能登半島地震が発生する以前、もともと豪雨災害を想定して開発された「災害情報マップ」の原型が出来上がるまでの経緯と、現在に至るまでの活用事例の報告を、このコンテンツを企画した小椋からさせていただきます。
「災害情報マップ」企画担当 小椋崇広
2001年入局。NHK報道局映像センター所属。
報道カメラマン。大学生時代は北海道大学で雪崩の研究。大学院時代に有珠山が噴火し、研究者として現地を調査。そこでNHKの災害報道と出会ったことがきっかけで報道カメラマンに。
開発提案のきっかけとなったのは、熊本豪雨取材でのある出来事
全国各地で毎年のように起こる豪雨災害。自治体から避難指示などが出されていたにも関わらず、避難が遅れ、多くの人が被災しています。
NHKでも命を守る行動につなげるための災害報道に取り組んできましたが、2018年の西日本豪雨発生の際に実施した住民避難アンケートでは、「テレビ・ラジオからの情報で避難した」と回答した方は、避難者全体のわずか4.5 %にとどまっていました。
そんな背景とあわせ、報道カメラマンとして現地入りした令和2年7月豪雨(熊本豪雨)での取材経験をきっかけに、私は強い気持ちを持って「災害情報マップ」の開発を提案することになります。
2020年7月3日深夜から4日にかけ、球磨川で流域の大部分にかかるように線状降水帯が発生して氾濫。人吉市の市街地が浸水するなど、県内では災害関連死を含めて67人が犠牲となり、今も2人の行方がわかっていない熊本豪雨災害。
私が今も印象に残っているのは、カメラマンとして現地入りし、上記の映像を撮影した直後のこと。家族4人全員が長靴の中まで泥まみれになり、公園の水飲み場で子ども2人の足を洗っていた父親を取材したときの出来事でした。
マンションの上層階にある自宅は被災を免れたが1階部分は完全に浸水、水が引いたところでやっと外にでることができたと話すその父親から、「知り合いが心配だ、浸水した地域はどこか」「避難所はどこにあるのか」と、問い詰めるように質問を受けたのです。
私は初動のクルーとして、東京から鹿児島空港を経由し、4日の午後5時前に熊本県人吉市中心部に入っていました。大雨の影響で多くの道路が通行止めとなっていた影響で、NHKのカメラマンで現場に入ったのは私が最初でした。
被災地の状況を俯瞰して知る術はなく、避難所の開設状況も把握できないまま動いていたため、私はその父親に対し、ここに来る途中で知った情報を教える程度が精いっぱいでした。
死傷者が出た現場など、その時点でも報道自体は多くされていたと思います。しかし、被災した人が必ずしもテレビを見る余裕があるわけではありません。きめ細かい情報を十分提供できていたとは、あの場にいた私自身は、今でも言うことができません。
あわせて、放送には時間の問題もあります。被害を伝える取材情報、カメラマンが撮影した現場映像など、NHKには災害に関する多くの情報が集まりますが、放送の時間の中で全てをお伝えすることは出来ません。感覚的には10撮影をして2、3放送されるかどうかといった程度です。
だからこそ、「どこで」「どんな被害」が起きたのかをわかりやすく、時間や場所に縛られることなく情報を届けることができれば、より被災者の役に立つことができるのではないか、という思いを強くしました。
そこで、命を守る災害報道とは何かを模索し、必要な情報をデジタルマップで可視化して提供したいと提案したのが、「災害情報マップ」という企画だったのです。
開発が加速度的に進むことになった「インターネットでの社会実証」
企画は採択され、プロトタイプの開発に取り組むことになりましたが、カメラマン出身の私にマップ開発に関する知識はありません。まずは知見を持ったメンバーを集めるところからの始まりでした。
開発の転機となったのは、2023年2月にNHKが実施した「インターネットでの社会実証」(これまで主に放送で果たしてきた役割・機能を、インターネットを通じてどのように果たせるのか)で検証するサービスの1つに、「災害情報マップ」のコンセプトが採用されたことでした。
熊本豪雨災害を例に、映像をマップ上で時系列に可視化し、過去の災害を追体験することで、将来の「もしも」の時に避難の行動変容を促すことはできるのか。
私を含め全国から応援で入ったカメラマンが撮影した映像や視聴者から寄せられた映像は、40分収録のディスクで150本以上にもおよびましたが、私もマップの担当者ひとりとして全てに目を通し、プロットしていきました。
社会実証では、テレビを持っていない方や日常的に利用されていない方など約1300人を対象に、実際にサービスを触っていただいた上で、その効果に関するアンケート調査を実施。 結果は、「もしも」の時に、避難の気持ちが強まる(「行動変容が生じる」と回答した方は全体の91.6%)という高い評価でした。そして、全体の8割近い人がリアルタイムでこのマップを利用したいと答えてくれました。
この社会実証のためのマップ開発の過程において、経験豊富なエンジニアや災害報道の中核を担ってきたデスクなど各分野のスペシャリストと連携し、意見を言い合えたことで、「災害情報マップ」の開発は加速度的に進んでいくことになります。
2023年7~9月には、放送での展開を前提とした災害情報へのマッピングのトライアルを5回実施します。マッピングのために現場のカメラマンには、スマートフォンで表示した緯度経度の情報を映像に写し込むなど、通常の撮影とは異なる対応をお願いしました。
緊急度が高い災害現場ほど時間に余裕がなく、緊迫した状況になりますが、そのような現場からも「被災者のために」と入局から間もない若手のカメラマンが積極的に情報を送ってくれたのは、個人的にもうれしかったです。
そういった経緯や多くの協力を経て開発が進められた「災害情報マップ」は、前半で紹介したとおり2024年1月1日発生の能登半島地震の際に大いに活用されることになったのです。
テレビと連動することで災害報道を深化させた事例の紹介
能登半島地震以降も、もちろん「災害情報マップ」は機能や利用方法に関してのアップデートを続けています。去年は大雨特別警報や台風などで計5回公開されてきました。
①山形県の大雨特別警報 (7月25日)
②台風5号 (8月12日 岩手に上陸)
③台風7号 (8月16日 千葉に接近)
④台風10号(8月29日 鹿児島に上陸)
⑤石川県の大雨特別警報 (9月21日)
ここでは3つほど展開の事例を紹介させていただきます。
(1)テレビでの解説と展開 山形県の大雨特別警報
7月25日午後1時、山形県の酒田市と遊佐町に大雨の特別警報が発表された際、被害情報などを100か所ほどプロットした「災害情報マップ」を公開しました。
午後7時の全国放送では、マップを使用して被害の状況を伝えるとともに、今後の注意点をお伝えします。あわせて、画面の右上に「災害情報マップ」のQRコードを表示し、視聴者がスマートフォンからもマップを確認できるようにしました。
都道府県別の「災害情報マップ」へのアクセスデータなどを調べたところ、山形県のユーザーの視聴時間は全国平均よりも倍近くの長さに。発災地域の方の「災害の状況を知りたい」といったニーズに一定程度応えることができたのではないでしょうか。
(2)ハザードマップの事前確認の促進 台風10号
日本列島に記録的な大雨をもたらした台風10号では、各地で浸水被害が発生しました。
「災害情報マップ」にプロットされた被害状況を確認したところ、少なくとも大分県、香川県、三重県、岐阜県、静岡県、神奈川県の6県で、車が水につかったり、冠水した道路を走行したりする事例が確認されました。
「災害情報マップ」では、「洪水想定最大規模」や「土石流」など、6種類のハザードマップを重ねて表示することができます。浸水被害があった場所をハザードマップの範囲と重ね合わせると、すべての地域において、川の近くや周囲より低い土地などで浸水リスクを指摘されていたことが判明しました。
記者は、映像にあった浸水車両の所有者を探し出し、車が水に浸かった状況をリポート。自治体が作成しているハザードマップをみて、自身が住んでいる地域の浸水リスクを事前に確かめておくことの重要性を訴えました。
(3)防災士や郵便局員との連携 石川県の特別警報など
災害が発生した直後は、取材クルーが現場に近づくことは難しい場合がほとんどです。
9月21日に石川県の輪島市や能登町などで発表された大雨の特別警報で「災害情報マップ」を展開した際は、浸水被害などの映像を30か所ほどマッピングしましたが、全体の6割は視聴者の方から寄せられた映像でした。
特別警報の発表直後も、能登町で氾濫した川の緊迫した様子がいち早くNHKに届けられましたが、撮影したのは地元の防災士の方。NHKでは、全国の防災士会の支部や防災士の団体など計47の組織と災害時の情報提供などの連携協定を結んでいますが、それが発揮された形となりました。
また、日本郵政・日本郵便とも防災・減災に関する連携協定を結んでいます。2024年8月の台風10号の際は、高知県内にある4つの郵便局の職員の方から、増水した川の様子や激しく降る雨の映像などを送っていただきました。
このように「災害情報マップ」を活用して、地域の方々と連携した災害報道が実現していく可能性が一層高まっていくのではないでしょうか。
「災害情報マップ」の今後の展望と果たすべき使命
今後の展望として私が考えているのは、気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」や災害情報「キキクル」など、気象に関するデータも地図に重ねる開発を進めていくことです。
NHKの提供する情報と映像に、気象データなどがデジタルマップでわかりやすく可視化されることで、より多くの人が災害を「自分ごと化」して捉えることができるようになるのではないでしょうか。
また、被災者向けの支援物資や医療支援などライフラインに関する情報については、テレビで放送される情報とデータ連携し、「災害情報マップ」に表示されるよう既に整備を進めています。
24時間365日、災害に即応して寝る間も惜しんで取材する記者たち。リスクが伴う災害現場で1つでも多くの映像を記録し、送り届けるカメラマンたち。被災者に寄り添い、命を守るという「報道」の使命を私たちが果たすためには、場所や時間にとらわれず必要な情報を届けられる「災害情報マップ」の持つ役割が、今後ますます大きなものになっていくと信じています。
このマップがより多くの人に認知され、利用されるようになるためには、より良いユーザーインターフェースの開発や持続可能な体制の構築など、まだまだ多くの課題が残っているのは事実です。しかし、1つ1つ乗り越えていくことで、被災地にいる人にとって本当に役立つ災害報道の実現につながるよう引き続き取り組んでいきたいと思います。