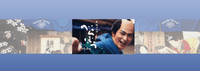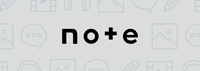大河ドラマの音楽はどうやって作られる? 「べらぼう」音楽制作の舞台裏
1963年の開始以来、60年以上の歴史を持つ大河ドラマ。これまで、作品ごとに印象的な音楽が数多く誕生してきました。
特に番組の冒頭を飾る約2分半のメインテーマ(オープニング曲)は、タイトルバックとともに登場人物の生涯や歴史的背景を表現する、まさに大河ドラマの顔とも言える存在です。
一年間にわたって物語を彩り、視聴者をその時代へと誘う音楽は、いったいどのように作られているのでしょうか。今回は現在放送中の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(以下、「べらぼう」)を舞台に、大河ドラマにおける音楽制作の裏側をご紹介します。
(聞き手:NHK広報局note編集部)
1.大河ドラマにおける音楽の重要性
音楽はどんなドラマにおいても欠かせない要素の一つですが、大河ドラマで特徴的なのはその「数」です。多様な登場人物、場面、時代を表現するため、音楽のバリエーションも曲数もほかのドラマに比べて格段に多くなり、制作期間は2年近くに及ぶことも。
そして、なんと言っても重要なのはメインテーマの存在です。フルオーケストラによる壮大な演奏でドラマの世界観を表現すると同時に、聴いただけでその作品が思い浮かぶような、番組の象徴としての役割も担っています。
「べらぼう」の舞台は、町人が経済や文化の担い手として活躍した江戸時代中期。音響統括を務める佐々木敦生は、音楽制作にあたって3つのコンセプトを重視したと語ります。
作曲を担当したジョン・グラムさんと何度も意見交換を行いながら、コンセプトを抽出していきました。
1つ目は「挑戦し続けるエナジー」です。身分も財産も持たない主人公・蔦屋重三郎(以下、蔦重)は、多くの壁にぶちあたりながら何度も立ち上がり、挑戦を続けます。そんな彼の根源的な強さを表現する音楽が必要だと考えました。
2つ目は「光と影のコントラスト」。光輝く場所があれば、その影もある。光がまぶしければまぶしいほど、影は深く濃くなっていく…その両面を音楽で丁寧にすくい取りたいと考えたのです。
そして3つ目は「町人の躍動感」。今回のドラマの主役は武士ではなく、江戸の町人です。町人ならではのフットワークの軽さや躍動感を表現してみたいと思いました。
さらに、ストーリーの変化を表現するうえでも音楽は重要な役割を担っています。
実はこれまでの大河ドラマに比べると、「べらぼう」では舞台があまり変わりません。戦への遠征や、国元から都に行くということもなく、蔦重はずっと江戸にいます。ビジュアルでの変化が少ないので、「音楽や音でどう変化をつけていくか」が重要なミッションとなります。
一方、登場人物は非常に多いのですが、立場や境遇といったキャラクターごとに「異なる」部分と、それぞれが抱く志や抱える葛藤など「共通する」部分があるのが特徴的です。それらが重層的に絡み合って物語が進んでいきますが、音楽的には、「異なる」部分についてはコントラストをつけ、「共通する」部分については統一感を持たせるのが重要ではないかと考え、ジョン・グラムさんと構想を練りました。
今回のドラマでは、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎が築かれていった過程と、生み出した人々の思いを「時空をまたいでいくような壮大なスケール感を持った音楽で彩りたい」と語る佐々木。
ジョン・グラムさんに作曲を依頼した理由についても聞きました。
「べらぼう」には合戦は出てきませんが、武士による「刀」ではなく、町人による「筆」での戦いが描かれていきます。その戦いの結実として生まれた書籍や浮世絵は、海を越えて世界に広がり、今もなお人々を魅了し続けています。
ジョン・グラムさんは、歴史や美術に造詣が深いだけでなく、浮世絵もこよなく愛されていて、江戸文化が世界を魅了していくムーブメントを自らすでに体感されていました。そんなジョンさんであれば、蔦重が挑んだ「筆」での戦いと、そこから生まれていったカルチャーをグローバルな視点で壮大に描き切って頂けるのではと思い、依頼させて頂きました。
蔦重の挑戦、彼を取り巻く人々の思い、花開いていく江戸文化――これらの要素を具体的にどのように音楽に落とし込んでいったのか。
ここからは、メインテーマをはじめ劇中の音楽を手がけたジョン・グラムさんのインタビューを通して、作曲に込めた思いに迫ります。
ジョン・グラム
アメリカ・バージニア州出身。文学、歴史、芸術、そして日本文化をこよなく愛する作曲家。イギリスで歌とオーケストラ作曲を学び、アメリカのウィリアムズ大学、スタンフォード大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で音楽を専攻。数多くのハリウッド作品のオーケストレーションを手がけた経験を生かし、革新的なハリウッド音楽制作手法を用いて、哲学的かつダイナミックな音楽描写を得意とする。代表作は大河ドラマ「麒麟がくる」、『キングスグレイブ ファイナルファンタジーXV』など。
2.メインテーマに込めた思い
――「麒麟がくる」に続き、大河ドラマの音楽を担当するのは今回で2作目ですね。オファーを受けた時の心境はいかがでしたか?
知らせを受けた時、音楽プロデューサーから冗談めかして「悪いニュースがある。この先1年くらい寝られなくなるよ」と言われたんです(笑)。その時はレストランにいたのですが、あまりにうれしくて、その場で席を立ってくるくる回ってしまいました。
「麒麟がくる」は自分にとって挑戦も多かったですが、本当にすばらしいプロジェクトだったので、正直こんな機会は一生に一度しかないだろうと思っていました。ですから、再び大河ドラマに携わることができると知ってとにかく感動したのを覚えています。
――大河ドラマの音楽を作るおもしろさというのはどんなところでしょう?
大編成のオーケストラのために曲を書ける楽しさもありますし、一つの作品の中で喜びや悲しみ、誇り、死など幅広いテーマを表現できるのが魅力だと思います。登場人物の体験や物語を音楽で作り上げていくことができるというのは、とてもやりがいを感じます。
――「べらぼう」のメインテーマは冒頭から力強く華やかな曲となっていますが、どのような着想から生まれたのでしょうか。
私の中で最初にイメージとしてあったのは浮世絵でした。浮世絵は江戸時代に世界中に広がって、現在はロンドン、パリ、ボストンなどいろいろな美術館で展示されています。海外の人々が日本という国に興味を抱くようになったきっかけの一つだと思いますし、私自身浮世絵が大好きです。
一方で、250年以上続いた平和というのも江戸時代の特色の一つだと感じていて、その時代の栄華や輝きを音楽で表現したいという思いもありました。
制作チームの「楽しい曲にしたい」という言葉に共感し、ダイナミックな時代を描くにふさわしいエネルギッシュで明るい曲にしようと考えて、このメインテーマが生まれました。
――曲中には特徴的な楽器が使われているそうですね。
「ツィンバロン」というハンガリーの楽器を使用しています。見た目はピアノに似ていて、弦をハンマーでたたいて演奏するのですが、キラキラした響きが特徴的な楽器です。
江戸時代は豊かな時代というイメージがあり、そのきらびやかな雰囲気を表現するのにぴったりな楽器だと思いました。
――作曲に最も時間をかけたのは、やはりメインテーマですか?
そうですね。メインテーマは番組全体の主題や雰囲気を表現しなければならないので、一番時間を費やしました。先ほどお話ししたきらびやかなイメージというのは早い段階で思い浮かんでいたのですが、それをどう表現するかというところで、ピアノやチェロ、グロッケンシュピールといったさまざまな楽器を加え、アレンジしていきました。
実は当初、この曲の最後はゆるやかに終わるイメージだったのですが、制作チームから「最後を大きく、力強いイメージで締めてほしい」と要望がありました。蔦重や市井に生きた人々の意志の強さを表現するうえで、そのアイデアは非常に効果的だったのではと感じています。
3.インスピレーションを受けた日本文化と登場人物
――日本の歴史や文化はどのように学ばれたのでしょう?
私はアメリカで言う“nerd”、つまり“オタク”なんです(笑)。アメリカの図書館では日本の書籍も閲覧できるので、とにかく大量の本を読みあさりました。国立国会図書館のデジタルアーカイブを翻訳して調べたり、カリフォルニアの博物館で開催された浮世絵の展示を見たりしたのも参考になりました。
――浮世絵がお好きということですが、特に好きな浮世絵師はいますか?
特に好きなのは歌川広重と葛飾北斎です。どちらの絵師も日々の暮らしを営むふつうの人々や自然の風景を描いているところが魅力的で、田舎道を旅する人々、夜の江戸の町で明かりやにぎわいを楽しむ人々、雨の中、橋を渡る人々…そうした情景の一つ一つに心を揺さぶられます。
「べらぼう」の音楽制作を開始した時、歌川広重の「名所江戸百景・猿わか町よるの景」という作品(木版画)を購入しました。スタジオに飾って、毎日眺めながら江戸時代に思いをはせています。
それから葛飾北斎の「冨嶽三十六景《甲州石班澤》」という作品も好きな作品の一つです。北斎の魅力は人と自然を並べて描く手法にあり、彼の作品には“はかなさ”と“永遠”とがせめぎ合うような感覚が不思議と息づいているように感じます。
――「べらぼう」にゆかりのある場所や撮影セットなども見学されたそうですね。
かつて吉原があった場所を訪れて、見返り柳や大門跡を見学しました。その後に東京で開催されていた「べらぼう」の展示にも足を運び、皆さんが楽しんでいる様子も見ることができて良かったです。
NHKで撮影セットを見学した際には、監督が町人の衣装やカツラを用意してメイクアップまでしてくれて(笑)。貴重な体験をすることができました。
――登場人物の中で作曲意欲をかき立てられたキャラクターはいますか?
まずはやはり蔦重ですね。お金もない、力もない、家柄もない…そんな境遇でも決して諦めずに道を切り拓いていったという点で尊敬するキャラクターです。
それから、吉原の女性たちにも影響を受けました。私自身、妻と3人の娘がいるので、当時吉原の女性たちがどんな気持ちで生きていたのか、どれほど苦しかっただろうということを考えるととても心を揺さぶられるものがあり、それをどう音楽で表現していくかということを考えていました。
――吉原の描き方には、視聴者から大きな反響がありました。
私にとって、吉原の描写は今回のドラマで最も敬意を表したい部分です。女性たちにとって吉原は逃れることのできない、まるで監獄のような世界だった…「べらぼう」ではそこをしっかりと描いています。これまで吉原を描いた作品はいくつもありますが、華やかさや楽しさ、美しさを描いた作品が多かった中で、過酷な環境やそこで生きる女性の苦しみを描くのは、NHKとしても勇気のいるアプローチだったのではないかと思います。
――瀬川の花魁道中のシーンで流れた音楽も叙情的で印象深い曲でしたが、この曲にはどんな思いをこめられたのですか?
吉原は悲しい場所でありながら幻想的で美しい場所でもあり、そこをまさに音楽で表現しようと意識しました。チェロをメインで使用したのは、この楽器がもつ曲線や旋律に女性的な優雅さがあると感じたからです。長い旋律をゆったりと歌うような調べで奏でながら、その中にキラキラした音も盛り込み、美しい花魁道中の様子を表しました。
瀬川役の小芝風花さんの演技は圧巻でしたね。多くの花魁が吉原を離れることができない中、瀬川はやっと離れることができる…しかしそれは同時に蔦重との別れを意味していて、複雑な感情があったと思います。とても大事なシーンなので、音楽が良い形でその世界観を表現できていたらうれしいです。
――ほかにもご自身の曲が使われたシーンで印象に残っているものがあれば教えてください。
「山師」という曲があります。英語版のタイトルは「Gambler」というのですが、蔦重にはリスクを取って賭けに出るところがあって、そんな彼の側面を表現したいと思いこのタイトルをつけました。三味線や琴を使ってエネルギーに満ちあふれた様子を表現した曲なので、多くのシーンで使われていてうれしいです。
4.蔦重という人物を音楽で描く
――今回の音楽制作において、「麒麟がくる」との違いはありましたか?
「麒麟がくる」は戦国時代が舞台で、家族や愛する人との関係性、そして戦や死というものを描いていましたが、それに比べると「べらぼう」はだいぶトーンが違う作品だと感じています。
蔦重という一人の人物の物語であり、彼をきっかけに浮世絵が世界中に広がっていく。作曲家として、彼のような“プロデューサー”は重要な存在だと思います。音楽プロデューサーがオーケストラを編成するように、蔦重も人々をつなぐ存在であり、彼を起点に多くの浮世絵師が花開いていきました。彼がいなければ、浮世絵がここまで海外で一般的な存在にはなっていないのではないでしょうか。
“プロデューサー”という存在に対して音楽を作っていくという意味では、「麒麟がくる」の時とはちょっと違うアプローチだったのではないかと思います。
――主演の横浜流星さんの演技についてはどのように感じましたか?
外見的な魅力ももちろんですが、彼の演技からは圧倒的な知性を感じますね。私は知的な方に対してひかれる部分があるんですけど、彼の演技には力強さがありながら聡明さも感じられて、とても魅力的な俳優だと思います。
彼が演じる蔦重という人物は内面に複雑な感情を抱えていて、それを音楽で表現したいと思い、今回のドラマではあえてリズムや響きが複雑な曲を書きました。その複雑さこそが、横浜さんの持つ知性や蔦重というキャラクターに似合うと思ったんです。
――映画音楽も数多く手がけられていますが、大河ドラマならではの魅力とは何だと思いますか?
これまで多くの作品に携わってきましたが、大河ドラマの魅力の一つはやはり歴史を描いているということ。歴史が大好きな私にとっては心動かされる作品です。
そして何よりすばらしいのは、監督、プロデューサー、脚本家、美術スタッフなどチーム全員が高い熱意を持って取り組んでいることだと思います。アメリカのテレビドラマにもすばらしい作品はたくさんありますが、2年にわたる制作期間の中で全員が一丸となって同じ熱量でプロジェクトに取り組むことができるのはなかなかないことです。だからこそ唯一無二の作品が生まれるのだと感じています。
5.最後に
大河ドラマにおける音楽制作の舞台裏、いかがでしたか?
今回の記事を通して、映像を彩る音楽がいかにして生み出されているのか、また歴史や文化を描く大河ドラマならではの作曲のこだわりなどを感じていただけたらうれしいです。
5月から新たな舞台の幕を開けた「べらぼう」ですが、物語の展開に伴って今後もさまざまな音楽が登場します。作品全体で100~120曲に及ぶ音楽を制作していると語るジョン・グラムさん。どの場面でどんな曲が使われているのか、ぜひ音楽にも注目してお楽しみください。
▼番組公式ホームページ
▼音響統括・佐々木の過去の記事はこちら👇