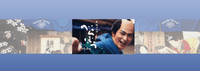浮世絵「ポッピンを吹く娘」が約43年ぶりに再発見!展覧会開催の裏側にせまる
江戸時代中期、天才絵師たちを世に送り出したことで知られる出版人・蔦屋重三郎。彼を主人公にした大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(以下、「べらぼう」)と連携した特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が、6月15日まで東京国立博物館で開催されています。
<特別展>「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」
会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)
会場:東京国立博物館 平成館
主催:東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション
https://www.event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=1807
会期中の5月12日、こんなニュースが飛び込んできました。
浮世絵の名作として知られる喜多川歌麿の「ポッピンを吹く娘」の初期作品が、約43年ぶりに再発見された――。
「ポッピンを吹く娘」はガラス細工のおもちゃで遊ぶ町娘を描いた版画で、蔦屋重三郎が版元として手がけた一作です。今回発見された作品は長らく行方不明となっていましたが、特別展を契機に日本にあることが判明し、急きょ展示が決定しました。
歴史や文化に焦点をあてる大河ドラマは、時にこうした意外な発見につながることがあります。今回は、作品が発見されてから展示に至るまでの経緯や、展覧会ならではの歴史の伝え方について、特別展の企画・運営を担当する2人に話を聞きました。
眞弓 敬次
NHK メディア総局 展開センター所属。2013年入局。これまで公開番組等のイベント中心の業務を担当し、現在は展覧会業務を担当。
梶谷 遥
NHKプロモーション所属。2020年入社。入社から現在までイベント事業の部署に所属し、主に展覧会業務を担当。
大河ドラマの価値は「エンタメ」だけじゃない
──「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎は、名高い浮世絵師を見いだし、数々のベストセラー作品を生み出した人物ですが、今回の大河ドラマで初めて知った方も多いのではないでしょうか。
眞弓 そうですね。ほかの歴史上の有名人物に比べると、蔦屋重三郎はその生涯が一般的にほとんど知られていません。例えば織田信長や徳川家康が主人公のドラマでは、「本能寺の変で死去する」「天下統一する」といった史実が分かっているので、そのプロセスをどう描くかが見どころになります。しかし、蔦屋重三郎については、次にどんな展開が待っているのか予測できないので、そういう意味では「べらぼう」は結末を誰も知らない物語と言えるかもしれません。
また、舞台も従来の大河ドラマと全く異なります。戦国時代の戦場や広大な国土を舞台にするのではなく、江戸という一つの街の中、それも吉原や日本橋という非常に限られたエリアが中心です。そこで蔦屋重三郎が取り組んだ出版という「文化的活動」を通じて、当時の人々の生活や価値観が描かれています。戦や権力争いではなく、市井の人々の暮らしや創造性に焦点を当てているというのは大河ドラマとしては珍しいと思います。
梶谷 「べらぼう」は、現代にも通じるビジネスパーソンの物語としても見ることができるのではと思います。蔦屋重三郎は今でいうスタートアップの経営者やプロデューサーのような存在と捉えることができますが、優れたクリエイターを見出し、新しい表現方法を開拓し、マーケティング戦略を練って市場を開拓していく姿は、まさにやり手のビジネスパーソンそのものですよね。
また、人間関係の描き方も現代的です。戦国時代の大河ドラマでは「家臣と主君」「敵と味方」という関係性が中心になりますが、「べらぼう」では友情や恋愛、仕事仲間との葛藤や慣習との衝突など、現代を生きる私たちにも共感できる部分があると思います。
──大河ドラマにはエンターテインメントとしての側面に加え、歴史や文化を伝えるという意義があると思います。眞弓さんはどう考えますか?
眞弓 大河ドラマによって、歴史への関心のすそ野が広がっている点が大きな意義だと考えています。放送期間が1年間と長いこともあり、ドラマに関連するさまざまな書籍や情報がでて、イベントも開かれます。作品ごとに全国のさまざまな場所が舞台になるので、その地域の歴史や文化に関心を持っていただくきっかけにもなるのではと思います。
──その中で、お二人が携わっている今回の展覧会はどのような位置づけになりますか?
眞弓 展覧会は、ドラマと相互に補完し合う関係にあります。例えば、大河ドラマで物語の背景を知ることで展覧会での鑑賞がより深まり、展覧会で実物を見ることで大河ドラマの世界観がより鮮明に感じられるようになる…そんな効果があると思っています。
──展覧会と大河ドラマでは、同じ歴史・文化を題材にしていても伝え方や魅力が異なると思います。その違いについて教えてください。
眞弓 ドラマと展覧会は、同じ人物を主役に据えながらも全く異なるアプローチで魅力を伝えています。大河ドラマは時間軸に沿って物語を展開し、登場人物の感情や葛藤を通じて歴史を体感するもの。視聴者は毎週、物語の展開に一喜一憂しながら歴史を追体験していきます。
一方、展覧会は作品を軸にした空間的な体験です。ドラマでは数秒しか映らない浮世絵の細部まで、自分のペースでじっくり鑑賞できるのが展覧会の醍醐味です。ドラマが時間の流れの中で歴史を伝えるのに対し、展覧会は作品を通して五感で歴史と対話できる場を提供しています。
梶谷 私が考える展覧会の魅力は、実物を肉眼でじっくり見られることです。江戸時代の本や浮世絵は、テレビやネットもない当時の数少ない娯楽で、恐らくその存在価値は現代の感覚とは大きく異なっていたはずです。
一方で、おもしろい話を楽しむことや、人気者や有名人が描かれた絵を手元に持っておきたいという感覚は現代にも通じるところがあるかと思います。実際に江戸時代の人々が手に取ったであろう実物を目の当たりにしながら、当時の生活に思いをはせることができるのも、展覧会の魅力です。
展覧会をきっかけに、歴史的な文化財を発見
──江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿の版画「ポッピンを吹く娘」の初期刷りが、特別展「蔦屋重三郎」をきっかけに発見されたそうですね。
眞弓 「ポッピンを吹く娘」は、喜多川歌麿がさまざまな女性の表情や仕草を描いたシリーズ「婦人相学十躰」の中の一作として出版されました(同シリーズは後に「婦女人相十品」と改称)。
今回新たに見つかった作品は「婦人相学十躰」と書かれていることから、東京国立博物館が所蔵する「婦女人相十品」という表記の作品よりも古く、初期に刷られたものだと判断されました。
展示期間:2025年5月20日~6月15日
浮世絵の木版画は、何百枚も同じ絵を刷ることができる画期的な技術ですが、刷る枚数が増えるほど木版は摩耗していきます。そのため、摩耗のない初期のものは線がシャープで色彩が鮮やかなことから、希少価値が高いのです。
これまで「ポッピンを吹く娘」の初期刷りは、世界中でホノルル美術館に収蔵されている1点のみが確認されていました。ところが、日本で新たに見つかったというのですから、これは美術界においてはビッグニュースです。
──どのような経緯で見つかったのでしょう?
眞弓 展覧会の開催を知った東京の美術商の方から、展覧会の会期が始まる直前にこちらの作品について東京国立博物館へ情報提供があり、同館研究員の方々が調査した結果、貴重な初期刷りと考えられる作品であることが判明したのです。
──発見からわずか2か月で展示が実現したのも驚きです。通常、こうした貴重な作品の展示には相当な準備期間が必要だと思いますが。
眞弓 そうですね、展覧会の作品借用は数年前から依頼することがほとんどなので、この短期間で展示されるのは通常ではあり得ません。今回は東京国立博物館の迅速な調査と、所有者の理解と協力があってこそ実現しました。
そもそも有名作品の新たな発見自体がめったに起きないことですし、「ポッピンを吹く娘」は浮世絵の中でもトップクラスの名作です。しかも、今回のように極めて良質な状態で見つかるのは、異例中の異例のことだと思います。
梶谷 この異例の展示が実現した背景には、作品の状態の良さも大きく関わっていたと思います。蔦屋重三郎や江戸の人たちが見たであろう色がほぼそのまま保たれており、保存状態も展示が可能なコンディションであると考えられました。このタイミングでこれほど状態の良い作品が見つかるという奇跡的な巡り合わせに、私たちスタッフ内では「蔦重が天国から見ていて、奇跡的なシチュエーションを演出してくれたのではないか」と冗談交じりに話しています。
大河ドラマのセットを博物館に展示
──具体的な展示内容についても教えてください。
眞弓 まずは、今回発見された初期刷りと考えられる「ポッピンを吹く娘」は見どころの一つです。また、大河ドラマに登場する作品が数多く展示されている点も特徴の一つだと思います。平賀源内のエレキテルや「吉原細見」(吉原の案内本)、北尾重政、勝川春章、朋誠堂喜三二、恋川春町、喜多川歌麿、山東京伝などの作品がめじろ押しです。
通期展示(※会期中、場面替えあり)
梶谷 蔦屋重三郎の戦略を時系列で見られることも醍醐味だと思います。例えば、喜多川歌麿にはそれまで主流だった全身像ではなく上半身に寄った作品を描かせたり、東洲斎写楽にはリアルな役者絵を描かせたりと、その時々の挑戦があります。大河ドラマでも描かれていますが、展覧会では同じ空間でそういった違いを見ることができます。
蔦屋重三郎は「コンテンツビジネスの風雲児」の展覧会タイトルの通り、江戸時代において前例のない出版業を展開し、多くの才能を発掘しました。常に新しい表現方法を追求し、当時の文化を大きく動かした革新性が展覧会を通してお伝えできると思います。
──展示にあたって工夫した点はどんなところですか?
眞弓 浮世絵の基礎知識がなくても楽しんでいただけるように、各展示で当時の時代背景や制作エピソードなども紹介しています。大河ドラマを見てから展覧会に来ると「あのシーンの作品がこれか」と発見がありますし、展覧会を見てから大河ドラマを見ると「展示で見た浮世絵が制作されるシーンだ!」と理解が深まるかなと思います。どちらを先に体験しても、もう一方の体験がより豊かになる。そんな関係性を大切にした展示構成を心がけています。
梶谷 一方、浮世絵に詳しい方には、専門的な視点からの楽しみ方もご用意しています。蔦屋重三郎の革新的な出版戦略や、彼が手がけた作品の技術的特徴、例えば刷りの品質や色使いの革新性といった専門的な側面も展示で解説しています。これまで個別に注目されることの多かった作品が、蔦屋重三郎という一人のプロデューサーを切り口に展示として構成されることで、浮世絵史の新たな側面が見えてくるものになっています。
眞弓 展示室の最初と最後には、大河ドラマのセットを手掛けた美術チームに協力してもらい、実際に使われたドラマのセットを持ち込みました。大河ドラマを見ている方には「吉原の大門だ!」という満足感を、見ていない方には江戸時代の空間を体感していただけたらと思っています。
(展示室の入り口にある吉原大門)
──展示室にドラマのセットを再現するというのは斬新な試みですね。
梶谷 この規模での展示はNHKとしても前例がない取り組みなので、再現にあたっては気をつけるべき点の洗い出しから始まり、多くの調整が必要でした。ドラマセットは撮影用に作られたものですから、一般の来場者が楽しめる展示物として再構築する必要がありました。
最後の部屋に展示した日本橋の「耕書堂」の中には実際に入ることもできますし、近くにある橋の先には市中の風景を大型スクリーンで映し出すなど、部屋全体で日本橋を感じられるように仕立てました。この空間は写真撮影が可能なので、ぜひ江戸の日本橋の雰囲気を楽しんでいただきたいと思います。
一期一会の展覧会を、蔦重ゆかりの地で
──最後に、会場や来場者の様子から印象的だったことがあれば教えてください。
眞弓 作品一つひとつをじっくりと見る方が多く、展示の意図が伝わっているようでうれしく思います。ドラマのセット展示も、多くの方に喜んでいただいています。
梶谷 最初と最後の展示室に再現されたセットは、大河ドラマの撮影を行った今回だからこそ実現できたものです。江戸時代の空気感を肌で感じていただける特別な機会となっています。ドラマと併せて展覧会も楽しんでいただけるとうれしいです。
また、展覧会が開催されている東京都台東区は蔦屋重三郎のゆかりの地でもあります。放送100年というタイミングで、蔦重とも縁の深いこの台東区で展覧会が開催できたことも、何か運命的なものを感じます。
眞弓 展覧会は一期一会の貴重な場です。この作品たちが同じラインナップで並ぶことは、二度とないかもしれません。また、過去の大河ドラマを思い返しても、文化財になるような作品がこれほど出てくる大河ドラマはありません。1話ごとに作品が登場し、それが展覧会場で実際に見られる。このような大河ドラマとの連動を感じられる展覧会は、今までにはない新たな試みだと思いますし、皆さんが江戸時代の文化や歴史に触れるきっかけになったら良いなと感じます。
取材:那木 丈裕、山城 さくら(BRIGHTLOGG,INC.)