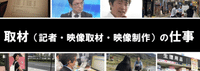沖縄が伝わっていない 地元出身の私たちが「沖縄戦80年プロジェクト」に込めた危機感
「首里城の地下にある日本軍の司令部壕跡を先端技術で体験してもらいたい」
「平和学習とは?沖縄戦の教訓とは?あらためて問いかけたい」
「これまであまり取材してこなかった、沖縄で戦死した全国各地の兵士について伝えたい」
戦後80年のことし、NHK沖縄放送局ではどんな番組を放送し、どんなプロジェクトを始めるか、さまざまな職種から集まったメンバーで考えてきました。若手から中堅、ベテランまで意欲的な提案が次々に出る中で、冒頭の3つの案は、どれも沖縄出身の記者やカメラマン、営業職員が手を挙げたものです。
80年前の沖縄戦では、日米両軍の激しい地上戦に巻き込まれて県民の4人に1人が命を落としました。6月23日の「慰霊の日」(組織的な戦闘が終結したとされる日)を中心に、ことしも各地でさまざまな追悼が行われます。
最近は「戦争についての番組や記事は、あまり見てもらえない」といった声が、制作現場から聞かれることもあります。そうした中で戦後80年の今をどう伝えていくか。沖縄局のみんなの取り組みと思いを、沖縄勤務2回目の、ニュースデスクの中村がご紹介します。
謎の日本軍司令部の地下壕に潜る
まずはカメラマンの加屋本 了。沖縄本島の中部にある西原町出身です。
これまで、NHKスペシャル「沖縄・空白の1年~“基地の島”はこうして生まれた~」や「戦後70年ニッポンの肖像 ~政治の模索~」などの番組の撮影を手がけてきました。地元、沖縄での勤務は2回目。常に笑顔を絶やさず冷静沈着、職場のみんなから頼りにされる「にーにー」です。
沖縄県の観光名所として知られる「首里城」の地下には、実は「第32軍司令部壕」という、太平洋戦争末期の沖縄戦で日本軍の司令部が置かれた地下壕があります。加屋本は去年、その最奥部を初めてテレビカメラで撮影しました。
深さおよそ10メートルから30メートルの地下にある司令部壕には5つの出入り口があって、南北に縦断するように坑道が掘られています。
この場所の地盤はアメリカ軍の攻撃に耐えられる強度を持っていたとされていて、また高台にあって周囲の戦況を把握しやすかったこともあり、ここに司令部がつくられ、当時、司令官など1000人以上がいたと考えられています。
この司令部壕への関心が高まったきっかけは、2019年に起きた火災による首里城の焼失でした。復元の話が進む中で、地下にある司令部壕もきちんと調査して保存・公開を進めるべきだという議論が出てきたのです。
この議論を取材する一方で沖縄局の取材班は、「まだ記録されていない司令部壕の中枢部付近が撮影できないか」という検討をしていました。実は過去に別の出入り口付近の撮影を行っていましたが、中枢部の撮影は、その時からのいわば「積み残し」になっていたのです。県に打診したところ、いくつかの条件をつけたうえで認められました。
年に一度しか開けられない壕を、限られた時間の中でどう撮影するか。機材や撮影方法はどうするか、綿密な打ち合わせを重ねました。
何より重要なことは、司令部壕内部の映像は公共の財産だということです。そのため撮影した映像は報道各社に提供するという条件で、撮影できることになりました。
慎重に準備を重ねて去年4月、ついに加屋本たち撮影チームは壕内部に入りました。小雨が降る中、長靴にヘルメット姿の管理業者と共に、ハシゴを15段ほど下り壕の中へ。内部は真っ暗で、ライトを照らさないと足元すら見えません。さらに、重く湿った空気で5分もたたずに汗が噴き出し、メガネは曇って視界が奪われました。
※加屋本たちが撮影した壕内の様子は、こちらの記事からご覧ください👇
薄暗い壕に入ってまず感じたのは、「これは公開は難しい…」ということでした。
県は公開を目指す意向ですが、壕の内部は水没していてポンプで水を抜き続けないと最奥部までは行けません。時期によってはほとんど天井まで水没する場所もあると考えられました。
また空気の状態も悪く、送風機で新鮮な空気を送り続け、酸素濃度計で安全かどうかを確認しながら進みましたが、最奥部では少し息苦しく感じる事もあったといいます。そのうえ落盤の危険もあるということで、場所によっては公開は難しいだろう、と。
そこで加屋本が考えたのは、「それなら壕の中にいるように体感してもらったらどうだろう」ということでした。私には「なんのこと…?」でした。
「VR」で司令部壕を体感してもらおう
カメラマンたちは、常に新たな映像表現を模索しています。
加屋本は仲間たちに相談した結果、今回は「映像を見た人がまるでそこを訪れたような体験ができる」、VR=バーチャルリアリティーの技術に挑戦しようということになりました。いろいろな角度から撮影した大量の画像を合成する「フォトグラメトリー」と呼ばれる手法を使って、司令部壕内を立体的な映像で再現する試みです。
ただし、立体映像もそれだけではシーンとした薄暗い洞窟のようで、その意味や歴史的価値は伝わりにくいかもしれないと考え、映像の中で、沖縄局キャスターの宮城杏里に案内してもらう演出も取り入れました。
完成した映像をさっそく私も体験したところ、360度を見渡せる臨場感ある映像とキャスターの解説によって、まるで自分が80年前の司令部壕の中にいるような緊迫感を体感できました。
VR映像を一般の人に体感してもらうイベントはことしの3月と5月、6月に首里城公園などで実施。イベントの調整や機材の手配なども加屋本が中心となって準備しました。初日の会場には若い世代からお年寄りまで、100人以上にお越しいただきました。
※3月25日の体験会の記事はこちら
これまでの取り組みを振り返って加屋本は、このように語っています。
「司令部壕を一般公開するには時間も手間もかかりますが、今ある最新技術で撮影、記録することが、カメラマンとしての私の責務だと思っています。撮影した映像を多くの人に見てもらい、戦争遺跡の現状を知ってもらって、米軍基地の問題や、今も残るさまざまな沖縄の苦悩や問題を考えるきっかけになればと思います」
(※司令部壕内を撮影したVR映像は6月22日に「おはよう日本」で放送)
子どものころに受けた教育が今の私に残っていない
そのプロジェクトのきっかけは、営業職員の何気ない発言でした。
糸満市出身の田島千明は、NHKの取り組みやコンテンツを地域に広げる活動をしています。
沖縄局が去年の4月から毎月開いているミーティングには、全ての職種から10人あまりが参加しています。その日の議論のテーマは「平和学習」でした。
多くの地域ではあまりなじみがないかもしれませんが、沖縄や広島、長崎などでは、小学校や中学校の授業で戦争体験者の話を聞いたり、展示を見学したりといった取り組みが継続して行われています。
田島が語ったのは自分が子どものころに受けた平和学習について、「あのときに聞いたことが、あまり自分の中で残っていないような気がする」という思いでした。同席した同年代の沖縄出身のメンバーも、その意見に同意していました。
このミーティングの参加者で沖縄の出身者は実は3人のみ。全国に転勤があるNHKではどうしても地元出身者の比率は下がりますが、それだけにその意見は貴重です。
田島は語りました。
「戦争体験者の話には圧倒されるものがあります。しかし、その場では心を揺さぶられて『おじいちゃん、おばあちゃんたちは大変だったんだ…』と思っても、それから年月がたって、あらためて沖縄戦とは何かと聞かれたときに、何も答えられないかもしれない」
自分の3人の子どもたちのことも考えたといいます。
「子どもたちが小学生になって、学校で平和や戦争のことを習って、私にも聞いてくるようになりました。『お母さんたちも勉強したよ』とは言ったものの、戦争はこわいものなんだ、大変だったんだという記憶はあるものの、子どもたちからの質問にそれ以上答えられない。何がどうだったということまで語り継ぐ知識を持っていない。だから熱心に語り継いできた世代の下の私たちが、学び直しをしなければいけないのではと思ったんです」
プロジェクトの議論は一気に活発になりました。考えてもらうにはどうするか。営業職員としてもともと行っていたワークショップに沖縄戦を取材している記者にも参加してもらい、議論の場を作ろうということになりました。
沖縄戦についてどのように伝えていけばいいかを高校生と一緒に考える、沖縄戦80年にあわせたNHKのプロジェクトです。
ことし3月に沖縄尚学高校で実施したワークショップで、生徒たちからは世界情勢についての情報を集めて自分なりに考えることが大事なのではないかといった意見や、選挙へ行くことによって平和に貢献できるといった意見が出ていました。
※3月のワークショップについての記事はこちら
田島の発言はほかのプロジェクトにも影響を与えました。ことし沖縄局がNHK放送文化研究所と実施する戦後80年の世論調査では、沖縄戦に関して、これまでの調査でたずねてきた質問に加え、沖縄戦の教訓として伝えたいものは何かなど、より踏み込んだ質問を盛り込むことにしました。
「日々感じていることを発言し、このプロジェクトで広がっていく。それを感じられたのはうれしいし、自分の力だけではどうしようもできないことが、発言したことで広がって、みんなで考えていける。それが放送局のよさだとあらためて感じました」(田島)
80年の今まで触れていなかったテーマを伝える
3人目は記者の西銘むつみ。沖縄局勤務が通算32年の大ベテランで、沖縄戦体験者の証言を語り継ぐニュースや特集を伝え続けています。
10年前、西銘は沖縄戦体験者の生々しい証言をおさめたおよそ1000本のテープを関係者から託され、チームで取材を進めて戦後70年の検証番組「沖縄戦全記録」を制作。報道界でも権威のある「新聞協会賞」を受賞しました。
西銘が戦後80年のことし取り組んでいるのは、沖縄に派遣された日本兵など、県外出身者の沖縄戦の体験を伝えることです。
沖縄戦で亡くなった20万人を超える戦死者の中で、日本軍の兵士は6万5000人。アメリカ軍は1万2000人とされています。西銘は、当時沖縄に派遣され戦死した兵士たちの慰霊祭を取材しようと考えたのです。
沖縄戦で戦死した兵士たちの慰霊祭は、実は毎年県内の各地で行われているのですが、NHKやメディア各社が取材をすることは多くはありませんでした。
理由のひとつは慰霊祭の数が多いことです。慰霊祭は秋から冬にかけてほぼ毎週行われ、1日に3つの地域の慰霊祭が行われることもあります。
もうひとつの事情は、当時の日本軍についての沖縄県民の複雑な感情があります。沖縄戦では、スパイとみなされた住民が日本軍によって殺害されるといった、住民と日本兵を巡る事件がこれまで幾度も伝えられてきました。
そうした複雑な事情について長年取材して体験者の話も聞いてきた西銘が、80年のことし、あえて日本兵のことを伝えようと考えたのはなぜか。
「沖縄戦についての記憶の風化が進んでいるからです。沖縄でもそうですから、沖縄以外の『本土』ではなおさらですよね。『沖縄戦は海の向こうで起きたこと』にとどまるのではなく、『沖縄戦で私たちの地域の人も亡くなったんだ』と、自分に近い事として沖縄戦をとらえてもらえればと考えました」(西銘)
当時徴兵され、沖縄に配属された日本軍の兵士には、職業軍人だけでなく農家や船乗り、中には人形師など、戦争とは無縁に暮らしていた人たちも多くいました。
沖縄戦では県民だけでなく、全国のさまざまな土地の人たちも戦禍で命を落としたことを知ってもらい、さらに自分の地域の戦争被害についても関心を高めてもらうことで、あの戦争についての記憶の継承につながれば――。
そう考えた西銘は、ことしは沖縄県内で行われる都道府県の慰霊祭を取材して、その内容をNHKの沖縄県内向けのニュースだけでなく、全国の各地域のニュースで伝えてもらおうと提案しました。
例えば沖縄戦での東京出身の戦死者の慰霊祭のニュースを、NHKの首都圏ネットワークの時間帯で放送してもらおうというのです。
そんな提案、全国にある地域の放送局が協力してくれるのか…?
不安もありましたが、全国に提案を連絡したところ賛同する局が次々に手を挙げてくれました。これまでに11府県で放送し、慰霊祭をきっかけに、各地の体験者や遺族の話の取材にもつながっています。
80年もその後も全員で伝え続ける、沖縄戦
NHK沖縄放送局のプロジェクトはそのほかにも、
・アナウンサーと技術チームが過去にNHKが特集した現場を訪ねて中継などを行う「ふたたび戦跡を歩く」。
・記者が集めた資料や映像などをまとめ、80年前に起きた出来事をたどる「沖縄戦タイムライン」。
・カメラマンが80年前に撮影された写真と同じ場所を再び撮影し、現在との違いを伝える「写真で見る沖縄戦」。
・地元新聞の沖縄タイムス、琉球新報との共同開催のシンポジウム
など、多数あります。
デスクとして私がいろいろな取り組みを見ていてあらためて感じるのは、NHKにはさまざまな人たちがいて、一人ひとりが社会とつながっているということです。そして地元出身の職員たちの「沖縄戦を風化させない」という危機感が原動力となったことに、NHKの地域局の底力を感じました。
NHK沖縄放送局では、これからも全員の力で沖縄戦を伝え続けます。
加屋本 了
NHK沖縄放送局 カメラマン
2001年NHK入局 佐賀、広島、静岡、東京、沖縄、鳥取に異動。
2023年から地元の沖縄放送局に再赴任。
<加屋本が手がけた主な番組>
NHKスペシャル「沖縄 空白の1年 “基地の島”はこうして生まれた」
「“国境の島” 密着500日 防衛の最前線はいま」などを担当。
田島 千明
NHK沖縄放送局 営業
2004年NHK沖縄放送局に営業職員として入局し、その後熊本放送局に異動。
2014年から再び沖縄放送局に赴任し、現在は受信料の理解促進業務のほか、地域と連携した視聴者リレーション活動を担当。
西銘 むつみ
NHK沖縄放送局 記者
1992年NHK入局。初任地が沖縄放送局。沖縄戦や戦後処理を取材。
その後、東京の首都圏放送センターで旧環境庁、旧沖縄開発庁、渋谷区、品川区などを担当。2000年に沖縄放送局に再赴任。沖縄戦、教育、環境、沖縄担当の解説委員を兼務。
<西銘が手がけた主な番組・記事>
NHKスペシャル「沖縄戦 全記録」
「”朽ちたシーサー“みたい? 沖縄で取材を続けて28年の今、私だから語れること」