[研究] 謎の薩摩弁「ちぇすと」はどのように生まれたか――鹿児島谷山方言とロシア語が結びついて流行語になり、誤解から「興奮とくやしさを表す雄たけび」に変化
私は去年まで薩摩弁の「ちぇすとー!」は英語の Chest(胸または箱)に由来すると思い込んでいたんですよ。
で、その線でマンガにも書いたんですけど、発表して直後に不安になって
「ほんとうにそうかな? 念のため検索しよう…」
と調べてみたら、はたして由来は不明だったのでした。
あわてて差し替えました。
私は戦国時代からある語だと思い込んでいたのですが、戦国時代からある語だったら英語由来なわけがないのです。
そのときはまあ、それっきりで
「かんちがいしちゃってたんだね。ちゃんちゃん♪」
で終わったのですが、ふと興味がわいたので調べてみました。
そしたらなかなか興味深い結論が出ましたよ……というのが、このエントリです。
## 結論:現代の我々が考える薩摩人の雄たけびとしての「ちぇすと」は誤解の産物
先に結論から述べます。
(1) 本来、「ちぇすと」は**鹿児島谷山町の方言で、「よっこいしょ」の意味**の言葉
(2) 明治時代の中頃に鹿児島谷山方言の「ちぇすと」と**ロシア語の「че́сть(名誉)」が結びついて称賛としての「ちぇすと」が鹿児島の知識人の流行語になった**
(3) 島津義弘の関ヶ原正面退却や宝暦治水を**称賛する言葉として**「ちぇすと関ヶ原」「ちぇすと松原」(※宝暦治水の千本松原のこと)が生まれた
(4) しかしロシア語の意味がわからない人が、(3)の使われ方から(2)を**悲しいとき・くやしいときに発する言葉だと誤解した**と思われる
(5) これらを踏まえて明治30年ごろに「ちぇすと」が**東京の学生や青年のあいだで「気合を入れる言葉」として流行し**、広く世間に知られるようになった
(6) 流行がしずまり現実では(2)と(5)を使う人は減り、**フィクションの中の薩摩人ばかりが使う言葉になった**
(7) 鹿児島県出身の作家である**海音寺潮五郎が(4)の意味でさかんに使用**(海音寺氏は谷山から遠く離れた現・伊佐市の生まれ)
(8) これが鹿児島県に逆輸入され「ちぇすと」が「くやしいときや気合を入れる時に薩摩人が発する言葉」だと**鹿児島県人が認めてお墨付きを与えてしまう**
(9) 司馬遼太郎をはじめ**多くの作家が(4)の意味で使用し、(3)の意味は失われていった**
(10) 結果として「気合を入れるときの雄たけび」と「くやしいときに発する言葉」という**異なる意味が「ちぇすと」の中に共存し、よくわからない**ことになってしまった
(11) そもそも「ちぇすと」は「よっこいしょ」という意味でしかない江戸~明治期の谷山町の方言なので、**多くの現代鹿児島県人にとっても使わないよくわからない言葉**である
さあ、結論だけ述べました。
あとはネチネチと証拠を挙げていくだけです。
エビデンスなんかいらねーよ!と納得して、ここで帰ってもかまいません。
長い話にお付き合いいただけるなら幸いです。
## いまネットに流布している「由来」の代表例
エビデンスの前に現状を確認しましょう。
ほとんどの記事が「由来は不明」としながらも、次のような説を紹介しています。
### 「知恵を捨てよ」に由来するという説が根強いが、文献は無い
>(ことばの広場)薩摩の「チェスト」 「知恵捨てよ」説も捨てられぬ? - ことばマガジン:朝日新聞デジタル — http://www.asahi.com/special/kotoba/danwa/SDI201901319495.html
### 地元の人は使わない。示現流の掛け声説を薬丸示現流が否定。小説家の創作という説も
>(ことばの広場)「西郷どん」の掛け声 薩摩剣士「チェスト」口にせず? - ことばマガジン:朝日新聞デジタル — http://www.asahi.com/special/kotoba/danwa/SDI201811144346.html
### 「強く行くぞ」「強い人」の転訛説
> チェストとは [単語記事] - ニコニコ大百科 — https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
このほか「血会すっぞ(ちえすぞ)」説や朝鮮語由来説がありますが、エビデンスが無いのはどれも似たり寄ったりです。
しかし、Yahoo!知恵袋に興味深い回答――というか、辞書からの引用がありました。
## 「詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声」と辞書にあり
> 昔の空手漫画等で見かける『チェスト!』って掛け声ぬはどんな意味があるので... - Yahoo!知恵袋 — https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11139050576
"詩吟・演説などの高潮した際に、聴衆から発する声援の掛け声(広辞苑)" それは知らなかった!
そうだった。
言葉の意味を調べるのに、辞書という基本ツールを使っていませんでした。
方言だし、これだけ由来不明と書かれてるのだから、辞書を引いても無駄だと思っていたんですよね。でも、辞書ではじめて得られた情報があったのです。
反省。
そこで、ウィクショナリーはこういうときはアテにできないから、コトバンクに頼りました。
>チェストとは? 意味や使い方 - コトバンク — https://kotobank.jp/word/%E3%81%A1%E3%81%88%E3%81%99%E3%81%A8-3183059#w-2044105
意味として新しい情報は得られませんでしたが、初出の実例が非常に示唆に富みます。
『くれの廿八日』(1898)〈内田魯庵〉が精選版 日本国語大辞典が見つけることのできた初出であると。
1898 は明治31年です。もう明治を三分割して残り1/3の始まりのあたり。
だとしたら、江戸時代からある言葉というのも疑わなければなりませんし、英語のチェスト由来である可能性も考えなければなりません。
ふむ……初出……
なるほど、では例によって国会図書館デジタルコレクションで時代順に雄たけびもしくは称賛としての「ちぇすと」を拾っていきましょう。
## 文献調査で明らかになる谷山方言由来とロシア語由来
### 1898年 内田魯庵『くれの廿八日』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1883433/1/183?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
日本国語大辞典が初出のひとつだとした小説。
私が国会図書館デジタル化資料で調べても、これが最古でした。
洋装の男性と着飾った若い女性の二人ずれ。男が急に葉巻を吸ってパッと煙を吐いたのが目立つ行為だったのでしょう。
通行人の注目を浴び、薩摩下駄の三人組の一人は「チェスト、」と叫んだというくだり。
やっかみのはいった「くやしい」の意味にもとれますが、ここはヤジのまじった称賛の意味と解釈すべきでしょう。
聴衆ではありませんが、通りすがりの観客として高潮しているのです。
国会図書館デジタル化資料がすべての文献を網羅しているわけではありませんが、1898年までまったくヒットしないということは、幕末や戊辰で使われてた言葉だと考えるのは難しいと思います。
### 1898年 本富安四郎 著『薩摩見聞記』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/766637/1/20?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
初出とされる内田魯庵『くれの廿八日』と同じ 1898 年(明治31年)です。
二か所、それぞれちがう使われ方のチェストが出てきます。
薩摩人気質についての話で、論破された薩摩人の学生が「チェストー」と叫んで喉をかっさばいて死んだという話。
本富安四郎氏は越後人で薩摩人ではありません。
そして、この話は氏が現場に居合わせたわけではなく
「…という話があるじゃないか。薩摩人は単純すぎる思考の持ち主なのだ」
という論の展開のために引き出された伝聞です。
当時の新聞にそういう事件があったかというと、国会図書館デジタル化資料からは見つかりません。
議論に負けた薩摩人が憤死するという話は、ありえなくはないと思います。
廃刀令のあとでよかったよね、そうじゃなかったら論破したやつ殺されてるからと思わないでもありません。
ロシアの皇太子訪日直前の議論なので、この薩摩人が首を切って死んだというのが事実なら 1891 年以前のこと。
8 年前の自殺を引き合いに出して、流行りの「チェスト」で脚色した……という可能性もあるでしょう。
ともあれ、1898 年の時点で「チェスト」に「くやしいときに発する叫び」の意味が存在していたことがわかります。
しかし、次をご覧ください。
こちらは薩摩の青年たちの鍋講の様子です。
豚汁を作って薩摩琵琶を弾き、歌って、大声で「チェスト」と叫んだというのです。
これらは美味い料理とたのしい時間に対する称賛と受け取れます。
しかし、「くやしーっ」と「たのしーっ」が同じ言葉であることに本富安四郎氏は違和感がなかったのでしょうか?
してみると、本富安四郎氏の「ちぇすと」の解釈は、「くやしーっ」とか「うれしーっ」とか「いくぞオラァァ!」に関係なく、薩摩人は感情が高ぶったら「ちぇすと」である、だったのでしょう。
うれしいだいすきしあわせ → 「ちぇすとー!」
くやしい絶対ゆるさない → 「ちぇすとー!」
哀しくて涙が止まらない → 「ちぇすとー!」
たのしいwwワロスww → 「ちぇすとー!」
いくぞーっ やるぞーっ → 「ちぇすとー!」
その解釈でエエんかな?と思いますが。
### 1899年 『講農会会報』(41)
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1505937/1/18?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
修辞の多い難解な文章ですが、要は「綺麗な景色を見た!チェスト!」と言ってるだけです。
つまり称賛であって、「ブラボー」とほぼ同じ意味の「ちぇすと」です。
記者は水戸の人らしく、薩摩人ではありません。
水戸人は薩摩とつながりが深いので影響があったかもしれませんが。
### 1903年 『少年世界』9(12) 勘忍なる大將 / 松原廿三階
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1800755/1/48?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC
少年向け軍隊小説です。
宇佐木くんというやる気のない若い陸軍兵士に困り果てた鬼教官(おそらく薩摩人)。
それでも怒りをおさえてていねいに教え諭し、やる気を引き出そうとするのだけど、若い兵士は逆にふてくされてしまう。
ずっと怒りの爆発を抑えてきた鬼教官もとうとうキレて「チェストー!」と叫んで蹴っ飛ばした……という場面。
いわゆる団塊世代、シラケ世代、新人類、バブル世代、団塊ジュニア、ゆとり世代、ポスト団塊ジュニアと、その前の世代の軋轢というおなじみのやつです。
人類は同じことを繰り返しているだけです。
まあ、それはともかく、この描写だけでは【薩摩人は腹を立てたら「チェスト」】なのか 【薩摩人は感情が昂ったら「チェスト」】なのか判断できません。
### 1904年 学習院輔仁会雑誌』(64)>秋季行軍記事
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1558785/1/114?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
なんだか文章がよくわからねえんですが、色白だから白木将軍というあだ名で呼ばれてる陸軍学校の生徒がクラスメートからからかわれた話のようです。
つまり嘲笑されているわけですが、「ステキステキ」「やい白木やい」などと並んでいて言葉の上では「称賛」の使われ方です。
からかわれた白木君がくやしくて「チェストー」と言っているのではありません。
### 1908年 探検世界
> https://dl.ndl.go.jp/pid/11186827/1/15?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
主人公が怪物(?)の写真を撮って「占めたりチェストー」と内心で言ってます。
「しめしめ、やったぜ!」な感じでしょうか?
くやしさ表現ではありませんが、聴衆として興奮して発しているわけでもありません。
聴衆であることは必須条件ではなくて、自分で自分に対する称賛でもいいようです。
### 1908年 『警察協會雜誌』(103)>警察古今風聞録
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1789989/1/31?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
巡査が「チェストー」と叫んで薬丸示現流の構えをとってます。
私たちのよく知る「チェストー」です。
現代の薬丸示現流の師範は「ちぇすと」なんて掛け声は使わないと言っています。
しかし執筆者がウソを書いているんじゃなければ、(おそらく東京の)この巡査は薬丸示現流を学んでて「チェストー」と叫んだのです。
### 1910年 『燕塵』第3年(3)(27)
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1468539/1/14?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
薩摩人の書生かなにかのエッセイと思われます。
朝寝坊を楽しんでいたら、先生でしょうか、一室から立派な詩吟がはじまって、飛び起きて正座して拝聴して思わず「チェスト!」
詩吟で聴衆で称賛の「ちぇすと」です。
### 1915年 凝香園 著『後の血染の聯隊旗 : 軍事探偵』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/904776/1/46?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
大正に入りました。軍事冒険小説です。
>"一番日本兵の得意の突貫やそしんたろうひつしをやつて遣らう、のるか反るかだ、チェストッ······」"
ということで、私たちになじみ深い「ちぇすと」です。
しかし、大事な点がひとつあります。
この新太郎君、べつに薩摩人または鹿児島県人だと描写されてないのです。
つまり、この時代に「ちぇすと」は薩摩の専売特許ではなく、日本人なら使って不思議じゃない言葉だったということです。
それくらいの流行語だったようです。
"一番日本兵の得意の突貫"って言ってますしね。
### 1919年 『三田文学』第1期,10(4)>猫又先生(小說)/南部修太郞
> https://dl.ndl.go.jp/pid/11030129/1/48?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
こちらも小説。秋季行軍記事(1904)と同じく、やってることは嘲笑なんだけど、言葉の上では称賛というやつです。
誉め言葉で冷やかすやつですね。
こちらも馬鹿にされてる先生がくやしくて「チェストオ」と言ってるわけではありません。
### 1921年 熊田葦城 著『少年美談』>西郷隆盛悪少年を懲らす
> https://dl.ndl.go.jp/pid/968245 (参照 2025-02-05) https://dl.ndl.go.jp/pid/968245/1/125?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
少年少女向けの伝記。
題材は西郷隆盛が妙円寺詣りの日に他の少年とケンカになった例の逸話。
熊田葦城は広島のひとです。
1921年は大正10年。
「ちぇすと」という言葉が文献に現れてから約30年。
言葉が鹿児島に逆輸入されて妙円寺詣りの日に「チェスト関ヶ原」と唱和するようになっていた可能性はあります。
しかし、西郷隆盛たちの時代にそれを言っていたかは、なお慎重であらねばなりません。
### 1926年 坪内逍遥 著『逍遥選集 : 12巻 別冊3巻』苐九巻>喜劇「登ろ!」
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1883255/1/185?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
有名作家が出ました。
多勢に囲まれた安兵衛が刀を抜いたら、その多勢がパッと逃げる。
逃げたところで安兵衛が長口上をたれて見栄をきる。すると逃げた多勢が「チェスト!」と叫ぶ。
さっきまで争っていたのだから、「くやしい!」という意味での「ちぇすと」かもしれません。
しかし喜劇であることを踏まえると、多勢が登場人物であることを忘れて観客目線になり称賛を送るというギャグかもしれません。
私は後者だと思うんですが、脚本からはちょっと断定できませんね。
### 1930年 『文明協会ニューズ』(5)>川柳と時代思潮 / 岡田朝太郞
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1580822/1/76?page=left&keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
随筆です。バンカラたちは「チェストー」と言いながら、ステッキで花の枝を叩き落としていたという話。
称賛としての「ちぇすと」ではありません。
かといって、猛烈にくやしいわけでもなければ、感情が昂っているわけでもありません。
カジュアルちぇすと派。こええ。
当時というのがいつかハッキリしませんが、バンカラが流行っていた明治末から大正にかけてのことなのでしょう。
彼らは薩摩人とは限りません。
バンカラ文化は薩摩の気風に強く影響されてはいますが、多くは東京人や日本各地から上京した若者たちです。
その彼らの間で「ちぇすと」が使われていたのです。
### 1935年 かにかくに>問疾の會
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1229400/1/198?keyword=%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%99%E3%81%A8
随筆集。
これは仏教関係者がなごやかに討論する会の話のようですね。常盤大定という博士(?)が詩を吟じたあと、自分で「チェスト」と言っていたという話。
自画自賛。おちゃめ。やはり自分で自分を称賛してもいいのです。
### 1935年 大日本聯合女子青年団 編『日本女性鑑』上>妻としての乃木夫人
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1466375/1/220?page=left&keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
薩摩では弱虫泣き虫な子に薩摩琵琶を聞かせながら「チェストがんばれ」とはげましたという話。
またもや称賛でもなく、くやしさでもなく、感情が昂っているわけでもない「ちぇすと」が出ました。
言葉においてはよくあることですが、どこかの段階で意味の変化が生じたと考えられます。
### 1936年 平凡社 編『大辞典』第十七卷
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1873490/1/176?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
きわめて重要な情報が得られました。
昭和に入ると辞書というものが充実してきます。ありがたいもんです。
その中で方言の「ちぇすと」を収録しているものがありました。それが平凡社『大辞典』。
いかがでしょうか。**方言としての「ちぇすと」は鹿児島県谷山町の方言であり、「よいしょ」の意味でした。**
おだてて持ち上げるほうの「よいしょ」ではなく、「よっこいしょ」の意味です。
動作の前に力をこめる掛け声ならば、人によっては斬るとか突撃するときとか喉をかさばくときに使うかもしれません。
「よっこいしょ」と言いながら他人を斬るの、ヤベえやつ感がものすごいですけど、「どすこいっ」「せいやっ」「おりゃっ」「そぉい!」「ヨガッ ヨガッ」の仲間だと思えば、そういうこともあるかなという気がします。
しかし、同じくらい注目に値するのは、その隣の「チェストー」です。
ロシア語の честь から来た言葉といわれる。
詩吟や琵琶等の演技の際に聴衆の叫ぶ讃辞的なかけ声とのこと。
ここまで出てきた「高潮した際に発する声援の掛け声」の由来がここに!
ロシア語だったとは!
確かめてみましょう。スペルが載ってるんだから簡単なものです。
> честь(ロシア語)の日本語訳、読み方は - コトバンク 露和辞典 — https://kotobank.jp/rujaword/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
チェースチ。ロシア語で名誉とか名声とか敬意という意味でした。
まちがいなく**明治31年前後から文献に出現する「称賛としてのチェスト」は、ロシア語に由来していた**のでした。
コトバンクの「精選版 日本国語大辞典」は慎重にも、「外来語と言われるが語源未詳」としています。
たしかに詩吟などの賛辞としての「チェスト」がロシア語の「チェースチ」に由来するという証拠はありません。
しかし、「名誉」という意味が讃辞として適切である点と、「ちぇすと」と「チェースチ」がよく似ている点、西郷が西南戦争後にロシアに逃げたという説が根強く、鹿児島に親露派が少なくなかったであろうことを考えると、かなり蓋然性があると思います。
谷山の方言由来と、ロシア語由来。
「ちぇすと」の意味がブレているのはふたつの由来が混交したからだったのでした。
調査の半分は終わったようなものですが、ここから
「なぜ、「よっこいしょ」または「すごいぞ!」の意味だった「ちぇすと」が、くやしいときや突撃するときの雄たけびに変わったのか?」
の謎を埋めるには、もうちょっと用例が必要です。
1950 年代まで調査を続けます。
### 1937年 安藤藤治郎 著『標準国語新辞典』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1030848/1/414?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
平凡社『大辞典』の翌年の本ですが「強い感情を表す言葉」と定義し、ロシア語の訛りとしています。
むろん「強い感情を表す言葉」というのが間違いであることは、みなさんおわかりですね?
「ロシア語の訛」という書き方だと「ロシアの方言」なのか「ロシア語が日本に入って訛った語」なのかよくわかりません。
それはまあいいとして。
重要なことは、薩摩人が始めた称賛としての掛け声「チェスト(名誉!)」を称賛とは限らず「感情が昂った時の言葉」だと定義している勢が少なからずいたということです。
辞書に採用されているのですから、編者ひとりの独自解釈ではありますまい。
「ちぇすと」からは早い段階でロシア語の意味が失われ、間違った解釈の方がメジャーになっていったと考えられます。
### 1947年 前田河広一郎 著『蘆花伝』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1341906/1/192?page=left&keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
1940 年前後になると、「ちぇすと」がパタッと消えます。
再び現れるのは戦後になってから。
徳富蘆花の伝記。酔っ払って学生たちの前に現れた文部大臣に対して徳富蘆花が「チェストオ!」と一喝したというくだり。
ダメ大臣に対して激昂したんでしょうか。
それとも徳富蘆花はカジュアルチェスト勢だったのでしょうか。
その線もありえますが、興味深いのは
"『黒い眼と茶色の目』には『ヒヤ、ヒヤア!』とあるが、『チェストオ!』が本当である」"
という記述です。
『黒い眼と茶色の目』は徳富蘆花の作品です。
本人がこうだと書いたものを、伝記執筆者が否定しているのです。
おそらく前田河広一郎はその場にいたか、その場にいた人に取材したのでしょう。
実際に『チェストオ!』と言っていたのが真実だと思います。
作者が常に真実を書くとは限りません。
しかし私には、徳富蘆花が『チェストオ!』と言った理由、『ヒヤ、ヒヤア!』に変えた理由を前田河広一郎は誤解しているように思えます。
徳富蘆花のやったのは、内田魯庵『くれの廿八日』や秋季行軍記事や南部修太郞『猫又先生』と同じく
「やってることはヤジなんだけど、言葉は称賛」
という意味での「チェスト」だったと思うのですよ。
それは学生と文部大臣という立場を考えると当然かと思います。
ひとり孤高の戦いを挑んだのではなく、群衆を隠れ蓑にしたヤジでしょう。
だからこそ『黒い眼と茶色の目』では『ヒヤ、ヒヤア!』に変えたのだと思います。
このように改変してもヤジという意味は変わりません。
明治後期に学生たちが好んで使った「ちぇすと」は流行語であって、『黒い眼と茶色の目』の頃にはダサくなってたうえに伝わらない語になっていたのでしょう。
事実、前田河広一郎には伝わっていないのです。
前田河広一郎はあのときの『チェストオ!』を義憤に駆られて感情が昂った結果の行為と解釈しているのです。
だから、『ヒヤ、ヒヤア!』という冷やかしであってはならないわけです。
つまり、称賛としての「ちぇすと」は、早々にロシア語由来であることが失われて、次に称賛であることも失われて、「感情が昂った結果の叫び」という誤解だけが残ったのです。
### 1952年 海音寺潮五郎 著『明治太平記』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1352954/1/34?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
1950 年代から鹿児島県出身の作家、海音寺潮五郎が薩摩人や薩摩をテーマにした時代小説を発表しています。
これはその一本。
何か行動をおこす際の「よっこいしょ」としての「ちぇすと」と、感情が昂ったときの「ちぇすと」が両立する使われ方です。
ロシア語由来の「ちぇすと」の本質は称賛にあるので、ただ感情が昂ったときに「ちぇすと」を発するのは誤用だと言わねばなりません。
しかし、流行語として称賛の「ちぇすと」が流行った頃から50年が過ぎていました。
海音寺潮五郎が生まれたのは 1901 年ですし、薩摩琵琶を聞いて育つような武士階級の家庭でもありませんでした。
おまけに谷山町から離れた現・伊佐市の生まれですから、谷山町の方言としての「ちぇすと」が「よっこいしょ」にすぎないことも知りません。
しかしながら、鹿児島県出身の海音寺潮五郎が誤用である方の「ちぇすと」を多用したことで「くやしいとき、感情が昂った時の雄たけび」としての「ちぇすと」が、フィクションの中では定番化してしまったのでした。
### 1956年 甲斐克彦 著『黒帯恋慕』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1354649/1/157?page=left&keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
歌い終わった後、自分で「チェスト」を言う、自賛のパターンです。
1950 年代でも、称賛としての「ちぇすと」が失われていない例が、あるにはあります。
しかしこの小説も別に歌で盛り上がったわけではなく、
「歌い終わったら「チェスト」と言う決まりである」
という慣習で言ってるだけという表現です。
ロシア語としての意味はまったく伝わってないことがわかる、ある意味でリアリティのある描写です。
### 1956年 氏原大作 著『若き血の肖像』
> https://dl.ndl.go.jp/pid/2983820/1/83?page=left&keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
伝記小説。
よりによって**高杉晋作に「チェストウ」と言わせてます**。これはひどい。
使い方はブラボーと同じ、賛としての「ちぇすと」
もしかすると作者は正しくロシア語由来であることを理解して、海音寺潮五郎への皮肉としてこれを書いたのかも……いや考えすぎか。
### 1960年 『九州人 : 日本民族の一祖型』,毎日新聞社
> https://dl.ndl.go.jp/pid/3006127/1/105?keyword=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%88
"チェストとは「こんちくしょうめ」である"
言い切っちゃったwwww
お墨付きを与えてしまったのは海音寺潮五郎氏に限りません。
新聞社ですら(だから?)こうなのですから、責任をすべて小説家のせいにするわけにはいきません。
「関ヶ原の復讐」説の震源が竹内理三博士だとわかったのが思わぬ収穫でしょうか。
### 司馬遼太郎
トリは司馬遼太郎に登場してもらいたいところですが、残念ながら国会図書館デジタルライブラリーでは館内限定になっていてウェブで閲覧できません。
断片的にヒットする部分だけ引用しましょう
> "伊東は、「チェストー」と吐きだすようにいってうしろをむいてしまった。薩摩人が、気分の〓揚したときや腹のたつときに"
まず、気分が高揚したときや腹が立ったときの「ちぇすと」
> "「チェスト!」と、叫んだ。薩摩人の掛け声である。腹のたつとき、気合をかけるとき、くやしいとき、うれしいときにかれらはこう叫ぶ。"
気分が高揚したときに「うれしいとき」も含まれる派でした。
> "川路利良が、不意に、「チェスト!」と、叫んだ。薩音のかけ声である。賛成だ、という意味であった。"
賛成が讃辞になるか微妙なとこですが、賛としてのチェストも漏らさず採用しています。
> "肝腎要めのときになると「チェスト関ケ原と言った。チェストというのは、薩摩の人たちがつかう気合ですが、「ここが分れ道ぞ!」という意味です。"
おいwwwww 作るなwwwww つーくーるーなーwwwww
ともあれ、定義が全部のせ状態なので、意外に影響は少ないかもしれないと思いました。
## 「ちぇすと」が感情発露の雄たけびに変わった経緯を推理する
さて私は、時系列で上げていく中で、ひとつの文献をあえて外して最後に持ってきました。
というのも、それこそがすべての謎をとくカギだったからです。
ようやく、この長いテキストもクライマックスです。
ここから私の推測(妄想とも言う)全開で行きます。ちぇすとー!(誤用)
その本とは、鹿児島県の谷山町の方言のまとめです。なるほどですねー。
### 鹿兒島縣鹿兒島郡谷山町方言集(下) / 山下光秋
> https://dl.ndl.go.jp/pid/1493046/1/4
「チェスト(よいしょ)」とあります。すでに『大辞典』(1936)で見た通りです。
右隣を見ましょう。「チエ(強い)」とあります。
現代のわれわれも「強い」を「つえー」と口語表現しますから、理解しがたい表現でもないでしょう。
してみると「よっこいしょ」の意味の「ちぇすと」は**「チエすっど(強くするぞ)」が変化して「チェすと」になったと推測できます。**
なんと、冒頭でウェブから拾った『「強く行くぞ」「強い人」の転訛説』は、核心の半分を付いていたのでした。
「ちぇすと」の「同義語として「ちぇいよ」があると↓このページでは言ってます。
> ちぇいよ – 【公式】鹿児島弁ネット辞典(鹿児島弁辞典) — https://kagoshimaben-kentei.com/jaddo/%E3%81%A1%E3%81%87%E3%81%84%E3%82%88/
他に「ちぇいよー」という鹿児島弁を解説しているサイトが見当たらないオンリーワンなのでちょっと信憑性に欠けるのですが、いちおう信じるとしましょう。
「ちぇいっど(強く行くぞ)→ちぇいよ」になったのだとすれば、「チエすっど(強くするぞ)→チェすと」である可能性がいよいよ高まります。
**本来、「ちぇすと」は鹿児島谷山町の方言で、「よっこいしょ」の意味の言葉だったのでした**
しかし「よっこいしょ」は「よっこいしょ」にすぎません。
谷山地区から戊辰戦争に行った兵士は 50 名程度とのこと(谷山市誌(昭和42年))。
戊辰戦争で薩摩武士が「ちぇすと~」と叫んで斬りまわった可能性はゼロではなくても皆無です。
変化が起きたのは明治の中頃と考えられます。
谷山には錫鉱山や焔硝蔵や鉄砲の演習場があったといいますから、谷山にいた薩摩藩士は技術者や砲兵が中心だったと思われます。
維新後は銃火器の時代ですから、彼らは指導者として重用されたはずです。
で、明治中期になってだんだん歳をとってくると、「よっこいしょ」という意味での「ちぇすと」を連発するようになる。
谷山っ子じゃない若い生徒はそれを
「なんですかそれ~」
と、師に対する愛情半分、からかい半分で面白がる。
そのうちロシア語を勉強している誰かが、「ちぇすと(よっこいしょ)」と「チェースチ(名誉)」が似ていることに気づいて、学生たちが大いによろこんだのでしょう。
初老の師に似合いの意味ですから。
それで、講義や指導のあとで敬意をこめて「ちぇすと」と喝采するのが鹿児島で大流行した推測します。
**鹿児島谷山方言の「ちぇすと」とロシア語の「че́сть(名誉)」が結びついて称賛としての「ちぇすと」が鹿児島の知識人の流行語になったのです**
称賛の言葉ですから、その言葉は師だけに向けられず、薩摩人の敬愛する島津義弘や平田靱負にも向けられたのでしょう。
**島津義弘の関ヶ原正面退却や宝暦治水を称賛する言葉として「ちぇすと関ヶ原」「ちぇすと松原」(※宝暦治水の千本松原のこと)が生まれたというのはありえることです。**
ただし、あくまで称賛です。
「偉大なり島津の退き口」
「偉大なり宝暦治水工事」
であって、「くやしい」という意味はこの時点の「ちぇすと」にはありません。
さて、明治政府で薩長閥がハバをきかせている時代です。鹿児島の流行は敏感に東京に伝わります。
すぐさま薩摩の議員の演説や、薩摩の芸能に対して「チェスト」で喝采するというのが東京でも流行る。
東京にだってロシア語を勉強している書生はたくさんいますから、ここでナウくてヤングでいまいイケてるグルーヴィーな誉め言葉「ちぇすと」が東京で鬼バズして方言を離れ若者語に変化したのです。
おそらく明治の中頃でしょう。
ところが、です。
鬼バズしたら当然、書生じゃないアホな若者や流行に乗り遅れたくない中年とかにも「ちぇすと」が知られることになります。
言葉は聞いたことがある。
でも意味はわからない。
という目線で身近な「ちぇすと」を観察してみると、薩摩琵琶の最後に涙を浮かべながら「ちぇすと」「ちぇすと」と連呼しているわけです。
それでその薩摩琵琶や薩摩人の講釈で語られる内容が関ヶ原の「島津の退き口」だったりするわけです。
あるいは薩摩出身の講談師が「偉大な西郷隆盛と悲劇の西南戦争」を講談してたりする。
これまた薩摩人の聴衆がラストで涙を浮かべて「ちぇすと」を連呼している。こーいったわけで
**ロシア語の意味を知らない一般人が「ちぇすと」を、悲しいとき・くやしいとき・気持ちが昂ったときに発する言葉だと誤解したのです。**
また一方でロシア語の意味とは無関係に「よっこいしょ」の意味としての谷山方言「ちぇすと」も薩摩人の若者を通じて、東京のバンカラ学生に流行ったとみえます。
バンカラ学生のお手本は荒々しい薩摩武士なのです。ですからバンカラ学生は薩摩武士をきどって「チェスト」と言いながら狼藉を行いました。
ところがバンカラ学生は若者ですから、おっさんおばさんのように、なにかするたびに口癖のように無意識で「よっこいしょ」とは言いません。
かれらが「よっこいしょ」というには「やるぞ」という意識を強烈に出さねばならないのです。
**東京の学生や青年のあいだで「なにかをやるときに気合を入れる言葉」「威風を示す言葉」として「ちぇすと」が流行し、広く世間に知られるようになったのです**
しかしいずれにせよ、流行語の命は短いものです。
大正も過ぎてしまうと使う人は激減します。
日露戦争があったのでロシア語を学ぶ人も減っていたかもしれません。
現実で「チェスト」を使う人は詩吟関係者くらいになり、その人々だって慣習で続けているだけで由来や意味をわかってやってる人は少なくなっていました。
それは鹿児島県人でさえそうです。
もともと谷山地域の方言であって、大隅はもちろん薩摩だって谷山地域じゃない人がわざわざ「ちぇすと」を使う理由は無いのです。
気に入って使い続けた人もいるにはいたでしょうけど。
ところが、廃れるどころかますます使われるようになった分野がありました。
フィクションです。この時代のメディアは小説中心で、風化するのが遅かったのです。
フィクションの中で
① 称賛を表す「ちぇすと」
② くやしいときに言う「ちぇすと」(誤用)
③ なにかをやるときに気合を入れる言葉としての「ちぇすと」(誤用とまでは言えないが「よっこいしょ」とはニュアンスが異なる)
④ 威風を示し威嚇するための「ちぇすと」(誤用)
が生き延びたのでした。
なぜなら、作中で「ちぇすと」と言わせておけば薩摩人っぽくなったりバンカラっぽくなるので、すごく便利だったからです。
**「ちぇすと」は役割語になり、フィクションの中の薩摩人ばかりが使う言葉になったのです**
しかし小説にも遅れて世間の流れがやってきて、昭和初期~戦中になるとフィクションの中の「ちぇすと」は激減しました。
徳富蘆花も『チェストオ』を避けて『ヒヤ、ヒヤア』に改めたくらい、ダサワードになったのです。
しかし戦後になると、一周まわって逆に新鮮だったのか、ズンドコと使われるようになりました
**鹿児島県出身の作家である海音寺潮五郎は②~④の意味でさかんに使用しました**
海音寺氏は谷山から遠く離れた現・伊佐市の生まれなので、谷山方言としての「よっこいしょ」の意味の「ちぇすと」は知らなかったのでしょう。
それにロシア語由来の称賛の意味での「ちぇすと」が流行したのは、海音寺氏が生まれたころほど昔のことになっていました。
そのうえ、由来がわからなくなってるのは流行が始まった鹿児島でも同様でした。
鹿児島県人は小説を通して、薩摩人は「ちぇすと」と言うものなのだと学習し、それが伝統であるかのように思い込んだのです。
それは谷山地域でしか使われてなかったにもかかわらず。
**「ちぇすと」は鹿児島県に逆輸入され「くやしいときや気合を入れる時に薩摩人が発する言葉」だと鹿児島県人が認めてお墨付きを与えてしまったのです**
鹿児島県出身の海音寺氏がさかんに使い、新聞社や鹿児島の公的な機関がお墨付きを与えたのに、疑う理由があるでしょうか?
もちろんありません。
**国民的時代小説作家の司馬遼太郎をはじめ多くの作家が②~④の意味で使用して、それが定着して現在に至ってたのでした**
称賛を表すロシア語由来の意味も、戦後しばらくは存在しますが、それも消えていきました。
なお、省略しましたが 1950 年代の現代小説で、
「『こんにちわ』と同義の意味で女性が『チェスト』と言う」
というシチュエーションを2例ほど見かけました。
意味がわからなくなってるのを逆手にとって「新しい女性」を表現したのかもしれませんし、1950年ごろに実際にそういう女性がいたのかもしれません。
いずれにせよ一過性のものだったようです。
以上が、「ちぇすと」の変遷の大まかな流れですが、ここでもう一度、鹿兒島縣鹿兒島郡谷山町方言集(下)を見直していただきたいと思います。
「ちぇすと」に続く語です。
「チェッソ」と「チェッソイケ」です。
前者は「チェスト」に似ていますし、後者は「チェスト行け」に似ています。
しかし、おそらくまったく無関係の言葉なのでしょう。
日本語に大量の同音異義語があるように、鹿児島方言にも同音異義語があり、谷山方言にも同音異義語があるのです。
そもそも南九州方言は言葉を縮める傾向があるので、同音異義語が発生しやすいのです。
これをふまえて。
谷山地区出身の教官が、あるとき「チェッソイケ(そら見ろ)」と言った。
谷山方言を知らない鹿児島の学生は、それを「チェスト(よっこいしょ)行け」だと聞き間違えた。
でも、よっこいしょ行けだと意味が通らない。
意味を聞こうかと思うものの、なんだか口調から嘲りがまじった良くない雰囲気を感じ取り、聞くに聞けなかった。
そして、どうやら「ちぇすと」にはよっこいしょの他に攻撃的な意味があるらしいぞと誤解して、流行語としての「ちぇすと」がバズったときに攻撃的な意味があるという誤解も広まったのかもしれません。
「チェスト行け」というフレーをよく聞いたなぁと思うので、そういう妄想をしました。
では、なぜ「チェッソ」「チェッソイケ」が「そら見ろ」なのでしょう?
これはもうほんと根拠薄弱に直感だけの私の考えを垂れ流しますけど、「チェッソ=知恵(が)遅(い)」ではないかと思います。
いや、発達障害という意味ではなくて。
「チェッソイケ=(ほらみろ)知恵が遅いけん(そういうことになるのだ)」
ということではないかと。
えー。まあ。
以上、長々と。
半分は推測ですが。
* 本来の「ちぇすと」は鹿児島谷山方言とロシア語のそれぞれ別の系統があった
……という点は事実として明らかにできたということで。
ほめてください。
世のため人のために拡散してください。
もし全部私の間違いでも、間違いだと指摘されることが世のため人のためになります。
木曜の男 (創元推理文庫 101-6) | G・K・チェスタトン, 吉田健一 |本 | 通販 | Amazon —
このエントリは筆者の Fnabox からのセルフ転載記事です。

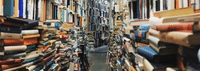
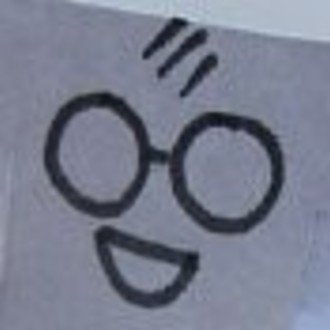
コメント
2mitimasuさま
おはようございます。
「ちぇすと!」考、面白く、ゆかしく拝読しました。
その昔、NHK ドラマ「国語元年」(井上ひさし)の中で、鹿児島出身の南郷重左衛門(浜村純)が、「ちぇすとー!」と気合いを入れて木刀を振り回すシーンを思い出しました。
初めてチェストを知った作品でした!
ありがとうございます。
私のちぇすとはどこから……か作品は覚えてないですけどw
小学生の時の雑誌記事かなにかだと思いますが
「ちぇすと行けーっ! 関ヶ原ーっ!」
と書いてあって、「ちぇすと」の意味がまったくわからなかったことと、どこにも意味の説明がなかったのを異様に感じたことを覚えています。