ビデオゲームの異常な乱数、または私は如何にして心配するのを止めて歪んだダイスを愛するようになったか
文・murashit
新聞をにぎわせる恐怖が、確率を使って繰り返し語られる。その可能性があるのは、メルトダウン、癌、強盗、地震、核の冬、エイズ、地球温暖化、その他である。恐怖の対象は(たぶん)これらではなくて、実は確率そのものなのである。
わたしの目の前のディスプレイには、たしかに「90%」と表示されている。命中率だ、良さそうやね。じゃあ攻撃っと。……外れる。そういうこともある。運が悪かった。もういっぺん試してみよう。攻撃、と。……外れる。まあね、そういうこともある。えらく運が悪かっただけだ。もういっぺん試してみよう。攻撃……と。
外れる。なんやこのクソゲーは!
もちろん冷静なあなたなら、1,000分の1程度のできごとなんてふつうに起こりうると知っているはずです。そういうこともある。だから「なんやこのクソゲーは!」と叫ぶわたしのことを、あざわらうのでしょう。たんに運が悪かっただけだよ。きみは確率のことがわからないんだねと、あざわらうのでしょう。
……いや、ちょっと待ってください。ビデオゲームにおける「偶然」は、そんなに単純なものじゃない。だから、そんなふうにわらうのを、ちょっとだけ待ってもらえませんか?
本稿の目標は、ビデオゲームになぜ「偶然」が必要で、どのように設計されているのかを検討し、そして冒頭のわたしの嘆きを部分的にでも救うことにあります。そのために、意図的に歪められたダイスを扱いましょう。すなわち『バルダーズ・ゲート3』(Larian Studios, 2023)の「カルマ・ダイス」です。いかにも均等な目が出るかのようにみせかけつつ実は調整されている……そんなダイスの検討に向けて、ビデオゲームにおける「偶然」の役割、疑似乱数の特性、そして人間の認知バイアスにこたえる「欺瞞」の実例といったものについてもみていくことにします。
秩序と混沌の狭間にて
というわけで、まずはビデオゲームにおける「偶然」について。
ビデオゲームはしばしば、インタラクティブなメディアだといわれます。けれど、「インタラクティブ」であるとはどういうことでしょうか。これにたいして美学者のAaron Smuts(2009)は、日常的な「対話」を範例として次のように答えました。すなわち、その対象がインタラクティブであるとは「(典型的なユーザーにとって)その対象に応答性があり、かつその応答が完全にコントロールできるわけでもなく、完全にランダムでもない」ときであり、そのときに限る、と。ビデオゲームの文脈にそくしていえば、プレイヤーの入力とその結果が相関するけれど完全には予測できない、それが「ビデオゲームはインタラクティブである」の意味するところだよ、みたいな感じでしょうか。完全に制御できるならそれは道具にすぎず、完全にはちゃめちゃな応答はノイズでしかない。
あるいは、人類学者であるThomas Malaby(2007)によるゲーム一般の定義をみてみるのもよいでしょう。Malabyによれば、ゲームとは「ゆるやかに区切られ、社会的に正当で、解釈可能な結果をうみだすような、企図された偶発性(contrived contingency)の領域」です。これが「ゲームの定義」としてうまくいっているかどうかはいったん措くとしても、なんらかの偶発性が重要なはたらきを担うことは間違いないように思われます。そしてそのうえで、Malabyはゲームにおける偶発性を以下の4つに分類しました。本稿で主に採りあげる「乱数」は「確率的偶発性」にあてはまるでしょう。
確率的(stochastic)偶発性:ダイスやカードのシャッフルに代表される確率的な偶然
社会的(social)偶発性:チェスなどにおいて相手の持つ情報や思考が見通せないことにもとづく偶発性
遂行的(performative)偶発性(*1):アクションゲームなどにおいて、ある種の行為が(参加者の能力的に)失敗しうるといういみでの偶発性
記号的(semiotic)偶発性:起こったこと、起こりうることにたいする解釈ないし「どうみなされるか」の偶発性
ゲームデザインの文脈でもこうした「予測のできなさ」や特に乱数によるそれは重視されています。たとえばJesse Schellの『ゲームデザインバイブル 第2版』(2019)では6つの主要な「ゲームシステム」のひとつとして「確率」を挙げていますし、ケイティ・サレンとエリック・ジマーマンによる『ルールズ・オブ・プレイ』(2011)でも「不確かさのシステムとしてのゲーム」にひとつの章を割いています。さらにGreg Costikyan『Uncertainty in Games』(2013)に至っては、1冊まるごとを「不確実性」(*2)にあてさえしています。
総じていえば、ゲームが人を惹きつけるために、あるいはゲームがインタラクティブであるためには、デザイナーによって意図的に設計され、秩序と混沌の狭間にちょうどよく配置された「偶発性」や「不確実性」が必要だということです。そして、確率的な「偶然」はその主要な源のひとつといえます。
*1: 言語行為論めいて聞こえる語ですが、ここでは「パフォーマンス」のような日常的な用法を想定したほうがしっくりくるでしょう。なお、Malabyは人間の認知や思考の限界によるある種の予測のできなさ(後述のCostikyanによる不確実性の源でいえばSolver's UncertaintyやAnalytic Complexity、Uncertainty of Perceptionあたり)について明示的には触れていないのですが、私見ではここに含めてよいのではと考えています。
*2: ここではcontingencyを「偶発性」、uncertaintyを「不確実性」と訳しています。同書のなかでCostikyan自身もMalaby(2007)を引きつつ述べているとおりニュアンスの違いはあるものの、さしあたって本稿の範囲では互換な語とみなしてよいと考えています。なお、ここではCostikyanによる不確実性の源の分類については詳述しません。日本語での紹介としてはたとえば「ゲームにおける“ほどよい不確定性” | 4Gamer」。
マシンはサイコロを振らない
ビデオゲームにおいて確率的な偶発性をもたらすのは、なんといっても「乱数」です。たとえば乱数に下駄を履かせることによってプレイヤー有利な結果を出しやすくする難易度オプションはさまざまなビデオゲームに搭載されていますし(『XCOM 2』(Firaxis Games, 2016)の例)、「マリオカート」シリーズにおける「トップとの差が離れるほど強力なアイテムが出やすい」という仕様(*1)のように、スキルの差をあえて埋める目的にも使われたりもします。また、(これはビデオゲームに限ったことではありませんが)決まりきった結果を避けることでリプレイアビリティを高めたり、不確実性に対処するスキルそれ自体を試したりといった目的で使われることもあるでしょう。
ここで思い出しておくべきは、ほとんどすべてのビデオゲームにおける乱数は、ものすごい計算能力を持つマシンによって決定論的に生成された擬似乱数であることです(*2)。ここからみちびかれる、ビデオゲームにおける確率的な「偶然」の特徴をみていきましょう。
まずわかりやすいのは、状態の保存と再現が可能なことです。『Minecraft』(Mojang Studios, 2011)において同じシード値を指定することで同じワールドを生成できるのはまさにこの性質のおかげですね。疑似乱数生成器の状態を保存しておけば、いつでもまったく同じ乱数(列)を再現できるのです。RTAやTASなどで乱数の「調整」を可能にする(そしてSmutsの意味でのインタラクションがこうした実践の場面において消える)のも、この特徴があってこそです(*3)。
また、きわめて高頻度で複雑な乱数の使用が可能になることも挙げられます。現実のダイスは、1個なら当然一様ですし、せいぜい複数のダイスを振って中心極限定理のお世話になるのが関の山でしょう(*4)。特定の分布を意図したカードをシャッフルすることはできるかもしれませんが、それを場面に応じて調整するのはなかなか厳しい。けれどビデオゲームなら、どんないびつな確率分布に変換することだって可能で、その際プレイヤーに負担をかけることもありません。おかげで『RimWorld』(Ludeon Studios, 2018)の「AIストーリーテラー」のように、「状況に応じて刺激的なイベントを提供してくれる」「コロニーの建設に十分な時間を与えてくれる」あるいは「ひどく気まぐれでどんな終わりが来ようとも頓着しない」といった「性格」さえ表現できるのです。
そしてなにより、ビデオゲームはいつ乱数が使われているのかを、そしてそれがどのような乱数なのかを、「隠蔽」できることが挙げられます。テーブルトークRPGではゲームマスターがスクリーンの裏でダイスを振るケースがないこともない(らしい)のですが、ビデオゲームにおける「隠蔽」は質を異にします。コンピュータが勝手にメカニクスを実現してくれる、実現してしまう。その裏でどのような計算が行われているかを知るすべはありません。そしてそんなとき(先にみたように複雑な分布を利用できることも手伝って)「歪められた」乱数がこっそりと用いられることもしばしばです。
実際、「ファイアーエムブレム」シリーズの一部に採用され俗に「実効命中率」と呼ばれるしくみは有名でしょう(西條・遠藤, 2015)。命中判定にあたって2つの乱数を使い、この値の平均を画面に表示されている名目上の「命中率」と比較するというもので、結果的には名目命中率が50%以上であれば実際には表記より当たりやすく、以下であれば表記より当たりづらくなります。たとえば名目上の「命中率」が70%なら「実効命中率」は約82%になるし、逆に名目上の「命中率」が30%なら「実効命中率」は約18%となってしまう。
あるいは、いかにも確率的であるようににみえてその実まったくそうでない例も考えられるでしょう。個人的には『ロマンシング サ・ガ2』(スクウェア, 1993)の年代ジャンプ条件が印象深いところです。長く皇帝の地位にいるとだんだん強制的に次の代に移行させられる「確率」が高まるのですが、実際のところその判定はとくだん確率的なものではなく、こなしたイベントと戦闘回数のみから決定されます。
それにしても、どうしてそんなふうに歪め、ときには隠しさえするのでしょうか。もちろんプレイヤーに楽しんでほしいからに決まっています。これは、わたしたち人間が、確率やランダムネスを正しく認識するのが苦手であることと関係します。
*1: 逆にこれを利用し、あえて下位の状態にとどまり強力なアイテムを入手したうえで一気に順位を上げる「打開」戦術があったりもします。そしてさらにはそれを(ある程度)防ぐアップデートがなされたりも。
*2: 疑似ではない「真の乱数」とはどんなものか(本稿では、物理的なダイスはひとまず「真の乱数」の源であるとみなします)や、擬似乱数の生成手法、乱数としての性質の良さの基準といった話はここでは割愛します。「偶然」一般についてはエクランド(2006)、擬似乱数生成手法についてはたとえば三宅・清木(2025)あたりからはじめるのがおすすめでしょうか。もうすこし本格的には杉田(2014)を。また、以降では「乱数」のみに着目しますが、これを含めたビデオゲームにおけるゲームメカニクス一般の特徴について考察したものに松永『ビデオゲームの美学』(2018)の第7章があります。
*3: RTAやTASの文脈ではありませんが、たとえば「乱数調整入門 | mizdra's blog」などはこうした擬似乱数の調整のイメージがわきやすいかもしれません。
*4: 中心極限定理とは、おおざっぱにいえば、特定の条件を満たす分布に従う母集団から無作為抽出を繰り返すと、その標本平均の分布は釣鐘型に近づくといった定理です。1つのダイスだと上振れも下振れも均等に起こってしまうけれど、複数のサイコロを同時に振って和をとることで「平凡な値」「極端な値」的なもっともらしさを表現できるようになる程度に考えればよいかもしれません。もちろんこのほかにも「2つのダイスを振って大きい方/小さい方の出目で判定する」(『ダンジョンズ&ドラゴンズ』第5版の有利/不利判定など)、「3つのダイスを振り、そのうち2個の出目が一致した際の残りの1個の出目を役とする」(チンチロリンの「目」)といったバリエーションはありますが、いずれにせよあまり複雑になると計算が大変になったりわかりづらくなったり、あるいはテンポが悪くなったりしてしまうでしょう。
誤謬と欺瞞
「ギャンブラーの誤謬」をごぞんじでしょうか。わたしたちが「コインの裏が5回連続で出たんだし、次はさすがに表が出るっしょ」とついつい考えてしまうように、独立した事象であるにもかかわらず、過去の結果が未来の結果に影響を与えると信じてしまう傾向です。あるいは、「ホットハンドの誤謬」と呼ばれるバイアスもあります。バスケットボール選手がシュートを連続で決めているとき、次のシュートも成功する確率が高いと信じてしまうような傾向です。ある種のギャンブルにおける「流れ」の感覚に類するものといえるかもしれません。
これらの誤謬は基本的には代表性ヒューリスティック、つまり「ある事象がどの程度典型的であるか」にもとづいて判断する認知的傾向から生じるとされており、わたしたちが少ないサンプルにたいしても全体を代表するような結果を期待してしまうことに起因するとされています(*1)。もちろん、極端な結果のほうが印象に残りやすいといった傾向も関係しているところでしょう。
つまり、わたしたち人間が「ランダムらしい」と感じる系列と真にランダムな系列とは異なるのです。実際、人間が自力でランダムな数列を作ろうとすると、すべての数字を過度に均等に使おうとしたり、直近の数字の繰り返しを意識的に避けたりといった偏りが生じることが知られています(*2)。真の乱数がしばしば示す偏りや連続を「不自然だ」と感じ、ひいてはそれがもたらす結果を「理不尽だ」と感じてしまうのです。そしてもちろん、こうしたバイアスのあることは当然ゲームデザインの文脈でもよく知られており、冒頭で挙げたような書籍でも実際に触れられています。
ところで、Stefano GualeniとNele Van de Mosselaer(2021)は、プレイヤーの期待をあるいみで裏切るように意図されたデザインを「欺瞞的(deceptive)ゲームデザイン」と呼びました。そこでは『Celeste』(Maddy Makes Games, 2018)の仕様として有名になった「コヨーテタイム」や、『しょぼんのアクション』(ちく, 2007)の「スーパーマリオっぽいゴールポール」の罠(*3)などが挙げられています。前者はプレイヤー体験のために最後まで明らかにされない例、後者はあとでバラして強い印象を与えるような例ですが、いずれにせよ重要なのは、いかに「欺瞞」といえど必ずしも「わるい」ものではないということです。実に、GualeniとVan de Mosselaerは、これらがむしろ驚きや興奮、あるいは過度なフラストレーションの軽減といった、プレイヤー体験の向上を目的としていることを強調しています。誠実な嘘、というわけです。
先のようなバイアスが知られていることを鑑みれば、「偶然」にかんする欺瞞的ゲームデザインがさまざまにみいだせるのは当然でしょう。前節で「ファイアーエムブレム」シリーズの「実効命中率」を紹介しましたが、せっかくギャンブラーの誤謬の話もしたことですし、乱数の系列を操作することで「がっかり」を避ける例を3つを紹介してみましょう。なお、これらは「嘘」であるというとおり、いかに公知であろうとも、原則としてオフィシャルには明示されづらいものであることに注意してください。
まず挙げたいのは、「テトリス」の「7-bag」システムです。ある時期以降の「テトリス」においては、次にどのテトリミノ(ブロック)を出現させるかを完全にランダムに決定しているわけではありません。7種類のテトリミノを1セット(これが「7-bag」)とし、その中から重複なく出現させ、7つすべてが出現したら再びセットを補充するような、つまり非復元抽出のしくみが採用されているのです。きわめて単純なしくみではありますが、これによりいつまでも「棒」が出ないような「理不尽なツモ」を回避できるというわけです。いわゆる「乱数テーブル」をあらかじめ用意しておき、そこから順に引いていくような古典的な実装も(系列が十分に長く予測しづらいことを除けば)この類例といえるでしょうか。
それから、『ウォークラフトIII』(Blizzard Entertainment, 2002)などの「疑似ランダム分布」の利用もおもしろい例です(*4)。同作の一部のパッシブスキルでは、仮に「25%の確率で効果が発揮される」と表記されていても、最初の試行での実際の確率は25%より低く設定されており、失敗するたびに実際の確率が少しずつ上昇、そして一度効果を発揮するとリセットされる……といった調整がなされています。これにより、長期的な命中率は表記の確率に近づける一方で、不運の連続も緩和しているわけです。ソーシャルゲームのガチャやハックアンドスラッシュのアイテムドロップにおけるいわゆる「天井」(pity timer)のしくみをより洗練させたものといえるかもしれません(*5)。
こうした工夫は、まずはプレイヤーが抱く「理不尽さ」を和らげるためのものととらえられます。これをさらにおしすすめてゲームの根幹に据えたのが『バルダーズ・ゲート3』の「カルマ・ダイス」でしょう。詳しくは次節で検討しますが、これもやはり失敗の極端な連続を避けるための調整となっています。
かように、ビデオゲームにおける乱数はわたしたちが素朴に考えるような「純粋な偶然」などではありません。プレイヤーの心理を読み解き、認知の癖に寄り添い、ときにそれをあざむくことで、よりよい体験をつくりだすためのデバイスのひとつなのです。
*1: いかにも逆の信念が同じように説明されていることについて疑念を持たれるかもしれませんが、Peter AytonとIlan Fischer(2004)やMatthew RabinとDimitri Vayanos(2010)あたりをみてみると(前者は「代表性ヒューリスティック」批判ではあるものの)もうすこし洗練された説明はされているようです。ただ、本稿ではそういったバイアスのあることだけを取り上げるにとどめ、メカニズムについてはこれ以上掘り下げません。
*2: Angelike & Musch(2024)などを参照。手軽には「人間乱数についての覚え書き | セミになっちゃた」がおすすめです。
*3: たまたま『人生オワタの大冒険』(キング, 2006)に影響を受けた2Dプラットフォーマーをピックアップしていますが、当該論文のなかではちゃんとほかのゲームも挙げられています! なお、冒頭で紹介したCostikyan(2013)でも『しょぼんのアクション』が「Malaby's Semiotic Contingency」の例として用いられています。なんでそんな有名なんだ。
*4: たとえば「Pseudo Random Distribution | Liquipedia Warcraft Wiki」を参照。なお、『Dota 2』(Valve Corporation, 2013)などのMOBAにもこの仕様は引き継がれているようです。わかりやすいしくみであり他ジャンルのゲームで広範に採用されている可能性は高いのですが、今回調査した範囲ではそれらしい記述を見つけられませんでした。
*5: 現代において特にリアルマネーが絡む場合、法律や倫理、プラットフォームのレギュレーションなどから(PRDも含め)青天井とすることは避け、さらには詳細を明らかにする流れとなっているというのもあるでしょう。ガチャの「公平性」は本稿との関連でもおもしろそうなのですが、紙幅やわたし自身の能力の関係で掘り下げられていません。
いかで偶然を破棄すべき
ここからはケーススタディとして、『バルダーズ・ゲート3』のカルマ・ダイスを掘り下げ、ビデオゲームにおけるわたしたちプレイヤーの「偶然」との関わり方について考えます。
本作は『ダンジョンズ&ドラゴンズ』第5版のメカニクスをベースとしたコンピュータRPGです。そして『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の象徴といえばダイスにほかなりません。本作においても20面ダイスによる判定はメカニクスの中核をなしており、攻撃の命中から会話での説得まで、あらゆる行動の成否がダイスロールで決まります。転がるダイスの演出に一喜一憂するのは、間違いなく本作の醍醐味のひとつでしょう。
そんな本作の設定メニューのなかには、この根幹をなすシステムに介入する「カルマ・ダイス」なるオプションが存在し、デフォルトでオンになっています。ただ、それが具体的になにをいみするのかについてゲーム内にはほとんど説明がありません。“Karmic dice avoid failure streaks, while keeping the results random”のみです(*1)。そのほか公式な情報としてもアーリーアクセス期のパッチノート(Patch #4、Hotfix #10)から漠然とうかがい知れるのみ。総合すれば、「敵味方を問わず、キャラクターの振る20面ダイスの下振れを連続させない」という処理がなされていることは確かなようですが、いずれにせよ詳細な計算式は公開されていません。なお、本作において20面ダイスが振られるのは、命中判定(攻撃側のアタックロールと防御側のセーヴィングスロー)、および戦闘内外での技能チェックにおいてです。
この仕様についての限られた知識から、それでも次の2点を指摘できるでしょう。まず、プレイヤーだけでなく敵にも同様に適用されるため、難易度を直接下げるものではないこと。そして、上振れはそのままに下振れの連続のみを抑えることから、こと戦闘においては敵味方問わず能動的で直接的な行動を奨励し、より劇的な結果を期待させることです(*2)。
けれどもちろん、それだけが目的ならもっと単純な調整でもよかったはず。やはり「理不尽」の問題があるはずです。ただ、このひとことでまとめるには少々根が深い。それは本稿の冒頭でも眺めたゲームにおける偶然の役割に関わっていると、わたしにはそう思われてならないのです。
(あらためていうまでもないのですが)プレイヤーが行動し、システムが(しばしば偶然を介して)応答し、その結果を受けてプレイヤーがまた行動する……この往復が「ゲームプレイ」です。ここでSmuts(2009)の指摘に立ち返りましょう。応答が完全にコントロール可能なら単なる道具であり、完全にランダムならノイズにすぎないのでした。つまり、インタラクティブなゲームプレイが成立するには、予測不可能でありながら無意味ではない応答の源、「対話」を機能させるための偶然が必要なのです。
そして、ビデオゲームはときにそれを確率として可視化します。「わざわざ」可視化しているといっていい。なぜって、「90%の成功率」といった表示が戦略的な判断の可能性をひらき、偶然との関わり方を変えるからです。プレイヤーは数値をみて期待値を計算し、リスクを評価する。あるいは信義則として機能するようになります。こうしたことはもちろん、ある種の対話を成立させはする。
けれど前節でみたとおり、わたしたちは確率を正しく認識できません。ギャンブラーの誤謬に囚われ、数学的にいえば千に一度は起こる事象を、どうしたって理不尽に感じてしまいます。あるいは、口八丁のカリスマ特化で育てたはずのバードが、重要なNPCとの交渉で成功率90%の説得に失敗し、成功率90%の威圧も失敗し、最後の手段である成功率90%のペテンにさえ失敗したとしたら? 平和的解決への道が閉ざされ望まない戦闘に身を投じる「交渉の達人」とやらは、それでもあなたが育てたキャラクターだといえるのでしょうか。
こうした場面ではもはや、プレイヤーは目の前のビデオゲームを「対話の相手」として認識できません。きっとそうに決まっています。ビデオゲームはメカニクスだけに閉じるものではない。「なんやこのクソゲーは!」というわめきは、理不尽な拒絶への非難です。ここにおいてビデオゲームは対話可能な他者でなく、ただのノイズと化している。
だから、カルマ・ダイスが行っているのは人間のゲームマスターのような融通をきかせられないマシンが、依然として対話を成立させるための調整なんです。認知バイアスを持つわたしたちにとって、物語というパターンを血眼で探すわたしたちにとって意味のある応答として受け入れられるよう、偶然を「保護」する。もちろんこれは偶然の廃棄ではありません。依然として失敗は起こりうるし、結果は予測できない。対話の断絶を慎重に避けているだけです。デフォルトでオンになっていてよかった!
けれどそれでも、ひとたびカルマ・ダイスの存在を知ってしまえば問題が生じるのでは? ディスプレイで転がるダイスはもはや「純粋な偶然」ではないのでは? それは「偶然らしく調整されたなにか」なんじゃ? ……疑り深いなあ!
ほんとうに、これはもはや偶然ではない、のでしょうか。
いや、こうした問いは的を外しているのではないか。さっきもいいましたよね、わたしたちがゲームに求めているのは、あくまで意味のある応答、その積み重ねによる対話だったはずです。思えば、ギャンブルだいすき古代ローマ市民たちが手にするダイスは、その多くが重心の偏った不正確なものばかりでした。けれどかれらがそんなことに頓着していた様子はない。かれらは意味をもちうる事象を求め、ただフォルトゥナと対話していただけなのでしょう。ではその末裔であり、現代のビデオゲームをプレイするわたしたちは? 愛と勇気と決定論的な擬似乱数だけが友達だったのでは? けっきょくわたしたちはいつだって、なんらかの形で「歪められた偶然」と付き合ってきたのでは? 畢竟、ゲームにおける偶然というのは、制御できないものでありながら意味をあたえられる「事象」であり、それ以上のものではない。ありません。
そのうえで『バルダーズ・ゲート3』をとりあげたのは、ダイスですべてが決まるこの世界への介入を「カルマ」という名のもとで開示し、対話の主題としてテーブルに乗せたことによります。古代のダイスの歪みが丸めきれなさの産物や不正の道具だったのにたいし、カルマ・ダイスは認知バイアスを持つ人間が偶然と対話できるよう、そこに/ここにカルマのあることを明確に述べてくれている。わざわざ「偶然の象徴」たるダイスを使って! だったれば、17世紀にようやく出現したばかりの(ハッキング, 2013)、数値化された「確率」なんて幻想を捨て、人間にとって意味のある偶然を積極的に構築していこうではありませんか!
そしてそうなりゃ、ここでは「知りつつ知らないふりをする」ことこそがお作法です。劇場の客たちが舞台装置のしかけを知っているように、わたしたちはもはや、ビデオゲームの「乱数」が決定論的なものであることだって、逃れられない認知バイアスの存在だって、デザインにおける欺瞞の存在だって、知りすぎるほど知ってしまっています。「確率」という概念だってそうだ。そんなさなかでさえ、ディスプレイにはダイスの表象が転がり、コンピュータの内部で擬似乱数が生成され、そしてわれわれの想像のうちに物語の命運が決せられる。そこに、カルマティックな調整さえ加わる。わたしたちは息を呑んで結果を待つ。クリティカルヒットに歓喜し、ファンブルを嘆く。そうしてようやく、狭間の地にある偶然が存在できるようになる。
「偶然をいかで廃棄すべき」という詩句でマラルメが偶然性を否定したかったのか肯定したかったのか、わたしにはよくわかりません。ただ、ビデオゲームが示すのは、そのどちらでもない関係性のようです。偶然は廃棄できないし、廃棄する必要もない。支配すべき対象でもなく、盲目的に讃えその奴隷となるべきものでもない。わたしたちが求めているのは、かれをつうじた対話だからです。カルマ・ダイスをオンにするかオフにするかだって、バイアスにまみれたわたしたちが偶然をつうじていかに対話してみせるかを表明するための選択にすぎません。だからこそ、この歪んだダイスを前に、わたしたちはわたしたちなりの「詩学」をみいだすべきであると、わたしはそうやって自分のわめきを正当化するのです。させてくれ。
*1: 日本語版では「有効にすると、カルマ・ダイスが連続した失敗や成功を回避し、結果はほぼランダムに保たれる」となっていますが、これは誤訳です。原文ではあくまでfailure streaks、つまり「連続した失敗」を避けるとしか書かれておらず、「連続した成功」については言及がありません。後述のパッチノートの記述を鑑みるに、当初の実装時のテキストをもとに翻訳したままになっているのでしょうか。
*2: 既プレイ者への補足。セーヴィングスローの失敗も減るならダメージが必ずしも減るわけではなく、したがって「劇的」とはいえないのでは? というのはもっともですが、セーヴィングスローが成功しやすくなるということはおおむねクラウドコントロールや状態異常が効きづらくなることにつながり、したがって「正々堂々」の殴り合いの比重が上がることが期待されるとはいえるはずです。
文献情報
Angelike, T., & Musch, J. (2024). A comparative evaluation of measures to assess randomness in human-generated sequences. Behavior Research Methods, 56(7), 7831–7848. https://doi.org/10.3758/s13428-024-02456-7
Ayton, P., & Fischer, I. (2004). The hot hand fallacy and the gambler's fallacy: Two faces of subjective randomness? Memory & Cognition, 32(8), 1369–1378. https://doi.org/10.3758/BF03206327
Costikyan, G. (2013). Uncertainty in games. The MIT Press.
エクランド, I. (2006). 偶然とは何か (南條郁子, 訳). 創元社. (原著1991年刊)
Gualeni, S., & Van de Mosselaer, N. (2021). Ludic unreliability and deceptive game design. Journal of the Philosophy of Games, 3(1). https://doi.org/10.5617/jpg.8722
ハッキング, I. (2013). 確率の出現 (広田すみれ・森元良太, 訳). 慶應義塾大学出版会. (原著1975年, 第2版2006年刊)
Malaby, T. M. (2007). Beyond play: A new approach to games. Games and Culture, 2(2), 95–108. https://doi.org/10.1177/1555412007299434
松永伸司. (2018). ビデオゲームの美学. 慶應義塾大学出版会.
三宅陽一郎・清木昌. (2025). 数学がゲームを動かす!. 日本評論社.
Rabin, M., & Vayanos, D. (2010). The gambler's and hot-hand fallacies: Theory and applications. The Review of Economic Studies, 77(2), 730–778. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2009.00582.x
西條由起・遠藤雅伸. (2015). 数学的確率に対する主観確率の誤認知に関する研究. 日本デジタルゲーム学会2015年年次大会予稿集, 229–230. https://digrajapan.org/conf2015/
サレン, K., & ジマーマン, E. (2011). ルールズ・オブ・プレイ(上) (山本貴光, 訳). ソフトバンククリエイティブ. (原著2003年刊)
Schell, J. (2019). ゲームデザインバイブル 第2版 (佐藤理絵子, 訳; 塩川洋介, 監訳). オライリー・ジャパン. (原著2015年刊)
Smuts, A. (2009). What is interactivity? The Journal of Aesthetic Education, 43(4), 53–73. https://doi.org/10.1353/jae.0.0062
杉田洋. (2014). 確率と乱数. 数学書房.
※煩雑さを避けるため、Webの情報については文責のあるものも含めリンクとして掲載しました。また、ビデオゲーム作品については文献情報として掲載していません。
執筆者について
murashit
インターネットが好きで、ブログを書いたり、ときどき小説を書いたりしています。
https://murashit.net/
お知らせ
「遊星歯車機関」は、実験的な試みのあるゲームをガイド/批評する同人誌企画です。メカニクスやUI、シナリオ分岐、乱数、報酬設計など、ゲーム特有の仕組みによって広がる物語の可能性に着目します。いずれ本稿群を『遊星 物語るゲームたち(仮)』として編み直し、一冊にまとめる予定です。寄稿をご希望の方はご相談ください。詳細は続報にて。

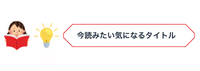
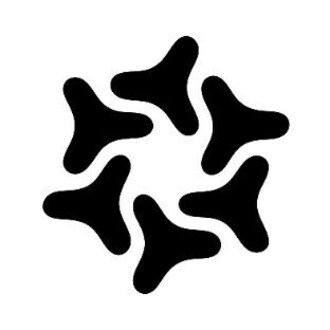
コメント