フォントの後ろのStdとかProとかPr6Nとかの意味がちょっとわかるようになるかもしれない話
新刊『本のつくりかた 企画・仕様設計・内容構成・デザイン・編集・校正』の中で、表記のゆれについてまとめた節があります。
そのうちの人名の漢字の話で、宮澤賢治/芥川龍之介/森鷗外を例に説明を試みたんですが、とてもひとことで説明できるようなものではなかったので、ここに書いておきます。
本のほうでは、時代によって使える漢字が違うので…という感じで3行くらいでざっくり終わらせています。
「鴎」は表外漢字(簡易慣用字体)、「澤」は旧字体(所属なし)というややこしさ。
ひと言では説明できないわけです。
まず、新聞やテレビ、出版などの公的なメディアでは常用漢字が使われる傾向がある、という前提があります。これで「宮沢賢治」と「芥川竜之介」は説明できます。
実際のところ、芥川は「龍之介」が多そうなのですが、岩波書店は「竜之介」でした。
ややこしいのは森鷗外で、「鴎」は『表外漢字字体表』の簡易慣用字体(2000年)、「鷗」は『表外漢字字体表』の印刷標準字体(2000年)&人名用漢字(2004年)。「鴎」は常用漢字に入っていないので、本来の「鷗」を使えばよいのですが、以前のワープロやパソコンでは「鴎」しか出なかったりで、そちらが使われていた時期も長いようです。あと、2000年以前に、常用漢字みたいなデザインに揃えよう、とすると、「鴎」のほう使うでしょうね。
↓試し読みコーナーです。ここにあるのは冒頭の初心者むけのイントロダクションで、そのあとに専門的な内容が続きます。
漢字については、他にもいろいろ気になることがあったので、校了後に深掘りしてみました。
(ただわたしは専門家ではないので、用語の使いかたが違ってたり、年号を間違えていることもあると思います。あと、それは「字形」ではなく「字体」では、といったとこもあると思いますが、ここでは漢字のかたちはざっくり「字形」って呼んでます)
難しい字と簡単な字
画数がやたらと多かったり、見慣れないかたちをしていたり、明治の文豪が使ってそうなのが旧字体、小学校で習ったような漢字が新字体、というのはなんとなくイメージできると思います。
で、生活の中でよく見かける漢字はだいたい新字体で、古い本や文献を読んだり、あえて好き好んで変換でもしないかぎり、旧字体を目にすることはそんなにないだろう、と多くのかたが考えているのではと思います。
(でもオタクは好き好んでそっちに変換するので、慣れ親しんでいるかたは多そうではあります…)
ところがです。
「そご」とか「にじみ」とか変換して拡大してみると、びっくりするほど難しい字に変換されていることがわかると思います。
「齟齬があってはいけないので…」とか、なんだかんだでよく使いますよね。
「薩摩」が「立」じゃなくて「文」になっているとか、いままで気づかなかったです。
「煉獄」とかそれっぽいし、「嘲笑」とかすごく笑われてそう。
これは、一部には、2000年に発表された印刷標準字体の影響もあるんじゃないかなと思っています。
印刷標準字体とNフォント
なぜ印刷標準字体は旧字系なのか
印刷標準字体というのは、2000年の『表外漢字字体表』に掲載された字形(の大部分)です。『常用漢字表』にない漢字についてはこれを参考にしてね、といった感じのガイドラインです。
ここに載っている字形が、ことごとく旧字系です。
「鞄」は革で包むと思っていたんですが、「包」のところが思ってたのと違ってた。
校閲さんから「こちらの字を使ってください」と難しいほうの漢字を提示されたことがあったんですが、
いま考えると、印刷標準字体に揃える、ということだったのかも。
なぜ旧字系にしたのかという理由は、「表外漢字字体表前文」に書いてありました。前文、どれもこれも長いんですけど、よく読んでみると関係者のお気持ちや当時の事情などが窺い知れて、とても興味深いです。
ざっくり要約すると、
常用漢字っぽい字形にすると、また中途半端な略字体を増やすことになるので、康熙字典体(旧字系)でいきます
ということらしいです。康熙字典体についてはあとで触れます。
(常用漢字、遠回しにディスられてるような…。本当は常用漢字もこっちに揃えたいのかも…という感じも受けましたが、もう広まってしまった字形をいまさら変えると混乱するのでそれはそのままにする、ということだそうです。「国民の生活の利便性がいちばん大事」という方針です。)
あといまはもうコンピューターで変換する時代なので、
手で書けなくても候補から正しいものを選べればOKですよね…
という事情もあるらしい。
Nフォントに気をつけろ
DTPやってるかたは、「Nフォントに気をつけろ」という話を、どこかで見たり聞いたりしたことがあるかもしれません。
Nフォントというのは「StdN」や「Pr6N」などの、フォント名の末尾にNがつくフォントで、JIS X 0213:2004で定められた字形を採用するフォントのことです(主にモリサワフォント系がこれで識別してますが、この書きかたは他のフォントベンダーでも使ってるみたいです。ただ、Nはたぶん「New」なので、単に「新しい」「今までと違う」という意味でこのアルファベットを使うこともあると思います。実際ややこしいことになってるみたいです)。
詳しくはこちら。
別にNフォントに問題があるわけでも厄介であるわけでもなく(むしろ使うならわたしは積極的にNフォントを選ぶ)、Nフォントと非Nフォントでは特定の文字で字形が変わることがあるので気をつけてね、っていう話です。
字形が変わる文字があります。Nフォントに戻すと字形も戻ります。
でも、非Nフォントに字形がないとは限らず、字形パネルで異体字を探すと見つかることがあります。
このフォントは「A1明朝」です。たまたまマシンに旧型(A-OTF Std)と新型(A P-OTF Pr6N)が
インストールされていたので、比較してみました。
ちなみにさっきの(Pr6Nで入力→変換)をStdに変更すると、こんな感じになります。
字形パネルで異体字を見ても、「齟齬」の簡単版は見当たらなかったです。
この字形が変わる話も、印刷標準字体が関係しています。
ふつうに考えて、常用漢字以外はこれを参考にしてね、というおふれを国が出して、フォントの世界が影響受けないはずがない(そもそも専門家がダブってるかもしれないけど…)。
ざっくりまとめると(かなり乱暴にまとめてます)、
印刷標準字体が発表される:2000年
↓
印刷標準字体がフォントに追加される
↓
JIS規格の例示字形が変わる(JIS X 0213:2004[通称JIS2004]):2004年
↓
それに対応したフォント(Nフォント)ができる:2007年
という流れ。
例示字形は、その文字を代表する字形(イデアっぽいもの)、といった感じで、体感的には、読みを入力して変換すると出てくる字形です。
たとえば、(お菓子の)「あめ」と入力して漢字に変換すると、Nフォントは旧字系、非Nフォントは新字系が出てくることが多いです。
(非Nフォントの場合、候補が旧字体で出てきても、実際に変換すると新字体になったりします)
JIS X 0213:2004についてはこちら。
Nフォントは旧字系(青い文字)、非Nフォントは新字系(オレンジの文字)の漢字に
変換されることが多いです。
文字によっては、どちらも同じものがでてくることもあります。
一般的な説明文とか、どっちでもいい場合はそんなに気にならないと思います(わたしも実は気にしたことはありません…)。
漢字にこだわりがある著者の小説を組んだり、出版社のガイドラインで「印刷標準字体に揃える」としていたり、その逆で、できるだけ簡単な漢字で統一するなどのルールがあったりする場合は、Nフォントか非Nフォントかを確認しながら、使うものを選んだほうがいいんじゃないかと思います(数が少なければ個別に異体字を探せばいいんですが、長文だとそれも面倒になるので)。
こういうの編集者も、デザイナーやDTP担当に最初に知らせといたほうがいいと思う(意味がわかるかどうかというのは別問題として…)。
ProとかStdとかPr6とか
フォント名の後ろのほうについている、「Std」とか「Pr6」ってなんだろう…と気になりつつもそのままにしている日本人の、なんと多いことか(おおげさ)。
これでわかる情報のひとつに、収録されている文字数があって、Std<Pro<Pr5<Pr6の順で文字数が増えていきます。
さらにNがついていれば、デフォルトの字形がだいたい印刷標準字体(旧字系)になります(例外あり)。
なので、同じフォント名でStdからPr6Nまでいろいろある場合、ひとまずPr6Nを選べば、一般的な印刷物に適した、最大の選択肢を確保できることになります。
(ただ、フォントベンダーによってはPr5相当のものを「Pro」と呼ぶこともあったりするらしく、この識別方法も一枚岩ではない…)
でも、文字数が多いゆえに動作が重い…という問題もあるので、そんな難しい字は使わないし、むしろ簡単な字形で揃えたいからStd、という選びかたもあると思います。
そもそもデザイン書体はStdやStdNが多いんじゃないかなと。でも、普通に使う文には十分だと思います。
字形がないものがでてきたりします。
Pr6Nで書いた小説をStdで組むと、そういう現象が起きたりするかもしれない。
対応表はこちらで見れますが、もしかしたら、この表が若干古いかもしれないです。いまStdにもProにもPr5にもNついてるのがあるので。文字数からみて、「令和」が発表される前かもしれない。
日本の漢字政策
常用漢字とか印刷標準字体とかいろいろ出てきて、そろそろ混乱してるんじゃないかなと思います。このあたりは、日本の漢字政策の流れを頭に入れると、ちょっとわかるようになります。
本当はこの話から説明するとわかりやすいんですが、最初に年表とか出してもたぶん見ないだろうな…と思ったのでここで。
常用漢字と人名用漢字と表外漢字
国が示している漢字のガイドラインは、だいたい3系統あります。
1)日常生活に必要な基本の漢字→常用漢字
2)常用漢字以外の、社会生活やメディアなどで使用頻度が高い漢字→表外漢字
3)名前に使える漢字→人名用漢字
(表外漢字と人名用漢字にはダブりがあります)
国が漢字に口出しするのは、漢字はコミュニケーションの道具なので、共通のよすがとなるものがないと混乱するから。
昔(当用漢字の頃)は使用を制限しよう、といった考えもあったみたいですが、現在は参考にしてね、というゆるやかな感じです。
ただし、(日本人の子供の)命名に使えるのは、常用漢字と人名用漢字に限定されています(「日本で生まれた外国人の子供」はゆるいらしい)。
1)の系統は、標準漢字→当用漢字→常用漢字といった具合に、新しいものが発表されると以前のものは終了、ということになっています。
が影響していると覚えておくといいです。
常用漢字や人名用漢字はちょこちょこ追加されているのですが、それは割愛しています。
漢字のラインナップは、文化庁や法務省のサイトで公開されています。
常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
人名用漢字
表外漢字字体表
Webでいつでも見ることはできるんですが、フォーマットがばらばらだったり、複数のページに分かれていたりすると見づらいので、本にまとまっているものが手元にあると便利です。
タイトルが『校正必携』なので、校正記号の使いかたとかなのかな?と思いがちですが、中身の大半は漢字やその使いかたのサンプルです。校正記号、がんばって勉強しないと習得できないもののように思われてるかもしれないですが、基本的なものは1ページの表におさまってしまう程度の量です。
長い前文なども読みやすい状態で載っています。わたしも、まあ手元に1冊おいとくか…くらいの軽い気持ちで買ったんですが、今までうっすら保留していた謎がとけたので面白くて、結局、隅から隅まで読んでしまいました。たぶん次、漢和辞典読み始めると思う。
『康熙字典』とは何だったのか
漢字の話になると、「康熙字典体を基準として」「康熙字典順で」みたいなフレーズがたまに出てくると思います。中国(清)の康熙帝の命により『康熙字典』が編纂された、は世界史のテストによく出てたので、わたしも名前だけは知っています。
で、『康熙字典』って何?
と思ったので調べてみると、収録文字数約4万9千字の漢字事典で、完成したのは1716年。日本だと、ちょうど8代将軍徳川吉宗の世が始まった年です。
正直、なんでそんな古い書物を基準にできるのかずっと謎だったんですが、見てみると旧字体(↓わたしが引いた赤の傍線)がところどころ混ざってるくらいで今とあんま変わらんな…という印象です。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2938232 (参照 2025-09-07)
考えてみたら、家康の駿河版銅活字の段階で文字のかたちは違和感ないので、それより100年も経っていれば、十分頼りにできますよね。
ただそのまんま、というわけにはいかないので、『康熙字典』っぽい字体、ということで、『表外漢字字体表』の前文では、「いわゆる康熙字典体」と呼ばれています。
『当用漢字表』と『当用漢字字体表』のトラップ
新字体を、『当用漢字字体表』に採用された略字や俗字のような字体、と説明することがあります。でも、当用漢字は『常用漢字表』より古く、戦後まもない時期の告示なので、わたしの中ではなんとなく旧字系のイメージがありました。
実際、『当用漢字表』は旧字系です。
でも、『当用漢字字体表』は新字系です。常用漢字と変わりません。
「表」か「字体表」で、ぜんぜん世界が違う。これを知っていないと、いろいろな説明を読んでも、当用漢字関連で引っかかってしまいます(何かの誤植かな?って思っちゃう)。
「当用漢字字体表」の字形は、いまの常用漢字と同じです。3年間の間になにがあった…。
終戦直後の1946(昭和21)年に告示された『当用漢字表』はこんな感じで、全体的に画数が多くて、簡単そうに見える字でもひとクセあって、いかにも夏目漱石や太宰治が使ってそうな感じがします。
旧字系には、わたしが赤い傍線を引きました。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11286406 (参照 2025-09-07)
それから3年後の1949(昭和24)年に告示された『当用漢字字体表』は、こんな状態です。現在よく目にする漢字と変わりません。
手書きなので、その時点で活字がまだ存在しなかったのでしょうか。終戦後の混乱期で、活字を用意する余裕がなかったかもしれない。
さすがにすっきりしすぎてオリジナルがわからなそうな字には、小さく旧字が添えてあります。
国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2963228 (参照 2025-09-07)
この劇的な変化には、どんなひとでも読めるように、書けるように、という願いが込められたりしているのかな…、と思ったりもしました。
(まああと、いつの時代でもあると思うんですが、(日本のオリジナルじゃない&西洋に倣えで)「漢字をなくそう」運動みたいなのもあるんですよ。そういうのと戦うための、漢字、難しくないよ、便利だよ、というアピールなのかな…とも思いました。あくまでわたしの推測です)
ただ、あまりにも変わりすぎていたので、いろいろ混乱はあったようです。とくに命名関連で。
横組みの右→左読み(「ネムラ」とか「道鉄」とか)が、左→右読み(「ラムネ」とか「鉄道」とか)に変わったのも、戦後の5年間くらいの間らしいのですが、劇的な変化があっても意外と短期間で慣れてしまうものなのかも。
国立国会図書館デジタルアーカイブの充実のおかげで、わたしの中では大正・昭和初期の書物を読む機会が増えてきたのですが、この対応関係↓を頭に入れておくと捗ります。推測できなそうな漢字のリスト(わたしが欲しかったもの)です。
でもわかっていても、「昼」と「画」の旧字体と、「書」は混乱します。
大正期のロシア語の教科書でロシア語を勉強していたとき、与格の「与」の字が旧字体で読みかたもわからず、画数が多いので黒々と潰れていて(「興」と見分けがつかない)、毎回ひっかかっていました。なぜそんなもので勉強してたのかというと、「どうしてもロシア文学を読みたい大正・昭和初期の書生さんの気持ち」になると覚えられるのでは、という精神的コスプレです。あと単純に、本のデザインがかっこよかった。本文も活版印刷だったし。
1942年の標準漢字
『当用漢字表』と『常用漢字表』の前に、『標準漢字表』というのもありました。1942(昭和17)年、太平洋戦争まっただなかの告示です。
収録されている文字数は、当用/常用と比べて多めです。行政と農業のほか、軍事と皇室に関する漢字が多いように感じるのは、時代を反映しているなあと思いました。
当用漢字以降、動植物の名称は仮名書きにする、ということになって、花や動物をあらわす漢字はばっさりカットされています。で、そっちは人名用漢字のほうにいろいろ入っています。「鰯」とか「鷗」とか。
当用漢字と常用漢字では、必要最小限に絞り込まれているようです。
どの時代でも「菊」はマストのよう。
『標準漢字表』はこちらで見れます。
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/hosoku/pdf/11_big_05.pdf
この活字、めちゃくちゃ見覚えあるんですが、築地明朝でしょうか…?
あと、こちら↓に戦前〜戦中の漢字字体が置いてあります。
混在している現在
やっぱり基準を康熙字典体に戻そう、ということにした結果、何が起きているかというと、『常用漢字表』の中での字形のゆれです。
ただまあ常用漢字の使用は強制じゃないので、各自、各媒体で方針を決めて対応すれば、困らないと思います。
そのため、「迷」は一点しんにょう、「謎」は二点しんにょうというゆらぎもあります。
教育現場は大変そうだなあ…と思って『学年別漢字配当表(教育漢字)』を見てみましたが、新旧でゆれそうなのは4年の「茨」くらいでした。しんにょうの漢字は思ってたより少なく(なぜか3年に集中しています)、すべて1点しんにょうだったので、そっちを書けば学校の漢字テストで×つけられることもなさそうです。
印刷標準字体はオール点つき、人名用漢字もほとんどそうですが、点がないものもあります。
これたぶん、「当用漢字表」の旧字も人名に使ってよい、の流れで人名用漢字に採用されたとか
そんな感じなのかなあと思っています。
『常用漢字表』の青文字は改正時に追加されたもので、点つきです。
選択できる字形が増えて、旧字系と新字系のどっちも使えるようになった現在、×2または×3…でどんどんバリエーションが増えてしまいます。
どういう方針で使う?というのを最初に考えておいたほうがいいのかも。
印刷物を見ていると常用漢字+印刷標準字体が多いですが
ロゴとかデザインの違いが気になりそうなところでは、新字体で揃えることもあるかも。
ひとつの文字の中に、旧字系と新字系でかたちが変わる箇所が複数あると、それだけ字形のバリエーションも増えてしまいます。ふつう、フォントの中に全部の用意はできないので、どれかが欠けることになります。
でもまあこれだけあったら足りるじゃん、って思いますが、人名の漢字はとにかくバリエーションが多く、ピンポイントでこれがない、で困ることもあるみたいです。
まあ、『標準漢字表』は『常用漢字表』に置き換わっているのでなくてもなんとかなるんでしょうか。
活版印刷時代の古本でこの字形を探してみようと思います。
人名用漢字については、こちらの記事も面白く、DTPやってると勉強になります。
以上、『本のつくりかた 企画・仕様設計・内容構成・デザイン・編集・校正』の本文3行くらいの行間に埋め込まれているお話(8000字くらいあるが…)でした。
ところで来年は、『ローマ字の綴りかた』が改正されるそうですね。1954(昭和29)年以来?


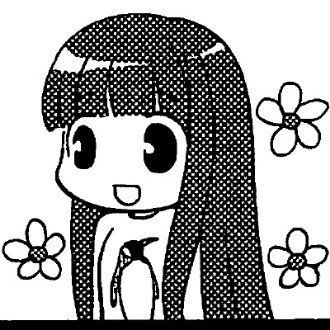
コメント