「記憶に残す」のではなく「印象に残す」
勉強というと、「覚える」「記憶する」ことが大切だと思われがちです。確かに、知識を定着させるためには暗記も欠かせません。しかし、ただ「記憶に残す」だけでは、どうしても時間が経つと薄れてしまいます。そこで大切になるのが、「印象に残す」学び方です。
印象に残ったことは、驚くほど長く覚えていられるものです。例えば、旅行先で見た景色や友達と一緒に体験した出来事は、何年経っても鮮明に思い出せることがありますよね。勉強でも同じで、「自分に関係がある」と思えたり、「なるほど!」と感動した瞬間の知識は、自然と頭の中に残っていきます。
そのために大事なのは、今勉強していることについて常に「自分にどう関わるのか」「自分ならどうする(どう使う)か」を考えるクセをつけることです。例えば、算数の割合の問題なら「もし自分がお店の店長だったら、どうやって割引を考えるだろう?」と想像してみる。社会科で歴史を学ぶときも、「もし自分がその時代に生きていたら、どんな行動をしただろう?」と考えてみる。こうしたちょっとした想像が、知識を「自分ごと」として受け止めるきっかけになります。
もちろん、子どもたちにいきなり「自分で考えなさい」と言っても難しいこともあります。だからこそ、教える側がシチュエーションを設定してあげることが大切です。「コンビニで100円のジュースが2割引になったら、いくらになる?」とか「もし戦国時代にタイムスリップしてしまったら、どの武将に仕える?」といった具体的な場面を提示すると、子どもたちのイメージはぐんと広がり、学びやすくなります。
さらに、もう一つ大切な視点があります。それは、勉強している内容を「発見した人」「考えた人」「作った人」に目を向けることです。教科書に当たり前のように載っている知識は、実は長い歴史の中で誰かが努力し、工夫して生み出してきたものです。例えば、地動説を唱えたコペルニクスや、元素の周期表を作ったメンデレーエフ。彼らの発見や整理がなければ、今の科学は成り立っていません。そう考えると、学んでいる内容がただの「暗記項目」ではなく、「人類の知恵の結晶」として見えてくるのです。
「これを考えた人、すごいな」と思えると、勉強は不思議と楽しくなります。感謝や感動の気持ちが湧いたとき、子どもたちは自然とその知識を深く心に刻むことができます。
勉強を「記憶に残す作業」としてだけ捉えるのではなく、「印象に残す体験」として積み重ねていくこと。それが、長く使える知識を身につける一番の近道です。そして、その学び方を支えるのは、保護者の方や私たち指導者のちょっとした工夫です。ぜひお子さんと一緒に、「どう関わる?」「誰が考えた?」と会話しながら、学びの楽しさを広げていければと思います。

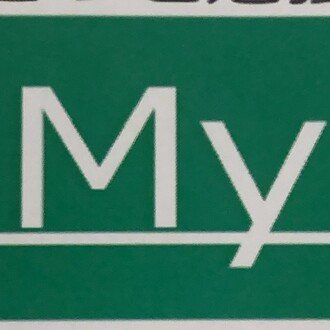
コメント