「日本人=NPC論」を読み解く:中国人視点で考える日本社会
最近、中国のSNSで『日本人=NPC論』というユニークな言説が注目を集めています。実際、中国SNS(小紅書)を見ると多くの議論を見ることができます。
NPCとはノンプレイヤーキャラの略称です。
ノンプレイヤーキャラクター(英: non player character, NPC)とは、プレイヤーが操作しないキャラクターのことを指す語である。プレイヤーに操作されるキャラクターを指す「プレイヤーキャラクター(PC)」の対義語である
本記事は中国での『日本人=NPC論』を読み解く試みです。
まず、その代表として一つのエピソードを紹介します。
日本人がNPCである証拠を見つけた
ファミマで会計をしていて、商品をカウンターに置きながら口にした。
「袋ちょうだい」
店員さんは「はい」と返事をして、そのまま操作を続けた。私はもうやり取りが終わったと思って、下を向いてスマホをいじり始めた。
すると数秒後、彼女が突然「〇〇ですか?」と聞いてきた。
私はスマホに夢中で全然聞き取れなかったけど、条件反射で「お願いします」と答えてしまった。
そして私たちは同時にフリーズ、3秒間固まった。ハッと気づいた。彼女がさっき聞いたのは「袋いりますか?」だったのだ。
つまり、私はすでに袋を頼んでいたし、彼女も「はい」と答えていたのに、袋についてのやり取りは本来「店員が聞く流れ」で進むものだから、さっきのやり取りをもう一度繰り返してしまったのだ。
そのままお互い2秒ほど見つめ合い、彼女のCPUが焼き切れたように見えた。
その時、彼女はふっと目を伏せ、深呼吸してから、気まずそうに笑い「すみません」と言った。そして袋を取り出し、お金を受け取り、レシートを渡す。
一連の動作はまるで流れるようにスムーズ。さっきまでのバグなんて存在しなかったかのようだった。システムが再起動した後のように、すべてが平常に戻った。
これは単なる日常の出来事を描いた体験記であると同時に、日本社会の「マニュアル化」を風刺した小さな記録です。コンビニでの一瞬のやり取りは、誰もが経験したことのあるささやかな場面かもしれませんが、そこに「NPC的だ」と感じさせる要素が凝縮されているのです。
実際、コンビニだけでなく、日本では統一化された行動やファッション、規則に従う態度が目立ちます。通勤ラッシュの黒スーツ、雨が降った瞬間に一斉に開くビニール傘、横断歩道で信号が変わると同時に歩き出す人々。
これらは外部の観察者から見れば、まるで「同じプログラムを読み込んだキャラクターが同時に動いている」かのように映ります。だからこそ、中国のネット文化の中では『日本人=NPC』という表現が、揶揄や風刺を込めて使われています。
この『NPC論』をより深く理解するために、ここでは別の文章も紹介してみたいと思います。以前に取り上げた中国人の思考法の特徴として「理詰めで全体を整理する」という姿勢があります。
彼らは物語を分析する際「キャラクター」と「物語構造」という二つの要素に分けて考え、さらにその相互作用を重視します。
これを日本社会に読み替えたとき、どのように社会の構造を理解していくのでしょうか。
日本は巨大なオープンワールドゲームのようだ
日本はまるで緻密にプログラムされたゲームのように感じられる。世界の大多数の国々と比べて、日本の社会運営・公共秩序・日常生活は、ランダム性が低く、制御されたエントロピーに従っている。
電車は定時イベントのように動き、街は常に整然とした状態を保ち、規則と秩序はゲームのシステムロジックのように安定している。ここでの偶然は、ゲームの疑似乱数のようにアルゴリズムに沿って動いているようだ。
もちろん、日本も現実世界の国家であり、自然や社会の面では予測不能なこともある。だがもし国連が「最もゲーム世界に近い国はどこか」という投票を呼びかけたら、私は日本に一票を入れるだろう。
留学初期の体験
日本に来て大学院に入ったばかりの頃、私はこの国のすべてに好奇心を抱いた。区役所の国際交流イベントに参加したり、大学のサークルに入ったり、ポストに入っていたチラシさえ読み込んだ。「日本のレストランはどんなプロモーションをするのか?」と。
そうして知れば知るほど、想像の中で固まっていた印象は崩れていった。よく言われるように、経験は固定観念を取り払う最良の方法だ。
しかし今でも時折強く感じることがある。それは、日本がまるで巨大なオープンワールドゲームのようだ、という感覚だ。
もちろん、これはあくまで私自身の一つの見方にすぎず、強い主観性を帯びている。
日本に暮らしていてもまったくこうした感覚を持たない人もいるかもしれないし、他の国に住んで同じような感覚を抱く人もいるかもしれない。どちらも十分あり得ることだ。
日本人の「NPC感」
もちろん、一人ひとりの日本人は生き生きとした個性を持っている。ただここで言いたいのは「共通して見られる高度な秩序性」だ。
秩序とは「列に割り込まない」といった狭義にとどまらない。特定の場面で、日本人の行動パターンはかなりの確率で予測できる。入力するプロンプトさえ間違えなければ。
例えばコンビニで水を一本買うと、レジの店員はほぼ必ずこう言う。
「合計110円です → お支払い方法は? → 袋はご利用ですか? → レシートどうぞ」
「普通じゃないの?」と思う人もいるだろう。
だがそうではない。私が行った多くの国では、レジ係は何も言わなかったり、決まりきった言葉が存在しなかったりする。
極端な例はエジプトだった。やはり水を一本買った時に、店員に突然「どこから来たの?車をチャーターしない?」と聞かれた。全く予想しなかった反応だった。
日本の店員のやり取りは、その低ランダム性の一例に過ぎない。行動が予測できる度合いが高いほど「NPCっぽい」、低いほど「生きた人間らしい」と言えるかもしれない。ここで優劣は論じない。ただ事実としての違いを指摘している。
秩序と生活感覚
最近、アメリカ人の友人と食事をした。彼は「円安で日本の給料はもうアメリカの背中すら見えない」と嘆き、帰国を考えているという。だが同時に「安全面を考えると今は日本人としかデートしていない。40歳近いからもう刺激は求めない」とも言った。その気持ちは理解できる。
今の私はむしろ、日本人が当日になって「やっぱり予定は無理」とキャンセルするだろうことを予測できるので、そもそも準備すらしなくなった。職場や生活で交わされる定型文メールや電話応対も枚挙に暇がない。
服装の統一感もNPC感を強めている。スーツ発祥の欧米では、すでに服装の自由度が広がっている職場が多い。しかし日本では依然として正装文化が根強く、白シャツに黒スーツはサラリーマンの制服だ。サービス業や工場労働者も業種ごとの制服を着用する。
私服においても規則性が目立つ。経済停滞が長引く令和の日本は、昭和・平成初期の華やかさから一転し、全世代の服装が黒・白・灰・茶といった落ち着いた色合いに統一され、女性は前髪を揃え、ロングスカートが多い。もちろん全員がそうというわけではないが、全体の傾向として目立つ現象だ。
都市の構造とゲーム感
日本人のNPC的な感覚だけでは、日本全体を「設計されたゲームプログラム」のように見せるには不十分である。もう一つの重要な要素は、日本の都市が非常に規則正しく整えられているレイアウトだ。
日本に住んだことのある人、あるいは日本について理解している人なら、おそらく気づいているだろう。日本の都市はすべて駅を中心に放射状に広がっているのだ。
池袋駅を例にすると、駅周辺は商業区画で賑やかだが、少し離れると一気に静かな住宅地に変わる。その切り替わりは唐突で、まるで編集済みのパラメータのようだ。
建物の外観も画一的で、直線的なデザインが多く、俯瞰すると「巨人が積み木で遊んでいる」ように見える。
渋谷のスクランブル交差点などは、まるでレゴの街並みのようだ。
また、日本の様々な施設にはゲーム的な特徴もある。たとえば、街中にあふれるコンビニや自動販売機は、ゲームに登場する薬屋や雑貨屋のようで、喉が渇いたりお腹が空いたら「ポーション」を買いに行く感覚に近い。
あるいは、電車や新幹線に乗るときにセキュリティチェックが不要で、鉄道網の密度が非常に高いため、どこへでも簡単に移動できる。その快適さは、RPGで気軽に各ダンジョンへ飛べる仕組みにそっくりだ。
労働システムのクエスト感
ゲームにはクエストシステムがあり、報酬が明確であることが多い。日本のアルバイトも同じように、時給は全国的にほぼ一律で、東京はやや高めだ。採用も比較的容易で、日本語さえできれば大抵すぐに働ける。
このアルバイトシステムは、まるでゲームにおける「固定クエスト」のようである。実際、日本人の中には正社員を持たず、必要なときだけ働いて、あとは休むという人も少なくない。これは「ガチ勢」ではなく「ライト勢」のプレイヤーに似ている。
最近読んだ投稿にはこんな話もあった。かつて日本に留学していた人が十数年ぶりに観光で訪れ、昔アルバイトしていたコンビニに立ち寄ったところ、当時一緒に働いていた同僚がまだそこにいた、というのである。
自然環境とACG(アニメ・コミック・ゲーム)文化
日本の発達した市街地と荒々しい自然地域との結びつきは非常に高い。ある時、仕事が終わってから東京から電車に乗って横浜へ海を見に行き、遠くに広がるスカイラインを眺めて、そのまままた電車で東京に戻ったことがある。
全行程で三時間もかからなかった。まるでゲームの中で自然探索をしているようで、不便さはまったく感じなかった。
最後の要素として、日本そのものが非常に濃厚なACG(アニメ・コミック・ゲーム)の雰囲気を持っていることが挙げられる。世界でもおそらく日本だけだろう、国家公務員の採用試験の広告にまで漫画を用いる国は。
長年の産業的蓄積によって、日本の多くの現実の場面が二次元ファンにとっての「聖地」と化している。たとえば、野原しんのすけの故郷・春日部市では、地方政府が『クレヨンしんちゃん』のIPを公式サイトにまで使用している。
私の知り合いのドイツ人は、初めて日本を訪れたとき、迷宮のような新宿駅を非常に正確に歩き回ることができた。というのも、彼はすでにアニメを通じて新宿を熟知していたからだ。私は二次元オタクではないが、それでも日本にどこか「ゲーム的」な感覚を覚える。アニメや漫画が好きな人なら、きっとさらに深い体験になるだろう。
結び
そのほかにも、より細かな要素が日本に「ゲーム的な雰囲気」を与えている。四角く小さな自家用車、端午の節句に掲げられる鯉のぼり、街頭で演説する政治家、初秋の花火大会。こうしたひとつひとつが、物語的な感覚を人々に抱かせるのだ。
ここからは、この文章から見える中国人独特の思考法を解説します。
キャラクターとプロットの二項分析①
この文章では「日本人一人ひとりは生き生きとした個性を持っている」と強調されています。しかし同時に、その個性は「秩序的行動や社会の仕組みによって予測可能」と描かれています。ここで「キャラクター性が薄れる=NPC的に見える」という視点が提示されています。
駅を中心とした都市構造、定型化された接客、画一的な服装、全国的に似通った時給や労働システムなど、社会全体をシステムやゲームのルールとして整理しています。これは「物語の構造=プロット」に相当します。
筆者の見る限り、中国のネット空間や知識人の議論においては、社会を解釈する際にある独特の思考のリズムがあります。それは大まかに言えば、感性と理性の往復運動です。
具体的には、次のような流れが多いように思います。
まず感性で受け止める
街に出て、人々の姿や日常風景を「なんだかゲームの世界みたいだ」と直感的に捉える。
それを理性的に解釈する
なぜそう感じるのかを分析し、比喩や概念で整理する。「NPC的なふるまい」、「オープンワールド的な社会構造」といった言葉がここで生まれる。
その解釈をもって再び感性で受け止める
理性で導き出した言葉を使って社会を見直すことで「ああ、やっぱり日本人はNPCみたいに見える」と再確認する。
冒頭で紹介したエピソードのように、このプロセスは一度きりではなく、繰り返し循環します。感性が理性を呼び、理性が感性を補強する。その往復の中で比喩や概念は強化され、やがてひとつの世論や文化的共通認識として広がっていく流れです。
なぜ日本で、このような社会が生まれたのでしょうか。実際に日本で働く中国人が見る、別の視点からその理由を知ることができます。
なぜ日本人は冷たいと思われるのか?
これはずっと議論を呼んできたテーマです。日本で留学し、働きながら3年半過ごしてきた私個人の感覚では、「日本人が冷淡だ」と言うよりも、むしろ「日本人は人と人との境界線を重視している」と言った方が正確だと思います。
日本社会は、他人に迷惑をかけないことを非常に大切にしています。子供の頃から独立することを教育されてきた日本人にとって、これは単なる礼儀ではなく、無意識のうちに生活のルールとなっています。
オフィスでも日常の交際でも、日本人は自分の行動を非常に慎重に考えています。自分が他人に迷惑をかけないようにし、また無駄に人情を負うことも避けたいと考えているのです。
この心情は、例えば会合の際の割り勘、仕事でのプロセス厳守、日常的な手助けにも一定の距離感があることに現れています。彼らは冷たく見えるかもしれませんが、実際には他人の自由を尊重し、自分自身の境界も大切にしているのです。
また、日本社会は非常に制度化されており、多くの事は人間関係に依存するのではなく、規則、プロセス、責任によって進行します。この方法は人間関係をより明確にし、摩擦を減らし、潜在的な利益のもつれを少なくします。彼らは感情を義務の中に持ち込むことを避けているのです。
ここに住んでいる人々にとって、誰もが自分の役割と限界を持っていて、感情はお互いの価値を測る主要な基準ではありません。
また、日本の社会保障制度や生活様式は、この独立感を形作っています。高齢者には年金があり、一般社員は終身雇用制度の恩恵を受け、大多数の人々は自分で生計を立てることができます。この環境は、他人に依存する必要性をなくし、独立心、理性、距離を保つことが最も安全で快適な生活方法となっています。
加えて、速いペースでの生活とストレス管理のために、適度な距離を保ち、交流頻度をコントロールすることで、誰もが自分にとって最も重要なことにエネルギーを集中できるようになります。
彼らは感情を無視しているのではなく、自分のエネルギーと感情を非常に大切にしており、それを長期間の付き合いや深い絆を築ける人々に精密に投資するのです。
親密な友達になる前には長い準備と観察の期間がありますが、一度友達と認定すれば、その関係は非常に誠実で信頼できるものになります。
(中国人のもつ)熱い人情には時に、個人の境界が侵害される可能性が隠れていることがあります。自由で独立した人生を送りたいと思うなら、しばしば不必要な人情を切り捨てなければならないのです。
私は個人的には、この2つの生活スタイルに優劣はないと考えています。大切なのは、自分の理想的な生活に対して合致しているかという判断です。
日本に住んでいる皆さん、この微妙な人情のリズムを感じたことがありますか?
この文章から、日本人が「NPC的」と感じられる理由を読み取ることができます。それは、以下の要素に起因しています。
人間関係の距離感と冷淡さ
日本人は人との距離を保ち、感情をあまり前面に出しません。これが冷たいと感じられる一因ですが、実際には個人が自立し、他人を尊重し、自分の境界を守るための行動です。この誤解が「NPC」のように感じさせる要因となります。
規則とプロセス重視の社会
日本では、感情よりも規則やプロセスに基づいて行動が進むため、予測可能で、個々の人間が「役割」を果たす形になります。このような社会では、自由な個人の感情や行動よりも、一定の枠組みで動くことが強調されるため、「NPC」感が生じやすいです。
キャラクターとプロットの二項分析②
そしてまた、この文章も個と構造の二項対立を前提にしています。
キャラクター=個人の感情
この文章は「日本人は冷たいのか?」という問いを出発点にしているが、実際には「冷たい」感情ではなく「境界を重視する」という個人の行動に焦点が当てられている。つまり、感情がなぜ生まれるのかを考察している。
プロット=社会の構造
行動様式の背景に、社会制度・生活様式・文化的規範といった「構造」があることを繰り返し強調している。この文章は「個の行動」が「構造」によって規定されていることを示す、典型的な「キャラクター×プロット」型の分析である。
「日本人=NPC論」は偶然ではない
「日本人=NPC論」は決して偶然の産物ではありません。日本社会に長く暮らす中国人が増え、その観察眼によってより解像度の高い評価が行われるようになった結果として生まれてきたものです。
かつて日本も、現在の中国と同じように長いデフレ時代を経験しました。しかしその過程で、中国の「内巻(意味の無い過剰競争)」に相当するような、社会の状況を一言で言い表す言葉は生まれませんでした。
筆者はその背景に、日中それぞれの社会が持つ「現実をどう評価するか」という違いがあると考えています。中国では社会の矛盾や行き詰まりが鋭く言語化され、それが新しい概念として拡散します。
「内巻」という言葉が生まれたことで、人々は自分の状況を説明する手段を得ただけでなく、その言葉を通じて行動様式までも変化させつつあります。
言葉は単なる説明にとどまらず、現実を規定する力を持っています。現代社会をどう認識し、どんな言葉で切り取るかは、その社会に生きる私たちの行動の選択にもつながっていく。筆者はそう考えています。
感性と理性を往復させるこの独特の思考スタイルは、単なる風刺や批評にとどまらず、日本社会をどう理解し、どう更新していくかを考えるうえで貴重な視座を与えてくれるのだと思います。
いいなと思ったら応援しよう!
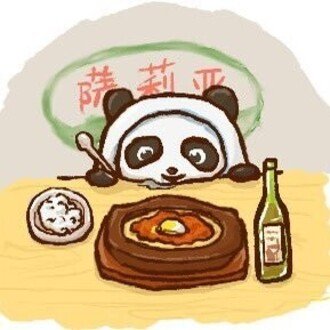 チップのご検討をいただき、ありがとうございます。
いただいたチップは全て記事を書くための費用として使わせていただきます。
チップのご検討をいただき、ありがとうございます。
いただいたチップは全て記事を書くための費用として使わせていただきます。

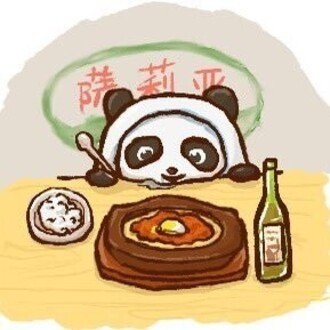
相変わらず面白いです。 中国のお二方の分析は、まあそうだよなーと思います。特に違和感がない。 ただまあ、やはり都市部中心に見ている感はありますね。 それから、言葉によって現実を規定し、規定された言葉が現実を作るというえいちゃんさんの考察面白いですね。言われてみれば、確かに中国ってすぐに現象を表す言葉つくるよなー、と思いました。 この違いがどう具体的な違いにつながるのか、変な言い方ですがちょっとわくわくしますね。 次も期待しています!