田中秀和すぎるメロディについて~王道進行編~
はじめに
何かとコード進行の奇抜さが取りざたされる作曲家の田中秀和さんですが、実のところ、彼の最大の個性はその圧倒的なメロディセンスにあります。
本記事では、王道進行やその派生のコード進行上で、個人的に田中秀和らしさをひしひしと感じるメロディを集めてきたので色々お話していきます。
長い記事になると思いますがお付き合いください。
「全部は見れないよ!」という方には『Sparkle』『CAFUNE』『さんさーら!』『Precious』『Prism Spiral』や「まとめ」、あたりを読んで頂くのがおすすめです。
あとこの記事のサムネイル画像、めちゃめちゃ勝手に使いすぎて怒られが発生しても全くおかしくないのですが、過去に田中秀和が自身のメロディについて言及していた番組の画像です。
昔はYoutubeで見れたのですが、現在は削除されてしまっているので恐らくBilibili動画でしか見れないと思われます。
気になる方は、「田中秀和 DTM LAB」で検索してみてください。
本記事ではすべての楽曲をCメジャーキー(Aマイナーキー)に直して扱っています。
また、コード進行はほとんどChordWikiを参照しています。
ChordWikiにない曲は軽く耳コピしたものを載せていますが、テンションなど細かい部分は分からないので参考程度にご確認ください。
本編
田中秀和らしさって?
田中秀和らしいメロディとはなんなのでしょうか?
ここではあくまで、私個人が「田中秀和っぽいな~」と感じるメロディについてではありますが、その要素を書き出してみます。
1.繰り返し
2.クロマチックアプローチ
3.ダイナミックな跳躍
4.アルペジオ
大きくこの4つがあげられると思います。
それぞれの要素について軽く説明しますが、具体例を見た方が分かりやすいのでここは軽く流してもらっても大丈夫です。
1.繰り返し
これは言葉の通り、同じメロディを繰り返すことが多いです。
全く同じリズムと音高なこともあれば、リズムだけ同じで音高が違うこともありますし、あるいは同じ音形を下にズラして繰り返す、とかもします。
田中秀和に限らず、ポップスのメロディは繰り返しが意識されることが多く、その方がキャッチーになりがちです。
2.クロマチックアプローチ
クロマチックアプローチとは、「半音隣の音に解決させる」前提で「その時の音階からは一時的に外れている」音を持ち込むことです。Sound Questより引用
これに関してはすぐ次のSparkleでもやってるのでそちらで説明します。
3.ダイナミックな跳躍
跳躍とは離れた音にメロディが移動することです。
メロディが大きな変化をするとそれだけダイナミックな印象になって心を揺さぶられる印象があると思います。
4.アルペジオ
アルペジオとは和音をばらして演奏することです。
歌モノのメロディに対して使う場合は、その時に演奏されているコードの構成音をなぞるという意味合いで使われる気がします。
コードトーンをアップダウンしたりすることで、彩りを生み出します。
これらのクロマチックアプローチであったりアルペジオであったりは、
ジャズのアドリブにおいて用いられることが多いです。
田中秀和のメロディは一言で言えば「ジャズのアドリブをよりポップスライクに落とし込んだメロディ」であると言えるかもしれません。
それではここからは実際に田中秀和の楽曲を見ながら、彼らしいメロディについて考えてみましょう。
『Sparkle』
まずはじめ、「あたま」で完全4度跳躍します。
「まからいっそ」と「ミネラルウォーター」は同じ音形で、繰り返しが用いられてますね。
さらに、彼らしさを特に感じるのは後半部分で、
「かぶっちゃえ」はⅢm7(-5)の構成音をなぞりながらアップダウンをします。シ♭の音が含まれててエモい…
そして最大の秀和ポイントはⅥ7上の「躊躇なく」=「ファミレ♯ミ」でしょうね。
これがまさしくクロマチックアプローチです。
「ミ」に対して半音の動きを作るために「レ」をシャープさせています。
仮に田中秀和三種の神器というものがあるとすれば、間違いなく
この「ファミレ♯ミ」が1つ目でしょう。
Ⅵ7上のアプローチノート「レ♯」はまじで頻出なのでこれだけでも覚えてください…!
ポップスらしくキャッチーでありながら、彩り豊かで情緒的なメロディ、
それが田中秀和のメロディです。
Sparkleに似ている曲で言うと、次の曲があげられます。
『GO-MA-N-E-TSU』
この曲は何と言っても「近づいて」のラ♭連打が強烈。
その後の「なるその」も「ソレシソ」とコードトーンをアップダウン。
極めつけにSparkleと同じくⅥ7上に「ファミレ♯ミ」が登場。
全体的に思わずクネクネしてしまう仕上がりです。
『Cidre』
「別れ際」の部分はノンダイアトニックノートではないものの半音の動きで、これも彼らしさを感じるポイントでもあると思います。
「終わりみたい」は「ソレシ♭レド♯」と、跳躍とノンダイアトニックノートの合わせ技。贅沢にも「シ♭」と「ド♯」を両方使うのが良い。
秀和の曲は難しいメロディでありながらもブレスが用意されてがちですが、この曲はとにかく詰め込む!
器楽的なメロディであると言えるかもしれませんね。
あと一応、コード進行が変すぎるので触れますが、これは秀和あるあるの
♯Ⅳm7(-5)|Ⅶ7|♭Ⅶ|Ⅵ7
というコード進行、をさらに複雑にしたもの。
こんな見た目でもちゃんと王道進行の派生です。
特に「夏のお」の部分の「ソ」の音は本来はⅢm7の3rdに位置するのですが、ここでは♭Ⅶに対して6th(13th)に位置していて、独特な響き。
この手の進行の♭Ⅶは♭Ⅶ6になりがちです。
『シンカケイスケッチ』
田中秀和ココニアリ
とでも言えるようなメロディ。ほんとに良いなこれ。
こんな良いメロディが書きたいものです。
まずはじめ、「昔ゆ」は「ドシシ♭ラ」と半音下行でスタート。
もう秀和。
「わたしのつ」は「ミミファファ♯ソ」という半音上行のフレーズ。
ミツキヨさんとかが良く使うイメージのメロディです。
彼にその意識があるか分かりませんが、最初の半音下行と対応させることを意識してたりするのかな。
「進行形」は「シ♭ドシ♭ラ」で非常に美しいクロマチックアプローチ。
歌詞も相まってほんとにワクワクする。日々が楽しくなる気がする。
ラテンフィールなど編曲面も合わせて、
秀和界でもトップレベルに良いBメロだと思います。
『CAFUNE』
田中秀和すぎるだろ。
初手から長六度跳躍。長六度は跳躍のなかでもちょっと特別感があって特段エモい気がします。
そして「朝焼け」はシンカケイスケッチの「進行形」と同じ「シ♭ドシ♭ラ」という非常に美しいクロマチックアプローチですね。
この曲はとにかく跳躍します。
跳躍をしすぎて、全体を見ると「Star」「愛」「朝焼け」が低音域、「light」「ささやく」「君を」が高音域というように音域がくっきり分かれてしまってます。
この高域低域が変わりばんこに来る感じと、音域による鹿乃さんの歌声の変化が奇妙な心地よさを生み出しています。
そしてこれだけしておきながら、「愛ささやく」と「朝焼け君を」は音形が非常に似ていて、似ている音形を数音下げて繰り返す、リフレインも意識されているという…
田中秀和、恐ろしい男だ。
メロディの音数としては少ないのにも関わらず、一音一音で確実に聴き手を揺さぶり、そして覚えていられるメロディ構造を作ることで、サビとしてとんでもない満足感を与えているように思います。
『さんさーら!』
これはお手本のような秀和イズムを感じさせるメロディ。
一聴すると「なんだこれ?これで合ってるの?」となってしまいそうですが、数回聴けば覚えてしまう、癖になってしまいます。
まず全体を見ると「友達」「百人」「できる」「できない」がそれぞれ同じリズムで繰り返されていますし、歌詞の切れ目にも沿っていてとても綺麗。
「友達」は「ラレ♯ミ」
♯Ⅳm7(-5)の3rdからクロマチックアプローチを経て7thに到達。
しかもこれ「ラレ♯」はトライトーンです。強烈…
「百人」は「ラミレ♯」
同じく「ラ」始まりですが、Ⅶ7の7thへと、コードから見た位置が変わっています。
そしてさきほどとはアプローチノートが入れ替わり、Ⅶ7の3rdに到達。
要するにコードが変わっているのに、
メロディは後半2音が入れ替わっただけなんです。
それでいて印象はガラリと変わるという。
↑この構造美が素晴らしい…
4776進行上で望ましいメロディを完全に熟知している…
「できる」は「シラソ」です。
「ソ」で着地することからも、やはり秀和はここでの♭ⅦのコードをⅢmの代理として捉えてることが分かりますね。
他が全体を見ると上行してる音形であるのに対し、ここは下行しており、
ここで一息ついて「できない」でまた上がる準備が出来ると思います。
「できない」は「レミド♯」で、
フレーズ終わりがノンダイアトニックノートになっちゃうタイプ。
「百人」でもⅦ7の3rdに着地していましたが、ここでもⅥ7の3rdに着地。
対応関係が美しい。
こうしてみると彼の曲は、何も知らなければ外した音を使っているだけのようにも思ってしまうメロディも、実際には全て意図されていて美しく用いられていて、まるで良くできた建造物のような構造美にウットリしてしまいます。
『Hoppin' Season♪』
ここで「ファミレ♯ミ」に続き第二の秀和神器、「ソ♯ラ」が初登場。
王道進行頭のⅣで頻繁に用いられ、「ソ♯」の部分にはⅠaugやⅠaug/♯Ⅳの和音があてられることが多いです。
Ⅲm7にかけて「ソ♯ラ」を全音下げた「ファ♯ソ」というクロマチックアプローチが用いられていますね。同じ動きを下げて繰り返す。
なによりここの「笑い」は「ソファ♯ソ」という長七度跳躍からのクロマチックで、合計すればオクターブ跳ねてます。
この曲はこの王道進行部分以外にも、特にサビ全体で跳躍やクロマチックが多く、ぜひフルで聴いて頂きたいです。
そして何気にこの曲は本来Ⅴの和音の部分が上ズレのblkコードにあたる、Ⅱaug/♯Ⅴが使われていますね。すごくめずらしい。
他の用例だとわんだフル・わんデイのサビとかですかね。
『Precious』
やりすぎ。
こんなメロディ、長瀬麻奈さん、ひいては神田沙也加さんじゃないと歌いこなせないです。
でもすごくかっこいい。それはもうめちゃめちゃかっこいい…
初手から秀和神器の「ソ♯ラ」ですね。ここでは♯Ⅳblkのタイプ。
「いを束ねて」は「ドレシ♭ラ♭シ♭ソ」で、「レシ♭」にかけて短六度跳躍します。
このメロディはCホールトーンスケールを想定しているか、あるいはCメロディックメジャースケールを想定しているかといったところ。
いずれにしても、この「ラ♭シ♭」周りは秀和神器の最後の一つと言ってもよいくらい頻繁に用いられます。
王道進行の文脈で使われることは珍しいので今回は扱ってませんが、他にも
シンカケイスケッチの「行動原理と」=「ソソファドラ♭シ♭ソ」
アマカミサマの「アマカミサマ」=「シ♭ラ♭ソファラ♭ソ」
花ハ踊レヤいろはにほ「風任せだと」=「ソラ♭シ♭ラ♭ソファソ」
などなど、あげればキリがないです。
「あなためがけて」にも「ファ♯ソ」や「シ♭」の跳躍など、秀和らしいポイントがもりもり。
そして「秒思いを束ね」「てあなためがけて」は対応関係にあって、リズムは同じです。
これだけ入り組んだメロディでありながら、大枠には繰り返しがあるのがやはりどこまでもポップスだな~と感心します。すごすぎ。
『アマカミサマ』
さて、ほんとはPreciousとPrecious memoriesを並べようと思ってましたが、Preciousの「ラ♭シ♭」周りでアマカミサマを思い出してしまったので泣く泣く挿入。
Ⅳの和音がⅣmM7になっているので、この部分でだけ聴くと違和感がすごいですが、これは前後の流れありきのコード進行って感じですね。
はじめの「わたし」で短七度跳躍。
その後の「したちの絶妙な」が「シ♭ラ♭シ♭ラ♭ソファソラ♭ソ」となっていて、神器である「ラ♭シ♭」周りのメロディがたくさん使われてます。
「さじか」の部分も「ミソシ」とⅢm7をなぞるアルペジオで、
こう聴くとなんで思い出せなかったんだろうと思うくらいには秀和らしいメロディですね。
『Precious Memories』
こんな良いメロがDメロで来たら泣いてしまう…てか泣いてる。
「両手でも抱えきれ」「ないほどの大切が」は対応関係にあって、
リズムが全く同じです。
最初に♯Ⅳm7(-5)に差し掛かるところで長六度跳躍。
やっぱり泣ける、長六度。
何気にここ、理論的には跳躍先の「ラ」が♯Ⅳm7(-5)の3rdに位置していることがこの泣ける印象をより後押ししてるんですけど、そうゆう話は別の誰かがしてくれるでしょう。
そしてⅣm6では短六度跳躍で半音下の「ラ♭」をしっかり抑えていますね。
その他、「ほどの」=「レド♯レ」のクロマチックであったり、
「大切」=「レレレ♯ミ」の半音上行などなど…
サビにもなりうるようなパワーのあるメロディを、Dメロで惜しみなく使ってしまうのがすごい。どこ聴いても実質サビです。
『STORY』(carriage for cutie)
歌詞があって扱いやすいのでSTORYとして扱っていますが、実際にはデレアニ劇伴、M03「carrige for cutie」の引用です。
「た夜でもみ」は「ミ♭ミ♭レドラ♭ソ」でⅣm7の7thの「ミ♭」から3rdの「ラ♭」をアプローチノートとしてソに着地。綺麗~
「見えるめ」は「ソシレソ」でこれこそⅢm7のアルペジオと言っていいんじゃないでしょうか。コードトーンをなぞってオクターブ上に到達。
このメロディ、個人的には相当田中秀和を感じます。
ところでこのメロディ、堂島孝平の『葛飾ラプソディー』に似てませんか?
まあ似てるっていうだけなんですが。
『M@GIC☆』
一番オーソドックスに美しい4736進行のメロディかもしれませんね。
そしてこのメロディ、Dメロと合わせて見てみるとちょっと面白いです。
「ぞれの手の」は「シドレシソ」というイントロの「シドレシラソ」と
すごく似ている音形を使っています。コード進行は同じですしね。
なんとなく、イントロで提示したメロディをアレンジしてDメロとかで聴かせると楽曲の統一感が出るというか、展開が多くてごちゃごちゃすることを防げるように思います。
そして「つなげて」では秀和神器の一角、「ファミレ♯ミ」が登場。
やはり素晴らしいメロですね。
『ステラ・ドライブ』
この曲、元から大好きだったんですけど、このnoteを書く過程でさらにもう一段階好きになりました。
正直このBメロはめちゃめちゃ異彩を放ってます。
全体を見ると、「街で暮らすまでの」「ストーリーアカシックな」が
同じリズムで繰り返されてます。
「すまでの」は「レ♯シレ♯ラ」で、Ⅶ7をなぞってアップダウンします。
特に「レ♯ラ」はトライトーン跳躍。なにをしているんだ。
そこから「ストーリー」は「ラシソ」
Ⅲm7で11thの「ラ」を伸ばして、「ソ」でやっと着地する。
あとこれに関しては秀和らしさとか関係ないですけど、
奇数小節目は頭からメロ入り、偶数小節目は遅れてメロ入りするのが好き。
結構際どいメロディな気がしますが、なぜか違和感が全くなくて。
楽曲全体を見るとコード刻みのリズムであったり、空間を感じさせるコーラスとか編曲もすごく良くて…
こんな曲作りたいよ~!!!
まじでこんな曲田中秀和にしか作れないと思います。
『七つの海のコンサート』
このnoteを書こうと思ったきっかけの曲です。
この部分田中秀和すぎるな~と思いました。
「大きな」で「ドミソド」と、Ⅰのアルペジオ。
「な海のどこ」「か君のメロ」は同じリズムを繰り返します。
何気に「海のどこか」の「ドシドラシソ」がすごく彼っぽい。
あえて言語化するなら、ミクロでみればアップダウンの動きをしながら、
マクロで見ると下行しているメロディ。伝われ。
そしてダメ押しのⅥ7上の「シ♭」
田中秀和でしかない
さて、次の曲からアイカツゾーンに突入です。
『Shiny day』
秀和っぽいポイントが盛り盛り!!
神器の「ソ♯ラ」から始まり、「ずっと」の「ソファ♯ソ」、
そしてⅥ7のシ♭などなど。
やはり4776進行上では、アプローチノート「ファ♯」が使いやすいですね。
そして相変わらず、「も花も木もずっ」「と気さくなままで」は同じリズム
『Prism Spiral』
王道進行というより2536なんですが、、、
9th乗ってますし、むしろメロディを見ればⅣM7を想定してるものと思います。ベースの都合でⅡm7(9)なんでしょうね。
全体を見ると、「あがるロマンス」「旅立つ瞬間」は対応関係にあり、数音下げて繰り返しています。
「あがる」「旅立つ」はそれぞれのコードトーンをなぞったアルペジオ。
そして「ロマンス」の「ス」が「レ♯」
今までの曲の場合、「レ♯」あるいは「ミ♭」が出てくる場合はクロマチックアプローチか、サブドミナントマイナー由来のものでしたが、
この曲ではⅤaug由来の「レ♯」のロングトーンが出てきます。
こんな感じでフレーズの終わりを外すのって、お茶目な感じとか「スンッ」とスカした感じがして、田中秀和らしさにかなり寄与していると思います。
さらに「ロマンス」は着地地点が「レ♯」、「瞬間」は「ド♯」と、対応関係にも事欠かずとにかく美しい。
全く同じ音形ではなく、「瞬間」で跳躍してアクセントを付けるのがたまらないです。
この曲はかなりお手本のような秀和イズムを感じますね。
『放課後ポニーテール』
コードが素直でとても見やすい曲ですね。
繰り返しはもちろん、「ラスとか」の「ミファファ♯ソ」や、
Ⅳm7上の「ミ♭」、Ⅵ7上で神器の「ファミレ♯ミ」など、
どこでも見られるシンプルなコード進行だからこそ、「じゃあ秀和ならどんなメロディをつける?」というのが顕著になる楽曲だと思います。
ところでこのメロディ、
kanakanakanatchさんの『微熱 because of』に似てますよね。
まあこれも似てるってだけなんですけど。
繰り返しの意識であったり、跳躍の多さ、blkコード上の「ラ♭」、
「ミファファ♯ソ」や、神器の「ソ♯ラ」と「ファミレ♯ミ」の併用など、
もはや田中秀和以上に田中秀和すぎるメロディかもしれません。
『オリジナルスター☆彡』
やっと正統な王道進行っぽいメロディが出てきましたね。
二拍コードチェンジタイプの王道進行。
「スペシャ」のオクターブ跳躍や、「コーデして」のクロマチックアプローチなど、2小節という短い間でも彼らしさを感じられます。
代表例としてオリジナルスターを使ってますけどこの系統の秀和曲はほかにもあります。
少女交響曲
Ⅵ7上のクロマチックがない分、秀和ポイントはオリジナルスターより低いですが、歌詞も相まってすごく似ている。
この曲は『田中秀和すぎるメロディについて~コンファメ進行編~』が存在すれば確実に扱うことになるでしょうね。(執筆の予定なし)
『Good morning my dream』
これもオリジナルスターの系統ですが、構造が見事なので節を立てます。
「めにあ」「つまっ」「じまる」「まいに」これら全て半音の動きです。
同じ動きを繰り返しながら上行してますし、クロマチックにも事欠かないという、かなり田中秀和すぎるメロディになってますね。
何気に「じまる」でアプローチノートとして用いた「ド♯」が
♯Ⅴdim7の構成音になっていて綺麗。
コードとメロディって常に一体ですよね。
『アイカツメロディ!』
同じ音形を下げて繰り返す。やっぱこれなんだな~。
跳躍もいっぱい。
そして「らとび」でクロマチックアプローチ、「ファ♯」が登場。
「このメロディ、4736進行に合いそうだよな」と思うのですが、
実際それもそのはずでサビ2週目では、ちゃんと4736になります。
こうするとアプローチノートの「ファ♯」がⅦ7の構成音としてすっぽり収まってより綺麗です。
彼は初めからこっちのコード進行を想定してメロディを作ってる気がします。
まとめ
ということで、ここまで王道進行上の田中秀和すぎるメロディについて色々見てきました。
繰り返しになりますが私の考えとしては、メロディの田中秀和らしさとは
1.繰り返し
2.クロマチックアプローチ
3.ダイナミックな跳躍
4.アルペジオ
にあると思っています。
繰り返しの意識によってポップスとしてのキャッチーさを保ちながら、
クロマチックアプローチや跳躍などによって
彩り豊かで、情緒的で、ダイナミックなメロディに仕上げる。
これらを複合的に用いて非常に美しい構造を完成させる。
これが田中秀和のメロディが他と一線を画す理由だと思います。
まあもちろん、メロディにも好みはあるのでもっとシンプルなほうが好きという人もたくさんいるとは思います。
また、特に頻出で彼らしさを感じさせるメロディ、
田中秀和三種の神器については
1.ファミレ♯ミ
2.ソ♯ラ
3.ラ♭シ♭周り
があげられると思います。
メロディメイクって、やっぱりセンスがものをいうというイメージがありますし、間違いなく田中秀和のメロディセンスはピカイチだと思います。
ですが一方で、これだけ構造として美しいメロディを作るためにはセンスだけでなく、膨大なインプットからくる経験や、理論によってメロディを洗練していく過程もまた不可欠なように思います。
このnoteが田中秀和ファンの皆さんや、作曲をする方々の参考になると嬉しいです。
以上、『田中秀和すぎるメロディについて~王道進行編~』でした!!!
おまけ
完全に自語りなのでおまけとしますが、私の曲にも秀和っぽいメロディがあったりするので紹介します。
ミラフォルテ
神器の「ソ♯ラ」から始まり、「かいも」=「レド♯レ」や
「ピント」=「ソファ♯ソ」のクロマチックアプローチなど。
「やけた」や「もピ」「トあ」など跳躍も多く、
かなり田中秀和すぎるポイントを押さえていると思います。
この曲作ってたの6月くらいなので、田中秀和のメロディについてしっかり言語化したり分析したりをする前の曲ですが、かなり田中秀和っぽいメロディになってて、「染みついてるもんなんだな~」と思いました。
「田中秀和っぽいメロディを作ろう!」と意識してるわけではなく、
自分の中での良いメロディがこのようにチューニングされているのかもしれません。
ただ、このメロディは本家秀和のように繰り返しの意識が弱く、構造的な美しさみたいな部分にも欠けるのでやはり秀和ほど秀和なメロディではないですね。それはそうと良いメロディではあると思います。
以上、おまけでした。

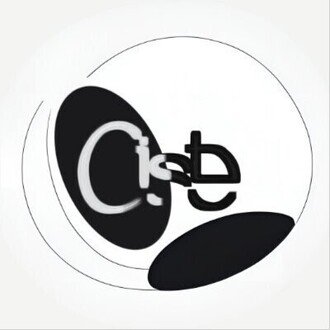
コメント