《魂の履歴書》第1章|幼き頃の祈り ——あの時すでに、祈りは始まっていた。
幼い頃、僕は「優しい子」と呼ばれていた。
たしかにそうだったと思う。人の顔色を見て、先回りして動き、
相手が悲しまないように、いつも空気を読んでいた。
だけどその裏には、“とても臆病だった”自分がいた。
ほんの小さなことで胸がいっぱいになってしまうような、
“繊細すぎる感性”を持て余していた。
それでも、「大丈夫」と笑っていた。
それが、僕の強さであり、同時に祈りだった。
「自分がやりたい」よりも「喜ばれるかどうか」
野球を始めたのも、父が喜びそうだったから。
ピアノを辞めたのも、譲らざるを得なかった家の都合。
それを責める気持ちはなかったけど、
何かを諦めるたびに、胸の奥が小さく疼いていた。
中学時代、恋をした。
でも、その想いを伝える勇気はなかった。
そのまま、心にしまって終わった。
その時の自分は、「傷つくよりマシ」と思っていた。
だけど、今ならわかる。
それは、自分自身とのつながりを断ってしまうような感覚だったんだ。
音楽に出会ったのは、表現したい気持ちが抑えられなくなったから。
それが初めて、自分の“本音”に近づいた瞬間だった。
だけど、バンドでも、自分は「2番手」だった。
センターにはなれなかった。
光を求めながら、常に影の位置を選んでいた。
小学生の頃、毎年秋頃になると長野のリンゴ畑に訪れていた。
東京から車で向かう旅は、家族との唯一の“心が緩む時間”だった。
農家さんの笑顔やりんごの香り、澄んだ空気と、柔らかい光。
子どもながらに、そこに**“見えない優しさ”**を感じていた。
今思えば、あれも祈りの原風景だったのかもしれない。
そして、もうひとつの風景——鹿児島。
祖父母の家に向かうと、星空に吸い込まれるような静寂があった。
祖父の手の温かさ、祖母の笑顔の奥にあるもの。
**「この土地が、この人たちを育んだんだ」**と
子どもながらに感じた。
あの時、風景の奥に“何か”を感じていた。
それはきっと、魂の記憶だった。
今になって思う。
あの頃すでに、祈りは始まっていた。
それは言葉じゃなく、行動でもなく、
「ただ、在ること」の中に宿っていたもの。
🌱この章は、僕の“始まり”を綴った記録。
まだうまく言葉にならなかった祈りが、
静かに芽吹き始めていた、そんな時代の話です。

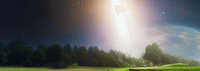

コメント