アニメ業界のM&A、成功と失敗を分ける条件を考える
■スタジオジブリも!相次ぐアニメスタジオ買収
グローバル市場が大きく成長するなか、いまアニメ業界ではM&Aが活発になっています。アニメ制作スタジオや関連企業の買収や売却、株式の取得です。
2023年の日本テレビによるスタジオジブリ子会社化は、大きなニュースだったので知っているかたも多いでしょう。
2024年にはKADOKAWAが動画工房を、東宝がサイエンスSARUを、バンダイナムコがエイトビットと大手企業の有力スタジオ完全子会社化が相次ぎました。
動画工房は『【推しの子】』 、サイエンスSARUは『ダンダダン』、エイトビットは『ブルーロック』といった作品を制作しています。
またこの7月、8月にはネット出版社アルファポリスがWHITE FOXを完全子会社化、AI技術のベンチャー企業Creator’s Xは木下グループよりガイナの株式を取得しグループ化しました。
日本テレビのスタジオジブリ子会社化は、株式追加取得100億円、企業価値は366億円と巨額になりました。ただアニメ制作現場の獲得というよりも、宮崎駿作品などスタジオの持つライブラリーが大きく評価されたと思われます。
2024年の3つのM&Aはアニメ企画・製作の大手企業によるスタジオ子会社化です。実際にアニメを作る現場獲得が狙いです。
また今年7月、8月のふたつのケースも制作スタジオ獲得ですが、異業種からのアニメ業界参入と様相は異なります。アニメスタジオのM&Aには、いま様々なパターンがあることが分かります。
■アニメ企業のM&Aが増えた訳
M&Aが増えたのは、グローバルでの成長産業としてエンタテイメント業界に関心が集まっていることが背景にあります。配信プラットフォームを通じて世界で人気を集め、キャラクタービジネスといった二次展開ができるアニメはその中核です。
いま多くの企業が事業戦略に「IP創出」を掲げますが、それを可能にする手段がアニメというわけです。
M&Aの最大のメリットは、短期間で事業が手に入ることです。アニメ制作ではクリエイティブが大きな役割を持ってますが、それを作るスタッフを集め、コントロールするには専門的なノウハウが必要です。加えて現在、アニメ制作スタッフは空前の人手不足です。スタジオを一から立ち上げて軌道に乗せるのはかなり大変です。
一般的なM&Aでも成功確率は3割から5割程度とされています。半分以下ですから、リスクは思っている以上に大きいです。
それでもすでにアニメ事業の基盤を築いている企業を手にすれば、ゼロから立ち上げるよりは失敗の確立ははるかに低いはず。M&Aがお金で時間を買うと言われる理由です。
■スタジオ買収の成功と失敗と
ではアニメ業界で行われているM&Aは、実際はどの程度成功しているのでしょう?
たとえばアニメスタジオの買収は?
アニメ業界のM&Aは過去にも多くありました。そして失敗ケースも少なくありません。
2006年にマーベラスエンターテイメントが子会社にしたアートランドや、2011年に携帯アプリ会社アプリックスが買収して子会社にしたAIC(アニメインターナショナルカンパニー)は、かなり厳しい結果でした。
紆余曲折があり、両社は事業縮小を続け、結局グループを離れました。現在、両社のアニメ事業は非常に小規模です。
一方で1994年にバンダイ(現バンダイナムコホールディングス)のグループ会社となったサンライズ(現バンダイナムコフィルムワークス)は、成功例です。今はグループの映像部門の中核としてバンダイナムコグループに大きな利益をもたらしています。
2009年にテレビ朝日の子会社となったシンエイ動画も、『ドラえもん』、『クレヨンしんちゃん』といった人気作品を作り続けています。制作と放送、劇場興行を巧みに連動し、安定した優良ビジネスになりました。
大きな成功も失敗もあるのが、アニメスタジオのM&Aです。
■救済型買収はリスクが大きい
成功と失敗を分けるのは何なのでしょうか?
いくつか重要な要素があります。
M&Aで、最もリスクが高いのは救済型です。売上が伸びない、赤字が続くなど業績が芳しくない企業を買収する場合です。
恒常的な赤字、累積債務の拡大、場合によっては債務超過、さらに資金繰りに懸念が出ている場合もあるかもしれません。事業継続が見通せず、新たな資金の提供者を探すことになります。結果として有力取引先などによるグループ会社化は、エンタメ業界に限らずよくあるパターンです。
しかしもともと経営に問題があっての経営危機で、それを解決できないからの現在です。外部企業が資本を入れ、経営に関与したから、それが一気に解決されると考えるのは楽観的でしょう。
買収前には見えなかった問題が次々の噴出するのもよくあります。リスクを勘案して買収金額を算出したはずなのに、想定外のリスクがさらに飛び出し、再建コストばかりがかかる。そうなると事業全体を収束に向かわせる結果になります。
アニメ業界からやや少し外れますが、2015年にイマジカグループが買収した米国の映像ローカリゼーション会社SDIメディアはそうした例でした。買収金額は140億円と少なくありませんでしたが、買収後にさらに追加投資を迫られました。しかし成果をだすことなく2021年に再売却をしました。
■5%、10% マイノリティ出資の投資効果は?
失敗とまでは言えませんが、難しいケースにマイノリティ出資があります。相手企業の株式の5%、10%と小さな株主として出資する場合です。
「資本のつながりを通して取引関係と信頼を強化する」ことは理解出来ます。2024年に実施された東宝とバンダイナムコの株式相互持合い、東宝のコミックス・ウェーブ・フィルムの6%出資は、そうした例です。
しかしこれまでつながりのない企業の株式を少数株主として保有しても、あまりビジネスが成功するとは思えません。相手の事業を本気で自社に取り込む、強力なパートナーシップを築くには、5%、10%の出資はほとんど意味がないでしょう。
自分たちが望まない方向にその会社が進もうとした時に、止める手段はありません。事業の方向性が合わなくなった時の株式の売却も結構大変です。
少数株主でも投資先企業の成長を見越した含み益、将来の売却利益を狙う純投資であれば合理性はあります。しかし、それは投資ファンドやベンチャーキャピタルの領域です。
真っ当なエンタテインメント企業が、本気でそれを考えているなら本業が心配です。すでに40年近く経ちますが、バブル時代に一般企業が不動産投資に入れあげて、バブル崩壊と共に次々に経営危機に陥ったことはいまでも教訓として残っています。
■価格が高くなってもいい会社の魅力
アニメ分野でリスクを抑えて成功するM&Aがあるとすれば、成長企業・優良企業の買収です。現在も確かな業績を残し、経営が順調な企業を対象にすることです。
通常、そうした企業には実際の企業価値にプレミアが乗せられ、買収金額が高くなる傾向があります。そのため買収時点では、「高値掴み」とネガティブに見られがちです。
ただもともと業績も経営がよい企業であればそのまま事業拡大し、成長がそのギャップを埋めます。シナジー効果が本当に働くならば、さらに加速するでしょう。
ソニーグループにおける配信会社クランチロール買収は、近年の大きな成功例です。買収当時は1300億円と高額となりましたが、ソニーグループと連動することでユーザー数は大きく伸び、事業領域も拡大しています。
■本当の優良企業を買収できるチャンスはあるのか?
「経営の優れた会社を買収して成長を加速する」は仮説としては成り立つけれど、実際は買収できる企業なんてほとんどないのではないか? そんな疑問も浮かぶでしょう。
つまりは、優良企業や成長企業がなぜ会社を売らなければいけないのか? です。
当然の疑問ですが、条件が整えば、そうした優良企業が会社を売りたいケースは少なくありません。
例えば、こうした理由です。
・事業承継
・企業のスピンオフ(事業の切り離し)
・現経営者の成長戦略により、成長投資の資金が欲しい
事業承継型は、実際に多いケースです。シンエイ動画やサンライズもそのひとつでした。
アニメ企業では、プロデューサーがオーナー社長として会社を立ち上げることが少なくありませんでした。特にアニメスタジオは、オーナー企業が多い傾向にあります。
オーナー経営者が高齢になれば、会社を誰が引き継ぐのか「事業承継」の問題は必ずでます。
親族や内部の事業パートナーが経営を引き継ぐケースも、もちろんあります。しかし現在は、アニメブームもあり、アニメスタジオの企業価値も大きく上がっています。それは悪くないことですが、相続税は重くなり、身近な事業パートナーが株式を買い取るには資金が十分でないことも多くなります。
結果として、信頼出来る企業への会社売却が検討されます。
スピンオフは、アニメ事業を保有していた会社が自社全体の事業戦略のなかで、非中核部門としてアニメ事業の一部を切り離すケースです。アニメ事業やスタジオはかつてはニッチな業界とみられ、成長性も低いと考えられました。こうした事業切り離し、売却もしばしば行われました。
三菱商事が2018年にADKに売却したディーライツをはそのひとつです。ディーライツは三菱商事子会社で、アニメ企画・製作として「ベイブレード」事業やスタジオジブリ関連事業も手がけた優良企業です。しかし成長部門とは考えられなかったようです。
最近では2023年秋にソニー・ピクチャーズがアニメ専門チャンネル事業のアニマックスをノジマに売却したケースもこれに近いでしょう。
事業切り離しは、自社グループではシナジー効果がない、一方で新たな企業であればより積極的に投資をし、成長チャンスがあるとの判断です。企業の活性化から考えれば、意味は大きいはずです。
最後はベンチャー企業や新興企業に見られるパターンです。経営者の野心的な成長戦略により、成長投資の資金が欲しい時です。
経営者はより速い成長、より大きな事業を狙うため、経営権の一部(株式の一部)を手放してでも大きな資金を得ようとします。時は金なりです。
ベンチャー企業の場合は、特有のチャレンジ精神と同時に大きなリスクもありますが、成功した時の投資の見返りは大きくなります。
■M&Aの役割
M&Aはマネーゲームと見られ、よい印象が持たれないことも少なくありません。しかし、企業がより相応しい協力やパートナーシップを見つけだす方法でもあります。それが新たな成長を生み出すことも多いのです。
しかし同時に、現在の狂乱に満ちたアニメビジネスブームには、危惧を感じることもあります。
「その企業とその企業の組み合わせは本当に正しいのか?」
「そのM&Aは成長につながるのか?」
時には投資ではなく投機では?と思えることもあります。
チャンスの多いいまだからこそ、そうしたことはきちんとした吟味はされるべきでしょう。

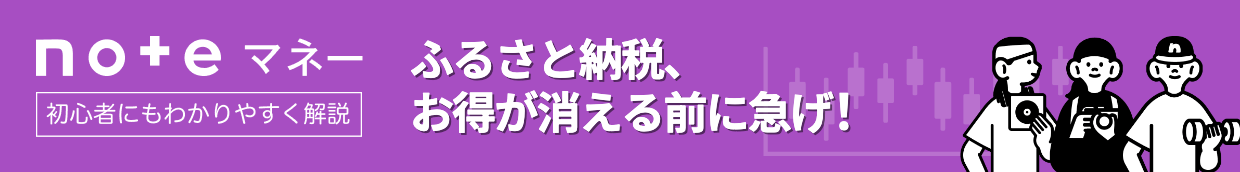
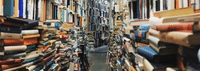

コメント