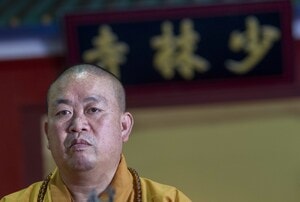2021年7月、チベット自治区を視察に訪れた習近平主席(写真:新華社/共同通信イメージズ)
2021年7月、チベット自治区を視察に訪れた習近平主席(写真:新華社/共同通信イメージズ)
「歴史は繰り返す」と、よく言われる。例えば、悲観的な国際問題の専門家たちは、「世の中が1930年代に似てきた」と言う。いまや「第3次世界大戦の開戦前夜」というわけだ。
私には、確信が持てない。ただ何となく、不穏で予測不能な時代に入りつつあるという気はしている。100年前に芥川龍之介が自死の前につぶやいた、「将来に対するただぼんやりとした不安」――。
それでも「中国ウォッチャー」として、一つ言えることがある。それは、1930年代にアメリカが推し進めた「ニューディール政策」を、中国がいまおっ始めようとしていることだ。
大規模なテコ入れを欲している中国経済
1929年10月に、それまで「黄金の1920年代」を謳歌してきたニューヨーク証券取引所が、突如、暴落。それが引き金となって、アメリカ発の世界大恐慌が巻き起こった。
そこで、長期不況から脱却すべく、1933年3月に就任したセオドア・ルーズベルト大統領が、「ニューディール政策」と呼ばれる一連の政策を実施した。その目玉は、テネシー川流域開発公社(TVA)という国策会社を作って、テネシー川の流域32カ所にダムを建設することだった。この空前の規模の公共事業によって、全国にあふれていた失業者を吸収したのである。
同時に、洪水の防止、電力の供給、農業生産性の向上、地域経済の発展などを目指した。地域の植林や道路整備なども行った。
実際、このダム建設を経て、ドン底にあえいでいたアメリカ経済は、V字回復していった。そして「ニューディール政策」の成功を基盤として、アメリカは第2次世界大戦の勝者となったのである。
翻って、現在の中国である。中国は自身の経済状態を「恐慌」などとは決して呼んでおらず、「今年上半期の経済成長率は5.3%に達した」と誇っている。
だが、こうした仕草も前世紀に「前例」がある。わが日本帝国軍が得意とした「大本営発表」だ。