Vol.32 岡澤 康浩 人文科学研究所 助教
物事をデータや統計によって理解するということは、いまや当たり前になっています。でもそれはどうやって生まれたのでしょうか。科学史とメディア論から、知識生産について歴史的および実践的・物質的な両方の視点をあわせて研究をしている岡澤康浩助教に、これまでの研究活動や方向性を紹介してもらいながら、科学者の役割や知的探究活動をどう捉えるかについて伺いました。
統計学の歴史と「データ」の誕生
――専門分野は科学史とメディア論ということですが、これらの領域を研究されるようになった経緯を教えてください。
岡澤助教 大学院生の時、はじめは東京大学の情報学環という学際的なメディア研究機関に所属して、メディア論の勉強を始めました。その時、私の周りの人たちが関心をもっていたのは、オーディエンスの研究でした。幻灯や、弁士による解説がついた無声映画などの視覚装置を楽しむ人たち、あるいはもっと現代に近い時代のオーディオやアイドルのファンなどを対象にした研究ですね。特に多かったのは、言論誌やファッション誌といった雑誌の「読者」の研究でした。私もはじめは、大量の数値やグラフといった文字ではないものが雑誌や政府報告書、統計年鑑といった形で大量に印刷され、流通するようになった歴史に、メディア論的な関心があったのだと思います。
人間生活の多種多様な側面を統計データという形で書いたり読んだりするという実践が登場するのはたかだか19世紀前半のことにすぎません。しかし、その実践は非常に短い歴史的スパンで一般化し、私たちの生きている世界を形作っています。これはちょっと驚くべき事態だと思います。統計データの出現によって、私たちは自分たちの生や死について、それ以前とは違うやり方で書いたり、読んだりすることができるようになった。その歴史は、面白いのではないかと思いました。
そうした読み書きの歴史として見たときに面白いのは、しばしば自然言語を使うよりも、統計データを使って書いたほうがより科学的だとされるところが多いことですね。歴史的にも、19世紀の統計データの登場は、自然科学から区別された別の形での人間についての科学、「社会科学」というものが可能なんだという新しいアイディアとも結びついていました。
しかし、人間の振る舞いや状態について書く方法には様々なジャンルがあります。文学や、ジャーナリズムなどがすぐに思い浮かぶでしょう。あるいはもっと日常的にも、私たちは「あの人の行動には、こういう背景があったはずだ」といった風に誰かの状態や行動について描写したり、報告したり、論評したりすることもある。
そうした書き方と、統計データと呼ばれる特殊な書き方は何が同じで、何が違うのかという疑問が生じるのは当然かも知れません。写真や映画、録音機など、文字以外にも映像や音声による描写を可能にするテクノロジーも後から出てきますからね。統計データなんていうのは数字を使った薄っぺらいものであって、もっと人々の生活に密着したものを、きちんとした文章で書いていくべきなのではないか、そう思った人は統計データが出てきた当時からいましたし、現代でもいなくなってはいないでしょう。
そこで、社会統計データの収集が盛んになる1830年代から70年代に主要な役割を果たしたロンドン統計協会(Statistical Society of London)と呼ばれる組織に注目して研究を始めました。彼らが発行していた学術雑誌『ロンドン統計協会誌』を分析すれば、わざわざ統計データなんていうめんどくさい方法で社会や人間を記述しようとした彼らの情熱はどこから来たのか、どうやったら人間を数字で書くなんていうことがそもそも可能になったのか、そして統計データという新しい書き方を手にすることで、私たちはどういう新しいやり方で私たち自身を理解し、私たちの生活に働きかける方法を手にしたのか、そういったことを理解できるのではないかと思ったからです。
情報学環にいたころは、もっぱら読み書きについてのメディア論的関心から研究していました。その後、イギリスに留学して所属先が歴史学部に変わってしまったので、そこからはメディア論的関心を科学史的な議論に翻訳しながら研究していきました。メディア論と科学史は全然違うと思われる方もいらっしゃいますが、私自身はあまり本質的な違いというのは感じていなかったと思います。博士論文の審査は当時滞在中だったドイツのマックス・プランク科学史研究所という科学史研究に特化した研究機関で行ったのですが、この研究所の中でも科学におけるイラストや写真の利用に注目した、かなりメディア論的な関心に近い研究がなされていました。
「偉大」ではない科学者の役割
――データによって物事を理解するというのは今では馴染みがある方法ですが、昔からそういうわけではなかったのですね。特にロンドン統計協会に注目されたのは何故なのでしょうか。
岡澤助教 もともと、私が統計協会というのに関心を持った一つの理由は、それが個人ではなくて、集団だったということがあったと思います。ニュートン、ガリレオ、ダーウィン、アインシュタインなど、偉大な科学者が何か重大な発見をしたり理論をつくるといったタイプの科学史はよくあります。それはそれでいいのですが、一方で、私が関心をもったのは、そもそも多くの人たちが集まって、集団として科学的活動をどうやってするのか、といったことですね。
私が扱った時期のロンドン統計協会には、「孤独な天才」みたいなひとは出てきません。それほどたいしたこともない人たちが集まって、何かをやっている。友人同士のサークルであれ、より公的な組織であれ、何かを「集団」としてやっていくと、メンバーの中で生まれてしまうズレや齟齬をどう調整するのかという問題が発生すると思いますが、科学となると「みんな違って、みんないい」ではすまないでしょう。そういう複数の人同士の協働を可能にする制度、インフラ、テクニックといったトピックも、科学論とメディア論にまたがる面白そうな論点だと思ったのかも知れません。
もう一つは、統計協会というのが単純に古かったというのがあります。統計の歴史というとデータ分析手法や理論の歴史を思い浮かべる方が多いと思いますが、そうした歴史は普通、19世紀末から20世紀頭にかけてはじまったとされています。その時期に、フランシス・ゴルトンが「回帰」概念を唱え、カール・ピアソンらが「相関係数」を開発し、さらにはロナルド・フィッシャーが「推測統計学」をつくり出したと言われるからです。しかし、ロンドン統計学会というのは1830年くらいからすでに活動をはじめていました。私が対象にしていた1830年頃から1870年頃にかけて、この協会からの統計学理論への貢献といったものはほとんど見られません。
一方、1830年前後には哲学者のイアン・ハッキングが「印刷された数字の雪崩」と呼んだような統計データの大規模な生産・流通が始まっていました。政府統計などが急速に整備されていくのもこの時期です。そして、この時期には統計学者と呼ばれるような人たちがそれなりの数で現れ、統計協会と呼ばれる組織までつくられたわけです。この統計理論の歴史としては空白の時代に、統計学者たちはわざわざ統計協会なんてつくっていったい何をやっていたのか。それが素朴に疑問だったんですね。
ロンドン統計協会は、「統計データ」と呼ばれる新しいオブジェクトを使って人間の生活を書き出し、それを巧みに処理することで自分たちの状態を新しいやり方で読むことができるようにする、そういう新しいリテラシーの環境を作りだしていたのではないか、私は今ではそう考えています。そうやって整えられた環境の中から、統計データの分析手法を発展させるひとが現れ、現在の私たちの知る統計的推論が繁栄する世界が生まれた。ある意味では、社会科学という新しい科学のやり方は、極めて特殊な新しい書き方の発明によって可能になったとさえ言えるかもしれません。
「大規模観察」としてのデータと人間の知覚能力
――最近は、テレビの視聴者を対象としたメディア論の研究プロジェクトをすすめておられます。
岡澤助教 テレビについて関心をもったのは、見ることの歴史と、疲れることや退屈することの歴史とが交差する場所として、面白そうだと思ったからです。意外なことですが、見ることの歴史と退屈することの歴史は、科学観察やデータ収集の歴史とも近いんです。
19世紀の統計学の歴史をみると、たくさんの人が情報を集めてきてそれをなんとか合算することで、最終的な「データ」というものができるわけです。私はこれを「大規模観察」の歴史、例えば気象データ、天文データ、現在ならパンデミックのデータ収集の歴史の一つのバージョンだとみています。
大規模観察においては、観察をする個々人はいわば、インプットをする一種の「装置」になるわけです。科学的観察に大勢の人が動員できると、個々人の負担が減るという点ではいいわけですが、そこには新たな問題も生じます。つまり、ある人と別の人が同じ対象に同じインプットを本当に返してくれるのかといった問題です。ここで大幅なズレが生じてしまうと、合成してできあがったデータの歪みやノイズが大きすぎて、信用できないということになってしまいますから、困ってしまうわけです。抽象的には個々の人間の振る舞いを「標準化」という形でコントロールすればいいわけですが、これは言うだけなら簡単ですが、現実的に実行しようとするとなかなか難しい。
計測器やセンサーなど、人間の代わりに機械が使える場合でも、大量の機械的装置が本当に同じように働いてくれるんだと信頼できるようにするには「キャリブレーション(較正)」と呼ばれるような作業が必要になるわけですから、コントロールしづらい人間が相手だと、かなり大変なことは想像に難くありません。そもそも、個々の人間観察者がもっている視覚、聴覚、判断力などの特徴や個体差について検査したり評価したりすることが必要になってくるかもしれない。興味深いことですが、大規模観察科学の組織化が進んだ19世紀には、同時に生理学や実験心理学など、人間の感覚や知覚を解明する研究も推し進められていました。
こうした人間を観測装置として考えたときに、私が関心を持っているのは、人間が飽きたり、疲れたり、眠くなったりするのではないか、ということです。ずっと同じものを見ていると退屈し、注意散漫になってしまうという性質が人間にはおそらくある。こういう、疲労、注意散漫、睡眠不足というのは労働現場で大きな問題になるので、産業心理学や労働科学などの重要なトピックとして研究されたりもしました。
でも、私はこれはメディア論の人たちがずっと関心を向けてきたトピックでもあるのではないかと思いました。たとえば、テレビを作っている人にとって視聴者が退屈してチャンネルを変えてしまうと困るわけです。なので、テレビ番組を作っている人たちは、彼らなりのやり方で視聴者の振る舞いについての理解を深めていきます。テレビの視聴者は、テレビ番組なんてそんなに真面目に観ていなかったりする。昔のテレビやラジオに関する雑誌などをみていると、放送番組制作者などは視聴者が「ながら視聴」をしたり、すぐチャンネルを変えてしまうといった自体にかなり初期から気づいていました。
なので、テレビ番組制作の現場には、生理学や心理学などの実験にもとづく注意力についての知識とは異なる、独特のモデルや知識が存在していたんだろうと思います。もし、視聴者というものを一つの手がかりとして、テレビを、人間についての知識が生産され、応用され、実験されていく場所としてとらえなおせば、応用的な人間科学の歴史とメディアの歴史が結びつく新しい歴史が見えてくるかもしれないと考えています。
書くことの歴史と科学の歴史
――科学史とメディア論の交差するところで研究を進めておられますが、その最終的な到達点、ビジョンとしてはどのようなものを描いておられるのでしょうか。
岡澤助教 すこし抽象的になってしまいますが、科学史とメディア論の交差点として、私は「グラフィー(-graphy)」の歴史、つまり、「書くことの歴史」といったものを考えています。英語では写真や音声記録、映像を書き出すことを「フォトグラフィー」、「フォノグラフィー」、「シネマトグラフィー」などといいますし、グラフィーには「エコーグラフィー(超音波検査)」、「エレクトロエンセファログラフィ(脳波測定)」など検査や測定も含まれている。もちろん、新しい描写や計測を与える方法や活動を示すものである限り、グラフィーという言葉をつかっているかどうかは本質的な問題ではないでしょう。たとえば、視線の動きを記録する「オフサルモグラフ」という装置がありますが、これは一般的にはむしろアイトラッキングとして、グラフィーとは関係のない名前で知られているでしょう。ですので、文字を含んだあらゆるタイプの書き込みを扱う「一般書記史」とでも呼んだほうがいいのかもしれません。
ともあれ、私が関心があるのは、文字はもちろん、数字、光線、音、電気信号など、様々なものを使って何かを書いていくことの歴史です。科学者というのは、眼に見えなかったり、人間の感覚器官では必ずしもとらえられなかったり、扱いにくかったりする対象を、うまく扱いやすいように変形する、いわば新しく何かを書き出す方法や装置をどんどん作り出していきます。新しい書き方を発明し、新しい研究対象を見つけたり、つくり出したり、操作できるようにしたりすることで、科学者は新しい知見を生み出していく必要があるからです。
でも、そうやって新しくつくり出された「書く」方法は、医療、産業、軍事、さらには日常的なエンターテイメントへと転用されることもしばしばある。こういう風に、メディアの歴史をグラフィーの歴史という観点から考えれば、書く方法や書く領域を積極的に拡大していく科学も含めた歴史が描けて、面白いのではないかと思いますね。
知的探究者のあり方や共同性の複数性
――所属先である人文研(人文科学研究所)の所報に書かれた「接続と断絶の科学史にむけて」(『人文』第69号, 2022年)の中で、人文研が推進してきた共同研究についても書かれていますね。こちらも、科学史とメディア論の交差点として興味深い事例に思えますが。
岡澤助教 そうですね。メディア論の人たちは、ある種の共有地(コモンズ)のような、異なる人たちが出会い、相互に交流し、インタラクションが生まれる場所をデザインするということに関心を向けてきたと思います。こういう問題関心は、科学的探究においても非常に重要なものでしょう。先ほどあげた大規模観察の例も、世界中に散らばる観測者や観測機械からなるネットワーク的集合体をどう運営していくのかという話だといえるでしょうし、もっと古典的なトピックとして、科学史では学会、学術雑誌、個人間の手紙のネットワーク、あるいは大学などが注目されてきました。
科学者というと、冷静沈着で、どちらかというと感情から遠い存在に思えるかも知れませんが、科学の歴史はしばしば科学者が怒りに駆られる瞬間を記録しています。科学者には「科学とはこうあるべき」という信念の強い人が多いんですね。これはよく考えてみると当たり前の話で、知的活動を集団で進めていくときには、どんな知的共同体が望ましいのか、その共同体のメンバーにとって望ましい振る舞いとは何か、どういった知的探究者として自分たちを律していくべきなのかといった、「あるべき」姿についての問題が浮上するからでしょう。
それをみるときに私が面白いと思うのは、「知的探究者」としてのあり方には、実はかなり大きなバリエーションがあるということです。その結果、異なるあり方やビジョンが時に衝突してしまうということもあります。極端なケースになると、自分とは違うタイプの知的探究者として生きようとしている人に、「お前がやっているのは単なる詐欺であり、学問への裏切りなんだ」と激怒する人が出てくるわけです。
「接続と断絶の科学史にむけて」でも取り上げましたが、人文研というのは歴史的に人文社会系の共同研究を推進することを使命の一つとしてきた研究所です。そうした方向性を牽引した最初期の重要人物にフランス文学者の桑原武夫がいました。
桑原は独特のアマチュア主義とも呼べる理念を信じていたようで、あまり自分がよくわからないことにも積極的に首を突っ込んでいくような、そういう独特の社交性をもっていました。こういう彼の態度に対しては、「ただおしゃべりをしているだけだ」、「単なる耳学問だ」などと批判されることもあったようです。議論するということは専門家同士が対象についての知見を着実に積み上げていくことなのだという考えの人から見れば、桑原のような態度は、真剣な学問に対する冒涜だとさえ思えたかも知れません。
一方で、桑原の「ただのおしゃべり」に見えるものには、ある種のビジョンや倫理のようなものが賭けられていたと思う。桑原は、異なる分野の人たちが、たまたま出会ってしまうような空間を作ることで新たな発想が生まれる可能性を信じて、そういうよくわかっていない人でも口を挟める環境を作りたかったのではないか、私はそう思います。
共同研究を通して知的共同体を作るという使命があるためか、人文研という場所はそういった知的環境のデザインに対して自覚的な人たちを多く輩出してきたように思います。私にとって一番印象的な人物は、批評活動や思想誌の編集によって「ニューアカ」とも呼ばれた知的ムーブメントを巻き起こした浅田彰さんですが、他にも大阪万博にたずさわったり、大学の外にシンクタンク設立をするなど様々な活動を展開した加藤秀俊さん、そして、知的生産の技術や情報の生態学を論じた梅棹忠夫さんなども含まれるでしょう。
私はこうした知的共同体を運営したり環境を整備していくような、ある種の建築家やデザイナーのようなひとたちに関心があるのですが、こういうひとたちの活動を正確に評価するのは、論文などの業績ベースのものでは少し難しいところがあります。私はフランス文学について何も知りませんが、桑原もフランス文学の「専門家」としては、もしかしたらそれほど重要な仕事をしなかったのかもしれません。でも、そういう知的な環境をデザインすることの重要性を信じたという意味では、興味深い知識人であり、メディア理論家だったと言えるかも知れません。学問の専門化を止める必要性があるとは特に思いませんが、一方で、専門性を深めるのとは別の形で知的生産や知的探究を行っていく人たちの役割を、大学の内外を問わずきちんと位置づけていくロジックが必要なのではないかと思います。
科学の歴史というのは、様々な点で異なる人たちが互いに協力しながら知的探究をすすめてきた、「接続」の歴史だと思います。でも、接続の歴史は「切断」の歴史とも複雑に絡み合っているでしょう。もし、目指される知的共同体にも色々な形があるのだとしたら、ある共同体から意図的に切断することは、必ずしも孤高を気取ってみせたり、独断主義に陥ることではないでしょう。逆説的になりますが、ある接続のやり方から切断すること自体が、同時に別のやり方で接続を志向することでもありうると思います。
接続と切断の歴史を考えていく上では、もちろん理念の検討だけではほとんど意味がないでしょう。接続とか切断を支えているのは、技法や技術、そして物質的な環境やそれが可能にする実践だからです。最悪の形の切断というのは、性別、人種、性的指向などにもとづいた差別的な排除でしょう。これは女性や有色人種といったあるカテゴリーに属する人間を直接的に狙って行われる時もありますが、同時に特定のカテゴリーに属する人が接続することの社会的・心理的コストをあげることによって機能するタイプの排除もしばしば見られます。なので、気持ちとしては接続を志向していても、その接続のやり方の中に気づかない形で切断がすでに埋め込まれてしまっていることもある。立派な理念を掲げることは大事なことではありますが、実際にその理念がどのような技法や物質的な環境、知的インフラ整備のレベルにおいて実装されているのかも同時に見ていく必要があるでしょう。
接続と切断の歴史を書く一つのイメージとして、知的な生態系の歴史のようなものを私は考えています。さまざまな知的探究者たちがそれぞれの理念や技法や資源をもとに各地でゆるやかな集団を形成する。彼らはみずからの生きる環境を改変し、あるいは環境の変化によって変容を迫られながら、その知的な生態系の中で互いに協力し、対立し、あるいは無関心を貫き、その結果として繁栄したり衰退したりする。
知的探究者たちの生態史を書くという作業は、もちろん科学史的課題だとも思いますが、それはメディア環境やインフラのデザイン、それにともなうアクセスの制御や排除についてメディア論が積み重ねてきた議論と大きく重なるのではないか。メディア論と科学史の交点に関心がある歴史家として、両者をうまく繋げる仕事をしていければと思っています。
(構成:藤川二葉)
岡澤 康浩(おかざわ やすひろ)
人文科学研究所 助教
岡澤 康浩 │ 京都大学 教育研究活動データベース
関連リンク
京都大学 人文科学研究所
瀬戸口 明久, 岡澤 康浩, 坂本 邦暢, 有賀 暢迪共訳. 客観性. 名古屋大学出版, 2021年
Okazawa, Yasuhiro. 2019. The Scientific Rationality of Early Statistics, 1833–1877. [Doctoral Dissertation, University of Cambridge].


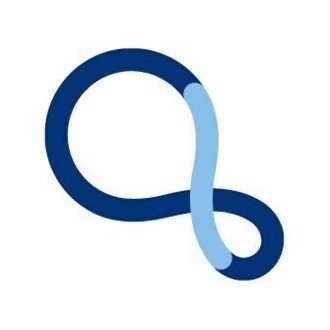
コメント