レイオフを伝えるという仕事
はじめに
2025年。AIの波は、もはやテック企業だけの話ではありません。
いま、すべての産業、すべての職種が再定義されようとしています。
それは、不可逆的なパラダイムシフトです。
私たちダイニーは、飲食という最もアナログな産業にテクノロジーを持ち込み、“次の50年のインフラ”をつくろうとしています。
そんな中、今回「レイオフ(※厳密には退職勧奨)」という、日本ではまだ珍しく映る意思決定を行いました。
欧米では当たり前であるこの決断ですが、日本では、レイオフ=経営難という誤解が強く根付いています。
日本のスタートアップ “村” においては、レイオフが行われると即座に「経営が傾いているのでは?」という見方がなされ、文脈のないままゴシップとして消費されがちです。
しかし、構造的な産業変化の只中にいるからこそ、私たちはこの意思決定を誤解なく、真正面から伝える責任があると感じました。
本稿は、そのための試みです。
この試みにより、少しでも、日本のスタートアップエコシステムが “前に進む” きっかけになれば嬉しいです。
なぜレイオフを実施したのか
日本のスタートアップにおいて、レイオフの実例はあまり多くはありません。
その理由の多くは、雇用を切ることへの社会的忌避、経営判断としての “見られ方” への恐れ、そして「成長 = 採用人数」という古い指標が、いまだに残っていることです。
まずはっきりさせておきたいのは、「ダイニーは経営難だから人を減らしている」わけではありません。
実際、私たちの売上は好調に伸びており、複数の新規プロダクト立ち上げも、目を見張る成果を見せています。
では、なぜ今なのか?
それは、「AI 時代における経営の在り方」そのものが、根底から変わってしまったからです。
2022年以降、AI による生産性向上・業務効率化のインパクトは急激に拡大しました。
世界銀行によると、世界の業務の40%以上が AI による代替可能性を持つとされ、米国ではスタートアップの平均従業員数が1/3に減少しているという統計すらあります。
「人を増やして成長する」ことそのものが、経営としての合理性を失い始めているのです。
つまり、労働集約型の組織設計は、AI 時代にはそもそも「合理的でない」のです。
日本の労働人口も減少し続けるなかで、私たちは「人を増やす経営」から「生産性で伸びる経営」へと、舵を切らなければなりません。
それは、テクノロジー企業としての宿命でもあり、飲食という巨大産業に対して責任を持つ立場としての使命でもあります。
採用を止めた理由と、誤解
実は、私たちは、Q1の時点で採用を止めていました。
その結果、いくつかの採用エージェントから「ダイニーやばい」という憶測が出回り、採用候補者や知り合いの起業家から「エージェントからダイニーやばいって聞いたけど、大丈夫なの?」と聞かれる場面もありました。
前述したとおり、経営は極めて順調で、「やばい」という状況からはほど遠い。
採用を止めたのは、「AI によって業務のあり方が大きく変わる」からこそ、今この瞬間に人を増やすべきではないと判断したからです。
この構造変化の中で、いかに正しい組織構成で次のチャプターに向かえるか。
その思考の延長線上に、今回のレイオフがあります。
グロースの裏で起きていたこと
ダイニーはこれまで、着実にグロースを遂げてきました。
私自身、全社が150人になるまでは全員の最終面接に入り、採用に対する規律を徹底してきました。
しかし、その後に AI の実用化が急進し、徐々のリソースと構造に歪みが生じ始めたのも事実です。
気づけば、「それって AI で代替できるのでは?」という業務が、社内のあちこちに存在するようになっていました。
これは、どのスタートアップにも起こり得る現象です。
グロースとともに、解像度が薄れ、組織の生産性が落ちる。
だからこそ、経営として自らにメスを入れました。
AI による生産性の変化
Q1 では段階的に AI の導入を進め、採用を止めることで、売上の伸びに対して人員構成が徐々に引き締まり、自然と AI を使わざるを得ない構造をつくろうとしました。
しかし Q2。北米のスタートアップやビッグテックの急進的な AI Adoption を見て、私たちも意思決定を加速させる必要があると判断しました。
Board Meeting で何度も議論を重ねた結果、「これはパラダイムが変わったのだ。ならば、私たちも一気に変わらねばならない」という結論に至ったのです。
実際、私たちの現場ではすでに AI 活用が急速に進んでいます。
議事録や社内資料の自動生成:毎週10時間以上の工数削減
一部のカスタマーサポートの AI 応答自動化:AIチャットボットで約60%の問い合わせが自動応答に
営業資料の自動構築:資料作成の時間が 1/4 に
仕様書・デザイン・コーディングの効率化:PdM・デザイナー・エンジニアの作業時間が月15時間以上削減
Mock 作成やリサーチ業務の省力化:3人×1週間 → 1人×1日 に短縮(約93%削減)
CTO の大友を中心に、AI をフルに活用して、プロダクトマネジメントやエンジニアリングのみならず、ビジネスやコーポレートサイドにおいてもにディープに関わったことで、私たちは AI の “効果と限界” の両面を現場から学びました。
一過性の流行ではなく、構造的に企業の経営と人材戦略が変わるフェーズにある。そう確信しています。
意思決定層の「キャッチアップ格差」
特に痛感しているのは、意思決定に関わるレイヤーこそ、AI に最もキャッチアップすべきであるということです。
AI 時代においては、「AI を使って成果を出せる人」と「使わずに評論する人」の間に、絶望的な生産性ギャップが生まれます。AI がまだ入りづらい CEO 業務においても、私の業務の生産性は以前と比べて約1.5倍になりました。
AI 時代において最も変わるのは、 “管理者” という存在だと、実体験でもって痛感しました。
旧来型の “管理者” としての在り方は、AI 時代には根本から問い直されます。
私たちは、全員が「自ら意思決定し、手を動かす」チームにならなければ、このパラダイムに適応できないのです。
旧来型の “管理者” が悪いわけではありません。
ただ、今の時代は、そのままでは価値を発揮しづらくなってきている。
だからこそ、私たちは「学び直し、再設計する組織」でありたいと思っています。
これは、CEO である自分自身にも突きつけている基準です。
トップダウンでの AI-native 化
こうした背景から、私たちは、経営として AI-native Company になると決めました。中途半端にはやりません。
その象徴として、CTO の直下に AI Ops チームを新設しました。もともと、プロダクト開発における AI Adoption は局所的には起こっていたのですが、今回改めて、全社において AI を実装していくという意思決定をしたのです。
このチームが、全業務・全職種のオペレーションに対して横断的に AI 適用を進めていく。
これはトップダウンの改革であり、会社全体を再構築するプロジェクトです。
レイオフの決断とその痛み
ここまでは「構造」の話です。
しかし、レイオフの本質は「人」の話です。
人を減らすというのは、経営者として最も辛い意思決定です。
私自身、何度も Slack の履歴を見返し、それぞれのメンバーが成し遂げてきたことや「この人がいたから助かった」と思った瞬間をたくさん思い出しました。
それでも、「会社として次に進むためには避けられない痛み」であると判断しました。論理として、正しい決断だと今も自信を持って言うことができます。
ただ、「正しさ」は、現場で人に向き合う瞬間の痛みを軽減してはくれませんでした。
この決断は、CEOとして間違いなくキャリアの中でもっとも辛く、もっとも孤独なものでした。
Board meeting にて何度も話し合い、社外取締役とも何度も 1on1 や 3on1 をしました。
眠れない夜も、何度もありました。Slack の履歴を見返しては、メンバーひとりひとりの貢献や言葉を思い出し、胸が締めつけられました。
「これは本当に正しいのか?」「別の道はなかったのか?」
日々、自問自答を繰り返しました。
準備も、検討も、熟慮を重ねました。
論理的には、納得している。
だが、実際にその判断を「伝える」ことは、想像よりも、はるかに重いものでした。
伝えるという行為の重さ
事前に、何度もシミュレーションしました。
言葉選び、導入のタイミング、可能な限りの誠実さを込めて、準備をしました。
しかしながら、実際に本人を前にして言葉を口にしようとすると、頭が真っ白になって、何も出てきませんでした。やっとのことで振り絞った声も、いつものような自信に溢れたものではなく、蚊の鳴くような頼りのない声でした。
「あなたの職務は、ここでは継続できない」
この一文が、こんなにも言いづらいとは思っていなかった。
こちらは「経営判断」を伝えているつもりなのに、相手の表情が「人生の分岐点」として受け止めているのが分かってしまう。
その乖離が、想像以上にこたえた。
中には、ご家族から「直接話をさせてほしい」と要望をいただいた方々もいらっしゃいました。
雇用契約上、法的には私たちに応じる義務はありませんでしたし、対応すれば火に油を注ぐリスクもあることは承知していました。
それでも、経営の責任者としてはもちろん、一個人としても誠実に向き合いたいと思い、自ら対応することを選びました。
案の定、厳しいご意見もいただきました。非難の言葉を投げかけられ、感情をぶつけられる場面もありました。
でも、それは当然の反応だと思っています。
非情な選択を迫られるような経営構造にしてしまったこと、もっと早くできることがあったかもしれないという後悔──そうしたものもすべて含めて、私自身の無力さの結果だと受け止めています。
だからこそ、その痛みは、逃げずに正面から引き受けようと思いました
他者の強さ、自分の弱さ
特に辛かったのは、相手が怒るでもなく、感情をぶつけるでもなく、静かに話を受け止め、こちらを気遣ってくれたことでした。
ある方は、こう言ってくださいました。
「Mao さん、大丈夫ですか?心理的な負担、相当大きいと思うので…くれぐれもご自愛くださいね。」
自分の雇用がなくなると伝えられたその直後に、です。
どうしてこんな場面で、こちらの心配をしてくれるのだろうと思った。ありがたくて、申し訳なくて、情けなくて、感情の収拾がつかなくなりました。
自分が誰かのキャリアを断つ決断をしたにも関わらず、その人から「気遣い」を受けるというのは、自分の無力さをこれでもかというくらい突きつけられて、きつい。
経営とは、合理の仮面を被った感情労働
今回、強く痛感したことがあります。
経営判断は「論理」として正しくても、伝えるという行為は極めて「人間的」な営みだということです。
「合理的であること」と「痛みがないこと」は、決してイコールではありません。
むしろ、合理的なほど痛みは鋭利になります。
こちらが伝えているのは、KPI でも PL でもなく、その人の明日を変えてしまう一文です。
その重みの前では、どんなに準備をしていても、揺らがないわけがなかった。
不思議なことに、伝える相手の表情が穏やかであればあるほど、こちらの精神は不安定になりました。
1on1 の後、一人で席に戻り、しばらく何もできなくなる時間がありました。気がつくと、オフィスにいるのに涙が止まらなくなってしまい、逃げ込むようにビルの共用スペースで仕事をしていました。
「経営者とは、合理の仮面を被った感情労働者だ」と痛感しました。
これからの山田真央
この経験は、自分にとって単なる通過点ではなく、経営者としての節目になると考えています。
不甲斐ない経験から、もう二度と仲間に辛い思いをさせないように、CEO としての成長を3つの行動指針とともに、心に誓いました。
① 組織構造と戦略の乖離を放置しない
事業が進化するスピードに、組織の重さが追いついていない局面は、どの成長フェーズにもある。
そのズレを、最低でも四半期単位で、ベースは月次で修正していくオペレーションに再設計する。
② 人の出口設計を、組織文化として内包する
退職は「想定外の出来事」ではない。むしろ、健全な組織ほど良いオフボーディングの文化がある。
今回のような緊急対応を防ぐためにも、「退職の設計」をマネジメント体系に組み込む。
③ 結果で証明する
去っていく人に、堂々と「ありがとう」と言うには、事業を進め、成果を出すしかない。
この決断が無意味でなかったと証明することが、唯一の誠実さだと考えている。
おわりに
レイオフは、資料の中では「リストラ」「人員再構成」と書かれます。
でも、実際は、一人の人間が、もう一人の人間に「ここではこれ以上、あなたを迎えられない」と告げる仕事です。
それ以上でも、それ以下でもありません。
そのとき、問われるのは論理の正しさだけではありません。
どれだけ敬意を持って伝えたか、どれだけ感情に向き合ったか。
そして、その後に何を選ぶか。
人に向き合う仕事には、必ず痛みがあります。
それでも、痛みに慣れてはいけない。
感じなくなった瞬間に、組織は鈍くなるし、経営者は人間ではなくなる。
今回かけられた「Mao さんもご自愛くださいね」という一言は、きっと忘れない。
この痛みを「対価」にして進んだのだと、自分の中に刻み続けたい。
朝日新聞社 の原さんに、今回の件について取材していただきました。
CNETに掲載いただいております。
ぜひ、ご一読ください。


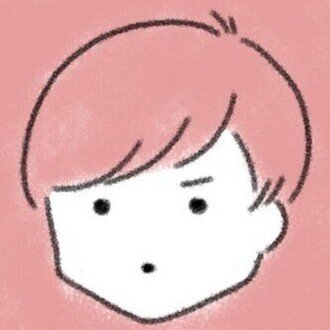
コメント
7ちゃんとパッケージ出した?
整理解雇の4要件ってコメントあるけど、いわゆる退職勧奨に当たるだけなので下手したら会社都合じゃなくて自己都合扱いになるんじゃないかしら?
経営は順調とかあるし、裁判とかになったら「人員削減の必要性」あたりは認められない気がする。
私の会社を抜けた人間はAIで代替可能ですって言いたいのかな
これは壁に書かないんですか?面白い字体で