RWAの「今」とは?なぜStellarはXRPFiみたいにDeFi要素を強めないのか?
みなさんお暑い中お疲れ様です。nomadです〜
記事奮発ウィークということで今回リクエストありました、上記画像から考察できることをまとめていきたいと思います!
免責事項(Disclaimer)
※本記事は筆者の解釈や考察を含むものであり、事実や確証された情報のみをまとめたものではありません。そのため、内容に基づいて生じたあらゆる損害について、筆者は一切の責任を負いかねます。
免責事項:本内容は情報提供を目的としたものであり、投資、法律、税務、またはその他の専門的な助言を意図したものではありません。具体的な判断につきましては、専門のアドバイザーにご相談ください。
※本記事は特定の暗号資産・投資商品を推奨するものではありません。
あくまで現行制度・政策・国際動向に関する分析および個人見解の共有を
目的としています。
こちらの投稿を読み解いていきましょう!
あなたは何か気づきましたか?👀
では、私の見解を述べていきますね。
出典:@hackapreneurの投稿+マーケットデータ
要旨
トークン化された現実世界の資産(RWA)は、伝統金融とブロックチェーンの融合領域であり、次なるWeb3インフラの中核になる可能性が高い。
特にStellar(XLM)やChainlink(LINK)などのISO20022対応銘柄が市場をリード。
一方、PAXGやXAUTのような「本物の裏付け資産」をもつトークンは価格安定性において他と一線を画している。
Algorand(ALGO)は急騰中で、今後のユースケース拡大が注目される。
トップRWAトークン:マーケットキャップ比較
(上位10銘柄)
そもそもの各プロジェクトの性質と位置づけ
復習も兼ねて記載しておきましょう。
🔳 XLM(Stellar)
特徴:ISO20022準拠、MoneyGramなどと提携、
法定通貨トークンや国際送金特化。RWA文脈:ステーブルコインUSDCなどのトークン化を支えるインフラ。例えばウクライナのCBDCプロジェクトに採用実績あり。
見解:規制順守型ブロックチェーンの代表格。
現実世界との接続性では群を抜く。
🔳 LINK(Chainlink)
特徴:オンチェーン/オフチェーンのデータブリッジ=オラクル。
多くのDeFiで基盤。RWA文脈:価格フィード、金利、為替など現実データの取り込みを通じて「RWAの実現を裏から支える」。
見解:トークン自体はユーティリティ寄りだが、
RWAの信頼性構築に不可欠な存在。
🔳 ONDO
特徴:米国財務省証券などのトークン化を推進。機関投資家向け。
RWA文脈:政府債券のトークン化という実需に最も近い存在。
見解:BlackRock支援など伝統金融との融合度は最も高く、
今後の拡大に注目。
🔳 ALGO(Algorand)
特徴:CBDC採用実績(マーシャル諸島)、イタリア政府プロジェクトなど。カーボンネガティブ。
RWA文脈:国家主導の資産・保証書のトークン化にすでに使われている。
直近の伸び(+32.1%)は、以下の背景を受けた投資家の期待反映と
考えられる:長期的成長を見据えた新ロードマップ
一般ユーザー向けの啓蒙キャンペーン
高インパクトな提携先との連携計画
分散性の強化(ノード拡大)
🔳 PAXG(Paxos Gold)/XAUT(Tether Gold)
特徴:
PAXG:NY金融庁認可、監査済み、1トークン=1トロイオンス金
XAUT:金裏付けは同様だが、PAXGほどの規制準拠ではない
RWA文脈:唯一「実物裏付け100%」の真正RWAトークン
見解:
PAXGは“金のETFのオンチェーン版”=現在は過小評価されがち
他が「トークン化の約束」に留まる中、
PAXGは現実的な資産保有の出口として実需がある流動性が限られるため、価格は安定しているが成長余地は小さいのもポイント
その他プロジェクト概要
QNT設立陣営は、ブロックチェーン相互運用規格(ISO TC307)の策定に深く関与し、
57カ国が採用した規格のワーキンググループを主導してきた背景があることに留意したい。
では 「RWAが金融の未来である」理由は?
RWAトークンは次のような
現実資産の効率的デジタル化手段として注目されています。
BCでの証明性と現実世界ではできない分割ができるメリットが
主であることを覚えましょう。
またアクセス性を高めるためにステーブルが必要不可欠である。
特に米国債や金といった伝統的資産がトークン化されることにより、オンチェーン経済が「現実経済の上位互換」になり得る未来が見えてきています。
また、ただトークン化するだけではなく、
ステーブルコインが今後の安定通貨の立ち位置であることが重要です。
よって今後の展望と投資家動向はこう予想される
ここまでの流れから、RWA銘柄は「単なる仮想通貨」から「現実資産のインフラ」への進化を象徴する存在とわかりますし、一方でISO関連プロジェクトで十分にRWAのトレンドの矛先をカバーできていることもわかります。
Stellar/XLM:既存金融との統合が最も進んだRWAインフラ
Algorand/ALGO:政府系プロジェクトの実績と将来性が急浮上中
PAXG/XAUT:トークン化の本質=「所有証明の実体化」を体現
ONDO/BUIDL:DeFi×伝統金融の橋渡しを担う新星
これらを冷静に評価し、「規制」「実需」「流動性」の観点で選定することが、RWA時代の勝者となるための鍵となるでしょう。
ここで賢い方は気付きます。
Stellar(XLM)が最も既存金融との統合が進んでいるRWAインフラであることは事実だとしても、
それが即座に「プロジェクト価値(≒トークン価値)」の上昇に結びつくわけではないのではないか?
その通りです。
Stellarは“技術的・制度的整合性”に優れるが、それ自体の資本価値=XLMトークンの価格上昇に直結しない構造にあるわけなんです。
したがって、
「国家・伝統金融とのパートナーシップの密度」こそが、投資対象としての信頼水準や資本成長の可能性を左右する可能性が高い。
という見解が私にはあります。
なぜ「Stellarの完成度=XLMの価値上昇」にはならないのか?
1. XLMはユーティリティトークンであり、ネットワークの使役通貨に過ぎない
XLMはStellarネットワーク上の取引手数料や最小残高に使われる“スパム防止用通貨”。
USDCなどのステーブルコインが主役であり、XLMはブリッジとしての役割にとどまる。
実際、MoneyGram連携やCBDC実証実験においてもXLM自体の「買い圧力」は生まれにくい。
2. 「公共インフラ的性質」がXLMの価格抑制要因に
Stellarは非営利財団(SDF)が運営し、金融包摂・トランザクション最小化(≒価格抑制)を理念として設計されている。
ネットワーク維持に十分なだけのXLMがあれば足り、価格が上がるほど利用者コストが上がるという逆説を抱えている。
まあ、そのためのstroop単位でもありますが。
では、何が価格に影響するのか?
「国・機関・金融エリートとトークン経済が連動しているか」です。
以下のような設計を持つプロジェクトは、トークン=権利証明・利得配分手段として位置づけられており、市場価値にもつながりやすいと考えられるわけです。
投資家にとっての「信頼水準の高さ」とは?
①技術の完成度 ≠ 信用スコア
Stellarのような完成されたネットワークは、既存金融の採用には耐え得るが、投資リターンには繋がりにくい。(=重要)
AZEROが優秀なのに仮死した理由もコレ
② 政府・伝統金融とのガバナンス共有こそが信用の源泉
例えば、Algorand財団がイタリア政府と共同で契約担保プラットフォームを運用したり、
BlackRockのような金融機関が直接担保資産や償還メカニズムを設計している場合、投資家にとっての信頼性は跳ね上がるわけ。
チェックリストのイメージ
この表を見ると、以下のことがわかります。
戦略的視点として、Stellarは「送金の道路」、ONDOやBUIDLは「課金型高速道路」ぐらい違う
Stellar:政府やUSDC発行体などが通る“道路”であり、
公共財的存在(価格より安定性が目的)ONDO・BUIDL:明確な収益構造があり、利用が増えると
トークン保有者に還元される
※誰も言及していないが、欲出して明確な収益構造のあるONDO等に飛び込みすぎるとブラックスワン時に大惨事になるため、総合的にもみて、やはりstellarのような使役通貨軸の資産防衛は外せないわけである。XPRやONDOの登場でstellarのような有事対応のものを手放すなら、結局利益を追って、「資産防衛」という目的から逸脱することになる
ということが今後数年で実感できるようになる。無論XPR建だとブラックスワンからの回避もあり得るが、そもそもstellarはSCPというプロトコルに価値があることに留意したい。
これは私の個人的な予想であるが、 そもそもStellar等の使役通貨の期待値は、「相対的に時価総額が上がること」である。 つまり、他がブラックスワンなどの有事で下がる中、決済の本質を抑えることで半ステーブル化されることにある。 XPRは有事までは、DID構成を最大限活かしたDeFiの威力が予想以上の事業規模を生み出しやすいが、その支えとなるユーザが有事でいなくなると地獄化、私から言わせていただくと、それは本当のDIDではない。有能だがややポンジー的なのだ。 Stellarは有事の影響を受けにくく、受けたとしても、いまのインフレからデフレへの変換のタイミングとなりうる。元々決済通貨なので、規制が価値を担保してくれる。 hederaはトークン化資産の関係から、それ以上に事業に打撃受けるが、物という必需がバネの役割をし、DAGが記録媒体として主要になる場合、結果的に時価総額にて2030年を軸にStellarを追い抜く可能性が高い。 無論、その他のアルトはこのきっかけにほぼ死亡する。 結果的にアルトコインは200銘柄生き残ったら良い方である。 このプロジェクトを考慮するためにはcoinbaseの仕組みを知る必要があるが、ここでは回答しない。
ではstellarが報われるシナリオはあるか?
将来的にネットワーク手数料が値決め対象になった場合
SDFがXLMを「エアドロ・利得配分」に活用し始めた場合
ステーブルコイン発行者がXLM担保によるレバレッジ型資産を出すような仕組みが整った場合
であれば、再評価の余地はあります。
では次の問いにいきましょう。
FLRやXRPがDeFiやスマートコントラクト機能の拡張に積極的であるのに対し、Stellar(XLM)はなぜそうではないのか?
それは単なる技術的な遅れではなく、むしろ「ステーブルコイン」や「法定通貨」との本質的な相関性を保つために、意図的にDeFi的要素を排除している戦略的選択なのではないか?
背後にある仮説構造を一緒に考えましょう:
法定通貨は利回りを持たないからこそ中立な決済通貨として機能する
同様に、Stellar上のXLMも「利回りやインセンティブを持たない」ことで、ステーブルやCBDCの中立的な受け皿として機能している
これは、XLMが「使うために保有する」枚数利権型トークンであり、収益を生まないことで“利害の中立性”を保つことを狙った構造なのではないか
つまり、Stellar(XLM)がDeFiやスマートコントラクトに積極的でないのは、戦略的に「ステーブルとの相関性」と「金融インフラとしての中立性」を重視しているからであり、むしろXLMという枚数ベースの利権構造こそが“意図された設計”である可能性が高いのでは?という考え方がこのケースの場合必要です。
詳解:なぜStellarはDeFi化しないのか?
1. XRPやFLRとの比較
2. Stellarの哲学:ステーブルと金融包摂の“土台”であること
Stellarは本質的に金融弱者向けの公共インフラを目指しており、
「高速・低手数料(0.00001 XLM)」
「KYC付き送金仕様(SEP-9/31)」
「オン/オフランプ設計(MoneyGramなど)」
など、DeFi的“自己利益構造”とは逆の方向性をとっています。
この設計は、ある意味で「法定通貨が利回りを持たない」のと同じであり、通貨的中立性を維持するために「DeFi化しない」という姿勢は合理的です。
3. XLMという枚数利権の意味とは?
そもそもXLMは:
値上がり益ではなく、「最低残高・手数料支払いのための保有圧力」が
設計的価値DeFi報酬や利回りにしないことで、“静かに使われる”インフラ資産に留まっている
結果として「誰にでも等しく割り当てられ、かつマイナーな利権として使われる」枚数主義のトークン
これは、国家の基軸通貨が金融政策目的以外で利得を出さないのと
似た構造です。
裏を返せば:「利回りを出さないこと」が
最大の強み
先ほどの画像のように利回りがあることが足を引っ張ることになるのでは?
という考え方があります。
過剰な利回り設計(APY構造)は、
短期流入と長期価値破壊を招く(=DeFiの陥穽)Stellarは「信頼・中立・金融インフラとしての役割」に特化し、
むしろ枚数利権だけで十分と割り切っているこれがCBDCやステーブル発行体が安心して
“乗せられる土台”としての強さではないのか???
次にいきましょう。
あなたがRWAを重要だと思いなら、以下の問いを重要視する必要があります。
問い:
ミームトークンや従来型DeFi銘柄と比較して、
RWA関連トークンはなぜ“切り分けてポジション管理すべき”なのか?
そもそも背後にある仮説構造:
ミーム銘柄やDeFiトークンは、
主に話題性・一時的な流動性・投機的需要に基づいて価格変動する一方で、RWAトークンは実際の資産裏付け・収益構造・制度対応など、実需・ユーティリティ・制度接続によって価格が形成される
そのため、RWA銘柄は 価格≒ファンダメンタルズ になりやすい
=真剣な評価軸が必要。
=あるいはこれまでのクリプトに使われた分析手法がおそらくRWAには通用しなくなるという面白い現象が起こる。
よって、問いの本質について2点考慮すべき。
① RWA銘柄は、単なる期待値や流動性による価格変動ではなく、経済的還元や制度統合といった実需に連動するため、
②時価総額が真面目に変動する領域として、他トークン群とは戦略的に区別すべきではないか?
RWA関連トークンは、「ユーティリティ(実用性)×経済的還元設計」に
よって、時価総額の変動が
ミーム系や従来のDeFi銘柄よりも「ファンダメンタルズ(実需)」に連動しやすくなっている、
つまり“真剣なプロダクト価値”に基づいた価格形成が起こりやすい、
というのがRWA文脈における大きな特徴です。※AIも似た動きを感じる。
対比:従来型トークン vs RWA型
トークンの時価総額形成ロジック
つまり、RWAプロジェクト/トークンは、
従来の「価格が上がるから買われる(≒バブル性)」から、
「使われてるから価値がある」
「収益が発生しているからリターンが見込める」
という資産的性格への転換が起きています。
これは、
RWA = トークンとして表現された資産 or 資産インフラ
投資家 = 保有することで間接的に「資産の利回り or 利用料の一部を享受」できる設計に基づいているわけですね〜
これは、より伝統金融に近い、「期待収益の割引現在価値(DCF)」的な評価が可能になるとも言えるんです。だからこそ投資家にとっても
RWAはweb2とweb3の架け橋になります。
たとえば…
BUIDL(BlackRockのMMF):
米国債運用益が1ドルに反映される設計
→ 利回りが金利水準と連動しやすいONDO(国債トークン化):
実際にT-Billを買ってくるオンチェーンファンド
→ US Treasuryに裏付けられた実需PAXG(金裏付け):
金価格に100%連動
→ トークン≒現物資産として取引されるALGOやXDC:
国家系プロジェクトで定常的に使われる
→ステーキング・ノード報酬=利得
これらは全て、価格が“使われていること”や“裏付けられていること”に
応じて変動する設計なわけです。
例えば投資戦略的にはこういう動向が考えられるのではないか?
ミーム/DeFi銘柄:
➤ 「短期スイング型」:話題性を逃さず“乗る・降りる”を高速判断
➤ トークン価格は“群集心理”の波に乗る運用が基本RWA銘柄:
➤ 「中長期インカム型」:実需・政策連携・収益設計の成熟度を見極めて保有
➤ 時価総額は、金融インフラとしての“信用”と“統合度”によって形成
まぁなんせ、以下が個人的結論です。
ミームやDeFi銘柄とは“構造が異なる”からこそ、ポジション管理・分析軸も完全に分けて考えるべき
これは、RWA時代における投資家の重要な心得になるでしょう。
では重要な問いに移りましょう。
RWAトークン市場において、時価総額の上昇を牽引するのは
「ISO規格準拠のチェーン」か、それとも「国家・伝統金融との信頼接続」+「トークン経済との連動性」を両立する本質型プロジェクトなのか?
これですよね〜
背後にある構造的な論点は以下です。
ISO 20022対応銘柄の価格上昇(例:XLM, ALGO, QNT, XDC)
↳ 現在の市場では、規格準拠による“インフラ候補としての期待”が先行しており、
本質的な実需やキャッシュフローの裏付けが薄くても、テーマ先行で資本が流入している。ONDOのような「The RWA」銘柄の本質性
↳ 実際の資産トークン化(米国債)、収益構造、BlackRockとの接続といった要素により、
制度・実需・経済設計を三位一体で備えた“完成度の高いRWAモデル”として機能している。しかしながら、ONDOが「すでにわかりやすく評価されている」のに対し、一部のISO銘柄(特にXDC, QNTなど)は「インフラの割に過小評価されている可能性」も存在する。(=重要)
この場合、RWA市場の今後を見極めるうえで極めて重要な
2つの評価軸のせめぎ合いが見えてきます。
⚪︎評価軸1:ISO 20022規格ベース/“金融インフラとしての接続性”
→ 価格上昇例:XLM, ALGO, XDC, QNTなど
⚪︎評価軸2:「国家・機関との信頼接続」×「トークン経済との連動性」
→ 成熟度・本質例:ONDO, BUIDL, PAXGなど
今後のRWAトークン市場は「規格インフラ先行型(ISO)」が牽引するのか、それとも「収益モデル連動型(ONDO)」が覇権を取るのか?
この問いに対する現時点での見解を、以下の3段階で整理しますね
【1】現象分析:
そもそもなぜ今“ISO銘柄”が暴騰しているのか?
※ただ今伸びているのを喜ぶなら、運に頼った博打になるのでは?
背景要因:
2025年末にかけてSWIFTや欧州決済インフラのISO20022完全移行が進行中→ 銀行側の対応完了とともに、「接続可能なチェーン」への注目が急浮上
各国CBDC設計やクロスボーダー送金改革で、“既存金融が最も統合しやすいチェーン群”に先物買いが入っている
ISO20022対応リストに名前があるだけで「政府系案件とつながる可能性がある」=Narrative Pump(語られた未来)
結果として、XLMやALGOが実態以上に「選ばれるチェーン」として資本流入していることを元のツイートが証明している。
【2】本質分析:では、ONDOのような「the RWA」はどう評価されるべきか?
ONDOの優位性(The RWA thesis):
既にトークン化された米国債を保有しているという事実ベースのRWA
機関投資家・BlackRock系と密接で、法定金利+スマートコントラクトという資本効率を持つ
利回り分配メカニズムがオンチェーンで明示されており、トークンが経済に直結
だが、ONDOのボトルネック:
分かりやすいが故に「すでに織り込まれた」説
ISO対応チェーンではないため、今後のCBDC接続性や国際決済参加では不利
長期的には、ONDOのようなプロジェクトが“どのチェーン上で拡張するか”が鍵(➡︎stellarと提携しているわけだから、stellarがDeFi要素を減らしていることと繋がり、私の中で信頼水準が上がった)
→ ここで重要なのが:
ONDOのようなRWA本質型が、ISOチェーン(例:Stellar, ALGO)を選ぶ未来がくれば、「両軸を統合した覇権」になりうる
この流れが成立すれば、規制網の中でONDOのような
トークンが流通可能になる土台が整うということです。
【3】中長期シナリオ分岐:
どちらが時価総額を伸ばすのか?
投資家戦略的には:
⚪︎ 短中期:
ISO銘柄は「テーマ的期待」が先行しやすく、まだ“過小評価”の余地あり
特にXDCやQNTは実用例が少なく割安感あり
⚪︎中長期:
ONDOやBUIDLのような「利回り連動型」は、
機関投資の流入増に比例して安定成長するそのとき「どのチェーンに載るか」が重要になるため、
“載る場所”としてのISOチェーンを押さえる意義は大きい
よって、RWA市場における戦略的見解(結論)
1. ONDOのようなRWA本質型はコア(基準軸)として押さえるべき
現実世界資産(T-Bill等)とトークンを1:1で結びつけた構造は、
最も純粋な「The RWA」ただし、現時点ではISO 20022接続性やグローバル決済インフラとの互換性が限定的で、将来性においてプラットフォーム依存
2. 一方、XLM・ALGOなどのISO準拠チェーンは“選ばれるインフラ”として先に資本が流入している
規格・標準・接続性への期待が先行し、今後もテーマ性のある資金が集まりやすい
特にXDCやQNTなどは実用性が未知数である分、“規格外”で過小評価されている可能性があり、要観察
3. 最重要ポイント:
ONDOのような“中身”が、ISO系の“外側”を選ぶ未来は
十分起こり得る
それはまさに「信頼の接続性 × トークン経済性」という
RWAの両軸統合=覇権構造というわけです、ONDOの価値が跳ねる契機は、“どのチェーンと手を結ぶか”次第である
SUI・stellarの次はどこかということです。
ここでのまとめはこうです。
🟣 ONDO = 現時点で最も本質的なRWAモデル(中身)
🔵 ISO対応チェーン(XLM, ALGO, XDC, QNT) =
インフラとしての接続期待(土台)🟢 「ONDO × ISOチェーン」が成立した瞬間、
その両者が資本の交差点となる
ONDOを低ボリュームでも継続監視しつつ、 ISO対応銘柄を主軸に据える戦略が、2025年後半〜2026年の市場シフトに最も合理的
もっと具体的にいうなら
つまり、これからのRWAの見方としては ONDOのような定番軸(今後のCBDC接続性や国際決済参加では不利という意味)を軽くは押さえながら、 実態以上に「選ばれるチェーン」として資本流入しているISO20022関連がメインとなる。 しかし特にXDCやQNTは実用例が少なく過小評価されているので無視できない。 もしONDOのようなRWA本質型が、ISOチェーン(例:Stellar, ALGO)を選ぶ未来がくれば、「両軸を統合した覇権」になりうるため、ONDOの期待値を上げて観察したい
図にするとこうなります
RWA評価マトリクス:特に市場構造図解
【未来の覇権ゾーン】
┌────────────────────────────────────┐
│ 両軸統合(RWA本質 × ISO対応) │
│ 例:ONDO が Stellar / ALGO 上に展開される未来 │
│ → 信頼性 × 標準性 × 経済性 が揃う │
└────────────────────────────────────┘
▲
│
│
│
実需・経済的還元性(RWAの本質)
│
│
┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ ONDO / BUIDL / PAXG │ │ XLM / ALGO │
│ ──────────────▶│───────▶│───────────────
│ 実態資産・利回りに直結 │ │ ISO規格チェーン │
│ 現在の実需を持つ“中身” │ │ CBDC・決済統合の軸 │
└────────────────────┘ └─────────────────────┘
│ ▲
│ │
▼ │
ミーム/DeFi銘柄群(SHIB, PEPE, 一部DeFi) │
┌─────────────────────────────┐
│ 話題性・短期ボラ主導、RWAとは構造的に乖離 │
└─────────────────────────────┘
ここで言いたいのは、「RWAは価格ではなく“接続構造”で読み解く」必要があるということですね。
ということで、以上となります!
ありがとうございます!
adiosssssss
ISO20022や他規制を満たした日本初の信用OS、mindpalaceも
応援よろしくお願いします!!!
いいなと思ったら応援しよう!
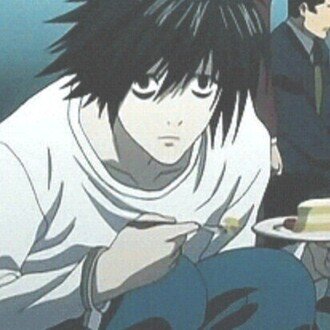 よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!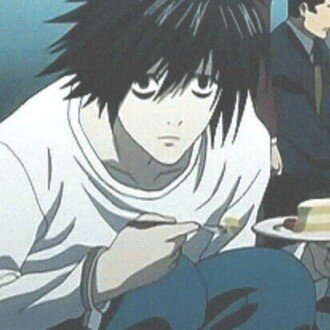

コメント