寺山修司『消されたものが存在する』の謎
図書館で寺山修司の詩集を借りた。
最近読んだ本の関係で詩に触れる機会が多くあり、詩に興味があったからだ。
どうして寺山修司なのか。詩に明るくない私でも名前を知っているくらいだから、有名な詩人なのだろうと思った。
私は、何かに新しく触れるなら、その世界で鉄板のものから入るタイプだ。
それに、寺山修司が好きな知人(Twitterのフォロワー)がいたのもある。
とにかく私は寺山修司の詩集を借りた。
目当てのものは別にあり、ついでに借りたから存在を忘れかけていたのだが、借りたことを寝る前にふと思い出して、その詩集を開いた。
ぱらぱらとページをめくって、軽い気持ちで目を通していると、表題の詩が登場した。
消されたものが存在する
はじめに私の名前を消す
あいうえお あいうえお あい えお
かきくけこ かきくけこ かきくけこ
さ すせそ さしすせそ さ すせそ
たちつてと たちつ と たちつてと
なにぬねの なにぬねの なにぬねの
はひふへほ はひふへほ はひふへほ
みむめも まみむめも まみむめも
やいゆえよ やい えよ いゆえよ
りるれろ らりるれろ らりるれろ
わゐうゑを わゐうゑを わゐうゑを
ん ん ん
次に消す
船
時代
血のつまった袋
歴史的感情
あいうえお あ うえお あい えお
き けこ か くけこ か くけこ
さ すせそ さ すせそ さ すせそ
た つ と ち と ち てと
なにぬねの なにぬね なにぬ の
はひ へほ はひふへほ はひ へほ
みむめも みむめも まみむめも
やいゆえ やい えよ いゆえよ
りる ろ らりるれ らりるれろ
わゐうゑを わゐ ゑを わゐうゑを
ん ん
最後に
二人の名前を消す
二人が同じ場所で出会うために
あいうえお あ うえお あい えお
き けこ か くけこ か くけこ
さ すせそ さ すせそ さ すせそ
た つ と ち と ち てと
なにぬねの なにぬね なにぬ の
はひ へほ はひふへほ はひ へほ
みむめも みむめも まみむめも
やいゆえ やい えよ いゆえよ
りる ろ らりるれ らりるれろ
わゐうゑを わゐ ゑを わゐうゑを
ん ん
五十音表が出てくるその詩はひときわ目立っていた。
面白い。こういった詩もあるのか。五十音表から消えていく文字、それらが指し示す言葉。ずいぶんと凝った詩だ。
そう思いつつも、私は自分でその詩を読み解こうとは思わなかった。
そして、怠惰でせっかちな性格から、インターネット及びSNS上でこの詩の解説を探しはじめた。
自分で読むより、解説を見て理解する方が手っ取り早い。タイパ至上主義というやつである。
しかしそんな私の思惑は外れる。答えをいち早く知ろうと検索したはいいものの、検索エンジンで解説はヒットしない。
それどころか、言及している人すらほとんどいないのである(このインターネット大時代にそんなことある?)。
仕方ないのでJ-STAGE、CiNii、Google Scholar、国会図書館デジタルコレクションでも探してみる。念のため英語でも検索してみる。note内でも検索してみる。けれどそれらしきものは全くヒットしない。一応ChatGPTに投げてみたが、案の定要領を得ない。
本当にこの作品は実在するのか? そう訝る頃には、仕方なく自力で読み解いてみよう、と諦め始めていた。
私の名前を消す
ひとまず指示に従ってみよう。はじめに、私の名前を消す。
あいうえお あいうえお あい えお
かきくけこ かきくけこ かきくけこ
さ すせそ さしすせそ さ すせそ
たちつてと たちつ と たちつてと
なにぬねの なにぬねの なにぬねの
はひふへほ はひふへほ はひふへほ
みむめも まみむめも まみむめも
やいゆえよ やい えよ いゆえよ
りるれろ らりるれろ らりるれろ
わゐうゑを わゐうゑを わゐうゑを
ん ん ん
消されているのは左列から順に、しまらてゆうしや。並び替えると「てらやましゅうし」。つまり、ここで消されている「私の名前」とは、寺山修司彼自身である。
五十音表が三つ用意されているので、各列から一つずつ選ぶ、または消えた文字の位置が読解に絡んでくる可能性を想定していたが、単純にこの方向性で解いて良さそうだ。
次に消す
船
時代
血のつまった袋
歴史的感情
あいうえお あ うえお あい えお
き けこ か くけこ か くけこ
さ すせそ さ すせそ さ すせそ
た つ と ち と ち てと
なにぬねの なにぬね なにぬ の
はひ へほ はひふへほ はひ へほ
みむめも みむめも まみむめも
やいゆえ やい えよ いゆえよ
りる ろ らりるれ らりるれろ
わゐうゑを わゐ ゑを わゐうゑを
ん ん
消されているのは、かくしちてふまよられんいきしたつのまゆろううきしたつねふや。
並び替えると、ふね、したい、ちのつまつたふくろ、れきしてきかんしよう、が成立し、そして、まらゆうやが残る。
残った文字は前回消えたものと重なっているので、一度消えた文字は復活しないと考えられる。
最後に二人の名前を消す
あいうえお あ うえお あい えお
き けこ か くけこ か くけこ
さ すせそ さ すせそ さ すせそ
た つ と ち と ち てと
なにぬねの なにぬね なにぬ の
はひ へほ はひふへほ はひ へほ
みむめも みむめも まみむめも
やいゆえ やい えよ いゆえよ
りる ろ らりるれ らりるれろ
わゐうゑを わゐ ゑを わゐうゑを
ん ん
先ほどの表と見比べてみる。が、特に消えた文字は見当たらない。
おかしいと思って、よくよく見直す。やはり見当たらない。
この記事は解読と同時に現在進行形で書かれている。五十音表も全て手入力だ。打ち間違いかもしれない。そう思って原本を確認する。しかしやはり見当たらない。
もしかして誤植なのではないか。巻末の電話番号を確認する。そんなわけない。
そうして困惑していると、詩の題名が目に入った。
『消されたものが存在する』
そういうことか、と私は得心する。
今回、文字は消されていない。ならば答えは簡単だ。消されたものが存在するなら、消されていないものは存在しない。つまり、二人は存在しないのだ。
消されたものの存在が、逆説的に、二人の不在を導き出す。存在しない二人は、決して消されることのない不滅の存在となる。二人が同じ場所で出会うには、そうするしかなかったのだ。
ああ、なんて素晴らしくも美しい詩だろう。私はこの美しい詩を永遠に忘れることはないだろう。
完
ちょっと待ってほしい。確かにその解釈は間違いではないと思う。筋は通っているし、何より解釈は自由だ。
けれど他の可能性を見落としてはいないだろうか。例えば、今回消えた文字が、今まで消えた文字と全て被っている可能性とか。
その場合、今回消えた文字は特定不可能なので、これまでに消えた文字の中から二つの名前を作り出すことになる。
つまり「かくしちてふまよられんいきしたつのまゆろううきしたつねふや」の中から二人分の名前を探す必要がある。
この時代の人間一人の名前を大体六文字と仮定しても、上記二十九文字から六文字選んで並び替え、さらに残りから六文字選んで並び替えるパターンの総数は、文字被りなしでも29C6×6!×23C6×6!。計算したい人はしてみればいいが、おそらくこのやり方は現実的ではない。
別の角度から考えてみる。どうして五十音表は三つ用意されたのか。
てらやましゆうし、では、し、しか被りがない。一度目に文字が消される段階では、二つで足りたはずだ。だから三つ用意されたのは、のちの展開に必要だったからだと考えられる。
つまり、船、時代、血のつまった袋、歴史的感情と、そこに忍ばせる二人の名前に、三つの文字被りが必要だったのだ。
そこでふと思う。
この詩では、消された文字が多すぎないか?
想像してみてほしい。
あなた(寺山修司)は消された文字の中に二人の人名を隠す詩を思いついた。あなたは二人の名前(それぞれ六文字ずつ程度)をまず初めに決める。
次にそれを並び替え、二度目に消す単語を考える。そこには自分の名前も含まれる。もしそういうふうに逆算してこの詩が作られていた場合、自分の名前と二人の名前の文字数の和、つまり二十文字程度で成立させられるのではないか。
無論、自分の名前を含み、二人の人名になり、かつ他の単語にもなるという条件から多少の余分な文字は想定されるが、自分の名前と被ることも考慮すると、九文字も余分に必要かどうかは疑わしい。
実際にここでやってみよう。
これはかなりいい加減な一例だが、てらやましゆうし+鷹、波、渡航、寒さ、乙、で、さとうおさむ、と、たなかみつこを隠すことができる。自分の名前以外被りなしでも総文字数は二十文字である。もし「二人」に寺山修司自身が含まれるなら、さらに削減可能だ。
素人の私でも五分で出来るのだから、言葉に卓越した詩人であれば、同じことをより精密に、より効果的に実現出来るはずだ。
けれどそうはしなかった。文字数を最低限に抑え、特定の余地を残す作りにはしなかった。
ということは、彼には、読み手に二人の名前を特定させる気がなかったと考えられる。
やはり最初の結論は、あながち間違っていないのかもしれない。そもそも、詩に明確な回答を見出そうとしている私の方がずれているのかもしれない。
やれやれ、詩に触れて真っ先に出てくる発想がそれとは、いかにも頭が堅くて、融通の効かない、それでいて風情がなく、感受性が死滅した、全くもって哀れな奴だ。詩というのは心と体で感じるものなんだ。物事全てを構造的に捉えて、必ずそこに論理的な意味があると思い込むのは君の悪いクセだ。作者はそこまで考えて書いてないんだよ。
そんな声が私の頭の中で響く。しかし私は諦めたくなかった。寝る前に軽い気持ちでページをめくったせいで、気づいたらこんな時間になってしまっているのだ。もはや取り返しはつかない。なんとしても真相を突き止めなければ気が済まない。どちらにせよ、このままでは気になって眠れない。
私はあらゆる可能性を検討する。
二人の名前を消す。二人が同じ場所で出会うために。
これがもし、一度目と二度目に消された文字のことだとしたら? 一度目と二度目に消された文字は、同じ場所で出会う。なら一度目と二度目に共通している、てしし、に何かの意味が......。なさそうだ。そもそも消された二人が同じ場所で出会うのだから、この考えでは筋が通らない。
「詩というのは心と体で感じるものなんだ」
先ほどの心の声が蘇る。そうか、読んだ時のリズムや音に、何か隠されているのかもしれない。
詩を音読してみる。ほぼ五十音表だこれ。
そうか、どうして私は二人の名前を、固有名詞だと思い込んでいたのだろう。
最初に文字を消す時、私の名前=寺山修司だったせいで、最後もそうだと勝手に決めつけていた。けれどそれはミスリードだった。
つまりこうだ。二人の名前を消す、というのは、表から、ふたりのなまえ、を消す、ということなのだ。
そんなわけない。もしそうなら、複数ある、りのなえ、はどれを消せばいいのか。そもそもここでふたりのなまえを消すなら、一連の流れ的に最後の表から実際に消えてないとおかしい。なにより、そんな小学生のいじわるなぞなぞみたいな寺山修司は嫌だ。
謎? 私は本を開いて薄目を凝らす。例えば、消えた文字の間隔に何か意味があるとか、表を重ね合わせたら何か文字が浮かび上がるとか、マスに当てはめて消えた部分を塗りつぶしたりしたら、なにかわかるだろうか。わかるわけない。パズルじゃないんだから。
どうやら自分の頭で考えるには限界のようだ。
引っかかる部分はまだいくつか残っている。
・二人が出会う、同じ場所とはそもそもどこを指しているのか。
・船、時代、血のつまった袋、歴史的感情という語に何か意味があるのではないか。例えば、大航海時代、戦艦、血が関連する、歴史的な出来事になぞらえた詩だったりしないか。
・私は寺山修司についてほとんど何も知らない。彼について詳しい人は、あの二十九文字の中からすぐに、彼に縁のある人物を見つけ出すことができるのではないか。
しかしそれらは、自分一人では知りようのないことだった。それを知るためにはまず、この詩が書かれた当時の情勢や、寺山修司個人について調べる必要がある。
翌日、私は図書館へ向かった。
さて、そんなわけで、いくつかの資料に目を通してわかったことがある。
私は最初、詩の独特の形態に目を引かれたと言ったが、どうやら彼の作品において、こういう形態の詩は珍しくないということ。彼は「パズルみたいな詩」を好んだようだ。
また後述する通り、彼は生涯を通して非常に多くの作品を世に発表した。そのため、誰も解説や考察をしていない作品があってもおかしくない。
『消されたものが存在する』は、1972年に未刊の詩集『ロング・グッドバイ』のうちの一編として、『現代詩文庫52 寺山修司詩集』に収録された。
発表されたのがこの年だというだけで、彼がいつこの詩を書いたのかはわからないが、この年代周辺に、何か関連する出来事があるかもしれない。
寺山修司の概歴
ということで、まずは彼の来歴について、簡単に触れていこうと思う。
寺山修司は、1935年12月10日に青森県弘前市に生まれた。しかし戸籍上は、彼の誕生日は一ヶ月後の1936年1月10日ということになっている。
これは、彼の出生当時、警官である父・八郎が秩父宮の警護にあたっており、母・はつが産後保養していたため、役場に届け出るのが遅れたことに起因する。
修司は、このことについて母親に尋ねたところ「おまえは走っている汽車の中で生まれたから、出生地があいまいなのだ」と冗談めかして答えたという。
父の赴任地の移動で転校することが多かった修司は、出自の曖昧さも相俟って、一所不在の理念を形成していく。
転校先ではいじめられ、母の躾は厳しく、敗戦が濃厚になりゆく幼少期、彼は漫画に夢中になり、自らも漫画を描いて過ごしていた。
そんな中、1945年に青森空襲が起きる。母と共に焼夷弾の雨をくぐり逃げ、奇跡的に無傷で生き延びた彼に、やがて終戦が訪れた。
父の戦死が知らされ、郷土に遺骨が届くと、母は洋裁鋏で手首を切断して自殺をはかり、修司にも無理心中を強いた。
その夜、母が洗面器に吐いた吐瀉物を、修司は川へ捨てに行く。のちに発表する歌集では、この時の心情を次のように表現している。
波止場まで 嘔吐せしもの 捨てに来て その洗面器 しばらく見つむ
1948年、中学校への進学と同時に母が米軍のキャンプへ出稼ぎへ行くことになり、修司は映画館を経営する祖父の家に預けられる。彼はここで洋画と出会う。
また、映画館の客であった、ボクシングジムに通う映画技師の朝鮮人の影響でボクサーを志し、上京に憧れを抱くようになる。
同時期、彼は中学新聞に短歌を、『黎明』『はまべ』に俳句を発表し始める。中学時代には島崎、志賀、田山、鴎外、谷崎、漱石、芥川を読んで過ごしたという。
高校へ進学すると、青森高校文学部会議を組織し、全国詩誌『魚類の薔薇』を発行する。同時に様々な雑誌に投句し、俳句に熱中を見せる。
少年時代に、私がもっとも熱中したのは俳句を作ることであった。十五歳から十九歳までのあいだに、ノートにしてほぼ十冊、各行にびっしりと書きつらねていった俳句は、日記にかわる〈自己形成の記録〉なのであった。
過酷な食事制限に耐えられず、ボクサーの夢に挫折した彼は、そうして文の道で上京を目指すようになる。
少年時代、私はボクサーになりたいと思っていた。 しかし、ジャック・ロンドンの小説を読み、減量の死の苦しみと「食うべきか、勝つべきか」の二者択一を迫られた時、食うべきだ、と思った。 Hungry Youngmen (腹の減った若者たち) は Angry Youngmen (怒れる若者たち) にはなれないと知ったのである。 そのかわりに詩人になった。 そして、言葉で人を殴り倒すことを考えるべきだと思った。 詩人にとって、言葉は凶器になることも出来るからである。 私は言葉をジャックナイフのようにひらめかせて、人の胸の中をぐさりと一突きするくらいは朝飯前でなければならないな、と思った。 だが、同時に言葉は薬でなければならない。 様々の心の傷手を癒すための薬に。 エーリッヒ・ケストナーの「人生処方詩集」ぐらいの効果はもとより、どんな深い裏切りにあったあとでも、その一言によってなぐさむような言葉である。
1954年、早稲田大学教育学部に入学する。入学当時の進路調査によれば、彼は教職員か出版社への就職を希望していたという。
しかしこの頃、啄木へ憧れていた彼は、『短歌研究』に掲載された中城ふみ子の短歌『乳房喪失』に感銘を受け、自らも短歌『チエホフ祭』を応募する。するとその作品が特選となり、巻頭に掲載される。
これにて一躍時の人になるかと思いきや、しかし、彼の作品は高い評価を得た一方で、その模倣性が厳しく指摘されることになった。
以下に示すのはそれぞれ、上段が寺山の作品、下段が模倣元とされた作品である。
向日葵の 下に饒舌 高きかな 人を訪わずば 自己なき男
人を訪はずは 自己なき男 月見草 中村草田男
わが天使 なるやも知れぬ 小雀を 撃ちて硝煙 嗅ぎつつ帰る
わが天使 なるやも知れず 寒雀 西東三鬼
かわきたる 桶に肥料を 満す時 黒人悲歌は 大地に沈む
紙の桜 黒人悲歌は 地に沈む 西東三鬼
莨火を 床に踏み消して 立ち上がる チエホフ祭の 若き俳優
燭の灯を 莨火としつ チエホフ忌 中村草田男
莨火を 樹にすり消して 立ちあがる 孤児にもさむき 追憶はあり
寒き眼の 孤児の短身 立ちあがる 秋元不死男
このことは発表後まもなく俳壇・歌壇で話題になり、模倣・剽窃にあたるとして各紙で非難が声高になった。
加えて、俳句を短歌に転用したという点についても「俳句は公式や符牒ではない、ましてや感覚的な言葉のクロスワードパズルではない」と批判を浴びることとなる。
寺山はそれに対し「既成の歌、俳壇ではインモラルなことと受け取られるらしいが、しかし至極ぼくには当然のように思われる」と反論し、自らの詩作に対する姿勢を示した。
彼の高校時代の友人である京武久美は、過去に自らの作品も模倣された経験を踏まえた上で「彼は、他人の言葉を使っても自分の方が上ならそれでいいという考えでした」と語っている。
また批判にはあたらなかったが、当時の彼の作風についてはその虚構的な側面も指摘されている。例えば『チエホフ祭』の一首に次のような歌がある。
アカハタ売る われを夏蝶 越えゆけり 母は故郷の 田を打ちてむ
当時の歌壇では「アカハタを売る感心な少年」はいかにも青森県らしい農村風景として受け止められた。しかし寺山はアカハタを売ったこともなければ、その時期に母が田を打っていたわけでもない。
また、彼が高校時代に詠んだ俳句に次のようなものがある。
ちちははの 墓寄り添いぬ 合歓のなか
この俳句は、秋元不死男選で「父母への追想の情がしっとりと詠われた」と評された。しかし当時、父は戦死していたものの、母は存命である。
さらに言えば、『チエホフ祭』の冒頭には『青い種子は太陽のなかにある ジュリアン・ソレル』というエピグラムが挿入されている。しかし、ジュリアン・ソレルが登場する肝心の原典、スタンダールの『赤と黒』に、この台詞は登場しない。
架空のものをあたかも実在するかのように扱う手法は、現在ではありふれている。しかし当時、殊に歌壇では体験的なリアリズムが信奉されていたため、詠われた事象はそのまま作者の実体験であり、事実であると見なされていた。
それゆえ、私性を超えようとする彼の作風とその虚構性は、たびたび歌壇・俳壇を騒がせた。
寺山はこの虚構性について、のちにこう述べている。
嘘の方が本当より好きなこともあるんです。これは確かだ。本当ということは、かつてあったことと一致しているから、だからたったそれだけの理由で正しいとされる。既にあったから、などとは面白いこととは言えません。嘘だってこれからあるかもしれない
翌1955年、高校時代から兆しのあったのネフローゼが発症し、入院する。
入院中、同学部の山田太一や、高校時代の恩師である中野トクと文通をするようになる。また同時期、大岡信、谷川俊太郎と親交を深める。
しかし最終的に、病気のため早稲田大学を中退する。
1958年に、第一詩集『空には本』を刊行。同年には詩劇グループを結成し、子ども向け番組での放送やスポーツニッポンでの小説連載など、活動の幅を広げてゆく。
また、グループの仲間である嶋岡と短歌論争を交わす。嶋岡は「寺山の作品からはエリュアールの童話集、飯島耕一、関根弘、谷川俊太郎の詩が想起され、センスのいいシャレたヒョーセツと思わせるだけである」と相変わらずの彼の模倣を批判し、それに対して寺山は「短歌とは遊戯であり、同時に遊戯こそ不条理克服の一つの方策なのである」と持論を展開した。
寺山は一貫して表現の遊戯性を強調し、言葉の制度化に反発することで、制度の破壊を目論んだ。その主張には、表現に決まった形式を持たないという彼の姿勢と、挑発的な性格が滲み出ている。
そんな既成の秩序への反発は、以後いっそう顕著になる。1959年、彼はラジオに熱中すると、自らラジオドラマを執筆し、投稿するようになる。
しかし翌年の1960年に放送された、子供が革命を起こし、大人を刑務所に入れるという内容の、寺山作のラジオドラマ『大人狩り』が、暴力を煽動する恐れがあるとして、公安の取り調べを受けることになる。ちょうど六十年安保の年であった。
彼はその反動で、さらに戯曲やテレビドラマの制作にのめり込んでゆく。また同年、石原慎太郎、大江健三郎らの「若い日本の会」へ参加する一方、「文学界」に小説『人間実験室』を寄稿する。
1961年、新宿にアパートを借り母と暮らし始める。この時期、ボクサー、家出少年、革命家、バンドマン、香具師など様々な経歴の人々に友を求める。また、ファイティング原田との出会いがきっかけでボクシング評論を始める。
1962年には競馬に熱中して競馬評論も手がけるようになり、翌年の1963年に、松竹歌劇団の九條映子と結婚する。この時期、寺山はラジオドラマ、テレビインタビュー番組、テレビドラマなど幅広い分野で活躍する。
1967年、演劇実験室・天井棧敷を結成する。当初は傴僂、ゲイ、デブ、変身願望者、美少女、侏儒を劇中に取り入れ、見せ物の復権を狙って結成されたが、次第に規模は拡大し、翌年には地下劇場が設立された。海外遠征も次々と行い、のちのミュンヘンオリンピック芸術祭展示では『走れメロス』を上映するなど、海外での評判は天井知らずになっていった。
しかし後年になって、寺山は次のように述懐している。
「正直言って私は、演劇史に奉仕するつもりなど、毛頭なかった。(中略)思想が生きのびるためには無構造的であるべきだとしても、演劇は無構造的にパフォーマンスをもつことなどできるわけがない」
そんな考えもあってか、以後彼はさらに活動の幅を広げるようになる。
彼は『書を捨てよ町へ出よう(1971)』『田園に死す(1974)』など、自身の詩を基にして次々に映画を制作し、映画監督として作品を世に発表しはじめる。
その一方で、彼は作詩家としての顔も持つようになる。ザ・フォーククルセイダーズ『戦争は知らない』、五木ひろし『浜昼顔』などを手掛け、中でもカルメン・マキ『時には母のない子のように』は百六十万枚を売る大ヒットとなるほどだった。
以後も彼は、俳句、短歌、詩、ラジオ、ドラマ、テレビ、演劇、エッセイ、映画、楽曲、あらゆる方面で精力的に活動を続け、1979年に肝硬変を発症したのち、1983年に亡くなっている。
さて、『消されたものが存在する』は、この時期に『ロング・グッドバイ』のうちの一編として、『現代詩文庫52 寺山修司詩集』に収録されたものだった。
ここまでを踏まえ、あらためて考察を進めようと思う。
彼の性格について
寺山修司は前述の通り、無私の表現者であった。彼の作品に「母殺し」のモチーフが多用されるのも、家出を勧めるのも、一つの場所に留まらず、あらゆるものに次々と触れ、それらを自らのうちに取り入れるというスタイルの現れだろう。
彼には自己への固執がなかった。コラージュの天才と称される彼は、使えるものならなんでも使う。それが模倣や剽窃と批判されても、型破りであっても、そうして作り出された作品が良いものであれば、それで良いのである。
自己なき男は、魅力的なものを掘り当て、あらゆるものを表現し尽くす。彼にとって創造は遊戯であり、そこに固定化されたイデオロギーは必要ない。
しかしだからと言って、彼がニヒリストだったかというとそうではない。むしろその対極である。彼は大学時代に自殺した同世代の歌人たちに向けて「彼らに共通していたのは、きわめて抒情的な倫理によって日常を支配していたことである」と述べ、自殺という行為を否定している。彼は、偶然の産物である自らの生を根本的に肯定していた。
また、彼はヒトラーについて言及した文章で、ヒトラーは芸術家であったと持論を展開したのち、最後にこう書いている。
最後に一つだけ補足しておきたいことがある。
それは行為と実践のちがいである。詩人もまた他の文学者たちと同じように行為者であるべきだが実践してはいけない。たとえば本気でデモの効果を信じ、テロを信じ、世直しのための実践活動家になってはいけないのである。
寺山にとって、表現とは一種のアジテーションであり、人々の実践を誘発する装置だった。
芸術家は、自ら実践してはいけない。人々を扇動し、人々が行為するように仕向ける黒幕でなければならない。
そこでは彼自身の存在は意味を持たない。彼の根底に流れるのはリベラリズムではなくアナキズムであり、それは思想として生み落とされる前に、現実に照準を合わせ、引き金を絞り、人々の実践を密かに誘発する。
彼が一切許可を取らずに市街地三十ヶ所で突発的に詩劇を行った「ノック事件」は、たんなる秩序への反発ではなく、彼によって引き起こされた、現実への侵犯行為なのだ。
彼が、「起こらなかったことも歴史のうち、過去はいくらでも修正できる」と考えるのは、「非歴史」を「歴史」に修正するその引き金に、指をかけている自覚があるからだろう。
そんな彼の考えが色濃く現れているのは、彼の必然性との距離感においてである。
競馬に熱中し、競馬評論をしていた頃、彼は電子計算機による競馬予想について、こう述べている。
コンピューターの役割は勝ち馬を推理することではなく、レースが終わる前に勝ち馬を教えることであり、それは、展開するレースの時間を追い越して、結果だけを先に発表してしまうことで、その勝利に必然性を見いだすことである。そこには、レースを分析してゆく科学的な大時間だけが存在し、個人個人の選択する運命的な小時間などは、存在しなくなってしまう。
彼はここで、勝負の勝敗からダイナミズムを排し、結果を必然性に還元させることを批判している。
さらに彼は、三島由紀夫との対談で次のようなやり取りをしている。
寺山 三島さんが賭博をおやりにならないというのは、反悟性的とお考えだからですか?
三島 偶然というのは嫌いですからね。偶然が生きるというのは、必然性がギリギリに絞られているときだけだ。たとえばA男とB子が数寄屋橋でバッタリ会う。「やあ、お久しぶり」「よく会えたね、ここで」というのは小説じゃないんですよ。ところが芝居だと舞台の両側から出てきて「やあ、珍しいとこで会ったね」「あなた、会いたかった」っていったっておかしくないんですよ。芝居は必然性のワナですよ。
寺山 必然性というのも、偶然性の一つです。ぼくらは偶然的に宇宙に投げ出されたのだ、とは思いませんか。
三島 思わない。つまり、必然性が神で、芝居のスピリットなんだよ。だから、ハプニングというものを芝居に絶対導入したくないんです。というのは、芝居は必然性があるから偶然性が許されているんで、ギリギリの芝居の線だと思う。
寺山 ぼくは賭博好きで、いつも科学から空想へ歴史をかぞえてます。必然性なんていうのは主に総括とか結果論の中でたしかめられる。だからユートピアはいつでも偶然的です。ユートピアなんて言葉はとてもいやだけど、ぼくは科学より少しはいいんじゃないかと思っている。コンピュータなんかは耐えられないですね。
三島 いやだね。あれ、必然じゃないよ。
寺山 しかしコンピュータが悟性的だと思われる時代が近いうちにやってきた場合に......。
三島 絶対反対だよ。でもそんなことはポール・ヴァレリーがとっくに予見していることだよ、そういう悟性の危機についてね。
(中略)
寺山 「出会い」がすべて必然だと考えるとこわいですよ。三島さんは昔、明日何が起るかわかっていたら、明日まで生きるのはおもしろくない」と書いていましたが、ロマネスクの構造というのはむしろ世界の偶然性です。
三島 ドン・キホーテが不思議なことにぶつかるのは偶然じゃないよ。ドン・キホーテの性格のなせるわざだろう。
寺山 性格は食い物で決まったりするんで、たまたま何を食ったか、近所にどういう食い物屋があったかという偶然性で決まる。偶然じゃない性格ってのはファシストに支配されている人間にしかないんじゃありませんか?
(中略)
寺山 悟性はダメで、偶然性しかないのだといういい方をする悟性の方が、執念深く長生きしてゆくのです。
三島 長生きするとか、長もちするとか、全然考えないものね。あなたのいってることは芸術行為だろう。芸術行為でそんな長もちするなんて考えないもの。芝居やってて、どうしてそんな考え持つの? それは一夜の歓楽だけじゃないか。小屋出たら、もう何もないでしょう。
寺山 ぼくは一夜の歓楽までも必然性だと思ってしまうのはこわいです。悟性の下男にしかすぎない肉体っていやじゃないですか? ぼくは、「笑え」と書いた台本を渡すといつでも笑う役者というのは、とても気持が悪い。
三島 それは同感だよ。(笑)気持が悪い。杉村春子が、あたし泣きたいと思えばいつでも泣けるって......ボタンを押すと涙出てくるらしいんだよ、すごいね。
寺山 しかし三島さんは、そういう人は素晴らしいという視点に立っておられるわけですか?
三島 そう。そういう人を使わなければ、ぼくの必然性の芝居ってのはできない。
寺山 ステージの上に一人の男が立っていて、勃起したまえというと、イリュージョンを使って、パーッと勃起するというのが素晴らしいわけですね。
三島 ボディビルの原理って、そこにあるんだよ。体の中から不随意筋をなくそうというんだ。
寺山 つまり、肉体から偶然性を追放するんですか?
三島 そうなんだよ。たとえば、この胸見てごらん、音楽に合わせていくらでも動かせるんだよ。(胸の筋肉を動かして見せる)あなたの胸、動く?
寺山 ぼくは偶然的存在です......。(笑)
三島 ある晩、突然動いたりしてね。
寺山 でも、たかが五尺七寸の体の中にどんな黄金がかくされているかという幻想でも残しておかないとたのしみがない。体の構造をすべて知りつくすと、中にあるのは水分とセンイだけですよ。三島さんの中にあるのは......。
三島が「必然性を前提に、そこから逸脱するものとして偶然性を位置づけている」のに対し、寺山は「あらゆるものが偶然であり、あくまで結果として、必然的な解釈が可能である」と考える。
三島は執筆前の段階でほとんど作品の構想を決めていたことで有名だ。『橋づくし』を筆頭に、彼の作風は数学的かつ論理的、帰納的かつ逆算的である。
対して寺山の場合、創作の出発点に必然性は存在しない。寺山の世界では、偶然性が必然性に先立つ。彼にとって表現とは、起爆剤を作成して扇動することであり、その結果を必然的なものに収束させることではない。
消された言葉について
次に、消された言葉についての考察を進める。二度目に消された言葉は「船」「時代」「血のつまった袋」「歴史的感情」。
「船」については、天井桟敷から音声演劇『阿呆船』が発表されているほか、船を題材にしている詩がいくつか確認できる。しかし、そこに繋がりは見えてこない。「時代」に関しても同様である。そもそもこの二つの語は一般名詞のため、それらの作品と関連性があるのか判断しづらい。
しかし、「血のつまった袋」と「歴史的感情」についてはその限りではない。
「血のつまった袋」は、カフカが『兄弟殺し』の作中で用いる表現だ。そして寺山がカフカの表現を流用したことは明らかである。彼は自身の別の詩『綴じられない詩集のための目次』において、「人間は血のつまったただの袋である」と、よりカフカの表現に寄せて使用している。
「歴史的感情」についても、彼はまた別の詩『なぜ東京都の電話帳はロートレアモンの詩よりも詩なのか─読者の選択による並べ替え自由の詩』内で、「歴史的な感情」というふうに、似たような言葉を使用している。
以上から、これらの言葉は、この作品のためだけに生み出された語ではなく、彼の中で反復されるモチーフであることが推測される。
実在の人物について
最後に、実在の人物と照合して検証を行う。
あらためて、最後の五十音表を見てみよう。
あいうえお あ うえお あい えお
き けこ か くけこ か くけこ
さ すせそ さ すせそ さ すせそ
た つ と ち と ち てと
なにぬねの なにぬね なにぬ の
はひ へほ はひふへほ はひ へほ
みむめも みむめも まみむめも
やいゆえ やい えよ いゆえよ
りる ろ らりるれ らりるれろ
わゐうゑを わゐ ゑを わゐうゑを
ん ん
もし仮に、最後に消えた文字が、今まで消えた文字と全て被っていた場合、この五十音表から消された二十九文字「かくしちてふまよられんいきしたつのまゆろううきしたつねふや」の中から、二人分の名前が作られるはずである。
そこで、彼と親交のあった人物から、条件を満たす組み合わせが成立するか検証する。
まず、元妻である九条今日子(映子)、父母の八郎とはつは条件に該当しない。祖父の家に預けられた時、世話を焼いてくれた坂本きゑも該当しない。初恋の相手で、彼の詩にも幾度となく名前が出てくる大学の同級生、石坂和子(夏子)も該当しない。映画に熱中していた頃の”推し”、テレサ・ライト、マリリン・モンローも該当しない。
その他、彼と関わりのあった人物を私が調べた限り列挙してみたが、該当する者はほとんどいなかった(京武久美、中城ふみ、中野トク、岸田大作、塩谷律子、坂本勇三、谷川俊太郎、広瀬隆平、鶴見俊輔、山口昌男、篠田正浩、塚本邦雄、三島由紀夫、大江健三郎、吉本隆明、美輪明宏、等)。
大学時代の友人、山田太一と、天井桟敷時代の好敵手、唐十郎だけは消された文字から作ることができるが、寺山修司と組み合わせる場合は文字が被って成立しない(法則に従えば、同時に同じ文字は使用できないはずである)。
山田太一と唐十郎を組み合わせる場合は成立するが、この二人の組み合わせには必然性がない。彼が必然性を重視していないことは前述したが、それでも、いやむしろ、だからこそ、父母や妻や初恋の人を差し置いて、彼らが必然的に選ばれるとは考えづらい。
結論
これまでの情報を整理する。
・彼は創作において、必然性を重視していない。私が示したように、消す言葉を最低限の文字に絞り、特定可能な語の組み合わせを逆算的に作るのは、むしろ三島的と言えるだろう。
・また、彼は二度目に消された言葉を自身の他の作品でも使用しており、中でも「血のつまった袋」には明確な引用元がある。これらは彼の中で反復されるモチーフであると推測される。
・そして検証の結果、彼と親交のある実在の人物の中に、適当な組み合わせは存在しない。
以上三点から、この詩は実在の人物を含むものではなく、形式を使用した主張としての詩であると考えるのが妥当である。
補遺
それでは、彼はこの詩で何を主張したかったのだろうか。
ほとんど根拠のない私見にすぎないが、彼の想いを少しだけ推察してみたい。
彼が亡くなった1983年5月4日、週刊読売に自筆原稿が掲載された。
私は肝硬変で死ぬだろう。そのことだけは、はっきりしている。だが、だからとい言って墓は建てて欲しくない。私の墓は、私のことばであれば、充分。
彼は自らの死を予言しながらも、墓を必要としなかった。
なぜなら、彼はすでに死んでいたからだ。
昭和十年十二月十日に
ぼくは不完全な死体として生まれ
何十年かかって
完全な死体となるのである
そのときが来たら
ぼくは思いあたるだろう
青森県浦町字橋本の
小さな陽のいい家の庭で
外に向かって育ちすぎた
桜の木が内部から成長をはじめるときが来たことを
子供の頃、ぼくは
汽車の口真似が上手かった
ぼくは
世界の涯てが
自分自身の夢のなかにしかないことを
知っていたのだ
寺山の直接の死因は、肝硬変に併発した急性腹膜炎による敗血症だった。彼によって書かれたことは、実現しなかった。コンピューターではなかった彼は、結果の発表に失敗したのだ。
けれどそれは、奇しくも彼の理念を実現することになった。
現実とは、偶然起きただけのものにすぎない。にもかかわらず、ただ一回起きたというだけで、正しいことになってしまう。
そしてそれは、書かれた文字にも当てはまる。
一度書かれたものは、事実としてそこに固定される。固定された事実は、身動きが取れなくなって、どこへも行けなくなってしまう。
だから彼は、書かれた文字を消したのではないだろうか。
過去にも歴史にも、事実にさえも、自らの手で修正する余地が残されているのだから。
鉛筆が愛と書くと
消しゴムがそれを消しました
あとには何も残らなかった
ところで
消された愛は存在しなかったのかといえば
そうではありません
消された愛だけが
思い出になるのです
どうせ、文字が消えたくらいでは、無かったことにはならないのだから。
消されたものが存在する。
彼は、現実も虚構も、生も死も超えて、すべては同じ場所で出会うことができると考えていたのではないか。
だからきっと、世界の涯てが自分自身の夢の中にしかなくても、それでよかったのだろう。
消しゴムがかなしいのは
いつも何か消してゆくだけで
だんだんと多くのものが失われてゆき
決して
ふえることがないということです
少女はとても上手に飛行船をかいた
だが
その飛行船に乗ることはできなかった
(どうしてもこの飛行船に乗りたい)
と一日中なやんでいましたが
とうとう消しゴムで消してしまった
ばかだねえ
その飛行船と一緒に乗っている自分をもかいてしまえばよかったのに
鉛筆があれば、書くことができるのだから。
本人の意に反して、寺山修司の墓は東京都八王子・高尾霊園に建てられた。
しかしその上には、何も書かれていない一冊の本が開かれている。
参考文献
寺山修司「ぼくが戦争に行くとき―反時代的な即興論文」,読売新聞社,1969
寺山修司「寺山修司詩集」,思潮社,現代詩文庫52,1972
寺山修司「ポケットに名言を」,大和書房,1973
寺山修司「黄金時代」,九藝出版,1978
寺山修司「寺山修司歌集」,国文社,現代歌人文庫,1983
栗坪良樹ほか「寺山修司」,新潮社,新潮日本文学アルバム,1993
寺山修司「続・寺山修司詩集」,思潮社,現代詩文庫105,1998
杉山正樹「寺山修司・遊戯の人」,新潮社,2000
高取英「寺山修司 過激なる疾走」,平凡社,2006
湯原公浩「寺山修司 天才か怪物か」,平凡社,別冊太陽 日本のこころ207,2013
齋藤愼爾ほか「寺山修司の〈歌〉と〈うた〉」,春陽堂,2021


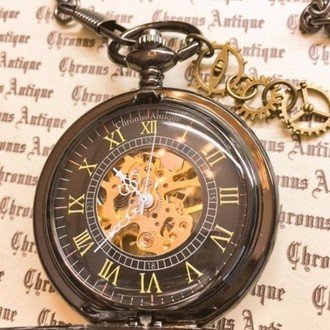
コメント
1こんばんは。寺山修司は旧くても、いつも新しいですね。高校生くらいのときに夢中になったことを思い出します。