太陽光パネルはどれくらい悪いか計算する
きっかけ
皆様ご教示方ありがとうございます.20年前の数字で止まっていた私の認識が今の時代に再生産されてしまうことは自然科学や技術への弊害であるため,それを防ぐべく,恥も残すという私のポリシーに反するのですがこちら削除させて頂き画像でのみ恥を晒すことと致しました.お騒がせしました.#TMU_SSL pic.twitter.com/u7UinnIG44
— 宇宙システム研究室@東京都立大学/佐原研究室 (@TMU_SSL) July 27, 2025
太陽光発電は本来地上に留まらない波長帯を電力に変えて消費して地上付近に排熱するので実はクリーンではないのでは、とするツイートを発端とする炎上があった。
ツイートの主張は撤回しているようだが、夏場に黒い服よりも白い服を着た方が暑くないし、こうして聞いてみると、なんとなくそのような気もするし、そうでないような気もする。
では、太陽光発電パネルはどれくらい悪いやつなんだろうか? を考えてみよう。
結論から言うと、たしかに太陽光パネルの本来地上に留まらない波長帯を電力に変える作用は地球を加熱するが、太陽光発電が化石燃料由来の発電を置き換えて二酸化炭素の排出を抑えることが冷却の方向にはたらき、その影響はせいぜい3年程度で相殺され、以後は地球を冷却すると考えてよい、ということらしい。
この記事は、なんとなく地球科学のモデリングについて興味があった物理学ちょっとわかるオタクが1日くらい関連記事や解説を読んで整理したメモである。
惑星の暑さ
太陽定数
また、惑星がどの程度太陽光を反射するかの指標があり、アルベド
上のふたつの数字を使って、地球の単位面積が太陽から1秒あたりに吸収するエネルギーを表現すると、
になる。反射率を引いた分が吸収だよね、というだけの式だ。どうして急に4で割っているかというと、太陽定数は垂直な直射日光を想定しているが、地球は球体だからである。球の表面積
地球はこの残った70パーセントで加熱される……のだが、毎秒こんな膨大なエネルギーを溜め込み続けているわけではない。地球の温度がだいたい一定に保たれているのは、入ってきたのとちょうど同じ分を放射して冷却しているからである。石焼き芋の石が出す遠赤外線と同じ原理である。なんやかんやがあって、温度
σはシュテファン=ボルツマン定数と呼ばれる定数で、かっこいいので名前だけ覚えて帰ってください。Tについて解くと、
となる。これで「太陽光パネルが地球を暑くする」を説明する道具は揃った。太陽光パネルを設置すると反射率=アルベド
温室効果をモデリングする
しかし、地球温暖化?には温室効果?というやつが効いているはずで、自然エネルギーは温室効果ガス?を出さないから地球を冷やすのではなかったか?
実は、上の単純なモデルは単純化しすぎていて温室効果ガスを扱うことができないのであった。ここで、もう一つだけ要素を加えたモデル、理想温室モデルを導入しよう。さっきの考え方に一層だけの大気の影響を足したモデルである。
前のモデルでは地球というでっかい塊だけを考えていたが、今度は間に大気という層があると考えよう。大気は地球の放射を吸収率εで吸収するものとする。
地表の式はさっきの式の最後に余計な項が一つついただけの式である:
この余計な項が、「吸収率εで温度
大気についても吸収した分と放射した分が釣り合う式が書けて(大気も際限なく熱くなることはないので)、このようになる:
上の画像の青い矢印の合計が「地球が受け取るエネルギー」で、赤い矢印が地球および大気の放射するエネルギーで、点線から下の釣り合いが「地表の式」、上の釣り合いが「大気の式」に対応するというわけだ。
(
これは連立方程式なのでムニャムニャすると、まず
が得られる。2の4乗根はだいたい1.19くらいなので、地表の温度と地表付近の大気って差が出るのか〜、気温とアスファルトの温度が変わるのってこれが原因なんかな? といった妄想が広がる。
式をさらにムニャムニャすると地表温度について整理できて
が出てくる。上のモデルと比べると
の部分だけが違っていて、これが温室効果による影響である。
要はバランスっしょ
二酸化炭素による温室効果は、上のモデルでは二酸化炭素が増えるとε(放射の吸収率)が増える、という形で説明できる。実際、εを大きくすると分母が小さくなって温度が上がる。ひとまず、これが地球温暖化だと思っていいだろう。
さて、新しい式でも同様に「太陽光パネルを置くとアルベドが下がり、温度が上がる」が言える。太陽光パネルを置くと気温が上がる、は真である。
しかし、「太陽光パネルを置くと化石燃料の使用が減り、CO2が減るので、温度が下がる」も言える。太陽光パネルを置くと気温が下がる、も真である。
ほな結局どうなっとんの、と考えるために、太陽光パネルの設置に関係している項だけを括り出してみよう。
これが太陽光パネル善玉悪玉指数(勝手に命名)である。この値が太陽光パネルを置く前より大きくなっていたら地球温暖化を起こす悪玉、小さくなっていたら善玉である。
ここで考慮する必要があるのが、これまで議論したモデルでは、アルベドが下がることによる温度上昇は即時に発生する一方、二酸化炭素を減らす効果は、稼働している時間だけ累積していくということだ。仮にtを時間、cを温室効果の増加速度として
とモデル化すれば、太陽光パネル善玉悪玉指数は
となり、時間がたつとctをどこまでも大きくできる(εは1を超えないしモデルが適用できる限界が来るのだが、そんな値の範囲のことは考えなくてよい)ため、cを減らす(化石燃料を太陽光発電に置き換える)と必ずどこかの時点で太陽光パネルを使った方が気温が下がる、と言えるのである。
つまり、太陽光パネルを置くと地表のアルベドが下がり、一時的に温度が上がるが、太陽光発電は化石燃料による発電を抑制するので、CO2の排出を減らす効果によって、いずれ必ずアルベド減による気温上昇よりも大きな気温降下の効果がある、というややこしい言明がこの話の結論である。
いずれってどれくらい時間かかるの
この「いずれ」が何十年、何百年もかかるのであれば意味がないわけで、これを上でやったものよりもずっと精緻な数理モデルや実測値から推定した研究論文がある。太陽光パネルを作ったり処分するのにもCO2が必要なので、そのあたりも考慮して計算をするらしい。
ここからは専門性がないのでちゃんと論文の妥当性を評価できているかはぜんぜん自信がないが……
どうでもいいが、この論文を出しているPNAS NexusのPNAS(米国科学アカデミー紀要 Proceedings of the National Academy of Sciences)のことを日本人はよくピーナスと略して呼ぶが、どう考えてもpenisに聞こえるので絶対に国際学会ではピーエヌエーエスと言わないといけないというあるあるがある(急なペニスの話おわり)。
論文では、この「アルベド変化による温度上昇をCO2減による温度降下が超える損益分岐時間、“break-even time” (BET)」がいつかを計算したところ、太陽光パネルの損益分岐時間は乾燥地帯においては2.5年で、2年半くらい使えば温度上昇の元が取れる計算になるそうである。
もちろん森林━━あったら涼しい気がする我らが癒しの森も比較していて、森林(周囲よりも暗いのでアルベドを下げてしまう)の炭素固定の損益分岐時間は94年から185年である。森林には他の複合的な役割もあるとはいえ、気温への影響効果だけを見れば、伐採して太陽光パネルを置くほうが温度降下効果が20~50倍程度すごいらしい。
オイオイオ〜イ
おまけ追記
なんでそんなことになる(森より太陽光パネルの方が冷却効果がある)の? そんなわけなくね? を考える上では、上の概念図のC fluxの項目を見るのがよさそうだ。太陽光パネルは
化石燃料は来歴を辿れば「過去に生物が太陽光を化学エネルギーとして蓄えたもの」と考えることができる。値を比較すると木が光合成で光を化学エネルギーに変える100倍の速度で化石燃料を燃やしているのが化石燃料発電と言えて、それを置換することの効果が大きすぎる、というのが今回森が大敗した主要因である。このレギュレーションの元では森は発電してないので負けた、と言ってもいいだろう。上で挙げた「実際に固定する」はたらきを担うものが必要なほか、森には土壌の固定や生態系の保全など、多種多様な他の役割もある。森をドンドン伐採して太陽光パネルを置こう、という議論はあまりにも乱暴である━━が、「森林は無条件でいいもの」というイメージもまた一つの排除すべきバイアスだろう。
もう一つ重要なのが、温度変化の局所性である。太陽光パネルによる温度上昇の影響は局地的(ソーラー施設の周囲数十メートルの気温が上がったという報告や、屋根にパネルをつけることで室温が1℃上がったなどの報告がある)で効果が実感される一方で、発電方法の代替を経由した冷却の効果は即時的でもないし、実感もできない。「ソーラーのせいでこのあたりが暑くなった」は実感のレベルでは正しいこともあり得る、というのが難しいところである。
また、気候ってそうした局所的な変化で非線形な何かが起こってそこからまた別の何が起こるかわからん世界なので、最終的にどんな桶屋が儲かるのかは、やっぱりよくわからない。
おわり

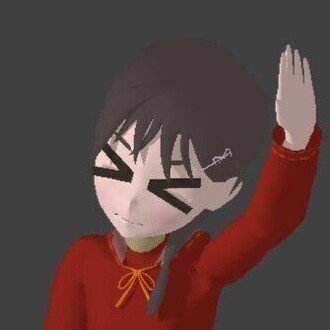
コメント