極右の傾向と対策まとめ① 極右の「Normalisation(正常化)」について
日本の皆さん、ついにこの時が来てしまいました。
都議選、参院選の結果をご覧になりましたか?
ついに日本にも、極右ポピュリズムの波が押し寄せてきました……
とはいえ、彼らは所詮、欧米の極右の後発コピーにすぎません。相手が先行する極右を模倣しているのであれば、私たちも先行事例を踏まえて対策を練ればよいのです。あなたは一人ではありません。世界中に仲間がいます。
私が暮らしているフランスでは、昨年の議会選挙で極右ポピュリズムがかつてないほどの躍進を遂げました。それに対し、新人民戦線は激闘の末勝利を収めました。極右の分析、知見、対抗のための戦略は、すでに山のように蓄積されています。これを活用しない手はありません。
もちろん、参政党が日本の歴史や文化、制度に応じて欧米の極右路線に独自のアレンジを加えているように、対抗する側にもある程度のローカライズは必要でしょう。しかし、重要な構造的特徴は多くの点で共通しています。
以下では、2024年10月に出版された極右の分析書『Une étrange victoire(奇妙な勝利)』の著者である哲学者ミカエル・フォエッセルと社会学者エティエンヌ・オリオンへのインタビューをもとに、極右の「正常化」戦略とその対処法について考察していきます。
本題に入る前に、まずはこの本『Une étrange victoire』の紹介文をご覧ください。いま日本で起きている極右の台頭と、響き合う点があるはずです。
極右について語られる「勝利」とは、いったいどのような勝利なのか? 期待されたもの、恐れられたもの、避けがたいもの――この勝利を形容するために形容詞がひしめき合っている。だがこの勝利は、まずもって「奇妙な」ものであるのかもしれない。たとえば、排外主義が共和国の防壁として掲げられたり、その経済政策が左派のそれに近いと聞かされたりするのは奇妙なことである。また、人工妊娠中絶(IVG)の憲法化を支持し、文化的リベラリズムに与しているのを目にするのも、奇妙である。 フランスでも他国でも、この「奇妙さ」こそが勝利の一要素となっている。
この勝利は、現代民主主義の政治的座標が混乱した結果として生じている。右派と左派の対立の弱体化、共有された記憶の放棄、公共的議論の崩壊が、一つの政治潮流を見分け難くしてしまった――そしてその潮流が勝利するためには、まさに見分けられないことが必要だったのだ。勝利したのは、極右の「思想」そのものというより、むしろその下部政治(infrapolitique)つまり「常識」や、時代の風に合わせて調整された「国民的価値観」といったものだった。このようなアイデンティティ的道徳に対し、筆者たちは「平等の政治」への再投資を提案する。そして、「わたしたちの国」への固定的帰属に代わる、もう一つの「わたしたち」を思考するよう呼びかけている。
現在の参政党の躍進においても、「極右なのに経済政策に左派的な要素がある」とか、「極右なのに女性候補が多い」といった指摘がなされ、その“奇妙さ”にすでに気づいている方も少なくないでしょう。こうした極右の躍進の背後にある「下部政治(infrapolitique)」を探るためにも、今回はまず「極右の正常化」という側面に焦点を当て、以下にまとめておきます。
極右の「Normalisation(正常化)」戦略について
はじめに 極右の定義とそのイデオロギー的背景
参院選の速報特番をいくつか視聴していた際、あるパネリストが「これまで奇抜または過激と受け取られる候補者が多かった中で、参政党はそうではなかった。そのため一定の支持を得たのではないか」と指摘していました。しかし、まさにこれこそが極右が用いる「正常化(Normalisation)」戦略の典型です。それにもかかわらず、日本の報道各社はいまだに、参政党を「右派」と呼ぶべきか「極右」と呼ぶべきか、判断をためらっているようです。
ミカエル・フォエッセルとエティエンヌ・オリオンへのインタビューでは、極右の定義として以下の三点が挙げられていました(これは、近年多くの報道機関や研究者に引用されている政治学者カス・ムッデ Cas Mudde の定義に基づいていると思われます)。
極右の定義
1 ナショナリズム: 極右は国家を重視し、ナショナリズムを掲げます。たとえばフランスの極右政党 国民連合(Rassemblement National)は、「国家の保護」や「国益の擁護」を強調しています。
2 ネイティビズム: 国の出身や血統に基づいて人々を優先する考え方です。たとえば「国民優先」「自国民第一」などのスローガンがこれに該当します。
3 権威主義: 法の支配や権力の分立に懐疑的で、しばしば「多数派による民主主義」を盾に、司法の独立や少数派の権利を軽視する傾向があります。
極右が取る「正常化(Normalisation)」戦略とは、極右が従来の政治スペクトルの“極”に属するというイメージ(排外主義、暴力性、差別主義など)を薄め、「受け入れ可能な政党・選択肢」として政治的正統性を得ようとする戦略です。
また、極右が登場しやすくなった背景として、「右でも左でもない」政治の台頭が挙げられています。エマニュエル・マクロンは2017年の大統領選挙において、「右でも左でもない」という立場を掲げ、伝統的な政治的対立軸を超えた路線を打ち出しました。これは、左右のイデオロギー的基盤を解体し、政治的スペクトル全体を再編するものとなりました。従来、左派は平等を、右派は競争と自由を重視してきましたが、マクロンの戦略はその二元論を曖昧にしました。この曖昧さが、極右の立場を「どこにでも属せる」ものとして浮上させ、位置づけを不明確にする効果をもたらしました。
⚠️日本でも、国民民主党の玉木雄一郎が「右でも左でもない」と語るようなポピュリズム的戦略を展開しており、それが参政党のような新興右派勢力への支持拡大と軌を一にしているように見えます。このような傾向は、フランスのマクロン政権誕生からの極右の躍進との類似性を持つと言えるのではないでしょうか。
1 極右の「正常化」戦略
① 脱悪魔化(Dédiabolisation)
目的:極右に貼られてきた「危険な存在」というレッテルを剥がし、公共圏における受容を広げることです。
手段:
・過激な主張のトーンダウン(例:EU離脱の放棄、同性愛者の権利への表面的な配慮)
・イメージ戦略としての、マリーヌ・ルペンによる「穏健化された」語り口
・過去との距離を示す姿勢(父ジャン=マリー・ルペンとの断絶をアピール)
⚠️ 参政党の場合:まだここまでの段階には至っておらず、初期のジャン=マリー・ルペンが登場した頃のように、過激な発言によって注目を集める段階にあると考えられます。SNSや街頭演説での極端な発言に対しては、「攻撃されている」こと自体をアピール材料とし、むしろ支持の正当化に用いており、協調やイメージ修正を試みる姿勢は現時点で多くは確認できていません。ただし、結党当初に顕著であった反ワクチン的言説や陰謀論的、スピリチュアルレトリックからは部分的に距離を取りつつあるようにも見え、一定の「脱悪魔化」的動きの兆しがうかがえるとも言えます。
② 言説戦略(語彙と価値観の転用)
目的:グラムシの「文化ヘゲモニー」の概念を応用し、まず言語や文化の領域で影響力を持つことを目指します。社会全体の価値観や考え方を変えることによって、極右の言語や主張が他の政党や一般社会に受け入れられやすくなり、自らの立場を正当化しやすくなります。極右は、民主主義・共和制・人民など、本来は左派的あるいは普遍主義的な語彙を再定義して用います。
具体例:
・「共和国」:本来は平等の象徴ですが、フランス文化への同化を強制する論理や、排他性の根拠として再定義されることがあります。
・「民主主義」:本来は多数派と少数派のバランスを前提としますが、極右は多数派の声を絶対視し、少数派保護の原則を弱体化させる方向で用いる傾向があります。
・「進歩派」は、しばしば「抑圧者」「検閲者」として描かれます。
・「エリート」批判:極右は、進歩派の知識人やメディア関係者などが大衆から乖離していると非難します。
・陰謀論の利用:「大置換」理論 : 「大置換(le grand remplacement)」理論は、移民や外国人によって国民が“すり替え”られているという陰謀論的な主張です。極右はこの物語を利用して、「国民 vs エリート」「大衆 vs 他者」という二項対立を煽ります。この対立の構図の中では、メディア関係者や中道左派の人物までもが「裏切り者」「抑圧者」として扱われる傾向があります。
・言葉の転用:「キャンセルカルチャー」の事例: 「キャンセルカルチャー」はもともと、権力者への批判や不適切な発言に対する社会的応答として使われてきた言葉ですが、近年では左派を攻撃する口実として用いられることが増えています。実際には、学問や文化への検閲・抑圧は保守派の側からも行われており、その影響は大学や公共施設にも及んでいます。
⚠️ 参政党の場合(言説戦略との接点)
・「民主主義」の再定義
民主主義とは、単なる多数決ではなく、少数派の権利保護や熟議的手続きを含む制度です。参政党は「参加型民主主義」を強調しますが、その内容はしばしば国体主義的です。憲法草案に見られるように、「国民主権」よりも「国体」や「天皇主権」に近い価値観が前面に出る場面もあります。また、外国人の地方参政権については明確に反対する立場を取っています。
・「人権」の再定義
本来人権は、すべての人に等しく適用される普遍的・個別具体的な権利です。しかし参政党には「外国人の人権ばかりが守られて、日本人の人権がなおざりにされている」といった主張が見られます(例:生活保護や教育支援に関して)。ここでは、「人権」という言葉が「日本人の生存権の優先」という枠に置き換えられ、普遍的な人権の概念が、民族的な帰属(ネイティビズム)と結びつけられるかたちになっています。また、「基本的人権」の議論が、「参政権の有無」などにすり替えられる傾向もあり、人権の概念が政治的に転用されていることがわかります。
いま参政党・神谷代表が、外国人の生活保護受給の一律停止に関しての「基本的人権があるのにそうするのか」との記者の質問に「参政権を認めていないから」と回答した。「生存権の話をしている」と言われ「基本的人権という意味で言っているだけ。国籍のあるなしで線引きはある」と答えた。もうだめだ… pic.twitter.com/mmI1atjEL9
— 黒猫ドラネコ (@kurodoraneko15) July 20, 2025
③ 世論とメディアへの適応
目的:極右は意図的に、多数派の意見に迎合することで「過激派ではない」と思わせようとします。また、メディアへの露出を増やし、他の政党と同様の扱いを受けることで、「普通の政党」としての定着を図ります。
具体例:フランス国民連合に見られる主張の柔軟な調整
・同性愛、経済、欧州統合 → 軟化
・移民、安全保障 → 強硬なまま維持
こうした姿勢の使い分けにより、極右は特定の主張を控えめに見せつつ、核心的なイデオロギーを保持し続けます。
⚠️ 参政党の場合
党幹部の神谷宗幣氏は、「『日本人ファースト』は選挙の間だけ」と発言しており、排外的スローガンを戦術的に使っている可能性があります。また、記者会見では「外国人特権は存在しない」と述べるなど、主張を一部トーンダウンさせる場面も見られます。
参政党の手のひら返しの速さ。
— 藤井セイラ (@cobta) July 21, 2025
ー外国人に特権はあると思いますか?
神谷宗幣党首「外国人特権…?(首をひねって)特に日本ではないんじゃないですか?」
ー憲法案を候補者は読んでいますか?
「読んでないんじゃないですかね。とにかく政策『カタログ』を指導しました」pic.twitter.com/ALaJLFzrrx
④ 政治的境界の曖昧化
極右の言語や主張は、他の政党、特に中道や中道左派によって部分的に取り込まれることがあります。その結果、極右と他党の境界が曖昧になり、有権者にとって両者の違いがわかりにくくなる状況が生まれます。
フランスにおける例:
・サルコジ政権による「移民・統合・国家アイデンティティ省」の設置
・社会党政権による、重大犯罪を犯した者への国籍剥奪の提案
こうした政策は、本来は極右の専売特許だった論点を、主流政党が選挙戦略の一環として取り込んだ事例といえます。
⚠️ 日本の事例として
2022年の参院選などの選挙戦においては、「外国人問題」に関する言説に、自民党や公明党が反応するかたちで乗ってくる場面が見られました。このように、選挙戦という局面で他政党が極右的言説を取り込むことで、両者の違いが一時的に見えにくくなり、極右の立場が正当な政治的選択肢として相対的に“正常化”される効果が生じます。
不法滞在者ゼロ、違法外国人ゼロへ
— 自民党広報 (@jimin_koho) July 18, 2025
 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
過日、難民認定申請を繰り返した男性が強制送還されたことがニュースになりました。令和5年の入管法改正(令和6年6月施行)以降、4,371人以上が帰国、送還されています。… pic.twitter.com/5aqlC0ICJB
🔥正常化のリスクまとめ
• 民主主義の用語や原則が歪められ、空洞化される。
• 極右のイデオロギーが「普通」であるかのように浸透し、警戒感が失われる。
• 政党間の区別がつきにくくなり、有権者の判断が曖昧になる。
2 極右の「正常化」への対策
では、こうした極右の「正常化」に私たちはどのように抵抗できるのでしょうか。上のインタビュー動画では、言葉の意味を極右から取り戻し、政治的基準と制度的抵抗力を回復することの必要性が強調され、具体的には以下のような提案がされています。
1. 語彙の再定義と明確化
・教育と啓発: 言葉の本来の意味を教育や啓発活動を通じて広め、再構成された意味に対抗する。「言葉の意味を取り戻すこと」「言葉の定義を明確にすること」こそが、極右に対する根源的な対抗になります。
2. メディアの役割
・政策内容への焦点の回帰 : 人物間の緊張や戦略ではなく、政党の政策の中身・一貫性・矛盾点を検証し、報道する。
・過去の言動の文脈を隠さない: 極右政治家の過去の差別的発言や立場転換について、歴史的・文脈的に正確に伝える(例:「失言」ではなく明確な名称を用いる)。
・内部対立ばかりを報じない : 極右政党内の権力闘争や人間関係のドラマを過剰に報じない。そのことで「普通の政党」としてのイメージが強化されるため。
・極右に特権的な露出を与えない: 極右がテレビや新聞に頻繁に登場し続けることで、「発言権の正当性」が与えられたと見なされるリスクを警戒する。
しかし、フランスでは極右の億万長者がメディアを所有または支配することで、報道内容に影響を与え、極右の主張や視点がメディアを通じて広まりやすくなっているとう現状も指摘されています。そこで極右の台頭に対抗するために重要な役割を果たすのが独立派メディアです。独立派メディアは極右の政策やプログラムの内容を批判的に分析し報道することで、極右の台頭に対抗するための重要な情報源として機能します。
3左派の「平等な政治」への再投資
・左派はアイデンティティ政治への依存を避け、より普遍的な価値に基づく政治言説を強化する。
ナオミ・クラインは、左派の中にも不寛容さが存在することを指摘しています。たとえば、アメリカの民主党は「改革」や「正義」の名のもとに、一部の大衆を見捨ててきたという批判があります。「進歩派」という言葉自体も、実は多様で、ときに矛盾する内容を内包しています。こうした中で、左派や進歩派は、「民主主義」、「表現の自由」といった言葉の意味を再定義・再確認する必要があるとされています。
左派自身もまた、自らの立場や言語を問い直す時期に来ているのです。とくに、社会の一部を置き去りにしたり、異論に対して過剰に反応したりする姿勢が、結果的に極右への支持を後押ししてしまっている可能性があります。だからこそ、進歩的価値の普遍性を改めて確認し、それを誰にとっても開かれたものとして再構築する努力が求められています。左派は「アイデンティティの罠」に陥ることなく、平等主義の原則を軸とした包摂的な政治を再び掲げるべきであると、彼らは警告しています。
おわりに
いかがでしたか? フランスの極右の「正常化」戦略について見てきましたが、その手法や言説のスタイルには、日本の現状にも通じる点が多々あるのではないでしょうか。極端な主張や排他的な価値観を、あたかも常識的で現実的な意見であるかのように装い、徐々に社会に浸透させていく戦略は、決して他国だけの現象ではありません。
極右は「極右」という呼称を嫌う傾向があります。「極右」という言葉には、一般的に否定的なイメージが伴い、極端で過激な立場を示すものとして受け取られるためです。そのため、彼らはこの呼称を避け、自らの立場をより穏健で、一般市民の声を代弁するかのように演出しようとします。こうしたレトリック戦略に無自覚でいることは、彼らのイデオロギー的本質を見誤る危険を孕んでいます。表面的な言葉遣いやイメージに惑わされることなく、その内実を見極める視点が今こそ求められているのではないでしょうか。

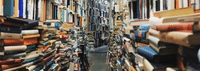

コメント
2まさに引用されている黒猫ドラネコさんが長年ウォッチしてきたように、参政党はマルチ的な手法での支持者の囲い込みや組織の構築を行ったり、スピリチュアル方面や自然派を介して左派の一部へリーチして地方議会で勢力を伸ばしてきたわけです。左派に置き去りにされたと感じている有権者の掘り起こしを伴いながらですが。
左派の政治的言説の再構築と言っても実際の非エリートの労働者が見捨てられたと感じている点では相当な不信を伴っていると思います(意地の悪い言い方をすれば自分たちは”頭のいい人たち”に煙に巻かれているとか、無下にされているとか。)。思想的な分析や概念的な政治方針の展開は結構なものとしても、もっと低レイヤーのプリミティブな部分で疑念なのは、この期に及んでも高踏性と無謬性の安全地帯に自らを置いたままなのではないか、理性的な自己批判と立て直しを行う本気があるのか、「頼りない」と思ってしまうところです。
分析についてはまったく同意します。
社会が取りこぼしてきた人達には、どの党も未来を託せそうな存在として見えていなかった。参政党は救いをもたらすと信じられたことが背景にあると思います。
SNSなどで支持者の発言をを見て思うのは、しばしば政治で使われる語句の意味、科学的であることの信頼性、社会の成り立ち方の構造的理解など、これまで市民が政治参加する上ではそれらは一定程度の共通理解がなされているとみなしていたことが、大きな勘違いだったということです。
せっかくこの大きな断絶が可視化されたのです。選挙を通じて修復すべき事柄のヒントが見つかったということを、私たちはむしろ喜ぶべきなのかもしれません。
これこそ民主主義の価値なのだろうと思っています。