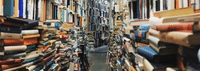パクリとオマージュの境界線について
ちょっと間が空いてしまったな。今日は「パクリ」について書こうと思う。なかなか厄介な話題ではある。でもこのタイミングでちゃんと自分なりの考えを文字にしておこうと思う。
「オマージュはいいけどパクリはダメ」だとか「リスペクトがあればOK」みたいな話はよく言われる。相手とその作品に対して敬意があればいい。それが感じられないものは模倣や盗用だ、と。でも、その「リスペクト」って何?という話。それってどう判断するの? どこにその境界線があるの?という話。
■「パクリ」とは何か
最近その手のことを考えるトピックがあった。
ラッパーのNENEが「OWARI」という曲で、「パクリ パクリ あいつもパクリ」「どいつもこいつもうちらのパクリ」というリリックで、ちゃんみな、SKY-HI、BMSGに名指しでビーフを仕掛けた。
この曲のリリックには「腐った音楽業界」「汚ねぇ音楽業界」というフレーズもある。「お前らはPOPS うちらはHIPHOP」という、ポップスとヒップホップコミュニティとの対立軸を煽るようなリリックもある。その後の「HAJIMARI」でチャートとかアワードに触れてることも含めてきっとNENEさんが糾弾したいトピックは他にもいろいろあったのだろうし、それについて思うこともあるけれど、そこはひとまず置いておく。
ビーフとかディスとか、ヒップホップ文化とその成り立ちについても、僕よりもっと詳しい人は沢山いると思うので、今回は置いておく。
YANATAKEさんと渡辺志保さんのblock.fmでのラジオ番組「INSIDE OUT」に出演したときのトークによると、NENEさんはHANAの「Burning Flower」の曲を聴いて、パクリだと確信したのだとか。
たしかに去年にNENEさんが出した『激アツ』は「アツい」ということをモチーフにしたEP。「ゲキアツ☆」には「あっちーちーちっちっちー」というリリックもある。このEPの全曲をプロデュースしているKoshyのプロデューサータグ(曲の冒頭で流れる短いフレーズ)は「Koshyアッツー」というもの。Koshyは千葉雄喜の「チーム友達」やミーガン・ジー・スタリオンの「MAMUSHI」などもプロデュースしてるわけで、NENEが言う「ヒップホップ界隈でアツいと言えばうちら」というのは一定の理路がある。
じゃあこれは「パクリ」なのか?
たしかにNENEの『激アツ』とHANAの「Burning Flower」は、モチーフが共通している。「アツい」=「イケてる自分たち」というセルフボーストのリリックというコンセプトも似通っている。
つまり、「OWARI」で主張されている「うちらのパクリ」というのは「アイディアやコンセプトの模倣」と捉えることができる。
ただし、「モチーフが重なっている=パクリ」という指摘が説得力を持つかどうかは、そのモチーフがどれだけ一般的なものであるかにも左右される。
加えて言うなら「アイデアやコンセプトを模倣された、盗用された」と他者を糾弾するということは、自身のオリジナリティを強固に主張するということになる。もしそこが脆弱なら足元をすくわれることにつながりかねない。
今回それを露骨に示したのが、NENEが「OWARI」を出した後に発表された歌代ニーナの「Mood Board」および「mood:bored」。この2曲では「OWARI」のリリックで「I'm on your mood board」というフレーズを使っていることについて「コンセプトごとパクられた」と糾弾している。
歌代ニーナさんいわく、「Mood Board」という曲はかなり前からライブで披露していて、MVもだいぶ前に収録済。NENEさんと共演もしているしスタイリストなどのスタッフも共通しているので、この曲をNENEさんが知らないわけはないだろうとのこと。
「mood:bored」は「OWARI」へのアンサーとして作られた曲。この曲のリリックでは「パクりネタでパクりディスはだめよ」「あんたのパシリがメイクとして潜入」「真似っこの話すんならクオリティーが足りない」と、上記の主張を歌っている。
たしかに、NENEさんのロジックで「『Burning Flower』は『ゲキアツ☆』のパクリ」と糾弾するならば、歌代ニーナさんの「『OWARI』は『Mood Board』のパクリ」というのも受け入れて向き合わなきゃいけない主張になるだろう。
前述の「INSIDE OUT」ではNENEさんは「知らないし、自分がそういうことをやるわけがない」と言っていた。その思いにウソはないのだろうとは思う。けれど、それでも「自分の曲はたまたまモチーフが重なっただけ」と言ってしまうと、主張がダブルスタンダードになってしまうのは否めないと感じた。
■「リスペクト」とは何か
一方、BMSGを率いるSKY-HIは「0623FreeStyle」でこの「OWARI」にアンサーを返している。
この曲のリリックにもいろんなトピックがあるのだけれど、重要なのはパクリの糾弾に対してちゃんとアンサーを返しているところだと思う。
お前が郷ひろみとスプリットしたら喜んでくれてやるよミリオン
世代が上の人なら気付くと思うけど、これは郷ひろみ「GOLDFINGER’99」の「A CHI CHI A CHI 燃えてるんだろうか」というサビのことだよね。「あっちーちー」を自分のオリジナルだと主張するなら、スプリット、つまりクレジットに名前を載せて権利を分配する相手は他にもいるだろう、という意味のリリック。細かく言うとあれはリッキー・マーティンの「Livin' la Vida Loca」の日本語カバーで、日本語詞を書いたのは康珍化なんだけど、まあそんなことを言っても誰にも伝わらないか。
NENEは「HAJIMARI」で「郷ひろみとかギャグに逃げんなよ」と返しているけれど、これはギャグでもなんでもなくて。前述したような「モチーフが重なっている=パクリ」という指摘が説得力を持つかどうかは、そのモチーフがどれだけ一般的なものであるかにも左右される、ということ。
「言ってる事わかるけど見直せその足元」というリリックもある。これは前述した歌代ニーナの件も含めて、パクリを糾弾するなら自身のオリジナリティをそこまで強固に主張できるか考え直したほうがいい、という指摘だろう。
ちなみに。
前述の「INSIDE OUT」でNENEさんは「他にもいろいろパクられてきた」と言っている。その実感は正直なものなのだろうと思います。
一方で、たとえばゆるふわギャング「Moeru」が宇多田ヒカル「One Last Kiss」をサンプリングしているように聴こえるけれどクレジットにその表記はないという指摘もある。
権利関係がどうなっているのかは当事者同士以外は預かり知らないところではありますし、法的なところには踏み込まないですが、もしこれが無許諾のサンプリングだったとするならば、著作権侵害として訴えられるリスクはそれなりに高いと思います。
また、SKY-HIの「0623FreeStyle」にはこんなリリックもある。
日本、極東のアジア からこんにちは どの道俺等同じ穴のムジナ
混ざりもんとまざりもんがまがいもんの押し問答置かれた場所で咲きなさいよ
これはアメリカの黒人文化から発祥したヒップホップを日本でやっている以上、どの道、完全なオリジナルなんてものにはなり得ない、ということだろう。どちらも結局はルーツを借りているということだ。
ただ、こういうロジックで「日本でヒップホップをやってる以上パクリとか偽物だと言ったって仕方ない」という主張だけに終わらせてないのがSKY-HIの「0623FreeStyle」のエラいところだな、と僕は思いました。
渡辺志保さんが「INSIDE OUT」で言っていたこととして、今回の「OWARI」は「NENE VS ちゃんみな」ではなく、もっと大きな問題、すなわち「インディペンデントにやっている小さなコミュニティの表現やアイディアを大手資本が搾取する」という構図なのだ、という主張がある。たしかにそうとも捉えられる。ファッションや他の業界においてもそういうことは多々あるだろう。
で、SKY-HIはそういう問題提起に対してもちゃんとアンサーしている。「0623FreeStyle」にはこういうリリックがある。
HIPHOPにRAPを借りてる以上リスペクトを払う俺POPSの意匠
長いクレジット払うスプリット
稼いだ分育てる次の才能
SKY-HI=日高光啓はもともとAAAのメンバーでありつつ、ラッパーとしてもクラブでの叩き上げの経歴を持ち、ヒップホップシーンの中で実力を認められ、存在感を示してきたキャリアの持ち主。なので日本のヒップホップのカルチャーとコミュニティへの敬意は当然ある。それでありつつBMSGはボーイズグループやガールズグループの事務所であるわけなので、活動のフィールドはポップスということになる。
その立場から「リスペクトを払う」と歌っている。
「リスペクト」とは何か?
言葉の意味はもちろん「敬意」なのだけれど、この曲の文脈では「リスペクトを払う」というのは、すなわち「ヒップホップのカルチャーとコミュニティに還元する」ということになるだろう。すなわち「搾取しているわけではない」という意思表示だ。「長いクレジット」というのは作詞作曲に携わったクリエイターの名前。「払うスプリット」というのは印税のこと。そして「稼いだ分育てる次の才能」というのは、具体的にはラッパーやトラックメイカーが稼げる道を作っていくということなのだと思う。
実際、BMSGは今年4月に「Bullmoose Records」というレーベルを立ち上げてSALUとBANVOXと契約している。BMSGは「才能を殺さないために。」というのをビジョンに掲げているわけなので、このあたりは有言実行でもあるなと思います。
NENEはこの「0623FreeStyle」を受けて「HAJIMARI」を出したけれど、そこからさらなるビーフの応酬という感じにはなっていない。ちゃんみなが何らかのアンサーを出すかどうかは彼女次第だけれど、それが待望されているムードもあまり感じない。なので、たぶん、この先も大きな動きはなさそう。
ということなので、この時点で総括すると、最もプロップスを上げたのは歌代ニーナだと思います。YouTubeやSNSのコメントをざっと見るかぎり、わりと多かったのが「これをきっかけに歌代ニーナを知ることができたのが収穫だった」「歌代ニーナを知ることができたことに感謝」という声。
数字としても7月18日現在で歌代ニーナのYouTubeチャンネル登録者数は8万人を突破していて、NENEが「OWARI」を発表したゆるふわギャングのチャンネル登録者数を短期間で上回る動きを見せた。
SKY-HIもプロップスを上げたと思います。きちんとアンサーを返したこと、そこでライミング含めてクオリティ高いパフォーマンスを見せたことで、BMSGを色眼鏡的に見ていたヒップホップリスナーを唸らせる結果になったのでは。数字とか人気とかとは別のところでこれも効いてくると思う。対してNENEは残念ながらプロップスを下げてしまったのではないかなと。
もちろんこれはあくまで僕からの捉え方です。全然違う見方をしている人も当然いるとは思いますのでそのへんはご容赦のほどを。
■「オリジナル」とは何か
さてここからようやく本題。
このビーフのことからは一回離れて、そもそも「パクリ」とか「オリジナル」って何?という話。
まず大前提として僕が言いたいのは、「何かと何かが似ているということだけを指摘して、作り手でもない第三者がそれを『パクリだ』とこき下ろすような考え方は、端的に文化とクリエイティブへの冒涜である」ということ。
なので、ここまでの話においても、僕はどの曲のことも、どの表現のことも「パクリ」だとは断じてはいない。NENEさんも、歌代ニーナさんも、自分の表現と創作物があるからこそ、その当事者として一人称で覚悟を背負って発信している。そのことへの尊重はもちろんある。
そのうえで、作り手でもない第三者からの「あれに似てる、これに似てる、これはパクリだ」という糾弾がちょっと幅を利かせすぎてるんじゃないの?という問題意識はある。過剰過ぎやしない?という。
実はこれ、僕も何度かインタビューでアーティストと対話している大事なテーマなのです。たとえば米津玄師「BOOTLEG」のインタビューでそういう話をした。
“パクり”っていうのも曖昧なもので、どこからどこまでパクりなのかとか、そういうことは自分が決めるものではないっていうのがまずある。いろいろ言われるじゃないですか、「バレるとヤバいのがパクりだ」とか「リスペクトがあるのがオマージュだ」とか。でもそのラインもあやふやなんです。そこに対して過剰すぎる人がいるのが、やっぱり気に食わないんですよね。例えるなら、木の絵を描いたことに対して「これは木のパクリだ」みたいなことを言っている人がすごく多いような気がする。いろんな文脈があって、その歴史があって、自分はその歴史の最先端の今というところでものを作っているわけで。いろんな場所から何かをピックアップしながら今の自分が生まれていると思うんですよ。
Vaundy「replica」のインタビューでもそういう話をしました。
全てのものはレプリカなんじゃないかということに行き着きました。あらゆるものがレプリカの組み合わせで出来てるんだっていうのが、僕の大学卒業のテーマだったんです。自分自身だってレプリカなんだと思います。
(中略)
曲を聴いて、あれに似てる、これに似てるという人もいると思うんですけれど、似てるのはもう当たり前なんです。それに、これからの時代、全部が見通せちゃうんで、何にも似ていないもの、違うものを書くというのは、たぶん無理だと思う。それはきっとAIでも。だったら振り切っちゃえばいいんですよ。遺伝子を受け継いだ上で、そのアーティストにできないことを探す。この人たちがやっていたことを今の時代に混ぜたらどうなるんだろう? とか。それは対象自体を理解していないとできないことなんで。
ここで米津玄師が言っていること、Vaundyが言っていることは、ほとんど共通していると思う。僕も同意。
そもそも、すべての創作や表現は大きく言ってしまえば先行する何らかの作品や作家の影響を受けているものである。文化というのは本質的にそういう営みの中で生まれてくるもののことを言う。
つまり、何らかの先行作品をリファレンスする、モチーフを参照して取り入れるという行為自体を「パクリ」として封印してしまうと、そもそもクリエイティブ自体が成立しなくなる、ということになる。
だがしかし。だからと言って額面通り「創作や表現は何もかもがパクリなんだ」「全てがレプリカでオリジナルなんて存在しないんだ」と言い切って、何もかもを擁護してしまうのも、とても乱暴な話。
実際のところ、ファッションやデザイン業界で起こっているようなことも含めて見回して考えると「これは粗雑な模倣だなあ」「これは悪質な盗用だなあ」と感じる例もある。これはオリジナルの作り手に対しての敬意を全く感じないなあ、という。そういうものが「パクリ」として問題視されているような例もある。
法的なところは置いておくとして、そういうものに対しては糾弾されてしかるべきだと僕も思います。まさに「バレるとヤバいのがパクりだ」という。全然オリジナリティを感じないなという。
じゃあ「オリジナル」って何だ。
そういうことについて考える機会がこないだあった。それが横浜美術館で開催されている「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」に行ったことと、ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を観たこと。
佐藤雅彦とブライアン・イーノは活躍しているフィールドもカルチャーの文脈も全然違う。でも僕が感じたのは、どちらも「圧倒的にオリジナル」だということ。
佐藤雅彦は「ピタゴラスイッチ」 「バザールでござーる」 「だんご3兄弟」 「スコーン」 「モルツ」 「ポリンキー」 「I.Q Intelligent Qube」などなどを作った人。TVコマーシャル、音楽、教育番組、ゲーム、いろんな分野でヒットコンテンツを生み出してきた。
ブライアン・イーノは言わずもがなのアンビエントの巨匠。『Eno』は自動生成システムを使ったジェネラティブ・ドキュメンタリーという作品で、これに関しては監督へのインタビューもしました。
佐藤雅彦とブライアン・イーノには創作活動の根幹の部分に共通点がある。それは「作り方から作っている」ということ。
「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」はまさにそのことをテーマにした展覧会だ。クリエイティブとは何か、どうすればオリジナリティのある創作をすることができるのか、という大学の授業のような内容になっている。
「バザールでござーる」や「ポリンキー」といったCMを作るにあたっては、創作の前に表現方法のルールを作り、さらにそこから独特のトーンを生み出していくという手法がとられている。
そして『Eno』は監督が言う通り「創造性というものをテーマにした映画」である。そもそもブライアン・イーノはアンビエント・ミュージックの先駆者でもあり、リアルタイムに自動生成されるジェネラティブ・ミュージック(生成音楽)の先駆者でもある。音楽という枠組みを拡張している。そこでも重要なのはルールとトーンだ。
もちろん誰しもが佐藤雅彦やブライアン・イーノのように「圧倒的なオリジナル」になれるわけではない。ジャンルやカテゴリそのものをゼロから生み出せるわけではない。
でもそれをヒントに「パクリとオリジナルの境界線」を考えることができる。
それは「ルールとトーンが自分のものであるかどうか」ということ。
表現方法自体をゼロから作り上げるのは常人にとって至難の業だとは思う。でも「こういう時に自分はこうする」という”自分内ルール”みたいなものは誰しも持ち合わせていると思う。創作や表現にあたっては、こういう色味や響きだったら格好いいとかイケてるという”自分内トーン&マナー”は誰しもが持ち合わせているものだと思う。
ルールというのは、言い換えるなら「美学」とか「美意識」と言ってもいい。トーンは「センス」と言ってもいい。
それが自分自身に由来するものであれば、何かのモチーフを参照したり、何かにインスパイアされた表現であったとしても、そのことを堂々と表明することができる。それによって「リスペクトがある」とみなされる。何かのスタイルを取り入れたとしてもオリジナリティを発揮することができる。
でも、ルールとトーンが借り物であるならば、つまり創作や表現にあたっての行動規範そのものを盗用しているならば、それは「バレるとヤバい」ということになる。
というわけで、著作権侵害とか商標とかそういう法的なところを抜きにして、とりあえずここで書いてきたことの結論。
「パクリ」というのは「アイディアやコンセプトの模倣」と捉えられている。でも、それを細かく腑分けするならば「モチーフやスタイルの参照」と「行動規範の盗用」に分けられる。
前者は米津玄師やVaundyが言うようにクリエイティブの必然である。どんな表現や創作だって何かしらの影響を受けている。一方で、後者が責められるのは必然的だよなとも思う。
もちろん、ここから先は前者でここからは後者だなんてハッキリと分けられるものではない。NENEさんだって「自分の美学を盗まれた」と感じたからこそ覚悟を背負って発信したんだろうし。その思いは本当のものだと思います。さっきは「プロップスを下げた」と書いたけど、正直、過熱したファンダムによって行き過ぎたバッシングとか誹謗中傷を食らっている側面もあるなとも思う。
ただHANAのルールとトーンは「No No Girls」やその他の作品などできっちりと示されているわけなので、ちゃんみなとBMSGが「行動規範の盗用」をしたとは、少なくとも僕は思わないかな。
パクリとは何か? それは悪なのか? リスペクトとは何か? オリジナリティとは何か?っていうのはとても面倒くさくて厄介な問題で、しっかり書こうと思ったら1万字近くになってしまった。
長いよ!
でもとりあえず今思っているのはこんな感じです。