「はい論破」と倫理学
先日、非常勤先の大学で英語ディベートクラブに所属しているという学生から「倫理学的なテーマでディベートをするような授業をしてみてはどうか」という提案を受けた。私はディベートについてルールもなにも知らないし、どのような教育効果があるかについて考えたこともなかったので丁重にお断りしたのだが[i]、それ以来ディベートに参加している自分のことを夢想して、なんとなくむずむずするような、落ち着かない気分になることがよくある。
全然知らなかったのだが、いわゆる競技ディベートでは、参加者が肯定側につくか否定側につくかは自分で選ぶことができないのはもちろん、自分がどちらの陣営になるのかが直前までわからないルールで行なわれることも珍しくないようだ。これはディベートが一種のゲームであり、純粋な競技として成立させなければならないことや、自分の内心から一度離れて純粋に事柄のメリットやデメリットを考えることの教育的な効果を考えれば、実はあたりまえのことであるとも言える[ii]。
このような最狭義のディベート(つまり競技ディベート)は具体的なトピックの是非を論じる倫理学や政治哲学的な議論とどれくらい近いだろうか。そして、私を含めて、あまり競技ディベートに関心のない哲学者が多いのはなぜだろうか。
ジョシュア・グリーンは自著のなかで自分が競技ディベートに参加していたときに倫理学(道徳哲学)と出会ったことを語っている。グリーンは十代の時分にかなり熱心にディベート競技に取り組んでいたようだが、あるとき「いかなる立場に立とうとも」功利主義者として振る舞うことで自分に有利な状況を作り出せることに気づいたという。
私はこのあらゆるものに応用がきく戦略をすっかり気に入って、あらゆるディベートで、どんな立場に割り振られても、功利主義を自分の価値前提とした。毎回、ミルやその仲間の権威ある言葉でぴりっと味付けした、よく使われる功利主義の口上ではじめた。そこから先は、自分に割り振られた立場が、より大きな善にいかに役立つかを示す証拠を都合のいいものだけ取り上げればよかった。
グリーンの連勝記録はあるとき対戦相手が「臓器くじ(サバイバル・ロッタリー)」の例を持ち出したことで終わりを迎える。彼はそれを機にディベートをやめてしまうのだが、それは彼が功利主義に限界を感じたからではなく「道徳的世界観を失った」ような感じを覚えたからだという。
もちろん、これは功利主義が議論の場面に役に立たないとか、欠陥の多い邪悪な思想であるとグリーンが考えたというわけではない。競技ディベートがある政策のメリット・デメリットを突き合わせるゲームである以上、意識的にせよ無意識的にせよ功利主義的な観点は不可避であるし、現在のグリーン自身が功利主義の強力な擁護者でもある。
十代のグリーンが感じたのは、功利主義の意図や背景、原理とそこから導きだされる帰結を理解することなしに、単なる議論戦略、レトリックとして用いてしまうことができることそのものへの嫌悪感であろう。競技ディベートは勝敗を競うゲームであり、その限りで自分の信じていないことを主張することが許されている。そして、自分の信じていない論点を正しいものとして正当化するのに便利な道具が「議論戦略としての」功利主義だ、というわけである。しかし、その戦略を使いこなすことと、倫理学説のひとつとしての功利主義を理解し、自分の道徳世界観にそれを組み込むことが可能だと考えることはかなりの落差があるのだ、と。
「哲学的な議論をするのであれば、自分の信じることのできる主張をしたかった」(グリーン 2015、143)と語るグリーンは、真理のためにソフィストと闘ったソクラテス以来、模範とされてきた(哲学者としての)倫理学者像に忠実である。ディベーターは議論によって論敵を屈服させるが、哲学者は議論によって真理に到達する。そして、その真理は自分自身で信じることができるものでなければならない。
これは一種の模範解答であり、なにより倫理学者自身にとって魅力的な倫理学者像である。倫理学者は、学問的な営みとしては、なんらかの政治的課題なり倫理的問題に向き合いつつ、複数の理論を考慮しながら、自分の信じる道徳的世界観を練り上げていく。その一方、互いの立場の正当性が問題になる議論の場において、倫理学者は論点整理をしながら、双方を真理へと誘導する手助けをする、というわけである。
これが近年注目を集めている「(議論)コーディネーター」としての倫理学者の役割である。コーディネーターとしての倫理学者は、例えば「(…)一歩引き下がった場所から、ときに人びとの感覚に形を与えて問題の所在を明らかにし、ときに倫理学理論を背景として浮かび上がる問題を提示することで人びとを触発する」(奥田 2012、195)存在として理解される。論争の場において、ひとりのディベーターではなく、コーディネーターないしファシリテーターとして姿を表すのが、道徳の専門家としての倫理学者である、というわけだ。
しかし、多くの論者が指摘するように[iii]、倫理学者もまたひとりの市民であり、その限りで自己の政治的利益を達成しようとする動機をもつことがありうる。そして、これが重要なことであるが、実際の議論の場において「それでは結局あなたはどちらの立場なのですか」という問いはごく自然に発せられるだろうし、それなりにもっともなものと言える。純粋なコーディーネーターが必要される場面など、現実には大学の授業内にしかないのかもしれないのである。
率直に言えば、私は「コーディネーターとしての倫理学者」というイメージを魅力的に思う一方で、議論は「話のわかる」専門家同士でしか行わず、熱意をもって論戦を挑もうとしてくる非専門家に対しては理論家ないし教育者として振る舞うことに後ろめたさを感じている。そして、もし本気の論戦に巻き込まれた場合、簡単に「はい論破」されてしまうような気がしてならない。それは、格闘漫画に出てくる、喧嘩自慢の素人にのされる武道家のようなイメージである。ディベートに参加する自分を想像したときのむずむず感は、そうした論戦であっけなく敗北してしまうことへの恐怖感と、なにかそれに対するマゾヒスティックなイメージがないまぜになったものなのかもしれない。
(この記事は、雑誌『フィルカル』のVol. 2, No. 1(2017年3月31日発行)に掲載された連載「生活が先、人生が後」第2回「スノビズムの舷窓」を編集部の許可を得て再掲したものである。noteへの再掲に当たって一部の表現を変更している。
[i] もっとも、英語圏において専門職倫理の授業でディベート型の教育プログラムは当たり前に行われており、エシックス・ボウルなる大学対抗の倫理討論競技も年一回開催されている。ただし、その主催者の多くは専門的哲学者というより、個別の学問領域で倫理教育を担当している研究者である、という伊勢田 2011の指摘は興味深い。
[ii] ただし、ディベートの実践家のなかでも、倫理的・政治的トピックについては無批判に討議テクニックを適用するだけではなく、一種の応用倫理学的な捉え方を併せて学ぶのでなければ議論そのものの意味がないと考える論者もいる。これについては柿田 1999を参照。
[iii] たとえば、品川 2013を参照。
文献表
伊勢田哲治(2011)「座談会記録 応用倫理学に未来はあるか:応用倫理学の標準化?」、『応用倫理』第5号:80−83
奥田太郎(2012)『倫理学という構え』(ナカニシヤ出版)
柿田秀樹(1999)「レトリックとディベートの政治的本質:倫理批評実践」、『JDA Newsletter Vol.XIV, No.4:日本におけるディベートの普及について(その3)』http://old.japan-debate-association.org/article/dissemination3.htm (2017年2月2日最終アクセス)
品川哲彦(2013)「倫理学者は常に倫理学者であり、それ以外ではないのか」、『応用倫理』第7号:29-35
ジョシュア・グリーン(2015)『モラル・トライブス 共存の道徳哲学へ(上)』竹田円訳(岩波書店)

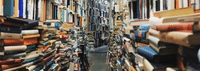

コメント