社会保険労務士として生きる道
社会保険労務士として仕事を始めてから、何をすることが自分にとって有益で、他者と差別化ができて、資格を生かすことができて、社会保険労務士として効率よく生きていくことができるんだろうと、考えていた。
行政書士、司法書士、税理士、司法試験の資格も取得してダブルライセンスとしてやっていくこと??別の士業の勉強をすることは無駄ではないけど、ベン図でいうと重なる部分が少なすぎて、お客さんにサービスを提供する上で最高の価値を創造するには不必要で無駄な知識が多いと思ってしまう。自分で学ぶよりも士業の仕事仲間を作って紹介するほうがCLファーストなんじゃないか…だって自分が専門家としてアドバイスするには知識の範囲が広すぎて、結局フワフワした回答しかできなくないか??って。
ダブルライセンスじゃなくてシングルライセンスでその道を究めているほうが、CLに明確な回答や提案をできると思ってしまう。
じゃあ、結局のところは社会保険労務士の専門業務を中心に付帯する業務を極めたほうがいいと思う。じゃあ一般的に社会保険労務士が生業としている業務はどんなことがあるんだっけ??と全国社会保険労務士会連合会のHPから社労士の仕事について引っ張ってみた。
1.労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい◎
2.各種助成金などの申請
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がございます。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。
助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を社労士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。
⇒ 雇用関連なら他士業とバッティングしないから極めがい◎
3.労働者名簿、賃金台帳の調製
法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社労士は、これらを適正に調製していきます。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい◎
4.就業規則・36協定の作成、変更
社労士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい◎
5.雇用管理・人材育成などに関する相談
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい○(やるなら一度は事業会社の人事部門で働きたい)
《役立つ資格》キャリアコンサルタント
6.人事・賃金・労働時間の相談
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい○(やるなら一度は事業会社の人事部門で働きたい)
7.経営労務監査
社労士は、就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい○(やるなら一度は事業会社の人事部門で働きたい)
8.年金の加入期間、受給資格などの確認
皆さまの年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度について、専門家である社労士がお答えします。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい○(ただし、C向けになるかつ複雑なので稼ぎ方は難しい)
《役立つ資格》年金アドバイザー、FP、DCプランナー
9.裁定請求書の作成・提出
年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、申請手続きが必要となります。
社労士は皆さまに代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。
⇒ 他士業とバッティングしないから極めがい○(ただし、C向けになるかつ複雑なので稼ぎ方は難しい)
《役立つ資格》年金アドバイザー、FP、DCプランナー
10.あっせん申立てに関する相談・手続き
問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。
⇒ 弁護士とバッティングするから×、勝てない
11.代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結
確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。
⇒ 弁護士とバッティングするから×、勝てない
12.補佐人として意見を陳述
社労士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。
依頼者は、相談の段階から支援を受けてきた社労士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。
⇒ 弁護士とバッティングするから×、勝てない
そんなわけで、やることは決まった。結局社労士が勝てるのは、他士業とバッティングしない業務だけだ。あと給与計算は毎月必ずやらなければいけないし、コンスタントに稼げる業務だから、極めていきたい。すっごく大変だけど。
他士業との合同事務所
健康保険組合、厚生年金基金の職員
コンサルタント会社等への勤務
一般企業の人事総務担当者
中小企業診断士
個人情報保護士
ビジネス実務法務

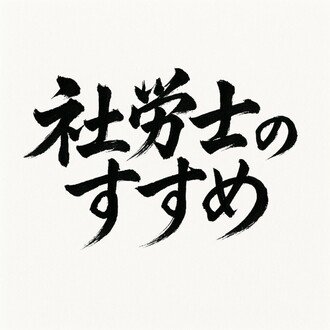
コメント
2共感します。
記事ありがとうございます。とても参考になります。自分は応用情報技術者(第一目標)→中小企業診断士(四十代目標)を目指しています。会社員には限界も感じています。