主流派経済学批判と実態経済への提言:経世済民の観点から
はじめに
日本の長期にわたる経済停滞、消費の冷え込み、実質所得の低下は、単なる景気循環や外部要因によるものではなく、構造的な政策選択と思想的土壌に起因している。特に問題なのは、緊縮財政とそれを正当化する主流派経済学の影響である。
本論文では、主流派経済学の限界を明らかにし、実態経済の本質――すなわち人間の欲求と行動に基づいた経済モデル――に立脚した政策的アプローチの必要性を提言する。
緊縮財政と主流派経済学の共犯関係
1990年代以降、日本は財政再建を最優先課題とし、増税・歳出削減といった緊縮政策を繰り返してきた。これは主流派経済学、特に新古典派マクロ経済学が提唱する「政府の失敗」や「財政の非効率性」に基づくものである。
その中核にあるのが、ラッファー曲線やリカードの等価定理などであり、「政府の支出拡大は将来的な税負担を増やすため、消費や投資が抑制される」といった理論である。だがこれらは現実と著しく乖離している。
リカードの等価定理の非現実性
リカードの等価定理は「減税しても将来の増税を見越して国民は消費を控える」というロジックをとるが、これは以下のような非現実的な前提に依存している
1 国民全員が将来の財政政策を予見できる
2 生涯所得を基に合理的な貯蓄行動をとる
3 完全雇用と完全競争市場が存在する
実際には、将来の税負担を正確に予測できる国民は皆無であり、可処分所得が増えれば大半の国民は喜んで消費活動を増やす。また、金融市場へのアクセスや雇用の安定性にも格差がある以上、等価定理は現実の政策判断において無意味である。
人間の欲望と実態経済の構造
経済の本質は「人間の欲望と感情」にある。
「美味しいものが食べたい」
「ブランドを持ちたい」
「誰かに認められたい」
「安心して老後を迎えたい」
これらの動機が消費・投資・労働・貯蓄といった経済行動に直結している。主流派経済学が想定する「効用最大化する合理的経済人(ホモ・エコノミクス)」は、あまりにも抽象的で非人間的である。
感情、文化、社会的文脈、制度的背景――これらを抜きにした経済モデルでは、現実の経済行動を予測することも、対処することもできない。
道徳的感情とスミスの誤解
アダム・スミスは『国富論』だけでなく『道徳感情論』においても、人間が「公平な観察者の目」を意識し、共感と倫理に基づいて行動することを説いている。主流派がスミスを「自由市場信奉者」として単純化するのは誤りである。
実際の市場では、人間の共感、文化、帰属意識といった“非合理的”要素が常に作用しており、これを無視して市場機構だけに頼ることは、経済の不安定化を招く。
貨幣の非中立性と信用の重要性
主流派経済学では「貨幣は中立的であり、長期的には実物経済だけが重要」とされる。しかしこれは信用経済における貨幣の創造メカニズムや、財政政策の乗数効果を過小評価している。
現代では、貨幣とは単なる交換手段ではなく「政府の債務であり、民間の純資産」である。この構造を無視して、インフレ=貨幣の過剰と単純化するのは誤りである。
結論:経世済民に立脚した経済学へ
経済とは「経世済民」――すなわち、世をおさめ、民を救うための学問である。
主流派経済学はその一部に有用な理論を持つが、過度に抽象的で非現実的な前提に立脚しており、実態経済に対する有効性は低い。
今こそ、制度派経済学、行動経済学、MMT(現代貨幣理論)などを融合させた、新しい経済モデルを再構築すべき時である。
実態に即し、欲望と不確実性を前提とし、人間の感情と制度的背景を理解する。そうした経済学こそが、真に「経世済民」を実現しうる。

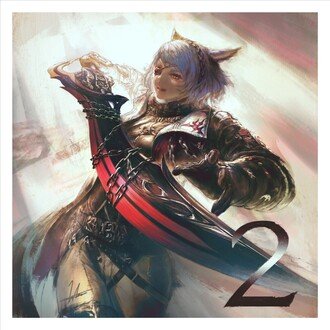
コメント